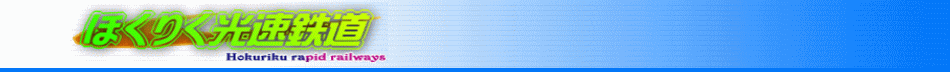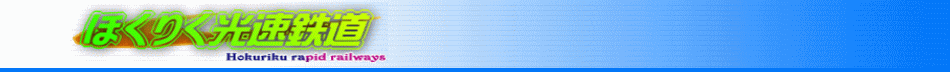|
モハ80形
モハ80型は南海鉄道電5型をルーツとする電車。1956年に日本車両で車体が新製され、同時に台枠も更新された。また従来、モハ80〜84の単行四両でしたが、1977年4月に組成変更され、モハ81+クハ81、モハ82+クハ82の2編成体制になった。その後、国鉄の廃車発生品を使ったカルダン駆動化が行われた。車内は千鳥配置のセミクロスシートであった。低床車導入により2006年に廃車となった。 |
 |
モハ120形
モハ120型は1950年に登場した自社発注車。一方、相方のクハは名鉄から譲受したモハ3001・3002が種車となっている。当初は名鉄からの2両が編成を組み、南越線で使用されていたが、南越線廃止後に形式が整理され、モハ120と編成を組み直されている。2編成が在籍したが-121の編成は1994年に廃車され、残った-122の編成は1997年にカルダン駆動化された。モハ120形は座席がロングシートであった。低床車導入により2006年に廃車となった。モハ122は越前市内で保存されている。 |
 |
 |
モハ140形
モハ140形は3編成が存在し、吊掛駆動・転換クロスシートの珍車。2両編成だが、両側で種車が異なる。武生新側の-1のうちモハ141と142は長野電鉄モハ300形が種車、モハ143-1は福井鉄道の前身の鯖浦電鉄デハ11がルーツ。一方、田原町側の-2については全ての種車が名鉄モ900形である。
モハ141の編成は非冷房車ながら2006年まで現役で活躍した。
|
 |
モハ300形
モハ300型は1986年に静岡鉄道から移籍してきた車両。製造から20年程度と比較的新しかったが、1000型に統一するため、福井鉄道へ移籍した。冷房や自販機が搭載され、座席はクロスシート化された。登場当初、塗装は静岡鉄道時代の銀+青帯であったが、視認性の問題が発生したため、白基調の新カラーに変更された。
低床車導入により2006年に全廃された。またモハ300型廃車以降見られなくなっていた300型標準色はモハ610型が受け継いでいる。
|
 |
モハ500・510形
1967年の北陸鉄道金沢市内線全線廃止に伴い、福井鉄道に移籍した車両群。
右上の500形501は八王子の武蔵中央電鉄が1929年に製造した車両。1942年に北鉄金石線の前身、金石電鉄に移籍、その後は北鉄モハ2050形となって廃線を迎えた。福鉄移籍後は福武線の路面区間を中心に使用され、1969年に廃車された。
左下の510形は琴平参宮電鉄から2両移籍した車両。北鉄モハ2060形として活躍した後、福鉄に移籍した。その後1969年に500形とともに廃車された。画像は記念きっぷ台紙より。
|
 |
モハ560形
モハ560形は1989年に福井鉄道に入線した軌道線車両。
1956年に日本車輌で製造され、北鉄モハ2202として1967年の路線廃止まで活躍した。金沢市内線の廃止後は親会社の名鉄に譲渡され、岐阜市内線で20年間使用された。1989年に福井市制100周年を記念し、軌道線区間の専用車両として福井鉄道に移籍した。
その後は北鉄時代の塗装に復元されイベント用車両として使われていたが、2001年にトランジットモール社会実験で期間限定ながら軌道線専用車として復活し、名鉄から借り入れられたモ800とともにすまいるトラムが運行された。2004年ごろからは福井大学と企業が共同開発したバッテリーを積んで、架線レスのバッテリートラムとして試験が行われた。
2006年に名鉄からの低床車両が導入されると、静かに引退した。現在は金沢市電保存会の方々によって復元作業が行われている。 |