
無名の人ですがあまりにおもしろかったので・・・・
幕府はベリーの開国の要求に対し 庶民にも広く意見を求めました。
かなりの返答があったのですが その多くは特に意見はありません というものばかりだった。
そんな中 ある遊女屋の主人の籐吉という者が よほど自信があったのか願書きの形で 次のような事を書いてきたそうです。
「決死隊を募り 最初は漁師が魚を捕っているふりをして だんだん黒船に近づき 外国人の好みそうな品を贈って仲良くなる。
そして 酒もふんだんに差し入れてよい気分にさせれば 上船を許すだろうから こちらもいっしょに飲んで騒ぐ。
そのうちあちらは酔いつぶれる。
そのときを狙って 隠し持った包丁で偉人どもを滅多切りにし 火薬庫に火をつけて爆発沈没させれば 成功間違えなしであります。」
なるほど さすが遊女屋のご主人 遊女をはべらし一杯飲みながらのお話としては 花丸合格であったでしょう。 特に包丁は秀逸です。
榎本武揚 と 資生堂 04-12-11

戊辰戦争において函館に蝦夷共和国をつくり 初代総裁となった武揚ですが 明治政府軍に敗れ 3年程監禁されておりました。
しかしその間に 焼酎 西洋ろうそく チョーク 硫酸 等々のさまざまな製法書を書いています。
それらで家族に送られたものの中に 石鹸 の製法書があったそうです。
その製法書を読んだ彼の親戚は その製造販売を家業とし大いに繁盛 数年後には会社を設立し その名を資生堂としました。
創業者は武揚より12歳年下の遠い親戚で 当時彼の推挙により海軍病院医局長となっていた福原有信氏で 現在のあの資生堂の始まりです。
ペリー オハグロはやっぱり嫌い 04-12-10

ペリー提督が 横浜の町役人宅を訪問した際 よほどオハグロにショックだったのか 「日本遠征記」に かなり詳細に書いてます。
「穏やかに微笑してルビーのような唇が開いていたので ひどく腐食された歯茎に生えている一列の黒い歯が見えた。
日本の既婚婦人だけが、歯を染める特権を持っており、染めるにはおはぐろという鉄の粉と酒とをふくんだ汚い成分の混合物を用いる。
この混合物は その成分から当然に推察されるように心地よい香りもしないし 衛生的でもない。 それは非常な腐食性のもので それを歯につけるときには 歯茎や唇などの柔らかい組織を何かで覆う必要がある。
そうしなければちょっとでも肉に触れると直ぐにただれて 紫色の斑点が出来てしまう。
いくら注意しても、歯茎は腐って赤い色と活力を失う。
・・・(数行略)・・・
そしてこの厭うべき習慣は 他の習慣 すなわち紅で唇を染める事でいっそう明らかになる。
赤くした口は、黒い歯と著しい対象をなすからである。
「べに」と呼ばれる日本の化粧品は 紅花で作られ陶器の盃に入れてある。
薄くひと塗りすると鮮やかな赤色となるが 厚く塗ると暗紫色となる。
この暗紫色が一番いいとされている。」
というように かなり調べてあります よほどショッキングだったのでしょう。
私の死んだおばあちゃんは明治36年生まれでしたが もちろん見たことがあるそうです。
ということは 明治維新後の洋装の麗夫人たちの多くもオハグロだったのでしょうか。
残念ながら 当時は笑顔を写真に撮る事がなかったのでわかりません。
十返舎一九はつまらない男・・・? 04-12-9

膝栗毛等のちょっと下品でユーモラスな作品を残している一九ですが まるで面白味のない人だったとする資料もあります。
当時膝栗毛の熱心なお金持ちのファンが このように滑稽な一九と一緒に旅が出来たなら さぞ楽しいだろうと思い 旅行に関する一切全ての費用を受け持つからと 一九に頼み込みました。
流行作家とはいえそれほど裕福でなかった一九ですから 渡りに船とばかりに お金を受け取り その金持ちと同行の旅をはじめたそうです。
しかしその時の一九は その金持ちが弥次喜多から想像したのとは まるで正反対の人物で むっつりとして口もきかず 宿に着けばさっそく机に向かい 几帳面な日記をつけるという始末でした。
あまりに退屈になったそのお金持ちは 途中で逃げ帰ったそうです。
その時 一九は 「してやったり。」 と にんまりしたのかな。
もともと一人旅の大好きな一九ですから そのあとはきっと楽しい旅を続けたのでしょう。
安藤昌益 生前も狂人扱い 04-12-9

近年 思想家として評価され マルクスやエンゲルスより100年も前に 同様な思想が鎖国日本に存在したとされますが 本来医学者である彼は 特に精神医学において当時のその根本を覆すどころか むしろ現代医学に近い解釈をしています。
明治になり発掘されたも同然なので 昌益の人となりについてはまるで残っていませんが その文章や文体から想像するに すこぶる頭は切れるのだが 偏屈で 粘着質な性格だったと思われます。 後に狩野幸吉が狂人と誤解したのも頷けるほどです。
昌益の生前には その土地の代官が 「近年この村に徘徊し邪(よこしま)な教えを説き郷人を惑わせる昌益という医者がいる。」 と記し残しています。
とくに幕府側の人間にとっては このように狂人と扱うほうがよかったのかもしれません。
でも やっぱり偏執狂であったのは間違えないと思います。
安藤昌益 狂人研究の資料となる 04-12-9

およそ300年前に生まれた昌益ですが 一時その存在は抹消されていました。
神仏はもちろん公家,武家による統治や その存在までも強く否定した昌益でしたから 江戸幕府にとって都合の良いわけも無く ましてやその論を広めれば命が危なかったのだから 仕方ありません。
その彼が評価されたのは 明治32年碩学研究者の狩野幸吉によります。
昌益の弟子が 「開ければ目がつぶれる謀反の書」 として代々秘蔵しつづけた 昌益の稿本「自然真営道」を 狩野が手に入れたことに始まります。
しかし当時は無名の昌益でしたから 狩野は当初 その文体、発想、意見を拾い読みし 「これはまさしく狂人の書いたものにちがいない。 それにしても100巻92冊をよくも書いたものだ。 狂人研究の参考になるかもしれない。」 として 数年間 医学博士呉秀三のもとに預けたそうです。
谷崎 羊羹を語れば 04-12-8

時代が新しくてこのページには合いませんが 漱石の羊羹も出たのでついでに。
谷崎潤一郎も 「陰翳礼讃」(昭和8年)にて 羊羹について書いています。
彼はもともと物事について このようにあれこれと表現するのが好きなようですが 漱石同様 妙に言葉多く書いています。
「玉のように半透明に曇った肌が。奥の方まで日の光を吸い取って夢見るごときほの明るさを啣(ふく)んでいる感じ、あの色合いの深さ、複雑さは西洋の菓子には絶対見られない。・・・・。だがその羊羹の色合いも、あれを塗り物の菓子器に入れて、肌の色が辛うじて見分けがつく暗がりに沈めると、ひとしお瞑想的になる。人はあの冷たく滑らかな物を口中にふくむ時、あたかも室内の暗黒が一個の甘い塊になって舌の先で融(と)けるのを感じ、本当はそう旨くない羊羹でも、妙に異様な深みが添わるように思う。」
漱石は青磁の皿でしたが 谷崎は塗りの菓子器ですか。 何かそれぞれの文学観の違いがこんな所からもにじんでいます。 それにしても耽美派の文章は・・・・・・。
漱石 羊羹を語れば 04-12-8

夏目漱石が 「草枕」のなかで羊羹について 妙に言葉多く語っています。
「菓子皿のなかを見ると、立派な羊羹が並んでいる。 余は凡ての菓子のうちで最も羊羹が好きだ。 別段食いたくは無いが、あの肌合いが滑らかに、緻密にしかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。 ことに青みを帯びた練り上げ方は、玉と蝋石の雑種のようで、甚だ見て心持がいい。 のみならず青磁の皿に盛られた青い練羊羹は、青磁の中から今生まれた様につやつやして、思わず手を出して撫でて見たくなる。」
このとき青い練羊羹を出してあげたら 頑固な漱石も目ぐらいは笑ってくれたかも。
寿太郎 ルーズベルトの信を得る 04-12-7

ポーツマス講和会議でのことです。
会議には 仲介の米大統領ルーズベルトと 日本から小村寿太郎が ロシアからはウィッテが臨みました。
講和会議成立後 ルーズベルトは 本国への知人に送った書簡の中にこう語っています。
「日本人は常に私に真実を語り きわめて秘密性を持ち 言明した事は必ず実行した。彼らは互いに信頼し 共同して行動する。」 寿太郎の飾らない誠実さは大統領の深い信頼を得たようです。 しかしロシア側に関しては 「互いに信頼せず けん制し 虚言を弄し きわめて不健全かつ普遍的な腐敗と利己を示した。」 と書いています。
さらにウィッテ個人については 「私は彼を好まない。彼の立派な発言は ただ愚を示すのみならず 日本人の紳士的な自重自制に比べれば 驚くほど粗野であるからだ。私は彼を高尚な思想の欠けた甚だしき我儘者とみた。」 とまで書いています。
服部南郭 儒者の語彙を雪隠(便所)と言う 04-12-7
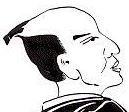
服部南郭は徂徠の門人で 古学を修めた人ですが 当時の儒者達が 先達の書にある文字の語彙にのみとらわれ 大意を理解しようとしないのを 快く思っていませんでした。
「語彙などは儒者の雪隠である。 無ければならんのだが 時々その臭気が鼻をついて堪えられない。」 と言って 学者気取りの儒者たちを罵倒していたそうです。 なかなかうまいことを言うもんです。
徂徠 新年を知らず 04-12-7

ある年の元日に 門人の服部南郭が師の徂徠を訪ねた時のことです。
書室に入ると 徂徠は机にもたれるようにして孫子を開いていました。 髪は乱れ 衣服ははだけたままの様子で 読みふけっていたそうです。
南郭を見つけた徂徠は 「まあ すわりなさい。」 と言うと そのまま彼をとらえ 孫子を論じてやみませんでした。
そして ついにこの日は新年の挨拶をする機会を失い 南郭は後日あらためて挨拶に伺ったそうです。
一九の遺言と辞世の歌 04-12-6

十返舎一九が 天保2年6月 67才でこの世を去る時のことです。
床の中の一九が
この世をば、どりゃお暇(いとま)に、 線香の
煙となりて、灰(はい)左様(さよう)なら
と 辞世の句を読み また 門人に 「わしが死んだら 魂はきっと天に昇るから くれぐれもこのままで火葬にするように。」 と 遺言を残しました。
門人達はその言葉に従い そのまま火葬をすると やがて爆発のような音がして 一条の焔が天に昇ったものだから 弔いにいた者達は皆々驚きました。
よく見るとそれは流星という花火で 一九がかねてから用意をしておいて火葬を命じたからの事でありました。
まったく死に臨んでも 人を弄ぶのが一九らしいというか 彼の魂は 皆が驚いて天を見るのを確かめてから成仏したのでしょう。
(大量の線香花火だった という資料もあります。)
徂徠 書商に命名する 04-12-5

荻生徂徠のところには 5人の書商が出入りをしておりました。
ある日 書商小林新兵衛が 徂徠を訪れたとき 「先生 私にはまだ屋号がございませんので ふさわしい名をつけてやってください。」 と頼むと 徂徠は笑って 「本屋で我が家に来る者の中で おまえのところの本が一番高い。 ちょうど嵩山の山が中国の五嶽のなかで抜きん出てるようなものだ。 どうじゃ 嵩山房というのは・・・ククク。 」 と言いました。
そんなわけで 新兵衛はその名を屋号とする事になったそうです。
ちなみに 今も出版や古書,古美術を扱う店に「嵩山房」という屋号をみかけるが はたして小林新兵衛の子孫なのか暖簾分けしたものなのか 全く関係ないのか どうなんでしょう。
ついでに 藤沢周平の小説に葛飾北斎と安藤広重がはじめて顔を合わせたのが 嵩山房の座敷となっています 面白い場面ですが 出所が小説で 資料は見ていないので その場面は却下。
東湖 大久保利通を戒める 04-12-4
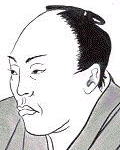

江戸末期に際して 諸藩の勤皇の志士は 常に藤田東湖の教えを受けるという時期がありました。
薩摩の西郷や大久保らも 東湖の門をくぐり留まって学んでいました。
そのなかで 大久保は弁論縦横無尽 人を凌ぐ様子であったそうです。
そこで東湖はこれを戒めようと思い ある日書生を集めて 順次にそれぞれの性癖を述べて戒めていました。
皆 押し黙って 神妙に東湖の言葉に頷いていましたが 大久保の性癖について語ろうとすると 「先生 僕の欠点は何です。」 と 大久保のほうから声を出してきました。
すると東湖は一睨みして 「君の欠点はその多弁で 出過ぎるところにある。」 と言い おもむろにその饒舌を戒めるべきことを教え諭したので 流石の大久保も深く恥じて それ以降は慎むようになったそうです。
東湖 象山と絶交する 04-12-4
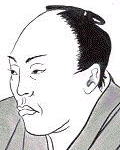

藤田東湖と佐久間象山は ともに時代の先覚者であったが その二人の意見はまったく一致する部分がありませんでした。
ある日東湖は象山を訪れて 互いに時事を語らいその意見を戦わせたが 象山は開国派の頭目で 東湖は攘夷派の領袖であったのだから その説は歩み寄ることなど 全く出来ませんでした。
ついに二人は声を荒げて 「君のような人とは絶交する!」 と言い放ちました。
そして 東湖が足音勇ましく帰るときになって 「それではまたお目にかかろう。」 と言うと 象山は 「すでに絶交した者に また遭う必要はない!」 と嘲り笑いました。
「そうではない! 兵馬の中でお目にかかり その首をいただくと言うのだ!」 東湖は怒鳴りたてて帰ったそうです。
一葉 物貰いに礼を言う 04-12-3

女流小説家として その天才を認められた樋口一葉ではありましたが 一時龍泉寺町の大音寺前に 子供相手の荒物と駄菓子の店を開いていました。
ある日 店先にひとりの乞食が来ました。
店先で遊び戯れていた近所の子供が 「やる物はないぞ!」と言うと 乞食は 「物を買いにきました。」 と言って 一文銭をいくつか出して塵紙を買って帰るので 一葉は 「ありがとう」 と礼を言いました。
翌日 一葉の師匠の中島歌子女史の宅で歌会がありました。
門を出入りする名士や令嬢達が 盛装を凝らしている中に一葉も混じっているとき ふと 昨日乞食に向かって 「ありがとう」 と挨拶した事を思いだして 何か感じる物があった と 日記に書いています。
小村寿太郎 圓朝を励まして諸大臣をからかう 04-12-3

大隈邸にて宴会が催されたときの事です。
そこには 時の政治家伊藤博文をはじめ 各省の大臣,次官,局長等が連なっていました。
余興として 圓朝の講演がありました。
噺が終わると 博文が圓朝に向かい にこやかに 「圓朝!盃をやろう!」と言いましたが 圓朝は恐れ多くて前に出ませんでした。
すると寿太郎は 当時まだ局長にもなれない一官吏でしたが 控える圓朝にむかって 「圓朝!そのように遠慮する事はない。 早く前に出て盃を受けたまえ。 この席では君がいちばん偉いのだ。」と言いました。
「ヘイ 恐れ入ります。」と圓朝が応えると 寿太郎はさらに 「どうだ 貴様が死んだら跡目を継ぐものはあるのか。」と聞くと 圓朝は 「それが居りませんので日頃残念に思っております。」と言いました。
すると寿太郎は すかさず 「それみろ そこが 貴様がこの席でいちばん偉いところだ。 ここには偉い方が大勢並んで居られるが 元老なり大臣なりが皆死なれても 後ろには後継ぎがいくらでも控えておるからな。」と言ったそうです。
残念な事ですが それを聞いた大臣等々の様子を伝える資料は 見つかりませんでした。
桜間青涯の居留守 04-12-2

江戸末期の画家桜間青涯は 画道に没頭するのみで 妻も子も無く ひとり貧しく暮していました。
雨が降れば部屋の中でも片手に傘を持ち 残る片手で筆を走らせるという有様でした。
それほど熱心であったから 友人の渡辺崋山は 青涯の画を高く評価し 「山水画にいたっては 私は青涯の足元にもおよばん。」 と 門人達によく語っていたそうです。
ある日崋山の弟子の椿山が 青涯の家を訊ねたとき 門は閉じてあるのですが 音がするので 「先生 ご在宅ですか 椿山です。」 と声をかけました。
「先生はお留守でございます。」 と返事がありましたが 青涯の声だったので 「そのお声はたしかに先生でございます。 なぜお留守と言われますか。」 と聞きました。
青涯は笑い声で 「物干しの洗濯物は乾いておりますか。」 と とんでもない事を聞くので 椿山は訳もわからず洗濯物を見て 「きれいに乾いております。」 と答えました。
青涯はこれを聞いて また笑いながら 「洗濯物が乾いていれば 先生はご在宅です。お入りください。 ついでに洗濯物を持ってきてください。」 と室内から言いました。
椿山は ただちに洗濯物を物干しから取って 家のなかに入ると 「失敬!失敬!」 と笑う青涯は なんと素っ裸だったそうです。
吉田東洋を評して 04-12-2

土佐の吉田東洋は江戸末期の名士ではあったが 彼を知る識者達がその人物を語るとき それはまさしく十人十色でありました。
しかし それぞれの評に共通な部分もみえるのです。 とくに辛口な3名の評があります。
伊勢の斎藤拙堂によれば 「あたかも名剣の鞘の無いようなもので ついには自らを傷つける事になるのは間違いない。」
東洋と親しかった松岡毅軒によれば 「東洋は才気溌剌であるが 惜しいことに徳が足らない。」
さらに水戸の藤田東湖は東洋にむかって 「君の才気を用いて 英明な藩主容堂公の政治をお助けするのは 土佐藩のためにはめでたい事ではあるが 君がよく考えを慎まなければ ただ君の不幸ばかりでなく 藩の盛衰にも関わってくる。」と言い。
同じく藤田東湖は 他日に土佐の重臣に 「東洋のような人物が容堂公を補佐するのは まるで気性の激しい荒馬に鞭をいれるようなもので危険極まりない。 東洋の相貌をよく見て御覧なさい 眼中に殺気を含んでいる。 惜しい事だが近いうちに不慮の災難に会うかもしれん。」と言ったそうです。
たしかにまもなくして 東洋は刺客の手に倒れたのでした。
漱石建築学を学ぶ 04-12-1

夏目漱石は帝国大学の予科を出る時 理科や数学の成績が良いので 一時建築科に進みました。 ただそれには もっと大きな理由があったようです。
「俺は変人だ。 このままでは世の中でうまくやっていけないだろう。 だから変人に向くような仕事を探さなければならない。 土木建築のような日常に欠かせない仕事さえすれば 生来のこの性格を変えなくてもすむだろう。 いくら相手が変人でも 必要なのだからおのずと人が頼みに来る。 そうすれば まず飯の食いはぐれはないはずだ。」 と 友人に語っていたそうです。
希典の指1本は百円なり 04-12-1

乃木希典は陸軍大将として日露戦争で大活躍の後 学習院院長を勤めました。
希典は毎月の給料を そのまますべて学習院内に預け置いていたそうです。
ある日 入用の時に 係の者に指1本を立てて 「1つ 貰いたい。」 と言いました。
「いくらですか。」 と訊ねられると 「百円です。」 と答えたので 係員は預っている巨額の預金のなかから 百円を出してわたしました。
すると希典は無造作にポケットに入れ立ち去りました。
それ以来 希典の指1本は百円で 2本は二百円 となったそうです。
諭吉と大隈 犬猿の仲から 04-11-30


明治の初めに福沢諭吉と大隈重信は まるで犬猿の仲ともいえる間柄でした。
もともと官吏嫌いの諭吉は 「大隈のする事は愚にもつかない事ばかりだ。」 と批判すれば 大隈は 「福沢のような世を知らぬ学者なんぞに 私の政策などわかるものか。」 とせせら笑っているありさまでした。
そんな様子を見てある物好きな人が この二人を呼び寄せ同席させることを企てました。
「こちらが大隈氏 こちらは福沢氏です。」 二人を紹介し いかなる事になるかと内心心待ちにしていると 会うのは初めてだった二人は 互いによくよく話し合ってみれば その考えや意見がぴたりと一致しているので それまで犬と猿のように喧嘩しあっていたことが さっぱり訳がわからなくなってしまったようです。
しまいには 「今後は喧嘩をやめて むしろ国家のために歩調を合わせて進みましょう。」 という事になり その後はともに食わず嫌いで毛嫌いしていた二人は 友好をさらに深めお互いの家を訪問しあうまでになりました。
慶応の出身者である矢野,尾崎,犬飼等と改進党の関係を見ても その影響はよくわかります。
象山 鏡をもって人を正す 04-11-30

佐久間象山はいつも鏡を懐に入れていたそうです。
それは自分を戒めるためだと言っていました。
しかし もし人が軽薄極まりない事を言ったときには おもむろに取り出し 「そんな事を言う自分の顔を御覧なさい。」 と鏡を向け 静かに諭していたようです。
瀧鶴台 藩の重臣をからかう 04-11-29

儒家の瀧鶴台が故郷の長州にいる時の事です。
藩の重臣と酒を飲む機会があり その時 「政治をするのに日本と中国とでは どちらが簡単か。」 と聞かれました。
鶴台は 「中国は難しいが 日本はたやすい。」 と答えました。
これを聞いてその重臣は 「それはどういうわけで。」 と さらに訊ねると 「中国では不学の人に政治をしてもらうのを 恥ずかしい事と思うのですが 日本では愚かな人が政治をしていても 皆平気でいるから 日本のほうが簡単で中国のほうが難しいのです。」 と説明した。
しばらくしてその重臣が 大真面目な顔でその話を藩主にすると 藩主はその重臣の顔を見て 笑いながら 「それは鶴台がおまえらに当てつけたのじゃ。そういうことを言ってくれるのはあの男だけじゃ。」 と教え聞かせたそうです。
象山 金満家への道を説く 04-11-29

いつの頃かは不明ですが ある人が佐久間象山に 「先生は何でもご存知と思いますが どうか大金持ちになる方法を教えてください。」 と訊ねた。
すると象山は 「それはたやすい事だ。小便のときに片足を上げてするようになさい。」と言った。
その人は 「それではまるで犬のようですが。」 と言うと 象山は 「そのとおり。 人情を持つ限りは金持ちなどにはなれませんから。」 と言ったそうです。
益次郎 酒盛りの音 04-11-28

大村益次郎がまだ青年の頃です。
友人と集まって話し合っていると 近隣の料理屋から宴会の三味線やら嬌声で 喧しくて仕方がなかった。
友人が益次郎に 「あれはいったい何の音だ。 うるさくてかなわん。」 と言うと。
「あれは金の逃げる音じゃ。」 とのみ答え まったく気にしなかったそうです。
勝海舟の首 04-11-28 
徳川幕府が初めて咸臨丸をアメリカに渡航させたときの事です。
まもなく港につく頃となり アメリカの祝砲に応じて こちらも祝砲を放つべきかどうか 艦内幹部で議論となりました。
艦長の海舟は 艦内の誰も祝砲の経験がない事から 「失敗して外国人に笑われるよりは むしろやらない方が良い。」 と考えたのです。
しかし 大砲運用方の佐々倉桐太郎が 「艦長閣下 私が必ず成功させます」 と言うと 海舟は 「馬鹿な。おまえが見事に出来たなら俺の首をやるよ。」 と罵り からかいました。
桐太郎は 「必ずやってみせる。」 と言いきり そして応砲に見事成功したのです。
桐太郎はこのとき 「勝艦長の首は俺のもんじゃ! けれども航海中は忙しいから しばらく当人に預けておく!」 と大喜びで叫んだそうです。
福沢諭吉の肝っ玉 04-11-27 
大阪にあった緒方洪庵の適塾を出て 江戸にいた頃の事です。
ある夜に今の新橋駅付近を通りかかった時 月明かりのなかに 向こうの方からひとりの武士が ツカツカと急いで進んでくるのが見えました。
当時は攘夷熱が盛んで 目の敵とされていた洋学を研究していたものですから 諭吉は切り殺されると思い 足がすくみました。
しかし 志ある者として 此処で逃げるわけにはいかないと勇気を奮って進んだのです。
刻々と近づいて お互いが肩をそびやかして通り過ぎる時 その肩と肩がコツンと突き当たりました。
その途端 諭吉も相手もびっくりして それまでの見栄をほっぽって 振り返りもせず お互いが走って逃げてしまいました。
後に 諭吉は福翁自伝の中で 「さても臆病者と臆病者との衝突で、世の中にはおもしろい揃いもあるもんじゃ!」 と書いています。
![]()