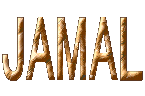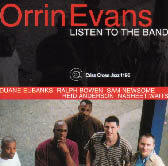|
|
|
||
| フリー・モーダル・リリカル・ファンク・・・なんでもござれ。 | |||
| こんどはフリー・ジャズに足突っ込んだのかよって思われたかも知れないけど、確かに興味が湧いてきたんだけど、僕としては用心深くそれこそ石橋を叩いて渡ろうかという気構えなわけ。石橋を叩く・・・バング・バング・ブリジストンですな。私の知り合いに石橋ってのがいて・・・ってもうネタはばれたか。やめとこ。で、この盤がフリー・ジャズへの橋渡しかって?そうとも言えるし、違うとも言えるってとこで難しいですな。ちょっと前の僕なら1曲目を聴いてあちゃ失敗したって投げてたでしょうが、今度は果敢におっしゃぁフリー・ジャズだぜって意気込んでいたら、その後で裏切られたって具合で喜んでいいのやら悲しんでいいのやらですわ。まあそんなところをかいつまんで書いてみましょう。なんせトータル時間が長い。最近意気地がないってのか腰が引けてるってのか、長尺ものは苦手になってしまって、だからいちいちあーだこうだ書いてられないって感じで、どうも駄目ですな。そんなことぐだぐだ書いてるんだったら先進めって?ま、そうですが。だからどうしても50年代ものを出してしまいがち・・・早くやれ? んだば、やっか。最初フリー、中モーダル、途中またフリー・・・ってこれじゃ駄目だよね。第一イントロなーんにも書いてないじゃん。ああ・・・もう駄目。へこたれた。明日にしよ。 (で、翌日早朝)そろそろいこか。まずイントロね。Orrin Evansについては何度も紹介してるし、サイドマンとしてもそこそこ活躍していて、僕は彼のGrownFolk Biznessってのが一番気に入ってるんだ。で、色々集めた中のひとつがこの盤だね。リリースされたのがGrown...の次くらいに来るらしいけど、すっかり忘れてたけど、この盤にもRalph BowenとSam Newsomeが入っていて3曲はこのホーン入りってことと、以前書いたものを読んで結構フリー・インプロバイズもやってたんだってことがわかった。駄目だね。好きな盤と言いながら大して聴いちゃいないんだから。(というところで今度は風邪薬が効いてきて眠くなったので一眠り) で、やっと本番だ。非常にリリカルな出だしで来るI want to be Happyでおーっという感じで聴いていると、来たきたNewsomeのソプラノがジワジワと入ってきて段々状況が怪しくなってくるんだ。ベースやらドラムがざわついてもうNewsomeはフリー・インプロバイズに突入だ。金切り声を上げるソプラノ。それに被さるNasheet Waitsの激しいドラミング。阿鼻叫喚ってとこだな。やっと体制取り戻したかという感じのEvansのピアノだけど、これも結構フリーってる。(これ造語)もうドシャメシャの感じになって止め知らずの状態だな。ドラムとベースがドロドロとやって終わり。 次がぐっと感じが落ち着いてモーダルなテーマのIn his Place。3管でのアンサンブルが雰囲気を出しているな。今度のNewsomeはまとも。(まともって言い方もヘンだけど)今度は落ち着いて聴いてられる。結構ドラムが変化をつけていいんだ。Evansはモーダルでセンシティブなピアノを弾いてくれている。こういう彼のピアノが好きだな。Bowenのテナーが入ってきて痺れるな。彼の略歴は右に書いておくね。うねり方も素敵だ。ここでReid Andersonのベースが少しだけピックアップされている。次第に怒濤感が湧いてきたかと思えば静まっていくという感じで唸るな。 次はEvansのオリジナルでMat-Matt。最初に出てくるのがBowen。いきなりインプロバイズで来てる。ベースとドラムでアクセントをつけてDuane Eubanksのトランペットが来てる。これもかなりフリーな感じ。で、Evansの切れのいいピアノが飛び出す。ベースとドラムとの釣り合いが抜群だね。 次のThere is a quie placeがいいんだ。Evansのしっとりとしたピアノがもう最高。たった3分ちょっとだけど素晴らしいね。リリカルで繊細で歌心があって、凝縮されたピアニズムが堪らない。僕はいくらフリーに足をかけたとしても、こういうのは絶対大事にしたいね。 次はEvansの低音ラインから入るFor Miles。急に怒濤の渦に入り込むスリル。これはスゲー。モード的展開になってBowenのテナーがうねるね。実に激しい。まるでColtraneサウンドを聴いている感じだ。少し落ち着かせるようにEubanksのペットが入る。これも徐々にパワーアップしてくる。はち切れんばかりのペットとドラムのぶつかり合い。そこへEvansが入ってきてグングン押し込むように弾くピアノはもの凄いね。これもドラムとのバトルだ。圧巻。Waitsのドラム・ソロが来る。スティックが見えてくるような激しさだな。モーダルなテーマに戻って終わりだ。 ここらで一息いれないと保たない感じ。 さて後半戦だ。後半最初はフリーのDorm Lifeだ。Newsomeのソプラノがピーヒャラ、ピーヒャラ・・・。それに被さるピアノとドラムが徐々にパワーアップしてくる。来るぞ来るぞって感じでNewsomeの激しいフリー・インプロバイズだ。それがふっと途切れるとEvansのピアノとAndersonのベース、そしてWaitsのドラムが複雑に絡みあって怒濤へと誘う。タイミングを見計らったかのようにAndersonのベース・ソロが入ってくる。これはききものだ。そこにWaitsのシンバルが入ってきて急に終わる。 次はW.Shorterでも書きそうな曲のForgiven。漠々たる感じでそこにAndersonの重量感のあるベースが呻る。Evansのリリカルでいながらフリーっぽさもあるピアノ。で、元のテーマに戻っていく。 やっと最後だ。EubanksのオリジナルでDiva Black。ファンクな感じのリズム。かと思ったらモーダルな怒濤が押し寄せる。フリーっぽくもある。何でもありだな、こうなると。で、長い。だからここらで自らフェイド・アウト。 |
 Ralph Bowen:ts,as 80年代O.T.Bっていうユニットで活躍していたんだ。紳士的な顔立ちだけど結構凄いテナーを吹く奴だなって思っていた。そうかこんなとこでお目にかかるとは思ってもいなかった。ってこれで彼の略歴ってことにして。駄目? |
||