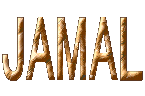|
|
|
|
||
|
|
ここまで来た日本のジャズ! |
|
||
|
|
|
|
||
|
日本のジャズがこれ程進化発展したという実感を抱いたアルバムだ。洗練されたコンセプト演奏技術、演奏のダイナミックさと研ぎ澄まされた感覚。もうこれ以上言うことなど必要ない。とにかく圧倒される。南博は1960年生まれ。サックスの竹野昌邦は63年。ベースの水谷浩章は63年。ドラムの芳垣安洋は59年。働き盛りの年代だ。頼もしいと言うほかない。日本のジャズという括り自体が意味をなさないレベルを持っていると感じた。僕は今最高に期待をかけたい一群だ。これがファーストアルバムであり、既に第2作も出した。日本のジャズユニットの永続性といいうのは、それ程長続きしないと思っているから、彼らがいつまでこの組み合わせでやってくれるのかは、知らない。しかし、たとえ彼らが発展解消したとしても、またあらたな細胞を増殖してくれることと思っている。 |
|