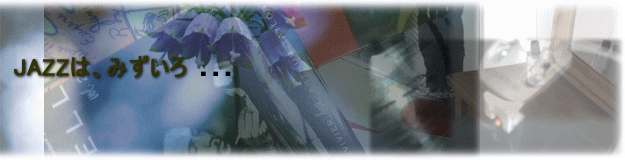|

|
|
MICHEL SARDABY
AT HOME
MICHEL SARDABY-p
RAY DRUMMOND-b
WYNARD
HARPER-ds
April 18 2004
SOUNDHILLS
|
|
1.JUST ALL OF US 2.LULLABY OF THE LEAVES 3.WHEN I
REMEMBER 4.EVIDENCE 5.SARDABY 6.WITH FULL OF LOVE 7.A TIME FOR LOVE 8.JUST ALL
OF US 9.SOMEONE TO WATCH OVER ME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
それは彼女の『阿修羅のごとく』が映画化されたのが切っ掛けだったが、たまたまその原作が書店に無かったために、代わりに買ったこの『父の詫び状』というエッセイが、思いのほか気に入って読んだ。これを読みながら、僕は何故女流作家、あるいは随筆家のものを気に入って読んでいるのかと、少々怪しげな性癖を疑ったりもすることがある。確かに僕は、マザコンの毛がないとは言えない。マザコンの僕がファザコンの向田のものを読む等は、おかしなものである。向田のことをファザコンと言ってしまったが、男の子は母親に、娘は父親を慕うという心情は、特段異常なことではあるまい。懐かしさの混じった臭いごと自分の懐にそっと仕舞っておくものではないだろうか。だから僕も普通なのだ。
しかし、そういう類の愛着というより、彼女らの筆致の細やかな生活感に親しみと共感を感じたからと言う方が当たっているだろう。
僕の母は、祖父である父親を尊敬しきっていた。それは夫である僕の父が嫉妬し僻みを感じるほどの慕い様であり、向田が自分の父親のことを性懲り無さも含めて慕っていたのとは、些か違っている。大抵、慕う心には幾分でもこの性懲りなさを寛容さで許す気持ちを含んでいるものだと思う。酒クセが悪いとか、家族に対する横暴さとか、変な癖とか・・・そんなものいっさいがっさいを、父親という存在感の中にひっくるめて許してしまう。それが普通の慕う心ではないだろうか。
ところが、僕の母は自分の父親を完全なものとして慕っているように僕にはみえた。確かに、落ち度のない高潔な人ではあったが。
そういう見事なファザコンの例で、森茉莉のことも思い出す。
文豪鴎外の娘で、彼女のものに『父の帽子』というのがある。
ともかく、向田の『父の詫び状』には、誰もが懐かしむ昭和の父親像が描かれているし、身の回りに起こった出来事の些細なことが、自分の昭和史とだぶってひどく懐かしく思えるのだ。
|
さて最近出たM.サダビーのアルバムが彼の父に捧げられたもののようだ。AT
HOMEというアルバムでTRIBUTE TO MY FATHERとある。自宅で録音されたものだ。
サダビーはオリジナルが良いという定評通り今回も哀感の籠もったWHEN I REMEMBER
やSARDABY(TRIBUTE TO MY MOTHER)のような自作曲を演奏している。
彼の書いた曲は耳に残り、聴き直そうする以前からもう僕の頭のなかで鳴っている。
これは一貫して彼のどのアルバムでもそうだ。一番最初に手に入れたBLUE SUNSETしかり、最近漸く念願のNIGHT
CAPを得たが、これまたそうである。
ザックリとした音づくりで、リズミックな音列の「間」に哀感が籠もっている。ダラダラとラインを繋げるタイプじゃない。後乗りの旨みが渋みのあるチョコレートが口のなかでジワっととけていくようだ。
今回のサイドマンは若手のドラマーW.ハーパーとベテランのB.ドラモンドで、サダビーの自宅で録音したというだけに、生々しい音が間近に感じられる。切れの良いスティックがシンバルやその他のドラム・セットに当たる音の心地よさと、いつもはベース・マイクを使っているのだと思うが、ボワーっとした音が嫌だったドラモンドのベースが、ウッドな生の響きを聴かせている。
T.モンクのEVIDENCE他のオリジナル以外も、いつものサダビーが聴ける。
今回のこのアルバムでは、ボサノヴァタッチのJ.マンデルのA TIME FOR LOVEが殊の外いい。
サダビー・ファンならやはり持っていたい一枚だろう。
|
|
|
|
|

|
 慕う
慕う