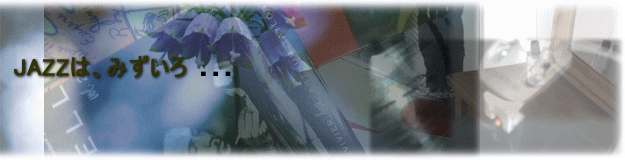|

|
|
BABY FACE WILLETTE
FACE TO FACE
FRED JACKSON-ts GRANT GREEN-g BABY FACE WILLETTE-org BEN DIXON-ds
1961.1.30
SIDE 1
1.SWINGIN' AT SUGER RAY'S 2.GOIN' DOWN 3.WHATEVER LOLA WANTS
SIDE 2
4.FACE TO FACE 5.SOMETHIN' STRANGE 6.HIGH 'N LOW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正月七日も過ぎたが、あまり季節感のない暮らしぶりだったなあ、と思う。
元旦、2日と年賀状が届き、テレビで正月恒例の番組をやっていたのだろうがそれも殆ど見ず。お節料理と餅つき機でつくった餅の一杯入った雑煮を食べたぐらいが正月気分であったのかも知れない。
季節感など衣替えをするとき位が精々で、日常からどんどん薄らいでしまっているけれど、それを感じないからといって支障があるわけでなし、便利な日常品が身の回りに増えていくに連れ、どんどん流されるように人の感覚から遠のいていくのだろか。
今年は戦後60年。戦後が定年を迎えたということで、新聞の一画に特集記事が載っていた。コカコーラが戦後まもなく進駐軍の必需品として日本に輸入されて、僕の記憶でも小学生の頃には、極めて風変わりな味の飲み物として市場に出回り始めたのを憶えている。これがアメリカの味かなんて当時の小学生だった僕は思いもしなかったが、それからどんどんファッションもアメリカナイズしていったのだろう。
でもあの頃まだまだ日本中が漸く貧乏から這い出したばかりで、北海道という地域性もあったろうが、冬には手編みのセーターに靴下が日常身につけるものだったし、石炭ストーブの燃える茶の間の天井から雪で濡らして帰ってきた僕らの冬支度がほかほかと湯気を上げていたものだった。
まだまだ貧乏だった。アメリカなど別世界のことだった。
コーラの話に戻るが、近年清涼飲料水の嗜好が変わってコーラが売れなくなってき、変わりにお茶類がシェアのトップを占めるようになってきたと紙面に書かれていた。なるほど確かに。
そんな様変わりする日本人の食べ物飲み物の嗜好や、興味関心の変遷、それに行政の容赦ないシステムの転換、そして季節感を失っていく生活なんてのをを眺めていると、なんとはなしに「無常」だなという気分になってしまう。
いっそ世の果て地の果てで浮き世からひっそり身を潜めてしまいたい気にもなる。
無常を噛みしめ数寄の遁世のなれの果てが、浮世離れしたジャズ喫茶のオヤジでもいいかも・・・と、あらためて思うこの頃である。
------------------------------
|
さて、世の中の無常を言えた義理ではない。僕の心変わりもいっぱしである。
今度はオルガン・ジャズに目覚めた・・・という程のことでもないのだが、ベイビー・フェイス・ウィレットだ。
BLUE NOTEの4000番台を集めていると、どうしたって出てくるのがこのオルガンの存在。
1500番台にはジミー・スミスしかいなかったオルガニストが、4000番台となると俄然花盛りとなる。
僕にとってオルガンは、一番遠ざけていた楽器だった。ピアノに比べて如何にも大雑把で、且つ感情過多、という印象を長年持ち続けていたし、音楽的にもR&Bやソウルといった真っ正面からジャズを感じるものではなかった。ハモンド・オルガンであるからアコースティックでもない。総じて「知性」が感じられないという理由である。
如何にも中途半端な「知性」を保持する黄色人種である日本人的偏見に他ならないわけだ。言い換えれば、黒人のソウルをわかっちゃいないだけなのだ。
で、頭でっかちは頭でしかわからないのは致し方ないけど、知識だけは知っておこうと思って、ピーター・バラカン(彼だって白人だ)の書いたものを読ませて貰った。(『ブルーノート再入門』7章「ソウル・フィンガーズ!」)
なるほど、時代背景を知れということなのだが、一番応えたのがハモンド・オルガンを備えた黒人街にある無数のバーやナイトクラブである「チトリン・サーキット」の存在だ。豚のモツ煮込みであるチトリンというソウル・フードも喰った事のない奴にオルガン・ジャズを云々する資格はない・・・というわけである。
でも、なぜだかこのウィレットのアルバムを聴いていて連想したのが、正月の雑煮だった。鳥肉や大根、にんじん、菜っぱ等と一緒に煮た餅が入った雑煮。チトリンとちとリン似てないか?(負け惜しみ、負け惜しみ・・・)
J.スミスの次に来るオルガン奏者と、G.アモンズの流れを汲むF.ジャクソンという組み合わせ、加えてギンギンのR&B調のG.グリーンのギター。と来れば、絵に描いたようにどっぷりソウルフルだろうなと思いきや、ロングトーンをあまり多用せず、小気味よいスタッカートをきかせて弾くウィレットのオルガンと小刻みにカットするグリーンのギターであって思いの外粘っこくない。
さっと焼いた餅が形を崩さない程度に煮てあって、粘りはあっても硬く締まっている餅の食感、それが具の食感と合わさる雑煮の風味?
だから嫌味のない程度にソウルフルで、少々時代かかったジュークボックスかディスコで流れるメロディを感じさせるテーマだが、陽気で軽快に踊る気分なのだ。
スローなブルース仕立てのGOIN' DOWNとなると流石にぐっと粘りが出て、黒人のソウルフルな血がドクドクと脈打つ感じだ。F.ジャクソンのテナーがむせび泣き、裂ける。
WHATEVER LOLA WANTSは昭和の歌謡曲にこんなのあったよな懐かしい気分で、少々含み笑いも出ようというものだが、所謂懐メロ風だが、時代の空気が伝わってくる。少し侘びしくせつない、昭和枯れススキ?という雰囲気か。いやいや労働に疲れた貧しい黒人の心を慰める哀切なメロディだったのだろう。
世知辛い世の辛さ侘びしさが冬の夜風のように身にしみて、ああ無常(無情か)・・・。
でもこのアルバム、仄かな哀しみが熱気の隙間から滲みだして来るけど、断然軽快で暗い気分など跳ね返すバイタリティに満ちている。それがかえってせつないのだが。
|
| |
|
|
|

|
 ああ無常・・・
ああ無常・・・