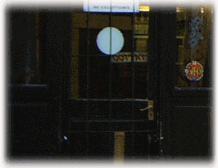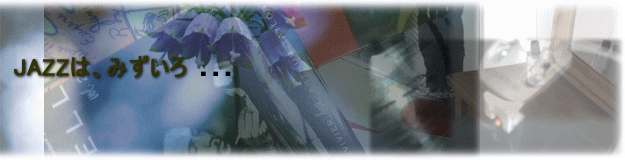|

|
|
IRON MAN / ERIC DOLPHY
ERIC DOLPHY-
RICHARD DAVIS-b
CLIFFORD JORDAN-ss
HUEY(SONNY) SIMMONS-as
PRINCE LASHA-fl
WOODY SHAW JR.-tp
ROBERT(BOBBY) HTCHERSON-vib
EDDIE KAHN-b*
J.C.MOSES-ds
Jul 1, 1963,Jul 4, 1963
EPIC
SIDE 1
1.IRON MAN* 2.MANDRAKE 3.COME SUNDAY
SIDE 2
4.BURNING SPEAR 5.ODE TO C.P.
|
 |
CONVERSASIONS/ERIC DOLPHY
(CELLULOID)
|
SIDE 1
1.JITTERBUG WALTZ 2.MUSIC MATADOR
SIDE 2
3.LOVE ME 4.ALONE TOGETHER |
 |
OUT TO LUNCH/ERIC DOLPHY
(BLUE NOTE) |
|
|
そう言えばアンプを管球にかえてから聴いてなかった。澤野の音の質感とこのアンプは相性がいいなと思う。
この前SJを立ち読みしていたら、オーディオのコーナーでカイン・ラボラトリー製の管球アンプが紹介されていた。価格の割に・・・と評価されている。それで少し良い気分で、ジョー・チンダモやヨス・ヴァン・ビーストなどをかけている。
--------------------------------------
最近手に入れて気に入っているものに、エリック・ドルフィーのCONVERSASIONSというのがある。
ドルフィーというとどちらかと言えば鬼面、強面、実直、純粋・・・という印象が強かったのだが、このアルバムの出だしですっかり心赦してしまった。
何せJITTERBUG WALTZときてる。
ドリフィーがJITTERBUG・・・というだけで嬉しくなる。
で、次もプリンス・ラシャとソニー・シモンズによる陽気なMUSIC MATADORという南国風の曲。
この2曲聴いただけですっかり気持ちのたがが緩んでしまう。
しかし、一面長閑に聞こえるこの花園的音楽が頗る楽しく思えるのは、実はドルフィーの別の面を知っていたからなのでは・・・という気にもなった。
演奏の細部に気を配れば見えてくる筈のドルフィーの裏も表も、いや二面だけはなく、幾面もの多角な面が光の当たり具合の陰影の違いで異なって見えるように、ここで見えるドルフィー像もまた陰影の異なる同じドルフィーなのだ・・・という気がした。
ほぼ同じ時期に同メンバーによって記録されたIRON MANを聴いた。
同じ時期同じメンバーにして、こうまで違うかといううねり狂ったドルフィーの姿がある。JITTERBUG
WALTZを長閑にやっていた彼らとは到底思えない。極限的なソロをぶつけてくるドルフィー。不協和音を重ね、エネルギーを発散しドルフィーの音との屈折を起こすウッディ・ショーにボビー・ハチャーソン他のリズムセクション。
いや、ドルフィーのアルト等が既に鋭い光の屈折を放っているところへ更に・・・だ。
怒濤のさなかにも構成力を感じさせ、眩惑を感じつつも「音楽」としての実体があるのを確認できる。
このIRN MANに近いものを挙げるとすれば、やはりBLUE NOTEのOUT TO LUNCHかも知れない。
メンバーこそ多少違うが、ハチャーソン、R.デイヴィスを伴っての演奏だ。フレディのトランペットはウッディ・ショーのそれと重なった印象も受ける。ドラムがトニー・ウィリアムズというところが、音の屈折具合もまた更に違って聞こえるが。
敢えて言えば、長閑なJITTERBUG WALTZを含むCONVERSASINSのドルフィーも鮮烈な音の屈折して錯綜するIRON
MANもそしてOUT TO LUNCHもドルフィーの音楽性のなかでは、何ら異次元のことではなく、ドルフィーは「ドルフィーというひとつのジャンル」を築いたというある人の言葉を実感するだけのことだと言える気がする。
優れたテクニックで飛翔するODE TO P.C.のようなフルートの演奏は、ドルフィーのもうひとつの面であろう。彼のアルバムを何かひとつ選べば、ほぼ必ずこういうのを披露してくれる。リチャード・ディヴィスとのデュオで広がる音空間。
孤独と安寧が共存した空間美がある。
これはCONVERSASIONSのB面にもある。
アルト一本で奏でるLOVE MEやバスクラとリチャード・ディヴィスのベースとのデュオでやるALONE TOGETHER。
テクニックと音楽性の鍛錬に最晩年までチャリー・パーカーの曲を練習していた彼だが、そんな目に見えない苦行がこうして彼独自の音楽世界に実を結ばせているのだろうと思うにつけ、修験者的趣をこの音楽に感じる。
ドルフィーは二人いない・・・という当たり前のことを思えば尚のこと、実感をもってドルフィーを興味深く感じ、末永く追い求める価値のある人だと思える。
|
|

|