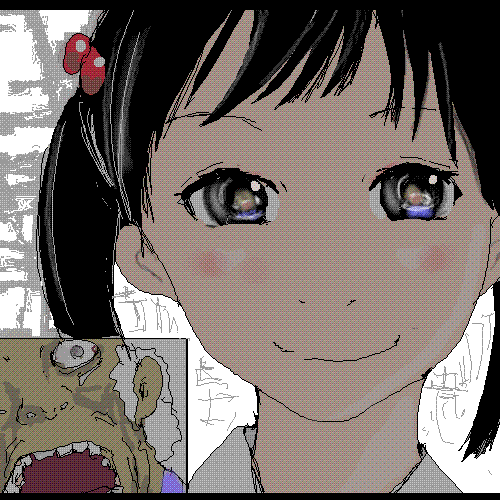
目覚めれば・・悪夢
イラスト・紅珠さん
「う、う〜ん」
俺は目を覚ますと、今にも崩れ落ちそうな廃工場の床に縛られて転がされていた。
「おれは・・・確か奴のネグラを見つけ、奴を捕らえようと女のマンションに・・・」
奴が潜伏していると情報を得た高級マンションに、一人で乗り込んだのだが、ドアを開けたとたん、甘い香りが顔にかかりそのまま気を失ってしまった。
「何で俺はこんなところにいるんだ。奴はどこだ」
錆だらけの支柱を使って、俺は身体を起した。剥がれ落ちたトタンの屋根や崩れ落ちた壁のから差し込む光に照らし出された廃工場の中は、何もなかった。人気はおろか、猫の子、いや、カラス一匹いなかった。
『一体どうすればいいんだ』
俺は途方にくれてしまった。こんな時、映画なんかじゃ、誰かが気付いて助けに来てくれるのだろうが、現実ではそんな事は、ありえない。俺はこのまま衰弱死するしかないのだろうか?そんな思いが俺の頭をよぎった。
『かっこつけて、一人で乗り込むんじゃなかったなぁ』
テレビや、映画の刑事モノの見すぎで、単独行動や、過剰捜査のやりすぎで、俺は内勤に回されていた。今回の事も、仮病を使ってやったことだった。でも、奴を捕らえられたら、現場復帰も夢じゃなかったはずなのだが・・・
『懲戒免職』の文字が、さっきから俺の頭の中でフレンチカンカンを踊っていた。
「おじいさん、こんなところで何をしているの?」
いつの間に現れたのだろう?髪を赤いプラスチック製のリボンの付いたゴムバンドで左右に縛った10歳ぐらいの女の子が立っていた。
「き、君は誰だ。どうしてこんなところにいるんだ」
「あら、それはおじいさんもでしょ?ここは取り壊し予定の廃工場よ。立ち入り禁止のはずよ」
「そういう君もそうだ・・・と、その前に、俺はおじさんじゃないぞ。まだ三十前のお兄さんだ」
「あら、三十だったら、おじさんよ。でも、私が言ったのはおじいさんよ」
「おじいさん?お前は目が悪いのか!俺の何処がおじいさんだ」
俺はこのこましゃくれた女の子の態度に無性に腹が立ってきた。
「でも、おじいさんよ。自分の顔を見たことがないの?」
そう言うと、女の子は、スカートのポケットから小さな鏡のようなものを取り出して俺の前にかざした。
「?」
女の子のかざしたモノの中に、両脇に、お情けで髪の残っているボロボロの歯をした皺チャくれの老人の顔があった。
「??」
俺は、自分の祖父であろう老人の写真を俺の目の前にかざす女の子の真意がわからなかった。
「何を考えているんだ?」
俺は不思議そうに女の子の顔を見つめた。女の子は、薄ら笑いを浮かべながら、手に持っていた鏡のような写真ケースの角度を変えた。
すると写真に写っているものが変わり、俺が着ている服と同じ物が写っていた。女の子は、角度をゆっくりと上へと動かした。
写っているものが徐々に変わり、やがて彼女の手に持っている写真ケースには、俺の着ている服と同じモノを着たさっきの老人が現れた。
「え?え、わわ、わわぁ〜〜」
彼女のかざした小さな鏡と、その瞳に、驚きで目と口を大きく見開いた老人が映っていた。
俺の名は、本郷健一。H県警総務課の署員だ。少し前までは、県警の捜査課の刑事だった。俺はある事件を追って、少しやりすぎてしまった。そのために第一線からはずされ、閑職へと回されてしまったのだ。
「な、なんで・・・どうして、俺がこんな老人になってしまったのだ。いったいなんで・・・」
「うふふ、おじいさん。元の姿に戻りたい?」
女の子は、微笑みながら言った。その妖しげな微笑に、なにかいやな物を感じたが、俺はその問いに答えた。
「当たり前だ。この姿では奴を追いかけることは出来ないじゃないか。これじゃあ、誰も、俺だとは信じてはくれないだろう」
「そう、それじゃあ、わたしと契約を交わす?」
「けいやく?」
幼い女の子からそんな言葉が出てくるとは俺は夢にも思ってはいなかった。テレビの影響か何かなのだろう。俺は小ばかにしたように女の子を見た。
「お嬢ちゃん、難しい言葉を知っているんだねぇ」
「うふふ、おじいちゃん、人を見かけで判断してはいけませんて、親から言われなかったのかしら?ああ、今は学校で躾けはされるのね?いいわね、今の親は楽で・・・」
女の子は、大人を小ばかにしたような言い方をした。俺はその態度に腹が立ってきた。
「お前こそ、親に言われなかったのか?目上の人との口の利き方を・・・」
「目上?ふふふ、まだ見た目に惑わされているのね」
そう言うと、女の子は何かゴニョゴニョと唱え始めた。
「クネクネコネコネめたもるぱわ〜〜」
女の子がそう唱えると、彼女の身体が、ぐにょぐにょと形を変え始めた。
そして・・・
「これでどうかしら?少しは生意気な口を利いてもよろしくて」
俺の目の前には、神をショートのカッティングした三十代前半の美女がにこやかに微笑んでいた。
「こ、これはいったい・・・お前は・・いや、あなたは誰なんですか?」
「うふふ、口の利き方が変わったわね。まだ見た目で判断する癖は直らないみたいね。まあ、いいわ。わたしはこういうものです」
そういうと、その女性は一枚の名刺を俺の前に差し出した。
『 あなたのお望みの姿に変えて差し上げます
魔性 化夜 』
「ましょう、けや?」
「ましょうかよ。セールスレディよ。お客様の望む姿に変えて差し上げるのが私の仕事なの」
「ほ、本当に姿を変えられるのかよ。俺を元の姿に戻すことができるのか?」
「ええ、あなたが思い描く姿にね。もちろん、ただじゃないわよ」
「い、いくらかかるんだよ。俺は安月給の地方公務員だから、貯金なんてないぞ。それに、手持ちもあまりないし・・・」
そういうと、俺は尻のポケットの財布を取り出そうとして、まだ縛られたままなのを思い出した。
「オイ、この縄を解いてくれよ」
「商談が成立すればね。頂く代償は、あなたの要らなくなったものよ。いかが、契約する?」
「いらなくなったものって何だよ」
「それは企業秘密よ。でも、本当に不要になるものだからいいでしょ?」
俺は女の言葉に一抹の不安を感じたが、この姿から逃れられるのならば、悪魔にでも魂を売る覚悟ができていたので、承諾した。元に戻ったら、難癖をつけて契約破棄をすればいいのだから・・俺の口元がかすかにほころんだ。
「うっととと」
俺は今俺が笑ったのを女の気づかれたかと思ったが、女には何の変化もなかった。さっきと同じように微笑んでいた。
「さて、はじめるわよ。なりたい姿をしっかりと思い描いてね。いいわね」
「ああ、わかった」
俺は元の俺の姿を思い描いた。そして、元の姿に戻ったとき、必ず奴を捕らえることを心に誓った。
「ところで、あなたが追っていた人ってどんな人なの?」
女が何気なく俺に聞いてきた。
「奴か、奴は、結婚詐欺だ。純情そうな顔しやがって・・・何人もの男を騙して、金を巻き上げているんだ」
「フフフ、そうなの。ひょっとして刑事さんもやられた口?」
「な、なにをバカな・・・俺は、そいつを長年追っているだけだ」
女の問いかけに、俺は奴の顔を思い出していた。
端正な顔立ち,ちょっと見は、どこかのお嬢さんと言った感じのする上品さがあった。それに俺も騙された。
俺が、捜査課から内勤にまわされる少し前、変な男に付回されていると言って、奴が警察署にやって来た。たまたま、その警察署に用があって来ていた俺は、彼女の話を聞き、その不審者を捕まえてやった。それが縁で、俺と彼女は付き合いだした。
彼女は、地方の資産家のお嬢様だった。箱入のままでは、今の社会やっていけないので、社会勉強のためにこちらに就職をして、一人暮らしをして折とのことだった。生活費も自分の働いた分で賄わなければならず、かなり質素な暮らしをしていた。
そんないじらしい彼女を俺は何かにつけて面倒を見ていた。そして、世間知らずの彼女は、知人の保証人になって、莫大な借金を背負い込んでしまった。
親元に話せば出してもらえる金額なのだが、一人で置いとくのは危ないと、親元に引き戻され、結婚をさせられるだろうと言うのだ。
まだ、こちらに居たいと涙ながらに告げる彼女のために、俺は退職金と、警察共済に借金をして、彼女にその金を用立てた。そして、その金を受け取った直後、彼女は俺の前から姿を消した。
詐欺の被害者になった警察官。それは、あまりにもみっともないと、俺は第一線から内勤に回された。俺が捜査課から移動になった真実はこういうことだ。表面的には、行き過ぎの捜査が問題になったからと言うことになっているが、県警内では誰もそんなことを信じてはいなかった。それからも、俺は、彼女・・いや、奴を探し続け、やっとそれらしい女を見かけたと言う情報を得て、奴の部屋と思われるところに行って、このざまと言うわけだ。
俺は、ますます奴の顔を鮮明に思い出してきた。
「ちくしょう、かならず見つけ出してやるぞ。さ、さっさとやってくれ!」
「いいのね、いくわよ。クネクネコネコネめたもるぱわ〜〜」
化夜は、あの呪文を唱えた。すると、俺の身体がまるで目に見えない何者かにこねられているような感触がして、身体が変形しだした。痛いとか、締め付けられると言う感じはなくて、やさしくマッサージをされているような感じだった。その気持ちよさに、俺は、眠気に襲われた。そして、眠ってしまった。
どれくらい経ったのだろう。目覚めると、あたりはすこし暗くなりかけていた。俺はいつの間にか廃工場の錆びた鉄柱を背にして眠っていたのだ。ふと見ると、約束通りに、俺を縛ってあったロープは解かれて、足元に放り出されていた。
「さて家に帰るか」
そう言って、立ち上がりかけて、俺は、ひざの辺りに、何か白いものがあるのに気づいた。それは一枚の紙だった。
「なんだこれは・・・契約完了通知書及び、領収書?」
それは、俺とあのふしぎな女との契約が完了し、約束通りに、不要になったものを貰っていったと言う通知書だった。
「いったいなんだったんだ。不要になったものって・・・ん?やけに胸が重たいなぁ。それにこの肩にずしっと来る重さはなんだ?」
俺は胸に手をやった。
ぷにぷに
「ん?なんだ?胸がはれ上がってるぞ。あの女なにをしやがったんだ。胸が腫れ・・て、胸だけじゃなくて尻のあたりが窮屈だ。それに、急に伸びたこの髪は・・いったいどうなったんだ。俺の姿はどうなってるんだ」
俺は自分の姿を映せるものを探した。ふと、朽ち果てた壁に夕日が当たってキラッと光を反射した。俺はそこに駆け寄った。
それは、壁に取り付けられた半分かけた鏡だった。俺は、夕日を反射している鏡に、顔を映した。
「えっええっ〜〜〜〜!」
そこに映し出されたのは、俺が本気で愛し、騙された女詐欺師のワンピース姿だった。
「ふふふ、まさか、あのお遊びで、もてあそんでやった刑事が、部屋に飛び込んで来るとは思わなかったわ。あわてちゃって、爺にしてやったけど、かわいそうだから元に戻してあげようと思ったら、自分から憎いはずのわたしの姿になるんだから、案外わたしのことを今でも好きだったのかな?さて、これからどうしよう。あの男になって男を楽しむのもいいかもね。あ、そうだ。その前に・・・もしもし警察ですか?指名手配の女詐欺師が、廃工場にいます。急いでくださいね。逃げ出すと大変ですから。わたし?わたしは善良な市民です。では・・・これでよし。彼が私の代わりに罪を償ってくれるわ。あの男もなかなかハンサムだったから、彼を使って女を騙そうかしら?」
そうつぶやきながら、女は、持っていた名刺を近くのゴミ箱に放り込んだ。『魔性 化夜』と書かれた名刺を・・・
あのあと俺は、突然現れたパトカーに乗っていた同僚の警官たちに取り押さえられた。警察官に詐欺をした女詐欺師として・・・
どんなに人違いだと叫んでみても、信じてはもらえなかった。それはそうだろう。どこから見ても女の俺が、男だと言っても誰も信じないだろう。
取調べの間中、わめき散らす俺に手を焼いた同僚たちは、俺を留置場に放り込んだ。留置場の中でも、わめいていたが、だんだんと落ち着いてきて、俺はあることに気がついた。誰が俺を、あの爺の姿にしたかだ。人の姿を変える力を持っている奴など、そんなにごろごろといるはずもない。と言うことは、あの『魔性 化夜』と言う女しかいない。俺は自分の尾行していた女に、老人にされ、最後は、言葉巧みに騙されて、奴の身代わりにされたのだ。
俺が元の姿に戻るには、あの女を見つけ出すしかないのだ。だが、それは不可能だ。なぜなら、人の姿はおろか、自分の姿も自由に変えてしまう女だからだ。いや、女とも限らないだろう。なぜなら、男だった俺が女になってしまったのだから。
俺は留置場の冷たい壁に背をもたれて、スカートをめくりあげた。そして、右手をワンピースの隙間から胸に、左手をまくれ上がって顔を出したパンティの中に差し込んだ。
むにゅむにゅむにゅ
くちょくちょくちょ
俺の手で、あいつの胸と秘部を撫で回し、もみまわして、屈辱してやることが、俺にできる唯一の復讐だ。
「うッわわっわわぁ〜〜ん、んんんぐん・・・気、気持ちいい・・シ、シヌワァ〜」
俺は休むことなく、奴を屈辱してやった。そして、わたしは・・・女を体感した。
「シネェ。シネ、シネェ〜〜」
俺は、奴を辱めることに快感を覚え、わたしは屈辱されて、身体をもてあそばれることに快感を覚えた。
「シヌ、シヌゥ〜〜」
「シネ、シネェ〜〜」
留置場の中で、一晩中、俺とわたしの快感におぼれたあえぎ声が鳴り響いた。