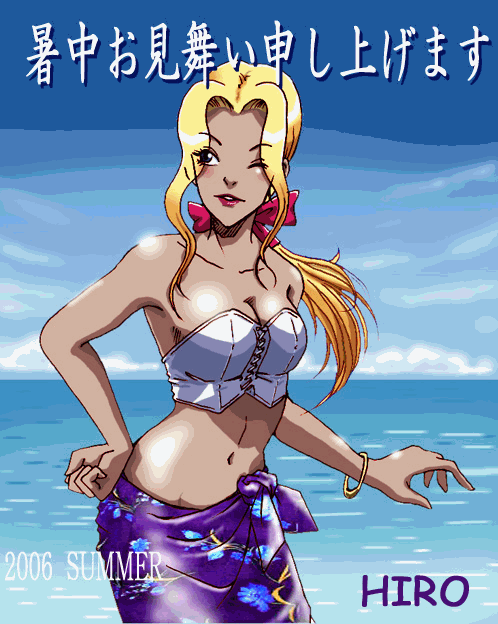
海辺にて
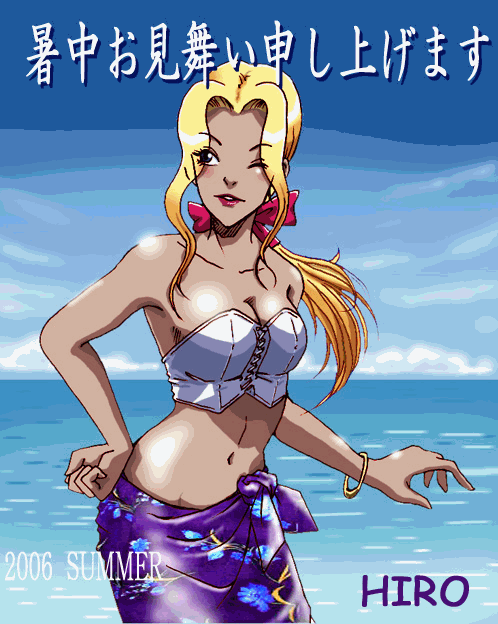
いらすと:HIROさん
怪人HIROからマリンブルーの海辺で遊ぶ金髪美人の写真をベースにした暑中見舞いが届いた。
奴の事だから、この海辺の美女は奴の変装なのだろう。だがしかし、この美女、きれいに日焼けしている。
我々が使うフェイクスキンは色素変化が不可能だった。だから顔色を変えるというのが難しいのだ。まして日焼けするなど出来なかった。
だが、この写真のHIROは、明らかに日焼けしている。このようにするには、最初から日焼けしたボディスーツを作るしかないのだ。でも、それは簡単そうに思えて結構大変な作業だ。自然光での日焼けは、日焼けサロンでの日焼けとは違って、身体中を均一に焼く事など出来ないからだ。どうしても身体のあちこちでムラが出来てしまう。普通の人は気付かないだろうが、我々変装を生業とするものには、はっきりとわかるのだが、この写真の女性は自然に日焼けしていた。
これほどの自然な日焼けをコピーしてボディスーツを作るのは不可能と言えた。それをHIROは、やってのけたと言うのだ。
我々は日焼けできないスーツか、日焼けしたスーツしか所持していないので、太陽の光が燦燦と降り注ぐリゾート地で、長時間太陽の下にいる事は出来ない。なぜならいつまでも白い肌のままで日焼けしないでいたり、日焼けした肌のスーツに変えて、急に日焼けしたりしては怪しまれてしまう。それに日焼けした肌だとしても、まったくその色を変えなかったら怪しまれるだろう。だから、炎天下での変装は難しいのだ。
それを、HIROは可能にしたというのだ。私はHIROのこの技術力の高さに敬服の念を持つと同時に、これだけの技術を開発したHIROの変装術に嫉妬の念を燃やした。
「くそ〜負けんぞ!」
「ねぇHIRO.一緒に泳ぎましょうよ」
「ああ、あとでな」
「もう、おかしなHIRO。あなたに会ってから、一度も身体を焼いているあなたを見たことがないわよ。泳ぎもしないし・・・あなたはなにをしにここに来たのよ。いつも日焼け止めクリームを塗って、日陰で寝そべっているだけじゃないの」
「私は、美しい黄金色の髪をなびかせるマーメイドプリンセスを眺めるために来たのさ。環が愛しきプリンセス」
「もう、HIROったら・・・」
彼の気障な台詞にあてられて、彼女は輝く金髪をなびかせてマリンブルーの海へと入っていった。
「ふふふ、あの写真が本物の美女の写真だとは誰も思わないだろうな。名人・達人と呼ばれる者たちは意外と単純なフェイクに引っかかるものだからな」
HIROは、正月にかけられた迷惑のお返しに、変装の達人たちにごく普通の写真を送ったのだ。だが、送られた者たちは、HIROからのハガキと言う事で、勝手に写真の美女をHIROと思い込んで、自らHIROの策略にはまって言ったのだった。
「しかし、彼女と一緒に遊べないのは辛いなぁ。でも、身体を焼くと、肌の色の違いが出て、ばれる可能性があるからなぁ」
HIROは、ビーチベッドの横に置かれたテーブルの上のトロピカルカクテルを手に取ると、ニヤリと笑った。
「先輩、同輩諸氏。我輩の復讐にハマリ、日焼けの謎を悩み苦しむがいい。フフフ・・・ワハハハハ・・・」
HIROの高笑いがビーチに響いた。だが、その笑いの意味を知るものは誰一人としていなかった。
「ワハハハ・・・・」