60年代英国ロック史
どうしてCamelはあんなにもブルージーなの?
5分で分った気になれるいい加減60年代英国ロック史入門編です。
タイトルは大層ですが、私が書くのですから、誰もが知ってる超有名盤しかありませんので悪しからず。
70年代は誰か書いてくれ !
全てはBeatlesから始まった…わけではない
1950年代。まずは、当時の音楽事情から...
アメリカでは、Chuck Berry、Little Richard、Elvis Preslyらが出現し、ロックン・ロールが産声をあげました。その一方、当時のイギリスの大衆音楽と言えば、トラッドと呼ばれるデキシーランド風のジャズが流行でした。
ライブ・ハウス「マーキー」のオーナーとしても知られているChris Barberも、そうしたバンドを率いるジャズマンのひとりでした。
ちなみに、Andrew
Latimerの父親もバンドを率い、自らドラムやクラリネットを演奏していたそうです。コルネット、クラリネット、トロンボーン等によるメロディーセク
ションに加えて、リズムセクションはチューバかベース、その他バンジョー、ギター、ピアノ、ドラムというのがデキシーランド・ジャズの基本編成と聞きま
す。
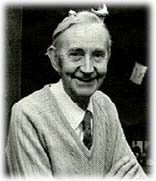
※写真: Andrew Latimerの父親 (Curriculum Vitaeより)
さて、そのChris Barberのバンドのステージにも上がっていたのが、King of SkiffleことLonnie Donegan。彼の1956年の英ヒット曲がRock Island Lineです。
フォーク、カントリー、ジャズなどの風味をないまぜにしたジャグ・バンド風の独自のスタイルは、スキッフルと呼ばれ一大ブームをイギリス全土に引き起こし
ました
。今だ戦後の閉息感から抜けだせていなかった当時のワーキングクラスのティーン・エイジャーたちは、皆スキッフルの虜になったようです。イギリス中にス
キッフル・バンドが雨後の筍のように出現したのでした。そうそう、Beatlesの前身となった Quarrymenもスキッフル・バンドでしたよね。
スキッフルはほどなく下火となりましたが、そのブームの中で頭角を表して来た一人のギタリストが、英国初の本格的ロックン・ロール・シンガーCliff Richardのバックを務めることなりました。そのバンドの名前はShadowsと言いました。
<参考音源>

■ Trad Mad ! The Pye Trad-Jazz Anthology 1956-1963
豪華CD3枚組セットです。Chris Barber's Jazz BandやLonnie Donegan with the Clyde
Valley Stompersほか多数のバンドを収録しています。 坂本九さんのSUKIYAKIは、英国Trad
Band経由でアメリカへと流れてヒットしたのですね。

■ Rock 'n' Roll (1975年)/John Lennon
あえて、Johnのソロ作を紹介します。多感な頃に愛聴したロックンロールの名曲のカヴァー集です。Gene VincentやChuck Berry、Little
Richard等々と、Beatlesがロックン・ロールの正統な継承者であることがわかる。後で紹介するブルース色の濃いその他の英国バンドとは微妙に
ルーツが異なることがわかり面白い。

■ The Skiffle Sessions (2000年)/Van Morrison, Lonnie Donegan, Chris Barber
英国ロック界の礎を築いた3人が一同に会しての楽しいコンサートです。しかし、Doneganのかん高い声はロックではなくC&Wかと思います。
赤いストラトキャスター
 Andrew Latimerのヒーローは、アルバムRajazの中の曲Straight to My Heartの歌詞にある通り、赤いストラトと眼鏡をトレードマークにしていたHank Marvin (1941年生まれ)でした。
Andrew Latimerのヒーローは、アルバムRajazの中の曲Straight to My Heartの歌詞にある通り、赤いストラトと眼鏡をトレードマークにしていたHank Marvin (1941年生まれ)でした。
60年代初頭にヨーロッパで絶大な人気を誇ったギター・インスト・グループShadowsのギタリストです。決して速弾きなどしないのですが、ナチュラルでとても美しい音色を奏でます。
1960年代半ばから1970年代半ばごろにデビューしたロック・ギタリストは皆、Hank Marvinに憧れてギターを手にしたと言ってもあながち間違いではないでしょう。
実際、Jeff Beck (1944年生まれ)、Ritchie Blackmore (1945年生まれ)、Brian May
(1947年生まれ)、Mark Knopfler (1949年生まれ)、Andy Powell
(1950年生まれ)と、並みいるギター・ヒーロー達が、Hank Marvinから影響を受けたことを表明しています。
そうそう、Tony Iommiも!
さて、そのHank
Marvinですが、実はShadows解散後もコンスタントにアルバムを発表しています。私が購入したのは、90年代のバラードを集めた企画盤の
Guitar Balladsです。聴きどころは、Brian Mayと共演したWe Are The Championsでしょう。
Brian Mayがくすんだ音色で凄まじい勢いでギター・バトルを仕掛けてくるのですが、Hank MarvinはGoing My Wayとばかりにクリアなトーンで1音1音丁寧に音を響かせます。
間違い無くAndrew Latimerのプレイ・スタイルに最も大きな影響を与えたギタリストでしょう。
(※写真: Shadows, アルバム The Shadows Greatest Hitsより)
ところで、1962年を迎えると、スキッフルに端を発した英国ロックンロールは一大転機を迎えることとなります。
そう、あのバンドのデビューです。
<参考音源>

■ The Shadows' Greatest Hits/The Shadows
1960年から1962年のあいだのヒット曲集のLPをCD化したものです。Apache (1960年)、Guitar Tago (1962年)など有名曲が32曲...かと思ったら、16曲×ステレオ&モノラルで計32曲でした。

■ Guitar Ballads (2004年)/Hank Marvin
本文で触れた企画盤です。2枚組で詳細ヒストリー、ディスコグラフィー付きの豪華版です。どちらかと言えば、静かな曲が多いです。Brian Mayのほか、Mark Knopflerとの共演曲もあります。

■ Twang (1996年)/VA
Hank MarvinとShadowsのトリビュート・アルバムです。Ritchie Blackmore、Peter Green、Brian
May、Peter Frampton、Mark Knopfler、Tony Iommi等々と蒼々たるメンツが参加しています。

■ Thunderbirds are Go
1966年の劇場版サンダーバードのサントラです。 Barry Grayのオケに加えてCliff
RichardとShadowsの曲も在ります。というか、そもそも、そっくりさん人形で映画に出演・演奏しているそうです。まあ、それくらい人気だった
といことなのでしょう。
British Invasion
1962年になると、いよいよBeatlesがレコード・デビューします。確かLove Me Doですよね。
Chuck BerryやLittle Richardといったロックン・ロールの正統な継承者にて革新者である彼等は、アメリカでも成功し、60年代前半は、これに続くグループが続々と名乗りをあげた時期でした。
いわゆる第1期British Invasionです。有名どころはRolling Stones、Who、Kinks、Animals、Themといったところでしょうか。
Beatlesに代表されるMersey Beat勢に対して、Rolling Stonesなどのロンドン勢は、いずれもブルース色が強かったようです。とは言え、やがて皆それぞれにスタイルを変化させていくわけですが...
迎え撃つアメリカ側の代表選手は1961年デビューのBeach Boysでしょう。
Andrew Latimerのインタビュー記事を見てみると、お気に入りのバンドにBeach Boysを挙げているものをちょくちょく見かけます。
Andrew Latimerの最初のバンドであったFantom Fourが結成された1964年は、こうしたバンドたちがしのぎを削っていた時代だった訳です。
もっとも、Fantom Fourはヒット曲のコピーを演じるスクール・バンドの域を出なかったようです。
メンバーは、Andrew Latimerのほかに、兄弟のIan Latimer (bass)、友人のRichard Over (rhythm guitar)、Alan Butcher (Drums)の4人でのスタートでした。

※写真: Fantom Four(Camel Productions ホームページより)
<参考音源>

■ Meet The Beatles (1964年)/Beatles
Liverpool Soundsの代名詞となったBeatlesの日本独自編集の1stLPです。カヴァー曲もありますが、自作曲が多いことにまず注目です。デビュー当時から既に独自の境地に達しています。

■ The Who Sings My Generation (1965年)/Who
モッズを代表するWhoは過激なステージ・アクトで有名でした。注目はKeith Moonのドラムが冴えるインスト曲のThe Ox でしょう。1965年にして、早くもハードロックの萌芽を見ることができます。

■ Kinks (1964年)/Kinks
Kinksというと、ひねたユーモアを漂わす軽快ロックンロールと言うイメージがありますが、ロンドン勢らしく、この1stではブルースっぽい曲もあります。You Really Got Meがカッコイイ。ちなみにギターはJimmy Pageが弾いてるのだそうです。

■ The Animals (1964年)/The Animals
Newcastle出身のAnimalsの1stです。Eric Burdonのワイルドなボーカルにギターとオルガンが絡むスタイルは今でもカッコイイと思います。

■ The Angry Young Them (1965年)/Them
Belfastを拠点としていたThemの1st。孤高のアイリッシュ・シンガーVan Morrisonの個性が爆発してます。ここでもギターはJimmy Page!です。更に注目はジャケ写真右から2人目はPeter Bardens !

■ Rolling Stones (1964年)/Rolling Stones
Beatlesを出すならStonesも出さね ばなるまい(笑
しかし、Beatlesに比べてこちらはかなりネチッコイ音。ブルース度はかなり高いです。まあ、バンド名からしてモロにブルースですからねぇ。
Bluesの洗礼
前述のバンド群のサウンド傾向を見ても分
かるように、当時のイギリスはブルース・ブームでした。アメリカではブルースはあくまで黒人社会の中だけのものであって、決して音楽シーンの表舞台に立つ
ことなど無かったこの時期、コアなロンドンっ子はVOAなどの海外向けラジオ放送を聴き、ブルースマンの輸入レコードを買い漁っていたようです。
まだオーディオが高価だった当時はラジオが重要なメディアでしたが、Andrew
Latimerも熱心にラジオ・ルクセンブルグを聴いていたことは、Straight to My
Heartの歌詞で明らかなとおりですよね。ちなみにAndrew
Latimer達が住んでいたGuildfordは、Londonから南方数10キロの所に位置しています。
こうした中、もっとストレートにブルースを指向するミュージシャン達がライブハウスに渦巻いていました。
その中心に位置していた先駆者がChris BarberのバンドにいたAlexis Kornerでした。1962年にBlues
Incorporatedを率いてデビューします。ジャズ・シーンとも関わりながら、ここから英国ロックの有名ブレイヤーが巣立っていきました。Jack
Bruce、Brian Jones、Charlie Watts等々とたいしたメンツが、このバンドの周辺に集まっていたといいます。
そのブルース・ブームを確固たるものにしたのがJohn Mayallでした。1966年の2ndアルバムJohn Mayall & the
Blues Breakers with Eric Claptonは、何とアルバム・チャートのTop 10に入るという快挙を達成しました。
もともとブルースとロックは兄弟みたいなものですが、とりわけ60年代の英国ロック・ミュージシャンは、皆何らかの形でブルースの影響を受けることとなりました。そして白人ブルース・ロックはアメリカへ逆輸入され、Janis Joplinなどのスターを生むに至ります。
一方、Fantom Fourの方はと言えば、リズム・ギターがRichard OverからGraham Cooperに交代となった時点で、バンド名が変更になります
一方、Peter Bardensはと言えば、既に英国ブルース・ロック・シーンで活発に活躍しており、結構名前が売れていました。

写真: From New Orleans to Chicago /Champion Jack Dupree
バックをEric ClaptonやJohn Mayallが務めた記念碑的アルバム。ちなみにAndy WardはChampion Jack Dupreeのライブに参加したことがあります。
<参考音源>

■ R&B from The Marquee (1962年)/Alexis Korner's Blues Incorporated
1962年のこの段階で既に白人ブルースは完成していたのかも。そう思わせるに十分な素晴らしい作品です。あとやり残したところがあるとすれば、ワイルドなエレクトリック・ギターだけでしょうか?

■ The Sound of 65/Graham Bond Organisation
英国ジャズの重鎮Don Rendellと活動をともにしていたGraham Bondによるプロジェクトで、Jack Bruce、Ginger
Bakerも在籍していました。ブルースやジャズがないまぜで不思議な感じです。意外にもロック色は薄く、いまいち方向性が定まりませが、ジャズ・ロック
の先駆者的に紹介されたりもします。

■ John Mayall & The Blues Breakers with Eric Clapton (1966年)/The Blues Breakers
Otis RushのAll Your Love、Freddie KingのHideaway、Robert
Johnsonの「さすらいの心」といったブルースの名曲をカヴァーしています。歴代在籍した人と言えば、Eric Clapton、John
McVie、Jack Bruce、Peter Green、Mick Fleetwood、Jon Hiseman、Keef
Hartleyと....きりがありませんのでもう止めときます(笑

■ Undead (1968年)/Ten Years After
2ndアルバムでライブ盤です。速弾きギタリストと言えば、当時はここのAlvin Leeが代表格でした。よくR&B系ハードロックの先駆者として語られますが、ずいぶんとJazz色が濃いです。

■ English Rose (1969年)/Fleetwood Mac
Peter Green在籍期のMacは、Savoy Brown、Chicken Shackと共に3大ブルース・バンドと称されてました。Black
Magic Womanなどの自作曲が素敵です。Mick FleetwoodやPeter GreenはBardensの盟友ですね。

■ Led Zeppelin (1969年)/Led Zeppelin
1969年にもなると、ロックの独自性が完全に確立してきます。Willie
Dixonの曲を演ってますが、単なるカヴァーに留まらずハード・ロックのカラーに染めています。「レコードとライブは別」という当時の観念を撃ち破り、
スタジオ盤にヘヴィネスをぶちこんだ名作です。
Strange Brew
Blues Breakersですが、御存知のように、前項のBlues IncorporatedやGraham Bond
Organisationとともに、英国ロック界の「虎の穴」的バンドとして、次々に有名プレイヤーを輩出していきました。一番手は、Yardbirds
を経て加入したEric Claptonでしょうか?
そのEric Claptonですが、Blues Breakers脱退後はGraham Bond Organisationに居たJack Bruce、Ginger Bakerとともに、Creamを結成したことは言うまでもないですよね。
さて、Fantom Fourの新バンド名ですが、なんとStrage Brew !いずれにしてもブルースへと路線変更となったことはまちがいないようです。
ところが、Ian Latimer、Graham Cooperの2人が結婚を期に脱退してしまいます。Andrew LatimerとAlan
Butcherは、オーディションにより迎えたベーシストDoug
Fergusonを加えて、Brewとして再スタートを切ったのが1968年のことでした。
そのBrewにAndy Wardが加わったのが1969年ですが、彼のオーディションではCrossroadやSpoonful、Killing
floorといったブルースの名曲でセッションしたとのことです。確かに、Andrew
Latimerの奏法をみても見ると、クリアな音色で下品にチョーキング、更に細かいビブラートをかけ、その上ボトルネックも使いますし、まさしくブルー
スの影響大かと思います。

※写真: Cream BBC Sessionより
<参考音源>
Crossroad


■ Wheels of Fire (1968年)/Cream
Creamの3rdアルバムです。ずいぶんとハードな感触となりました。スタジオ盤とライブ盤のカップリングですが、ライブでCrossroadを演って
ます。オリジナルの冷え冷えとした緊迫感はありませんが、ロック的なワイルドさ、Claptonのフレーズの奔放さは必聴です。
■ The Complete Recordings/Robert Johnson
悪魔に魂を売り超絶技巧を手にしたというクロスロード伝説を持ち、27才で毒殺された伝説のブルース・マンRobert Johnson (1911-1938)の全曲集です。美しくも切ないギターと声に注目です。
Spoonful


■ Fresh Cream( 1966年)/Cream
Creamの記念すべき1stです。軽めの曲もありますが、Spoonfulではしっかりブルースしてくれています。
■ I Am the Blues/Willie Dixon
この爺さんただ者ではありません。 ずいぶんと、お洒落なブルースを聞くことができます。Creamとは好対照? もしかして今の若い子はDixonの方を好むかも?
Killing floor


■ BBC Sessions/Jimi Hendrix
アメリカ人ですが英国に渡って成功しました。Miles Davisにも影響を与えたことは有名でしょう。ここでも米英間でのダイナミックな相互関係をみることができます。さて、Killing Floorですが、ずいぶんと走る奔放なアレンジになっています。
■ His Best-Chess 50th Anniversary Collection/Howlin' Wolf
Willie Dixonのプロデュースということもあり、ずいぶんとお洒落な路線となっています。もちろん、ボーカルの方は、ダミ声でHowlingしてくれてます。
Psychedelicの流行 そしてSgt.Pepper
60年代後半になると、西海岸のヒッピー文化から飛び火したサイケデリックが音楽界を席巻しました。ドラッグによる幻覚は時とし
て神秘主義とも密接に関わりながら、当時の若者を虜にしていきました。しかし、こうしたドラッグと神秘主義の流行は、いくつかの素晴らしいアルバムとひき
かえに、多くの有能な若者の命を散らすことになるのですが...
やはり先鞭をつけたのはBeatles。1965年のRubber Soulでは早くもシタールの導入が試みられ、東洋文化への傾倒が見え始めます。
続く66年のRevolverでは、Tomorrow Never Knowsなどの強烈なアシッド感覚あふれる曲でアルバムは覆い尽くされました。アメリカでもJefferson Airplane、Grateful Deadらがデビューします。
さて、そのBeatlesですが、1967年にSgt.Pepper's Lonely Hearts Club
Bandを送り出します。Psychedelicな名盤ですが、その一方で、コンセプ
ト・アルバムという手法の有用性を知らしめた作品としても有名ですね。両面合わせて50分という広大な器を持つLPレコードで何が
できるのかという命題への画期的な回答が出されたのです。
実際のところSgt.Pepperには、明確なコンセプトも特段のストーリーも無かったのですが、緻密な全体構成、曲から曲へと切れ目なく繋がるショー仕
立ての演出は高い評価を得て、次々と追随者を生みました。とりわけ70年代のProgressive
Rockの諸作品に大きな影響を与えたことは言うまでもありません。
さて、我等がCamelですが、Snow
Gooseあたりはコンセプト・アルバムとは言っても、この頃(60年代)のものとは違ってメッセージ性は薄いのですよね。S.F.
Sorrowにしても、ArthurやTommyも随分と歌詞世界のウェイトが高いのに対して、全曲インストなのは特徴的かと思います
。歌が下手だったとか、歌詞を書くのが苦手だったなんて言っ てるのは誰だ!
まあ、彼等の場合作曲のためのインスピレーションを得るための「手法」という意味合いの方が強かったのかなと思っています。

※アルバムジャケット写真は、Marc Bolanも一時在籍したJohn's Childrenのスタジオライブです。Andy WardとDoug
Fergusonは、Brew参加前にJohn's Childrenの系列異バンドMisty Romanceで一緒に活動していました
<参考音源>

■ Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967年)/Beatles
天才が本気でサイケに取り組むとこうなります。細かな録音技術を駆使した緻密な音づくりは、当時としては驚異的であったと思われます。コンセプト・アルバ
ムはZappaが先だ、Beach Boysが先だという議論はありますが、影響力という点ではBeatlesが一枚上手のようです。

■ The Piper at tha Gates of Dawn (1967年)/Pink Foyd
Syd Barrett在籍1967年のPink
Floydの1st。サイケでポップできらきらと輝くようなサウンドですが、Sydの頭抜けた存在感に圧倒されます。でも、ライブは更にハードだったとの
ことです。当時のアングラ・シーンの牽引者は、Pink FloydとSoft Machineだったようです。

■ My People Were Fair and Had Sky in Their Hair But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows (1968年) /Tyrannosaurus Rex
John's Childrenに居たMarc Bolan率いるバンドの1stです。後にT-Rexと改名し、70年代初頭にはグラム・ロックの祖として有名となります。
ここでは民族音楽的な要素を詰め込んだ、サイケデリックなフォークソングを聴かせてくれます。

■ S.F. Sorrow (1968年)/Pretty Things
デビュー前のRolling StonesにいたDick Taylor (g)を中心としたバンドです。
WhoのTommyに先駆けて発表された初のロック・オペラ作品です。
ちょっと地味ですが結構良い作品かと思います。

■ Days of Future Passed (1967年)/Moody Blues
なぜか現在ではプログレの文脈で語られることが少なくなってしまった彼等ですが、なんたってJimmy Pageがプログレの代表例として挙げたバンドなんですから...この作品は、コンセプト・アルバム、オーケストラとの共演という点で先駆けと言えるでしょう。

■ Arthur - Or The Decline and Fall of the British Empire(1969)/Kinks
Kinksらしい醒めたユーモアを漂わせながら、平凡なイギリス人の夢や挫折をテーマとしたコンセプト・アルバムです。
軽快なロックン・ロールですが、結構、良い曲があって楽しめます。

■ Tommy (1969年)/Who
怒れる若者の代表、ハードロックの祖、パンクのアイドルだったはずの彼等もコンセプト・アルバムに挑戦しています。これだからブリティッシュ・ロックは面白い?
後に映画化、ミュージカル化までされることになるロック・オペラです。結構手のこんだアレンジしてます。
70年代前夜
60年代も後半に入ると、Beatlesはロックに留まらずポピュラー・ミュージックにおける巨人と化していました。
JohnとPaul稀代の天才2人が、最新の録音機材で金に糸目をつけずにアルバムを制作するのですから、普通のビートロック・バンドは、軌道修正を余儀なくせざるを得ない状況となりました。
というわけで、60年代終盤は、いろいろなアプローチでBeatlesへの反撃が開始されました。
クラシック音楽の導入に関しては、イギリスでは前項のMoody Bluesが先鞭をつけましたが、その他、Renaissance、Niceらがそれぞれ独自の方法論でのアルバムづくりを展開しました。
ジャズに関しては、先に述べたように、そもそも英国ロックの成り立ちからして密接な交流があったわけですが、新しい動きとしては、Miles
Davisによるジャズのエレクトリック化に敏感に反応したミュージシャンが、ロック界、ジャズ界の双方から現われたことも挙げられるでしょう。
まあ、色んなバンドが色んな試みを始めたわけでして、前述のサイケデリックの流行と相まって、当時の英国ロック・シーンはカオス状態、ジャンルの敷居が異様に低かったようです。
Brewもまた、そうしたカオスの中で、ブルースだけでなく新しい物をどんどん吸収していたのだと思います。
もちろん、もう一人の若者(Pete Bardens !)もまた新たな刺激を求めていたであろうことは、想像に難くないと思われます。
ただ、皆、出自が出自だけに、どうにもブルース・フィーリングは隠しきれてないかなぁ?

※写真: アルバムDust and Dreams (1991年)ブックレットより
シンフォニックな作品だが、Mother Roadのような曲があるところがCamelらしい。
とにもかくにも、1969年にはKing CrimsonやYesの1stが出て、本格的なプログレ時代が幕を開けるのでした。
<参考音源>

■ A Whiter Shade of Pale (1967年)/Procol Harum
プログレではありません(笑
バッハの旋律を使ったということでロックへのクラシック導入の先駆者的な紹介がされますが、ここでのオルガンは、ずいぶんとジャジーかと思います。

■ Traffic (1968年)/Traffic
プログレではありません(笑
R&B、フォーク、ジャズなど様々な音楽要素が混在した不思議な感覚の作品ですが、B面は、あと一 歩でプログレと言う感じです。68年とは思えない完成度の高いアレンジには感嘆。Stevie Winwoodならではでしょうか?

■ Liege and Lief (1969年)/Fairport Convention
もちろんプログレではありません(笑
米国へ来た人々の労働歌がブルースを生み、英国からの移民の民謡がヒル・ビリーとなり、両者が合わさりR&Rとなった。そんな思いを馳せると、英国の地でもフォークとロックの融合が発生したことは感慨深いです。

■ Shades of Deep Purple (1968年)/Deep Purple
ブルース・ロックのカヴァーやサイケなアレンジの曲もありますが、後のハードロック路線のエッセンスが随所に垣間見られます。彼等の一番の功績は、直接ブルースに依拠しなくてもハードロックが成立することを示したことかと思います。

■ Live (1969年)/Don Rendell Ian Carr Quintet
この後Nucleusを結成するIan Carr参加の英国ジャズユニットです。Ian CarrのプレイにはFusionへの指向が見えかくれする気がします。

■ Soft Machine (1968年)/Soft Machine
Psychedelicな音を出すグループの中でも、一 番の硬派がSoft Machineでした。70年代に入りJazz Rock、Fusionへと突き進むことになったのは必然か?

■ Valentyne Suite (1969年)/Colosseum
Jon Hisemanのせわしないドラムをバックに、Greensladeの印象的なオルガン、曲によっては管も入って相当にジャジーな印象です。ブルースの影響下にありながらも、ジャズ・ロックへと踏み出した好作品。Camelの1stが好きな方にお薦めです。

■ Stand Up (1969年)/Jethro Tull
ブリティッシュロック然としたプログレシブ・ロックの基本形は、Tullによって確立されたのかなと思います。フルートの導入という点でもCamelと共通する部分も多々あるかなぁ。

■ BBC Sessions 1969-1970/Yes
まだ、成熟してはいないものの、叙情に流れない若く奔放な演奏が素敵です。ハードロックとプログレシブロックの分水嶺にあるような音かと思います。

■ In the Court of the Crimson King (1969年)/King Crimson
研ぎすまされたその音楽性は60年代を総括するとともに、来たる70年代の指針となりました。ブルース・ ロックは受難の時代に?
Camelの音楽性が形成されるに至った背景を書き記したかったのですが...
まあ、ブルーズに片足を置いてることだけは分っていただけたかと思います。
なお、このコーナーの記述は、キーフハートリー著の「ブリックヤード・ブルース」を参考にしています。
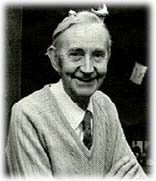



 Andrew Latimerのヒーローは、アルバムRajazの中の曲Straight to My Heartの歌詞にある通り、赤いストラトと眼鏡をトレードマークにしていたHank Marvin (1941年生まれ)でした。
Andrew Latimerのヒーローは、アルバムRajazの中の曲Straight to My Heartの歌詞にある通り、赤いストラトと眼鏡をトレードマークにしていたHank Marvin (1941年生まれ)でした。









































