

| ◆補足 まあ、「サンタナ、シカゴ」のネタはずっと温めていたモノなのですが、逆のパターンの時に(逆転優勝)使いたかった。NGワードは「歴史的大失速」です。 |

| ◆補足 家族全員テレビに釘付けでした。更なる盛り上がりとなると、侍ジャパンへの女性選手選出しかないでしょう。 |

| ◆補足 全く脚色なしです。Greensladeのジャケットを目にして、これだと確信しました。 |

| ◆補足 King Crimsonで3枚選べと言われたら、私ならコレも入れます。 |

| ◆補足 消毒薬やマスクの確保、時差出勤に在宅勤務、感染者発生時の応援体制確保等々と、家庭より仕事場での対応に気をすり減らしました。 |

| ◆補足 永井豪のオチは「決まった」と悦にいっていたのですが、友人に下品と言われてしまい凹みました。 |

| ◆補足 いろんなビブスをつけた警官や国の職員が応援に来てました。長期戦となったので、警察関係の皆さんは大変そうでした。 タイトルは別にすればよかったかな? |

| ◆補足 電気温水器、ユニットバス、システム・キッチンの魚焼機と次々に壊れていきました。 |
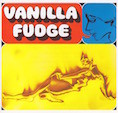
| ◆補足 ちょっと真面目に怒ってしまいました。 |

| ◆補足 その後、ポンプを交換して少し音が小さくなりました。 |

| ◆補足 御存知のように,カートリッジとは針でレコードを擦ってその振動で発電する器機です。基本原理はフレミングの左手の法則、材料はコイルと磁石ですが,動き が加わる部分が磁石かコイルかで方式が大別されます。MMとはMoving Magnet,MCとは,Moving Coilの略です。 実はこの記事、今だに頻繁にアクセスがあります。 |

| ◆補足 ダンカン引退後はカワイ・レナードがチームの顔になりましたが、しばらくしてラプターズに移籍してしまいました。 |

| ◆補足 警視庁警備部第9機動隊広報係に所属する男性隊員だそうです。 |

| ◆補足 さらっと書いてますが、職歴中で一番辛い一年でした。 |

| ◆補足 バスケ部人口は多いのですが、中学限りでやめてしまう人が多いようです。 |

| ◆補足 ご承知のとおり私もWordPressに移行したので、バック・アップのやり方について模索していましたが、SeaMokeyを使う方法に落ち着きました。 |

| ◆補足 動画編集もゲームもしない私には、今のMacやiPadはオーヴァー・スペックで値段に見合いません。ついつい浮気して、クローム ・ブックを買ってしまいました。 |

| ◆補足 「四陣の風」はアルバム中のAstronomyという曲の歌詞にある「At Four Winds Bar」を受けてのことです。 |
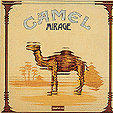
| ◆補足 私のtwitterの使い方は、2010年当時から大幅に後退しました。 |

| ◆補足 年々アナログへの情熱が冷めていくばかりですが、既に持っているレコードはレコードで聴いてあげるのがいいかなと思っています。 |

| ◆補足 Last.fm、懐かしいです。 ちなみに、FM放送のFMはFrequency Modulation(周波数変調)」の略です。 |

| ◆補足 新型インフルエンザ覚えていますか? 私はこの時マイコプラズマ肺炎に感染し受診したのですが、新型インフルエンザを疑われ、かかりつけ医の先生が滅茶苦茶びびっていたのを思い出します。 |

| ◆補足 実は、私が今使っているiMacは、ターゲット・ディスプレイ・モードに対応しており、外部ディスプレイとしても使用できるのですが、OSのダウン・グ レードに加えて特殊なケーブルが必要となるなど、何かと制約が多くて見送っています。そろそろ延命は無理かなと思っています。更に、USB Aの周辺機器をどうしたものか思案しています。 |
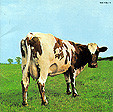


| ◆補足 解説不要かと思いますが、フロイドはアランのサイケデリック・ブレックファスト、ジェネシスはサパーズ・レディ、バンコは最後の晩餐ですね。 |

| ◆補足 小林さんは2010年に57歳の若さでお亡くなりになられました。合掌 |



| ◆補足 全く改善されていません。ずびばせん。 |

| ◆補足 特になし |

| ◆補足 Recent Reportにあげましたが、今年もちゃんと咲きましたよ。 |

| ◆補足 その後も7、8年毎にオーバーホールをお願いしています。新製品を買わないのは心苦しいです。 |
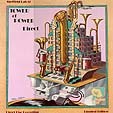
| ◆補足 本当のことを言うと、このLP、音が鮮烈すぎてリラックスして聴けません。 |

| ◆補足 何が怖いかって、この話1ミリも脚色していません。 |

| ◆補足 この時は、まさかCamelが5.1ch化されるとは思いもしなかったです。 |

| ◆補足 こちらのお店で高校の先輩が働いていたのですが、その方は今は欧州にいるらしいです。 |
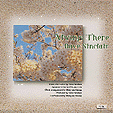
| ◆補足 Daveさんは、近所(?)の島に在住されていますが、その後お会いできていません。CDはあれこれ買ってます。 |

| ◆補足 全く気付いてなかったようでした。 |
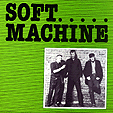


| ◆補足 これも全く補正なしの実話です。曲名くらい見ろよと言いたい。 |