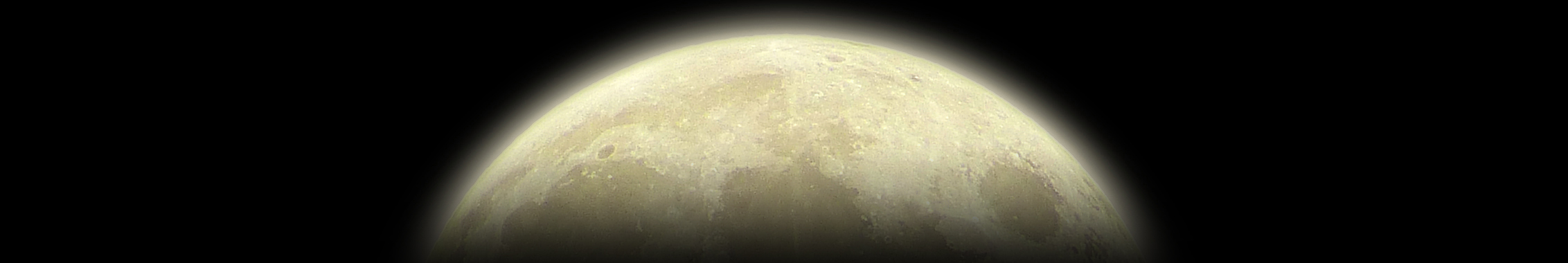作:いくねえ様
カンベエは自分の屋敷の濡れ縁に座し、低く垂れ一杯に花を付けた紅梅を、見るとはなく眺めていた。
屋敷に戻ったのは二月ぶり、ほんの3日ほどの休みである。
もっとも自分のせいではない負け戦の後で、自宅でおって沙汰を待てといったところで、どこかに出かけるわけにも行かない休みであった。
カンベエが率いた先鋒はしっかりと切り込み道を開いたのだが、後が続かず、しかもその戦の総大将の立てた作戦があまりに勢い任せのものであったため一度崩された陣形は建て直しが不可能であった。
実は最初から後が続かなければこの作戦の成功はあり得ないと感じていたカンベエは注進もしていたのだが聞き入れられず、隊の全滅も覚悟していた。
それがあまりに早く後続がつぶれたせいで逆に下がまだ包囲されておらず、敵戦艦を何基か落とし、隊士は全員生還させたとあらば責められることはないと思うのだが、大将は自分の浅慮の責を誰かに押し付けたいらしく、上の方で揉めているとのことである。腹を切れとはまさか言われまいが、恐らく最前線の砦への補充部隊とされるのではないかと覚悟を決めている。
大戦は長く続いていたが、徐々に二つの勢力に別れて行き、そしてカンベエの属する側はこの数ヶ月押されている様相が明瞭となってきていた。いくつかの大きな合戦で、これまでこちらの中心となっていた知将が何人か倒れ、その後に座るものは名はあるもののまだ戦経験が浅い若造で、周りの下克上を狙う狐や狸に振り回され、ろくな策を立てられていない。前線に回されれば、恐らくもうこの屋敷に帰ってくることはできないだろうと、カンベエは考えていた。
早春のまだ肌にはやや冷たい空気から、己の肌をだまそうとするかのように、カンベエはくいっと酒を喉に流し込んだ。
まだ日も高いが、昼間から花を愛でつつ酒を飲むなどもうできないかも知れないと思うと、まあいいかと徳利から猪口に次の一杯を注ぐ。
もう既に二合ばかり空けているので頬が少し温かい感じがする。梅の枝は随分低くまで伸びており、縁側に座ったままでも手が届きそうだ。花も酒を嗜むだろうか…
「カンベエ様」
柔らかい声が、カンベエのどこかへ飛びかけた心を呼び戻した。
「カンベエ様、お珍しい。今日は御酒が進みますな。」
シチロージが新たにつけた徳利をもって横に座した。金色の曲げをふわりと揺らめかせ、副官はカンベエとの距離を縮め、肩口に顔を寄せる。
二人とも今は軍服は纏っていない。白い紬の普段着を着流して寄り添う、そう、ただの思い人同士である。
先の戦でシチロージも危うく死なせかけるところであった。
侍である限り、お互い常に覚悟はできているつもりである。
戦っているその最中には意識はしない。しかしいつも戦が終わった後、シチロージが生きていたことに安堵し、またシチロージが死んでいたかもしれないことを思うと、足元からくず折れてしまいそうな恐怖感を感じる。
一体どこでそうなったのかわからないのだが、己はこの柔らかい笑みを浮かべる、その実阿修羅のような副官にどこかを預けてしまったようなのだ。
「シチロージ」
「はい、カンベエ様」
「…次の戦、恐らく空の砦に常駐となろうぞ」
「…そうですね」
「特攻部隊ということだ」
「はい」
「お前のような優秀な侍をむざむざそのようなところにおきたくはない、この度の負け戦、責任を取るのはわしだけでよいと思うのだが……よその隊に行ってくれと言っても、行ってくれはしないのだろうな」
「何を当たり前のことを口にされますか」
シチロージはそのままカンベエの腰にするりと腕を回した。
「何度も…何度も申しましたが、まだわかっておられませんか。私はあなた様のおられぬところでは生きている気がしません。私がおらぬところでカンベエ様が戦っているところなど想像することもできません。カンベエ様と背中を合わせて戦うのはわたしです。他に誰がおりましょう?」
そういいながら、カンベエの体をずるりと室内に引きずり込む。
「シチロージ、わしはもう少し梅を眺めていたいのだが?」
苦笑しながらカンベエも抵抗はしない。
「カンベエ様が梅となにやら相談されているようで、私も仲に入れて頂きたかったのでございますよ。」
そういいつつ、シチロージの手はカンベエの腰から大腿にかけ、ゆっくり撫で下ろし、また撫で上げてくる。
「日もまだ、随分と高いぞ?」
緩やかなその手の動きに、心地よさを感じながらも一応釘を刺してみる。
「なに、明るい陽射しは、一層あなた様の肌の美しさを際立たせると言うもの」
「何を…たわけたことを」
その時大腿を撫で上げてきたシチロージの掌がそのままカンベエの前をやわりと擦った。
びくりと震えたカンベエの体を、畳の上に敷きっぱなしだった布団の上に貼り付けるようにして、シチロージは愛しい人の首下に顎を埋めた。
そのまま頚を吸い、少しずつ降りていく。
「お前のような美丈夫が、そのようなことを、いっても、な」
「もう、本当にこの方は、いくら言ってもご自分のことがわからないのだから…」
シチロージは本気の苦汁顔で一瞬溜息をついたが、すぐ柔らかな笑顔に戻って呟いた。
「でもそこがあなた様のまた、可愛いところでございますが」
そういって両の胸の飾りをきゅっと摘みあげた。
カンベエの背が、う、と反り、目が少し苦しげに閉じられた。
いつの間にか紡ぎの前は肌蹴られ、両肩が露となっている。
浅黒く、そしてシチロージの言う通り艶やかに滑らかなその肌は、いつもの行灯の灯の下で見るのとは違い、早春の陽射しの下縮緬のような光沢を見せる。
胸から腹の筋肉の筋に舌を這わすと、少し息を詰めて、それから苦しげにふ、と吐く。
何もかもが愛おしくて、シチロージはカンベエの顔を両手で支え、深く口付けた。