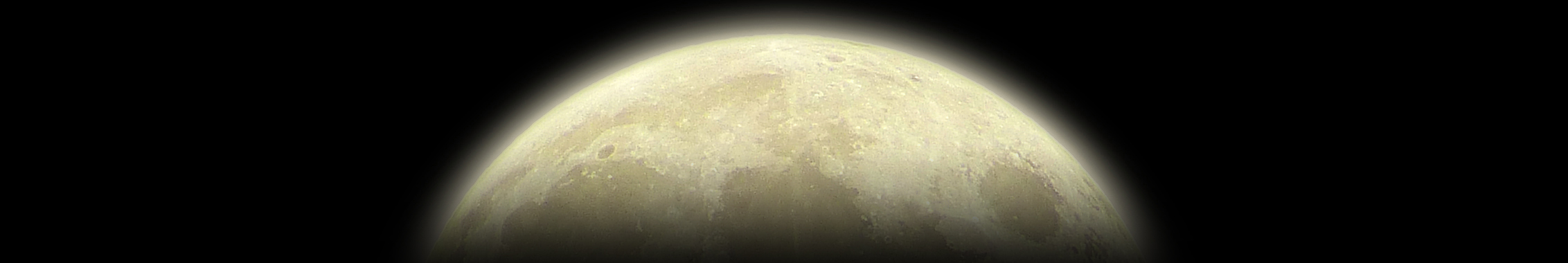作:いくねえ様
その街は虹雅渓から大分と離れたところにあった。古くからある旧南方の地方都市で、大戦の折も復興できないほどには損なわれず、大戦以前の町並みも見られる。虹雅渓ほどの賑わいはないが、その分人々は穏やかに行き来し、路地を入ると子供らが遊んでいる姿が見られる。
カンベエ達はカンナ村を出た後、一旦は虹雅渓に入りユキノのもとに挨拶に行った。カンベエはそのままシチロージに黙って蛍屋を去ろうとしたが、容易に出し抜けるわけもなく、無言で牽制し合いながら二、三日が過ぎた。その緊張感に堪えかねたユキノが溜息をつきながらカンベエに行った。
「旦那、あの人を連れて行ってやって下さいな。あの人はもう居残りなんざあきあきなんですよ。」
「戦があるわけではない。居残りも何も、シチロージをユキノ殿からお借りする理由がない。」
「あの人は心配なんですよ。アヤマロが差配に戻って、旦那達が都を落としたことはうやむやになったけど、訳を知りもしないで旦那達のことを悪く言う人はたくさんいます。右京が派遣してそれぞれの村に居ついた侍達もそう。
いくら旦那が強いからって、何処で寝首をかかれるか知れたもんじゃありませんよ。だからあの人を連れてって下さい。そしてほとぼりが冷めるまで虹雅渓から離れていて下さいな。何年かすりゃ皆忘れっちまいますよ。そしたら旦那も一緒に帰ってきて下さればいいんです。」
「だが…。」
「それに、」
ユキノはにっこりと微笑んで言った。
「無理矢理置いていっても、何日ももたずに旦那を追っかけて出て行っちまうのは眼に見えてますよ。カンナ村でだって、結局追いかけてきちまったじゃありませんか。」
カンベエはその笑顔を見て、ユキノが全てわかった上で言っているのだと確信した。申し訳なさでユキノの顔を見ていることが出来ず、カンベエは深く頭を下げた。
結局この街にあるユキノの亡くなった亭主の知り合いの店に厄介になることになった。
カンベエには行く当てがないわけではなかったのだが、シチロージが一緒となると紹介してくれたユキノへの義理も立てておかねばならない。当面の間、ここに滞在することとした。シチロージはその知り合いの店を手伝い、カンベエは主人が紹介してくれた道場に時折出稽古に出る。
そうして迎えた初夏であった。
シチロージがある日、カンベエの袖をひっぱって言った。
「カンベエ様、今日からこの店は床をやるそうです。」
いつもの整った穏やかな笑顔だが、カンベエにはシチロージが随分とうきうきしているのがわかった。
「ほう。…それで?」
「ご主人がね、日が落ちちまってからでよけりゃまけてあげるからいらっしゃい、とおっしゃるんです。」
じれったそうに、そして期待を眼に浮かべてシチロージが言う。
副官時代からカンベエと話す時には静かに冷静に話そうとするが、実は結構瓢げた性格であり、何かあれば浮かれる方である。
商人相手の店であり、まけてくれても決して安い金額ではないのだろうが、こういうシチロージを見るのは再会してから初めてで、否とはいえなかった。
「わかった。では今日は少し贅沢をするか。」
苦笑しながらカンベエが答えると、遂に堪え切れず、やった!と漏らしシチロージは破顔した。
湯浴みをすませて待っていると、店が一段落ついたシチロージが戻ってきてそろそろ行きましょうと声をかけた。自分もざっと湯浴みをすませて出てきたシチロージがはい、とカンベエに浴衣を渡した。
「これは、どうした?」
細い縦縞の浴衣を見てカンベエは不審気に尋ねた。
「ここに来てすぐの頃に古着屋で見つけましてね。カンベエ様の丈に合う古着なんぞそうそうないものですから買っておいたのですよ。」
「…それも、買ったのか?」
しゃあしゃあというシチロージはというと、戯画の描かれたまた随分と派手な浴衣を纏っている。
「安かったので一緒に買ったんです。祭りでもあれば着たいと思いましてね。」
「…お主、はしゃぎ過ぎではないか?」
少し呆れてカンベエは言ったが、そのシチロージの様子が、随分と懐かしい…、はぐれてしまう前の例えどんなに苦しい戦況でも飄々とし、些細なことでも楽しんでいた彼を思い起こさせ、心の奥に暖かく湧き出るものを覚えた。
再会してから、拒んではいたものの只管に求めるシチロージに負け、身を任せてしまった。ユキノへの申し訳なさが心にあり、シチロージを思い切れなかった己が情けなく、抱かれていながら、シチロージの気持ちを受け止め切れなかったところがある。さらにはそのような状況で、カンベエが今は亡き侍達それぞれに好意と信頼を持っていたものだから、シチロージにしてみればカンベエを他の誰かに奪われるのではないかという昏い思いにすっかり囚われてしまっていたのだろう。
己に向かって話す言葉は静かで、顔は笑みを作っていても、見詰めるシチロージの眼はいつも切なく暗かった。
終わってみれば、生き残ったのはカンベエとシチロージ、それにカツシロウだけであった。大戦時に己が率いていた者達にも匹敵する、優秀で、そして快い連中を失ったことは、慣れた痛みとはいえ重く、しばらくは言葉もなく日々を過ごしたが、しばらくすると徐々にシチロージの顔から険が落ちていった。それでも、カンベエが自分をおいて去ってしまうのではないかという不安からは逃れられなかったのだろう。
ユキノからああ言われてしまえば、少なくともカンベエは当面逃げることは出来ず、随行することを許されてシチロージはやっと心を安らげることができたのだ。
―女将には最初から全て見通されているような気はしていたが。これでシチロージを置いていったら、かえって女将に不義理をすることになってしまうのだろうな。
好いた男を離すまいとするのではなく、望むようにさせてやろうとする気持ちの大きな女性だ。それだけに、これ以上彼女の意に染まぬことは出来ない気がして、軽い足取りで前を行くシチロージの背中に眼をやり、カンベエはひっそりと苦笑した。
夏場だけ開くという川床を設ける別店は他の床を置く店より少し川上にあり、暑い盛りに涼を求め、山の空気を楽しみながら旨いものを味わうという客が主で、日の落ちる少し前が客の多い時間である。すっかり暗くなった今は残っている客も少ない。
カンベエ達は他の客から少し離れた席に案内された。それぞれの席は簀垣で仕切られているだけだが、ざわざわとした山の梢の葉鳴りと川のせせらぎに紛れ、意外と声は響かない。遠くの方に川下の床の明かりが多く見え、賑わう人々の影がちらちらと映る。街に近いそちらはむしろこの時間からが掻き入れ時であろう。
食前酒が出され、亭主が顔を見せた。
「カンベエ様、ようこそおいで下さいました。」
にこやかに挨拶をした後、亭主自ら先附を配す。
「主人、今日はお声掛け頂いて感謝する。これ、シチロージがすっかり調子に乗ってこの格好だ。」
カンベエも穏やかに返す。
「いやいや、シチロージさんは派手なくらいがよくお似合いですよ。
下の店ではお座敷を賑やかに盛り立ててくれますし、華やいだ場に合われますからね。
実際よく動いてくれて助かります。仲居達がすっかり頼りにしてますよ。年増連中までがきゃあきゃあ言っています。」
「ほう…。」
「私が叱るとぶすっとしている者達でも、シチロージさんが言ってくれるとはいはいと聞いてくれますから、全く現金なものですよ。」
主人はクスクスと笑いながら言った。
ちら、とシチロージを見ると、何やら焦った風でカンベエを見ている。
「さあ、どうぞお召し上がり下さい。
ああ、それから讃良様が」
讃良というのはカンベエが手伝っている道場主である。カンベエより二回り近く年上で、旧南方の侍であったという。大戦の終わりと共に退役し、以来この地で剣術を指南している。腕はなかなかのものだが、同僚が機械化していく中で生身を捨てられず出世し損なった。だが結果としてはそれでよかったと、からからと笑っているような御仁である。
「カンベエ様が床に来られるならこれを、と。」
主人が、氷を張った盥の中で冷やされた四合ほどの玻璃の酒甕を仲居に運んで来させた。
「カンベエ様と立ち合うと、昔に戻ったような気がして背筋が伸びる気がする。弟子達もその空気を感じるのか気の入り方が変わってきたと。弟子もカンベエ様が来られてから随分増えられたとか。とても感謝されていらっしゃいまして、今日こちらでお食事をされるなら、是非これを上がられて欲しいと使わされました。」
カンベエは、新しく入った弟子達の顔を思い浮かべ、少し困った顔で髭を撫でた。カツシロウとまではいかないが、讃良を差し置いて、先生先生とカンベエにまとわりついているのが何人かいるのだ。讃良は、血気盛んな若い連中はカンベエの本物の気に酔ってしまうのだと、面白げにいう。
「それは…忝ないことだ。讃良殿にはこちらが世話になっているというのに。」
「先日絞られたばかりの生酒でございます。さっぱりとした飲み口のものですから最初の方のお食事と一緒にどうぞ。」
亭主が最初の一杯を杯に注いでから去ると、カンベエは乾杯をしようとシチロージの方を向いた。だがシチロージは何やら言いたそうな複雑な顔をしている。
「店では随分ともてているようだな。」
カンベエが笑いながら言うと、堰が切れたかのようにシチロージが言い募ってきた。
「とんでもない!私は仕事がしやすいように、楽しく盛り立てているだけですよ。女が多いところでおばさん方に睨まれちゃあまともに仕事が進みませんから。
それよりもカンベエ様!弟子が増えたって。またそんなに人を惚れさせてどうするんですか。まさか、言い寄ってきた奴などいないでしょうね?」
それか、とカンベエは天を仰いだ。
「カツシロウと変わらぬぐらいの若者達だぞ…町にいくらでも若い可愛い娘達がいるのに、あり得ぬことを疑うな。」
「讃良殿も随分カンベエ様のことを気に入られておいでで。」
カンベエはこめかみを押さえていった。
「讃良殿は機械の体になるのを躊躇うほどの愛妻家でおられるのだ。普通に気があっているだけだとどうして考えない?」
それでもシチロージはまだ不服げな顔をしていたが、カンベエがこんな面白くないことで絡むのなら帰ると臍を曲げかけたので、慌ててもう言いませんと頭を下げたのだった。
いきなり痴話喧嘩になりかけたが何とか気を取り直し、料理に手をつけるとカンベエの曲がりかけた臍もすぐにまっすぐに戻った。
先附の鱧の落としと山芋と枝豆の和え物は一気に食欲を思い出させた。
「やはり夏は鱧だな。」
嬉しそうにいうカンベエに、シチロージはほっとした。そしてしんみりとした声で言った。
「カンベエ様、覚えてますか?」
「ん?何をだ?」
「私がカンベエ様のお屋敷に初めて伺った時に、鱧を食べさせてくれたことですよ。」
カンベエの眼が少し遠くなった。
「流石に何を食したかは覚えておらぬよ。ちょうど今ぐらいで、お主が嬉しそうに食べていた様は眼に残っているが。」
そして思い出すように小さく笑った。シチロージはわざとらしく悲しげな顔をしてため息をついた。
「まーったく。カンベエ様はつれないのですから。私はお誘い頂いて有頂天だったのに。
あの日何を食べたか私は全部覚えてますよ…。鮒の洗い、岩魚の塩焼き、鱧の吸い物…」
そしてカンベエを見つめながら言った。
「カンベエ様。」
ぷっとカンベエが軽く酒を吹いた。
ちょうど椀物を運んできた仲居が何事かという顔をした。
続く料理も美味だった。椀物は空豆を練り込んだ白身魚のつみれが実で、口に入れるとほろほろと崩れて旨みが染み出したし、刺身は鮮度のよいカンパチやマナガツオ、アワビが氷の皿に盛られ、紫蘇の穂に飾られて出てきた。虹雅渓は海に近かったから、蛍屋で新鮮な刺身が出た時にはそうも思わなかったが、海から結構離れた内陸の山の中で、こういう物を食べられるとは本当に贅沢だ。
次には山の幸が来た。塩で流紋が描かれた塗りの大皿に泳ぐ鮎の塩焼き、からりと揚がった茄子や山葵の葉の天ぷらを食べ終わる頃には、冷たく冷やされた生酒はすっかり空となっていたが、久しぶりの贅沢な食事とうまい酒の時間が心地よく、二人は主人おすすめの酒を温めの燗にしてちびちびと飲み続けた。
シチロージはすっかりよい調子で都々逸を詠っている。
「お酒飲む人しんから可愛い 飲んでくだまきゃなお可愛い…」
暑気払いにと出された鰻とつやつやとした香りのよいご飯、止め椀が済んで、最後に食べやすい大きさに切られた西瓜が出された。まだ飲んでいそうな様子に香の物を少し足して仲居が、お食事はこれで終いですがどうぞごゆっくりなさって下さい、と裏に引いた。
酒も好きだが甘い物も好きなシチロージが、赤く熟れた西瓜を嬉しそうに食べている。カンベエは自分の西瓜の皿をシチロージの方に滑らせた。
皿を押しやった左手を引こうとした時、シチロージの右手が、つ、とその手を捉えた。
左手で頬杖をつき、カンベエの手を握ったままシチロージはうっとりとカンベエの顔を眺めている。
しばらく待ったがシチロージが手を離す気配がないのでカンベエは言った。
「見られるぞ。いい加減離せ。」
「見られたって構いません。というか、カンベエ様が嫌がるからしませんけど、本当はここであなたに接吻けしたいのを我慢しているくらいです。」
「お主相当酔っているな。」
二合徳利が大分空いている。こんなに飲んだのは随分久しぶりだ。シチロージとて、カンナ村に同行してからは酔っぱらうほど飲む機会はなかっただろう。カンベエもかなり気持ちよく酔っているが、シチロージも相当飲んでいるはずだ。少し箍が外れかかっている。
「私が随行することを許して下さって、本当に…本当にほっとしました。
もし、カンベエ様が私を捨てていかれたら、もう生きていられないと思っていました。それならいっそ、カンベエ様を刺して私も死んでしまおうかと、何度も考えましたよ…。」
閨でカンベエを組み敷きながら耳元で囁くようなことを、こんなところで口に乗せる。
じっと見つめてくる熱く深く蒼い瞳が己の中に染み通ってくるような気がしてカンベエは眼をそらし、杯を口に運んだ。反らした先にはさらさらと流れる川面がある。流れる水が涼を運び、酔いに火照った頬を覚ます。
―シチロージになら、刺されても構わぬ―
心の中でそう思ったが、それを口に出すのは己には似合わないような気がして黙っていた。
黙り込んだカンベエに焦れたように、その手をさらに自分の方に引き寄せ、指を絡ませて握り込んだシチロージが、今にも卓を乗り越えて自分にのしかかりそうな気配であったので、カンベエは目をそらしたまま小さく言った。
「せめて部屋に帰るまで待たぬか。」
待て、をかけられ少し目を見開いた元副官は、そのまま眼を細めてふわりと微笑み、承知、と呟いた。