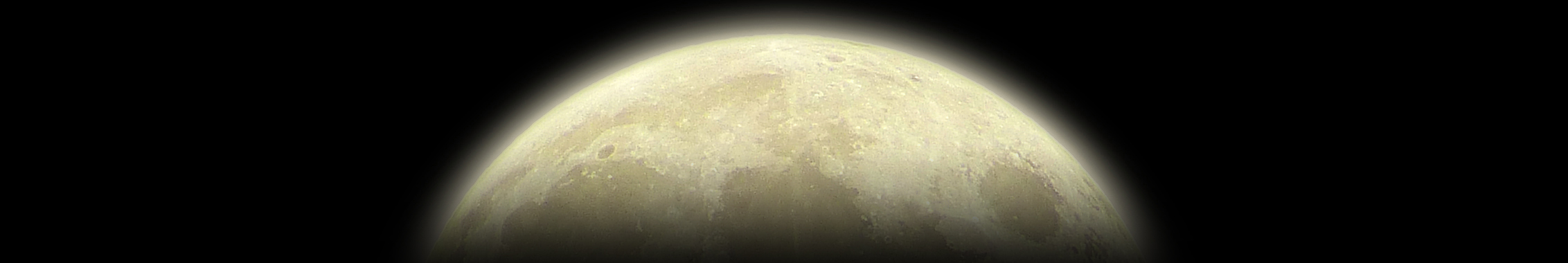作:いくねえ様
家を飛び出した女子高生。補導されてしまうが、優しい補導員に女子高生の心は・・・
なんてね。AVの定番、女子高生モノです。
ちなみに、第4話も同じ設定です。相手は違いますが。
「ただ今帰った。」
帰宅部のカンベエが玄関を上がって、キッチンを覗き込むと、母親のヒョーゴはいつもと違うパープルのスーツでいそいそと立ち上がった。
「どこかに行くのか?」
カンベエが訝しげに問うと、いつもの不機嫌そうな顔に少しだけ笑みを浮かべてヒョーゴは言った。
「うむ、父上がな、今日明日は差し迫った案件がないので町内会婦人支部の温泉旅行に行ってこいと言われたのだ。」
ひっそりとカンベエは眉を潜めた。だが声音は変えずヒョーゴに問う。
「それはまた急な・・・母上が会社を空けても大丈夫なのか?」
「町内会でご近所とのお付き合いを深めるのも営業だからな。」
そう言いながらにやりと笑う。実は温泉旅行に行きたかった母の気持ちにカンベエも気付いていなかったわけではない。ただヒョーゴは、自身の再婚相手、カンベエにとっては義理の父アヤマロの秘書であり、町内会の旅行で会社を空けるわけにはいかないと諦めていたのだ。デフォルトの不機嫌面に浮かぶ笑みは、実は隠し切れない喜びが漏れ出でているのである。
休みなく働く母に与えられた暫しの休息は喜ばしいことだったが、しかしカンベエにとっては大きな問題があった。尤も、それをヒョーゴに伝えることは出来なかった。
「そうか・・・。」
「明日の夜には帰って来るが、晩ご飯は何か頼むか、父上と相談するがいい。
おっと。カンベエ。スカート、やはり短すぎるぞ。」
うきうきと支度をする母にカンベエは笑って頷くしかなかった。
母親が家を出たことを確認すると、カンベエは制服のままスクールバッグを抱えて、キッチンのテーブルに「晩飯不要 カンベエ」と書いたメモを置き、そっと家を出た。早く家を離れないと、義理の弟のキュウゾウが帰って来る。そうなるとどこに行くのだ、とうるさく聞かれて出られなくなるかも知れない。
カンベエが恐れるのは、義父のアヤマロだった。
実父を早くに亡くしたカンベエは、ヒョーゴが勤め先の社長と再婚すると聞いて、複雑な気持ち半分、家族が増えることに期待半分でいた。新しく家族となる父や弟と仲良くできるかどうか・・・出来ればうまくやりたい、と気を使った。
それが功を奏したのか、奏しすぎたのか、最近アヤマロの様子がおかしくなった。
はっきり言えば、カンベエの体を・・・、肢体を眺めている時間が長いのである。
風呂場の曇りガラスの向こうに大きな影が何度か映った。気配に気付いたカンベエが、
「何か用か?」
と問うと、風呂が長いぞよ、と答えて去っていくが、それほど長風呂をしたわけではなく、カンベエも段々とその意味に気付いていた。
先日ついに、朝食時アヤマロはすれ違ったカンベエの短いスカートのお尻を触った。
驚いたカンベエが振り向くと
「今時の女子高生はこんなに短いスカートを穿いておるのか。すぐめくれるではないか。」
と笑ってごまかした。
貞操の危機・・・という言葉がカンベエの頭を過ぎった。ヒョーゴに相談しようかと考えなかったわけではないが、それ以上何かをされたわけではないし、もしそれが原因で、離婚、などという話になれば、別れるだけではない、ヒョーゴがこれまで何年も働き地位を得た会社を辞めなければならなくなる可能性が高い。おいそれと言える話ではなかった。
だが、大人しくアヤマロの餌食になるのは嫌だった。
カンベエはキュウゾウの帰宅路とは別方向の駅に向かった。駅前のコーヒースタンドでカフェラテを頼むと、仲のよいシチロージに今晩遊びに行ってもよいかとメールした。しかしシチロージから返事が返ってきたのは少し後で、大変申し訳ないが今日は既に家族と映画を見に出掛けてきてしまっているのだということだった。
シチロージのところに転がり込もうと考えていたあてが外れてカンベエは思案した。明日は学校に行きたいので制服で出てきたが、こうなると私服に着替えてくればよかった。制服のままではビジネスホテルは泊めてくれないだろう。
21時を回った頃キュウゾウからまだ帰らないのか、とメールが入った。友人宅に泊まる、と返事をしたが、実際には行く当てもなくファミレスでパスタを突いた後ぼんやりと雑誌を眺めていた。
そろそろ店員の目が痛くなってきた23時頃。
ふっとテーブルに影が差した。
頭を上げると、大柄な男がカンベエを見下ろしていた。
「高校生がこんな時間に一人で外にいてはいかんぞ。ん?」
高飛車な様子ではなく、穏やかに言われて、カンベエはリアクションに困った。無視を決め込んで雑誌にもう一度目を落とすと、男は前の席に座った。
「誰かを待っているのか?」
「・・・別に。帰りたくないだけだ。」
「ほほう。親御と喧嘩でもしたか。」
「お主には関係なかろう。」
これはナンパ、というものなのだろうかと、カンベエは相手を改めて見た。大柄なカンベエよりももう一回り大きい。そして浅黒いカンベエよりもずっと黒い肌をしている。銀色の髪を短く刈り上げ、彫りが深く少し影の落ちた眼窩で灰褐色の瞳が面白げに細められている。頬に白く浮き上がる大きな疵が、すわ、やの字のつく職業の人か、とも思えたが、あまり高くはなさそうなジャケットをしかし、きちんと着ている辺り、あまりそういう雰囲気でもない。
「・・・・・・援交はしていない。」
男は一瞬きょとんとした顔をして、それから破顔した。
「いや、これは失礼した。其、そのように見られていたとは少々ショックだが。確かに、こちらもお主がそのような相手を待っているのかと邪推したところもあるので、お互い様だな。」
そういうと男はカンベエの前に居座るつもりか、店員を呼んでコーヒーを注文した。
「決して下心はござらん。だが、妙齢の女性が制服のままでこのような時間まで外をうろうろしているとなると、やはり心配でな。家出されたのか?」
「違う。今日だけ帰りたくないのだ。」
「其が付き添ってやるから、一緒に帰っては如何かな?」
「・・・・・・余計な世話だ。儂には儂の事情がある。」
少し眉間に皺を寄せてカンベエは再び目を伏せ、氷で薄くなったオレンジジュースを口に運んだ。
向かいで大男は、困ったように人差し指でぽりぽりと額を掻いた。
「その、事情とやらを其に教えてくれるわけにはいかんか。何か力になれるかも知れぬ。」
お節介な男だと、カンベエはジュースを啜りながら、男を伺った。
「あー、其、名は片山ゴロベエという。お主の様子からすれば、あまり悪さをしようとしているでもなさそう故、身分を明かそう。其、実は警察委託の補導員でな。この辺りは高校生の喧嘩や犯罪も多い故、見回りに出ているのだ。」
カンベエは内心ぎょっとした。悪いことはしていないが、補導員と聞いていい気分の高校生はいない。こんな時間に一人で外出したと学校に報告されるといろいろ面倒そうだ。
ならば、相手の同情を乞うて見逃してもらうに越したことはない。
「力になってもらえるとは思えぬが、事情は話す。」
ゴロベエが頼んだコーヒーが来ると、カンベエはゴロベエに己の窮状を話した。
「ううーむ・・・」
ゴロベエは腕組みをして天を仰いだ。随分と難しい問題である。
カンベエの気持ちもわからないでもない。年頃の娘が、義理の父親に嫌悪感を抱いても何ら不思議ではない。だが実際にその義父が、嫌らしい目でカンベエを見ているのか、誤解されているのかそれは分からない。尻は触られたらしいが、襲われたわけではないのだから。だが襲われてからでは遅い、というのもまた確かである。
義父に不快を感じていたにも関わらず、カンベエはこれまで我慢していた。今日家を飛び出したのも、母親が不在だからだ。ここで無理矢理家に帰しても、カンベエの大人への不信感を煽るだけであろう。
今晩はまずは己が保証人となって、どこかビジネスホテルにでも泊まらせるしかないかと思案した。
「儂のいうことが信じられぬか。」
探るようにカンベエが問うた。苦笑してゴロベエは答えた。
「疑ってはおらぬ。お主の不安はよくわかる。だから今日は帰れ、とは言わぬ。
しかし、このままファミレスで朝まで時間を潰すわけにもいかぬのでな。」
「儂は構わぬ。」
「お主がよくても、其がよくない。補導員として、このまま放っておく訳にもいかんが、其も仕事を他に持つ身でな、徹夜でここにいる、というわけにはいかん。
ホテルには事情を話してやるから、どこかビジネスホテルにでも泊まれ。」
「お主、このような事はよくあるのか?」
ゴロベエをじっと見詰めてカンベエは聞いた。ゴロベエは、辛抱強くカンベエに答えた。
「お主のようなケースは初めてだ。援交目的の女子高生は補導員がいるとなると、さっさと家に帰る。野郎共も話を聞いて家に帰るように諭すが、な。付き添ってやったことはあるが。」
しばらくゴロベエの目を見詰め、そしてカンベエは言った。
「ビジネスホテルには泊まらん。お主のうちに泊めてくれ。」
ゴロベエは慌てた。
「ご、ご冗談を。それはまずい。其、男一人所帯故、女性を、しかも高校生を泊める訳にはいかん。」
「お主が泊めてくれぬのであれば、儂はここに朝までいる。」
ぷい、とそっぽを向いたカンベエにゴロベエは頭を抱えた。全く若い女の子の思考回路は読めない。だが、流石に補導員の自分が高校生を家に連れ込んでは不味かろう。もちろん何かするつもりなどないが、疑われるようなことをするわけにはいかない。
やはり、ここで朝まで付き合うしかないか、とカンベエに目をやると、カンベエはこちらを見ていた。
「だめか?」
その目は探るようで、少し不安げで、ほんの少し甘えるような口調に、ゴロベエの理性は、うっかり陰りをさしてしまった。
男の一人暮らしの部屋など入るのは当然初めてだった。
マーシャルアーツの道場を経営し、また健康器具のネット販売をしているというゴロベエのマンションはかなり広さのある3LDKだった。扉の閉まっている部屋を指さしカンベエがここは?と問うと、普段仕事に使う書斎だという。そちらには入らず、広いリビングダイニングにカンベエを招き入れると、どっしりとしたダイニングテーブルに付かせて、ゴロベエはキッチンに立ちティファールのポットに水を入れスイッチを入れた。
「リビングの横が寝室だ。ベッドを使うがいい。」
「ゴロベエはどこで寝るのだ?」
「其はリビングのカウチで寝るさ。」
「儂がそっちで寝る。押しかけておいて、ベッドを奪うまで出来ぬ。」
「気にするな。若いからといって、ぐっすり寝ぬと肌が荒れるぞ。」
くすり、とカンベエが笑った。
「すまぬ。でもまだ眠くない。リビングを見てもよいか。」
「好きにしろ。TVのリモコンはテーブルの下だ。」
カンベエは物珍しそうにリビングに入っていった。家族の匂いがしない一人暮らしの部屋というのは、馴染みのない雰囲気があるのだろう。
ゴロベエはカンベエが落ち着くようにとハーブティーとクッキーを用意した。健康器具を扱う関係で、健康食品の会社とも多少取引がある。無農薬有機栽培の紅茶というのを買った際に、進められてハーブティーも少し買っていたのだ。女子高生ならばこういうものが好きかも知れないとゴロベエは普段は使わないマイセンのティーカップにそれを注ぎ、盆に載せてリビングに入った。
入ったところでゴロベエは硬直した。
「何をみているのだ。」
カンベエはTVをつけていた。BSチャンネルを見ていたのだろう。
問題は、それがAVチャンネルだと言うことだ。
ゴロベエの方を見ずに、カンベエは答えた。
「一度こういうのが見てみたかったのだ。」
画面の中では男が女の秘部に顔を付け、じゅるじゅると舐めている。
ゴロベエはローテーブルに盆を置くと、カンベエの手からリモコンを取り上げチャンネルを変えた。
「これは18歳未満は見てはいけないのだ。」
「義父はこういうことを儂にしたいのだろうか。」
呟くようにいうカンベエは眼を少し伏せた。
ゴロベエが何も言えずにいると、カンベエはふいっと顔を上げ、ローズティーは好きだ、と言いながらゴロベエの入れた茶を取り上げ唇を寄せた。
今時の高校生にしては化粧っ気のないカンベエの厚い唇がマイセンの白い陶器に触れた時、何やらどきりとしてゴロベエは視線を落とした。途端、無造作に膝を立てたカンベエのスカートがめくれてその奥が露わに見えた。紺色のニーハイソックスからタータンチェックの超ミニのスカートの間に、浅黒く逞しい太股が続き、その先に白い下着が覗いている。慌ててそっぽを向きゴロベエはカンベエから身一つ分離れてカウチに腰を下ろした。
「ゴロベエは彼女はいるのか?」
また唐突にカンベエが尋ねた。
「・・・いや、今はおらぬ。特定の相手というのはいろいろと難しいものなのだ。フリーが気楽でよい。」
「そうか・・・。ゴロベエのような大人は割り切って考えるものなのだろうな。」
カンベエはゴロベエの横顔を見詰めながら言った。ゴロベエは自分の心中が何やらざわついてくるのをやり過ごしていた。
気付かない振りをしているのにカンベエはそっと躙り寄ってきた。そしてコツンとゴロベエの肩に頭を乗せた。
「何故初対面のお主に義父のことを言ってしまったのであろうな。」
「お主はずっと誰かに相談したかったのだろう。おいそれと、話せる内容ではない。其のような、他人の方が話しやすかったのだろうな。明日、お主の母御に義父親の態度は伏せて、お主が年頃なのだから気を使わないといかんと上手くいって進ぜよう。」
「それはありがたい。」
「家に帰らなかったことは叱られることを覚悟しておけよ。」
「仕方あるまいな。ゴロベエが一緒に謝ってくれるのであろう?」
「其の家に泊まったことは言わぬ方がよい・・・朝までファミレスにいたことにしておけ。」
「承知した。」
そう言いながら、カンベエはずりずりとゴロベエに体をすり寄せた。
「おいおい、あまりくっつくな。」
「嫌か?」
「若い娘にくっつかれるのは嫌ではないが、其も男だ。油断をするな。」
「ははははは。」
軽く笑うとカンベエは膝立ちになって、ゴロベエの頚に腕を巻き付けた。
「儂のような色気のない者でも誘惑できるのか?」
カンベエの長い癖毛がゴロベエの頬を掠めた。今時流行の薄い顎髭を蓄えたその肌はしかし、はち切れないばかりに艶やかで瑞々しい。
ふくよかな唇が再び目に入った。ローズティーに濡れたそれが、誘うように開く。
ゴロベエは強くならないようにそっとカンベエを押しのけた。
「ご冗談を。そのような悪ふざけをするものではない。そんなことを他の男にしてみろ。あっという間に押し倒されるぞ。」
押しのけられたカンベエはじっとゴロベエを見ていた。
「学校で巫山戯て男子に抱き付いたが、誰も押し倒しなぞしなかったぞ。」
それは、皆互いに牽制していたのではないのか、とふっと思ったが、そんなことを問い詰めている場合ではない。
「男と二人きりならば、押し倒されている。」
「ゴロベエなら押し倒してもよい。」
「おい。そのようなことを軽々しく言うものではないぞ。」
「でも、いつか処女は失うモノなのであろう?」
「また、突拍子もない・・・だが、処女を結婚するまでとっておくというのも悪くはないことだ。」
「いつか失うものなのであれば・・・。」
ふいにカンベエはゴロベエに抱き付いた。
「それならばゴロベエがよい。」
ゴロベエは慌てた。仮にも己は少年補導員だ。これはまずい。
懐いてくれたのはよいが、これでは自分が犯罪者だ。
「その、気持ちは嬉しいが、其を信頼してくれた気持ちはありがたいのだが、カンベエ、これはまずい。お主其を犯罪者にするつもりか。」
少し逃げ腰になったゴロベエの背中に縋るようにカンベエはゴロベエに抱き付いていた。そのまま体をゴロベエに沿わせ、剥き出しの太股がぐいっとゴロベエの腰を挟み込んだ。
「そんなこと、誰にも言わねば知れぬ。義理の父に犯されるかも知れないなら、せめて最初は好いた人にもらって欲しいのだ。」
まずい。ゴロベエは眼を瞑った。カンベエの匂いと今の言葉に、己が反応してしまった。いい年をしてどうしたことだ。
「頼む・・・ゴロベエ。儂の処女をもらってくれ。」
ずくり、とゴロベエの男が疼いた。
いけない、と思ったが己の腰を挟み込むみっしりと筋肉の張った剥き出しの太股に思わず掌を這わせてしまう。
「そんなことを、言って・・・。絶対後に後悔するぞ。」
「後悔など、せぬ。」
カンベエはゴロベエの背中に顔をすり寄せた。
駄目だ。いけない。
そう思いながらも、ゴロベエの中に衝動が生まれつつあった。
背中に抱き付かれたまま、ゴロベエは左手をさわさわと動かし、スカートの中に入れた。内股の付け根をつつ、と擦り上げると、自分の体にまとわりつく若い体がすいっと緊張するのを感じた。
だが逃げる気配はなかった。ゴロベエは諦めて、カンベエの方に向き直った。
カンベエはゴロベエを逃がすまいと、シャツを握って離さない。その端正な顔とどこか歳に似合わない憂いを秘めた瞳を見詰め、ゴロベエは翻弄されてもよいか、という気になっていた。いずれ、自分よりずっと年上の自分のことなど忘れて、他の男に気が移る時が来るだろう。縋ってくるのならば、その時まで守ってやればよいのだ。
そっとカンベエの滑らかな頬に大きな掌を添えると、その厚い唇に己のそれを押し当てて強く吸った。
巫山戯てキスをしたことぐらいはあったが、ディープな口づけは初めてだった。生暖かい他人の舌が己の口中を蠢いて、舌に絡められる。上顎を舐められ、そして舌を強く吸われる。次第にカンベエの頭はぼうっとなっていった。
ゴロベエがセーターの裾に手をかけ脱がせようとしたので手を挙げると、ゴロベエは頭を抜いたところでそのままカンベエをカウチに押し倒した。セーターが両腕に絡んで動かせない。
ゴロベエの分厚い舌がカンベエの首筋を舐めた。
「あ・・・。」
思わず声が出て自分で驚く。その間にもゴロベエの掌が、薄いブラウスの上から胸を、腹を背中を撫でまくった。物心ついてからこんなに他人に体を触られたことなどない。くすぐったいような感じに身を竦めたが、ゴロベエの手がブラウスの中に入ってくるとじわりとそこから肌が熱くなった。
ゴロベエの手はブラウスをそのままに、背中に回りブラジャーのホックをはずした。そのままブラジャーを頚の方にずらせると、ゴロベエの指がカンベエの乳首を捕らえた。
「あ・・・ン・・・。」
また思わず声が漏れた。そして今度は、その声は止めることが出来なかった。自分の乳首をまさぐるゴロベエの指は強く摘んだかと思うと、次は掠めるかのように細かく先端を擦り、かと思うと乳輪を円を描くようになぞる。
カンベエは自分が喘いでいることに気付いた。
ああ、これがセックスで感じると言うことなのか。
その内に、ゴロベエの片手がブラウスのボタンを外し始めた。ラインの入ったリボンはそのままに、胸から下だけがはだけられる。ゴロベエの顔が降りてきて、既にぷくりと実ったカンベエの乳首を吸い上げた。
「ああ・・・んんんん!」
何かずしりと下腹部に響く感じがして、カンベエは少し仰け反った。
「あ、ゴロベエ、何か、変・・・。」
「そのまま身を任せておけ。気持ち良くしてやる。」
ざらり、と舐め上げそして舌で転がすように乳首を弄ぶ。カンベエの息ははあはあと上がって来ていた。
ゴロベエの手は既に太股を内から、外からなで回していた。
みっしりと筋肉の詰まったカンベエの太股は、鞣し革のように滑らかな肌に覆われ、無駄な肉はなく指で筋肉の筋が追える。内股の四頭筋の作る溝を人差し指で追うとぴくりと跳ねるように膝が閉じようとする。
だが足の間にはゴロベエの大きな体があり、足を閉じることは出来ない。逆にゴロベエの手が、その膝を割り開くようにぐいっと押した。
人の前で大きく足を拡げている恰好は、恥ずかしかった。だがその足の間に男の求めるモノがあることも分かっていた。
ゴロベエの手が肝心の部分を避けるように、尻の肉を撫で回し、むにゅりと掴むのがなぜか少しずつもどかしくなってきた。そうでなくとも弄ばれている乳首がなにか疼いて堪らない気持ちになっている。
と、ぐっとゴロベエの手がカンベエの褌の前を掴んだ。
「うんん!」
そこが既にかちかちに硬く立ち上がっていることにカンベエ自身が驚いた。お年頃故カンベエもそこを自分で慰めたことがある。だが今は触ってもいなかったのに、気付けば褌を突き破りそうにテントを張っているのだった。
「気持ちよいか?」
ゴロベエが耳元で囁く。
「よ、く、わからん・・・」
「そうか。おぼこであったな。」
ゴロベエはチェックのスカートの裾を捲り、純白の褌に包まれたそこを晒した。
「だがな、カンベエ。褌には既にお主の汁が浸みているぞ。」
かっとカンベエは頬に血が上るのを感じた。
「お主は今気持ち良くなって来ているのだ。その感じを追いかければいい。もっと気持ち良くなれる。」
そういうとゴロベエは褌の上からカンベエのモノを舐め始めた。
今度はダイレクトに下腹部にずくりとした衝撃が来た。
もう褌の中の己が膨らみすぎて痛い。カンベエの体が自然と捩れた。ゴロベエが褌ごとカンベエ自身を掴んで擦った。
「あ、あ、んん!ゴロベエ!も、出そうだ!」
その途端ゴロベエの太い指が、ぐっとカンベエの根本を押さえた。発射寸前の衝撃は食い止められ、カンベエは息を詰めた。
「もう少し、我慢しろ。もっと気持ちよくしてやる。」
喘ぐカンベエにもう一度口づけて、ゴロベエは言った。ルームライトを背にして一層黒く沈む顔に白く縁取られた褐色の瞳がじっとカンベエを見詰めて、その先にあるものが少しだけ、怖い、とカンベエは思った。
体を裏返され、褌が解かれた。腕に絡み付いたセーターとブラウスも、捲れ上がったスカートもそのままに、秘部だけが露わにされ、心許ない気持ちになったが、両の尻たぶにゴロベエの掌がかけられ、ぐい、と割り開かれた途端、かっと頬に血が上った。己の望んだこととは言え、人目にさらす場所ではない。知らず、ゴロベエの手に逆らうように尻がすぼむ。
「カンベエ、お主の孔は皺も細かくて可愛いぞ。」
ゴロベエが息を吹きかけながら、囁く。そして、足の間に垂れるカンベエのふぐりを舌で突いた。その舌が、そのままずるずると這い上がり、カンベエの秘所をざらりと舐め上げた。
「ああ・・・」
それだけの事なのに、体中が疼く。今は嬲られていない乳首が物足りない。
ぴちゃり。じゅっ。
ゴロベエが音を立ててそこを吸う。かと思えば、舌をぐり、と捻子込む。
「嫌・・・なんか・・・変・・・」
自分の腰が、勝手に揺れて、ゴロベエの顔に押し付けたくなる。
その時たらり、と何かが腰に垂らされた。ひやりとしたその感覚に、ふっと覚めるような感じが一瞬したが。次の瞬間尻孔に捻子込まれた、ゴロベエの指の感触に体が竦んだ。
「力を抜け。・・・そう・・・ゆっくり息をしろ。」
ゴロベエの低く柔らかい声が囁く。指が、ずるり、ずるりと出たり入ったりする感じは奇妙で、だが、そこから下腹部に広がる波は、今まで感じたことのないものだった。
「あ・・・あ・・・ゴロベエ、変だ・・・痺れる・・・」
段々と譫言のようになるカンベエに、ゴロベエは指を増やしながら言った。
「それでいい、よければよいと言え、そこをもっと嬲ってやろう。」
ぐちゅ、ぐちゅ、と音を立てて壺を捏ねくられ、カンベエは自分の頭の芯がだんだんぼやけてくるのを感じた。
ずる、とゴロベエの指が抜かれて、カンベエはその喪失感にゴロベエを振り返った。
「あ・・・」
カンベエの目に入ったのは、ゴロベエの股間に聳える、巨大な逸物だった。
裸になったゴロベエのそれは、カンベエの大きめのそれより、更に一回りは大きい。それが今、天を衝くように硬くそそり立っていた。
「咥えられるか?」
目を見張り固まってしまったカンベエの顔に、膝立ちで己のそれを近づけてゴロベエは言った。
ごくり、と息を飲んで、それからカンベエは恐る恐る口を開けた。
これをフェラチオというのだ、と、それくらいの知識はある。自分も同じモノを持っているのだから、大体どうすれば気持ちがよいのか予想は付く。
カンベエは口いっぱいになるまでゴロベエを含むと、次に口を窄ませるようにして引いた。ゴロベエの雁の部分を丁寧に舐める。
手はまだ絡まったままで使えないが、その分一所懸命舌を動かした。鈴口の先から先走りの透明な滴が流れ出し、その塩辛い味に、カンベエはゴロベエが己の舌に舐められて感じてくれているのだと知った。
もっと、気持ちよくなって欲しい。そして、自分ももっと気持ちよくして欲しい。
ちゅう、とゴロベエのモノを吸い上げると、頭上で、く、と息を詰める気配がした。
ゴロベエの大きな掌がカンベエの髪の毛に差し入れられ、支えた。ゆっくりとゴロベエが腰を動かしカンベエの喉を突いた。
咽せそうになったカンベエが思わず口を開け、けほっと咳き込むとゴロベエは腰を引いた。
「苦しかったか?」
「心配は無用だ。」
少し涙目になりながらカンベエはゴロベエを見上げた。
「それよりも、お主がさっき弄ったところが疼いて堪らぬ。ゴロベエ・・・続きを早く・・・」
半裸となった逞しい胸の飾りは赤く大きく熟れ、チェックのスカートの下からは跳ね上がった若々しいカンベエの肉棒が顔を出している。
ゴロベエは絡まったセーターとブラウスを脱がせてやって、もう一度カンベエを四つん這いにさせた。
痛いほどに張り詰めた己のそれにローションを塗り、ゆっくりとカンベエのそこに当てた。
「カンベエ、お主の処女、もらい受けるぞ。」
めり。
重量に、割り開かれる感覚に、カンベエは息を飲んだ。
「あああ・・・ご、ゴロベエ・・・!」
ぐ、ぐ、と少しずつ押し込まれるそれに、カンベエは二つに裂けそうに思えた。歯を食いしばって耐える。それは痛みではなく、どうしようもない圧迫感だった。
どれほど入ったところか。突然それは逆に引かれた。
「ひぃ・・・あああ、んんん。」
己の口から一際高い喘ぎ声が漏れ、カンベエはそれが自分の声かと驚いた。しかし、もう声は止まらない。
ぐじゅり、ず、ぐじゅり、ず。
徐々に深くなる注挿に全身を揺さぶられ、切ない喘ぎ声は途切れることなく響く。
腰から競り上がる快感は前の刺激で感じるモノとは違い、内股も胸までも痺れるような感じがする。
後からゴロベエが伸し掛かり、その手がカンベエの胸と棹を嬲る。
「ああ!うう、い、いきそうだ、あ!」
ふいに、注挿が止まり、カンベエが深く息をしていると、ゴロベエが中に入ったままカンベエの体を表に返した。
体の中に硬い棒を押し入れられたまま動いたその刺激に、カンベエはゴロベエの腕を強く掴んで仰け反った。
ゴロベエが、残されたスカートを跳ね上げるカンベエのモノに手を掛ける。
カンベエは潤んだ目を開いて、ゴロベエを見上げた。
「そのような、艶っぽい目で見上げてくれるな。我慢できなくなる。」
ゴロベエは少し切羽詰まった口調で苦笑し、カンベエのモノを扱きながら注挿を再開した。
分厚い唇で胸の飾りを啄む。
カンベエの喘ぎ声は段々と大きくなり、泣いているかのようだった。その腕はゴロベエの頭に周り、しっかりと抱き寄せていた。
注挿はだんだんと激しくなり、ぱんぱんと体が打ち付けられた。同時にカンベエの体内で一際快感が競り上がってきた。
内股と胸だけではなく、腹の中で何かが膨れ上がり、突如としてそれは脳天まで衝き上がってきた。
「ひ・・・あ・・・ご、ゴロベエ!いく!いってしまう!」
掠れたカンベエの悲鳴に、ゴロベエは汗を散らせて更に、強く打ち込んだ。
カンベエの腕に力が入り、まるでゴロベエの体を押しのけようとするかのように体が反った。ゴロベエの体を挟み込んだ足が、痙攣するように伸びる。
ごぶり、と腹の間にカンベエのモノから白濁した熱い熱がぶちまけられた。
「そ、其も、耐えられぬ。中に、出すぞ。」
一層強く腰が押し付けられた瞬間、カンベエの体の中に、どくり、と熱い塊が打ち込まれた。数回大きくゴロベエは脈打ち、そして、ゆっくりとカンベエを抱き締めた。
力の抜けた腕をそれでも、そっとゴロベエの首に回して、もっと愛してくれ、と囁くカンベエに、全くご冗談を、と苦笑しながら、ゴロベエは再び己のモノが力を取り戻すのを感じずにはいられなかった。