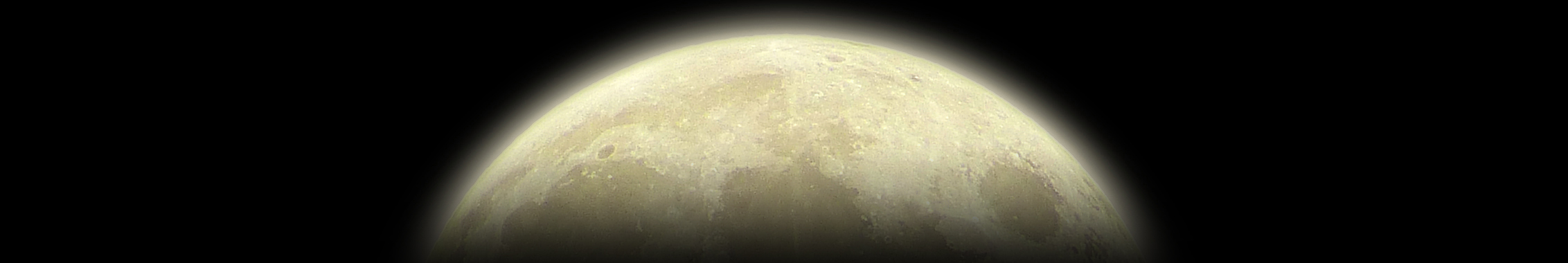作:エデイ様
この話は「第7話 癒す! 」「第8話怒る!」「第15話 ずぶ濡れ! 」「第16話 死す!」の4話連作パラレルシリーズとなっております。
各話完結しておりますのでどの話からお読み頂いても問題ないと思いますが、一応上記番号順に読み進めていただくことを想定しております。
ゴロ×カンオンリー。糖分過多。
ギャグなのか、シリアスなのか、それが問題だ(…)。
大人でダンディーなゴロさんをお求めの方にはオススメ出来ませんのでご注意ください。
小さな机を、まるで枕でも抱えるようにして熟睡しているカンベエの姿を放課後のがらんとした教室の隅に見つけて、ゴロベエは廊下を歩く足を止めた。
開け放たれた窓からは5月の心地良い風がカンベエの長く垂らした髪の先端を微かに揺らし、柔らかな春の陽射しが黒板の前に舞い散る塵芥を銀粉のように光らせている。
ゴロベエは右腕に嵌めた腕時計で職員会議が始まるまでに30分ほど時間に余裕があることを確認すると、教室の扉を開けた。
「カンベエ殿」
つかつかと机に伏せて眠ったままでいるカンベエに近づくと前の席の椅子の背もたれを長い足で跨ぎながら逆向きに腰掛け、カンベエの耳元に顔を寄せながら再び大きな声で名前を呼んだ。
しばらくすると、カンベエから「ぅぅ…」と獣が唸るようなくぐもった声が聞こえてきた。
「カンベエ殿。お主は今日、一日中そうして寝ておったであろう。昼飯の時間以外」
「…よく見ておるな」
「それは勿論」
ゴロベエは肩の力を抜きながら大きなため息を一つ吐いた。
「学校は昼寝をする場所ではござらぬ」
ふっと空気を漏らすような苦笑と共に、ようやくカンベエが眠そうな目を擦りながら顔をあげた。
「昨夜お主に肛門が痺れるほど犯られたせいで、立てぬ」
「カンベエ殿!」
ゴロベエは咄嗟に顔を赤くしながら眼鏡のフレームの淵に手をかけて、ニヤニヤと人の悪い笑みを浮かべているカンベエを睨んだ。
昨夜夜桜見物と洒落込んだ二人は、酒を片手に深夜の校庭に忍び込み大いに盛り上がった。
散りかけた桜の木の下でほろ酔いに目元を赤く潤ませたカンベエはたまらなくゴロベエの欲情を誘い、飽きることなく何度も何度も口を吸い、何故かけらけらと笑い出したカンベエを桜の木の下に押し倒して緩んだ着物の襟元から手を忍ばせてみれば突然カンベエに、「ここではイヤダ」と拒絶された。
なけなしの理性を総動員させ、逸る気持ちを抑えながら足元が覚束ないカンベエを引き摺るようにしてやっとの思いで家に辿りついてみればカンベエは、乱れた着物もそのままに、ぐうぐうと眠りこけていたのだった。
叩いてもつねっても全く起きる様子はない。
結局ゴロベエは泣く泣くカンベエの寝顔を横目に一人寂しく左手の世話になっていたのだ。
天地天命に誓って、“肛門が痺れるほど”犯らせてもらってなど、いない。
しかし寝姿を眺めているだけでは飽きたらず、寝ているカンベエの体の至る部分を舐めたり、何をしても起きないことを良いことにありとあらゆるポーズを取らせていたら、それはそれで大層興奮したのだった。
今朝ごそごそと何かが動き回る気配に目を開けてみると、カンベエがベッドの周囲に散乱しているティッシュの屑をしげしげと観察していた。
唐突に意識のない男の体を散々好き勝手に弄くり回していた記憶が蘇ると同時に後ろめたさに襲われて、一瞬で目が覚める。
「…いつの間にか寝てしまっていたようだな」
不自然なくらいのんびりとした声に、ちらりと送られる流し目。
明らかに昨夜自分が寝ている間何をされていたのかということに気付いている。
ゴロベエは背中に冷たい汗が伝うのを感じなら、カンベエの視線を避けるようにして「勝手に寝てしまった借りは、今夜返してもらう」と宣言したが、その声は弱弱しく小さかった。
「ははは、冗談だ。今夜きっちりと借りは返すから、お主の好きなようにしろ」
カンベエのこんな何気ない言葉一つで熱を持ってしまう己の体が恨めしい。
笑いながら両手を上に伸ばして体をほぐしているらしいカンベエの顔を見ないようにしながら、ゴロベエは空咳を一つ零した。
「それはともかく、こんなことではまた赤点を取りますぞ」
「む?それは不味いな。赤点の取りすぎで留年するなど、格好が悪い」
「同感ですな」
「…超ヤベー」
ふざけた言葉を棒読みにしながら今度は大きな口を開けて欠伸をし、カンベエはゴロベエの顔を見てにっこりと笑った。
カンベエからは当然のように何の緊張感も伝わってくることはない。
顎鬚を生やした面構えはどこをどう間違って見ても女には見えないというのに、白いブラウスに丈の短いプリーツスカートという奇妙な制服姿。
自分を含めた年下の教師陣に対して、態度はどこまでも偉そうでふてぶてしい。
そのくせ何が楽しいのか時折、今のように昨今の学生を真似したかのようなはすっぱな言葉を好んで使う。
そのどれもがカンベエの魅力を損なうことなく、むしろ愛らしさとして目に映るのだから、ほとほと自分の病は重症なのだろうと思う。
つまり教え子で、恋人で、兄でもある、目の前に座っているこの年上の男に自分は夢中なのだった。
伸びをしているカンベエの白いブラウスの胸元に留まった大きなリボンが揺れて、滑らかな褐色の色をした喉の隆起が艶かしくゴロベエを誘っている。
ゴロベエは喉を鳴らすと、カンベエの顎に手をかけて顔を寄せた。
唇が触れ合う寸前に視界が遮られ、気がつけば唇にはカンベエの手に持つ大学ノートが押し付けられていた。
「ノートが汚れる」
澄ました顔をしてノートを机の下にしまっているカンベエをゴロベエは恨めしそうな顔をして見つめていた。
すでに教師としての威厳など跡形もなく霧散しているということに本人は気付いていない。
「カンベエ殿。キスしたい」
「帰ったらな」
「…出来の悪い生徒をこれからつきっきりで教えるご褒美が今欲しい」
カンベエは駄々を捏ねる甘ったれな年下の恋人に向かって困ったように眉を下げてみせたが、諦めたようにゴロベエの首にぶらさがるネクタイを引き寄せるようにして口付けた。
触れるだけのキスであったが、カンベエに押し当てられた唇から甘く痺れるような刺激が伝わってきて体の芯が疼く。
与えられた熱が離れてゆくのを名残惜しく感じながら、ゴロベエは逃げてゆく温もりを留めておくかのようにそっと自分の唇を指の腹で押さえた。
カンベエはそんなゴロベエの様子を満足そうに見つめながら、秘密めいた微笑を浮かべていた。
「今日の帰りは遅いのか?」
「職員会議が終わり次第、飛んで帰る」
カンベエは頷くと、机の横にぶら下げられているショッキングピンクの色をしたリュックのジッパーを開けて、中からタータンチェックの柄模様の生地で作られた花のコサージュがついた髪ゴムをゴロベエに手渡した。
ゴロベエはカンベエの背後に回ると、カンベエの長い髪を手櫛で耳よりも少し高い位置で一つにまとめ、渡された花のコサージュがポニーテールの下に納まるようにして留めた。
癖の強いカンベエの髪は大きな花のコサージュをくるむように半円を描きながら揺れている。
「可愛い」
「当然だ」
「でも言いたい」
二人は肩を並べながら教室を出ると、長い廊下を下駄箱のある昇降口まで歩いた。
踵をつぶした上履きを脱いで茶色のローファーに無造作に足を入れるカンベエの姿をぼんやりと眺めていると、靴を履き終えたカンベエがくるりと体を反転させて、唇の両端を上げる。
「ゴロベエ先生、さようなら」
「某が帰るまでに宿題を終わらせておくのだぞ」
鼻に皺を思い切り寄せながら舌を出して去ってゆくカンベエの後姿を見送りながら、ゴロベエはぽきぽきと肩を回して職員室へと向かった。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2年と2ヶ月と3日の間だけ、弟と暮らしていたことがある。
弟は4つ年下で、名前をゴロベエといい、新しい母親と一緒にやってきた。
母親は安っぽい化粧の臭いが体臭となって染み付いているような人で、自分と同じような浅黒い肌をした幼い弟は初めのうちこそ不安そうな顔でカンベエの様子を伺っているようであったが、野球ボールを握らせてやると、すぐにくったくのない笑顔を見せて恥ずかしそうに「ありがとう」と呟くと、ボールを持っていない方の手で自分の手を握ってきた。
それまで酒に酔っては怒鳴り散らす父親と自分の二人しかいなかったアパートの部屋で、幼い弟が自分の帰りを待っている。
初めて出来た兄弟の存在が嬉しくて、カンベエは毎日のようにゴロベエの相手をして遊んだ。
自分が持っている数少ない玩具の全てを与え、育児を放棄しがちな母親の代わりに風呂に入れ、弟が食事を抜かれて腹をすかせることがないようにと世話をした。
柔らかな銀色をした髪を撫でてやると弟は子猫のように目を細めながら嬉しそうに擦り寄ってくる。
そのうち弟は何かするたびに「いい子して」とカンベエに頭を撫でることを強請りながら甘えてくるようになった。
何でもカンベエの真似をしたがり、後をついてきては、大きな声で笑う弟が心の底から可愛いと思った。
だからカンベエは父親が次第に新しい母親に向かって暴力を振るうようになったことについて、子供らしい正義感による怒りを感じるよりも、弟を奪われることに対する警戒に怯えていた。
父親は酒に酔っては母親に向かって散々暴言を吐いた挙句力任せに殴る蹴るの暴行を加えた。
このままでは死んでしまうのではないかと思われるくらいそれは容赦がないもので、カンベエが止めさせようと間に入ると、ますます逆上して手が付けられなくなる。
カンベエはこの母親についてあまり好きにはなれなかったが、それでもこの母が弟を連れて家を出て行ってしまうことだけは絶対に避けたかった。
万が一この人が一人で家を出たとしても、父が幼い弟を家から追い出さないという保障はどこにもない。
小さな体で100%の信頼をぶつけてくる幼い弟の存在を自分から奪わないでほしい。
きっと今のような生活は長くは続かない。近い未来、必ず崩壊は訪れる。
子供特有の鋭い勘がカンベエにそう告げていたが、それでもカンベエは家族4人で暮らす今の生活を1日でも長く続けたかった。
ある日父親に殴られて泣き叫ぶ母親の前に立つと、血走った目をした父親に力任せに壁に叩きつけられ、軽い脳震盪を起こしてその場に蹲った。
空ろな瞳で母親の姿を探すと、怒りに顔を赤くした弟の姿が目に入る。
弟の手には小さな体に不似合いな大きな包丁が握られていた。
「よせ」と叫んだつもりが、声にはならなかった。
父親は突然現れた弟を見て鼻白んでいたようだったが、弟は包丁を向けたまま父親目掛けて突っ込んでいった。
父親は簡単にこれをあしらったが、弟の握り絞めている包丁を取り上げようとして苦戦しているようだった。
弟は無茶苦茶に体を捩って抵抗していた。
しばらく揉みあっていたかと思うと、突然カンベエの目の前に鮮血が飛び散った。
父親が驚いたように後ずさる。
弟は血の滲んだ包丁を手にしたまま、泣き声一つあげることなくその場に立ち竦んでいた。
弟のふっくらとした左の頬はざくりと割れて、ざくろのような赤い肉からぼとぼとと血が流れ出して着ていたTシャツを赤く染めている。
カンベエの耳には母親の劈くような叫び声も、父親の言い訳をするような喚き声も聞こえてはこなかった。
全ての音が消え去ったかのような静寂の中で、言葉を失ったまま血に染まった弟の姿をひたすら凝視していた。
弟はカンベエの方を振り向くと、静かに笑った。
沈黙が弾ける。
「兄ちゃん」と弟が自分を呼ぶ声が届く。
そしてゆっくりと体を傾けると、頭を自分の前に差し出した。
「いい子して」
初めて出来た弟という存在が嬉しくて、ずっと一緒に居たかった。
一人で食べる弁当も、弟が一緒だとご馳走のように感じられて楽しかった。
呪文のような弟の鼻歌混じりの歌を聞いてやることだって、ちっとも嫌なことではなかった。
弟と一緒に学校に通うようになったら、宿題を手伝ってやる。
同じ野球チームに入ったら、弟とキャッチボールをするために小遣いをためてグローブを買う。
弟が喜ぶことならば、何だってしてやりたかったのに。
頬に一生消えることのない醜い傷跡を残した弟は、その後母親に連れられて家を出て行った。
父親は以前に増して生活が荒れて、暴力の矛先は自分に向けられるようになった。
そして酒が抜けると痣だらけになった自分の体を抱きしめながら涙を零して懺悔した。
「寂しいんだ」と父親はカンベエに言った。
淋しい。
音もなく降り積もる雪のように、しんしんとした淋しさがカンベエの空っぽの心の隙間を埋めるようにして満ちてゆく。
苦しい、と淋しいはとても良く似ている。
弟に会えなくなって、自分もずっと淋しかった。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
シャラリ、とゴロベエが取り出してきたそれを見て、清潔なベッドの上で不自由な姿勢を取らされていたカンベエはひゅっと小さく咽喉を鳴らした。
艶やかなパールピンクの色をした球体が、間に乳白色に光る紛い物の真珠の粒を挟んで繋がっている。
留め金の外れたネックレスのように連なったそれは、ゴロベエの褐色の色をした太い指の隙間から滴り落ちるようにして垂れていた。
ゴロベエは言葉もなく吸い寄せられるように凝視しているカンベエにこれを見せ付けるようにしながら、ゆっくりとオイルを摺りこんでいった。
大小の粒はゴロベエの掌の内で禍々しい軟体動物が身を捩るように蠢き、ベッドサイドに置かれたスタンドライトの淡い光に反射して控え目な輝きを放っている。
カンベエは、あぁ…と溜息のような息を吐いて、睫を伏せた。
下半身がずくりと熱を持ったように、疼いた。
ゴロベエがカンベエの窮屈な穴の中を解すために厭らしく音をたてながら埋めていた二本の指を名残惜しそうに引き抜くと、両腕を一括りに縛られたまま獣のように四つ這いの姿勢を取らされ、尻だけを高く持ち上げたカンベエの咽喉から音のない悲鳴が漏れる。
オイルで滑りが良くなった責具の先端をひくひくと収縮を繰り返すカンベエの後ろの窄みに押し込むと、ゴロベエの愛撫ですっかり柔らかく溶けた穴は、くぷりと丸い球体を苦もなく飲み込んだ。
周囲を白い粘着質の液体で濡らした窄まりはゴロベエが見つめる中まるで「もっと」とおねだりでもしているかのように切なくその入り口を閉じる。
責具を咥えた淵の周囲をなぞるようにして指の腹で擦りながら、ゴロベエはゆっくりと連なる球を更に奥へと押し込んでいった。
「ふぅっ…、っ…んんっ…」
大小異なる大きさをしたパールピンクに光る球が次々とカンベエの狭い器官の奥へと埋め込まれてゆく。
カンベエはじわじわと内臓が圧迫されてゆくような苦しさに肩で大きく息をつきながら、切なげに眉を寄せて大きく喘いでいた。
時折、悪戯のように球と一緒に入り込んでくるゴロベエの指がカリっと内壁を擦り、その度に入り口がビクリと引き攣るような動きを見せる。
「辛い?」
カンベエの耳元で、吹き込むようにして囁かれたそれは、この場に不自然なくらい労わりに満ちた優しい声だった。
カンベエは唇を噛んだまま、長い髪を揺らして首を横に振った。
じわりと、額に汗が滲む。
下半身が重苦しく、埋め込まれた異物が熱を発しているように、熱い。
くぷり、とまた一つ大きな球が挿入されていた。
きつく閉じる内壁を掻き分けるようにして大小の球が蠢き、痺れるような熱が背筋を這い登る。
以前同じような責具を使われた時は、ビー玉よりも小さな球が2m以上も連なったものだった。
気が遠くなるような長い時間をかけて2mもあるビー玉の数珠の全てをみっちりと詰め込まれた苦しさに悶えていると、口を塞がれたまま突然一気に引き摺り出され、快楽の淵へと真っ逆さまに突き落とされた。
あの時の内臓が引き攣れ目が眩むような強烈な衝撃を思い出しながら、カンベエは恐怖と期待に体を熱くしていた。
今度のものは、その時のものより球の大きさは倍以上あるとはいえ、はるかに短い。
「あと、3つだから…」
背後から聞こえるゴロベエの声にカンベエは肩を震わせることしか出来ずにいた。
下腹部が押し込まれた球体でいっぱいになっているような不快感に耐えながら、ぽたりとついにカンベエの眦から涙の雫が零れ落ちた。
ようやく全ての球がカンベエの内臓へと納まる頃には、全身が汗に濡れていた。
触れられてもいないのに、カンベエの前の部分はこれから起こるであろう快楽への期待に屹立し、先走りに先端をしとどに濡らしている。
密部が収縮を繰り返すたびに埋め込まれた球が内部で不快な連鎖反応を起こしてカンベエを苦しめる。
ゴロベエはカンベエの両脇の下に手を差し入れて軽々と抱き起こすと、濡れた睫を舌の先で拭うように口付けを落とした。
カンベエの逞しい胸筋は大きく上下し、割れた腹筋を覆う薄い皮膚の上にはぴりぴりと緊張が走っている。
玩具を孕みながら欲の部分を勃たせて、内股を細かく痙攣させている様が卑猥だった。
胡坐をかいたゴロベエの前でカンベエは浅い呼吸を繰り返していた。
「…っ、ゴロベエ」
「ん?」
ゴロベエはゆっくりとカンベエの体を引き寄せると、半開きになった唇に吸い付いた。
「ぅ…んっ…」
カンベエの歯列の裏をぞろりと舐め上げ、しばらく舌先で突くように口腔を堪能してから舌を絡ませる。
唾液を喉の奥へと流し込みながら、尻の中に収まっている責具の先端部分を少しだけ引っ張るようにして弄ると、途端にカンベエからくぐもった悲鳴のような嬌声が漏れた。
逃げを打ち始めた舌に吸い付き、責具を咥えたままの後孔の周囲を弄ると面白いようにカンベエの体がビクビクと跳ねる。
硬く張詰めた互いのペニスが腹の上で擦れあう。
飲み込みきれない唾液が、カンベエの口の端からだらしなく垂れ流されていた。
長すぎる口付けからようやく解放されると、カンベエはゴロベエの肩に額をこすり付け縋るようにして身を支えなければならなかった。
「ゴロベエっ…っ!」
切羽詰ったように自分の名を呼ぶカンベエを、じらすようにゴロベエがゆっくりと首を傾げる。
「も…苦し…っっ…」
甘えたような鼻にかかった声でカンベエが限界を訴える。
「カンベエ殿、かわいい…」
ふふっとゴロベエは頬を緩めながら、カンベエの背中にまわした腕に力を込めた。
「…っ、早くっ…」
熱の固まりはカンベエの奥で、今にも弾けてしまいそうなほどに膨張している。
「普段の尊大な兄さんぶった態度とは大違いだ」
「ゴロっ…ベエ!」
カンベエは己の屹立したものをゴロベエの下半身に擦り付けるようにして先を強請った。
ゴロベエはカンベエの上気した頬に残る涙の痕を指の腹でなぞるようにして優しく撫で上げると、カンベエの耳元でそっと囁いた。
「自分で、出してみせて」
「な…に…」
カンベエは驚きに両目を瞠くと、目の前で嫣然と微笑む男の顔を見つめた。
カンベエの両の腕は手首と親指の部分で縛られて自由が利かないようになっている。
「出っ、出来ぬ…」
怖ろしいものでもみるように顔を強張らせて首を振るカンベエの頬を挟むように両手を添えながら、ゴロベエはカンベエの豊かな睫の上に再び触れるようなキスを落とした。
下腹部に埋め込まれた熱はもう耐え切れないほどに熟している。
いつまでも口を閉ざしたまま返事を返さないゴロベエにカンベエは絶望的な眼差しを向けると、ついに両目を閉じて項垂れるようにして頷いた。
それが合図だった。
「んーーーーっ、っ、…ふぅっ、…」
カンベエのひくつく濡れた穴からまた一つ、ぬめった球が半分顔を出している。
少しでもカンベエが力を抜けば、再び奥へと引っ込んでしまいそうだ。
初めのうちはゴロベエの前に尻を突き出すような格好で球体をひり出すように強制されていたカンベエだったが、今は体を起こされてゴロベエに両肩を支えられながら、しゃがみ込む姿勢で後ろに埋め込まれた球を排出しなければならなかった。
「ぅう…」
はあっという大きなため息と同時にカンベエのくびれた腹の筋肉がうねり、プシュっと一つ哀れな穴から丸い球体が一つ産み落とされた。
「ゴ、ゴロベエっ…ぁ、…ぅ…も、や…」
一括りにされた手首で震える自分の体を支えるようにしながら俯くカンベエの、耐えていた涙が堰を切ったように頬を伝う。
ゴロベエは崩れ落ちそうなカンベエの体を自分の胸で支えるようにして抱き寄せると、片方の手でベッドの脇にあるサイドテーブルの引き出しを開けて、中から銀色をした細いペンのようなものを取り出した。
それは段階式に伸びる差し棒になっていて、さらにグリップの部分を捻ると先端部分のバイブのスイッチが入るようになったものだった。
「無理ではなかろう?」
そう言うと、ゴロベエは振動する差し棒の先端をカンベエの乳首に押し当てた。
「あああああっ」
途端にカンベエの体がビクビクと電流のように体を駆け巡る快感に打ち震え、背中が撓る。
ゴロベエはしばらくカンベエの左右の乳首を苛めるように差し棒を押し当てていたが、徐々に鎖骨やわき腹へとその先端を移動させ、ついにカンベエの硬く勃ち上がって透明の雫を垂らす亀頭の先端にそれを押し当てた。
「うぁっ、…んんっ、あああ」
そのままぐりぐりとバイブの先端を尿道に差し込むように入れると、カンベエは堪らずに体を仰け反らせて甘い悲鳴をあげた。
カンベエの後腔から勢いよくパールに光る球体が続けて2粒飛び出してゆく。
内股に広がる快楽の痙攣が漣のように全身に伝わり、脳内に閃光が走る。
「ゴ、ゴロベエっ…ぅ…ぁ、…ぁあっ…ん」
すすり泣くような濡れた声で名を呼ばれて、ゴロベエは堪らずに目の前で厭らしく腰を振り続ける男の体を抱きしめた。
背中を抱くようにしながら、差し棒の先端をピンクの責め具を咥えている後の孔から奥へと押し込んだ。
「ひっ…、あああああ」
ビクンと硬直し、一瞬棒のように突っ張らせた体が仰け反るようにしてがくがくと前後に跳ねる。
意識を半分飛ばしたような顔をして涎を垂らしながらカンベエは射精していた。
差し棒を引き抜くと、粘液に塗れた尻の割れ目からパールピンクに光る球が飛び出して、ぼとりと最後の1粒がシーツの上に落ちた。
ゴロベエも限界だった。
息つくまもなくカンベエの双丘を乱暴に鷲掴み、捩じ込むようにしてひくつく穴に怒張を突き立てた。
ゴロベエの太いもので突き刺されたカンベエは声にならない悲鳴をあげた。
柔らかく絡みつき硬く締め付けるカンベエの内部をゴロベエは欲望のまま貪り、背後から獣のような格好で串刺しにされながら何度も男のモノに突かれる愉悦にカンベエは、髪を振り乱しながら淫らに喘いだ。
<SEX and HONEY 2 夏 「怒る!」に続く>
- note -
どこが「癒す!」なのか。
…カンベエさまがゴロベエにラブラブされていると、アタクシが癒されるのでございます!
あ、殴らないで…(汗)。
ピンクなオモチャの名前が<ザ・癒す!>(100均で売っていそうだな…)でも良かったんですけどね…そんなとこでギャグとっても仕方なしと止めました。
こんな感じでひたすらいちゃついているこの二人の話が過去と現在を行きつ戻りつ続く予定(…)。