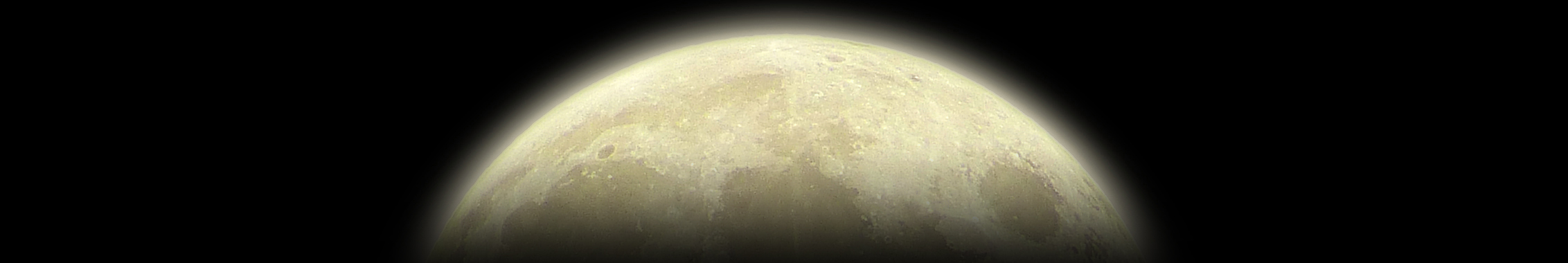作:いくねえ様
傷ついた心を抱えて鄙びた温泉を訪れたカンベエ
美しいカンベエに心惹かれたシチロージの優しくも強引なアプローチに、カンベエは身も心も、少しずつ溶けていく・・・ 。
んだけれど、シチロージがカンベエ様を壊しちゃいそうです。加減しろ。
別れの予感はずっとあった。
兵糧学部の卒業論文は11月中に提出でその諮問は1月だが、提出してしまえば余程のことがない限り卒業は確実となる。まじめな学生のリキチが落とすはずはなく、〆切ぎりぎりまで推敲はしていたが、当日は午前中には提出を済ませ、夜はゆっくりとカンベエと過ごした。
いつものようにカンベエの胸や浮き上がった腹筋を飽くほど舐め回し、カンベエが眦に涙を浮かべるほどしつこく後の孔を弄くりながら棹を吸った。カンベエが出しそうになる度に根本を押さえ、カンベエの方から、頼む、入れてくれ、と強請って遂にその後孔を穿った。ごりごりと入り口を擦り、前立腺を突き上げる衝動に、カンベエが耐え切れず放つと、リキチも堪っていた己の欲をカンベエの腹の中に打ち込んだ。卒論のためしばらくカンベエを抱いていなかったせいか、リキチの脈動は中々止まず、敏感になったカンベエの後孔はしばらくうねるような快感を引き摺った。
ひくひくと疼くカンベエの体をしばらく抱き締め、50前とは思えぬ滑らかな肌に頬ずりをしながらも、いつもより一層無口なリキチに、カンベエの方から促した。
「で、儂に何を言わねばならないと思っているのだ?」
はっと目を見張り、それから顔を背けてわずかの間リキチは逡巡していたが、ぼそり、と呟いた。
「おら、卒業したら郷さけえるだ。」
「・・・そうか。」
それ以上説明される必要はなかった。就職活動をしていないリキチを見ていれば、わかっていたことだった。
リキチが入学したばかりの頃、学部は違うが学年全体の生活相談担当となったのがカンベエだった。オリエンテーションや親睦会の際に、田舎から出てきて一人孤立しがちなリキチを気に掛けてやる内に随分と信用されたらしい。ある日、カンベエの戦略学部准教授室にリキチが尋ねてきて、言いにくそうにしながらも、誰にも言えなかった自分の性癖について告白したのだった。
リキチは農村の土地持ちの総領息子だった。自分も百姓の後を継ぐことに誇りを持っていた。地元の農学校ではなく都会の大学に来たのは偏に勉強熱心故のことである。だが、都会に出てきてリキチは、今まで気付かないふりをしていた己の一面を意識せざるを得なくなった。田舎の冴えない同級生達には感じなかった欲を、街の垢抜けた、・・・そう、同性に感じてしまったのである。
郷にはサナエという許嫁もおり、お互い嫌いではない。親にはもちろん言っていないが婚前交渉も既にあった。都会の女性は確かに化粧も上手く、雑誌に載っているような流行の恰好を難なく着こなしており見惚れる事もあったが、サナエに感じる以上のものを覚えることはなかった。だが、同じ軍営大学の戦略学部の学生達、目付きの鋭い、威風堂々としたサムライ予備生達が同じ一般教養のクラスで、憚ることなく俺はこいつの念兄なのだ、と言った時に、ぞくりと背中を何かが這った。自分が同性に対して性欲を感じているのだと、気付かずにいるには都会は情報に溢れ過ぎていた。
それをごまかすために彼女を作る、というのも一つであったかも知れない。だがそれは、さすがにサナエを裏切ることになると根のまじめなリキチは行き詰まっていた。思い悩んで相談担当のカンベエを訪れたのである。
カンベエも思いもよらない相談に少し呆気にとられたが、リキチがまじめなことはよく知っていたし、恐らく思い詰める性格であることも気付いていたため、何とかしてやりたいと思った。もちろん最初は自分が相手をすることになるなどとは思っていなかった。ただ、カンベエ自身同性愛者であり、比較的安全に遊びで済む相手を見つけられる場所への出入りがあったため何度か連れて行ったのである。
リキチの相手が運良く見つかった時は、自分も他の男に誘われるまま店を出たが、リキチの相手が見つからなかった時はカンベエも誰も相手をせず帰った。ある日リキチがカンベエに問うたのだ。
「先生は、今は決まった相手はいねえだか?」
「うむ・・・最近はおらぬ。忙しいこともあって、決まった相手を作るもままならぬ。」
苦笑するカンベエに、リキチは意を決したように言った。
「なら、おら、おらの相手にはなってくれねえだか?」
ひどく驚きはしたが、リキチが、自分はいずれ郷に帰り結婚しなければならない、でもハッテンバで知らない人とその場限りの出会いを求めるのは性に合わない、ならば恋人になって貰えなくても知った人の方がいい、と顔を真っ赤にしながら利いた風な言い訳をするのがちょっと可愛くなって、まあよかろう、と関係を持った。
そのまま、リキチの卒業までその関係が続いたのである。
夢中になっていたのはリキチの方だった。カンベエよりも大分背は低かったが農作業で鍛え上げられた体は腕も胸板もサムライに劣らず分厚く、牛のような強さでカンベエが気を失うまで抱くのだった。
だが、カンベエがいざ火急の時となれば戦場に立つサムライであることを捨てられぬように、リキチも土を捨てることはできなかった。二人の道は最初から分かれることが決まっていた。
「確かにそろそろ潮時だな。お主も家を継ぐ心持ちを固める時期だ。
もう、ここにも、儂の研究室にも顔を出すなよ。」
さらりとカンベエが言うのを聞いて、リキチは、少しショックを受けた様子だった。
「当たり前だ。お主に振られて泣いている儂の顔が見たいのか?」
優しく微笑んで言うカンベエの言葉に、リキチの方こそが泣き出しそうな顔をした。
リキチに惚れ込んでいたわけではなかったが、嫌いだったわけではない。4年も付き合えば情も移る。あっさりと別れを受け容れたカンベエとて寂しくないわけではなかった。だが、中途半端に引き延ばすことは互いにとって苦しいばかりである。切るべき時は切ることが必要なのだと、それが年長者の己の責任だとカンベエは思っていた。それでも、研究室の窓からふと外を見れば、Xmasイルミネーションの輝く街が思いの外寒さを感じさせて、意外と自分もショックを受けているのだと思った。
大学は既に冬休みに入っており、教職のモノは会議がなければあまり出勤をうるさく言われることはなかった。少し休もう、そう思った。
その宿は街からは電車と車で二時間ほどであったが、存外と山奥にあった。知る人ぞ知る、と言った類の高級温泉旅館で一日に数組しか客を取らない。随分と高くネット割引もないのに、週末やシーズン中は半年先まで予約が取れない密かな人気宿だ。しかし、Xmasも前の年の瀬、平日であったためか運良く予約を取ることが出来た。思い切り贅沢に旨い料理を食べて温泉にでも浸かれば少しは気が晴れるかと思ったのだ。
最寄りの駅まで迎えにきた宿の車に乗ると、それは曲がりくねった山道に入っていた。両側の山肌には既に雪が見られ、信号すらなく延々と続く道に、カンベエは傷ついた獣が逃げ込むにはぴったりだと独りごちた。
民家も途切れた林の奥に隠れ家的に佇む民家風の建物の前で降り立つと、きん、と冷えた空気の中にふうわりと湯の香りが漂って、それだけでも何かほっとする予感がした。
シチロージは自分の4WD-SUVを従業員用の駐車場の奥に止めて、残雪を避けながら建物に向かっていた。この高級温泉旅館「癒しの里」は、シチロージがプロデュースしたチェーンの一つだ。リーズナブルなビジネスホテルを展開する一方で、高級感に特化した割烹旅館も展開し、それは確かに当たった。送迎をしっかりとすれば田舎でも割烹は普通に客を取れる。そちらは雑誌などにも売り込み、大々的に宣伝した。一方でそれに付随した温泉旅館はかなり高級感をアピールし、予約数も限定する。料理が気に入ったセレブが後日私的に使用する、という案配だ。限定されると人は興味を示すモノで、部屋数は少ないが充分に利益が出た。ユキノという女将がしっかりしているので全面的に任しているが、時偶視察と自分の休息を兼ねて訪れる。自分でも気に入っている宿の一つでもある。
宿の前に車が止まる音がして、ああ、今日の客が来たのだな、とふっとそちらを見た。
送迎車から降り立ったのは一人で、一瞬靡いた長い褐色の髪に女性かと思ったが、すっと伸ばした体躯はがっしりと上背があり、偉丈夫であると知れた。なんだ男かと思ったが、何故か目が離せず、旅館の入り口に近づいてくるのを見ていた。
恐らくハリスツイードだろう、かっちりと仕立てのよいライトグレイのジャケットに深いブラウンのタートルネック、生成のコットンパンツをはいた脚はすらりと伸びている。長い癖毛から覗いた横顔は浅黒く、薄い顎髭を整えたそれは端正で、そして、どこか憂いを秘めていた。
気になって帳場に行き確認すると、この昼過ぎの早い時間に一番乗りで来たのは今の客だけで、男一人なのだという。シチロージは仲居を差し置いて、急いで着物に着替えると自ら挨拶に出向いた。
先に玄関でその客に挨拶をした女将のユキノは、いつにないシチロージの態度に呆れたように言った。
「まさか男のお客様に手を出す気じゃないでしょうね。」
女の客に関しては前科があるシチロージである。バイだとは聞いているが、いくら美形でもあの大柄な男に粉を掛けるとは思えなかったのだが・・・。
部屋の扉を軽くノックし、失礼致します、と声を掛けると、窓の外を覗いていた客は振り向いて、おや、という顔をした。普通は仲居か女将が顔を出すであろうところを男が顔を出したので不審に思ったのであろう。
「癒しの里のオーナー、シチロージと申します。」
深い挽茶色の絣の着物に藍の羽織を纏い、淡い金髪を奇麗に撫でつけた男が座敷への障子を開け、躙って入ってきた。
低い穏やかな声でシチロージは言った。
「本日はこちらの宿にご宿泊頂き、真にありがとうございます。至らぬところもあろうかと存じますが、島田様にごゆっくりとして頂きたく存じますので、何なりとお申し付け下さいませ。」
そう言いながらシチロージは持ってきた玉露を頃合いを見計らって湯呑みに注いだ。
「御一服どうぞお上がり下さいませ。」
「忝ない。」
カンベエは座卓にもたれると、玉露を一口口に含んだ。こくり、と喉仏が上下し、シチロージは、その長い首筋にまた目を奪われた。
「旨い・・・。」
「ありがとうございます。」
三つ指をついて頭を下げるシチロージにカンベエは言った。
「オーナー自ら挨拶に来られるとは少し驚いた。随分とお若いのだな。」
穏やかに言うカンベエにシチロージは極上の笑みで返した。
「どうやら私は年よりも大分若く見られるようでして。まだまだ修行が足りないのかも知れません。行き届かぬところがありましたら遠慮なく仰って下さい。
実を申しますと少しお願いがございまして参りました。私も今日は客としてここに来ているのです。お客様の立場に立ってみないと見えないこともあるので、時偶客になってみるのです。」
ほう、とカンベエの目が眇められた。興味を持った様子である。
「もっとも一人で食事をするのは随分と味気ないものでして・・・。島田様はお一人と伺い、もし宜しければ御夕飯をご一緒して頂けないかと。もちろん、お一人でゆっくりと上がられたいのであればご無理は申しません。真に図々しいお願いだとは承知しておりますが、如何でしょうか?」
低く少し掠れたシチロージの声は心地よくその滑らかな口調に、のんびり話をしながら料理を頂く方が旨そうだ、とカンベエは快諾した。カンベエとて、旨い料理こそ誰かと楽しく食べる方がよいと考える方である。シチロージは嬉しそうに、にこりと微笑んだ。
「それでは御夕飯は6時にこちらのお部屋にご用意致します。
それから、差し出がましいとは存じますが、他のお客様は御夕飯時にお宿入りされますご予定ですので、今は大浴場も広々とお使い頂けます。お声をお掛け頂ければお背中などお流し致します。どうぞお使い下さいませ。
お部屋にも露天風呂は付いておりますが、大浴場から見える冬景色はまた格段です。」
カンベエは少し考えていたが、ではます一風呂頂くか、と腰を上げた。シチロージは浴衣はお持ちしますので、そのままでどうぞと促した。
お主も客なのであろうが、とカンベエは笑った。
大浴場の脱衣場に付くと、シチロージは浴衣を籠に入れて、棚に置いた。タオルはいくらでも使えるようになっている。
「大浴場は時々宿の者が様子を見に入りますが、皆様でお使い頂くところなのでご容赦下さいませ。洗い場で垢すりなども致しております。
お洋服は宜しければお部屋にお持ちしておきますがどうされますか。下着などはこちらの袋に入れて下されば結構でございます。」
「そこまでしてくれるのか・・・では、宜しく頼む。」
「畏まりました。貴重品はございませんでしょうか。ではごゆっくりとお寛ぎ下さいませ。」
脱衣所を出る際にそっと振り向くと、シャツを脱ぐカンベエの肌が目に入った。引き締まった背筋、伸び上がり肩に繋がる脇腹の美しいライン、無駄の全くないそのシルエットに、ぞくりと体が震えるのを感じた。
無造作に服を脱ぎ捨て、褌だけ袋に入れるとカンベエは、水墨画風の透かし模様が入ったガラス戸をからりと開けて洗い場に入った。外まではもう一度扉がある。洗い場で髪と体を洗い、湯に浸からないように簡単に髪を団子にして外に出た。
街よりも格段に低い気温に鳥肌が立って、急いで露天風呂に足をつけた。それは適度な温度で、すぐに肩までつかることができた。ほう・・・と息をついた。
各部屋に付いた露天風呂とは違い、やはり大風呂の露天は随分と広かった。気温が低いためか湯煙が濃い。風呂は自然の池のように少し入り組んだ形になっており、カンベエは少しずつ奥の方に行った。岩の影になったところからは風呂場の入り口は見えず、生け垣の向こうには遠くの山が見える。連なる山峰には白い覆いがかかり、冬の澄んだ空気に蒼穹が広がる。しんと静まる中、くみ上げられた湯がとぽとぽと流れる音だけが響く。
ここならば、誰からも見えないと思うと、カンベエは目を閉じて寛いだ。岩に頭を凭せ掛け、ぐっと足を伸ばす。
そういえば、ここではないがリキチと温泉旅行をしたことがあった。檜の内風呂に浸かり火照った肌を、リキチが散々に嬲り、湯中りしかけて風呂から這い出したところを穿たれた。いつもと違うシチュエーションにすっかり興奮したリキチに抱き潰されるかと思った。
くすり、とカンベエは想い出に笑った。
でも、農作業ですっかり硬くなったリキチの掌で乳首を、棹を擦られるのは決して嫌ではなかった。いや、ごりごりとした感触は時に耐え難いほどに快感を与えてくれた。
「ン・・・」
思い出した感触に、自分のモノが少し立ち上がったのを感じた。後ろめたさに目を開けて周りを伺うが、もちろん誰も見てはいない。いけない、と思いつつも手が乳首と己のモノに伸びた。軽く棹を握ったまま、乳首を摘む。ぎゅっと引っ張ると、じわりとそこから快感が広がった。まだ日は高い。柔らかい冬の日差しとはいえ、日の光の中全裸で、湯の中で己の乳首を嬲っている自分の指に感じ始める。握った手を動かしてはいないのに、下腹がうずき始める。
「リキチ・・・」
ゆる、ゆる、と棹を擦り始める。
―先生・・・きれいだ・・・おら、我慢できねぇ・・・―
そう言って、カンベエの体を隈無く舐めたリキチの舌の感覚が蘇る。
「う・・・。」
カンベエは、もう一度周りを伺ってから、そっと湯から出て岩にもたれた。誰か来てはまずい、と思いつつもう手が止まらない。痛いほどに乳首を捻り、分身を強く擦るとあっという間に達し、岩の上に白濁が飛び散った。
湯を掬い証拠を洗い流しながら、空しさが襲ってきた。温泉で暖まった体は中々冷めない。まだ火照りの残る体を冷たい空気に晒して岩にもたれる。自分は一体一人で何をやっているのだ。思ったよりもリキチとの別れがダメージになっているのだと、思い知らされた。
「島田様?」
ふいに岩の向こうからシチロージの声がして、カンベエはびくりと跳ねた。
「おや、こちら側におられましたか。お湯にあたられましたか?」
「うむ・・・いや、少し熱くなっただけだ。もう冷めた。」
何気なさを装って、カンベエは微笑んだ。
腰を手ぬぐいで覆っただけのシチロージが岩陰から覗いた。
「いえ、失礼ながらお背中でもお流ししようかと思ったのですが。宜しければ垢すりマッサージも致しますよ。」
「ああ・・・。それではお主、客ではないではないか。」
「いやいや、宿の者には内緒で、私が勝手にさせて頂きますよ。こう見えても、マッサージの資格も持っておりますし、ボディエステも一通り修めています。ご安心下さい。」
カンベエが岩陰でしていたことには気付いていない様子に、何事もなかったかのように装おうと、カンベエはでは垢すりでも頼むか、とシチロージに従った。洗い場に戻ると、檜の寝台に横たわらせられた。まずは俯せになり、裸で横たわるカンベエの体にシチロージが湯を掛けた。
「お湯加減は如何ですか。」
「丁度よい。」
「では始めますね。」
クリーム状に泡立てられたボディソープが体中に塗られ、擦られた。少し痛いぐらいの垢すりは心地よく、先程感じた後ろめたさも薄れてカンベエはぼんやりと身を任せていた。次に仰向けになり、ごろごろしないように髪を解き頭側に跳ねると、シチロージは髪を丁寧に撫でつけタオルで包み、目元には冷たいタオルを当てる。全身を擦られて垢を流された後に、今度は蜂蜜の香りがするローションが塗られた。ミトン状になった垢すりタオルを外し、シチロージの素手が体にそれを塗り込んでいく。
両腕が終わり、首元から肩に掛けて、そして手は徐々に降りていった。
すっと両の乳首をシチロージの指が掠めた時に、思わず体が竦んだ。シチロージの手はカンベエの胸元を背中から掬うように撫でる。上がってきた掌は、指を開いたまま乳首を擦っていった。タオルに目を閉ざされたまま、カンベエは少し首を反らした。突然シチロージの手が意識され始めた。それは臍の周りに円を描き、尻を巡り、また胸に上がって乳首を何度も掠めていく。
その内それは太股に至った。片足ずつ持ち上げ、根本から膝の辺りまでを何度も往復し、・・・付け根を擦る。その手の甲がふぐりに当たる。
まずい、と思った。自分では分からないが、多分乳首は立っているだろう。それだけならば寒さのせいにできるが、段々と下腹部が熱を持ってきた。横たわった時にはくにゃりと萎れていたモノが、徐々に芯を得てきているのが分かる。早く終わってくれ、と焦っていた。
その時、シチロージの手がまた胸元に上がり、そこで止まった。
「島田様。」
先程より、一段低い、潜めた声でシチロージが囁いた。
「私の手でよければ・・・お慰め致しますが。」
「な・・・」
反論する間はなかった。既にシチロージの手はカンベエのモノにかかり、はちみつローションの付いた手で扱き始めていた。
起き上がろうとしたカンベエは、う、と仰け反った。それでも、目元を覆ったタオルは外し、シチロージを睨もうとしたが、シチロージはカンベエにそっと顔を近づけ、耳元でまた囁いた。
「ご遠慮なさらずに。もうとっくに硬くなっておられます。」
少し掠れた低音は耳から腰に抜けて、カンベエに抵抗する気を失わせた。
「お主・・・こういうことを、どの客にもする、のか?」
「まさか。ただ、島田様が少し寂しげな表情をされていたのがとても気になりまして・・・。
それに、私の手に反応されましたので、男の手でも大丈夫なのだ、と。
どうぞ、御身をお任せ下さい。」
そう言うと、今度は胸の飾りを啄んだ。
びくりと跳ねたカンベエの体を押さえ込むように右手で左胸の乳首を嬲り、舌で右の乳首を転がし、左手は玉と棹を捏ねくり回す。
徐々に唇は下がり、カンベエの臍を少し吸うと、カプリと男の根を咥えた。
「あ!ぁぁ・・・」
思わず喘ぎ声が漏れた。じゅぶ、じゅぶ、と音を立ててシチロージは吸い、舐める。
そして、手はフグリを嬲り、蟻の戸渡りを押し、後の入り口をさすり始めた。
「ああ、そ、そこは・・・」
「こちらに、欲しいのでしょう島田様・・・」
シチロージはカンベエの逞しい太股をぐいっと持ち上げると、そこに顔をつけて、べろり、と舌を這わせた。ちろちろと舐めると、頭上の喘ぎ声が強くなる。
ローションをつけた指を一本捻子込むと、一際切ない声が漏れた。自分の長い指で前面を探り、盛り上がった部分をぐいと押す。
「い、や、駄目、だ、ぁぁ・・・くぅ」
敷いたタオルを握りしめ、カンベエの体が仰け反った。ローションで艶々と輝いた浅黒い肌が波打ち、割れた腹筋が更に影を濃くする。既に触られなくても胸の飾りは小指の先程に立ち上がり、物欲しげに震えていた。
押さえようとしても押さえきれないカンベエの喘ぎ声を耳にして、ちらりとその撓む体に目を向けたシチロージは、予想以上に扇情的な光景に、ずん、と下腹に血が流れ込むのを感じた。
やばい。
やばいと思っていたが、これはとんでもなく、蠱惑的だ。
指を増やしながら壺をこねくり回し、カンベエの鈴口に舌を割り込ませながら、シチロージは我慢できなくなってきた。
顔を離して、カンベエを見ると最早凄惨なほどに色気を漂わせて潤んだ瞳を向けられた。
「し、島田様、入れますよ。」
返事を待たずにシチロージは押し込んだ。
「あああ・・・うううぅぅん・・・」
カンベエの体が捩れた。
ぎゅう、と後孔が締め付ける。シチロージの頭はぐらぐらと湧きそうだった。
ほんとに・・・来る。
この体、極上だ。
「し、しま、だ、様。堪りません・・・動き、ますよ。」
シチロージはカンベエの体を揺さぶり始めた。ゆっくりと差し入れ、ぐっと引く。前立腺が内から衝かれ、粘膜が引き出される。
カンベエはもう、口を閉じることもできず、絶えず喘ぎ声を漏らしていた。
シチロージのモノはどうしようもなくよいところに当たる。
びらびらと返される入り口の粘膜からさざ波のように強い快感が沸き始めた。それは前の刺激から来るものよりも強くていつまでも止まらない。
「あ・・・あ・・・どう、して、」
こんなに気持ちよいのか。カンベエは朦朧とした頭で問うた。快感は最早太股を波打たせ、下腹を痙攣させ、カンベエを大きく仰け反らせたまま声すら出なくなっている。
男根の付け根が大きく膨れ上がる気がして、カンベエは爆ぜた。どく、どく、と何度も吐出しながら中々快感は去らない。
「ああ、島田様、済みません、気持ち良すぎます!」
シチロージが喘いで、抜くとカンベエの腹に精子を飛び散らせた。
ぐったりと足を投げ出したカンベエの体を奇麗に洗い清めると、シチロージはカンベエを抱きかかえるようにして脱衣場に運んだ。
「も・・・よい・・・」
快感の後の脱力感に足がもつれたが、やっと何とか体を支えられるようになった。
シチロージが髪と体を拭い、浴衣を着せて手を添えて立たせる。
「せめて、寄りかかって下さいませ。湯中りされた、ということで。」
何か釈然としないとものを感じながらも、カンベエはシチロージの肩に腕を預け、背中を支えられながら歩いた。通りがかった仲居に水を部屋に持ってくるように言うと、女将のユキノが急いでやってきた。
ユキノは、シチロージに寄りかかるカンベエの無防備に発散するフェロモンに毒気を抜かれてしまった。匂うような色香、浅黒くてわかりにくいが僅かに頬が上気して潤んだ目、しっとりと濡れた唇、湿った髪が張り付く艶やかな肌。
(食ったわね・・・)
と、シチロージを睨むと、まずい、と言う顔をしてそっぽを向く。
「すまぬ、女将。いきなり長風呂をしすぎた。」
意識せぬ流し目をくれながら、カンベエがよろり、と足を踏み出すと、シチロージの手がすっと腰まで降りて支えた。
白い目でシチロージを見ながら、ユキノは部屋まで一緒に行き、仲居と共に布団を敷いた。
「お食事までもう少しお時間がございます。少しお休み下さいませ。」
そしてカンベエの見えないところで、シチロージの頭を一発殴った。
それでも少しうとうとすると、体は妙にすっきりとしていて、夕食前には起き上がり、浴衣を整えた。どっしりとした丹前を羽織り、美しく整えられた庭を眺める。これも各部屋毎に区切られており、他に客がいるのかどうかも感じさせない。
そうこうするうちに、二人分の豪勢な料理が運ばれてきた。同じ浴衣と丹前を羽織ったシチロージが、何食わぬ顔で入ってくる。少し気まずい気がしたが、穏やかに微笑むシチロージに気も解れて、旨い料理に舌鼓を打った。
客商売をしているだけあって、シチロージは穏やかにしかし飽きさせることなく話を運ぶ。どちらかと言えば無口なカンベエからも、上手に話題を引き出し、時には笑わせる。昼間の事が少しだけ引っかからないでもなかったが、それでもカンベエはすっかり気を許していた。
いつの間にかシチロージが「島田様」から「カンベエ様」と呼び方を変えても、それは妙に耳に馴染み、酒が入ると共に気は緩んだ。
だから、話が少しずつプライベートに及んだ時、つい白状をしてしまった。
「カンベエ様、時に、このような時期に何故お一人で温泉になど?」
「うむ・・・まあ、俗な言い方をすれば・・・傷心旅行、だな。」
「おや・・・まさか、離婚でもされた、とか。」
じわりじわりと踏み込んでくるシチロージに、何となく嘘もつきづらく正直に答えてしまう。
「お主、もうわかっておろう。儂は男に抱かれる体だ。」
卑下するでもなく、少し寂しそうにそれだけ言って、カンベエはまた酒を口に運んだ。
その手元をシチロージはじっと見ていたが、すっと立ち上がってカンベエの横に来ると、手をとって言った。
「カンベエ様、お部屋のお風呂もようございます。お酒が回り切らないうちに、入りませんか?」
透き通るように白く滑らかな、しかし筋の浮いた男らしい手に指を絡め取られて、カンベエは誘われるまま湯船に向かった。
部屋の風呂も内風呂と露天に二つに分けられていて、檜の内風呂で暖まった後、露天の岩風呂に浸かり、頭だけ冷やした。昼はよく見なかったが、シチロージの体はカンベエに勝るとも劣らず鍛え上げられていた。肩幅や腰回りはむしろカンベエの方が細いぐらいだ。風呂にカンベエを促しながら、シチロージの手や腰が、時々触れる。触れたところが疼くように思えて、カンベエは伏し目がちとなった。
湯に並んで入りながら、一方のシチロージは舐め回すようにカンベエの体を見ていた。
美しい。
無駄に筋肉だけを鍛えた体ではなく、実戦に即した引き締まった体だった。盛り上がった胸筋、奇麗に割れた腹筋、少し動くだけで滑らかに蠢く腕や大腿の筋肉・・・地の黒い肌は、しかし肌理が細かくつるりとしていて、外の落とされた照明の中では艶やかな大型猫の蠢く肢体のようにも見えた。
濡れそぼった男の徴は今は下を向いているが、それでも充分に大きく、それが本来の目的では用いられないのは女性にとって不幸かも知れないと思ったが、しかしシチロージにとっては幸運だったとしか言い様がない。
シチロージが持ってきたヘアクリップでざっくりと髪を上げているが、後れ毛が幾房か落ち、濡れて首筋や顔に張り付いている。雫の付いた顎髭は柔らかそうで、夜になっても肌が青くならないところを見ると髭は元々薄いようだ。
ぴったりと湯の中で体を密着させたが、カンベエが嫌がる様子はなかった。
遂にシチロージは耐えかねて、カンベエの胸に手を這わせながら耳元で囁いた。
「嫌なことなどお忘れになって、私に体を委ねて下さい。もう、私も我慢できません・・・。」
そう言いながら、首筋に舌を這わせ始めた。
「湯、湯の中は、拙かろう・・・」
「部屋の風呂は一回ごとに抜いて改めますのでお気になさらずに。」
そう言うと、カンベエの体に己の体を絡みつけて、嬲り始めた。
耳の中に舌を差し入れ舐る。回した手で顎を押さえ、口中に指を入れカンベエの舌を弄ぶ。
反対の手は湯の中で両の乳首を交互にこねくり回し、足の間に捻子込んだ膝で、カンベエの股間を揉んだ。
暗い灯りの中でもキラキラと潤むカンベエの瞳に惑わされて、何度も深く口を吸う。
「うん・・・し、シチロージ・・・上せる・・・」
「では、内風呂に戻りましょう。」
そう言ってシチロージはカンベエを後から抱きかかえるようにして、檜風呂に移った。暖まった風呂場の檜の湯船の縁にカンベエを座らせると、シチロージは跪いてカンベエの足の間に顔を埋めた。後にもたれ片膝を立てた恰好で、カンベエは前のモノをシチロージに食まれていた。刺激を受けて立ち上がったカンベエの肉棒は口に入り切る大きさではなかったが、じゅぶじゅぶと舐り、雁を甘噛みし、鈴口を舌でぐりぐりと擦ると、カンベエは仰け反って喘いだ。
放置された乳首も真っ赤に色づいて突き出している。
「カンベエ様・・・私のモノも可愛がってやってくれませんか。」
うっすらとカンベエは見た。
シチロージの巨根が目の前にあった。昼間これが己の中を掻き回したのかと思うと、それだけで体が疼く大きさに驚きながら、カンベエはそれを口に含んだ。
「ああ、カンベエ様・・・気持ちいい。」
シチロージが溜息をついた。
シチロージのがっちりとした腰に手を添え、右手で巨根の根本を扱きながら舌を這わす。これが自分の中に入ることを想像しただけでいきそうになる。
先走りがじわりじわりと滲み出し、時折、うっ・・・とシチロージが呻いた。
口に含んだまま求めるようにカンベエがシチロージを見上げると、優しげな顔に少し獣の表情を浮かべてシチロージがカンベエを引き起こした。
湯船に手を付かせ、カンベエを後ろ向きにすると、シチロージは湯を後の孔にかけながら指を捻子込んだ。
「あ!やめ・・・嫌だ・・・ひっ」
二本の指で割り開かれた後の孔に、突然湯を注ぎ込まれてカンベエは狼狽えた。
「気にすることはありません。出るモノがあれば出してお仕舞いなさい。」
変わらず口調は優しげに、しかしシチロージは更に奥を刺激して、掻き出すように指を動かす。
堪えようとしたが、注ぎ込まれた湯の刺激に腹が渋り汗が出てきた。シチロージがもう一度ぐい、と孔を拡げると耐えきれず、下腹に力が入り後の孔から零れ落ちるのを感じた。
「勘弁してくれ・・・これは、嫌だ、シチロージ。」
「何、洗い流してしまえばよいだけのこと。カンベエ様のここも随分と広がって、ひくひく蠢いていますよ。」
そう言うとシチロージはまた指を捻子込んでぐちゅぐちゅと音を立てて捏ねた。
「あ・・・ん!」
激しい羞恥心に一旦萎えかけたカンベエのモノも再び力を持ち始める。シチロージの指の動きに合わせてカンベエの腰が揺れ始めた。
「気持ち、よいですか、カンベエ様。」
崩れ折れそうになりながら、はっ、はっ、と喘ぐカンベエの胸を空いた手で嬲り、首筋を強く吸いながらシチロージは問う。
「いい、気持ち、よい・・・」
譫言のように呟くとシチロージは指を抜いた。指よりもずっと太い棒が広がった孔に押し当てられ、ぐぐぐぐぐ、と侵入してきた。
「ひ・・・」
強烈な圧迫感に一瞬意識が飛びそうになる。みっしりと己の腹の中が埋められて、腸壁がごりごりと擦られる。
「ああ、カンベエ様、カンベエ様の中はとんでもなく気持ちよいです・・・。」
シチロージが呻いた。激しい注挿が始まった。
ぱんぱんと尻に打ち付けれる勢いに一杯になった下腹部が弾けそうだった。カンベエの膝がぐらり、と折れそうになった。
シチロージは繋がったままカンベエを檜の床に寝かせた。ぐりぐりと中を捻られてカンベエの体はびくびくと震えている。髪の毛はすっかり乱れ、長い褐色の癖毛が風呂の床に広がった。昼以上に快感に蕩けたカンベエの顔を見てシチロージのモノは更に大きくなった。
「ひ、まだ、大きく、なる・・・」
「カンベエ様がいやらしすぎるから・・・」
シチロージはすっかり熟した胸の飾りを囓りながら再び己を叩き込み始めた。
「おお、き、すぎる、シチ、ああ、いや、壊れる、ん!」
意識が朦朧としカンベエは呻いた。仰向けになったことで、シチロージの巨根は激しく前立腺を襲う。長いストロークは入り口をどうしようも刺激し、カンベエの体は引き攣り始めていた。
びくびくと、カンベエの胸が仰け反り、爪先が開いて足が突っ張る。
カンベエのモノが白い液体をびゅくり、と吐き出し、後の孔がぎゅうう、と窄まった。
「くうぅ!」
その強い収縮に思わずシチロージも中に放ってしまった。どくん、どくん、と吐き出しながらもカンベエの収縮が心地よすぎて、己のそれは力を失わない。
「カンベエ様、駄目だ、まだ許しません、あなたの体はよすぎます!」
己の放った液体が更に潤滑剤となり、びしゃびしゃと音を立ててシチロージは注挿を続けた。絶頂に至ったカンベエは強い快感から解放されず、体を震わせたまま仰け反っている。
「ひっ・・・あ・・・」
脳天まで突き抜け、最早苦痛に近いエクスタシーに止めてくれ、と言いたいが、もう言葉を紡ぐことも出来ない。
どうしようもなく溺れたシチロージは動きを止めようとせず、カンベエはとうとう意識を手放した。
何回放っただろう、やっとシチロージが体を離した時には、カンベエは虚ろな眼で、それでも体は時々ひくついた。
後の孔からはシチロージの放ったモノが溢れ出し、互いの精液でカンベエの下腹部はどろどろになっていた。
カンベエを抱き起こしして背を支えると、やっとカンベエの目が焦点を取り戻した。
ぐったりとシチロージに身を預けながら向けられた流し目は、どうしようもなく艶っぽくシチロージは深くカンベエに口づけた。脱力はしていたがカンベエもその口づけに答えた。
汗と精液に塗れたカンベエの体を支えながら湯で清め、バスタオルで拭ってから姫抱きにして部屋に入った。カンベエも何も言わずされるがままになっていた。浴衣を着せ布団に横たえると、カンベエはそのまま気を失うように眠りに落ちた。
仲居に言って、シチロージの布団もこちらに伸べさせ、朝食はシチロージの部屋に用意するようにいうと、シチロージもカンベエの隣に横になった。
すっかり上気した顔に、しかし少し隈が浮いているのを見て、申し訳なさを感じたが、まだ抱きたいと思わせるその寝顔に、自分がどうしようもなくこの男に嵌ったことを自覚せざるを得なかった。
目を覚ますと、カンベエも起きていて、横たわったままシチロージの顔を見ていた。
「おはようございます。カンベエ様。」
ごぞり、と乱れた金髪をなぜながら起き上がると、カンベエが呟いた。
「体がだるい・・・。」
「おや・・・」
シチロージは苦笑しながら、しかし強引にそのままカンベエの布団に潜り込んだ。
戸惑うカンベエの体を抱き締める。
「マッサージが足りませんでしたかな。」
「お主、強すぎる。」
唇を啄むシチロージに苦笑しながらでも、カンベエはだらりとしたままだ。
ついつい、悪戯心が鎌首を持ち上げる。
うーん、と伸びたカンベエの首筋に吸い付いた。
「朝から盛るな、儂はそれほど若くないぞ。」
呆れて呟くカンベエに、シチロージがどうですか、やってみないとわかりませんよ、と言い放った。
え、とカンベエが思う間もなくシチロージは布団に潜り、カンベエのモノを咥えた。
「あ、し、シチロージ、本当に無理だ。あん!」浴衣は着せられていたが、下帯はつけておらず、剥き出しのそこを突然襲われる。
朝立ちするほど若くはないが、それでも寝起きは些細な刺激で勃起する。
「く・・・ううん・・・」
抵抗したくてもシチロージの巧みな舌使いに腰は砕ける。そうでなくとも、荒淫といってもいい昨夜の行為に体は重くいうことを利かない。
力無くシチロージの頭をのけようとするカンベエの手を塞いでしまおうと、シチロージは浴衣をぐいと肌蹴、乳首を強く摘んだ。
「ひ!ん!」
ぐにぐにと乳首を引っ張る指を払い除けようとするが、その間にカンベエの男はそそり立てられてしまった。
「朝ですから軽くしておきますよ。」
風呂場からアメニティのミルクローションを持ってくるとシチロージはそれをカンベエの後に塗り込んだ。
「ど、どこが軽い。それでは、フルコースだ・・・」
もう抵抗出来なかったが、カンベエは悔し紛れに憎まれ口を利いた。
「そう仰らずに・・・朝飯前の運動も悪くはありません。」
そういうとシチロージはぐいっと押し入った。
どうしようもなく、体の相性がよいとしか思えない。
些か乱暴なほどにシチロージが入ってきたのに、カンベエの体は一気に追い上げられる。昨夜の感触があっという間に蘇って、触られていないところまで熱を帯び始める。
浴衣がまとわりついたまま、胸を肌蹴、剥き出しの尻を自分も同じモノを持っている男の証でごりごりと屠られる。
「た、頼む・・・中には、出さないで・・・」
朝から腹の中に出されたら、今日帰ることも出来なくなりそうだ。
「ふふ・・・承知。では・・・」
シチロージはカンベエの体がいきそうになった寸前にカンベエの根本を押さえた。
吐精を押さえ込まれたカンベエは体の中を渦巻く行き場を失った快感に悶えた。
その顔にシチロージは自分の熱を放った。
「う・・・」
完勃ちしたままの己に身を捩らせながら、カンベエが恨めしげにシチロージを見る。
頚に、顎に、頬や口元に飛び散った粘つく液体が、シチロージの嗜虐心を擽る。
「中には出していませんよ。」
少し意地悪な顔をしてシチロージは言い、カンベエの顔を指で拭い口の中に入れた。思わずそのシチロージの指を舐る。昨夜あれほどカンベエの中に出したのに、まだこれほど出るとは、とシチロージは自分でも驚きながら、糸を引く己の雫をカンベエの口に運んだ。
「お主、案外ひどい男だ・・・」
中途半端に止められたカンベエは、治まらぬ身に息をつきながらシチロージを睨んだ。
「続きは朝ご飯の後に・・・あちらの部屋の風呂も楽しんで頂きたいので。」
涼しい顔でシチロージは言うと、歩きにくそうにしているカンベエの腰に逃さないとばかりに腕を回し、食事の支度が出来たと声をかけた仲居が呆れ顔で見送るのも平気でカンベエをもう一つの部屋に案内した。
激しい運動をさせられたせいか、豪華な朝飯も残らずさらえたが、シチロージはそのまままたカンベエを内風呂に引っ張り込んだ。この部屋の内風呂には大きな鏡が付いており、シチロージはカンベエを背中から抱え込み鏡に向き合った。
「見て、カンベエ様・・・」
自分の足でカンベエの足を押さえ目一杯拡げ、後から手を回して、カンベエの胸と肉棒を嬲る。
それはカンベエの前の鏡に映り、嬲られ悶える己の姿が目に入らざるを得なかった。
「なんていやらしい・・・こうやって弄るとぎんぎんに起っていますよ・・・」
シチロージの声が風呂場に響く。背中にはそう言いながら己もかちかちになったシチロージのモノが当たっている。
「ほら、自分で握って・・・」
「も・・・許せ・・・シチロージ」
己の浅ましい姿に目を背けるが、シチロージの手はカンベエの手を上から包み込んでカンベエのモノを扱く。
そうしてカンベエの体を一旦前に倒し、腰を浮かさせると、後の孔に屹立したモノをずぶり、と刺した。
「あああ!・・・・・・ひぃんんんん!」
そのまま体をもう一度起こされると、これ以上入らないと思ったそれが更に奥に食い込む。
ぎゅうううう、と締まった感触に、危うくシチロージは放ちそうになったが歯を食いしばって耐えた。
カンベエの腰を持ち上げては落とす。鏡にはカンベエの孔を犯すシチロージの刃が露わに映り、それを目にしたカンベエの菊座はさらにきゅうきゅうと締まった。
「ね・・・カンベエ様。このまま外に出ましょう?」
後を穿たれたままのカンベエは抵抗など出来ない。シチロージを後に挟み込んだままよろよろと立ち上がり、戸外に押し出される。
こちらの部屋は庭に埋め込まれた陶製の湯船の露天風呂だった。
「ほら、カンベエ様、しっかり歩かなければ転んでしまう・・・」
後から相変わらず、カンベエのモノを嬲り、腹を抱え込んで前へ促す。カンベエはふらふらと、周りに置かれた陶製の置物に捕まりながら風呂に至った。シチロージは風呂の縁にカンベエを横たわらせると、今度は大きく片足を持ち上げ、斜になってより深くカンベエを穿ち始めた。
陶製の地面は冷え切って、熱に浮かされたカンベエの体も冷ます。だがそれは、再び後の孔の感覚も鋭敏にし、繰り返し擦られて麻痺しそうになった菊座がまた快感に波打ち始めた。
午前中の静謐な空気の中に、そこだけ場違いな淫靡な光景が広がる。足を大きく割り開かれ、てらてらと汗に濡れ悶える浅黒い体と、抜けるように白い体を興奮に上気させ、腰を打ちつけて獲物を食する獣。
「あ・・・また、来る・・・」
襲い来る激烈な快感の予感が体を震わせ始めた。
「い、や、ああ、ああ、んんん!あ、あ、あ、~~~~~~-!!!」
もう声にならなかった。再び体中が痺れ、口を閉じることも出来ず捩れ、カンベエはのたうち、屹立した肉棒が脈打ってどくどくと子種が流れ出した。出る物がなくなっても、脈打つ衝動が止まらない。
後の孔もどうにもならず収縮を繰り返し、シチロージは耐え切れず中にぶちまけた。
「ああ、くぅぅぅ。だ、駄目だ!」
搾り取られるような快感にシチロージも注挿が止められない。
長く続いた吐出が、ようやっと沈静化し、シチロージはそのままカンベエを湯船にひきづり込んだ。
カンベエを抱き締めながら、ゆるゆると体を撫でる。シチロージの肩に力無く頭を乗せていたカンベエの目が、やっとうっすら開いた。
「中に、出すな、と頼んだのに・・・。」
拗ねた口調が自分より年上なのに可愛くて、シチロージは思わず口づけた。
「すみません・・・責任をもってお宅までお送り致します。」
え、という風にカンベエの目が開かれた。
そのカンベエの手を握りしめ、シチロージは唇を当てる。
「まさかこの場限りで終わりにされるおつもりなのですか?」
切なげにカンベエを見詰めると、気圧されたようにカンベエは目を伏せる。
「振られたばかりの哀れな体に、サービスしてくれているのかと、思った。」
惚けたカンベエの言葉に、妙にがくり、と来た。
「どうやったらそうなるのです・・・。どう見ても私があなたに溺れてしまったのは明らかでしょうに。」
「溺れたのか?」
シチロージはぎゅう、とカンベエを抱き締めると言った。
「ええ、もう離しませんから。」
来た時よりも明らかに憔悴してよろよろとチェックアウトを済ますカンベエをユキノは哀れみを込めて見た。当のシチロージはここに何のために来たか奇麗さっぱり忘れて、完全にいってしまった眼でカンベエを見詰めている。
自分の車を宿の前に回し、カンベエに抱き付かんばかりの勢いでエスコートするオーナーを、仕事しろ!とばかりに、ユキノは後からもう一度引っぱたいた。
助手席のシートを少し倒し、ゆったりとカンベエを座らせると、シチロージは街への帰路へ付いた。車中カンベエはとろとろと眠り続け、昼飯も欲しいとは言わなかった。高速に乗ると、意外なほどあっけなく、車は街に着き、都会の喧噪に包まれた。
カンベエのマンションに着いたのは少し日が傾く時分だった。
「すまぬ。助かった。」
と、微笑んで車を降りようとするカンベエの手をシチロージは強く掴んだ。
じっとカンベエを見詰める。
困ったように握られた手を眺めていたカンベエだったが、諦めたように苦笑すると言った。
「わかった。茶でも飲んでいくがよい。だが、頼む。
今日はもう、止めてくれ。身が持たぬ。」
ほっとしてシチロージは答えた。
「承知。」
マンションの来客スペースに車を止め、寄り添うように付き随うシチロージに、カンベエは家を出る時には重かった心がすっかり癒えていることに気付いた。
現金なものだ、とまた苦笑してしまったが、隣にある温もりに、これもまた、縁、と小さく呟いた。