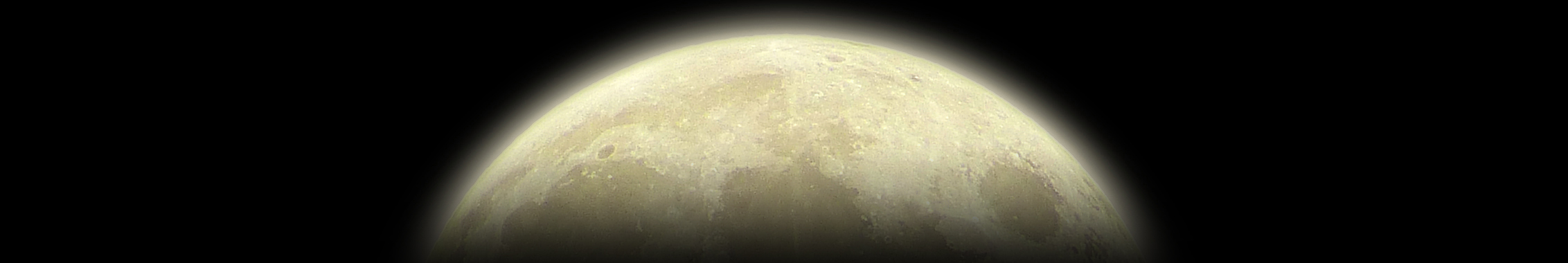『SEX and HONEY 2 夏』
作:エデイ様
この話は「第7話 癒す! 」「第8話怒る!」「第15話 ずぶ濡れ! 」「第16話 死す!」の4話連作パラレルシリーズとなっております。
各話完結しておりますのでどの話からお読み頂いても問題ないと思いますが、一応上記番号順に読み進めていただくことを想定しております。
ゴロ×カンオンリー。糖分過多。
ギャグコーティングシリアスエロ。
大人でダンディーなゴロさんをお求めの方にはオススメ出来ませんのでご注意ください。
真夏の焼けた太陽が白く舗装されたアスファルトの上に濃い影を落とす。
向日葵の前を横切る蜂が物憂な顔をして、熱に沈んだ景色の中をスローモーションのようなゆっくりとした動きで飛んでいた。
「兄」が殴られている姿を目にして夢中で刃物を突き刺した相手から頬を切り裂かれたあの日も、こんなギラギラとした太陽が昇る熱い夏の日だった。
その後ゴロベエは母親に捨てられるようにして、施設に預けられることになった。
同じ部屋で暮らす子供が5人、ずらりと人が並んだ朝食の長テーブル、先生や優しい寮母さんたち。
学校にも通うようになった。
それまで育児に関心がない母親から獣同然の暮らしを強いられてきたゴロベエは、これほど大勢の大人や子供に囲まれた経験がなく、初めのうちは不安に怯えて 母や兄の姿を探しては泣き、攻撃的な行動を取ることも多かったが、それもやがて落ち着くと徐々に新しい生活に順応していった。
何しろ施設では決まって三度の食事とおやつが出されるので、腹を空かせても食料をあちこちから漁る必要がない。
熱を出した時はリスのアップリケがついたエプロン姿の女の人が自分のために水枕を用意して、甘いヨーグルトを口まで運んでくれた。
今まで母親は勿論、兄以外の他の誰からもこんな風に扱われたことなどなかった。
脱走を繰り返す子供もいる中で、温かい食事と自分に差し伸べられる優しい手の存在はゴロベエに大きな力で庇護されているという安心感と、ここでの生活を受け入れる気持ちのゆとりを齎したが、それでもたった一つ、どうしても満たされないものがあった。
夜になり、自分の場所と決められたベッドに敷かれた布団の中にもぐりこむと、必ず別れた兄のことを考えてしまう。
兄は今頃何をしているのだろう。
自分が今こうして兄のことを思っているように、自分のことを覚えていてくれるだろうか。
かけっこが驚くほど速くて、笑うと八重歯がほんの少し見える。
公園までの秘密の近道だとか、誰にも見つからないようにこっそりと柿を盗る方法、笛のように音が鳴る草、猫が集まる場所、何でも自分に教えてくれた、優しくて頼もしい兄。
穴倉のような暗い家の中で、兄の存在だけが光だった。
学校から帰ってきた兄の後について外に出ると、すれ違う他の子供達が格好良い兄を独り占めしている自分を羨ましそうに見つめているようで、誇らしい気持ちでいっぱいになる。
兄に会いたい。
話をして一緒に遊んで、頭を撫でてもらう。
たまらなく、兄さんに会いたかった。
ゴロベエは自分を捨てた母よりも、短い間一緒に暮らした茶色の綺麗な瞳を持つ兄を忘れることが出来ずに一人枕を濡らした。
兄に対する思慕は薄れて行くどころか逆に楽しかった思い出ばかりがゴロベエの胸の内で純化され、会いたいという気持ちが日増しに募ってゆく。
ゴロベエがようやく施設から小遣いを渡される歳になり、一人で兄に会いに行くことが出来るようになるまでに5年の年月がかかった。
詳しい住所も電話番号も覚えてはいなかったが、兄が通っていた公立小学校の名前と住んでいたアパートの裏にあった公民館の名前はしっかりと記憶に刻み込まれていたので、学校の図書館を使えるようになった歳にすでにおよその場所については地図で検討をつけていた。
何度も何度も兄と住んだ家のある場所を地図の上で辿っていたので、今ではすっかり周囲の地名まで頭の中に叩き込んである。
あとは目的地までの交通手段を調べるだけだった。
ようやく辿り着いたそこは、記憶にあるアパートよりも随分と小さく古ぼけて見えた。
突然やってきた弟の顔を兄は覚えてくれているだろうか。
そんな不安もちらりと胸を過ぎたが、姿を見たい、会って話がしたいという気持ちが勝ってアパートの前で兄の姿を待った。
ようやく会うことが出来た兄は成長した弟の姿に驚きつつも自分と同じくらい、もしかするとそれ以上に再会を喜んでくれた。
施設では無断で一人行動することは許されていない。
こんな遠方まで小学生の自分が一人で電車やバスを乗り継いで出かけて行くことが知られたら、反対されるに決まっている。
ゴロベエは職員やホームの子達の眼を盗むようにしてこっそりと、三ヶ月に1度は兄に会うためにバスと電車を乗り継いだ。
中学にあがる頃には、戸籍上自分たちは兄弟の関係にはないということを理解していたが、それでも会いにゆくことは止めなかった。
そんな書類一枚で、兄と自分との間に漂う強烈な親密さだとか、信頼だとか、安心感、目には見えなくとも確かに存在していると感じることが出来る「絆」を説明することなど不可能だ。
会いに行く日は必ずカンベエの父親が家を空ける、第三土曜日の午後と決められていた。
しかし、ある時ゴロベエは兄の誕生日に突然現れて驚かせてやろうとこの決まりを破って黙って兄の住むアパートへと向かった。
プレゼントを何にしようかと考えて、地区大会で自分が入っている野球部が優勝した時に貰ったバッチを渡すことにした。
わくわくしながら呼び鈴を押すが、何の応答もない。
どうやら留守らしく、ドアノブを回してみると鍵がかかっていた。
落胆しつつ、ふと兄がドアの桟の上に手を伸ばして鍵を取っていた姿を思い出して手をかけてみると、果たしてそこに鍵はあった。
躊躇いつつも、そのまま中に入る。
勝手に入ったことを兄は咎めないような気がしたが、万が一父親が先に帰ってきた場合は兄に匿ってもらおうと、空になったカップメンが一面に散らばり、饐えた臭いが充満する台所を過ぎて兄の部屋へと向かった。
会うたびに兄の体には喧嘩で作ってきた新しい打撲の痕や傷跡が刻まれていて、それはまるで自分を痛みつけることを目的としているかのように癒える間もなく次々と増えてゆく。
問い詰めてみても、「別に」とか「さあ」といった要領の得ない返事が返ってくるばかり。
兄は自分のこととなるとそんな風にして口を閉ざすくせに、弟についてはどんな些細なことでも知りたがった。
「施設の子達とは上手くやっているのか」「弁当はどんなものを食っている」「好き嫌いは良くない」「学校は面白いか」「部活はどうだ」「学校の勉強は」「仲良くしている友達はいるのか」等々。
こんな何でもない自分の日常のあれこれを聞くことが兄にとっては大層面白いらしく熱心に耳を傾けてくるものだから、兄の笑顔が見たい一心で、気がつけば兄と会う時間は自分ばかりがおしゃべりに夢中になっているのだった。
兄の部屋はポスターの1枚飾ってあるわけでもなく、パイプベッドと勉強机、それに合板で出来た安物の洋服ダンスという必要最低限の家具がぞんざいに置かれているだけの殺風景なもので、それはこの家に対する兄の心象を現しているかのようだった。
ゴロベエは勉強机の下にもぐりこむと、プレゼントのバッチを握り締め、塞ぎそうになる心を閉め出すように膝を抱えて兄の帰りを待つことにした。
いつのまに寝てしまったのか、人の気配に目が覚める。
壁の向こうから、荒い息遣いのような音が聞こえてくる。
ゴロベエは、足音を忍ばせるようにしてそっと兄の部屋を出ると、居間に続く襖の隙間から中を覗き見た。
初め、二人が何をしているのかわからなかった。
裸のまま兄が、父親と同じ方を向くようにして父の膝の上に乗せられて抱かれていた。
兄の顔は苦痛に歪み、激しい運動をしたあとのようにぐったりとした様子で大きく肩で息をしている。
5年ぶりに目にするカンベエの父親の顔は記憶にあるそれよりも頬がこけて目が落ち窪み、白髪が増えていたが間違いなくその顔は自分の顔を切りつけた男のものだった。
上下する兄の平らな胸の上を、男の筋張った指が気味の悪い節足動物のように這い回っているのが見える。
兄がゆっくりと顔を上げ、自分のいる正面を向いたがその瞳は潤んで焦点が定まってはいない。
半開きになった口からは涎が垂れている。
男が脇の下から兄の体を抱え込むと、兄の体が人形のようにゆさゆさと揺れて、そのたびに額にかかった柔らかそうな癖の強いこげ茶色をした髪が撥ねた。
ハッハッという二人の短く荒い息遣いが部屋の中に充満し、自分が覗いている細く開いた襖の隙間から漏れ出てくるように感じられて、息苦しい。
ネチネチという微かな粘着質の水音が耳の奥の神経を刺激する。
それでもゴロベエはまるで視線を縫い止められてしまったかのように父親に抱かれている兄から目を離すことが出来ずにいた。
男によって兄の体が高い位置に持ち上げられると、兄の目が恐怖に見開かれる。
兄の細く撓った体が抵抗するように震えている。
「や、め…」
弱弱しく首を振りながら、涙を零して懇願する兄を嘲笑うかのようにして、兄を支える手が突然離されて、がくんと腰を落とされた兄の喉から悲鳴のような嬌声が迸った。
そのまま背中を仰け反らせて、がくがくと体を震わせている。
男が無茶苦茶に腰を振り始めた。
あっあっあっ、あ…
虚ろな兄の瞳には何も映し出されてはいないだろう。
弱った獲物を嬲るように、兄はひたすら自分の目の前で男に揺すぶられ犯されていた。
ぐちぐちと粘膜の擦れる水音と、ヤダともイイともつかぬ意味をなさないうわ言のような音の合間に、
ゴロベエ
と兄の唇が自分の名を形作っているように見えて、ゴロベエは固まった。
ゴロベエ、、ゴロベエ、、ゴロベエ…
陵辱されながら、兄が自分の名を呼んでいる。
錯覚による思い込みかもしれない。
それでも目の前で男に体を開き、快楽に震える淫らな兄が涙を零し縋るようにして自分の名を呼んでいるという想像は、ゴロベエに体の芯を貫くような激しい衝撃を与えた。
「イ、イク…ッ」
兄が硬く目を閉じて白濁を撒き散らすのと同時に自分も下着を汚し、そして逃げるようにして外へ飛び出した。
カンベエ。
カンベエ。
カンベエ。
兄さんの狭い器官に己のモノを突き刺し、我武者羅に腰を振る。
想像しただけで下半身が熱くなり、痺れるような快感が背筋を這い伝って脳内で弾ける。
兄を、滅茶苦茶にしたいという凶暴な欲求が募る。
兄を苦しめるあの男が憎い。
五年前のあの日、あの男が兄を殴る姿を目にした瞬間自分は包丁を掴み、夢中で男の前に飛び出した。
兄を傷つけるあの男が、許せなかった。
それなのに今、自分はあの男に嬲られている兄を残したまま背中を向けて、逃げ出している。
あの男に犯されている兄を見て、自分は酷く興奮していた。
襖一枚を隔てた距離で、あの男の姿を自分と重ねながら、自分は兄を犯す妄想に硬く勃起していた。
「家族」という絆に囚われ、父親という肉親の情を断ち切れずにいる兄が哀れだった。
それ以上にそんな兄の情につけ込む卑劣な男が兄を犯す暴力のようなファックを見て、はっきりと肉の欲望を感じていた自分が惨めだった。
短い間しか一緒に暮らすことはなかったけれど、ずっと兄が好きだった。
2年と2ヶ月と3日この家で暮らし、兄に慈しまれた日々は、自分にとって他の何よりも掛替えのない大切な思い出だった。
兄に触れて、触れられて、抱きしめて、抱きしめられて、優しい言葉をかけられて、それに対して自分はちょっと照れたり、笑いかけられて、笑い返して。
喧嘩なんてしたことはないけれど、もしかすると一度くらいする日がくるかもしれないと、そんな想像すら楽しくて仕方がなかった。
兄に褒めてもらいたい一心で勉強し、兄が好きな野球に打ち込んだ。
子供の頃からカンベエは自分にとって自慢の兄さんで、憧れの人だった。
好きで、好きで、好きで、たまらなく好きで。
この気持ちを大切にしたいだけなのに。
あの男のファックと、自分が兄に対して抱いてしまったこの欲の違いがわからない。
あの男と同じ場所に墜ちたくない。墜ちたいとも望まない。
兄弟であることを理由に、兄に依存して生きたいとは思わない。
兄を蝕み、搾取するだけのあの男を、はっきりと憎んでいる。
だったら自分はどうしたら良いのだろう。
この日からゴロベエは、カンベエと会うのを避けるようになった。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
部屋のドアを開けた途端にクーラーに冷やされた空気が、足元に纏わり付くようにして流れ込んでくる。
分厚い遮光カーテンに遮られた室内は薄暗い。
カンベエは体に張り付く汗に濡れたブラウスが急速に冷えてゆくのを感じながら、背にしていたショッキングピンクのリュックをその場に落とすと、俯くようにして腰掛けているゴロベエの前に立った。
ゴロベエは組んでいた両手の上に乗せていた顎を上げると、黙ったまま自分の前に立ち尽くしているカンベエの目を見て口許を緩めた。
たったそれだけのことで胸が詰まるような喜びが込み上げてくる。
愛しいものを目に見える形にしたらゴロベエ、きっとお主のような男が出来上がる。
「おかえり…」囁くように落とされたカンベエの声に、座っていたゴロベエが徐に立ち上がった。
「ただいま」という返事と共に嵐のような性急さで口付けられる。
唇を重ねたまま、前ボタンを引き千切るような勢いでゴロベエに制服のブラウスを脱がされてゆく。
首筋のラインを確かめるようにして這わされた大きな掌から伝わってくる熱が心地良くて、カンベエはため息のような息を吐いた。
ゴロベエが出張していた三日の間、カンベエにとって一日がとてつもなく長く感じられた。
何度も無理にでもついてゆくのだったと後悔した。
これ以上待たされるのは、限界だった。
「カンベエ殿…」
久し振りに直接耳にするゴロベエの声に、背筋にぞくりとした悦が走り抜ける。
声を聞くだけで、イッてしまいそうだった。
ゴロベエに対する狂おしい欲望が募って胸が張り裂けそうになる。
「ゴロベエ…」と切羽詰ったような濡れた声で名前を呼ばれて、ゴロベエはカンベエの首筋に噛み千切らんばかりに歯を立てた。
制御できない感情に突き動かされるようにしてゴロベエは、骨が軋むほど強くカンベエの体を抱きしめた。
苦痛に喘ぎながらもどこか淫猥な表情を浮かべているこの人を滅茶苦茶にしたい。
体が粉々に砕け散るほどに嬲り揺さぶって、壊れるまで乱暴に犯したい。
この体が自分のものだと所有の証を体中に刻み付けたい。
泣いて縋って、自分だけだと、この人の口から言わせたい。
どこにも、行かせたくない。
「くっ…」
たまらずにカンベエが自分の喉元に喰らい付くゴロベエを引き剥がそうとして押し退けると、今度は引き摺られるようにしてスプリングのきいたベッドの上に体ごと投げ出される。
体勢を立て直す間もなく、カンベエの体を組み伏せるようにしてゴロベエが圧し掛かる。
膝立ちになったゴロベエはカンベエに「脱げ」とだけ短く命じた。
ノロノロと制服のスカートのホックを外し、下着と靴下を一緒に丸めたまま床に放り投げる。
チラリとゴロベエの顔を仰ぎ見ると、間髪入れずに頭を抱え込まれ、無理矢理開かされた口の中にゴロベエの怒張を押し込められた。
えづきそうになるのを堪えながらも健気に奉仕を始めたカンベエをゴロベエは冷ややかな顔で見下ろしていたが、そのうちにカンベエの頭を両手で固定すると、乱暴に腰を動かし始めた。
「ぐっ、…ぅ」
満足に息継ぎすることもままならないまま、カンベエは口腔一杯にゴロベエのペニスを含まされて、目には生理的な涙が浮かぶ。
雄の臭いが充満し、怒張を無理矢理喉の奥まで挿入されて、酸欠に視界が滲む。
ゴロベエはカンベエの口の中を存分に犯すとそのまま射精した。
飲み込みきれない白濁がカンベエの唇の周囲を汚し、むせながらこれを拭おうとする腕を遮ってゴロベエは休むまもなく再びカンベエの口に引き抜いたばかりのペニスを突き立てた。
「これが好きで好きで溜まらぬのであろう?カンベエ殿」
2度目も口の中で放たれて、ようやく解放される。
ゴロベエは肩で息をつくカンベエを転がすようにして押し倒すと、今度はカンベエの胸の突起を強い力で引っ張り捏ね回し始めた。
痛いくらいの刺激にシーツを握るカンベエの指に力が入る。
「…ひっ…」
乳首を弄られながら、弱い首筋から鎖骨にかけての性感帯を吸われてカンベエの口から悲鳴のような嬌声があがった。
男に征服されて喜ぶ体が、与えられる快楽を貪欲に拾おうと淫らに悶えながら、妖しく誘っている。
「厭らしい体だな…こんな扱いを受けながらおっ勃てておる」
触れられてもいないカンベエのそこは、ゴロベエの性器で口腔を蹂躙され、弱い胸の部分を乱暴に愛撫されただけで透明の雫をだらしなく零しながら屹立していた。
ゴロベエが3日間の出張を終えて帰宅すると、カンベエはまだ学校から戻ってはいなかった。
唐突に不安が込み上げて、つい30分ほど前に携帯のメールで帰宅時間を確認したばかりだというのに、再び携帯を取り出す。
カンベエは戻ってこないかもしれない。
一緒に暮らすことになり、ゴロベエのマンションにやってきたカンベエの荷物は驚くほど少なかった。
それまで海外で暮らしてきたとはいえ、学校の教科書のほかに鞄が一つという身軽さはそれまでカンベエが何に対しても執着を示すことなく歩んできた人生をそのまま現しているかのように思えた。
誰にでも捨てることの出来ないものの一つや二つあって然るべきだ。
それまでフリーのカメラマンをしていたと聞いたが、カメラは勿論、それに付随する機材の一つ見当たらない。
「仕事は辞めた」とだけ簡単に口にするカンベエの言葉を信じたわけではなかったが、ゴロベエはカンベエの過去を詮索するようなことはしなかった。
カンベエの胸に走る鋭利なもので裂かれたような大きな傷跡についても、「事故だ」とだけ説明するカンベエをそれ以上追求しようとはしなかった。
カンベエにとって唯一捨てることが出来ずにいたものは、弟である自分だけなのかもしれない。
そんな風に考えることはゴロベエにほんの少しの甘い陶酔を齎したが、同時にどこまでも乾ききって空虚なカンベエの心の淵を覗き見るような気がして切なかった。
過去にカンベエが何をしていようが、構わない。
今こうしてカンベエが自分の傍で笑っていてさえくれれば良い。
ある日ゴロベエはカンベエが持ち歩くショッキングピンクのリュックのジッパーが開いたまま部屋に置かれて、中に以前自分がプレゼントしたギラギラと光るキティのポーチが入っているのを見つけてほくそ笑んだ。
以前カンベエが店の前で物欲しそうな顔をしているのを見て、誕生日に買ってやったものだ。
白やピンクのラメスパンコールで埋め尽くされたキティというキャラクターの猫の顔の形をしたポーチで、ゴロベエから見ればおそろしく悪趣味な代物だったが、やはりあの顔は欲しかったのであろうなとこれを選んだ。
包み紙を解いて出てきたものを目にした途端、図星を指されたのが余程悔しかったのか初めのうちは「スージーズーがイイ!」だの「ダッフィーの方が可愛 い!」だのビービーと訳の分らぬ文句を喚いていたが、こんな風に持ち歩いて使っているところを見るとやはり嬉しかったのであろう。
何を入れているのだろうかと、悪いとは思いつつカンベエがいないことを良いことにポーチの中を開けてみた。
出てきたものはパスポートと認識票だった。
パスポートを開くと中は聞いたことがないような小国の名が記されたスタンプでびっしりと埋め尽くされている。
認識票の方は一目見ただけで、明らかにただの装飾品ではないということがわかる素っ気無い造りをしたものだった。
目を凝らしてみれば、ステンレスの上に細かい傷が縦横に走っているのが見える。
KANBE SHIMADA
名前のほかに生年月日、性別、血液型、その他見慣れぬ番号などが刻印されていて、下の方が擦れたように光沢を失い、磨耗していた。
カンベエにはブラウスの胸元ついたリボンの端を指で擦る癖があった。
おそらく首にぶら下げられたこの認識票を、癖になってしまうほど長い間、磨り減るまで指で擦っていたのだ。
どのくらいの時間を費やせばそんなことになるのかは解らない。
何日か、何ヶ月か、それとも何十年か。
張詰めた緊張の中、認識票を擦りながら死と隣り合わせにある1秒の生を繋ぐようにして、生きながらえている。
そんな不吉で恐ろしい想像を振り払うように、ゴロベエは首を振った。
自分がプレゼントしたキティのポーチに、パスポートと認識票。
これらは、カンベエがいついかなる時でもすぐに、再び元の世界に戻ることが出来るように備えているということを示していた。
カンベエは先の約束を決してしようとはしなかった。
来月のクリスマス、来年の誕生日、いつか犬を飼えるような家に引越そう。
こうした話になると巧みに話題をそらした。
明日の小テストのことで頭がいっぱいだ、数Ⅱの宿題が解けぬ、学園祭ではトン汁係になった、など。
いつかカンベエは自分のもとを去ってしまう。
自分に抱かれて、あられもない格好をして、悦がって、欲しがって、淫らにもっともっとと切なく啼いているくせに。
それは明日かもしれないし、明後日のことかもしれない。
体の下で悶えるカンベエを組み伏せるようにしてゴロベエが唇を合わせると、待っていたようにカンベエの手がゴロベエの背中にまわされる。
固く尖った乳首がゴロベエの逞しい胸の筋肉に擦られて、それだけで痺れるような快感が背筋を走り腰が砕けた。
舌先で隈なく口の中の性感帯を刺激され、唾液を大量に飲まされてカンベエの喉が鳴った。
ゴロベエがこんな汚辱に塗れた体を欲しがるのならば、余すことなく持って行けば良い。
乱暴に体をひっくり返され、満足に準備が整っていない後孔におざなりにローションを塗られただけで凶器のようなゴロベエの屹立を突き立てられる。
悲鳴があがりそうになるのを喉元で堪えながらカンベエはきつくシーツを握って奥歯を噛みしめた。
まるで暴力の捌け口にされているようなセックスだったが、カンベエにはこれがゴロベエの苦しい胸の内を吐露する悲痛な叫び声のように感じられて胸が痛んだ。
ゴロベエが何に苦しんでいるのかはわからなかったが、まるで言葉を知らない子供のように、抱えきれない剥き出しの感情をセックスにぶつけてくる。
ゴロベエが抱える苦しみや怒りを僅かでも自分が取り除くことが出来るのならば、こんな体いくらでも投げ出す。
グローブのような大きな掌で腰を掴まれたまま容赦なく抽挿を繰り返されて、熱い飛沫を奥に注ぎ込まれる刺激にカンベエの体が戦慄いた。
放ったばかりだというのにゴロベエのそこはすぐに硬度と質量を増してカンベエの内壁を圧迫する。
カンベエ自身も哀れなほどにひくついて、解放の時を待っていた。
「後ろだけでイケそうだな」
己の放ったもので更に滑りが良くなり、容赦なく深い部分まで貫かれる。
ゴロベエの太いモノで串裂きにされながら、カンベエはびくびくと体を震わせながら達していた。
射精後の筋肉の収縮に締め付けられる愉悦を貪るようにして、ゴロベエはカンベエの腰を掴んで腰を打ちつけた。
ゴロベエのペニスを咥え込んでいる結合部分から、ぐちゅぐちゅと卑猥な水音を立てながら粘着質の液体が溢れ出る。
中はとろとろに熱く、ゴロベエの自身を硬く締め付けた。
快楽に溶けた自分の体を恥らうかのように目元を赤くするカンベエに向かって、何度目かの精を放つ。
奥を濡らされた刺激にカンベエの中心も再び芯を持ち始めていた。
「カンベエ殿のココ、まるでおなごのようにどろどろになっておる」
ひくひくと震えて、せわしない呼吸を繰り返すカンベエを見下ろしながらゴロベエはサイドテーブルの引き出しの中からコンドームを取り出した。
ベッドの上のカンベエを起こして大きな姿見の前に立たせると、封を切って取り出したゴムに慣れた手付きで息を吹き込む。
カンベエの背中を支えながら鏡と向き合あうようにしゃがみ込ませると前の部分を刺激して、ゴロベエは手にしていたゴムをカンベエのゆるゆると勃ちあがっているペニスに装着した。
「なっ…」
カンベエが驚きながら問うような眼差しを自分の背を抱く鏡に映ったゴロベエに向けると、ゴロベエはゴムを被せられたカンベエのペニスを弄りながら口許だけで笑みの形を作って囁いた。
「カンベエ殿のココはどうせ使わぬのだから、構わぬであろう?」
カッと羞恥に顔を赤くするカンベエのコンドームが装着された性器が正面にある鏡に映るように、容赦なく股を割り開く。
何度も抜き差しを繰り返された後ろの穴は、背後から挿入されるゴロベエのものを軽々と呑み込んでゆく。
膝下に手を差し込まれ、深い部分まで貫かれる刺激にカンベエは苦しげな息を吐きながら耐えていた。
ゴロベエのものをみっちりと埋め込まれた下腹部が熱い。
ゴムを被せられたままの哀れな性器が勃起して、隆々と天を向いている。
何度も突き落とされるような快楽に与えられて、カンベエはついに装着されたゴムの中にじゅくじゅくと生ぬるい欲を吐き出した。
ゴロベエはこれを見て満足そうに目を細めると、カンベエの奥に熱い飛沫を飛ばした。
「ぐっ、うぅっ…」
「男のくせに、後ろから挿れられて…情けない姿だな」
半分意識を飛ばしたような空ろな目をして、崩れ落ちそうになるカンベエの体をゴロベエは壊れ物を扱うようにそっと抱きしめると、涙に濡れて青褪めた頬に優しく口付けを落とした。
「刺激してやれば、すぐに濡れる」
カンベエの吐き出したものが溜まったゴムを、ゴロベエは背後から手を伸ばして外していった。
「ゴロベ、エ…」
はあはあと荒い息を吐きながら、痙攣が治まらない体を何とか持ちこたえるようにしてカンベエは背後のゴロベエに向き合うと、両手でしっかりとゴロベエを抱きしめた。
「何が、不安なのだ…」
カンベエの言葉に、ゴロベエはびくりと大きな体を震わせた。
「お主…、辛そうな、顔をしておる」
しっかりと合わされた視線に、ゴロベエは心臓が喉元までせり上がってくるような激しい動悸に襲われて唇を噛んだ。
所詮自分はカンベエという男に守られるばかりで、何かを刻み付けることも、穢すことも、何一つ出来ないのだ。
ゴロベエは無力な自分を責めるように項垂れながら、どちらのとも解らない精液に塗れたカンベエの躰を包み込むようにして背中にそっと手をまわすと、その逞しい肩の上に額を乗せた。
「…どこにも、行かないで」
今にも泣き出しそうな小さな声で、堪えていた本音がぽろりと落ちた。
どんなに自分がカンベエに愛を囁いたとしても、カンベエは「兄」という立場を捨てきれず、いつの日か弟が妻と子供という「普通」の幸せを手に入れることを望み、そしてそれをはっきりと口にした。
同性しか愛することが出来ない自分とは違い、弟はもともとノーマルなのだ。
今は自分という長年執着の源だった男が目の前に現れたことに夢中になっているだけで、そのうち目が覚めるようにして本来の幸福な「家庭」というものを築くようになる。
ゴロベエが何度、そんなお仕着せのような夢を押し付けられても迷惑だ、あり得ないとつっぱねても、頑として態度を変えようとはしなかった。
カンベエが何を夢見ようと勝手だ。
でもそれを、彼のことが好きで傍に居たいと希う男に押し付けるのは、残酷だ。
だから初めのうちは、この関係は一時的なもので、いつか自分はカンベエに捨てられて終わりがくるのだと遠回しに釘をさされているのだと思っていた。
悔しくて、悔しくて、何度その口から「好きだ」「愛してる」と言わせても虚しさが募るだけで満足することができなかった。
しかし自分がプレゼントしたキティのポーチからパスポートと認識票が出てきたのを目にした瞬間、自分がとんでもない間違いを犯していたことを悟った。
鞄一つ分しかないカンベエの過去の中で、唯一つ捨てることが出来ずに持ち続けてきたもの。
それは間違いなく「弟」である、自分だ。
カンベエが捨てずに持ち続けてきたのは、「兄弟」という絆だけだ。
25年という決して短くはない年月の中で、遠く離れた異国の地から自分に対する連絡だけは、決して絶やすことがなかった。。
カンベエは、初めて出会ったあの日から弟である自分のことを一番に優先してきた。
すべての外敵から身を守るように小さな体で幼い弟を庇いながら大切に愛しんできたのだ。
だからこそ、自分もそんな兄の存在を忘れることが出来なかった。
そしてそれは気が遠くなるほどの長い時を経ても、悲しくなるほど変わる事がなかった。
カンベエが何よりも望んでいるのは、「弟」である自分の幸せだ。
弟が、妻と子供という当たり前の家庭を築き「普通」の幸せを手にしていると信じることで、己を安心させたいのだ。
たった一つ大切にしてきた「弟」という存在が、自分のせいで不幸になる姿を見ることを何よりも恐れ、恐れている自分というものを決して認めようとしない。
父親との歪んだ関係が、カンベエを自分に価値を見出せない男にしてしまい、生死の境でしか己の居場所を見つけることが出来ない男にしてしまった。
長すぎる孤独は、傲岸不遜に生き抜く術を身につけさせる代わりに、自分には儚い幻影のような幸せしか望んではいけないと頑なに信じる臆病な男にしてしまったのだ。
「家を空けておったのはお主のほうであろうが…」
さりげなく視線をずらすカンベエの伏せた睫が近い。
愛しくて愛しくて、体がばらばらになりそうなほど、この人のことが好きなのに。
理由なんて、どうでもいい。
弟としか思われなくたって、いい。
家を空けるたびに、帰ったらもうカンベエは居ないかもしれない、戻って来ないかもしれないと考えては、眩暈がするような絶望に囚われる。
再び幻影の中に生きる「弟」だけを道連れに、自分のもとを去ってしまうのではないかと怯えた。
「カンベエ殿がいつかここを出て行こうと考えていることは知っておる。
その時はお願いだ。某も一緒に連れて行ってくれ。
カンベエ殿がここを去るならば、某も一緒に着いて行く。
料理も掃除も洗濯もする。
もしもカンベエ殿が、他の誰かと一緒に暮らすことになっても、決して邪魔はせぬ。
だから、だから頼む。
傍に居させて…もう二度と、某を置いてゆかないでくれ。
居場所がなければ、某は押入れの中でも物置小屋でも何でも良い。
食事も少しで良いし、狭いところは昔から慣れている---」
「ゴロベエ!お主一体何を言い出すのだ」
驚きに目を瞬かせるカンベエの目の前で、ゴロベエは頭を下げて両手をついた。
「だから、だから頼む。
----ずっと傍に居させてください。
お願いだから某に黙って、出て行かないでくれ…」
情けなくても、格好悪くても、卑怯だと罵られても、カンベエの傍に居られるのであれば何だって良かった。
父親が兄に向ける暴力、自分が兄に持つ欲の正体、本物の家族のような兄弟になりたいだとか、兄弟ではなく恋人のように兄を抱きたいのだとか。
25年という歳月は、余分な感情を保つには膨大でありすぎた。
一つ一つ薄皮を剥ぐようにして色褪せた悩みや苦しみが過去の抜け殻となって抜け落ちてゆく中で、たった一つ残された、祈るような願い。
この人の傍に居たい。
もう二度と離れ離れになりたくない。
カンベエが自分に勝手な理想を押し付けようが、己が触れることの出来る幸せを手に入れることを全力で拒否していようが、そんなことは構わない。
カンベエの傍に居たかった。
他の誰を愛してもいいと思えるほどに
ずっとその姿を見ていたかった。
今まで会うことが出来ずにいた時間の分だけ
ずっと、ずっと、その姿を見ていたい。
この人が笑っている顔を目にするだけで、泣きたくなるくらい幸せなんだ。
苦しくなるほど幸福に包まれる。
それだけだった。
それだけなんだ。
訪れた沈黙の中でゴロベエは顔をあげることが出来ずに俯いたまま、カンベエの言葉を待った。
「学校は、楽しいな。ゴロベエ」
カンベエは視線を床に落としたまま、ぽつりと呟いた。
唐突なカンベエの言葉に、ゴロベエはのろのろと顔を上げた。
「何の役立つのかわからない定義だとか、教科書に書いたラクガキ、友達、学食のメニュー、校庭から聞こえてくる歓声、アイスクリームの自動販売機だとか教室の窓から見える雲、屋上でする昼寝、体育館の匂い…」
訥々と語られる言葉を一言も聞き逃すまいと耳を傾ける。
「ワシは学校というものにろくに通った記憶がなかったから、お主が教職に就いたと知り無性に学校というものを見てみたくなった」
「…それで、面白い?」
ゴロベエは途惑いながらも教師の顔を作りながらぎこちなくカンベエに向かって微笑んでみせた。
「ああ」とカンベエは頷いた。
いつもの人を小ばかにしたような表情ではなく、そこにはとても真面目くさった顔があった。
「だから、卒業したい」
「…うん」
なんだか、いとけない子供を相手にしているようでつきりと胸が痛む。
「優秀な教師が、ワシをつきっきりで個人指導してくれるのであろう?」
「…多分、こんなに態度がでかくて生意気で出来の悪い生徒を導くことが出来るのは世界広しといえど某しか居らぬと思うが、何しろカンベエ殿は我校始まって以来の赤点大将だからな。何年かかるかは解らぬ」
ははは、とカンベエは笑ったが、その顔は泣きそうに歪んでいた。
「最後まで…責任取れよ」
ゴロベエはカンベエの顔を覆っている両手を外すようにしながら、口付けた。
「勿論」
今はこれだけで十分だった。
兄弟という絆も自分には必要ない。
カンベエが弟である自分しかいらないと嫌ってもいい。
カンベエが誰を好きになっても構わない。
これから少しずつ、自分がどれほどカンベエの傍に在り続けたいと願っているのか、イヤというほど認めさせてやる。
ゴロベエは再び熱に溶けたように重ねられてきた体を抱きながら、ゆっくりと押し倒していった。
それが自分にとっての幸せで、貴方にとっての幸せなのだと。
ゆっくりと、時間をかけてこの人に浸透させてゆく。
<SEX and HONEY 3 秋 「ずぶ濡れ!」に続く>
- note -
カンベエ様ってば一体どんなガッコ通っているんでしょうね!(笑顔)
この部分またもやギャグへの領域侵犯侵しそうでしたが(…)、微妙なラインを保ちつつ(ええ、ギャグじゃないのです。うっかり超えちゃった人はすみやかに元の位置に戻ってください)、まだまだ続きます。
次回はカンベエたまの25年。