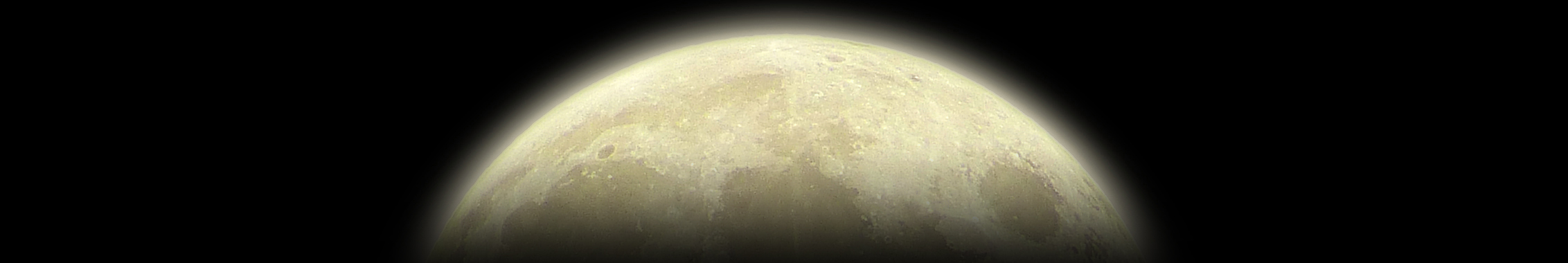『SEX and HONEY 3 秋』
作:エデイ様
この話は「第7話 癒す! 」「第8話怒る!」「第15話 ずぶ濡れ! 」「第16話 死す!」の4話連作パラレルシリーズとなっております。
各話完結しておりますのでどの話からお読み頂いても問題ないと思いますが、一応上記番号順に読み進めていただくことを想定しております。
ゴロ×カンオンリー。糖分過多。
ギャグ領域不可侵条約締結。
大人でダンディーなゴロさんをお求めの方にはオススメ出来ませんのでご注意ください。
真夏の焼けた太陽が白く舗装されたアスファルトの上に濃い影を落とす。
肌を切り裂くような、冷たい雨が降っていた。
カンベエは濡れた舗装の上に貼り付く赤や黄色に紅葉した落ち葉を踏みつけながら、靴が濡れるのも構わずに水溜まりの上を歩いていた。
面白半分に選んだ制服はヴァカンス気分を堪能するには十分過ぎるほどの効果を発揮して、たとえ一時的な錯覚にせよ全く別の生き物にでも生まれ変わったかのような心地がして気に入っていたのではあるが、それも今は朝方から降り続けている雨の中を歩くうちに何の防寒の役目も果たすことのない惨めな布切れと成り果てている。
足を上げる度に湿ったプリーツが太股に貼り付くのを不快に感じながら、カンベエは歩く速度を速めた。
もう二度と会うことはないだろうと諦めていた幼い頃別れた弟が自分に会いたい一心で遠い施設からたった一人、交通機関を乗り継いでやって来た。
5年ぶりに目にする弟は大人びた顔つきで身長もおどろくほど伸びていたが、恥ずかしそうに笑うその笑顔は幼い頃そのままだった。
1日だって忘れたことなどない。
込み上げてくる喜びに眩暈がしそうになる。
嬉しくて、嬉しくて、大きくなった弟を両腕で力一杯抱き締めた。
「兄ちゃん」
弟の自分を呼ぶ声に、誇らしさが込み上げてきて胸が熱くなる。
生きていても死んでいても大して変わりがないと信じていた自分というものが、突然尊い何者かになったような気がした。
自分だけだ。
世の中にどれほど多くの人間が存在していようとも、ゴロベエにとっての「兄ちゃん」は自分だけしかいないのだ。
実の父親に抱かれる。
性器に催淫剤を塗られ、ひいひいと情けない啼き声をあげながら殺したいほど憎い相手に縋りつき、腰を振る。
惨めな思いに押し潰されそうになりながらイライラとした気分が収まらず、夜になると殴り合いが出来る相手を求めてハイエナのように街を彷徨った。
暴力の渦中に身を置いている間は目の前にある相手のことだけを考えていれば良い。
やがてカンベエは自らの体を鍛えることに没頭し始めた。
すべてが疎ましく穢らわしかったが、体を動かしている間は何も考えずに済む。
トレーニングを終えると繁華街へと繰り出した。
夜の繁華街には居場所を求めて彷徨うカンベエと同じ年頃の少年や少女達がたむろしていたが、互いの傷を舐め合いながら群れるにはプライドが高すぎて、相談できる相手もないままカンベエは孤独だった。
世界は醜悪で何の秩序もなく、カンベエは自分の奥に巣食う塊のような怒りがひっそりと成長してゆくのを冷えた心で感じながらふいに襲ってくる暴力の衝動に身を任せ、その痛みの中でしか次第に生を感じることが出来なくなっていた。
いっそ堕ちるところまで堕ちたら少しは楽になるのだろうかという暗い誘惑に駆られながらも、それでもカンベエをギリギリのところで留めていたのはやはり弟の存在だった。
腐った魚に囲まれて暮らしているような反吐みたいな日々の中で、カンベエにとって弟と過ごす時間だけがたった一つの輝くリアルだった。
リアルな世界は眩しいほどの明るさに満ち、空気は新鮮で清々しく、人間が人間らしく生きていることを感じることが出来る。
カンベエにとってかつてこの家で弟が一緒に暮らしていた証であるささやかな痕跡すらが大切すぎて捨てることが出来なかった。
閉ざされた世界。周囲は常に暗い海の底のように闇に覆われている。
足を引き摺るようにして忌まわしい家に戻り、気紛れに現れる父親に体を開きながらクスリで朦朧とした頭で考える。
弟が帰る「家」は、ここより他にどこにもないのだ。
そんな弟も、中学校に入ってしばらくすると顔を見せにやってくることはなくなった。
野球部の練習が忙しいのだと電話口の向こうで弟は言い訳をするように早口にまくし立てた。
弟には、弟の生活がある。
それは自分のような泥にまみれたクズのような男が決して介入してはいけない「リアル」な世界。
だからカンベエは、どんなに弟に会いたくても自分から弟に会いに行くようなことだけは絶対にしないと決めていた。
自分が弟にしてやれる「兄」らしいことといえば、もうそのくらいしか残されていないように思えた。
第三土曜日の午後、弟は会いに来なくなった代わりに、電話をかけてくるようになった。
弟が中学を卒業すると同時に、カンベエは誰にも行く先も告げないまま、あてもなく逃げるようにして家を飛び出した。
中学を卒業しても弟はこのまま自分の前に姿を現さないかもしれない。弟に決定的に避けられているという想像はカンベエに足元が崩れ落ちるような恐怖を与えた。
弟の前では、いつまでも頼りがいのある「兄」を演じて居たかった。
弟と一緒に暮らしていた頃のままの、明るくて優しい「兄」のままで居続けたい。
亀裂を突きつけられるくらいならば、見せ掛けでも良い。この関係を維持するためならば、何でもする。
糸一本でも自分と弟は兄弟として繋がっているのだと、救いを求める人が信仰に縋るような気持ちで信じ続けていた。
弟だけが、暗い海の底に這う自分にリアルな世界を垣間見せてくれるたった一つの光だったから。
カンベエは弟に自分と同じ狂った父親と同じ血が流れていないことに安堵しつつ、それでも弟と自分が兄弟として繋がっていたいという矛盾した願いに苦しみ喘いでいた。
カンベエにとってもう弟のほかに欲しいものなど何一つ存在しなかったから。
きらきらとした瞳をまっすぐに自分に向けて眩しいほどの笑顔を浮かべる、あの綺麗な弟だけがカンベエが唯一欲しいと望んだものだったから。
逃げ続けることが卑怯だというのなら、自分は卑怯者で構わなかった。
地区大会優勝と刻まれた見覚えのないバッチを自分の部屋で見つけたあの夜、カンベエは弟を失うかもしれないという絶望に、一晩中吐き続けた。
吐いて、吐いて、吐いて、吐瀉する固形物がなくなってもそれは続いて、いっそこのまま汚物に塗れて死んでしまいとさえ思った。
翌日弟から連絡があり、カンベエは自分がまだ弟にとって「兄」として許されていることを知った。
声が震えるカンベエを訝しむ受話器の向こうに居る弟に向かって、カンベエは風邪をひいたらしいと言って誤魔化した。
「誕生日、おめでとう。…遅くなって、ごめん」
「…いや」
「具合悪そうだ」
「大した事、ない」
「そう」
受話器を置くなり、声を殺して嗚咽した。
涙がとめどなく溢れて止まらない。
要らない。
弟以外、何も要らない。
強くなろう。
自分以上に、弟の幸せを願うことが出来る兄であり続けるために。
弟に、依存して生きないように。
いつか弟のすべてを笑って受け止めることが出来るような、大きな人間になるために。
弟だけが、自分にこの腐りきった醜悪な世界の中で、美しく大切にしたい何物かがあるのだと教えてくれたから。
この世に弟が居る限り、兄として生きていたい。
カンベエにとって弟だけが、自分をこの世に繋ぎとめるただ一つの楔だった。
家を出てからは、第三土曜日になると今度はカンベエの方から弟の携帯電話に連絡を入れるようになった。
互いに居場所を明かさず、弟が電話に出ることを拒否するなり、番号を代えてしまえば終わってしまう細々とした関係が続いた。
弟がコールに出なくなったその日が、弟との完全な別離を意味している。
一年ほど根無し草のような生活を続けた後カンベエは、この国を飛び出した。
声を聞いているうちに、弟に会いたくて、会いたくて、会いたくて、顔が見たいという気持ちが募って堪らなくなった。
受話器越しに聞こえてくる弟の息遣い、吐息のような相槌、思いがけず零れてくる笑い声一つ聞き逃すまいと全身を耳にして集中していると、手を伸ばせばすぐそこに弟が居るような、そんな錯覚に囚われてはっとする。
気がつけば、姿を見たい、触れたいとそればかりを考えている自分に慄然とする。
自制が効くうちに、兄としての矜持が僅かでも自分の内に残されているうちに、この国を出てゆく必要があった。
そうでなければきっと自分は弟の生活を壊してしまう。
どんなに待ってももう弟が自分に会いに来てくれる事はない。
弟が自分に会いに来ない理由を何万通りも考えては眠れない夜をこれ以上過ごすことがないように、何処でも良い、可能な限り弟がいる場所から今すぐにでも離れる必要があった。
いくつかの国を彷徨い、様々な仕事に就きながら放浪を重ねてカンベエはいつしか外人部隊に籍を置くようになっていた。
契約で結ばれた乾いた関係の中に身を委ね、金で雇われ戦場に起ち、命があれば再び次の契約を待つ。
殺伐とした暮らしはカンベエの肌に馴染んだ。
そして状況が許す限り、第三土曜日になると遠い国から故国で暮らす弟に電話をかける。
弟は教師になっていた。
弟には、自分はフリーのカメラマンということになっている。
ある作戦時に自分たちの部隊に同行したカメラマンの姿を見て思いついたものだった。
立派な職業に就いている弟の兄弟が、ならず者のゴロツキであってはいけない。
死んだ仲間の遺品を遺族に届けに向かう途中、地平線がどこまでも続く景色を遠くに目にしながら弟に電話をかける。
第三土曜日の午後。
弟の暮らす時間が日付変更線を超えていないようにと祈りながら赤茶けた大地の上に立ち、受話器を握るカンベエの癖の強い長い髪を獣が咆哮するような渇いた音を立てながら乾いた北風が嬲っていった。
カンベエの掌に納まる死んだ仲間が遺したちっぽけな認識票。
二つ並んだタグの一つは遺体代わりとして墓の下で眠り、残されたもう片方のタグを、残された遺族である兄の許へ届けるためにカンベエはもう三日の間ジープを飛ばしていた。
ワンコールで弟が電話口に出た。
「元気か」と訪ねると、ぼんやりしたような声で「うん」という返事が返ってくる。
学校は楽しいか?仕事は辛くないか?同僚とはうまくやっているのか?お主は案外腹が弱いのだから寝冷えしないように気をつけるのだぞだとか、忙しくてもちゃんと朝食を食えだとか、今でも野球は続けているのか?だとか。
どんな小さなことでもいい。
弟のことが知りたくて、知りたいという思いが矢継ぎ早の質問となって溢れ出て、止まらない。
弟はこんなおしゃべりな兄に呆れながらも律儀に短い返事を返す。
何だって良いのだ。
弟が元気にしているという実感が欲しい。
他愛の無い日常の中で健やかな生活を築いているのだという実感が欲しかった。
結婚は?
と言いかけて、口を噤んだ。
ふいに訪れた短い沈黙を破ってのんびりとした弟の声が聞こえてきた。
「そっちは今、夜?」
白い空に輝く大きな星を見上げた。
「ああ…十字架のように並んだ星が、とても綺麗だ」
「そう…。こっちは、山が燃えているように紅葉が見事でな。明日は遠足なのだが、生徒以上に某の方が楽しみにしておる」
くすっと小さく弟が笑う声が耳の奥で優しく溶けた。
「…そうか」
声が震える。
弟が、笑った。
たったそれだけのことで、染みるような温かい気持ちが胸に広がってゆく。
カンベエは受話器を耳朶に押し付けるようにしながら、瞼を閉じてそっと深い息を吐いた。
「子供の頃、神無山に登って二人でドングリの実を集めたこと、覚えてる?」
「…ああ」
通話口から聞こえてくる弟の声に耳を傾けながら握り締めていた拳を開き、掌の上にある認識票に視線を落とす。
椰子の葉が生い茂る密林の奥、大木の根の部分を覆い尽くすようにしてびっしりと生えた光り苔が蒼白い燐光を浮かび上がらせる異国の地。
降るような月の光の下で小さな沼地の水面に光る白い花をもっと見ようとカンベエが近づくと、それは死んだ兵士の顔だった。
同じ傭兵仲間であったその男の体は手も足も制服を裂いてはち切れるほどぶくぶくに膨れあがり、異様な白い物体となってぼんやりと浮かびながら、異臭を放っている。
肢体の半分を水中に沈めた男の遺体に目を向けながら、カンベエは弟の顔を思い浮かべていた。
「兄さん」
キャッチボールしに行こうよ。
そんな声が聞こえてきそうな笑顔だった。
自分の弟は、たった一人の大切な弟は、故国で幸せに暮らしている。
平和で安全な世界で、穏やかで満ち足りた生活を送っている。
母親に捨てられ、辛い目にも散々あってきた、決して順風満帆とは言えない様々な苦境を乗り越えて、今では立派に学校の教師をしているのだ。
すまない、と死んだ仲間に向かってカンベエは深く頭を垂れながら呟いていた。
弟が誇らしくて、そんな弟の兄である自分が誇らしくて、生まれてきて良かったと喜びが滲むようにして胸に満ちてゆく。
どうか自分にこんな風にたった一人の弟を思い続けることを許して欲しい。
弟が暮らす故国では今、紅葉が見事だそうだ。
明日の遠足が楽しみだと、弟がそう言っている。
「…もしもし?聞こえてる?」
「…ああ」と返事を返しながら、嗚咽を堪える。
泣きたくなるほど自分は今、幸せだった。
通話が切れた受話器を握りながら、カンベエは祈るようにして送話口に口付けた。
ふと顔を上げるとカーテンのような雨の向こうに、小さなビニール傘を差したゴロベエが直立している姿が透けけて見えた。
ゴロベエが自分の前に姿を現したあの日から、今日という日がやってくるのを恐れるような気持ちで待っていた。
「カンベエ殿」
傘を差しているにも関わらず、ゴロベエの両肩はぐっしょりと濡れてスーツを色濃く染めている。
晩秋の雨は冷たい。
「…ここの住所は教えていない筈であったが。生徒に関する個人情報について教師の特権乱用は許されておるのか?」
カンベエの皮肉に、ゴロベエは硬い表情を崩すことのないまま「話がある」とだけ答えた。
アパートにあるカンベエの部屋に通すなりキョロキョロと物珍しそうな顔をしてあちこち眺めているゴロベエの濡れたスーツの上着を脱がせ「とにかくこれで濡れた体を拭いて、着替えろ」とタオルと着替えを半ば押しつけるようにして手渡した。
ゴロベエが着替えている間に冷蔵庫の中から二人分のビールを取り出す。
この部屋で飲む習慣がないせいで、冷蔵庫の中には喉を潤すために置いたこんなものしか入っていなかった。
カンベエは部屋のストーブに火を点すと、ビールの栓を抜いた。
背後からのそりと着替えを終えたゴロベエが現れる。
顔を上げて自分のシャツを着たゴロベエの姿を目にした途端に、幼い頃自分のお下がりをもらって喜んでいた弟の姿を思い出してカンベエは慌てたように冷えた体に冷たいビールを流し込むようにして煽った。
「女モノじゃない…」
どうやらゴロベエはカンベエから手渡された服が男物であったことに途惑っているらしかった。
カンベエは苦笑しながらゴロベエに座るようにと促した。
「制服はともかく、特に女装が趣味だという訳ではない」
よく見ると、肩のラインと腕の長さが窮屈そうだった。
弟はいつの間に自分の背丈を追い越していたのだろう。
カンベエの返事にゴロベエは「そうか」とだけ頷くとカンベエの正面に腰を下ろした。
机の上に置いたもう一本のビールの栓を抜く。
弟と、いつか一緒に酒を飲める日が来るかもしれないと想像した時もあった。
その夢が、たった今考え得る限り最悪な形で実現しようとしている。
「あの出来損ないのような者が集まる学校にお主が転任してくるとは驚いたぞ。まさか教師にも左遷とやらがあるのか?」
笑い飛ばそうと開いた口はカンベエの意に反して上手くゆかずにくにゃりと歪んだ。
沈黙が重い。
点灯したストーブの火が、互いの半身を赤く照らしていた。
「ワシはまた、すぐにでもこの国を出るつもりだ。安心しろ…」
一年前。次の招集はお前抜きだと、繋ぎと呼ばれるコーディネーターからカンベエのもとに連絡が入った。
今度の雇い主は、個人的な恨みからアジア系を酷く嫌っている。
金で雇われている以上、こんなこともあるのだ。
部下の数名を借りるが、作戦に従事せずとも物資の空輸という高額アルバイトの口なら紹介してやっても良いという話をカンベエは断った。
故国を飛び出して20年の月日が経っている。
このまま異国の地で朽ちる覚悟だったのが、一目で良い。思いがけず唐突に空いたスケジュールに、弟の暮らす故国をもう一度この目で見たいという気持ちが込み上げて溜まらない気持ちになった。
これが最後かもしれない。
現役として戦場に立つには、そろそろ限界に近づいている。
引退した傭兵は軍事コンサルやセキュリティ業界へと転職する者も多かったが、カンベエは刀を捨て、軍服からスーツに着替えて働く自分の姿を想像することが出来ずにいた。
生死の狭間にしか自分の居場所を見出せない男は、死ぬまでそこで生き続ける他に術はない。
暗い海の底に産み落とされた深海魚は、所詮光ある場所で飼い慣らされて生きることなど出来はしないのだ。
弟に会いたいという気持ちはとっくの昔に消え失せていた。
ただ最後の戦場に起つ前に、一目弟の暮らす国をこの目で見たい、弟と同じ空を見あげたい、肌でその風を感じてみたい。
何かに急かされたように、それだけを願っていた。
気紛れに入った学校は、無意識だったにせよ頭の片隅に弟が教鞭を揮う学校というものに触れてみたかったという思いが残っていたせいかもしれなかった。
そもそも自分は学校というものに、まともに通った記憶がない。
その学校で、まさか生きて会うことは二度とあるまいと思っていた弟が、新任教師として赴任して来ようとは夢にも思わなかった。
最後に会ったのは、少し大きめの学生服を着て、頬の辺りにまだ幼さを残した少年の頃。
「兄さん」
と、はにかむようにして笑いながらきらきらとした瞳を輝かせ、自分に会うためだけに少ない小遣いを捻出してやって来た。
25年という歳月は、すべてを変えてしまうのに十分すぎるほどの時間だ。
それでもカンベエには全校生徒が集まる体育館の中で頬に傷跡を残す新任教師が紹介されている姿を一目見た途端、すぐにそれが別れていた弟であることが解った。
いつだって自分の中心には弟の笑顔があったけれど、どうしたって学生服を脱ぎ成人した弟の顔を想像することは難しくて、それがまさかこんな形で目にすることが出来る日がこようとは夢にも思わなかった。
押し出しの良い、威厳すら感じられる堂々としたその姿が眩しくて、いつまでもその姿を見ていたかった。
自分の目に焼き付けるようにして目で追うことを止める事が出来なかった。
生徒たちに向けられる眼差しはどこまでも優しく、慈愛に満ちている。
想像したとおり、いやそれ以上に弟は道を誤ることなく立派な大人になった。
こんなおかしな姿をしたろくでなしの人間が、兄であって良い筈がなかった。
「今ならばまだ、まさかお主とワシが兄弟であるなどと気付く者もあるまい」
沈黙を埋めるようにして繋いだ言葉が虚しく響く。
これ以上弟の顔を見ていたくなくて、カンベエは視線を避けるように水滴に濡れた空のビール瓶に目を落とすと、ゴロベエが重いため息を吐くのがわかった。
窓を叩く雨の音が一際高く鳴ったように聞こえる。
弟に迷惑をかける気など露ほどもなかったのだ。
もう少しだけ、もう少しだけと立派になった弟の姿を見ていたくてずるずると日が経ってしまった。
明日にでもすぐに出立しようと、カンベエが顔をあげた時だった。
ゴロベエは泣いているような、怒っているような顔をしていた。
「そんなことは、どうでも良い」
「どうでも良い?どうでも良いとはどういう意味だ」
眉を上げるカンベエの探るような視線を正面に受け止めながらゴロベエは重い口を開いた。
「某は、カンベエ殿のことを兄だとは思っておらぬ」
吐き出すように投げられた言葉がカンベエの胸に突き刺さる。
「…兄だとは、思っていない?」
聞き間違いであって欲しいと縋るような目をしたカンベエの前で、こくりとゴロベエは頷いた。
アニダトハオモッテオラヌ。
弟は、自分のたった一人の弟は、自分のことを兄と認めていなかった。
25年もの間、ずっと答えを知ることを恐れてきた。
何故、弟は幼い頃のように自分のことを「兄さん」と呼んでくれないのだろう。
単純なことだ。
弟にとって自分は、すでに赤の他人だったのだ。
兄弟だと、血の繋がりなどなくてもずっと兄弟であると信じてきたのは自分一人だけだったのだ。
隠してきた弱い部分にギリギリと爪を立てられ血を流しているような苦痛に喉が震える。
それでもカンベエはゴロベエの告白をどこか酷く冷静に受け止めている自分が居ることに安堵していた。
何時の日か、こんな日がやってくることはわかっていた。
今ならばまだ最愛の弟に、これまで長い間弟でいてくれたことに対する感謝の気持ちを伝えることが出来る。
手帳に挟んだカレンダーを何度も穴の開くほど見つめては、三度目の土曜日であることを確かめて弟の声を聞く。
地球の裏側から心の中で弟の幸せを願っているだけで、自分は十分すぎるほど幸せだったのだ。
二度と生きて会うことはないと信じていた弟の立派に成長した姿を目にすることが出来て、死んでもいいと思えるくらい嬉しかった。
迷惑をかける気などなかったのだ。
気付かれないうちに姿を消すべきだったのに、遠目に見る弟の生徒たちに向けられる笑顔が眩しくて、幼い頃と変らないくったくのない笑い声をもっと聞いていたくて、もう少しだけ彼の傍に居たいと欲が出た。
想像の中の弟は、優しい奥さんと小さな可愛らしい子供が待つ家と、本物の「家族」を持っていた。
弟の奥さんは大食いな夫の胃袋を満足させるのに苦労して、優しい弟はそんな彼女のために買い物に付き合う。
弟の子供はきっと誰よりも可愛いはずだ。
弟はずっとペットを飼うという事に憧れていたから、弟の家には犬か猫が一緒に暮らしているかもしれない。
自分にはどれも永遠に手にすることが出来ないものだけれど、彼には誰よりもそんな幸せな景色が良く似合うから。
そんな姿を一目、見たかった。
一体何時から弟は、自分のことを兄と呼ばなくなってしまったのだろう。
つきつめて思い出そうとすると、答えを出すことを拒むかのように頭の奥がズキズキと痛んだ。
弟は、これまでどんな気持ちで第三土曜日を過ごしてきたのだろう。
勝手に「兄」と名乗る孤独な男からの連絡を、憐れに思って兄弟ごっこに付き合ってやっていたのであろうか。
「いつからだ…」
掠れたような声で問うカンベエに、ゴロベエは逡巡しながらも静かに答えた。
「もう、ずっと以前から」
カンベエの短く息を呑む痛々しい音に、ゴロベエは眉をぎゅっと寄せながら両膝の上に置いた拳を硬く握った。
酷いことを言っている、という自覚はある。
しかしカンベエが望む言葉を、嘘で固めた飴玉を与えるようにして差し出すわけにはゆかなかった。
「それは、すまぬことをしたな…」
カンベエは視線を床に落としたまま立ち上がると、空になったビール瓶をダストボックスの中に落とした。
「それでもワシは、お主が弟で、嬉しかった。最後にこうして一目でも会うことが出来て、嬉しかった…」
「違う。そんな言葉が聞きたくて言ったのではない」
弟の声がはっとするほど近い場所から聞こえてきたことに驚いて振り向けば、背後から強い力で抱きすくめられていた。
「ゴロベエっ?!」
「偶然などでは、ないのだ」
「何?」
振りほどこうとすると、ますます腕に力を込めてくる。
「放せ」と言うと、今度はしがみつくようにして肩口に顔を押し付けられていた。
自分より肩幅がほんの少しだけ広く、自分より背がほんの少しだけ高い。
こんな時なのに、会わない間の弟の成長を肌で感じることが出来ることが嬉しいだとか、そんな場違いな感慨に耽りそうになる自分に呆れながら、カンベエは力を抜いた。
密着した部分から弟の少し高めの体温が伝わってくる。
彼にとって自分はもう赤の他人であろうとも、カンベエにとってゴロベエはいつまでたっても愛しい「弟」だった。
「…何が偶然ではないのだ、ゴロベエ」
「カンベエ殿が戻ったと知り、着信番号から居場所を探し出してこの学校を突き止め、職員採用試験を受けた」
「…何?」
流石にこの言葉には驚いて、カンベエは顔を上げた。確かに今使っている携帯電話を入手する前は、まさか居場所を突き止められるとは思わずに公衆電話や店にある電話を使って弟に連絡を取ったことがあった。
「どうしても、会いたかったから」
「…」
「会いたくて、会いたくて、たまらなかったから」
畳み掛けるようにして弟の口から繰り返される単純な言葉に思考が麻痺してゆく。
どくどくと心臓を打ち付ける音が激しい。
会いたかったという言葉をどう受け止めてよいのか、返す言葉の一つ見つからないままカンベエは途方に暮れていた。
弟の顔が見たいと思っても、今のこの体勢ではそれも叶わない。
「カンベエ殿のことを、兄だと思っておらぬと言ったのは…」
ゴロベエは一旦言葉を切ると、再び体を硬くしているカンベエの肩から顔を上げた。
「あの日から、カンベエ殿を、兄として見ることが出来なくなってしまったから」
ゴロベエの告白に、カンベエは苦いものが胃の腑からせりあがってくるような吐き気を感じて口を押さえた。
甘い言葉にのぼせていた気持ちが、凍てつくようにして冷えてゆく。
やはり弟は、“あの日”父親と寝ている自分の姿を見て、会うことを避けていたのだ。
目を背けてきた自分の醜い部分を無理矢理直視させられているような苦痛はむしろこの場合自分にふさわしいものだった。
汚らわしい。
顔も見たくないと避けられるのは当然のことだった。
むしろ責められるべきは自分の方であって、恨まれてしかるべきだった。
血の繋がりもなく戸籍上の関係ですら認められていない男から、20年以上もの長い間「兄弟」の関係を押し付けられてきたのだ。
「軽蔑した、だろうな」
弟の顔を、目を、見ることが出来ない。
「会いたかった」などと言われて一瞬でも期待した自分は底無しの屑だ。
それでも、こうして弟に会うことが出来て、声を聞くことが出来て、自分は嬉しかった。
弟が自分を糾弾するためにやってきたのだとしても、それでも自分は弟に会うことが出来て嬉しかった。
たとえそれが弟の、希望を与えて打ち砕くというのが彼の手段だったとしても。
会って、話をすることが出来て、嬉しかった。
俯きながら自嘲に顔を歪めるカンベエに向かって、ゴロベエは首を横に振っていた。
「そうではないのだ…。軽蔑されるべきは某の方だ」
ノロノロと振り向いて物憂げな様子で問うような眼差しを向けるカンベエに向かって、ゴロベエは唇を震わせた。
「あの男に抱かれている兄さんを見て某は、あの男が自分だったら良いと、あの男に自分を重ねてカンベエ殿を心の中で犯した」
ぴくりと抱いているカンベエの肩が僅かに震える。その肩を掴むゴロベエの指先も色を失っていた。
「あの日から、何度も何度も大好きな兄さんを頭の中で犯すことを止められない。そんな自分に絶望して、ずっと苦しかった。
夢の中の兄さんは優しく微笑んで、某に向かって体を開きながら言うのだ。
お前は自分の大切な弟なのだから良いのだと。
それでは、あの男と自分は何も変らないことになる。
兄さんを、弟だから、兄弟だからなどという言葉で縛りたくはないのに…」
再びしがみつくようにして自分の背中に抱きついてくる弟を、振りほどくことが出来なかった。
どうしてあの呪われた男と、この愛しくて愛しくて何よりも大切に思ってきた弟が同じであるなどと考えることが出来るのだろう。
「愛してる。兄としてではなく、一人の男としてカンベエ殿を、もう長い間ずっと、愛してる」
ゴロベエの言葉を呑み込むようにカンベエは、自らの唇でゴロベエの唇を塞いでいた。
受け入れてはいけない、間違った感情だと解ってはいたが、理性が働くよりも先に弟の首を掻き抱くようにして唇を貪っていた。
すぐにゴロベエの舌がカンベエの舌を捕らえるように絡みついてくる。
痺れるような熱が体中を這い回り、奥へ奥へと弟の舌を吸い、弟の唾液を夢中で飲んだ。
弟の大きな手で頭から顔を滅茶苦茶に撫で回されている。
今だけだ。
きっとこの瞬間自分は何もかも失う。
それでも、目の前にいる弟を愛さずにはいられない。
いられなかった。
荒い息を吐きながら雄の目をして自分を欲しがっている弟の顔に手を添えて、父に切りつけられた頬の傷跡に口付ける。
惨たらしい引き攣れの痕をなぞるようにして舌を這わせてゆくと、逞しく成長した弟の体がビクリと震えた。
安物のベッドの錆びたスプリングが二人の男の体重を支えきれずにキイキイと不快な音を立てる。
短く浅い呼吸の合間に、堪えきれない喘ぎ声が積み重なるようにして、狭い空間を埋め尽くしてゆく。
剥ぎ取るようにして脱がせたふざけた制服の下から現れたカンベエの体に、ゴロベエの目は釘づけにされていた。
頭の中では何度も兄の体を裸にして陵辱の限りを繰り返してきたというのに、実際に男とセックスをするのは初めてだった。
他の男で試そうとしたこともあったが、女とは異なる同性の体を目の前にするとどうしても受け付けることが出来なかった。
だから、いざ夢に見ていたカンベエの体を実際に目の前にして自分が役に立つのか全く不安がなかったとは言い切れないというのが正直なところではあったのだが、今自分の目の前に存在しているカンベエのしなやかな筋肉が描く稜線は、ゴロベエの目に非凡なほど美しく艶かしく映り、ゴロベエを圧倒していた。
漠然と運動することが好きなだけの自分の体躯とは明らかに異なる、実践的な目的に沿って鍛えられているのが一目でわかる無駄のない造形。
肌理の細かい褐色の肌が、自分を誘うように優しく開かれている。
この体を思うままに組み伏せて好きなように弄り悶えさせることを想像するだけで、甘い痺れが体中を駆け巡る。
カンベエの大きく開かれた胸に走る傷跡をそっと唇で辿り、小さく尖った胸の突起を摘んで押しつぶすように捏ねると、堪えきれないため息のような吐息が漏れた。
「すまない、男は初めてだ」と正直に告白すると「ワシも…弟とするのは初めてだ」と呟くように返された言葉に、どこか途方に暮れたような横顔が垣間見えてたまらない気持ちになった。
まるで好きな人とするのは初めてだと告白されているような、いじらしさを感じて胸が詰まる。
カンベエが「弟」と口にするとき、それがどれほど彼にとって特別で大切なものの名であるかということを、甘く切ない響きが想いの深さを伝えてくれるから。
弟のままで居られなくて、すまないと心の内でそっと呟いた。
「好きだ」と「ごめん」を繰り返し
25年分の想いの丈をぶつけるようにして、熱い体を抱いた。
天上からぶら下がる古めかしい形をした電灯の明かりを消そうと伸ばされた腕を遮ると、心持顔を赤くしたカンベエに睨まれる。
そんな思いがけない表情一つに簡単に胸の鼓動が撥ねる。
「明かりを消したらカンベエ殿が見えない」
と言うと、呆れたように「お主、男は初めてなのであろう。明かりなど点けたら興冷めだぞ」という返事が返ってきた。
「嫌だ。ちゃんと見たい」と言ったのに、怒ったような「たわけ」という言葉と同時に有無を言わさず明かりを消されて、尚も抗議しようとする口を塞がれた。
暗がりの中で組み敷いた熱い肉の蠢く様子に、凶暴なまでの欲を感じてごくりと咽喉が鳴った。
セックスなど、みっともない姿を曝け出し、ひたすら互いの粘膜を擦り合わせて快楽を貪るだけの行為であって、それ以上でもそれ以下でもない筈なのに。
父親に抱かれるようになってからカンベエは、セックスをする時には必ずクスリを必要としていた。
大概それは薄めたコカを少量性器に塗りつけることが多いのだが、媚薬の入ったローションを用いることもあった。
手っ取り早く快楽を得るにはこれが一番だったし、相手も大概それを歓迎して共に使用することが多かった。
しかし故国に帰ってからは、当初はこれほど長期に渡って滞在する考えがなかったせいもあって、こうしたクスリの持ち合わせは何もなく、カンベエは容器の柄が気に入って購入していたハンドクリームを通学に持ち歩いているリュックの中から取り出して、ゴロベエに手渡した。
今ゴロベエは、掌の中でハンドクリームを捏ねまわすようにして伸ばしながら、クリームのついた指先でカンベエの後ろの窄みを押し広げるように動かしている。
たとえクスリを手にしていたとしても、カンベエは弟とのセックスにこれを使いたいと思わなかった。
クスリを使用しないセックスはカンベエに少しの不安と痛みへの恐怖を齎したが、それでもそれが弟が自分に与えるものならどんな痛みでも欲しい。
しかしカンベエの決意も虚しくゴロベエは酷く慎重だった。
時間をかけてたどたどしくカンベエの良い所を探ろうとする動きが逆にカンベエにとってもどかしく、「ココ?気持ちよい?」「柔らかくなってきた」といった拙い言葉を耳にしていると、弟に背徳的な行為を迫っているという罪悪感が、逆にカンベエを昂まらせ追い詰めていた。
「もっ、良いから、…早く」
強請るように腰が揺れてしまうのをどうすることも出来ない。
メリメリと音がしそうな勢いで押し入ってきた硬くて熱い弟のモノを感じると、意識の全てが引き摺られるようにしてその一点に集中し、カンベエは悲鳴のような嬌声を上げていた。
みっしりと重量のある弟のペニスが内壁を侵蝕し、狭い器官を蹂躙してゆく。
弟に揺さぶられてカンベエは淫らに泣いていた。
濡れて泣きながら悶えて、もっと、もっと欲しいと強請った。
弟を自分の体の奥で受け入れている。それだけで脳天が痺れ、達しそうなほど興奮した。
快楽に負けてがくがくと震える体を弟に捻じ伏せるようにして押さえ込まれ突き上げられながら、カンベエは吐精していた。
せわしなく上下する胸の上に尖った、小さな突起。
そっとつまみ上げて擦り、指で捏ねていると芯を持ってピンと立ち上がる。
口に含んで甘噛みすると途端にカンベエの口から色のある声が漏れて、ここが気持ち良いんだと知る。
もっと知りたい。
ぎうぎうと自身をきつく締め付けるねっとりとした内壁の気持ち良さに持っていかれそうになるのを堪えながら、淫らに揺れる腰を押さえつけるようにして射精したばかりの前の部分を強めに握り締めて乱暴に扱くと、浅く忙しない呼吸の合間に、すすり泣くような吐息が聞こえてきた。
「ゴロベエ…、っ」
濡れた声で名前を呼ばれ、「ッ、また、…イクッッ…」とゴロベエの手の内にあるカンベエの自身がビクビクと跳ねるように白濁を零して、ゴロベエもカンベエの奥へと欲を吐き出していた。
射精後の気だるい倦怠の中で、褐色のカンベエの割れた腹筋の上に飛び散る白濁をぼんやりと目で追っていると、徐にカンベエが起き出した。
「シャワーを浴びてくる」
「…某も行く」
「付いてくるな」
そう言い残すなり風呂場へと消えていった。
昇り詰めた快楽を吐き出してしまえば、潮が退くように現実だけがカンベエの目の前に横たわっていた。
小さな風呂場の中でカンベエはシャワーのコックを捻ると、湯になりきらない冷たい水のまま頭からシャワーを被っていた。
戦場で命のやり取りを続けていると、人肌に触れるということがどれほど人の心を癒してくれるかということについて嫌と言うほど実感することになるのではあるが、今のカンベエには弟を穢してしまったことに対する罪悪感と、男は初めてだと告白した弟が果たして満足を得ていたのかという混沌とした不安しか感じることが出来なかった。
弟の逞しい腕に抱かれて熱に浮かされたように、自分ばかりが夢中になってしまった。
父親に抱かれている自分を見て弟は苦しんだと言っていた。
弟を失いたくないという自分のエゴによって同じ苦痛を今再び自分が与えてしまったのかもしれない。
壁に手を当てるようにして体を支えながら俯くカンベエの背後で扉が開く音が鳴り響き、カンベエははっとして振り向いた。
「某も一緒に入る」
カンベエの制止する声も聞かずに、ゴロベエはずかずかと狭い浴室の中に入ってきた。
「後悔しておるのか?」
壁を背にするカンベエにゴロベエが距離を詰めて近寄ってくる。
カンベエは諦めたように、ため息を吐いた。
「…後悔などしておらぬ。ただ、ワシは、自分のせいでたった一人の弟を失ってしまった」
出しっ放しにしてあるシャワーの飛沫に目を瞬かせながらゴロベエは首を傾げた。
「カンベエ殿は弟ではない、片山ゴロベエという男は嫌いか?」
「お主を、弟以外の…他人だと考えたことはない」
「それでは今から知ることだ」
「何?」
壁に手をつき、カンベエを押さえ込むようにしながら顔を近づけるとゴロベエはにっこりと微笑んだ。幼い頃と変らない、屈託のない笑顔だった。
「弟ではない現実の某という男を、時間をかけてゆっくりと知るというのも宜しかろう。某の方はイヤだと言われてももう二度とカンベエ殿の傍を離れる気はないので安心なされよ」
追い詰められる格好になりながら、カンベエは近すぎる距離にある男の目を覗き込むようにして見あげた。胸の動悸が激しい。
「…それでも、弟としてしか見ることが出来ぬと言ったら?」
「ふむ」と、ゴロベエは片手で顎を擦りながら、天上を仰ぎ見た。
カンベエがなおもじっとそんなゴロベエの様子を観察していると、再び極上の笑みを浮かべながらゴロベエは頷いた。
「だとしたら、カンベエ殿には兄に欲情する弟として愛してもらうしかないでござるな」
「何だと?」
ゴロベエの言葉にカンベエは拍子抜けしたように、肩の力を抜いた。
もやもやと胸の内でわだかまっていたものが、厚い雲の切れ間から射し込んできた太陽の光に一掃されるかのようにして霧散してゆく。
過去に縛られ、ぼんやりとした不安に押し潰されそうになっている自分が馬鹿馬鹿しく思えてきた。
掴みどころがないという点では、ゴロベエは太陽というより雲に近い男かもしれなかった。
「教師のくせして何をたわけたことを申すのだ…」
カンベエが呆れたように呟くと、ゴロベエは笑った。
「残念ながら某は本気でござるよ。何しろこの歳になると残された時間は少ない故、つまらぬ意地を張ったり体面に拘わるのは時間の損というもの。
カンベエ殿にしかと現実の某を知って頂くまで諦めぬから、せいぜい覚悟することですな」
「…現実の、お主?」
ぼんやりと自分を見上げるカンベエの瞳に視線を合わせたままゴロベエはこくりと頷くと、そっとカンベエの頬に手を添えた。
「こうして、目をあわせ、触れることが出来る、生きて呼吸をして、カンベエ殿に恋焦がれている片山ゴロベエという男よ」
「もう良い。…お主と話していると頭が変になりそうだ」
顔を背けるカンベエの頬が赤く染まって見えるのは、風呂場に籠もる熱気のせいだけではないだろう。
ゴロベエはくくっと咽喉を鳴らすように笑うと、啄ばむようなキスをカンベエの額に落とした。
「このままでは風邪をひく。いい加減離れろ」
「む?カンベエ殿の体は某が隅々まできちんと洗って差し上げますぞ」
「なっ、結構だ。お主はそこのバスタブの中にでも入っておれ」
子供のように唇を尖らせながらもようやく大人しくバスタブに沈むゴロベエの姿を横目で確認すると、カンベエはそろそろと後ろに手を伸ばした。
バスタブの中からゴロベエが自分を凝視している視線を痛いほどひしひしと感じる。
「見るな」と言うと、即座に「何で?」という返事が返ってきて、返答に詰まった。
今更そんなことに照れるような歳でもないし、むしろ後処理を相手にさせることの方が多かったカンベエではあるが、これが相手が弟であるとなると話は別だった。
ゴロベエ自身は長い間自分をそうした対象として考えてきたのかもしれなかったが、カンベエにとって弟という存在は、自分のような男がたとえ想像の中といえども穢してはならない、神聖なものだったのだ。
衝動的に抱かれてしまったとはいえ、こんな白々とした蛍光灯の明かりに照らされた狭い浴室の中で、自分の生々しく浅ましい姿を曝け出してしまうには抵抗が強かった。
未練かもしれない。
過去に弟に対してこうでありたいと願ってきた自分の姿に対する未練を捨てきれないでいる。
「ひょっとして、恥ずかしいのか?」というゴロベエの声に、「違う」と強がりを口にしつつ、ぬめった後孔に当てた指をつぷりと埋めてはみたものの、どうしてもそれ以上すすめることが出来ずにカンベエは俯いたままじっとしていた。
金縛りにでもあったかのように弟の視線に雁字搦めにされたまま、体を動かすことが出来ずに硬直している。
これまでの短くはない人生の中で、空っぽな心をたとえ幻想であったとしても弟に対する希望だけで満たしてきたのだ。
今更それを急に別の何かで埋めろと言われてすぐに態度を変えることが出来るほどの若さもなければ、柔軟さも持ち合わせてはいなかった。
ついに肩を震わせはじめたカンベエの背中を、バスタブから出て来たゴロベエが背後からそっと抱きしめた。
「…お主、性格が悪いぞ」
ぼそりと呟かれたカンベエの言葉にゴロベエはカンベエの耳元に顔を寄せるようにしながら「うん」と小さく頷いた。
「どんなカンベエ殿でも良い。…ありのままの貴方を見せて」
背後からゴロベエに中指を後ろの孔に差し込まれて、カンベエはびくりと体を震わせながらじっと耐えていた。
二本に増やされたゴロベエの指が、掻き出すように狭い器官を広げ、ぐちぐちと奥を掻きまわされる。
後孔からごぼりと白濁したものが流れ出して、カンベエの内股を伝う。
「ッン…、クッ…ァ、…」
内壁を強い力で擦られる刺激に、声が漏れてしまうのを押さえることが出来ない。
カンベエは硬く目を瞑ったまま、唇を噛んだ。
「カンベエ殿っ…」
余裕のない切羽詰ったようなゴロベエの自分の名を呼ぶ声に、カンベエは薄く目を開いた。
「アッ…、な、何だ…」
「我慢出来ぬ」
欲望に掠れた声にカンベエが反応を返すよりも早く、ゴロベエはカンベエを正面に抱くとしゃぶりつくようにして唇を重ね、そのまま白濁でぬめったカンベエの後ろに己の怒張を突き立てていた。
「あああっ…あっ…はぁっ…ッ」
衝撃にカンベエの背中が弓のように撓った。
尻の双丘を大きな手で鷲掴みにされたまま、乱暴に揺さぶられ突き上げられる。
「カンベエ殿っ…カンベエ殿っ……カンベエ殿っ」
壊れた蛇口のように自分の名を呼び続ける男の顔を、カンベエは水の溜まった目で追っていた。
セックスで親愛の情が生まれるということはない。
快楽はただの快楽であって、それ以下でもそれ以上でもない。
それでも、今ひたすら自分の体を貪るように突き上げ、腰を振る目の前の男が愛しいと思った。
弟に理想を夢見てきた。
自分の中で弟はいつまでたってもあどけない笑顔を浮かべた少年のままで、それは同時に、空虚な弟の姿に自分の夢を好きなだけ投影し、実態のない影を愛してきたようなものだった。
リアルな世界で弟は幸せに暮らしていると信じることで、身の置き所のない自分を誤魔化してきた。
そんな自分に、目の前にある現実を見ろと、弟と同じ顔をした血と肉を持った男がカンベエに暴力のような快楽を突きつけながら迫ってくる。
お前が愛してきた幻影の正体を見極めろ。
弟の名は、片山ゴロベエといった。
愉悦に喘ぎながらカンベエは愛しい男の名を呼んだ。
ゴロベエ
何かを失ったのか、それとも何かを得たのか。
もう、どちらでも構わなかった。
触れあう肌から伝わってくるこの熱を信じることが出来る、それだけで十分だった。
<SEX and HONEY 4 冬 「死す!」に続く> 未完