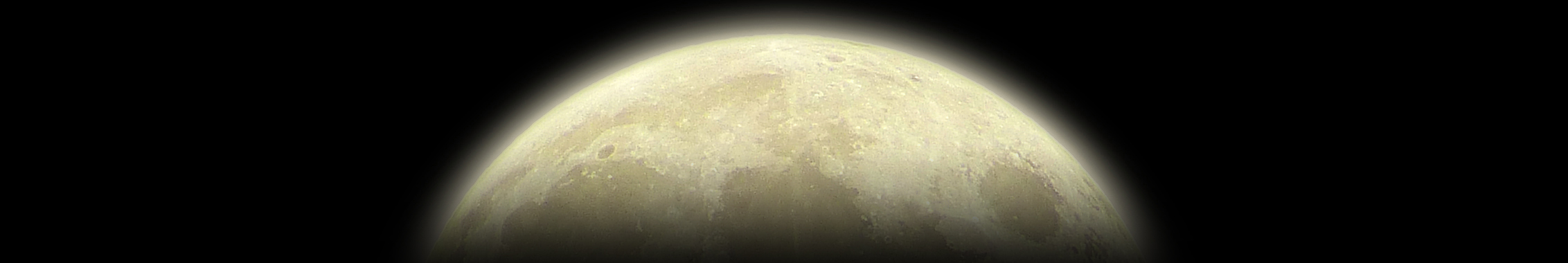ゴロベエ×カンベエ、シチロージ×カンベエ
御存じ、泉鏡花の『海神別荘』のパロディです。
< 登場人物 > 海底にある宮殿の公子→ゴロベエ、地上の美人→カンベエ、僧都、黒潮騎士、腰元、侍女
海底にある宮殿の扉のひとつが開き、腰元衆がずいぶんと着飾っているのを眺めて僧都は声を上げた。
「これは大層美しい。しかし、それはどこの風俗かな、ずいぶんと変わっているが」
「今夜は若様のかねてからお望みが叶かない、地上から美しき方がいらっしゃるのでございますもの。そのため、このような姿となりました。たびたび地上にでていらっしゃる僧都であればご存じでしょうに」
「儂が姿を現すのは暴風雨あらしのときくらい。墓の船に死骸ばかりが蠢くところ、なんで雅な人の姿など見えようものか」
そう云う僧都に腰元衆は笑った。
「僧都はいかがいたしますか。緋の法衣など召されては」
「なんの。儂の身は墨染の暗夜にこそ。緋の法衣など纏ってしまっては、ずぶ濡れの提灯じゃ。戸惑いをした魚などといわれよう。そうだ、忘れぬ前に申上げたい儀があってまかり越したのだった。若様にお取次を頼む」
「畏まりました。ただいま・・・」
腰元のひとりが戸をくぐるとすぐに浅黒い肌に銀色の髪のゴロベエは、緑地錦の直垂、黄金づくりの剣を佩く常より一層 臈たけた 姿で現れて、上段の一階高き床の端に端然として立った。
「爺い、用か」
「これはこれは、御休息の処を恐れ入りましてござります。この度の儀に就きまして、紺青、群青、白群、朱、碧の御蔵の中の品々を先方へお遣わしになりましたこと、念のため申上げに参りました」
「おお、美人の養い親に。陸で結納といわれるものだな」
「はあ。いや、御聡明なる若様。それはちと覚え違いでございます。陸の上での結納とは親々が縁を結び、媒妁人の力を借りて婚約の祝儀、目録を贈りますもの。しかしながら、この度は美人の養い親というものが若様の御支配遊ばすわたつみの財宝に目をつけ、財宝を手に入れるために眉目容色、世に類なき美人を海底へ捧げ奉るというものでございます。養父に望みの宝を遣わしたことによって、養父は誓言の通り、美人を波に沈めましたのでござります。されば、お送り遊ばされた数の宝は、彼等が結納と申すものではなく、美人の身代というものでございます」
ゴロベエは軽く頷いた。
「それで養い親というものは、こちらから遣わした美人への身代というものを満足したであろうか」
「御意。満足いたしましたればこそ、美人を沈めました儀にござります。もっとも真鯛、鰹、真那鰹、その金銀の魚類のみで満足をせず、続いて三抱え一対の枝珊瑚を、夜の渚に置いたところ、月の光に輝くそれを抱いて白砂にひれ伏し、一命も捧げ奉ると有難がたがりましてございます」
「養父の命など冗談であろう。そんな魂を引取ると、クラゲが増えて迷惑だ」
ゴロベエの言葉に僧都、腰元たち一同は笑い声を立てた。
「しかし僧都。そんなもので満足する人間の欲は浅いものだな」
「あれは人間の中では、欲が深い方でございます。自分が育てた者を身代わりにして海の宝を望むなど、慾念がたくましいためでしょう。ただ人間は、そのようなものであろうと思います」
「馬鹿なものだ」
愚かと嘲る僧都に、ゴロベエは珊瑚が飾られた椅子から立ち上がり、同意するように笑った。
「若様に想われ遊ばした美人は、天地かけて、波かけて、お仕合せでおいで遊ばします」
「早くお着きにならないものか、私どもも待ち遠しゅうございます」
ゴロベエと僧都の話が終わったところで腰元たち間に入ってきて云う。ゴロベエは腰元たち応えて「居間の鏡を寄越せ」と命じた。
「道中の様子を見よう、旅の様子を見よう」
腰元たちは鏡に近づき、僧都も覗き込むように鏡を眺めた。
「おう。あれだ、あれだ。あの一点の光だ」
寂寞として波濤の音が聞こえる暗黒の中に花白く葉の青き蓮華燈籠が灯る。
そこに白の振袖、綾の帯、紅の長襦袢、胸に水晶の数珠をかけた美人の姿があった。
雪のごとき竜馬に乗せられた美人を囲み、ひしと守るのは黒潮騎士およそ十人。皆、槍を立て、白い穂先を光らせて、あるものは燈籠を槍に結び、あるものは手にし、あるものは腰に結んでいる。
「お疲れでございましょう。一息、お休みなさいますか」
黒潮騎士が尋ねても、美人は先ほどから一言もない虚ろな様子。
ただ何度か目の今回は、僅かな応えが返ってきた。
「・・・・・・儂の体は・・・、足を空にして倒れて落ちているのか・・・。儂は波に沈んでいっているのであろうか・・・」
「いいえ。美しいお髪一筋、風にも波にも乱れておりません。お身体が倒れているなど、どうしてそんな事がございましょう」
「・・・儂は昨夜か・・・、それとも今夜か・・・。儂は養父に薬を盛られて動けぬままに舵も櫓もない舟に乗せられ波に流された・・・。船は左に右に流れて、波に散った・・・。そして・・・あの世の蓮華燈籠が見えた・・・」
「それはあの世の蓮華燈籠ではなく、貴方様への道しるべ、また土産にもと存じたこの燈籠でございます」
黒潮騎士は美人の前に燈籠をかざして見せたが、養父に盛られたという薬のためか、美人の反応は遅く、ふた呼吸ほどの間をおいて、「なぜ波で灯りが消えずに・・・」と呟いた。
「燃えた火が消えますのは陸での事でございます。この国では風は吹かず、ただ花の香がほんのりと通うばかりでございます。燃ゆる灯もまたたきながら消えない星。貴方様のお召ものも濡れることはなく、お髪も乱れておりません」
「・・・儂は故郷の浦の近い峰で月を見たと思ったきり、引かれる船が沈んで波に落ちたはず。そのときの幻に燈籠を見て儂の身の魂を導く鬼火と思うたが・・・。・・・・・・前途に・・・、遥か下と思う処に、なぜ、月と同じ光が見えるのだろうか・・・」
「あれは月ではございません」
「・・・雲が見える、・・・空が見える・・・、瑠璃色の、そして、真白な絹糸のような光も見える・・・、ここはあの世といわれるところなのではないか・・・」
「雲は波、空は水。月と見えますのは、海の御殿でございます。私たちはあの宮殿へ、貴方様をお連れするために、お迎えに申し上げたのです」
「儂の体はどうなってしまったのだ・・・・」
虚ろな美人は黒潮騎士の言葉を理解しようとせず、黒潮騎士はその様子を見て「今は何事も申しますまい」と呟いた。
「・・・・・・あの世にはまだかかるのか」
「陸では五十三次などと申す東海道を十度ずつ、三百度往復して三千度いたすほどでございます」
「それほどに・・・」
今度は話が通じた美人であるが、その瞬間大きく身体が傾き、黒潮騎士は支えた。
「まだお薬が残っている様子。少しお休みくださいませ。黄金の欄干、白銀の波のお廊下、花の香りの中を参りますれば、やがて宮殿に到着いたします」
「・・・そこがあの世か・・・、潮風や磯の香がなく清しい、よい薫がする。・・・いや、なんであろう・・・このぞっとするような生臭い香りは・・・」
「人間の魂が貴方様を慕ってついてきているのでございます」
「・・・人間の魂・・・」
「海に参ります醜い人間の魂は、皆、クラゲになって彷徨うのでございます」
「・・・では、儂もそのうちクラゲになるのだな・・・」
美人はそう言って目をつむってしまった。寝ているように見える様子を見て黒潮騎士は無言でクラゲを追い払った。
「貴方様がクラゲになることはございません。ん? 眠ってしまわれたのであろうか」
美人を覗き込む黒潮騎士を別の黒潮騎士は急きたてた。
「とにかく急ごう。このような美しい方であれば、黒鰐や赤鮫が襲ってくる。さすれば修羅となるぞ」
「さよう、さよう」
黒潮騎士は美人を守って先を急いだ。
その頃、ゴロベエは枝珊瑚の椅子に腰かけ姿見の傍にあった。ゴロベエの斜に 僧都 と黒き珊瑚の小形なる椅子に腰かけた髯黒き博士がいて、その間に花のごとく侍女七人が立っている。
「博士、お呼立てをした」
敬礼する博士にゴロベエは、姿見の面を指した。
姿見は、一人の美人とそれを守る黒潮騎士の姿を映し出している。
「入道鰐や坊主鮫の一類たちは、美人とみれば途中を襲い美しい血を呑もうとするため守備のために黒潮騎士を附添わせた。花に露の点滴るような鮮やかな装いに月の光に包まれたような麗しき者。あれほどな美人であれば坊主鮫は髪を吸い、胸を裂いてその肉を喰らおうとするであろう」
「至極のお計らいと心得えまする」
「ところが僧都があのような迎えの仕方はかの国で罪人を捉えたときの姿に似ているため忌まわしいというのだ。美人が目を覚ましたなら、このまま市を練って引廻し、苦痛と恥を与えて刑場に送り殺されると思うであろうとな。それであれが忌まわしいものなのかと伺いたくて呼んだのだ」
「はぁ・・・、若様はいかがお考えでしょうか」
「私はいささかも不祥と思わん。槍で囲み、旗を立て、馬に乗せた姿は市を練って引廻し、苦痛と恥を与えて刑場に送るなどとは、平凡に病で死ぬより愉快なことではないのか? そえれが何の罰になるのか。それにかの者が竜馬に乗った姿は花野の行くごとく、錦の山を行くごとに、歩いたり、駕籠に乗るより、一層艶やかなものと見える。そして美人を守るは選抜された剽悍な黒潮騎士の精鋭どもであれば守られた美人は得意と思うのではないのか」
「たしかに私は地上の刑罰について一通りの記録を持っておりますが・・・、それらの記録をすべて調べることは大変に時間がかかります」
「いや、そこまではいらん。美しき者を飾りたてて馬に乗せ、槍を立てて引廻したというようなことが地上にあるのか知りたいのだ」
「若様が仰せられます通り。美人の道中の馬上の姿ですが、不祥ではあるまいと存じます。あのようなことは地上の小説や浄瑠璃などという時の人情と風俗を表すものの中のことかと思われまする
「ふむ」
ゴロベエは博士から納得のいく応えを聞いて頷き、鏡の中の美人を見た。
「ところで一つ見馴れないものが見える。胸に珠を掛けた、あれは何であろうか」
この問には博士に負けた僧都が応えた。
「若様。あれは水晶の数珠でございましょう。冥土に参る心得のため持たされたものと思われます」
「この国を冥土とは・・・・・。陸の者達のおかしなことよ。仇光りするあれはなんだろうか」
「さて・・・」
博士に負けじと応えたものの、僧都もそこまではわからない。
「あれは硝子でございましょう」
そして今度もまた、博士が応えた。
「私の恋人ともあろうものが、そのようなおかしなものを身に付けてくるものだ。金剛石、また真珠の揃うたのが良い。博士贈ってしかるべき首飾りを調べてくれぬか」
「畏まりました」
「よくみれば指環の珠の色も怪しい。お前たち、どう見たか?」
「地上ではにせが多いそうにございます」
「博士、ついでに指環を贈ろう。僧都、すぐに出向うて、途中で硝子やそのまがい珠を捨てさして参れ。老寄りに、苦労をかけてすまぬが」
「若様には美人の御到着の遅いばかり気になされて姿見の中の御馬の前に映りまする神通を忘れていらっしゃる」
ゴロベエのせっかちな命に僧都は 観念して応えた。
「ははは」
博士は去り、僧都は美人の元に向い、残った侍女達はゴロベエの前に傅いた。
「心が急いていかん―――かの者を待つ間、いかにして時を過ごそうか」
美人を待ち焦がれるゴロベエに、侍女たちも微笑んだ。
「そうだ。歌がよい。誰か、美人の住む陸の歌を知っておらんか」
「存じております。浪花津に咲くやこの花冬、今を春へと咲くやこの花・・・」
「若様、私も存じております。浅香山を・・・」
「いや、そのようなものではない。女の国の東海道、道中の唄だ。何とか云うのだったか・・・」
「十三次のでございましょう、私が少し存じております」
「おぉ、歌うてみないか」
ゴロベエに云われて侍女は「都路は五十路あまりの三つの宿、・・・・・・と歌いだした。
その時である。侍女のひとりが、きゃっと高い叫び声を上げた。
「あれをご覧くださいませ!」
「あれぇ、あれぇ、鮫が! 鮫が! 入道鮫が!」
侍女たちが鏡を見て口々に叫び声を上げるのに、ゴロベエも鏡を見た。
「何! 入道鮫だと!」
見れば、美人の周囲には三百ばかりの黒鮫が取巻き、群がっていた。黒潮騎士が美人を守っているがいかんせん黒鮫の数が多い。黒鮫は鋭い牙を振い、凶暴な尾で黒潮騎士を翻弄していた。
「おのれ! やはり美人を見逃さぬか! あの牙に喰われようものなら美人は骨も筋も断たれよう! 鎧を寄越せ!」
ゴロベエは侍女たちに命じ、侍女たちは急いで鎧の用意をした。
侍女たち二人が出て引き返し、一領の鎧をゴロベエに捧げ、背後よりさっと肩に投掛く。
ゴロベエがうなじよりつらなりたる兜には角ある毒竜という凄まじき頭を頂けば、侍女は鎧の裾をさばいて外套のごとく背に垂らした。
「あれ! 若様! あれをご覧くださいませ!」
鏡の中では目覚めた美人がなんと、黒潮騎士が手こずる黒鮫を、刀を借りてひとつ、またひとつと斬ってゆく。その姿は白い花が躍る如く優美にて、ゴロベエと侍女は美人の危急のときを忘れて、しばし麗しき姿に魅入ってしまった。
だが、黒鮫は次から次に現れて、美人に襲いかかっている。美人がいかに優れた技の持ち主であろうと、やがて黒鮫の餌食となることは明らかだった。
紫の鱗、金色の斑点連り輝く鎧姿のゴロベエは、正気に戻り、刀を抜いて頭上にかざし、窓外を睨むと刃を下に引いた。
「まぁ! 若様の御威徳により、数百の鮫が重なって、蛇か蜈蚣のように見えたのが、あのように、ちりぢりに!」
「まるでめだかのように鮫が逃げてゆきまする!」
ゴロベエは刀を鞘に納め、安堵の溜息をもらす侍女たちに命じた。
「黒潮たちが戻ってこよう。お前たちは出迎え、介抱してやれ」
「若様」
黒潮騎士の一同はゴロベエの前に槍を伏せてうずくまった。
「おお、帰ったか」
「若様のお力を持ちまして」
「何ほどのこともなし。皆、御苦労だったな」
「はっ!」
ゴロベエの言葉にますます恐縮して黒潮騎士たちは頭を下げた。
「僧都はどうしたか。途中で出会っただろう」
「我ら仲間を率いて、入道鮫を追いかけて行きました」
「ははっ! 先ほど博士を相手に悔しい思いをした僧都であれば戦闘は見物であろう―――皆、休むがよい」
なおも宮殿を守ろうとする黒潮騎士を下がらせ、ゴロベエは侍女を呼んだ。
「かの者はどうした?」
「御安心遊ばしまし。あれほどの戦闘で疵ひとつ受けていらっしゃいません」
美人は薬がまだ残っていたのか、鮫が去ると気を失い、意識の戻らぬまま、宮殿にやってきたのだった。
「ん、もうよい。お前たちも下がるがよい」
それだけいうと、ゴロベエは、侍女に見送られて奥の部屋に消えた。
カンベエは水から浮き上がるようにして目を覚ました。しかし体は動かない。目を覚ましたといってもそれは意識のことで、体はまだ寝ているようだった。
幽境を彷徨うような心地の中で、カンベエは自分の中にもうひとつ命の息吹があるのを感じた。
命を宿すことのない身のカンベエだったが、その感覚はよく知っていた。
カンベエの中にある命は熱く、固く、大きい。その命の膨らみから 悦びの さざ波が立ち体中に広がるのに、カンベエは「あぁ・・・」と歓びの溜息を洩らした。
カンベエにこの歓び与える者は、今は一人しかいない。
シチロージというその男はカンベエが戦場を共に生き抜いた男だった。シチロージは光り輝く金色の髪を 3 つの髷にするといった目立ちたがりなところがあるが顔立ちの良い男で、虜となった女も少なくない。そんな女達の中には女房と考えた女もいたらしい。しかし、カンベエと共にあるようになってからは、親兄弟でもこれほどには思われるほどにカンベエに尽くしてくれている男である。
そんな男に応える術は、カンベエにはその身を預けることくらいしか考え付かない。
脚を大きく抱え上げられ、カンベエはシチロージの名を呼ぼうとしたが、適わなかった。少しひやりとしたものが唇に触れたと思ったら、熱く柔らいものが咥内に侵入してきて占領されてしまった。舌を絡め取られ、その気持ちの良さに、んっと甘えた声を漏らすとカンベエの中のものはさらに膨れ上がった。
中をいっぱいに押し広げられる凶暴な快楽に、カンベエは嬌声を上げたが、それは咥内の熱く、柔らかいものに吸い取られてしまった。体の中で波打つ熱に翻弄され、すがるよすがを求めて彷徨う腕は、厚く躍動する筋肉に覆われた背を見つけ、カンベエはその背にすがった。
その背は広く、そして逞しい。
そこでようやくカンベエは違和感を覚えた。
シチロージの背は厚い筋肉に覆われているが、体はカンベエより頭半分小柄であった。
力の限りすがりついても、いささかの揺るぎもない広く、強靭なこの背は、カンベエに繋がっている腰の逞しさは、カンベエの中にあるものの熱さ、固さ、厖大さはシチロージのものとは異なっていた。
だか、カンベエの疑いは、すぐに頭の頂点から、指の先、足の先まで貫く快楽に押し流されてしまった。カンベエの中の熱いものは去ったかと思うと、また押し入ってくる。その度にカンベエに肉襞は震えて切なさを生むのだった。
いつの間にか解放された唇は苦しさと切なさに、高い嬌声を上げた。あまりの愉悦の波に、カンベエはぽろぽろと涙をこぼし、溺れぬよう、逞しい背にすがるばかり。
やがて体の中のものは最奥を刺し貫き、さらに熱いものを噴出した。それは無限とでもいうように何度も何度も噴出され、その度にカンベエを法悦の極みに押し流す。
カンベエは躰の水という水が、それで一杯となる幻想を見た。溢れようとする瞬間、カンベエの意識は柔らかな光に包まれ、そして途切れた。
「私の恋人がようやく目を覚ましたようだな」
「若様のご寵愛を受けられたのですから三日三晩お休み遊ばしました。目が覚めて、ひどく驚かれた様子です」
「そうであろう、よく介抱してやれ」
「二人が付き添っております。あぁ、もう廊下まで・・・」
二人の女房に付き添われてやってきたのはカンベエである。
彫りの深い、端正な顔立ちには動揺の色は見られず、廻廊を進み、床を上段に昇る裾捌きも静か。見た目は白い花のようであるが、態度はふてぶてしくもあった。
女房は、カンベエを上段にある紅珊瑚の椅子に導いた。
「お掛け遊ばしまし、カンベエ様」
カンベエは椅子に腰かけしばらく俯いていたが、やがて顔を上げて正面のゴロベエと目を合わせた。
二人は瞬きも忘れて見つめ合ったが、カンベエは俄かに目を逸らした。
「いかがされました」
「ここはあの世ではないと聞いたが・・・」
女房はすぐに事情を悟り、ゴロベエに云った。
「おお、若様。その鎧をお解き遊ばせ。せっかく、ここはあの世ではないとお話しましたものを・・・」
「解いてもよいが・・・、いや、解かずともよいであろう。・・・最初に見た目はどこまでも付き纏う。そなたはこれを恐れてはいかん。私はこれあるがために強く、これあるがために力があり威がある。またこれを使って、そなたを入道鮫から助けたのだから」
「・・・そのような鎧があるとは、ここでも戦が行われているのであろうか」
「はははは。敵のいない世界がどこにあろうか。仇は至る処に満ちている。そなたの養い親はすでにそなたの仇ではないのか」
ゴロベエの指摘にカンベエは俯いた。
「私は、この強さ、力、威あるがために敵に勝つことができる。閨にただ二人ある時でも私はこれを脱ぐまいと思う。私の心はすでにそなたを愛している。そのためこの鎧にて、敵から、仇から、世界からそなたを守護しよう。ともにこの鎧に包まるるうちはそなたもまた、ここでの王である。気ままにふるまってくれて構わない。私は鱗をもって、角をもって、爪をもって愛するそなたを守ろう」
「養父に海の幸に授けてくれたこと、儂を乗せた船を沈めた津波を起こした力、道すがら、使いの者から金剛石の首飾り、宝玉の指輪をいただいたこと、それだけで威徳はわかる」
「そなたが掛けている赤珊瑚の椅子に比べれば首飾りや珠なぞ、些細なこと」
見れば足を付けている床すらも最高級の翡翠であるろうかんの一枚岩を敷き詰めたもの。ゴロベエの鎧の竜頭は、光輝いて城にある金のしゃちほこのように見える。カンベエは首を振って周囲を見回し、顔をゴロベエに戻した。
「まさか、このような御殿がこの世にあろうとは・・・」
「そなたのいた陸にも名山、佳水、峻岳、大河があろう。それと変わらぬ」
「だが、このような御殿は見たことはない」
「そなたがあるのを知らぬのだ。宝蔵の珠玉金銀が見せる虹に更科の秋の月、錦に染まった木曾の山々が劣るものではない。峰には秋の紅葉を彩る竜田姫がおるであろう。それを人間は知らんのか、知っても知らないふりをする。陸は尊い、景色は得難い。そうそう、絵も尊い」
「絵には活きたものはおらぬ」
「いや。住居をしている。色彩は皆活きて動く。それを人は知らず、見ないのだ。美しいものは滅びない。・・・そしてそなたは美しい。だからこの国に迎えたのだ。そなたはここへ来たことを喜ばなくてはならない。嬉しいと思わなくてはならない。悲しむことなど何もないのだ」
「先ほど私もお喜ばしい、おめでたい儀と申しました。嘆くことなど何もないのです」
ゴロベエに続けて女房もカンベエの曇った顔に言い募った。
「・・・いや。こうなった以上、嘆いても、悲しんでもおらぬ。ただ儂を歎く者、悲しむ者を故郷に残しておる」
「カンベエ様。カンベエ様の姿はもう人間には見えません」
「儂はこうして生きているというのに・・・」
「竜田姫が見えぬ人間に見えるものか」
「養父にも」
「見えるものか。それにそなたの養父が悲しむ事は少しもなかろう。はじめからそのつもりで、約束の財を得た。しかも満足だと云ったのだ」
「では傍にいた、親しき者は・・・」
カンベエの瞳が揺れるのを見てゴロベエは憎々しくなって「そなたは見えると思うのか」と屹として云った。
「儂はこうして生きておる。なれば親しい者くらいには見えるのではないか」
「確かにそなたが波に沈んだのは、養父に薬を盛られたからだが、その間、親しい者とやらは何をしておったのだろうな」
「儂と共に囚われたのだろう。だから無事を確かめたいのだ」
朝な夕なに海坊主のような黒いものがやってきては養父に催促し、その度に養父に泣きつかれるのを疎んじてカンベエは情人のシチロージと共に逃れたところで囚われ、薬を盛られて船に乗せられたのだった。
「その必要はあるまい。そなたのいう親しきものとは、 3 つの髷を結った男であろう。その男ならば浜でそなたの名を呼んでいたらしいが、そなたが目覚める前に若い女が迎えにきたそうだ。それからそなたの名を呼んだことはない。これがそなたのいう親しき者というのか」
ゴロベエの言葉にカンベエは顔を曇らせ、俯いた。
「そなたを責めるつもりはない」
ゴロベエはカンベエが可愛そうになって慰めた。
「よしそれが人間の情愛なれば、それでよい。私には係わりのないこと。しかし愛するそなたが故郷を思って嘆いたり、悲しんではいけない」
「いや・・・・。嘆いても、悲しんでもいない。シチロージが、儂の名を呼んでいた男が無事であったというのならばそれでよい・・・。海の中で生きろというのであればそうしよう」
「それでよい! しおらしく、哀れな花を手折って眺めることになるかと思ったが! これからは鳥のごとく楽しく歌うがよいぞ! 誰か酒をもってこぬか」
ゴロベエの命にたちまち侍女たちがやってきて酒と白金の皿に一対の杯をもってきた。侍女はゴロベエとカンベエの前に杯をおき、両方に酒を注いた。
「お召しあがりくださいませ」
「いや、今は酒は・・・」
「カンベエ様には薄紅の桃の露、若様には菊花の雫。どちらも海では最上の飲み物です。気分が清しくなります。どうぞ召あがれ」
侍女の何度もの強い薦めに、仕方なく杯を飲み干したカンベエだったが、曇り空が晴れたように、花が蕾をつけて、大輪の花を咲かせたように、顔色を明るくした。
眉間に僅かにあった憂いも晴れて、透き通った湖面のような瞳は暗く沈んだ色から光を取り込み明るく輝いている。
「何という涼しく、爽やいだ・・・。まるで、よみがえったような気する」
「気がするのではない。儂が植えた命が、この酒によって芽生えたのだ。そなたは今、ここでの新しい生命を得たのだ」
ゴロベエの言葉にカンベエは目元を染めて睫を震わせて俯いた。男のものを深く含み悦んだ、あれは夢と思われた出来事が現実であったことがわかったのである。ゴロベエはカンベエの腕を引いて胸に抱いた。
「まぁ、睦まじい・・・」
その様子に侍女たちが小さな笑声を漏らす。カンベエはその笑い声に身の置き所がないという風に、ゴロベエの胸に顔を伏せるしかなかった。
ゴロベエは侍女を下がらせてカンベエと二人きりとなった。
「そなたは今より儂の恋人として生きてここで暮らしていくのだ」
「ここで暮らしていくのであれば儂が無事であること、皆に知らせてやりたいが・・・」
「別に見せる必要はなかろう」
「しかし養父もシチロージも、ほかの者も儂が死んだと思うているのであろう?」
「勝手に思わせておけばよいではないか。それとも帰りたいというのか、故郷へ」
「いや、儂はここにいる」
「では、なぜ知らせようとする」
「この国ではどうかは知らぬが、儂が死んだとなれば、儂を知っている者達は儂を偲ばなくてはならん。だが儂は生きている」
カンベエは地上では、死者を偲ぶ習慣があること。葬式や墓守の話をゴロベエに聞かせた。
「ふむ」
カンベエの言葉に納得したゴロベエだったが、すぐに思いなおして、「止したがよかろう」と冷ややかに云った。
「なぜだ? 儂は少しの自由も許されぬのか」
「まさか! ここは獄屋ではない。この腕から逃れること以外は大自由、大自在だ」
ゴロベエにカンベエを腕の中に閉じ込めると、カンベエの唇を吸った。カンベエもまた、目をつむって口づけを受けた。
「そなたは自由だ。だからこそ、儂の命をそなたに分け、秘蔵の酒も飲ませた。そなたが憂うものはこの国にはひとつたりと置いたりはせぬし、海の果であろうと陸の終りであろうと思って行かれないところはない。故郷ごときはただの一飛。瞬きをする間に行くことができるだろう。しかし・・・」
「しかし?」
「一生黙っているつもりであったが、そなたはすでに人間ではない」
「人間ではない?」
「美しい蛇身となっている」
ゴロベエの言葉にカンベエは目を見張った。
「儂を蛇にしたのか!」
「そうではない。そなたの身に輝く首飾りも髪飾りも指輪も人間には輝いて見えるだけ。そしてその身は人間には蛇と見えるのだ」
カンベエは信じられぬと己の手を見た。刀を使う手には肉刺こそあれ、鱗などは一切ない。
「そなたに鱗などあるはずがない。そなたは美しく可愛い恋人だ。しかし人間の目には蛇と映る。故郷を訪れてもそなたの知る者、たとえ親しい者にも大蛇として見える。ものを言えば大蛇が炎の舌を吐いたと思われ、吐息は煙が渦を巻き、悲歎の涙も硫黄となって草木を爛らす。長い袖は生臭い風を起こして木を倒し、豊かな髪は筋となって大蛇の背を覆って見えるだろう」
「そんな、馬鹿な! そんなことは信じられぬ! お前は儂が生まれ変わったといった。儂を蛇に生まれ変わらせたのであろう!」
ゴロベエを突き離し、腕から逃れたカンベエは、屹とゴロベエを睨んだ。
「そなたは人間だ! だが人間には、そなたは人間には見えぬ! そのような目をするのならば、信じられぬというのならば試してみるとよい」
「そうさせてもらう! 故郷へはどのように」
「そこに」といってゴロベエは姿見を指した。
姿見を覗いたカンベエは故郷の浜を見たと思った瞬間には、故郷の浜に立っていた。
「あれ、若様。カンベエ様はいかがなさいました」
様子を見に来た侍女にゴロベエは姿見を部屋の中央に運ぶように命じた。
「もうよいであろう。陸の様子を見てみよう」
鏡の中では一匹の大蛇が大勢に矢を射かけられていた。中でも鋭いのは 3 つの髷を結った侍であった。大蛇に矢が効かないとわかると、背から朱色の槍を取だし向って行く。大蛇はひたすらに逃げたが、 3 つの髷の侍は、大蛇の髪の一房を掴むと、大蛇の背に跳びあがり、槍を突き刺すべく振りかぶった。
そこでゴロベエが手を振ると、辺りは一瞬暗くなり、再び明るくなった部屋の姿身の傍らには床に伏せたカンベエの姿があった。
「故郷はどうであった」
ゴロベエの声に顔を上げたカンベエは涙を流してはいなかった。しかし眉に瞳にも苦悩の色は濃く、全身が悲しみに包まれていた。
「いった通りであったろう。そなたを知るある者はその姿に気絶し、ある者は矢を射かけて参ったではないか。そなたに限らず人間は私を見ても矢を射かけ、刀を振るうであろう。人間の目はそういうものだ。そんな処に用はあるまい。そなたが心痛めることはない」
だがカンベエはゴロベエの話など聞かぬとばかりに背を向けた。
すかさず侍女がカンベエに駆け寄る。
「カンベエ様。若様は悲しむことがお嫌いです。御機嫌に障るようなことをなさってはいけません。この国は、楽しむ処、歌う処、舞う処、喜び、遊ぶ処ですよ」
「・・・・・・」
「そなたに矢をいかけ、槍を突こうとしたあんな故郷に何の未練がある。さあ、機嫌を直せ。この国では悲哀は許さんぞ」
「許さぬというのなら、どうにでもするがよい。どうせ儂の身体はそなたの魔法なのであろう」
ふてくされたようい云うカンベエにゴロベエは忿怒の顔となった。
「どこまで疑うというのだ。そなたを蛇体と思うのは、人間の目だと云うておろう! それを魔法とは許さん! 悲しむことも許さん! そなたが悲しむのは、そなたの親しき者が槍で突こうとしたからであろう! なおのこと、許さん!」
「許さぬというなら、どうだというのだ? どうぜ、そなたの魔法によってできた身体、殺したいなら殺せばよい!」
言葉の勢いはどちらも収拾がつかず、侍女たちはゴロベエとカンベエの間で右往左往するばかりだった。
「黒潮騎士はおらぬか! カンベエを処置せよ!」
「若様!」
黒潮騎士はカンベエを引き立てて錨に縛り付けると、乱れる髪を掴んで喉を晒し、刃を突きつけた。その様子に侍女たちは叫び声をあげる。
「あぁ、若様!」
「床を血で汚されますのか!」
「美しい男だ。花を毟るのと同じ。花びらがばらばらになるだけのこと。その後は手箱にでもしまっておこう」
「どうせなら、ゴロベエ。そなたの手で儂を殺すがよい」
刃を突き尽きられてなお不敵なカンベエに、ゴロベエはつかつかと寄り、ためらわずに刀を抜き、そして二人は見つめ合った。
「儂はあれで故郷も何もかも忘れた。さぁ、ゴロベエ、殺すがよい」
微笑むカンベエはまさに花のようで、ゴロベエは無言でカンベエを見詰めた。
そうして二人はしばらく見つめ合い、しばらくしてゴロベエは「解け」と黒潮騎士に命じて、カンベエの戒めと解かせた。
カンベエを錨より降ろすと黒潮騎士はするすると後ろに下がりやがていなくなった。侍女たちもまたいつの間にか姿を消して、ゴロベエとカンベエの二人ばかりである。
「こちらにおいで」
カンベエは素直にゴロベエの手を取りゴロベエに抱き寄せられた。
「終生を誓おうぞ、カンベエ。腕を出すがよい」
ゴロベエはカンベエの手首を取って刃を引くと、そこから紅血が滴り落ちた。ゴロベエは刀を返して自らの腕を引くとそこからは紫の血が滴った。
「呑もう」
盃を交わして互いの血を飲みあうと、姿身の中に映るカンベエの故郷の浦の磯に、岩に、紫と紅の花が咲いた。
「あれは一体なんであろうか。誰か、博士を呼べ!」
ゴロベエの命に博士が呼ばれて姿見を覗き込んだ。
「博士、あの花は一体になんだ?」
「あれは竜胆と撫子でございます。若様とカンベエ様のお心が通いまして、折からの霜に、一際色が冴えました。若様とカンベエ様の血の俤にございます」
「人間にそれが分るか」
「心ないものには知れますまい。しかし詩人か、画家か、認めるものもありますでしょう」
「カンベエ、これで私の悪意ある呪詛などではないことがわかったであろう」
「ん。見捨てることのないように、幾久しく頼む」
ゴロベエがカンベエの手を携えて進むと、美しき花が降り、待った。さらに歩いていくと音楽が聞こえてくる。
「ここは極楽か?」
「そんなところと一緒にされてたまるものか。ここはそなたと私の国ぞ」
終わり
やりたかったことなので、すっきり。
カンベエの変わり身の早さにあきれるばかりですが、原作の通り。
原作の美女もかなりなにです。
ゴロベエの一人称をどうしようかと悩んだのですが、王様みたいなものですから、それが「某」というのはどうだろうということで「私」にしております。