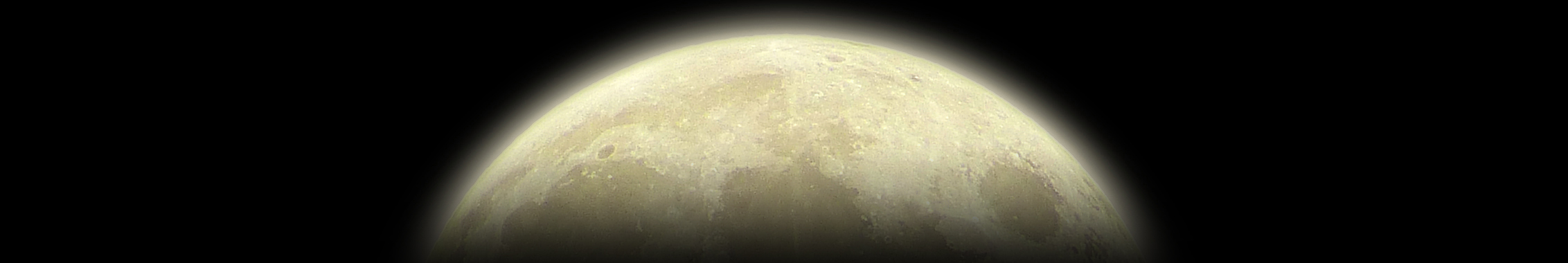こちらはオフ本『白詰草』のその後の話になります
『白詰草』あらすじ
長く続いた戦によりいつしか武家の力は衰え、逆に戦によって巨万の富を得て力をつけた商人達は都を組成し、戦を終結させます。
そして武家の中でも突出した戦闘能力を誇る侍は、戦災の恨みを受け、ほとんどが自然の厳しい北の地に封じられます。
北軍の侍が一人、島田カンベエもまた軍師の身分から裁きを受けることになり、処分が決まるまでの間、ほかの侍たちと共にある武家に預けられます。
しかし、武家の中には侍に対して妬みを持つ者も少なくなく、侍達は責め殺され、カンベエもまた 凌辱され殺されるところでしたが、運よく大野セイザエモンという商人に助けられます。
以後、カンベエは大野屋に雇われ、蓄電筒の輸送隊の護衛として働くようになりますが、一方で大野屋の商いのため、商人達の相手もさせられます。
カンベエの心臓には、大野屋に雇われるにあたり、侍の力を恐れる都によって機械が埋め込まれており、セイザエモンの側を離れることはできませんでした。
終戦間際の戦でカンベエと離ればなれになったシチロージは大戦から 5 年後に、救命艇で眠っているところを虹雅峡の色町、癒しの里にある蛍屋の女将・ユキノに助けられますが、左腕と宙にいたときの記憶を失くしていました。
ユキノと割りない仲となり、幇間として蛍屋で暮らし始めるシチロージですが、あるとき蛍屋で行われた商人達の宴席で、護衛の中にカンベエを見かけて思い出せない記憶の中の何かに突き動かされカンベエを追いかけます。しかし寸でのところが逃してしまいます。
それからシチロージはカンベエを探しますが、どこの誰とも、行方も知れず、月日ばかりが過ぎていきます。
そんな二人がいろいろあって再会してカンナ村の百姓に雇われ野伏せりを退治。
カンナ村の戦、都との戦を通じてカンベエは、ずっとシチロージは記憶を失っていると思い続け、戦が終わると蛍屋に帰るようにシチロージを説得しますがシチロージは聞き分けず、諍いに。
しかしある雪の日。カンベエの手の六花の入れ墨が、六花の花ではなく、実は雪の形を模したモノだというシチロージに記憶が戻っていることを悟り、カンベエは張りつめていたものが切れたように、シチロージの胸に崩れるのでした・・・・・・
オフ本『白詰草』はこんな感じの話です。
『白詰草』では都との戦の後、カンベエとシチロージは、大野セイザエモンがカンベエに残した別荘に移動しています。
障子を開けたとたん、吹き寄せてきた冷気にカンベエは肌を粟立てた。障子も硝子戸も開け放たれた部屋の中はすっかり冷え切っている。それは内縁に座り込んで空を眺めている男の仕業に違いなかった。シチロージは、振り向くことなく空を見上げていた。朝から厚い雲が垂れこめていたが男の背超しに見える空は低い灰色の雲に覆われて、そこから白いもの落ち舞っている。
「雪か・・・」
北方と区別されるこのあたりの冬は早く、年の瀬前に気温が零下になることがある。ただ雨が少ない地ゆえ、雪は滅多に降らない。辺りはすっかり新雪で白く染められており、珍しさにカンベエは魅入った。
そのとき、一陣の風が吹き、縁側まで雪が舞い込んできた。縁側に落ちた雪はすでに外気と変わらぬ部屋の中ではすぐには溶けない。カンベエは雪が落ちた縁側が濡れて色が濃くなっているのを見咎めて眉をしかめた。
一向に振り向かない頑ななシチロージの背にカンベエはぼんやりと思った。
―――やはり、連れてくるのではなかった、か・・・
昨夜、カンベエはシチロージと言い争いをした。虹雅峡に帰れというカンベエに、シチロージは帰らないと言い張り、物別れとなったのだった。
都との戦でシチロージは足に傷を負い、その傷は軽くはなかった。カンベエも大きな傷こそなかったが疲れていて、カンナ村の村人の歓迎もあり、シチロージの傷が塞がるまで厄介になろうと考えていたのである。だが、そこに式杜人から迎えがきた。
歩くのもままならないシチロージを村において行くわけにもいかず、カンベエは式杜人に頼み、シチロージを虹雅峡に戻そうとしたのである。しかし、ユキノの迷惑になる、面倒をかけるのが嫌だというシチロージの言い分もわからなくもなく、セイザエモンがカンベエに残した別荘に連れてきたのである。
―――シチロージの傷は、儂が戦に連れ出したため・・・
建前はそうであったが、本当のところは別れたらもう二度と会うこともなかろう、という気持ちの方が強かった。
シチロージの傷は太腿の銃創で、運よく骨も太い血管も反れて貫通しており、ゆっくり養生していればよいものである。カンベエはシチロージの世話をしながら乞われて、記憶がないという宙での戦のことを語った。そして、シチロージが歩けるようになったのを見て、虹雅峡に帰るように言ったのだった。
吹く風の中に冬の気配が色濃く感じるようになり年の瀬も近い。ユキノ殿も心配していよう、新しい年は夫婦ともに迎えるがよいというカンベエの話を、最初、シチロージは大人しく聞いていたのである。だがカンベエ様はこれからどうされるのですか、というシチロージの問いに言葉を濁した辺りからシチロージが愚図りだした。カンベエは苦笑して、当分は式杜人の仕事を手伝うことになろう、その後はわからぬが何とかなろうと説いたが、シチロージはカンベエの説明に逆に納得できないようだった。「式杜人がそれほど信用もおける者たちですか」はその通りのことだが、それが高じて「このままカンベエ様と一緒に」などと言うシチロージに、カンベエは思わず「虹雅峡に帰れ!」と怒鳴ってしまったのだった。
―――目の前にいる男はこの身を預けた男ではない
わかっていても、昔と変わらぬ顔と声で昔と同じ言葉を言われると心が揺れる。怒声に顔色ひとつ変えないシチロージも小憎らしかった。結局、「帰れ」「帰らない」の言い合いとなり、そうなれば説得もない。カンベエは己の下手を思いながらシチロージをおいて部屋を出て行ったのだった。
それからシチロージとは顔を合わせてはいない。
朝は台所に立ってみたものの、飯を炊く気にもならず、餅を焼いて食べ部屋に籠ってしまった。
カンベエの部屋の文机の周りにはセイザエモンが急死して大野屋を畳んだときに、運び込まれた大野屋の大帳類や式杜人分限帳、蓄電筒の開発の記録がある。カンベエはこの別荘に隠れ住んでいた頃からこつこつと目を通していたのだった。文机の上には証書などの類の書類があった。セイザエモンは、この別荘をはじめとして、土地や金などかなりのものをカンベエに残していて、それはいずれ整理をしなくてはならないものだった。式杜人がカンナ村に迎えに来たとき、別荘に戻ることにしたのはそれらのことがあったためである。
書物を開いたものの考えるのはシチロージの頑なさであった。
―――傍らに美しく優しい女がいて、命のやり取りのない、穏やかな日々を送ることができるというのに、一体、何の不満があろう・・・・
一晩経った今は怒りよりもやるせない気持が強い。
考えに沈んでいたカンベエだったが、ふと、別荘内のあまりの静けさに不審を覚えた。別荘とはセイザエモンの言い様であって、実際には小さな庵である。部屋数は三つほどしかなく、人がいれば何かしら物音もする。
―――シチロージは出かけているのか?
耳を澄ましても周囲からは物音ひとつ聞こえない。あまりの静けさに耐え兼ねるようにカンベエは部屋を出て、廊下を渡ったところにある部屋の障子を勢いよく開けた。
―――古傷のある身に寒さは堪える。
どうやら長い間そうしているらしいシチロージを咎めようとカンベエは部屋の中に入ったが、シチロージが漏らした言葉に部屋の半ばで足を止めた。シチロージは吹き込んできた新雪を機械の方の、左腕で受け止めて眺めていた。
「左腕に雪が落ちると、雪の形がよくわかります。カンベエ様の左手の入れ墨と同じ・・・」
カンベエの左手には六花の入れ墨がある。カンベエが宙に上がった頃、部隊ごとに入れ墨を入れるのが流行り、入れたものだった。
入れ墨を見た者の大抵は六弁の花だと思い、カンベエもそれをいちいち正したことはない。だが、入れ墨は実は六弁の花ではなく、部隊が創設された地に由来している。豪雪地だったことから、雪の結晶から考えられたものだった。それを知っているのは限られている。シチロージの言葉に、カンベエは色を失った。
「・・・・・・シチロージ、そなた記憶が・・・」
「記憶なんざ、とっくのとうの昔に戻っていますよ」
「なっ・・・! しかし、ユキノ殿は、そなたは宙での記憶を失くしていると・・・」
「ユキノにはいってないですからね」
カンベエの驚愕をよそに、ユキノにはばれていたような気もしますけどね、とシチロージが鷹揚なくいう。そのシチロージの丸まった背を見ながら、カンベエは憤りとも怒りともいえるものが湧き上がるのを感じた。シチロージが生きていたと喜んだのもつかの間。記憶を失っていると聞いたときの、喪失感は大きかった。シチロージとユキノは幸せそうに見えた。すべてを忘れ、幸せに暮らしているのなら、それでよいと断ち切った情もある。それがどうだ。
―――記憶が戻っていただとっ!
さすがに腹が立ち、カンベエは声を荒らげた。
「なぜ、黙っていたのだっ! 言う機会はいくらでもあったであろうっ!」
「カンベエ様のせいですよ」
「なにっ?!」
まさかそのような返しがあるとは思わず、カンベエは声を荒らげた。
「ほかの者に心寄せてらっしゃるカンベエ様に、昔のことを持ち出してどうするっていうんです? カンベエ様、蛍屋でユキノがアタシの記憶がないといったとき、ほっとなされたでしょう」
「それはっ・・・」
シチロージに乞われるまま大戦時のことを話し聞かせたが、大戦後については詳しく語ったことはない。まして終戦時に預けられた先で凌辱されたこと、大野屋で商売相手に身を開いていたことなど話せることではなかった。だからシチロージの記憶がないと聞いたとき、詳しく話す必要はないと安心したのは事実だった。
「カンベエ様、ときどき左胸に手を当てていること、気づいていらっしゃいますか? カンベエ様の胸の痣は、大野屋に雇われた印だそうですね」
カンベエの左胸には 4 つ葉の白詰草のような痣がある。それは大野屋に雇われるにあたって都に機械を埋められた手術の痕だった。無意識のうちに左胸に手をやってしまうのは、ここに機械が埋められていると信じていたときの癖のようなものだった。
「ヘイさんに聞きました。大野屋の主人でしたね、カンベエ様の雇い主は。カンベエ様をそりゃあ、大事にしていたそうですね」
「・・・・・・」
先ほどまでの怒りは霧散し、カンベエは沈黙した。細かい事情を何も知らないヘイハチから見ればセイザエモンがカンベエを囲っているようにも見えたことだろう。
「 4 年くらい前になりますか。その頃はまだ記憶があいまいだったのですが、蛍屋でカンベエ様を見かけたことがあるんですよ。ウキョウからカンベエ様を庇うように立っていた商人、あれが大野屋の主人でしょう」
カンベエの姿に、懐かしさ、切なさ、いろいろな感情が噴き出し、追いかけたものの、追いつくことができなかった。苦い記憶を思い出にシチロージの口調の中には棘が混じっていた。
そのときのことはカンベエもよく憶えている。シチロージが蛍屋にいるかもしれないと探しに行きたくても、セイザエモンの側を離れるわけにもいかず、庭に降りて蛍を見ていたところをウキョウに見咎められたのだった。
「それからずいぶん経って、カンベエ様の名前を知って、それですべてを思い出したんですよ。それが、大野屋が潰れてカンベエ様が生きているはずはないって!」
そのときの絶望を思い出し、シチロージは声を荒らげた。
「・・・・・・、ですが・・・、こうして再びお逢いすることができた。カンベエ様がなんといおうと、アタシはもうカンベエ様と離れる気はありません」
カンベエ様が生きていないと聞いたとき、アタシがどんなに・・・、と恨みを呟くシチロージの言葉を聞きながら、カンベエはその場に崩れてしまった。何か、張っていた糸のようなものが切れてしまった気がする。体から力が抜けてとても立っていることができなかった。
「カンベエさまっ!?」
シチロージは崩れたカンベエにぎょっとして慌てて駆け寄った。肩を抱きカンベエの上半身を起こす。シチロージを見上げる色の薄い瞳は、湖面のように静かに、だが微かに揺れていた。
「カンベエ様・・・」
「・・・シチロージ」
今のこの気持ちをどういったらいいのか、話したいことは山ほどある。だがどこから話せばいいのか、どれを話せばいいのかわからず、その代わりにカンベエはシチロージの胸に顔を埋め、すがるように薄紫の襦袢の衿を掴んだ。
驚き戸惑うのも一瞬。シチロージは顔を歪めてカンベエを抱きしめた。カンベエの髪の中に顔を埋め腕に力を込める。胸が痛み、喉がひくつき、鼻の奥が痛かった。
「カンベエ様っ」
苦しいくらいに抱かれたカンベエもまた、溢れるものを捕まえるようにシチロージの背に腕を回した。
「・・・シチ・・・」
小さな嗚咽を聞きながら、カンベエも目を閉じた。
どのくらいそうしていたのか。カンベエは、シチロージの体に妙な熱があるのに気づいて目を開いた。長い時間、外気に晒されていたらしいシチロージの、カンベエの背を抱く機械の腕は氷のように冷たい。だというのに、布地を通して伝わるシチロージの体は熱かった。
「シチロージ?」
シチロージの腕は強くカンベエの躰を抱いていたが、胸を押すと、あっさりと放すことができた。その胸は忙しない呼吸に上下している。
「シチロージっ! 熱が・・・」
シチロージの頬は赤らみ、潤んだ瞳はよく焦点を結んでいなかった。
「・・・くそっ・・・、ようやくカンベエ様が・・・」
ぐらりと揺れた体をカンベエは抱き留めた
「シチっ!」
「・・・・・・申し訳、・・・ありません、カンベエさ、ま・・・」
それからシチロージは高熱を発し、熱が下がった後も左腕の痛みにより体が思うようにならず、さらに半月ほど寝込むことになった。
土地が隆起してできたという岩山の頂上、朱槍を振るう男の姿がある。
「ふっ!」
シチロージは一回転しながら下から掬い上げるように槍を振り上げ、目の前の巨岩に向けて槍を振り下ろすと、額ほど距離で刃先をピタリと止めた。一呼吸おいて槍を引く。大きく息を吐いたシチロージの肩からは湯気があがっていた。
朝から空を覆っていた厚い雲は、とうとう白いものを零し始めていた。息を整えつつ舞い落ちる雪を眺めていたシチロージはおもむろに上を向いて大きく口を開けて舌を出した。だが雪はシチロージを避けるように落ちていく。それでもしばらく口を開けていたシチロージだが、雪は本降りになりそうな雰囲気である。
「いけねぇ、また冷やしちまう」
シチロージは顔を戻すといけねぇ、いけねぇと繰り返し、岩から岩へ跳んだ。途中、まるで岩から生えているように、岩と岩の隙間に根を張ったアカマツにひっかけていた上着を槍尻でと取り上げ纏う。シチロージがこの地に来て 2 度目の雪だった。シチロージは岩場を跳ぶようにして駆けた。
都との戦で負った傷が完治していなかったことやら、ろくに調整もせずに機械の左腕に無理をさせたことやら、そこに体を冷やしたことやらが重なって、シチロージが発熱して寝込んでいたのはひと月ほど前のことだった。
この辺りは武家であった式杜人の領地の飛び地らしいが、商業街道からも外れているため戦中に人が住まなくなったという。そのような土地だが、大野セイザエモンは蓄電筒の事故により汚染された領地の代わりと考えていたらしく、だからこそ別荘を建て、ときどき利用していたらしい。そのため別荘の中は不自由なく暮らすための設備が整っていた。火を熾すにも、飯を炊くのも、風呂を沸かすのも、洗濯するのも機械を使って行うことができ、二人ならば数カ月は困らないほどの蓄食料の備もあった。ただし備蓄食料は日持ちのする乾物が多く、種類も少ない。そのため山の向こう側に住んでいる老夫婦が週に一度、新鮮な野菜などを運んできてくれる。
そんな別荘だが病を得たときには不便極まりない。別荘には大戦中も使われていた抗生物質をはじめあらゆる薬が常備されていたが、医者を呼ぶには山を越えて老夫婦にところに行き、式杜人につなぎをとらなくてはならなかった。小型艇を使えば、老夫婦のところまで半刻もかからないが、あいにく小型艇はカンベエが虹雅峡に行くために使ってそのままだった。おかげでシチロージが倒れ、カンベエは医者を呼ぶのに老夫婦のところに走らざるを得なかったのである。
シチロージの様子がただの発熱ではないと看取ってすぐに医者を呼んだカンベエの判断は正しく、シチロージは感染症を起こしていた。一番の原因は都の戦で負った太股の銃傷だが、ろくに調整をせずに左腕に無理を強いてきたことやカンベエと諍いをして体を冷やしたのも良くなかった。老夫婦のところに駆ける前にカンベエが 抗生物質を投与してくれていたおかげで、医者がやってきた頃には熱は下がり始めていたものの、負荷がかかっていた左腕の生身と機械の接合部分はひどい炎症を起こしていて、激痛のため起き上がることができなかった。式杜人だという初老の医者の手当により、左腕の炎症が治まって、体を動かせるようになったのは十日ほど前のことである。それからシチロージは、寝たきりで落ちてしまった筋力を取り戻すべく、岩場を駆け、槍を振るっていた。
―――そろそろカンベエ様と立ち合うこともできるのでは・・・
と思うほどに、筋力は戻ってきている。体の復調に合わせて気持ちも上向いてくるようだった。
シチロージが稽古をするようになると、カンベエも再び部屋に籠って式杜人の分限帳などを読み解くようになった。料理の腕はシチロージよりカンベエの方は確かだった。そのため飯炊き以外の家事をシチロージが行い、女中などを雇う必要もなく、文字通り二人きりで過ごしている。
朝と夕方には向かい合わせで膳を前にして、山間に日が落ちる夕暮れを共に眺めて冬の日の短さを思うこともあれば、冴え冴えとする満月を見上げることもある。出会ってから、これほど穏やかな日を過ごしたことはあるだろうかという、なんとも言えない、くすぐったいような日々を過ごしているのだった。おかげで、シチロージはカンベエにはまだ触れていなかった。触れるきっかけを作り損ねている。
数え切れぬほどに肌を合わせ、カンベエの熱に包まれた記憶は、救命艇から目覚めてからしばらく記憶をなくしていたこともあろう、シチロージにとってはまだ克明だった。体に力が戻れば当然ながら欲もでてくる。 10 年の時を経てもシチロージの記憶と変わらぬカンベエが目の前にいれば手を伸ばして肩を抱き、口を吸い、その肌を貪りながら、繋がりたいとは思う。
大戦中は明日をも知れぬ命と思い、共にいられる時間を無駄にすまいと、刹那に駆られてずいぶんと無茶をしたこともある。優れた体格を持ち、体術もよくするカンベエが本気で抗えば二人の交わりは成立しないから、カンベエも同じような心持だったのだろう。はじめは抗ってもカンベエは最後にはシチロージを許し、受け入れてくれた。
だがそれは戦場という場所ゆえことだった、ということをシチロージは完全には否定できない。下手をして、またカンベエに虹雅峡に帰れといわれるのも勘弁なら、言い争いをもしたくはなかった。
カンベエに記憶が戻っていると告げたあの日、熱で倒れてしまったことがつくづく悔やまれる。
―――あのままカンベエ様に触れていれば・・・
シチロージの思考の行きつく先といえば、いつもそこだった。
「おやっ?」
別荘に戻ったシチロージは横づけされた小型艇を見咎めた。
「カンベエ様、ただいま戻りました」
案の定、部屋の中にカンベエと向かい合わせでいたのはソウベエで、シチロージは部屋の中に入ると軽く頭を下げた。ソウベエは手広く商い行っている商人だが、式杜人の一人である。カンナ村、都の戦で武器を提供する代わりに、都を討つことをカンベエに持ちかけたのもソウベエだった。
そのソウベエの横には大きな男がいた。肩幅といい、座高の高さといい、肩の肉の盛り上がりといい、胸の厚さといい、カンベエも大概に大兵だが、そのカンベエよりも一回り大きい。毛深い質らしく、膝においた手も毛深く、着物の袷からはふさふさとした胸毛が覗いていた。だが、その巨体に乗っている顔はひどく若い。釣り合いが取れない様子に思わずシチロージはじっと見詰めてしまった。若者は不躾な視線に顔をそむけたが、その様子も子供が拗ねているようである。小さく笑いそうになったシチロージだったが、振り返った人物に思わず声を上げた。
「よぉ、シチさん」
「誰かと思えば、マサムネのおやっさんっ!」
振り返った男は虹雅峡で屑鉄屋ならぬ、鍛冶屋をやっているマサムネであった。見た目はしょぼくれた親爺であり、実際、屑鉄に囲まれて暮らしている変わり者だが、腕は一級であった。シチロージの左腕もマサムネにつけてもらったものである。
「おやっさん、なんだってここに?」
「儂がソウベエ殿に頼んだ。そなたの左腕は特注ものゆえ、施術した技士に調整してもらうのが一番良いと若松殿に聞いたのでな」
「カンベエ様・・・」
若松殿というのは先日来、シチロージが厄介になっている医者である。
「じゃあ、シチさん、早速だが腕を診ようか」
マサムネはそう言ってカンベエにうなずいた。どうやらだいぶ待たせたようで、その間にすっかり打ち解けた様子である。
「ここに原動機があるだろう? 神経から脳に伝わる電流を感知して動くんだが、この腕にゃ電流を感知する端子が、普通の義手の倍以上ある。だから、生身の腕とほとんど変わりなく扱える」
カンベエに見せるように言うマサムネの言葉にシチロージは頷いた。慣れた今では左手に不便を感じたことはない。
「その分、負担も大きい。この腕は侍のシチさんだから使うことができるシロモンだ。だが、いくら強靭な体を持つ侍だって限度はある。使い過ぎれば支障も出てくる。シチさん、頭痛とかあったんたんじゃねぇのかい?」
マサムネの言葉に動揺して見詰めてくるカンベエにシチロージは慌てて否定した。
「一晩寝ちまえば何とかなったくらいのモンですよ。でなければ、あれだけ働けやしませんて」
大したことではないと言うシチロージをカンベエは疑わしい目で見詰めたが、マサムネの邪魔になると思ったのか、何も言わなかった。
「医者の腕が良かったようだな。接合部は問題ない。中の部品も、・・・交換の必要はない」
マサムネの太鼓判でカンベエは眉間の緊張を解いた。式杜人の医者の腕を疑ってはいなかったが、腕の施術から調整まで、これまですべて厄介になっていたマサムネの言葉にシチロージも安堵の吐息をつく。
「戦するなら、ちょくちょく調整をした方がいいぜ、シチさん」
「あぁ」
マサムネの言葉にシチロージは苦笑した。蛍屋の女将の情夫に機械の腕の調整が必要になるはずがない。そもそも戦ができるこの機械の腕をシチロージにつけたのもマサムネだった。変わり者だが腕のよいこの親父は、独特の嗅覚を持って救いようのない、侍の性をシチロージから感じ取ったに違いない。
―――つまり、そうゆうことだ・・・
と心打ちでつぶやいてシチロージはカンベエを見詰めたがそれとなく視線をそらされてしまった。っそこにシチロージがマサムネに腕を見てもらっている間、外していたソウベエと若者が戻ってきた。
「カンベエさん、食いモンは台所に運んでおいた。あと倉庫にあったモン、もらっていくよ」
「ソウベエ殿、かたじけない」
「倉庫のモンって、あれですか?」
「ん。ソウベエ殿に話をしたら、式杜人が使うというのでな」
大野セイザエモンが死に、カンベエがこの別荘に隠れ住んだ時、ヘイハチが一緒で別荘の中の機械に興味を示して暇があれば工作をしていたらしい。それらはカンベエ達には使いようがなく、倉庫で埃を被っていたのだが、式杜人にはそうではないらしい。
「カンベエさん。こいつのことなんだが」
シチロージが入れなおした茶をがぶりとうまそうに飲んだソウベエは顎で隣の若者を示した。
「さっきの話だが、しばらくこいつを預かってもらえないかい? そっちの兄さんの体慣らしにでも使ってやってくれ」
「ん、部屋がひとつ余っておる。シチロージ、よいな?」
「は?」
シチロージは思わず素っ頓狂な声を上げた。よいなといわれてもシチロージには訳が分からない。いない間に出来上がっているらしい話の説明を求めてカンベエを見詰めたが、応えたのはソウベエだった。
「こいつはウチの若いモンなんだが、ちょっとばかり刀が使えるものだから、勘違いして村を飛び出してきた」
俺は侍だ! という斜め後ろからの声をソウベエはまったく無視した。つい最近、聞いたような台詞である。チロージは「はぁ」と気の抜けた返事をした。
「十になった途端、三つ上の幼馴染の娘との悪戯を始めとして村の女の三分の一はこいつと一度はことに遊んどる。そんな奴だから、村から飛び出してきたのはいい。商隊の護衛で働かせてやるのもいいが、勘違いしたままってのはまずい。それでカンベエさんに、ちっとばかり高くなった鼻をへし折ってもらえないかと頼んでいたんだ」
シチロージはすかさず心打ちで「そんな奴はいりません」と叫んだが、カンベエに聞こえるはずもない。結局、シンジロウとかいう若者を預かることになってしまい、用事は済んだと、ソウベエとマサムネは帰ってしまった。
―――カンベエ様はやっぱり・・・
アタシを虹雅峡に帰そうとしているのか、とシチロージはひとりになり布団の中で一人ごちた。
ふたりで穏やかな日々を過ごすことが存外に楽しく嬉しいものだと、その気持ちを共有していると思っていたシチロージには、カンベエがシンジロウを簡単に受け入れたのに裏切られた気分でいた。本人を連れてきている以上、ソウベエに押し切られるのは仕方がないにしても、カンベエに困惑する気配もなく、むしろシンジロウを気にかけている様子なのがシチロージの気持ちを泡立たせている。
あのシンジロウという奴と一緒に体よく追い払うつもりではないか。ともすればそんな風にも勘ぐってしまう。このまま傍らにいることを許してもらえると思っていたが甘かったようだ、と寝返りを打ちながらシチロージは考えた。
虹雅峡に戻れというというのが自分のことを思ってだということはシチロージもわかっている。だが、シチロージはすでにカンベエとともに行くことを決めてしまっている。本当に望むことを曲げて生きることが幸せだとは思えない。その結果、野垂れ死になったとしてもそれはカンベエのせいではない。
今年で 18 歳になるというシンジロウは、ずっと式杜人の隠里に育っただけに、いかにも無鉄砲で恐れ知らずである。そのくせ素直な一面も見えてからかいがいがあるというのがシチロージの印象だった。ソウベエが懸念するのも無理はない、と思う。小生意気な小僧を叩きのめすのはそれなりに楽しいが、今は邪魔であった。
―――大体、何だってソウベエは、よくカンベエ様を訪ねてくるんだ? その度に菓子やら書物やらカンベエ様のご機嫌を伺いやがって・・・
シチロージの左腕を診るためにソウベエがマサムネを連れてきたことや、それをカンベエが頼んだことなどをすっかり忘れシチロージは腹を立てた。考えつく限りの悪態をつく。一通り悪態をついて少し気が晴れたような気がした。
―――こうなれば、泣きが入るまで、シゴいてやる
やつあたりという結論に達したシチロージは、すっきりして体の向きを直し、やがて安らかな寝息をたて始めた。
カンベエは小さな吐息をつくと、書物を閉じて布団に突っ伏した。枕を抱えて寝ながら書物を読んでいたため、上半身が固まってしまっている。あおむけになり、んっ唸り声をあげて体を伸ばした。雪は周囲をすっかり白く染めて日が暮れる頃に止んだ。雪が周囲の音を吸収してしまうのか、いつもよりあたりが静まり返っているように思われる。その静けさの中にときおり聞こえる唸り声だか、叫び声だかはシンジロウだった。
ソウベエに押し切られた形とはいえ、カンベエがシンジロウを預かることにしたことがシチロージのカンに触ったのだろうということは承知している。カンベエもシチロージと穏やかな日々を過ごすのは初めてのことで、心地よくは感じていたが、諍いになったことを忘れてはいない。それをあやふやなままで、二人の間に他の人間を入れるというのは結論の先送り、もしくはごまかしとシチロージに思われても仕方のないことだった。
実際、カンベエはまだシチロージのことを考えあぐねている。
カンベエがシチロージと出会ったのは宙で、カンベエが知るシチロージというのはまさしく侍であった。しかし、その宙のときの記憶を失い、待っている女がいるのであれば、シチロージは虹雅峡に帰るべきだ。カンベエはそう思っていた。記憶を失くしているのであれば、侍を捨て、別の生き方ができるはずだと、女と夫婦となり、子供を作り、家族となって穏やかな暮らしを営むことができるはずだと。しかし、シチロージは記憶を取り戻していた。侍のシチロージに侍以外の生き方をすることができるか、と考えるとそこで思考が止まってしまう。
カンベエには侍以外の生き方をすることができない。カンベエにとって生きるということが侍であることだからである。儂よりもシチロージはずっとい来るのか器用―――と思っても自分にできないことをシチロージにしろとは言いずらい。実際、シチロージは侍として生きることを望んでいるのである。
だからといって、共に行こうと言いきれないところもある。シチロージのいう「カンベエ様のそばに」という言葉の中には「昔のように」という気持ちが隠れているからだ。
大戦中、シチロージは情人でもあった。 5 年前に目覚め、そして記憶を失くしていたシチロージにとっては大戦時のことをつい昨日のことのように考えるのだろう。だが戦が終わってカンベエには 10 年経っている。記憶が思い出になるには十分な時間だった。まして、この 10 年、己の望まないところで体を開かされてきたため、情交に醒め切っているといってもよい。
情があったといえるのは脇坂タケアキくらいである。だがタケアキはセイザエモンと同じく不能であり、カンベエの中に穿つことはできなかった。それが逆に強く記憶に残ることとなっている。
シンジロウはその 脇坂タケアキの甥であった。
脇坂タケアキも式杜人の一人で幼少時から大野セイザエモンに仕え、大戦中にはセイザエモンと共に参戦している。セイザエモンが大野屋を興してからは、蓄電筒の護衛としてセイザエモンに仕えた。セイザエモンが死んだ後は、遺言に従って大野屋を畳み、カンベエをこの別荘に隠し、そしてある日、この別荘から姿を消して、そのまま戻ってくることはなかった。
タケアキがウキョウを討ち損じて命を落としたとソウベエに聞いたのはしばらく経ってからである。その報を聞き、カンベエは虹雅峡に向かい、シチロージと再会した。
長く傍にいながらタケアキが己のことを話したことはなく、カンベエは何とはなしに天涯孤独な身の上と思っていたから、シンジロウを紹介されたときはずいぶん驚いた。タケアキはカンベエよりもさらに一回り以上大きい巨体で、シンジロウもまた背丈もあり肩幅も大きい。しかし凡庸な顔つきだったタケアキに比べて、シンジロウは顔立ちがはっきりしている。だが、血の繋がりというものか、シンジロウがタケアキの姉の子、甥と聞かされ、カンベエはなんの疑問を感じることはなかった。
これからのことに考えるべきなのだが、とりとめのない考えが浮かんでは消え、浮かんでは消えていく。そうしているうちにカンベエは布団の温かさに誘われ、眠りに落ちていった。
「ほら、どうした! その程度かっ!」
「ちくしょうっ!」
渾身の一撃を簡単に弾かれ転がったシンジロウは、岩の上で自分を見下すシチロージに顔を真っ赤にして悪態をついた。
シンジロウは最初、カンベエに立ち合いを申し込んだのである。しかし、「ふざけんな、馬鹿」の一言と共に頭上から槍が降ってきた。あまりの衝撃に座り込み、目の前に瞬く星を、頭を振って散らせると、そこには槍を肩にかけたシチロージがいたのだった。
「アタシに 1 本だって打ち込むこともできないくせに、カンベエ様がお前の相手なんてするか、阿呆」
「誰が、アホウだっ!」
「じゃ、間抜け」
「ふんぬーーー!!」
今日で 3 日目。ジンジロウはシチロージと立ち合っているが、軽くあしらわれては転がされ、痣を増やしている。
岩場から立ち上がったシンジロウは憤然としてシチロージに向かっていった。しかし数十回の打ち込みをすべてあしらわれ、さすがに肩を揺らしてぜーぜーと荒い息を吐いた。シンジロウの刀は重く、長い。それだけ振り回すには腕力が必要である。とうとう腕力の方が尽きたのか、シンジロウはだらりと両腕を垂らした。
シチロージはその姿にふっと口の端で笑った。一見、力を抜いた姿だが、シンジロウが気を練っているのがわかる。シンジロウの剣は確かに力任せのものだが、下半身が強いのだろう、足運びは確かだった。そして踏み込みの迅さはシチロージをして目を見張るものがあった。
力尽きた様子で誘い、槍を繰り出す瞬間を狙って懐に入り、最後の一刀を放つ。シンジロウの思惑を承知で、シチロージは槍を繰り出した。案の定、シンジロウが踏み込んできたところをシチロージは後ろに飛んでかわし、シンジロウよりさらに低く身を伏せると、槍の長さを変えて逆に踏み込んでいった。そして踏み込んできた太腿を狙って槍を突き出す。仕掛け槍の刃は、当然、仕舞ってある。
「ぎゃっ!!」
突かれた太腿の痛みにシンジロウは足を抱えて蹲った。それでもうなり声を上げ、歯を食いしばりシチロージを見上げる、その意地っ張りな様子にシチロージは笑った。
「今日はここまでだな。歩けるか?」
助けようと近づいたシチロージの手をシンジロウは払った。笑われたのがよほど腹に据えたのか、顔を真っ赤にして刀を杖にして一人で立ち上がったが、すぐによろける。
「骨はやっちゃいないはずだから、歩けなくはないか。また雪になりそうだ。帰るぞ」
軽快に岩から飛び降りたシチロージは後ろを振り返った。シンジロウは這うようにして岩を降りていく。しかし途中で手が滑らし、転がりながら落ちてきた。
「っ~~~~!!」
「あーあ、手間がかかるな、坊主」
「誰がっ・・・、坊主だっ!」
「一人で歩けないんだ、坊主だろうが」
「歩けるっ!」
「無理だな、お前を一人で置いてきたリしたら、アタシがカンベエ様に叱られる」
シチロージはシンジロウの右腕を肩にかけると、痛みに唸り、悪態を付くシンジロウを無視してどんどん歩き出した。
別荘は風呂を沸かすのもすべて機械まかせで、湯殿は手足がゆっくりと伸ばせるほど大きい。シチロージは左腕を縁にかけ、たっぷりの湯に浸かって極楽気分でいた。そこに喧しい足音が、と思ったら、はたしてシンジロウであった。
「こらっ! 足を打っているから風呂はやめとけっていっただろう」
「わかってるよっ! でも、カンベエが水をかぶるのやめとけっていうから、いてぇ!」
湯船から出たシチロージはシンジロウの頭の天辺にげんこつを落とした。
「カンベエ様だ、湯をかぶるだけにしとけよ、湯船には入るな」
言い返してくるかと思えばシンジロウはシチロージの腕に息を詰めていた。
「それ・・・」
「何だい、アタシの機械の腕はいつも見ているだろう」
「俺の村には機械の腕や足を使っている奴はいなかったんだ。そんな風になってるのか・・・」
シチロージの左腕は生身の部分に機械が食い込むような形で接続されており、あまり気味が良いとはいえない。
「その足・・・」
足の銃創を見咎め、傷跡の生生しさに息を飲むシンジロウに、改めてこいつは戦を知らない、とシチロージは苦笑して風呂から上がった。水をもらいに台所に行くと、甘い香りが漂っていた。
「おや、よい匂いが・・・」
白玉を茹ででいたカンベエは、手元を覗き込んできたシチロージに隣の鍋の蓋を開けてみせた。途端、喜色を浮かべるシチロージにカンベエは小さく笑った。酒はうわばみ、その上シチロージは甘い物も好物である。
「ソウベエ殿が持ってきた食料の中に小豆と白玉粉、砂糖がたっぷりあったのでな」
「どうりで・・・」
シチロージが入っている風呂にシンジロウがやってきたのはこの甘い香りに我慢ができなくなったに違いない。
シンジロウが 5 杯、シチロージが 3 杯、カンベエは 1 杯の白玉善哉を食べて鍋は空になった。食べている間はさっぱり気にならなかったようだが、シンジロウの太腿は腫れあがって一回り大きくなっている。
「今日は熱が出るかもしれんな。体の打ち身もひどい。 2 、 3 日休むことだ。」
「あのオヤジ、手加減って知らねえ」
布団の上にシンジロウを下したカンベエはその言葉に、クッ、クッと喉を鳴らして笑った。
「何だよっ!」
「儂はずいぶんシチロージが手加減していると思っておったが」
「これでか!?」
「太腿を打たれるとしばらく立てなくなる。そなたを休めるため打った傷。シチが本気で打ったなら、それくらいではすまん」
カンベエの言葉にシンジロウはウーと唸った。手加減されていることが悔しく、不本意なのである。
「そこは急所のひとつ。傷つければ敵は出血多量で死んでいく。戦場のやり方だ」
カンベエはシンジロウの傷をポンと叩いた。
「イテェ!」
痛みに蹲るシンジロウを見詰めてカンベエは立ち上がった。
「・・ま、待てよ! いや、待ってください」
「なんだ?」
「オヤジ、・・・じゃないカンベエ、さま。あのおっさん、もしかし強いのか?」
あのおっさんとはシチロージのことである。 10 代のシンジロウからしてみれば無理からぬ言い様ではあるが、カンベエは内心おかしかった。
「儂でも数本に一度、いや・・・、 3 本に一度は取られるか・・・」
顎鬚を撫でながら言うカンベエに、シンジロウは「あんな役者みたいなおっさんが、まじかよ・・・」と、蒼然として呟く。その様子にカンベエは小さく笑った。
「カンベエ様もいかがですか?」
「もらおう」
甘党のシチロージも善哉 3 杯の甘味は過ぎたのか、盆の上には湯呑と一緒に漬物鉢があった。
「シンジロウはどうだ?」
「迅いですよ。踏み込みが鋭い。ときどき、ひやっとさせられます。しかし無駄が多すぎる」
「ふむ」
タケアキも迅かった。とカンベエは心内でひとりごちた。甥のシンジロウはその血を継いでいるのであろう。剣の速さは確かに大事である。だが、重要なのは間合いと呼吸であった。それを会得するには、経験が必要となる。
「シチロージ、腕の方はどうだ?」
腕の慣らしにと、すっかりシンジロウのことは任せきりにしている。カンベエは気遣わし気にシチロージを見詰めた。
「調整を行わずとも大事ないのか?」
「この程度では。遊んでいるようなものですから」
シチロージはカンベエににっこりと笑ったが、じっと見つめるカンベエの瞳に目が離せなくなってしまった。
「カンベエ様・・・・・・」
つ、と膝を詰めたシチロージだったが、建物を揺るがすような振動に、一瞬でカンベエとともに部屋を出た。
「シンジロウ・・・」
「・・・・・・何をやってるんだ、お前は」
見れば、廊下で派手に転んだらしいシンジロウがうつ伏せで倒れていた。
「しょ・・・ションベン・・・・」
「あー! わかった、わかったっ! 連れていってやるっ!」
「ちょっ! おいっ! おっさんっ!」
シチロージはシンジロウの無事な方の足首を掴むと、そのままずるずる引きずっていった。その様子をカンベエは呆れて見送った。
よほど頑丈にできているのか、単に鈍いのか。シンジロウは熱を出すこともなく、 2 日ほど大人しくしていて足の腫れが引くと、すぐさまシチロージに立ち合いを求め、そして転がされた。
「お前も懲りないねぇ・・・。ころころ、ころころ転がって、趣味か」
「んなわけ、あるかーー!!」
ぜーぜーと肩で息をしながら刀を横に払ったシンジロウだったが、またもやあっさりシチロージに躱され、ついでに槍尻で突かれて、またも後ろに倒れてごろりと転がった。
「・・・ちょくしょうっ、いつになったらカンベエにぃっ・・・・、っってーーー!!」
「トリ頭。何べん殴られたら口の聞き方を覚えるんだ? 『カンベエ様』だろうが。アタシに一太刀つけることもできないというのに、カンベエ様がお前の相手などするか」
頬を腫らせて不貞腐れるシンジロウにシチロージは呆れた。
「そんなにカンベエ様と立ち合いたいのか?」
「・・・・・・・・・」
「真面目な話だが、カンベエ様に教えを乞いたいっていうなら、やめといた方がいいぞ。必ずしも練者が名指南じゃないっていってな・・・」
「・・・そんなんじゃねえや」
「じゃあ、なんだよ」
「・・・・・・、叔父さんのこと、聞きたくって・・・」
「叔父さん?」
「母ちゃんの弟。若いときに村を出てって戦にも出たって」
「へぇ・・・」
もとは武士である式杜人であるから、戦働きをした者がいても不思議はない。
「あいつが・・・、島田カンベエのせいで、叔父さんは死んだんだっ!」
「なんだと?」
「誰がそのようなことを?」
シチロージに首根っこ掴まれて別荘に戻ったシンジロウは、カンベエの前で、ぼそぼそとシチロージにいった言葉を繰り返した。
「誰って・・・」
シンジロウの斜め後ろに座ったシチロージがシンジロウを叩こうとするのを制してカンベエは尋ねた。
「タケアキがそう言っていたのか」
シンジロウは首を振ると、観念したようにぽつぽつと語りだした。
「・・・・・・あんたのことは叔父さんから聞いた。叔父さんは、あんたに仕えてたんだろ?」
顔を上げてジンジロウはカンベエをじっと見詰めた。
「叔父さんがウキョウとかいう奴を討ちに行ったっていうのは、あんたがやれっていったんじゃないのか?」
「それを確かめにここに来たのか」
シンジロウは首を横に振った。
「俺は侍になりたくて、村を出たんだ。だけどちょっと喧嘩しちまって・・・。ソウベエのじいさんが牢屋から出してくれたんだけど、そんなに侍になりたいなら本当の侍を見せてやるっていわれて・・・。それで、ここに来た」
「そうしたら、儂がいたというわけか」
コクリと頷くシンジロウにカンベエはふむ、と一呼吸おいて尋ねた。
「なぜ儂がタケアキにウキョウを討てと命じなければならん」
「え? ウキョウって奴は都の天主なんだろ? 都をやったのだって、都が戦の始末を全部侍におっかぶせたもんだから、それを侍が恨んでやったって、みんな言ってるぜ」
「みんなとは?」
「え? みんなっていったら、みんなだろ。街じゃ、そう言ってだぜ」
シンジロウの言葉にカンベエは腕を組み、瞑目した。考え込むカンベエが理解できずシンジロウが振り向いたが、シチロージは肩をすくめて応えた。
「儂はウキョウや都を敵とは思ったことはない。ウキョウを討ち、都を墜としたのは、仕事のうち。儂は仕事をしただけのこと。それ以上でもそれ以下でもない」
「へ!?」
ようやく目を開いたカンベエの言葉はシンジロウには意外だったらしく、素っ頓狂な声を上げた。
「儂の中に都を恨む気持ちはない。すべての侍が、とはいえぬが、ほか侍達もそうではないのか」
「でも、侍だけ割りを食って・・・」
「戦とはそうしたもの。負けた者が責を負うことになっている。・・・あの戦で、侍は自ら戦をやめたのだ。都にふいを打たれて総崩れになっていたとはいえ、宙にはまだ生身の侍が 1 万近くいた。大きな犠牲はでただろうが、都との一戦、できなかったわけではない。実際、都と一戦交えようとする者もいた。だが、多くの者は刀を納め、都に下った」
「なんでだ? やればよかったじゃないか。侍は戦艦だって斬ることができるんだろ? 勝ったかもしれないじゃないか」
「戦が長く続きすぎていたのだ。その結果、大地や民たちがどうなったか。手柄を侍たちに独占させまいと、武士たちは次々に巨大な機械の侍になっていった。二度と生身の姿に戻れないというのにだ。誰にも戦を止めることはできなかった。それを都が、商人たちが終わらせたのだ」
カンベエの言葉にシチロージは膝に目を落とした。そんなシチロージをちらと見て、カンベエは、都の裁きはけして一方的なものばかりでなかった、と話しを続けた。
「・・・・・じゃあ、・・・じゃあ、なんで叔父さんはウキョウなんか・・・」
「第一にタケアキが儂に仕えていたというのが違う。タケアキは儂に仕えていたのではない。タケアキが仕えていたのは、大野セイザエモンという大野屋の主人だ。儂はセイザエモン殿に雇われた侍にすぎぬ」
「えっ! 商人っ?」
「セイザエモン殿のこと、知らぬのか?」
シンジロウは頷き、膝に目を落とした。
「俺・・・、叔父さんのこと、よくは知らないんだ。俺だけじゃなくて母ちゃんも。・・叔父さんは十四のときに村を出て、それから一度も村に帰ってこなかったのに、戦が終わった頃からときどき帰ってくるようになったって。でも帰ってきてもあんまり話さなかった。村のモンと会うとかもなかった。ただときどき、カンベエ様っていう侍のことを話してくれたから、その侍に仕えてるんだろうと思ってた」
シンジロウは上目使いでカンベエを見た。
「俺は叔父さんに剣を教わった。・・・俺が侍になりたいと思ったのも叔父さんから剣を教わったからだ」
カンベエはシンジロウからタケアキが若くして村を出たという話を聞き、その理由が朧げにわかるような気がした。多感な時期に肉体の、男としての不具が心にどのように影響を与えたのか想像に難くない。
「教えてくれ、叔父さんは何をしていたんだ、どうして死んだんだ?」
それはともかく、シンジロウは何も知らないようである。じっとカンベエを見詰める瞳は納得を見るまでは引きそうにもなかった。シンジロウの斜め後ろにいるシチロージにしてもカンベエの口から直接、戦後のことを聞くのは初めてのことゆえ、身を乗り出すようにしている。カンベエはシンジロウとシチロージを交互に見て何を、どこまで話すべきかを考えつつ口を開いた。
「タケアキが仕えていたのは、大野屋の主人、大野セイザエモン。そなたと同じ、式杜人だ」
「え? 式杜人? 式杜人がなんで・・・」
戸惑うシンジロウにカンベエはセイザエモンが式杜人であることを隠して商人となり、大野屋という大店を構えていたこと。そして商いの利益で式杜人を裏から支えていたことを話した。
「大野屋は主に蓄電筒の商いしていた。蓄電筒は野伏せりが狙うところ。儂は大野屋の護衛として雇われ、タケアキと共に働いていた」
「へー、じゃあ、北からやってきたのか?」
いいや、と否定するカンベエにシンジロウは首を傾げた。シチロージも同様である。戦の咎を受けて侍は北方の僻地に封じられている。カンベエもそこで大野屋に雇われたのだろうと今まで思っていたのである。
「え? だって侍は・・・」
「商人に雇われた侍はほかにもいるが、皆、商人に命を救われた者たちだ。儂もそうだった。儂は大戦中、軍師をしていたため処分を受けることになっていた。処分が決まるまでの間、武家にお預けになっていたところをセイザエモン殿に助け出された」
終戦時のカンベエの身分は 一小隊長に過ぎなかったが、作戦立案の能力が認められ軍師の称号をもっていた。シチロージはそれが処分の対象になったという理由を聞き、衝撃を受けた。今までもカンベエと再会できたことを幸運と思っていたが、だがそれは本当に紙一重のものだったと知らされる。
「だが都は侍の力を恐れた。超人的なその力が自分たちに向かうことをな。そのため、都は処分される侍たちを救い、枷を課した 」
「枷?」
カンベエはそっと左胸をおさえた。
「侍の命をいつでも断てるよう、ここに機械を埋めたのだ」
「!」
「!」
「処分を受けるか、商人の下で働くか。侍たちは商人に雇われることを選んだ。儂もそうして大野屋に雇われた」
「・・・やっぱり、都は侍の敵なんじゃないのかよ」
膝の上で拳を握りしめ、怒りに震えるシチロージに語りかけるようにして、カンベエは話を続けた。
「儂が都であっても枷もなく侍を使うことはしないであろうな。だが・・・、侍と雇い主の商人は必ずしも冷たい間柄というわけではなかった」
「え?」
「雇い主の商人と心通い、護衛として働くことに満足していた者も多い。野伏せりの襲撃で命を落とした侍もいたが、丁重に弔われ、その家の者たちと一緒の墓に入れられたと聞いた。儂も・・・、セイザエモン殿には大きな恩を受けておる。機械は雇い主が死んだ場合にも作動するようになっていたため、セイザエモン殿が死んだとき、当然、儂の心臓も止まるはずだった。しかし儂の心臓が止まることはなかった」
「機械が故障したのか?」
「いや。セイザエモン殿が都の技師たちを買収して、機械を埋めさせなかったらしい。セイザエモン殿が病死した後、タケアキから聞かされた。儂が生きていることが都に知れてはまずいため、ここで隠れていたのだが、タケアキも一緒だった」
「! ここに叔父さんがいたのか」
「タケアキは大野屋を畳んだ後、店で働いていた者たちの世話もしていて、出かけていることが多かった。そのため儂はソウベエ殿に聞くまで、タケアキがウキョウを討ちにいったこと、全く知らなかった」
「・・・・・・・・・」
「タケアキは、セイザエモン殿が亡くなった後、大野屋を畳み、店で働いていた者たちの暮らしが立つように、すべての始末を一人で行った。それはすべてセイザエモン殿の遺言によるものらしい」
「じゃあ、叔父さんがウキョウを討ちにいったのは、そのセイザエモンっていう人の遺言だったから・・・。」
「さて。そこはわからん。ただ、セイザエモン殿とタケアキは戦場で苦楽を共にした仲だと聞いた。戦場で共に戦き、生きて帰ってきた同士というのは、格別なものだ。そしてタケアキはずっとセイザエモン殿ただ一人に仕えてきたのだ」
じっと見詰めてくるシチロージをカンベエもまた見詰めた。
「共に働いていたとき、大野屋の商いが第一のタケアキに腹を立てたこともある。だが・・・、タケアキには世話になった。大野屋の護衛の者たちに一人の死者も出さすにすんだのは、タケアキの助けがあったからだ」
語り終え、カンベエはほっとした想いを抱いた。嘘は言ってはいない。だがすべてを語ってもいない。しかし、口にしたことでそれがまるで真実であるような、そんな心持だった。そして、それでよいとも思った。いろいろあったが、それをすべて明らかにしたところで誰の得になることでもない。今、こうして、生きていることこそが大事なことだった。
今一つ釈然としない、しかし何がわからないのか分明できないといった様子のシンジロウにカンベエは内心、苦笑した。戦をしたことがないシンジロウには、戦場を共に駆けた同士の濃密な関係は理解が難しいだろう。カンベエはシンジロウからシチロージに視線を移した。
「シチロージ」
「はっ」
「今日は体を動かし足りぬのではないか?」
「え? えぇ、・・・まぁ」
「久しぶりに、どうだ?」
「!」
シチロージは目を見開いたが、すぐに不敵な顔になって「願ってもない」と返した。
いきなりな展開にシンジロウはわけがわからないといった様子でカンベエとシチロージを交互に見た。
大戦時の軍服に似た出で立ちのカンベエと向かい合わせとなったシチロージは、カンベエの姿をしみじみと目詰めた。
カンベエの立ち姿は美しい。今の目の前にいるカンベエはシチロージの記憶にある姿と何ら変わりはなかった。力を抜いて悠然と見える姿は、どこからでも打ち込みが出来そうに見えて実際はできない。踏み込めば、一瞬のうちに間合いを詰められ打ち込まれる。
この立ち合いでカンベエが何か答えを出そうとしているのをシチロージは感じていた。答えを出さなくてはならないことといえばひとつしかない。きっかけは初めて戦後のことについて初めて口を開いたことだろう。だが、そんなことはどうでもよかった。所詮は侍同士。話し合いなどでカタを付けるよりも、この方が似つかわしかった。
カンベエがどう答えを出すかはもちろん気がかりではあるが、それも体の中から湧き上がる闘牙が強くなるにつれてどうでもよくなっていく。カンベエとシチロージの立ち合いが見たいと、少し離れたところシンジロウが見詰めていたが、それもどうでもよかった。
―――これだから侍はしようのない・・・
戦がどんなに罪かを知っていても、戦うことをやめることができない。逆に喜びを感じてしまう。
向かい合うカンベエからも青白い炎のような、冴え冴えとした闘気が立ち上るのを感じる。カンベエもまたシチロージと同じであるに違いなかった。カンベエがゆっくりと刀を抜き、中段に構えるのに、シチロージもまた仕掛け槍の伸ばし、肩幅に足を開くと腰を落として構えた。
「カンベエ様、よろしいでしょうか?」
「ん・・・」
カンベエの部屋の障子を開けたシチロージは促され部屋の中に入った。カンベエは丁度書き物をしていて、振り向くと「少し待て」といってまた文机に向かった。シチロージは未だカンベエとの距離感を測り兼ね、距離をおいて障子の近くで膝を折った。カンベエの背を覆う髪を何となしに眺め、部屋の中を眺め、この部屋に入ったときから目を惹いていたものに目を留める。カンベエの部屋は寝支度が出来ていて、枕元には小さな行灯と煙草盆が置かれ、香も焚かれていた。カンベエにとっては、意味はないのかもしれないが、シチロージには違う。意識して仕方がない。
「すまなかった、シチロージ。シンジロウの様子はいかがであった?」
いつの間にか書き物を終えて振り返っているカンベエにはっとしてシチロージは応えた。
「うんうん唸ってはおりましたが眠っておりました。熱もないようで。まったく、頑丈な奴ですよ」
「そうか、よかった」
小さく笑うカンベエにシチロージも苦笑した。
カンベエとシチロージの立ち合いは決着がつかなかった。場所を変えながら刀と槍を交わしていたが、十数手を交わしたところであろうか。互いに超振動を放ち、それぞれに躱したとき、轟音と叫び声にカンベエとシチロージは刃を引いた。互いに放った超振動が岩山を崩し、シンジロウが崩れた岩の下敷きになったのである。立ち合いを上からよく見ようと思ったのか、カンベエとシチロージも立ち合いが白熱するあまり、岩場にシンジロウがいることに全く気が付かなかった。助け出したシンジロウは意識はあったが、全身を強く打って立ち上がることもできなかった。別荘に戻り、手当をしながら骨をやってはいない様子に安堵したが、体中いたるところで痣ができ、内出血をおこしていた。その体に薬を塗り、興奮覚めやらぬシンジロウに薬を飲ませて先ほどようやく眠らせることができたのだった。
「だが、明日は念のため医者を頼み、そしてシンジロウをソウベエ殿のところに帰そう」
カンベエの言葉にシチロージは頷いた。もとより追い出すつもりで扱いていたのだ。しかし、いざ出ていかせるとなると、少しばかり残念な気持ちがあった。
「シチは傷の手当はしたか」
「かすり傷です。もう塞がっておりますよ」
カンベエの刀を躱しきれずに負った右腕の傷は塞がり、風呂で多少ぴりと痛んだ程度である。無言で立ち上がったカンベエは、たばこ盆の引き出しから傷薬を取り出すと、シチロージと膝が触れる距離にやってきた。
「カンベエ様は?」
カンベエの右腕の肘にもシチロージに穂先に掠られた傷がある。
「儂はすませた」
カンベエの言葉にシチロージは素直に袖をまくって腕を見せた。シチロージのいう通り、傷は赤い筋となっているだけだったが、カンベエはそこに丁寧に傷薬を塗った。
「シチロージ」
まくった袖を治そうとする機械の腕をカンベエに掴まれ、シチロージはカンベエを見詰めた。機械の腕にはもとより触覚も、そして痛覚もない。しかし掴まれた拍子に腕が動いたことによって接合部がその感覚を感じ取り、まるで腕があるように錯覚させてくれる。
「シチロージ、腕は大事ないか」
気遣わし気なカンベエに、シチロージは安心させるように小さく微笑んだ。
「何ともありません。カンナ村や都との戦の後、確かに頭痛はありました。ですが、僅かなもので、本当に、一晩寝れば治る程度のものだったんですよ」
本当ですよ、というシチロージに応えず、カンベエは機械の腕に目を落とした。カンベエが意識してシチロージの機械の腕に触れるのは初めてのことだった。表面は滑らかだがよく見ると擦れたような傷があり、撫でると微妙な凹みもあった。思ったほど冷たくもなく、それが不思議で顔を上げると、間近に淡い水色の瞳があった。唇に温かいものが触れてすぐに離れていく。見詰めてくる水色の瞳は戦場では酷薄といわれていたが、カンベエが生まれたところにはシチロージのような瞳を持つ者はおらず、いつも美しいと思っていた。その瞳が、今はひどく切実な色をたたえている。再び唇に温かいものが触れてきたとき、カンベエは逃げなかった。
褥に横たわる一糸纏わぬカンベエの、鍛え抜かれて均整の取れた体をシチロージは惚れ惚れと見下ろしてゆっくりと体を重ねていった。立ち合いの余韻が残っていたためだろう。僅かな前戯に二人ともすっかり昂っている。その昂ったものを擦り合わされ、カンベエは小さな嬌声とも吐息ともつかぬものを漏らした。腰から生まれた快楽の波が波紋のように全身に広がっていく。
「っ・・・、・・・んっ、・・・、・・・っ、・・・っ、・・・シチッ、・・・」
望まぬ情交では体は熱くなっても、頭の隅の一片はひどく冷めきっていた。ところがどうだ。シチロージから与えられた熱は、体ばかりか頭の中まで溶かしていくようだった。
「・・・・・・カンベエ様」
シチロージと繋がるための場所に香油を塗りこめられ、ほぐされるがもどかしい。両足を抱えられてシチロージの熱いものが入口に押し当てられたときには、カンベエは安堵の吐息を漏らした。内臓を押し上げられるような挿入の感覚は確かに苦しい。だが、その苦しさこそほしいものだった。すべてを含むと、カンベエは再びシチロージを得た想いに腕を回して背を抱いた。
「シチロージ・・・」
「カンベエ様っ!、 カンベエ様っ」
カンベエに包まれたシチロージは、記憶にあるよりも強烈な快楽に、すぐにも爆ぜてしまいそうなのを動きを止め、額に汗して耐えた。カンベエの中はシチロージのものをみっしりと包み込み、さらに奥へと誘っている。抱きしめた体はどこにも女のような柔らかいところはない。胸や太腿は肉づいていても、握れば確かな感触を伝える弾力のあるもので、間違いなく男の体だった。しかし、その男の体がシチロージを熱く、燃え立たせる。正しくは、カンベエだからシチロージは昂る。
腰を使うと、カンベエの唇から小さな嬌声が漏れた。己のものでカンベエが悦んでいることを感じてシチロージのさらに昂り、さらに激しく腰を使い快楽を追った。
「シチっ・・・・、っ」
「カンベエ様っ!」
カンベエの中で極めたシチロージは、カンベエの首筋、髪の毛の中に鼻を埋めた。小さな嗚咽が漏れる、震える体をカンベエはきつく抱きしめた。
翌日、早々にシチロージはシンジロウを山向こうの式杜人のところに送って行き、昼過ぎには戻ってきた。シンジロウを送るにあたっては一騒動があって、カンベエとシチロージの立ち合いを見たシンジロウは、すっかりカンベエに心酔して手をついて弟子入りを願ったのだった。傍若無人な振る舞いを改めて深々と頭を下げるシンジロウにカンベエは呆気にとられ、シチロージはこめかみに青筋を浮かせた。大きな体を畳んでどうか、どうかと縋りつかんばかりのシンジロウは、何とかしてやりたいと思わせる健気さがある。だが、カンベエはカツシロウで懲りていた。
「そなたはソウベエ殿からの預かりもの。ソウベエ殿に伺いもなく、儂のところに置くことはできぬ」
「では、ソウベエのさんの許可をもらったら、お仕えしてもよいでしょうか?」
「熱は出なかったようだが、体中、相当に傷むのであろう。まず傷を治すことだ」
そしてシチロージは離れがたいといった様子のシンジロウの尻を叩き、輸送機代わりにとソウベエが置いて行った鋼筒にシンジロウを乗せて老夫婦のところに向かったのだった。
「ごくろうだった、シチロージ」
「シンジロウのあの調子じゃ、すぐに戻ってきますよ、カンベエ様」
どうされるおつもりです? という意味を込めて流し目をくれるシチロージに、カンベエは「しばし待て」と応えると、再び文机に向かい筆を走らせ、文に封をしてから振り返った。
「シチロージ、昨夜のことだが・・・」
「はっ」
昨夜のこと、とは、情交の後の寝物語りのことであるとシチロージはすぐに察した。体の始末をした後も離れがたく、カンベエとシチロージは昨夜、共寝をした。そして眠りに落ちるまでの間、いろいろな話をした。その中で北方に封じられている侍たちの話におよび、部隊の者たちが生きていることをシチロージは知ったのだった。そしてあのときカンベエが何と言ったのかも覚えている。
「いつか北方へ行ってみたい」
カンベエはそう行ったのだった。
「今の季節は難しいかもしれん。だが、だからこそ訪ねることができるかもしれん」
カンベエは文机から一冊の冊子と地図を取り出し、シチロージに示した。大野セイザエモンが残した北方の資料である。侍が封じられている場所についてはほとんど知られていない。しかし大野屋は北方から鉄鉱石など鉱物資源の買い付けを行っていた。資料には城壁都市とその場所、城壁への入り方などが詳細に記載されていた。
「カンベエ様、これは・・・」
驚くシチロージにカンベエは頷いた。なるほど、これなら侍を封じることができる、とシチロージは合点し、地図を読んだ。軍師であったカンベエはもとより、斬艦刀乗りであったシチロージも地形を読むのに長けている。城塞都市は山岳部にあり、そこに行くまでもいくつか冬山を越えていかなくてはならない。都はなくなったが、警戒は解かれていないだろう。城塞都市に入るにも厄介そうだった。それでも行けないことはない。都合がよいことに別荘には鋼筒がある。見つからずに行くには丁度良かった。
「カンベエ様・・・」
「よい機会だと思わぬか?」
シチロージは力強く頷いた。シンジロウには可哀そうだが、カンベエが言葉をうまくして何一つ約束をしていなかったのを知っている。
「面倒なことになるかもしれんがな」
ソウベエがこの別荘にときどき訪ねてくるのは、式杜人の戦力として取り込みたいということもあろうが、北方の侍たちとの繋ぎとして使いたいのだろうとカンベエは考えている。侍は世間から未だ恐れられるだけでなく、シンジロウの話からするに都や商人に恨みを持って騒乱を起こす一派といわれているようである。
侍が再び世に出るためには式杜人の力が思わせるために・・・。
というのは想像の域を話だが、あながち誤りではないだろうとカンベエは思っている。そんな式杜人のソウベエはカンナ村に迎えを寄越すくらいに、カンベエを警戒している。北方行は何らかの作用をもたらすことは考えられた。
「カンベエ様、参りましょう。皆のところに」
そう言って笑うシチロージに昔からこの目の前の男に背中を押されて来たことをカンベエは思い出した。そして今も背中を押されている。
「シチロージ」
「お供しますよ。どこまでだって」
真摯なシチロージの言葉に、カンベエはただ、頷いた。
終劇