|
成年禮、婚禮、喪禮、祭禮に代表される・・・
韓国の伝統的冠婚喪祭
  |
|
成年禮、婚禮、喪禮、祭禮に代表される・・・
韓国の伝統的冠婚喪祭
  |
|
韓国の[관혼상제]は、漢字で(冠婚葬祭)ではなく、(冠婚喪祭)と書く。
いうまでもなく、관례(成年の禮)、혼례(婚禮)、상례(喪禮)、そして제례(祭禮)の4つの禮を言う。 韓国の[관혼상제](冠婚喪祭)は、日本のそれと比べて、より儒教の色彩が色濃く残っている。もちろん、伝統的な儀式と比較すると、大分現代的な合理化が進んではいるものの、それでも日本とは比較にならないほど、儒教的である。 「儒教的」という意味で、もっとも顕著な部分は、やはり先祖に対する尊敬・感謝の念が強く現れている点であろう。 それぞれの儀式は、地方により、家庭により、独自のしきたりや考え方があり、同じ韓国の中でも、千差万別である。先祖に対する祀りごと、と言う意味では、共通しているものの、その手順や、やり方は必ずしも同一ではないようだ。 韓国でも核家族化が進み、子供たちが故郷を離れ都会に生活するようになると、家族意識にも次第に変化がみられるようになり、儀式の内容が簡略化の傾向にあることは否めない。 したがって、このページでは、できるだけ、伝統的な儀式と現代的な儀式とを対比して述べてみたいと思う。 しかし、いくら簡略化されていくとはいえ、根底に流れている先祖への恩、尊敬、感謝の気持ちが、儀式に反映されていることは忘れてはならない。 それでこそ、韓国の儀式のもつ意味合いが、過去・現代を問わず、理解することができるのではないかと考える。 |
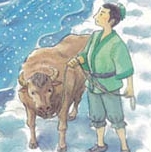
성년의례(成年の禮)

성년의례(成年の禮)は[成人式]である。現在は、男女とも満20才になると、成人として認められ、陽暦で5月の第3月曜日にお祝いが行われる。
韓国では、高麗時代の昔から、15~20才で成人として認められる儀式が行われてきた。これが、성년의례(成年の禮)の原点である。 この성년의례(成年の禮)は、男性の儀式は관례(クワルレ:冠禮)と呼ばれ、女性の儀式は계례(ケレ:筓禮)と呼ばれる。 男性は、髪の毛を上の方にまとめて상투(サントゥ)を結い上げ、その上に관모(冠帽)と呼ばれる帽子(写真 下左)をかぶって、관례(冠禮)の儀式に臨む。(写真 右) 
 一方、女性は髪に비녀(ピニョ:笄)と呼ばれる簪(かんざし)(写真 左右)をさしてまとめあげ、계례(筓禮)という儀式に臨む。(写真 右)
一方、女性は髪に비녀(ピニョ:笄)と呼ばれる簪(かんざし)(写真 左右)をさしてまとめあげ、계례(筓禮)という儀式に臨む。(写真 右)しかし、現在では、このような伝統的な관례(冠禮)、계례(筓禮)による성년의례(成年の禮)が行われる光景はほとんど見られなくなったようである。 地方の一部では、未だ、行われているところもあるようであるが、大部分は、公式の祝賀行事もなく、家族や親しい友人たちなどと、お祝いして過ごすそうである。 |

혼례(婚禮)
[伝統的な結婚式]
혼례(婚禮)とは言うまでもなく「結婚の儀」のことである。しかし、単に男女の個人的な儀式というより、儒教の影響を色濃く受けた家族の結びつきに力点をおいた儀式が営まれてきた。そのため、両家にとって非常に重く受け止められた荘厳な儀式である。
現在ではほとんど見受けることのできない伝統的な韓国の혼례(婚禮)の扉を開いてみたい。 ①의혼(ウィホン:議婚) 結婚適齢の子供をもつ家庭では、父母が子供の配偶者を決める慣わしだが、実際に 配偶者を選ぶのは主として중매쟁이(仲人)を通して行われる。중매쟁이はあらゆる情報を収集して新郎・新婦に相応しいカップルを見つけ、双方の家にその情報を伝えると、父母たちの間で注意深く検討がなされる。 その結果、新郎側が適当であると判断すれば、新郎の家から新婦の家に正式な求婚書を送り、新婦側の父母はその可否を決定する。 これが의혼(ウィホン:議婚)の儀である。 当のカップルはお互いに会うこともなく何も知らないうちに、すべてが進行する。 
②납채(ナプチェ:納采) 新婦側から求婚が受け入れの連絡を受けると、新郎の家では新郎候補の生年月日と生まれた時刻の干支を白い紙に記した사주(サジュ:四柱)を用意して新婦の家に送る。(写真 右) 新婦の家では、これに基いて占い師に相談して結婚式の日にちを決める。 そして、決まった日にちをすぐに新郎側に送る。これを연길(ヨンギル:涓吉)といい、合わせて、新郎の体型を問い合わせる。 ③납폐(ナプペ:納幣)  結婚式の前日までに、新郎の家から新婦とその家族たちに、함(ハム:函)という箱に入れた贈り物をする。これが납폐(ナプペ:納幣)と呼ばれる儀式で、日本でいう結納に当ると考えればよい。(写真 左)
結婚式の前日までに、新郎の家から新婦とその家族たちに、함(ハム:函)という箱に入れた贈り物をする。これが납폐(ナプペ:納幣)と呼ばれる儀式で、日本でいう結納に当ると考えればよい。(写真 左)함(ハム:函)の中には、혼서(婚書), 채단(采緞), 혼수(婚需)の三つが入っている。 혼서(婚書)は送る人の名前を書いて結婚を約束するものであり、채단(采緞)は新婦が着る赤・青のチマ・チョゴリ用絹織物、そして혼수(婚需)は新郎の両親から新婦に贈る装身具である。 この함(ハム:函)を担いで新婦の家に届けるのは、함진애비(ハムジンアビ)といい、新郎の親友の一人が担ぐのが慣わしである。 新婦の家では、餅やご馳走を準備して、この함진애비(ハムジンアビ)をもてなすそうである。 ④전안례(チョナンレイ:奠雁禮) 結婚式は普通新婦の家で行われた。両家の父母や近所の人たちが見守る中、新郎は조랑말(小型の馬)に跨って、新婦の家に到着する。 そして、馬を下りると기럭아비(キロクアビ:雁を手に持って新郎を新婦の家に導く人)の導きで新婦の家に入る。 新郎は기럭아비(キロクアビ)から木製の雁を受け取り室内のテーブルの上に載せて、新婦の母に礼を捧げる。新婦の母はその雁を抱いて部屋に入る。 これが、전안례(チョナンレイ:奠雁禮)の儀式で雁を捧げる礼と言われるものである。 ⑤교배례(キョベレイ:交拜禮) 新郎と新婦は大抵結婚式当日が初対面である。式の間中、新郎・新婦を手伝ってくれる仲間がそれぞれ二人ずつつく。 その手伝いの人たちが、テーブルの下にむしろを敷くと、新郎・新婦は、テーブルを挟んで向かい合って立つ。 すると、手伝いの人たちが、新郎・新婦の手をきれいに洗って清めてくれる。 その後、やはり手伝いの人の助けを受けながら、お互いに敬礼をする。最後に二人が膝まづいて向かい合い、お互いに結婚の約束を承諾し確認する교배례(キョベレイ:交拜禮)の儀式が終わる。 ⑥합근례(ハプクンレイ:合排禮) 結婚式の最後は합근례(ハプクンレイ:合排禮)と呼ばれる儀式である。これは日本の[三々九度の杯]の儀式に似ている。 手助けの仲間たちが、新郎と新婦に交互に盃にお酒を満たし、それを飲む。新婦は飲むしぐさだけのことが多い。これを二回繰り返すと最後に二人が向かい合って敬礼する。父母、祖先、客にもそれぞれ敬礼をして、結婚式が終了する。 
⑦폐백(ペベク:幣帛) 結婚式が終了すると、新婦はすぐに舅と姑に会い、폐백(ペベク:幣帛)という儀式が行われる。 結婚式の隣の部屋に、屏風を背にして舅と姑が座り、新婦は四回敬礼をして、婚家とその先祖に対して尊敬と忠節とを誓う。 その後新郎・新婦が広げた白い布に向って、栗となつめの実を投げる。そしてキャッチした数だけ子宝に恵まれると言われている。栗の実は女の子、なつめの実は男の子を意味するそうである。(写真 右) 最後に時舅と姑に簡単な食べ物を捧げ、 幣帛(ペベク)の儀式が終わる。 ⑧우귀(ウギ:于歸) 新郎・新婦は結婚後3日間、新婦の家の신방(シンバン:新婚夫婦の部屋)で過ごす。 そして、3日後、二人は新郎の父母の家に行く。このとき、新郎は自分が乗って来た조랑말(チョランマル)に跨り、新婦は籠に乗せて新郎の下人たちが連れて行く。 これを우귀(ウギ:于歸)と言う。 新郎の父母の家に入ると、新郎の家族たちに正式に新婦を紹介して、これで新婦は新しい嫁として迎えられることになる。
今でも、韓国の一部の地域では、この伝統に則った혼례(婚禮)が行われていることがあるという。
次に韓国の現代の結婚式について簡単にふれておきたい。またソウルなど大都会でも、特別な場所で、伝統婚禮をやってくれるところがある。 したがって、これを利用するカップルもいるようだが、大抵は、洋式の現代的な結婚式に変わってきている。 「現代の結婚式」を読む
 [現代の結婚式]
[現代の結婚式]
韓国ではかつては、동성동본불혼(同姓同本不婚)といって、本貫が同じもの同士の結婚は法律で禁じられていた。しかし数年前に民法が改正され、現在は8親等以内でなければ結婚することができる。
韓国の現代の結婚式は日本とほとんど同じであるので、概要を簡単にまとめて見る。伝統結婚式と比較して読んでいただくと、かつての味わい深い結婚が一層顕著に感じられることと思う。 ①상견례(サンギョンネ:相見礼) 当事者の二人が結婚の意志を固めると、両家の両親と顔合わせをし、結婚の許可を得る儀式である。普通は静かなレストランの個室などを利用して食事をしながら初顔合わせをすることが多いようである。 この儀式で両親の同意が得られれば、ただちに式の日取りが決定され、1~2ヶ月の間に、式場探しと予約、新居の決定、家具・調度品の購入、한복(韓服)の購入、ウェディング撮影の決定、新婚旅行の予約など、多忙な日々が続く。 ②혼수(ホンス:婚需) 結婚が決まったら、早期にやらなければならないのが、新居の決定である。これは、新郎側の責任と費用で行われる。しかし、普通は、전게(チョンセ :伝貰/専貰)といって、契約時にまとまったお金を払い、家賃を払う必要がない制度で、このお金は 契約満了時に全額戻ってくるもので、実質的に新郎側の負担にはならない。 一方、電化製品や家具など日常の生活で必要なものはすべて新婦側が準備することになっている。これを혼수(ホンス:婚需)といい、やはり相当の金額負担になる。 ③예물(イェムル:礼物)・예단(イェダン:礼緞) 예물(イェムル:礼物)は、新郎新婦の二人が結婚の記念に取り交わす品物である。宝石、アクセサリー、時計、指輪などが多いようである。 また、예단(イェダン:礼緞)は、新婦から新郎の両親に贈る贈り物である。新婦にとっては、何を贈ればよいのか悩みの種だが、最近は現金や商品券が一般化しているようである。 これは、結婚に際して、新婦側から新郎側への正式な挨拶の儀式である。 ④ウェデイング撮影 韓国では結婚式の数日前までには、ウェディング撮影を済ませて、立派なアルバムを用意してしまう。 スタジオで撮影するのが一般的であるが、美しい宮殿の中や、さまざまなシチュエイションの中で撮影される。 新郎新婦は、何回も衣装を変え、特に女性は、ウェディング・ドレスはもちん、伝統韓服のチマ・チョゴリ、洋装など、いろいろな衣装替えだけでも大変である。 アルバムというより、立派な写真集である。 ⑤함(ハム:函) 함(ハム:函)とは、結婚式前日に、新郎側が新婦側に贈る結婚の感謝を込めた贈り物である。 おもしろいことに、これを届けるのは結婚する当人ではなく、その友人たちによって行われ、結構にぎやかに行われる儀式である。友人たちが騒ぐので近所迷惑になり、最近はこの儀式を行わない場合も多いそうである。 ⑥결혼식(結婚式) 結婚の式場は専門の結婚式場、ホテル、教会・寺院など、当事者たちの考えによって、多様である。 式のプロセスは、概ね日本と同様であり、間に주례(チュレ:主礼)と呼ばれるいわば仲人役の人を立てて進行する。 まず新郎・新婦が入場する。そして、二人が祭壇に向かって立つ。 ここで、주례(チュレ:主礼)から新郎・新婦に対して주례사(チュレサ:祝辞)と呼ばれるお祝いの言葉があり、結婚することを宣言する。そして、二人は誓いの言葉を述べて、指輪の交換が行われる。 このあと、新郎・新婦から、参列者への挨拶があって、結婚式は終了となり、退場する。 きわめて短時間の儀式である。 結婚式への参加は比較的自由で、招待状は一応発送するが、持っていない人でも、自由に参加して祝福することができることが多い。また、服装も自由であり、ジーンズでもミニスカートでも構わない。要するに、そんな形式的な問題より結婚する二人を祝福しようという意味合いが強いのである。 ⑦폐백(ペベク:幣帛)  結婚式を終えた二人は式場に隣接する폐백실(幣帛室)に入り、ここで伝統の幣帛の儀式が行われる。
結婚式を終えた二人は式場に隣接する폐백실(幣帛室)に入り、ここで伝統の幣帛の儀式が行われる。新郎は사모관대(サモグァンデ:紗帽冠帯)、新婦は원삼(ウォンサム:円衫)に족두리(チェクトゥリ:冠)という 独特の한복(韓服)に着替え、폐백실(幣帛室)に待つ舅・姑に큰절(クンジョル:礼)の挨拶をする。その後舅・姑は新郎・新婦からお酒の杯を受け、お祝いの言葉を贈る。 その後新郎・新婦が広げた白い布に向って、栗となつめの実を投げる。そしてキャッチした数だけ子宝に恵まれると言われている。栗の実は女の子、なつめの実は男の子を意味するそうである。(写真 右) 舅・姑からは、절값(チョルカッ:挨拶料)と呼ばれるお金の袋をもらって終了する。 このあと、親族に順に挨拶をする。 最後は、新郎・新婦二人の儀式がある。二人でお酒の杯を飲み、新婦が口にくわえたなつめの実を二人で食べる。どちらか、なつめの実が口に入った方が結婚生活で主導権を握る、といわれている。その後、新郎が新婦を背負って部屋を一周すると、폐백(ペベク:幣帛)の儀式は終了する。 日本にはない、韓国伝統の儀式である。 ⑧披露宴 日本のような形式ばった[披露宴]は行わないのが一般的である。結婚式場に隣接する大きな食堂やレストランで、ビュッフェ・スタイルのパーテイが設定されており、新郎・新婦が結婚式・幣帛などをやっている間に、既に飲食は始まる。 そして、そこに結婚式を終えた新郎・新婦が合流する形をとる。 参加者はご祝儀を包むが、だいたい30,000~50,000ウォン(3,000~5,000円)程度である。入口でお金の包みを渡して会場に入って、あとは自由に飲食すればよい。もちろん、引き出物のようなおみやげはない。 式と披露宴はあわせて1時間程度で終わる。 ⑨結婚式後の諸行事 結婚式が終わると、二人は新婚旅行に出発する。韓国国内が依然人気があるようだが、最近は近隣の海外旅行に出かけるカップルも増えているようである。 大変なイベントが新居への引っ越しである。引っ越しをすると、집들이(チプトゥリ:引っ越し祝い)が行われ、友人を新居に招いてもてなす。 最後に忘れてはならないのが、婚姻届の提出である。 ここまで済ませると、ようやく結婚にかかわる一応の儀式が一段落することになる。 「現代の結婚式」を閉じる
|
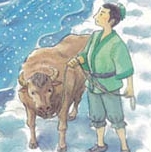
상례(喪禮)
[伝統的な喪禮]
韓国の伝統的な喪禮は朝鮮時代から伝わるものとされている。
多分に儒教的な思想に溢れたものであり、丁寧で荘厳である。この様式は現在では薄れてしまっているが、しかし、喪禮おける儒教精神は現在でも立派に生きている。その様子は、[現代の喪禮]の項を参照されたい。 ここでは、まず、その源となった朝鮮王朝時代の喪禮の手続きを簡単に纏めておくことする。 ①첫째날(第1日目) a)臨終を迎えて、その운명(殞命:死亡)を確認することを초종(初終)という。 喪禮は、この초종(初終)によってはじめられる。 운명(殞命)を確認したら、死体の魂を呼ぶ儀式を行う。[북(複)] b)そして、喪禮の喪主を決定する。[입상주(立喪主)] c)초종(初終)と북(複)を通じて完全な死を確認したら、死者に対する禮遇の意を表すため、服を脱いで食べ物を絶つ。[ 역복불식 ( 易服不食)] d)호상(護喪)と사서(司書)は、상가(喪家)のために親戚や同僚たちに訃報の通知を発送する。[부고(訃告)] e)死体を沐浴させ、きれいにする。[목욕(沐浴)] その上で、死体に死に装束を着せる。この儀式を[습(襲)]という。 f)禮饌 を準備し、その前には향로(香爐), 향합(香盒), 초(燭)を設置する。[습전(襲奠)] そして、喪主以下全員が大声を張り上げて泣く。[위위곡(爲位哭)] ②둘째날(第2日目) a)第2日目の重要な儀式は、소렴(小斂)である。 この儀式は死体を白い布で包み、更にあらかじめ用意しておいた소렴금(小殮衾)と呼ばれる布団で包む儀式である。 これは、後に故人を棺に入れる準備のための儀式である。 b)死体の前に예찬(禮饌)を設置し、향로(香炉), 향합(香合), 초(蝋燭)を準備する。[전(奠)] ③셋째날(第3日目) a)소렴(小斂)の翌日、即ち3日目に대렴(大斂)の儀式を行う。 この儀式は、布と布団で包んだ遺体を紐でしっかりと縛り、納棺する儀式である。 棺の中には故人と共に、生前愛用した品物なども一緒に納める。 ④넷째날(第4日目) a)대렴(大斂)の翌日、儒教の오복제(五服制)に従って、喪主をはじめとする人々が喪服を着ることができる。この儀式を성복(成服)と言う。 b)このあと、故人の冥福を祈り、喪主を慰労する弔問を受ける。[조(弔)] ⑤喪禮の儀式 a)訃報を聞いた親戚などは、遠方のため喪に服するか、駆けつけるかして、弔問する。[문상(聞喪)] b)葬儀の時間や場所が決まり次第、墓地の準備をする。墓石をはじめ墓地に必要な各種道具類の制作を進める。[치장(治葬)] c)발인(發靷)の前日に、霊柩に移る旨祖先に祈りをささげる儀式を行う。[천구(遷柩)] d)葬儀が終わると、遺体は棺を乗せる輿に移され、墓地に出発する。[발인(發靷)] e)霊柩が墓地に到着すると[급묘(及墓)]、遺体を輿からおろし埋葬する儀式を行う。[하관(下棺)] d)埋葬後は位牌をもって、家に戻る。悲嘆にくれて大声で泣き叫ぶことを반곡(反哭)と言う。 これ以降は、お酒を飲むことも、肉類を食べることも禁じられる。 ⑥葬儀後の儀式 a)葬儀の当日から3日間にわたり우제(虞祭)と呼ばれる제사(祭祀)が行われる。 葬儀の日、埋葬が終わって家に帰ったときに行われるのが、초우제(初虞祭)である。 翌日の朝には、재우제(再虞祭)を行う。 そして3日目に行うのが、삼우제(三虞祭)である。 この儀式は、霊魂が安らかに安心していることができるように、という目的で行われる제사(祭祀)である。 b)葬儀から100日たつと、もう泣くのはやめる、という意味で、졸곡(卒哭)と呼ばれる제사(祭祀)が行われる。 졸곡(卒哭)の儀式が終ったら、もう泣かないと言われている。 c)졸곡(卒哭)の翌日には、亡くなった人の靈を祖先の傍に合祀するための제사(祭祀)が行われる。この제사(祭祀)を부제(祔祭)と言う。 d)亡くなってからちょうど満1年、つまり13ヶ月目に소상(小祥)と呼ばれる제사(祭祀)が行われる。これは、いわゆる一周忌の儀式である。 そして、同じく満2年目に行われる제사(祭祀)は、대상(大祥)と呼ばれる。 e)27ヶ月目には、담제(禫祭)という제사(祭祀)を行う。この儀式は平常の状態に帰することを祈るもので、담제(禫祭)が終わるとはじめて酒を嗜み肉類を食べることが許される。 f)담제(禫祭)の翌日、길제(吉祭)が行われ、葬事のすべてが終了し、平常の生活に戻ることができる。 先祖の位牌は5代までが祀られるものと決められている。しかし新たに亡くなった人の位牌を安置するため、一番遠い祖先の位牌を下げなければならない。 そのため、제사(祭祀)を行って最も遠い祖先の靈牌を下げ、それを墓地に埋葬する。 今度亡くなった人の位牌を祀壇に祀ることにより、再び5代分の先祖の霊牌が祀られ、家は正式に新しい主人に代替わりすることになる。 これが、길제(吉祭)である。
韓国の儒教社会が、先祖に対して何代にもわたって如何に丁重に敬い慕って祀っているかが、よく伝わってくる喪禮の儀式である。
実際には、地方により、また家々によって、喪禮のやり方は様々であったようであるから、すべてがこの伝統に則って施行されていたとは限らない。 また、上に述べたプロセスが、韓国儒教社会における標準喪禮であるとも限らないことを注記しておきたい。
次に韓国の現代の葬礼について簡単にふれてみたい。
「現代の喪禮」を読む
[現代の喪禮]
韓国における現代の喪禮は、伝統的なものに比較すると、大分簡略化されてきているものの、もっとも一般的な儀式は、やはり儒教的流れを底辺として構成されているようである。
宗教的な要素もあるので、仏教的側面があったり、キリスト教的側面があったり、無宗教的なものであったり、さまざまである。 近年、韓国の一般的な葬礼は、삼일장(3日葬)と呼ばれる葬式と、それに続く삼우제(三虞祭)に代表される제사(祭祀)とで執り行われる。 ①첫째날(第1日目) a)臨終を迎えて死亡が確認されると[운명(殞命)]、新しい服に着替えさせ白い布や白い布団をかけてあげる。 屏風で隔てた隣に、遺影を準備しその両脇に蝋燭を立て、線香をあげる。[수시(收屍)] b)大声をあげて泣きながら外に喪を知らせ、”喪中”、”忌中”と書いた紙を家の門や入口に張る。[발상(發喪)] c)故人の親しい友人たち、知人、同僚など交友があった人に喪を知らせる。更に死亡時刻と場所、出棺日時と場所、墓地、喪主、喪祭などを決めて記録しておく。[부고(訃告)] ②둘째날(第2日目) a)死体をきれいに洗い清め、수의(寿衣:死に装束)を着せる。[습(襲)] b)次いで、故人の口に生米を入れて、口の中をきれいにする。[반함(飯含)] c)その後死体に白い布を被せ、소렴금(小殮衾)と呼ばれる布団で包む。[소렴(小斂)] d)소렴(小斂)が済むと、死体をしっかりと縛り、棺に安置する。この際、棺の中の死体の周囲には、故人が生前愛用したものなど、さまざまなものを一緒に入れる。[대렴(大斂)] e)대렴(大斂)が終わると、喪主をはじめ配偶者、子孫、親族のすべてが喪服を着用して、弔問客を迎える。喪服は黒のスーツに喪章を巻く。[성복(成服)] ③셋째날(第3日目) a)第3日目にいわゆる告別式を行う。これを발인식(發靷式/出棺式)と言う。 家で行う場合もあるし、斎場で行う場合もある。お供え物を添えて、まず簡単な제사(祭祀)を行う。 そのあと、儀式に入るが、宗教によってその儀礼は若干異なる。一般的には、開式のあと、拝礼をし、故人の略歴紹介、追悼、焼香、献花、そして閉式となる。 b)발인식(發靷式/出棺式)のあとは、土葬か火葬かによって異なるが、土葬なら棺を葬儀車に移動し墓地に運び棺を下してお墓を作る。 火葬の場合には、火葬場にいって簡単な제사(祭祀)の後火葬にする。遺骨は散骨するなり納骨堂に安置するなりの方法をとる。 この一連の儀式は、운구(運柩)と呼ばれる。 c)埋葬を終えて家に帰ると、제사(祭祀)を行う。 これは、死者の魂を、再び家の中に呼び戻すためのものであり、반혼제(返魂祭)と云われる。 ④초우제(初虞祭) a)葬儀の当日埋葬後、반혼제(返魂祭)を行うが、死者の魂を平安にさせるために葬儀の日から3日間毎日제사(祭祀)を行う。 最初に行うのは、초우제(初虞祭)と言って、반혼제(返魂祭)と一緒に行う場合が多い。この儀式は必ず葬儀当日に行わなければならない。 초우제(初虞祭)が終わると、喪主をはじめとしてみんながお風呂に入ることができる。しかし櫛で髪をとかすことは許されない。 ⑤재우제(再虞祭) 초우제(初虞祭)を行った翌日の朝行う제사(祭祀)を、재우제(再虞祭)という。 一般的には、葬儀の翌日に行うことになる。 ⑥삼우제(三虞祭) 재우제(再虞祭)の翌日の朝、すなわち葬儀から3日目の朝に行われる제사(祭祀)が、삼우제(三虞祭)である。 삼우제(三虞祭)では、たくさんのお供え物を供える。その種類は家風によって異なるが、ご飯、スープをはじめ、お酒や果物、魚類、肉類、野菜類など多様である。 삼우제(三虞祭)を済ませると、喪主はようやく墓地に行くことが許される。 お墓に行って、簡単な묘제(墓祭)をした後、お墓がちゃんとできているかどうかを詳細に調べる。 こうして、 삼우제(三虞祭)を終え、묘제(墓祭)を済ませると、ようやく喪服を脱いで、一連の葬儀の儀式が終了する。 ⑦탈상(脱喪) 上に述べたように、一般には삼우제(三虞祭)、묘제(墓祭)が終わると、「喪が明ける」ことになり、これを탈상(脱喪)と言う。 しかし、故人が親、祖父母、配偶者の場合には、탈상(脱喪)は、死亡した日から100日目であり、これを백일탈상(百日脱喪)と言う。 ただ、最近では、葬儀の簡略化、短縮化が進んでおり、백일탈상(百日脱喪)に変わって、사십구일탈상(四十九日脱喪)で「喪があけた」とする家が大部分であるという。 탈상(脱喪)の日には、一般的な제사(祭祀)を行って、喪服を脱ぐ。 ⑧弔問 a)訃報に接した後なら、いつでも弔問することができる。 弔問客の服装は、特に決まりはないようだが、黒系の地味な服装が望ましいとされる。明るい色調やアクセサリーの着用は厳禁である。 b)弔問に際しては、부위금(賭儀金:香典)を準備していく。 金額は故人との生前の親しさにより、30,000~100,000ウォン程度の範囲とされる。 専用の封筒は文房具店やコンビニなどで売っているので、購入して行くのがよいだろう。 c)弔問では焼香の習慣はなく、一般には線香をあげる。 線香をあげたあとは、遺影と喪主・遺族に向って拝礼をして、簡単に慰労の言葉をかける。 「現代の喪禮」を閉じる
|

제례(祭禮)
韓国の제례(祭禮)には、제사(チェサ:祭祀)と차례(チャレ:茶禮)の2種類がある。
目的が異なるだけであって、제례(祭禮)そのものの形式や手順、決まり、しきたりには大差がない。 제사(チェサ:祭祀)は先祖の靈を供養することが目的で、いわゆる日本の法事に相当する。家庭ごとに異なるが3~5代までの先祖の供養する。 先祖の陰暦の命日の前日、親族が本家に集まり、命日の午前0時すなわち深夜に제사(チェサ:祭祀)がはじまる。 祭祀そのものに参列するのは、男性だけである。昔は韓服を着て正装で参列していた。 最近は簡略化・合理化が進み、開始時刻ももっと早めたり、女性が参列する家庭もあるし、副葬も極端に派手でなければ韓服にこだわらないようにしている家庭も多いようだ。 一方、차례(チャレ:茶禮)は、祖先を迎えて、共に収穫の喜びや年の節目をお祝いする儀式が目的である。 차례(チャレ:茶禮)が行われるのは、陰暦の1月1日(설:正月)と陰暦の8月15日(추석:秋夕)が原則である。しかし家庭によっては、陰暦1月15日(대보름:デボルム)などの名節や先祖の誕生日に行うところもあり、さまざまである。全体的には、차례(チャレ:茶禮)の回数は減少してきている。 제사(チェサ:祭祀)と違って、開始時刻は当日の朝である。 なお제사(チェサ:祭祀)なり차례(チャレ:茶禮)が終わると、そのまま성묘(墓参)に出かける場合が多い。
次に제례(祭禮)の進め方や、手順、しきたりなどについて、まとめてみる。
제례(祭禮)では、先祖を祀る祭壇を配置し、そこに茶禮床を置く。このとき北側が上座になるようにする。 まず、祭主たる主人が茶禮床に酒を注ぐ。そして、祭壇の前で절(チョル)と呼ばれる最敬礼を行う。 次いで、제례(祭禮)の参加者も、全員祭壇の前で절(チョル)を行う。 そのやり方・作法は地域や家庭によってさまざまである。 参加者全員の拝礼が終わると、先祖の食事時間となり、全員がしばらく部屋から退席する。 先祖の食事が終わる頃を見計らって、再び祭主が祭壇の前に進み、茶禮床の酒を飲み干す。 제례(祭禮)の儀式は、これで終了である。 その後は、全員が集まって、茶禮床の料理を取り分け、酒を酌み交わしながら、その料理を食べる。 제례(祭禮)の日の主婦は大変である。忙しく、いろいろな料理を作って準備しなければならないからである。 茶禮床に並べられる料理は、その食材や調理法、並べ方に一定のしきたりがあり、その通りに準備し、並べなければならない。 料理の味付けはあっさりとした単純なもので、辛いものやニンニクは使ってはならない。 茶禮床には、普通3~5列程度の料理が用意される。(写真 右)  お膳の1列目(一番手前)の真ん中には한과(韓菓)と呼ばれる菓子を置き、その左右両側に홍동백서(紅東白西)あるいは조율이시(チョユリシ:棗栗梨枾)に従って果物を配置する。 홍동백서(紅東白西)とは、東側(右手)に赤い果物、西側(左手)に白い果物を置く、という意味である。 조율이시(棗栗梨枾)とは、果物を左からナツメ、栗、梨、柿の順に並べる、という意味である。 次に2列目には、中央にキムチや惣菜などの나물(ナムル)類を置き、その両側に좌포우혜(左脯右醯)に従って左手に干物、右手に식혜(シッケ)を配置する。 3列目中央には소탕(蔬湯)(野菜や豆腐で作ったスープ)を置く。 その両側には、어동육서(肴東肉西)の定めに従って、右手に오탕(鱼汤)、左手に 육탕(肉湯)を配置する。 4列目は、적(炙:火で焼いたもの)と 전(煎:油で揚げたもの)を置く。어동육서(肴東肉西)にしたがって、魚類は右手に、肉類は左手に配置する。このとき、魚類の配置にはルールがあって、두동미서(頭東尾西)と言って、魚の頭を右に尾を左に置かなければならない。 最後の5列目には메(飯) と 국(羹)(肉や野菜を入れた熱いスープ)を置く。このとき、ご飯は左手、汁は右手に配置する。 家系によっては、餅、雑煮、麺類などを置く家庭もある。
제례(祭禮)の儀式は、儒教思想によるものであり、基本的には先祖の恩に感謝し、敬い、供養することを目的としたものである。
제례(祭禮)については、本サイト内の下記ページも参照されたい。しかし、今日、次第に簡素化・縮小化されてきていることは否めない。 제사(祭祀)だけでも、先祖5代にわたって供養すると、1年に10回もの儀式をしなければならない。その都度、本家のある故郷に行かなければならないのも大変だし、主婦の労力や費用も大変である。そのため、先祖3代までの供養にするなどの縮小も進んでいるようだ。
収穫を喜び祖先を敬い祀る
|
|
|