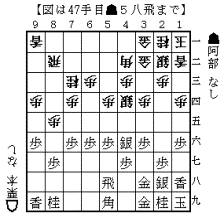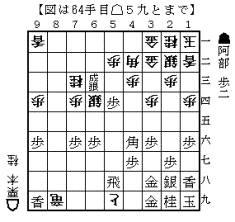2日目
2日目はA級上位校の東大、早稲田、慶應と当たる。勝つのは非常に厳しいと考えていたので、少しでも多く勝数を増やそうと思っていた。だが、主力の中島が風邪を引いたため欠席、奈良は寝坊で慶應戦には間に合わないかもしれないということで状況はさらに厳しくなった。 3回戦 慶應大学 慶應の主力は森本氏、神谷氏、井元氏。アマ強豪の小関氏が抜けたとはいえ、今でも手厚い。 相手はベストメンバー(上から、井元、阿部、神谷、川上、森本、斎藤、小澤)で来ると思ったので、それに合わせて考えることにした。栗本は副将で阿部氏と当てて勝負。菊池は慶應7番手と思われる川上氏にぶつける。奈良は七将に置き、今季の個人戦で勝った小澤氏と。 当たりは友安―井元、栗本―阿部、鎌田―神谷、菊池―河合、阿部―川上、川島―森本、奈良―小澤。慶應は六将で出ていたレギュラーの斎藤氏を下げて河合氏を出してきた。四、七はやや有利、副は互角、ほかはどれも苦しいといった状況である。 まず奈良が試合開始に間に合わず不戦敗。その後は友安、阿部が負け菊池が勝ち、鎌田、川島、栗本が負けての1−6負けだった。 4回戦 早稲田大学 早稲田の主力は河崎氏、岡部氏、杉村氏でこのあたりはうちの主力でも厳しい。また、鹿島氏、金子氏に加えて一年生の芦田氏も強い。 予想は上から(鹿島、河崎、杉村、芦田、金子、岡部、中山)だったが早稲田は3回戦の千葉戦では芦田氏を下げ、副将の位置に8番手と思われる下山氏が出ていた。とりあえず、奈良は中山氏に当てて1勝をとることにする。また、山元を副将に置いて河崎氏をかわし、栗本は三将にして新人戦で勝ったことがある杉村氏にぶつけることにする。もし副将に下山氏が出て栗本―河崎となっても、山元は古新戦で下山氏に勝ったことがあるので、下山氏が出てきても勝負になると考えた。 当たりは友安―鹿島、山元―下山、栗本―河崎、鎌田―杉村、菊池―芦田、川島―岡部、奈良―中山。七は有利、副は互角であとはどれも苦しい当たりとなった。 友安が相手の主力鹿島氏に勝ったものの、奈良が二歩により反則負け。その後山元、菊池、栗本、鎌田、川島も討ち取られての1−6負けであった。 ここでは友安の将棋を紹介しよう。
下図(先手友安)は△4五歩と歩を合わせたところ。
先手は香損しているものの玉頭へのプレッシャーも
相当なものがあり難しい局面になっている。
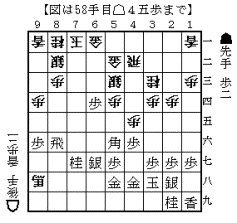
以下▲6六飛 △6二歩 ▲8四歩 △同歩 ▲8三歩 △7三銀
▲6五桂 △6四銀左 ▲7三桂成 △同銀 ▲7四銀 △同銀
▲同角 △7三銀 ▲8二銀 △同銀 ▲同歩成 △同玉
▲8三銀 △7三玉 ▲5二角成で下図。
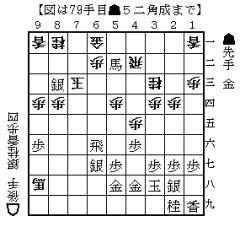
後手の△4五歩は緩手だったのであろうか。
▲6六飛〜8四歩がすこぶる厳しい。
△4五歩のところでは△9七馬などとして6四の歩を払うような手を
見せた方がよかったのではないか。
あとは棋譜のとおり,流れるような手順(相手のミスもあるが)で
一気に寄せきった。
5回戦 東京大学 東大は今までの主力に加えて、個人戦全国優勝経験者の高橋氏、山口氏、それに団体戦全国優勝の阿部氏など、大型新人が多く入学している。 おそらくうちは、奈良以外は誰と当たっても非常に厳しいので、奈良を何将で出すか考えた。単純に七将で出すと高橋氏か重野氏と当たる可能性が高いので、それなら五将で出すことによりこれまで全勝の高橋氏をかわし、山口氏を狙っていこうと考えた。また、1年生の鈴木諭を七将で出し、団体戦という場を経験してもらおうと思っていた。 当たりは友安―大野、栗本―阿部、鎌田―小林、菊池―山内、奈良―山口、鈴木貴―高橋、鈴木―重野。大将はこの試合いきなり出てきたので、実力はよくわからなかったが、どこも苦しい当たりだ。 友安が勝ち、奈良、鈴木諭が負けたが栗本が勝ち、鈴木貴、菊池、鎌田が負けての2−5負けとなった。 では勝った栗本の将棋を見ていただこう。
図は相穴熊の中盤である。ここから栗本は△8六歩と仕掛け、▲同歩ととる1手なのだが、相手は▲5五歩とわが道を行き、以下、△8七歩成 ▲5四歩 △5二歩 ▲3七角 △7八と ▲5五銀△同銀 ▲同角 △6四銀 ▲4六角 △8九飛成 ▲7二銀△6九と ▲6三銀成 △5九と (下図)となり、優勢に立った。
以下、かなり差を縮められ、形勢が怪しくはなったが、何とか相手を寄せきった。 2日目は友安が中島のいない穴を十二分に埋めてくれたのが大きかった。ここまでの成績は1勝4敗。ここまで5連敗のチームは中央大学と千葉大学の2校で、この2校はこれから直接対決するので3日目の中央大学戦に勝てば残留できるという状況になった。