オーダー
今年は、去年の主力メンバーがほとんど出場可能であることに加えて、去年のレギュラーと遜色ない実力をもつ新入生、松原が加わったことで昇級は十分可能な戦力がそろった。レギュラーは菊池、村田、松原、栗本、小川、鎌田の6人。このうち栗本が2日目にしか出場できないため、残りの5人で勝ち星を取りにいき、苦しい当たりを準レギュラーで回避していく作戦をとった。オーダーは市村、菊池、松本、村田、山元、松原、中山、栗本、中島、岡垣、小川、高梨、鎌田、鈴木とした。
1日目
出場できない栗本に代わり実力者、中島が助っ人として参戦してくれることになったため戦力は十分。連勝スタートが目標だ。
1回戦 筑波大学戦
筑波は寺師氏と新入生の牛久氏以外にはレギュラーなら十分に勝てる。初戦なので、レギュラー全員と中島、準レギュラーの中では強く、経験も豊富な山元を出すことにした。
当たりは次のようになった。(以下、当たりは全て敬称略)
菊池―寺師、村田―中村、山元―天田、松原―佐藤、中島―前川、小川―牛久、鎌田―佐藤。大将戦が互角、3将戦と6将戦が苦しそうだが、他は十分に勝ち星が見込める。まず、大将戦の菊池の将棋(菊池が先手)を見ていただく。菊池は序盤、不慣れな横歩取り3三桂戦法を採用され、作戦負けになってしまった。苦しいながら耐えて迎えたのが図1。
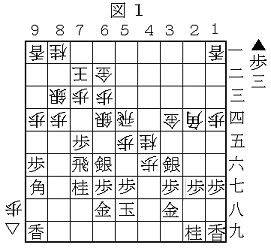
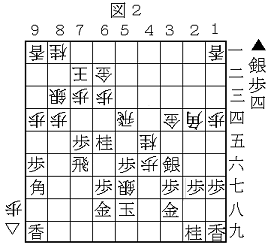
ここで▲2六歩なら苦しいながらもまだ長い勝負だったが、▲6五銀とぶつけてしまった。以下△同銀▲同桂△5六歩▲同歩△5七銀で敗勢に(図2)。最終手△5七銀が好手で、▲同金△同桂成▲同玉は△4七歩成▲同玉△5七金で詰んでしまう。以下▲4九玉△6八銀成▲4三銀△5七桂成▲5四銀成△2八金で投了。7人中1番早く負けになってしまった。
次に、期待の新人、松原の将棋を見ていただく(後手が松原)。図3は1九飛成と香車をとったところ。まだ難しいが・・・。

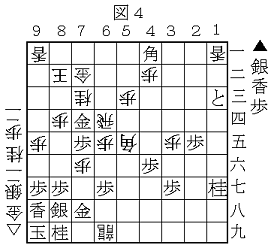
図3から▲6九桂△5五角▲7四銀△7七香▲7三銀成△同桂▲7四金△7八香成▲同金△6九龍で後手優勢(図4)。
▲6九桂が悪手。7七をうけたつもりが△5五角〜△7七香とされて受けになっていなかった。図4で▲7九香も△7七桂で受けにならない。以下は▲7三金△同金▲7四香△8三金となり、最後は端の位が生きて勝ちとなった。
今年の筑波は予想外に強く、松原、中島、鎌田は勝ったが、菊池、村田が両方負けてしまい、3−4で黒星スタートとなってしまった。
2回戦 法政大学戦
ここは絶対に勝っておきたい所。注意すべきは池戸氏で、その他はレギュラーならば互角以上だと思っていた。ただ、初戦も同じようなことを考えながら負けてしまっているので油断は禁物である。
当たりは次のようになった。
菊池―藤城、村田―畠山、松原―市原、中山―津田、中島―池戸、小川―川合、鎌田―伊藤。池戸氏との対戦となったのは中島。しかしこの手合ならばどちらが勝ってもおかしくはない。他は互角かそれ以上の当たりである。
まずは6将、小川の将棋(小川は後手)。相手がミスをしたため一瞬にして優位に立つ。初手から▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲4八銀△9四歩▲2五歩△3三角▲5六歩△2二飛▲6八玉△2四歩で、定跡書などでよく見る居飛車不利の図が出現。対戦相手の川合氏はこれを見落としたことにひどくショックを受けていた。以下、優位を拡大して迎えた図5。
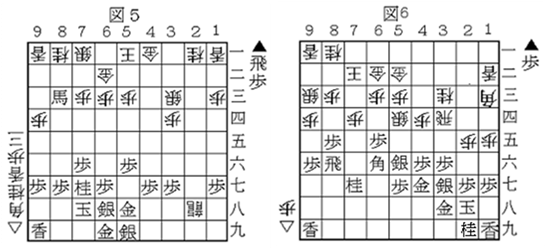
図5から△8二香▲6五馬△9五桂と手薄な8筋を攻めるのが早い寄せ。先手は金銀が受けに使えないのが痛い。以下、寄せ切って快勝。
次に、3将の松原の将棋(先手が松原)。図6では先手作戦勝ちである。以下、▲9五歩△同歩▲9三角成△同香▲9四歩が手筋の攻め。△同香は▲8四歩△同歩▲同飛で香取りが受けにくい。以下、▲7五角△7六飛▲9四香△8六銀と進みやや先手優勢。後手は9筋、3五、2三に傷があり、まとめきれない。
続いては5将、中島の将棋(中島が先手)。後手が序盤に無条件で1歩損をしてしまい、その後先手が持久戦に持ち込んで作戦勝ちに。迎えた図7は後手が6四歩とついたところ。
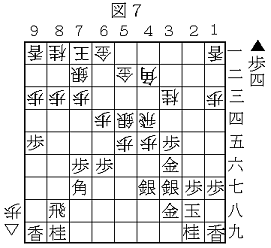
ここから▲9四歩△同歩▲9三歩△同香▲9七桂と持ち歩を生かしての美濃囲いの急所の端を攻める。以下△6五歩▲8五桂△6六歩▲同角△6五銀▲5五角と自然に角まで活用できてはすでに勝勢に近い。以下は相手に何もさせずに完勝であった。
準レギュラーの中山が負けてしまったものの、他が勝って全体では6−1で勝ちであった。
初日は1勝1敗のスタートとなった。注目は筑波大学で、東工大、中央大学という上位校に勝っての2勝により一気に昇級候補になった。これにより、2日目以降の昇級争いはより厳しいものとなった。