

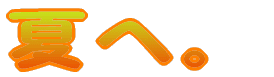
![]() 函館 茜木温子
函館 茜木温子
朝市の空
=プロローグ=
『東京からの851便はただいま到着しました……』
到着ロビーに放送が響き渡る。周りにいた出迎えに来ているような老夫婦や、親子連れが顔を笑顔にして到着ゲートに集まりだす。
「着いた……彼が函館に……」
到着ロビーにある待合椅子から温子はゆっくりと腰を上げる。
ざわつくロビーには東京の名前の入った紙袋を持つ人々が目的地に向って歩き出している。その周りには出迎えの人々が鈴なりになり、さっきまでの静寂さを否定するようだ。
彼は? この便で間違いがないはず。
温子は流れてゆく人の流れを一人も見逃さないように視線を投げかける。
「もぉ、何でこんなに人がいるのよぉ、さっきまで全然人がいなかったのにぃ!」
温子の口がアヒル口のように広がったときに、懐かしくも、まるで昨日会ったようなそんな感覚に陥る姿が飛び込んでくる。気がつくと温子はその姿に向って走り出していた。
あそこに……あそこにあたしの安らぎがある!
「おっ!」
彼が声を上げる前に温子はその安らぎに向って飛び込む……。
「エヘヘへ……お帰りぃ〜」
ドスンという音が聞こえたが、彼は今までと同じようにあたしを受け止めてくれた。
「ウッ、ウン……ただいま」
彼はちょっと顔をしかめている……そんなにあたし重くなった? そういえば最近……ちょっと体重計に乗っていないかも……。
「どした?」
温子は小首をかしげながら彼の顔を見上げる。その顔は苦笑いを浮かべながらも、いつもと同じ笑顔……ウン、幸せかもしれないなぁ。
「いや、やっと来たんだなぁって、温子ちゃんの顔を見たらほっとしちゃったよ」
ヘヘ、嬉しい事をいってくれるなぁ。
「そう? なんだか『来ちゃった』って言うような顔をしていた気がするけれど?」
彼の腕にしがみつきながら温子は意地の悪い顔で彼の顔を見上げる、そんなはずないとは思っているがちょっと気になる。
「エッ? そんな顔していた? 困ったなぁ……」
ちょ、ちょっとそこで困らないでよぉ……あたしは『そんな事ないよ』という台詞を期待していたのにぃ。
「あっ、あなた?」
温子は心配げな表情で彼の顔を見上げる。しかし彼のその顔は、意地の悪い顔をして温子の事を見つめていた。
「ハハハ、そんな事あるわけないだろ? やっとの思いでここ函館まで来られたんだ……数年前まではまったく知らなかった土地が俺の第二の故郷になったんだよ、感慨深いものがあるのは当然だよ」
彼は鼻先を掻きながら温子の顔を見る。その顔は逞しく見える。
「もぉ、いじわるぅ!」
温子は力いっぱいに頬を膨らませながらそっぽを向く。
=新居=
「車はどうしたの?」
函館空港の駐車場に向かいながら温子は彼の顔を見上げる。相変わらず寒いのには馴れていない彼の顔はロビーを出たとたんに凍えたものになる。
「ウン……今知り合いの工場で寒冷地仕様に改造してもらっているよ……そうしないとこの寒さにきっと絶えられないだろうから……にしても寒いぃ〜、俺も寒冷地仕様にしないといけなかったかな?」
彼の口からはガチガチとまるでわざと鳴らしているのではないかと言うぐらいに震えている。もぉ、そんなに寒いのぉ? 温子は自分の体を彼に押し当てる。
「そんなのでこれからどうするの? まだ今日はこれでもいい方よ? まだこれから寒い日があるかも……どうする?」
彼が驚いた表情で温子の事を見る。今日はまだ雪が降っていない。今年の函館は例年になく雪が多く、寒い日が続いている。
「そうしたら、いつもこうやってくっついてくれると嬉しいなぁ……」
目じりを下げながら彼が言う、その視線はあたしが押しやっている胸……もぉ〜えっちぃ〜。
「いくらか暖房がきいてきたかな?」
駐車場に止めてある『茜木鮮魚店』の社用車……いわゆる軽トラックはアイドリングを始めてしばらく経つ。
「ウン、暖かくなってきた……そろそろ行こうか?」
助手席に座る温子、彼は当たり前のように車の鍵を温子から取り上げ、自身を運転席に滑り込ませる。
「お店でいいかな?」
ギアをセカンドに投入しながら彼はあたしに視線を投げかける。
「うーん……その前に」
温子はそう言いながら、彼をナビゲートする。
「今年は雪が多いみたいだね?」
駐車場脇に積み上げられている雪山を見ながら彼が言う。
「ウン、そうかもね? 一月なんて市内でも吹雪いちゃってお店に行けなかった事があったぐらい、今日も午後から雪ってテレビで言っていたし、ちょっとウンザリかも……」
温子は苦笑いを彼に向ける。その表情に彼の顔もウンザリ顔に変わる。
「ほらぁ、そんな顔しないの! これから慣れていかなければいけないんだからそのうち雪があったほうがいいなんて言い出すかもよ?」
「……それはないでしょ?」
彼は口を開けながら笑い出す。
「そうしたら、そこを右に入って……そこの『ラッピ』の信号を左」
ちょうど正面に『五稜郭タワー』が見えてくる、彼はなれない雪道を緊張した面持ちでハンドルを操る。
「そこの角を入って……ハイ、とうちゃ〜く」
一軒の古い家の前で車を止める。
「ここは?」
車から降り、彼はその佇まいを見上げる。一応二階建てのその家は、だいぶ年季が入っている、恐らくあたし達より年上ではないかしら?
「ここがあなたの新居!」
温子の一言に、彼は驚きの表情を隠さずそのままの顔で温子を見つめる。
「エッ? 俺の……こっちでの住まい?」
そう言い再び彼はその家を見上げる。
既に卒業論文を書き終えたといっていた彼はこっちでの住まいを探すといい、今日来たのもその為だった、でも、あなたの家はもう確定しているのよ? だってあなたはあたしの旦那様なんだから。
「そっ! 正確にいえば『あなたとあたしの』家っていう事になるわね?」
温子の顔が不意に赤く染まる。
自分で言って、何照れているんだろう……。彼もそうみたい、頬が赤く染まって照れている。
「……俺たちの家」
感慨深そうな顔で彼は玄関に向って足を向ける。
「ん? 表札がかかっている……あかねぎ……って?」
その表札を見て、彼は目を白黒させる。
「そう、ここがあたしのうち……あたしとお母さんの家……新しく借りるのなんてもったいないでしょ? それにこの家も二人で住むにはちょっと広いし、男手がなくってちょっと無用心だからあなたが来てくれると助かるってお母さんが……もしかして迷惑、だったかなぁ」
彼の顔が呆気に取られているように見える、もしかして嫌だったのかなぁ。
「……ここが温子ちゃんの家かぁ」
たたずまいを見る彼の顔が徐々に笑顔に変わってくる。
「じゃあ俺は居候っていう事になるかな? それとも住み込みの従業員?」
意地の悪い顔で彼が温子の顔を見る。
「違うに決まっているじゃない! あなたは……あたしの……そのぉ……もぉ意地悪ぅ」
ゴニョゴニョと温子が言葉を濁していると彼は楽しそうに笑う。
もぉ!
「ただいまぁー」
朝市にある茜木鮮魚店に温子の声が響きわたる。
「お帰り、若女将……オォー、若旦那もお帰りなさい」
源さんが彼を見ながら冷やかすように言う、確かにお母さんが大女将でその娘のあたしが若女将、となるとあなたのポジションはやっぱり若旦那ね?
「源さんやめてよ……」
彼はその台詞に戸惑ったような表情を見せるが、源さんは嬉しそうにその台詞を何度となくはく。
「お帰り温子」
店の奥からお母さんである早苗が出てくると、彼の顔が引き締まる。
「あっ、お母さん、これからよろしくお願いします」
彼はやたら丁寧にお母さんに挨拶する。ハハ、緊張しているのかしら?
「なぁに、こちらこそよろしく頼んだよ、温子の事をね」
お母さん……。
「さて、早速で悪いけれど、彼には配達に行ってもらおうかね? 行き先はここ、源さん、一緒に行ってお客さんに紹介しておくれ」
お母さんは彼に新しいエプロンを渡し、彼の表情を見る。
「はい、いってきます」
「アイヨ、若旦那、おいらが一緒で悪いな? 若女将と一緒がよかっただろ? キヒヒ」
源さんは荷台に荷物を積み込みながら彼を冷やかす。
「源さん、無駄口叩いていない!」
温子の雷が落ち、その隣では彼が微笑んでいる。
「さぁ、遠慮なく食べて、飲んで」
茜木家の晩餐がはじまる、彼を囲むようにお母さんとあたしが彼の顔を見つめる。
「はい、遠慮なく!」
彼も笑顔で目の前にあるものをパクつく。
「今日は飲んでもかまわないのよ? 車じゃないし、後はお風呂にはいって寝るだけ」
温子がそう言うと彼の顔がほころぶ、ウフ、いつも飲めなかったもんね? 温子はそう言いながらビールをお酌する。
「ウン、うまいなぁ……これはお母さんが作ったんですか?」
彼は満足げな顔をしながら目の前にある煮物をつっつく。
「あぁ、そうだよ、でもその魚の煮付と肉ジャガは昨日の晩に温子が作ったやつだ、味が浸み込んでいるだろ?」
今日彼が来るという事で腕によりをかけて作った肉ジャガ、我ながら美味しくできていると思うけれど。
「へぇ……」
彼がそれを口に運ぶ。どう? 温子は動きが止まり、その様子を見逃さないように覗き込む。
「……」
彼は無言のままに口を動かす……失敗しちゃった? 温子の目が潤みだす。
「……うーん、美味い! 絶妙な味付けだね? ジャガイモにも味がしっかりとしみていて、肉も硬くなることなく……本当に温子が作ったのか?」
「ちょ、ちょっとぉ、本当にってどういう意味よぉ!」
温子は頬をぷっくりと膨らませながら彼に抗議の表情を浮かべる。
「アハハ……なんだかいいねぇ、賑やかな食卓ってさ、久しぶりだよ」
お母さんが彼にビールを注ぎながら笑い出す。
「お母さん……」
二人はちょっとしんみりしている早苗の顔を見つめる。
「こんな日が来るなんて思ってもいなかったよ……しかもこんなに早く」
優しい目で早苗が二人を見わたす。
お母さんも喜んでくれているのかしら、あたし達の事を。
「さてと、温子後片付けは任せたよ、あたしはもう寝るから……明日は休みだ、二人でゆっくりしなよ、旦那」
ちょっとお母さん……。早苗はあくびをしながら立ち上がり、寝室に向って消えてゆく。
「……旦那……かぁ」
彼が感慨深そうにつぶやく。
「……エヘ、ちょ、ちょっと照れるわね?」
温子の顔も紅潮する……。
「あっ、あの! ふっ、お風呂、ど、どうぞ」
意味もなく動揺している温子、その動揺がうつったのか、彼の表情も何か落ち着かないものになっている。
「ウ、ウン……ありがとう」
彼はそう言いながらお風呂場に消えてゆく。
=買い物=
「買い物に行こうか?」
住まい探しのために来た彼のスケジュールはこの家が住まいに確定したこともあって空白になった今日、温子が朝食の後片付けをしているときに彼が声をかけてくる。お母さんは朝から用事があるといって出かけている。
「買い物かぁ、そうね、色々と用意しなければいけないものもあるものね?」
彼の引越し荷物はまだ着いていない、また東京に戻ってから引越しをしてその後本格的にこっちに移り住む予定のはず。
「ウン、買い揃えなければいけないものもあるし、温子にも見てもらいたいしね?」
彼はそう言いながら腰を上げる。
「何買うの?」
家に程近い五稜郭公園に向かい歩きながら彼の顔を見上げる。
「ウン、日用品や食器なんかも買い揃えないといけないし……ホントうちにある引越し荷物は家電ぐらいなんだよねぇ」
彼は鼻先をかきながらそう言う。聞いた話によると食器らしい食器はダンボール一箱でも余裕があるぐらいしかないらしい。
「だったら、ベイエリアに行かない? あそこならいろいろな食器とか置いてあるし……ウン、そうしよう、決まりぃ」
温子はそう言い、函館市電の『五稜郭公園』電停に足を向ける。
「市電に乗って『十字街』で降りるとベイエリアまですぐよ……どこにしようかなぁ」
市電を待ちながら温子は既にお店を検索しているようで、ニコニコしながら首を右左に傾けている。
「ベイエリアって、観光地というイメージがあるけれど、そんなお店があるの?」
そんな様子の温子を微笑みながら彼は見つめる。
「ウン、あの『金森倉庫』の中はね、お土産物屋さん以外にもアンティークショップがあったり、ブティックが入っていたりして結構地元の人も通う場所なのよ?」
自慢げに鼻をひくつかせる温子に対し、彼は感心した様子で鼻を鳴らす。
「まずはここ『はこだて明治館』よ、ここは『旧函館郵便局』を改造したもので、中にはガラス館やオルゴールを展示販売しているの」
赤レンガにつたが絡まり趣を出している外観は歴史を感じさせるには十分よね?
「このポストなんていまだに現役なんですって、すごいよね?」
入り口にある丸型ポストを指差し温子はにっこりと微笑む。
「へぇ……こういうやつはたいていレトロを演出するだけの飾りだけれど、フム、物持ちが良いというか、実益主義というか」
彼もにっこりと微笑み温子の事を見る。
「グラスやマグカップはここのがいいかも『はこだて硝子明治館』、ここでは裏にある工房で作っている物を展示販売しているの、サンドブラストといって自分で好きな絵をかいて作ることもできるみたいだし、あなたやってみる?」
温子が彼の顔を覗き込むと彼はフルフルと力なく首を横に振る。
「……やめておく、絵心なんてまったくないもん」
はは……やっぱり?
「おっ、これなんて綺麗だな……」
彼は話題を換えるように手元にあったマグカップを取り上げる。
「あら、ホントね? あぁ、こっちのやつも可愛いわよ?」
温子は違うマグカップを持って彼に見せる。
「ウン……でも、それペアカップだよ?」
彼はちょっと照れたように視線を泳がせながら温子に言う。
「本当だ、良いじゃないペアカップ……記念になるしね?」
記念、彼との……エヘ、ちょっと照れちゃうかも。
温子はちょっと頬を赤らめながら彼を見ると、彼にそれが伝染したかのように顔を赤らめる。
「さてと、もうお昼になったわね? なに食べに行こうか」
赤レンガで買い物を済ませると時間は既にお昼を回っていた。
「そうだねぇ、あっ『やきとり弁当』、これって前に一緒に食べたやつだよね?」
大きな『やきとり弁当』の看板が目立つ『ハセガワストアベイエリア店』の前に二人はたどり着く。
「そっ、この前は『笹流ダム』で食べたわよね?」
「ウン、ここがそうなんだぁ……」
彼はその看板を見上げながら懐かしそうに言う。
「ここにしよ」
温子はそう言い店内に入ってゆく。
「何にしようかな?」
コンビニという雰囲気の店前からは想像できない店内に入り込むと彼はちょっと意表をつかれた様な表情をうかべる。
「驚いたな、コンビニだと思ったけれど、こんな立派な厨房があるんだ」
店の中はコンビニというよりは、お弁当屋さんのような雰囲気があるが、しかし店の奥にはコンビニのような棚が置かれていたりして、初めての人はちょっと戸惑うかもしれない。
「このお店はね『イートインコーナー』があってお店の中で食べられるの」
カウンターの前にはテーブルが配され、そこでは何人かの観光客らしい人たちが舌鼓を打っている。
「さて、あたしはいつもと同じにするとして、あなたは?」
彼は、メニューをみながら思案顔になっている。
「タレと塩……かぁ……」
「ここの塩はただの塩と違っていて肉の味が引き立って美味しいよ、この前あなたに買っていったのは塩よ? タレも嫌味な味じゃないし、どっちもお勧めね」
温子がそういうと彼の首はさらに大きく傾く。
アハ、本気で悩み出しちゃったみたいね? そんな時は……。
「任せてくれる?」
温子は彼の袖を引き、すべて任せろという顔で見る。
「……頼む」
「すみませーん、小の塩と、塩二本とタレ二本のミックスを大でお願いします」
そういうと店員さんは笑顔で温子の顔を見て元気よく返事をする。
「ミックス?」
彼は不思議そうな顔をして温子の事を見るが、温子はおかまいなしに店内に入りお茶を買う。
「そっ、悩んだときはこれよ、塩もタレも両方食べられる、『ハセスト』の裏技なの」
温子はそう言いながらお茶のペットボトルを取り出し、彼に振り向く。
「あぁ……満足、美味かったなぁ」
店から出ると彼は満足げな表情を浮かべながら一息つく。
「でしょ? ここ函館にきたら絶対に食べなきゃいけない味よ? 『とり弁』は函館市民の味なんだから」
温子はそう言い彼にウィンクを送る。
「さて、後は何が必要かなぁ」
大体の食器関係は買い揃えた、後必要な物は……。
「歯ブラシとか買わないといけないんだよねぇ」
そうね、だとするとうちの近くのお店に行こうかしら? あっちのほうが安いだろうし。
温子は再び市電の『十字街』電停に足を向ける。
「歯ブラシは……ここで買いましょう、後ついでに夕飯の買い物もしていかない? 今日は何にしようかなぁ」
家の近くにあるスーパーに立ち寄り、店内を物色する。彼と一緒に夕飯の買い物、ちょっと憧れていたのよねぇ、二人仲良く手なんかつないでさ……エヘヘ。
「あれ? 温子じゃない?」
買い物が佳境になってきたとき、不意に声がかけられる。
「ん? あぁ、美弥さん?」
温子に声をかけたのは、寒いにもかかわらずミニスカートにブーツといった格好の女性。温子はその女性に笑顔を向ける。
「久しぶり、元気だった?」
その女性は屈託のない笑顔を温子に向け、手を取り再会を心から喜んでいるようだった。
「はいおかげさまで美弥さんは?」
温子とは正反対な雰囲気を持つ美弥はにっこりと微笑みその長い髪の毛を揺らしうなずく。
「ウン、元気だった、都も元気よ」
温子の隣では彼が、何が起きているのかわからないとった表情で立っている。
「そちらは?」
美弥は、温子の肩越しに遠慮なく彼の顔を見つめる。
「ハイ……彼は……」
温子は顔を赤くしてうつむきながらぼそぼそと言うと、美弥は意地の悪い表情を浮かべ再び彼の顔を見つめる。
「ハハァン……都から聞いているわよ、彼がそうね?」
いつの間にか彼の隣に立つ美弥はそういいながら彼の顔を舐め入るように見る。
「……何か?」
彼はちょっと頬を赤らめながら美弥の視線に対応する。
「フーン……」
美弥は鼻を鳴らしながらいきなり彼の腕を取り、自分の胸を彼の腕に押し当てる。
「うぁぁあ」
彼は一瞬の出来事に身を引くが思いのほか力強い美弥の腕は振りほどけず、相変わらずDカップはあるだろう胸は彼の腕を包み込むように変形したままだ。
「ちょっ!」
温子の表情も険しくなる。何しているの? 声を出そうとするが、その目の前の刺激的な光景が温子の言葉を失わせる。
「フフ、可愛いわね? 温子この人良い目をしているわ……気に入った」
美弥の顔に妖しい表情が浮ぶ。
「み、美弥さん?」
温子は美弥の胸から解放された彼の腕に無意識に抱きつく。そして温子の脳裏に嫌な予感がよぎる。
まさか、美弥さん彼のことを……。
美弥には前科がある、といっても温子が直接被害にあったわけではないが、友達の彼が美弥に横取りされたという経緯を聞いたことがある。
「うふふ……良いわねぇ、完全にあたしの好みの男よ」
今にも飛びつきそうな目をしている美弥、何となく眼も潤んでいるようにも見えるし、彼はまるで蛇に睨まれた何とかみたいに固まっている。
「美弥さん、彼はあたしのフィアンセなんです、変な事考えないでください!」
温子の声が思わず大きくなる。
周りにいた人の視線が三人に向けられているみたいに感じる、でも、これだけは譲れない彼はあたしのフィアンセなの、他の人になんて絶対に渡さない!
温子の表情は一層険しくなり、まるで敵をみるような目で美弥を見る。
「別にあたしは気にならないわよ? 人のものであれなんであれ……それが人の旦那でも、あたしは気にしないわよ?」
「気にしてください!」
再び温子の声が大きくなる。
「アハハ……まぁいいわ、またどこか出会いましょう、ねっ、旦那?」
美弥はそれだけを言いウィンクを彼に飛ばしながら二人に手を振りながらその場を去っていく。隣ではヒラヒラと彼が手を振っている……キッ!
「……誰?」
まるで今まで金縛りにでもかかっていたかのように動けなかった彼が、美弥がいなくなったとたんに動き出す。
「友達のお姉さん!」
温子は憤慨まだやまずといった感じで言葉尻に怒りを表している。
「……もしかして、流氷に乗ってロシアに行こうとした人?」
「そんなこともあったわね!」
温子の一言一言には怒りが溢れている。
「あの人が……フーン」
彼のその一言に温子が反応する。
「駄目よ、あの人について行ったら、ぜぇったいに許さないからね!」
温子の目がさらに険しくなる。
=バレンタインデー?=
「いらっしゃぁーい!」
茜木鮮魚店前で元気な声を上げているのは彼。
「旦那……若女将どうしたんだい?」
源さんが声をひそめながら彼に声をかけている……まだサボっているわね?
温子の視線を感じたのか源さんは温子に背を向ける……。
「昨日からなんだよね……なんだか機嫌が悪くって……」
「なんでぇ、早速夫婦喧嘩か? 旦那最初が肝心だぜ、言う時はガツンといわないといけねぇ……がつんと……ってぇ〜?」
「がツンとねぇ」
源さんは彼の背後に立っている温子に気が付き、蒼い顔をしてその場から離れるが彼はまだ気が付いていない。
「あなた! 仕事!」
あたしがガツンと言うわよ!
「どうしたんだい?」
隣のお店のおばさんが温子の後ろで元気にお客さんの呼び込みをしている彼の姿を見ながら声をかけてくる。
「アァ、おばさん……ちょっとね?」
温子は笑顔を浮かべておばさんに声をかけている……つもりだがどこかその笑顔は引きつっている。
「夫婦喧嘩かい?」
おばさんは意地の悪い顔を浮かべながら温子の顔を見る。まだ夫婦になってもいないのに夫婦喧嘩もないでしょ?
「そ……そんな事ないよ……たぶん……」
温子は相変わらず引きつった笑顔を見せながらおばさんの顔を見る。
「……何があったんだい?」
おばさんが優しい顔を見せる……ありがとう、おばさん。
温子は、事の経緯をおばさんに話す。
「アハハハ……!」
おばさんの笑い声が市場に響き渡る……もぉ、おばさん笑う事ないじゃない、本人はいたって真剣なんだからぁ。
温子はプクッと頬を膨らませる。
「ゴメン……でも……若いねぇ、ウン、可愛い!」
おばさんはそう言いながら再び笑い声を上げる。
「だって……」
温子の顔に不安の色が浮かぶ。
「あっちゃんは、彼が好きでしょうがないんだろ? だからやきもちを妬くんだ」
やきもち?
「好きでなかったらやきもちなんて妬かないでしょ? だから『あたし以外を見てもらいたくない、あたし以外に彼に触れないでもらいたい』って思うわけよ」
好きだから……。
温子の顔がその台詞に対し顔を赤らめ答える。
「ほら、もてる彼……じゃない、旦那を持つと苦労するわね? うちなんて結婚してからそんな心配一度だってしたことないよ」
おばさんはそう言いながら自分の旦那さんを見る。
「ハハ、そんなもんですかねぇ?」
温子は苦笑いを浮かべおばさんを見ると、そのおばさんは残念そうな表情を浮かべながら首を振る。
「ホント、そんなもんだよ……ほら、あっちゃんお客さんだよ」
その言葉に振り向くとそこに立っているのは美弥だ。
「こんにちわぁ〜」
美弥は、温子の事など眼中にない様に彼に向って一直線に進む。
「アァ、美弥さん、こんにちは」
彼は困った笑顔を浮かべながら美弥を見て、その美弥の後ろで目を吊り上げている温子の顔を見る。
「嬉しいなぁ、あたしの名前覚えてくれたんだぁ……今日はこれを持ってきたの……ハイ!」
昨日とは打って変わった雰囲気の美弥は持っていた大きな包みを彼に差し出す。
「ハァ……これはどうも……」
彼は気の抜けたような返事をしてそれを受け取る。
「エヘヘ、今日はバレンタインデーだもんね? ちなみに本命だよ?」
バレンタイン……。
「あぁっ〜……バレンタイン!」
素っ頓狂な声を上げる温子に、彼と美弥が振り向く。
「温子ちゃん?」
彼は正直に驚いた表情を浮かべながら温子の事を見る。
「わ……忘れていた」
目頭が熱くなる、いや、既に涙が溢れているであろう……昨日からイライラしていたせいですっかりと忘れていた。
その一言に、源さんと美弥が呆れた表情を浮かべる。
「女将……旦那に忘れるなんて……新妻のくせに」
源さん、わかっているよ……。
その様子を見ていた美弥の表情が不敵な笑みを浮かべる。まるで勝ったというような顔だ。
「冷たい奥さ……」
「ゴメン、本命なら俺貰えないな……」
彼はその包みを申し訳なさそうな表情で美弥に戻す。
「エッ?」
意外そうな表情で美弥は彼の事を見る。
「だって、俺には……その……奥さんがいるわけだし……もし本命なら受け取る訳にはいかないよ、それはもっと違う人に渡したほうが良い」
彼は照れくさそうな表情で美弥を見る。
「あなた?」
温子はキョトンとした顔で彼の顔を見つめる、その視線の先の彼は優しい顔で温子の事を見る。まるで何事もなかったかのように。
美弥の表情は驚いた顔をしていたが、徐々にその表情に笑顔が膨らんでゆく。
「へぇー……」
美弥は満面の笑顔を浮かべながら温子の顔を見る。
「やっぱり気に入ったわ……本気で」
美弥はそういうと彼に抱きつき、彼の口に自分の口をつける。
「!!!」
温子はその状況が一瞬訳わからずその場に立ちすくみ、次の瞬間美弥から奪い取るように彼の腕を引き、美弥と同じ行動を取る。
「おっ、女将?」
源さんや隣のおばさんは呆気に取られたような表情を浮かべ、その様子を眺めている。温子の気持ちの中には恥ずかしいという気持ちはなかった、ただ、彼はあたしだけのものであってもらいたい。それだけだった。
「……」
彼に口をつける温子の瞳には涙が流れ、その涙は彼の頬に伝う。
「……フフ、諦めないわよ」
その様子を呆気にとられながらも、しっかりと見ていた美弥はそう捨て台詞のようにつぶやきながらお店を後にする。
=二人の記念日=
「温子、こっちに来て座りな」
神妙な面持ちの早苗が夕食の片付けをしている温子に声をかける。
「なぁに?」
エプロンで手を拭きながら温子は台所から顔を出す。
「いいから座りな!」
お母さんはそう言い、彼の隣に座るように指差す。何が始まるの? 隣にはお母さんと同じ様に神妙な面持ちをした彼が座っている。
「……」
温子はその様子にちょっと戸惑いながら指定された場所に座る、目の前に広がる机の上には堅苦しい雰囲気を持つ用紙が置かれている。
「ん? これは……」
温子はその用紙の表題を読み表情が硬くなる。
「お前はどうする?」
お母さんの表情は今までみたいに二人を冷やかすようなものではない。目の前に置かれている用紙の表題は、
「婚姻……届」
温子は神妙な表情でその表題を読み上げ早苗、そして彼の順に見る。
「……あんた達二人が決めることだ、無理強いはしない……」
彼がその届を穴が開くほど見つめている。
「……」
二人の間にしばらく沈黙が流れる。
「はは、ハンコがここで役に立ったよ」
そう言いながら彼はやおらその用紙に名前を書きハンコを押す。
「!」
驚いた表情を浮かべている温子を尻目に彼は一連の動作を終え、温子の顔を見る。
「……俺の気持ちは、これだけ」
さわやかな表情を浮かべながら彼は温子に向って微笑む。
用紙の『夫となる人の名』の欄にはあまりきれいではないが力強く書かれた彼の名前、その隣の『妻になる人の名』はまだ空欄になっている。ここにあたしの名前を書けば、あたしはあなたの妻になる。
「あ……なた……」
彼のそのさわやかな表情が温子の視界で揺らぐ……あなたの進むべき道はそこなの? あたしはあなたと一緒に歩んでいっていいの? あなたの伴侶としていて良いの? あなたの妻として胸を張っていいの?
温子は心の安らぎでもある彼の胸に顔を埋める。
=エピローグ=
「はい、受理しましたよ……二月十六日」
市役所に提出された書類はあまりにもあっけなく受け取られた。
「ありがとうございます……」
彼も呆気に取られた表情で窓口の男性に声をかける。
「呆気ない……よね?」
市役所を出たところで彼がほうけた顔で温子に声をかけてくる。今朝から降っている雪は既に白いじゅうたんを道に作り上げている。
「ホント……なんだか実感がわかない感じかも……」
今提出してきた書類は婚姻届……法的に二人が夫婦になった証。
「まぁ、まさかクラッカー鳴らしておめでとーって言う感じではないだろうなとは思っていたけれど……ちょっと拍子抜けかも……」
温子もちょっと拍子抜けした表情を浮かべる。
「でも、ついに温子は俺の奥さんになったわけだ……」
感慨深い表情で彼は温子の事を見る。
「はい……ふつつかものですがよろしくお願い致します、あなた!」
温子はそう言い、彼の腕に抱きつく。
「こちらこそよろしくね? 奥さん!」
彼もなんだかちょっと感慨深い表情を浮かべているかな? 結婚記念日は二月十六日、あなた忘れないでね?
「帰ってきたな?」
店先で源さんが二人を出迎える。
「お帰り〜若夫婦! 早速お客さんが来ているよ」
源さんの視線の先には美弥がにっこりと微笑みながら立っている。どうやら源さんに二人の行ってきた場所を聞いたようね。
「温子! いくら夫婦になってもあたしは諦めないわよ? 本気で惚れるなんてめったにないんだもん、彼はあたしの心のオアシスなのよ!」
美弥はそう言いながら彼に抱きつく。
「美弥さん、ちょっとぉ〜」
温子は慌ててその間に割り込む。
その間でやれやれとした表情の彼は、雪の降る朝市の空に向って白く濁るため息をつく。
「これからも色々ありそうだな?」
fin