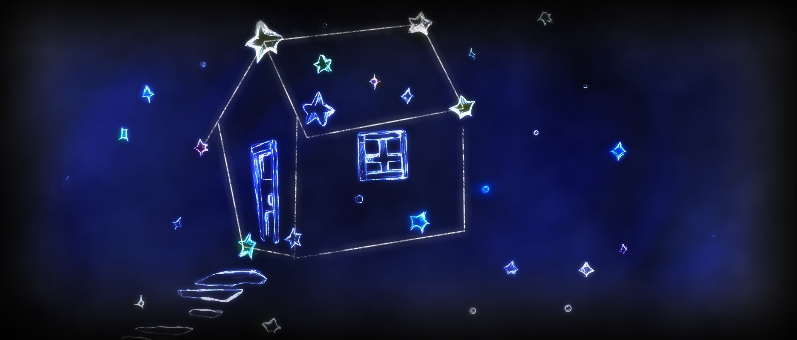《アリスとアーチュス》
- Aris - t - Archus -
大きな真鍮の珠が外れた瞬間、支えを失った全ての弧が崩れ落ちる。
見上げても最早、そこには何も残っていない。何もかもが壊れて消えた……
ポットのお茶も残っていない。お茶菓子は言わずもがな。
12もの惑星を1つ1つ丁寧に片づけていったのだから、当然か……しかし、ずいぶん話し込んだものだ。
「もう残っているのは、私たちみたいな小さな星屑だけね。きっと、見える景色も変わってるわ」
アーチュスがそういうので、私は窓から外を見ようと、カーテンの裾をそっとめくった。
明るい。太陽が失われているというのに、この明るさはなんだろう。
「これが宇宙に目を向けたとき、本来見えるべき景観」
アーチュスも、私の肩越しに外を見ていた。
私はここへ来るときに聞こえてきた言葉を思い出した。
月よりももっと強く輝いていた太陽が隠していたものが全て、今ここに広げられている。
天の川は視界の隅から隅まで流れるように走り、星の海が淡く全天を照らしていた。
「太陽の軛から私たちは離れた……この星空の仲間入りってわけだね」
「亜莉珠、私たちはこれから恒星の間隙を行くことになる。主星、父なる太陽を持たぬ存在になってね。
でも……行先はバラバラね。仕方ないわ、軌道傾斜角も違うんだもの」
私は無言で頷いた。窓を開け放つと宇宙の風を受けたカーテンが大きく翻る。ここから一歩踏み出せば……それは彼女との別れを意味しているのだ。
「一緒に太陽の周りを幾度も幾度も巡っている間……楽しかったよ、アーチュス」
「私もよ、亜莉珠。
銀河系を巡る内に、また出会うこともあるかもしれない……だから、またね」
そんな確率がどれほどあるだろう。それこそ1/この宇宙に広がる星の数にも満たないだろう。
だけど、そんなことは関係ない。私も彼女と同じ気持ちだった。
「……そうだね。お互いにいい旅をして、その間のことをきっとまた話そうよ。2人でお茶を飲みながらさ……なんなら今度は銀河の星を壊してまわるのも面白いかも」
そして最後に、もう1度だけお互いの目を見て
窓枠に足をかけ、果てなき星の海へと視線を移す。
別れの言葉は無しに、私たちはそれぞれの一歩を踏み出した。
Picture Märchen
- Aris - t - Archus -
《 アリス と アーチュス 》


古代ギリシャの天文学者。サモス島出身。紀元前310年ごろ~紀元前230年ごろの人。
15世紀のコペルニクスよりも1700年ほど早く「地球は太陽の周りを回っている」と唱えた。

小惑星番号3753。
アデン群に分類される地球近傍小惑星。
地球の準衛星の1つで、ケルトの部族集団クリフニャ族の名を持つ。

小惑星番号10563。
アポロ群に分類される地球近傍小惑星。
古代カルデアの太陽神の名を持つ、地球の準衛星の1つ。
地表からの見かけ上、その惑星を周回しているように見える小天体のこと。疑似衛星とも。
同じ主星の周りを公転しているが、公転周期が一致しているためにそのように見える。
あえて無視。