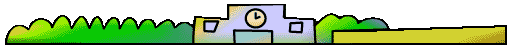
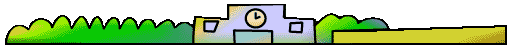
| 以前,PTA研修会で,ママポリスの話を聞くことがありました。 その中で,万引きをした子についての話がありました。 もう随分前のことではっきりとは覚えていないのですが,ある部分だけは鮮明に覚えている箇所があります。 話はこんな内容でした。 |
| 万引きをして,警察に連行された子を迎えにきた親の態度についていろいろなタイプを紹介された時のことです。 子を迎えに来たほとんどの親は子を叱ったり,殴ったり,または,逆に警察に何かの間違いだろうというような子をかばう態度をとったりするという話をされた後,一人だけ違う態度がみられたという話をされました。 ある万引きをした子を迎えに来られたのは,その子のおばあさんでした。 多分,なにかの事情で,おばあさんが育てておられたのでしょう。 そのおばあさんは,警察に来て,その子に会うなり,その子を抱きしめて, 「わしが悪かった。わしの育て方が悪かった。すまんことをした,すまんことをした・・・」 と,ただただその子に泣きながら謝るばかりだったということでした。 |
これは,きっとその子にとっては,殴られるより痛い思いをさせたのではないでしょうか。
もし,本人自身が本心から「悪いことをした」と情けない思いになるとしたら,叱るより,かばうより,このおばあさんの一言の方が可能性があるように思いました。
本当にその子のことを思うからこそ,万引きするようになってしまった姿を不憫に思い,そんな子にしてしまった自分自身のふがいなさを申し訳なく思うのでしょう。
だから,そういうところから出る言葉には人の心に届く命がともるように思います。
私も今までに二度ほど,
「先生が悪い。」
という話をしたことがあります。
確かにどちらも,クラスの子どもたちは,神妙に聞いていましたし,その後しばらくは特にしっとりとした人間関係になりました。
どちらも高学年でしたが,一度目は,男の子たちが少年野球の練習で,休みの日に学校に来て,どこからか職員室に入り,給湯室にあったコーヒー等を飲んだ事件(?)の時でした。
昔のことなので,よくは覚えていないのですが,なぜかそれが6年の男子がやったのだとバレてしまい,職員会で問題になり,担任の私としては,説教をしなければならない事態になりました。
問題の多いクラスでもあり,よく叱っていたので,この時も男の子たちはカミナリが落ちるのを覚悟していたようです。
その時,ふと(もう叱り疲れていたのかもしれませんし,まあ,これぐらいのことはいいじゃぁないかと思っていたようにも思います)
「こんなことをしてしまうクラスにした先生が悪い。」
という話をしました。
もう十分子どもたちは「自分たちが悪いことをした」ということは分かっているのですから,これ以上言うこともないのです。
そして,
「みんなの姿は,先生の姿なのだから,もうこれからはこういうことがないように先生も頑張る。今日は,先生が悪いと謝ったけど,もう,ここでこうして注意したのだから,今度こういう事件が起きたら,今度は,みんなのせいにして,思いっきり叱るので,覚悟しておいてほしい。」
なんてことを言ったように思います。
それからの一時期は,子どもたちとの関係が大変スムーズだったことを覚えています。
もう一度は,児童会の話し合いの場である,代表委員会があった後です。
前回とは違う学校でしたが,そこでも,やはり6年生の問題が出されました。
高学年として責任を果たしていないというような内容でした。
それに対して6年生が反論していると,後ろにいた教師が6年と言い合いを始め,とうとう6年の一人を泣かしてしまいました。
その後,チャイムが鳴り,時間だからと,その教師と他の学年の子たちは教室に帰っていきました。
後には,泣いている子一人と,シ〜ンとした6年生たち,それに,担任の私・・・
その日は,忘れもしない,2月3日。
節分の日で,みんなで食べようと用意していた豆をそっと出して,(とても今日は,これを食べるような雰囲気じゃないなァ・・・)と淋しく見つめていたのを覚えています。
一体何があったのかというような,嵐の後の静けさでした。
しかし,担任としては,ここで何か高学年としての自覚を高めるような説教をしなければなりません。
言いたいだけ言って,さっと帰っていった教師に(オイオイ,ソレハナイダロウ・・・)とは思いながらも,子どもたちの前に立ち,つい,こう言ってしまいました。
「まいったなぁ。」
子どもたちは,もう十分打ちのめされているように思いましたから,これ以上非を責める気にはなれませんでした。
そして,
「高学年として,しなければならないことがある。それができていなくてこのような問題が起きるのは,みんなにそれだけの力をつけられていない先生が悪いんです。」
と,生涯二度目の「先生が悪い」を言った後,
「今日から,また頑張ろう。」
のようなよくある話をしていきました。
子どもが自分で既に「悪い」と思っていれば,教師はもう「泣きっ面にハチ」のような説教はせず,「まいったなぁ」と共感(?)してやり,向き合うのでなく,一緒に同じ方向を向き,これからまた頑張ろうや,とローギアからの発進をしていけばいいのではないかと思います。
このことだけではなく,毎日起きる様々な小事件に対して,教師がどのような立場でどのような態度をとるかで,子どもたちとの心の距離も変わってきます。
この時も,この後子どもたちとの関係も,高学年としての行動もプラスの方向に向かっていったように思います。
この「先生が悪い」は,1年間に一度ぐらいなら効果があるかもしれません。
もし2年間の持ち上がりなら,2年に一度です。
これをいつも言っていては,ただの情けない教師でしかありません。
また,厳しい教師の場合ならこれも逆に意外性のインパクトがあるかもしれませんが,いつも優しい先生の場合は,なめられてしまいますね。
そして,できれば,こんなこと言わなくてすむようなしっかりした指導を毎日していきたいものです。