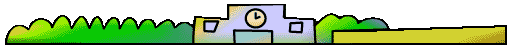
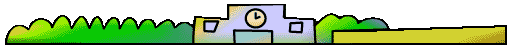
| 個人懇談内容に入れている項目の1つに「テストの分析」があります。 ここでいう「分析」とは知識理解や思考面がどうのこうのという話ではありません。 |
| 普通,テストを子どもが家に持って帰っても,家の方は(直して100点になっている前の)「点」を見られてある時は喜び,ある時は落胆されておしまいになっていることもあるのではないかと思います。しかし実はその「点」は正しく「理解」の程度を示しているとはいえない場合もあります。 なぜ間違っているのか どういう原因でそういう答を書いたのか を家の方に知らせることで,「理解不足,思考不足」だけでこの点になっているのではないという理解をしてもらいます。 そして,一番伝えたいのは,注意して丁寧に読み,よく確かめていれば点はもっとよくなっていた,ということです。 すると悪い点を見る見方も変わってくるはずです。 実際には次のようにします。 まず個人懇談までに,それぞれの子の「テストの答え方の特徴」を象徴的に表しているテストをピックアップして保存しておきます。 例えば次のようなミスをする子がいます。 テスト問題(6年生理科「動物のからだのはたらき」)
この答えに(酸素)と書いて×になった子がいます。その子になぜ酸素と書いたのかを後で聞いてみました。すると,
と答えてくれました。 こういうミスはよくあります。問題を単語で見て,思い込みで関連する事柄をさっと書いてすませるのです。「問題をよく読んで」と何度言ってもあります。そして,一度書いた答えはもうそれで完成していて,確かめを一応しても答えの方を優先したような確かめをしていきます。頭脳より性格で点が変わってくるのが小学校です。 懇談ではそんなことは言いませんが,「こういう惜しい間違いをすることがある」ということをテストの実物を見てもらいながら説明していきます。 そして大事なのは,こういう分析だけで終わってしまわないことです。そういう実態から,今どのような取り組みを学校ではしているかをはっきり伝えなければなりません。 私の場合は,注意ミスが続く子にはオリジナルのトレーニングプリント「たしかめ君」に取り組ませることにしています。これは学習問題とは全く違う次元での「文章を注意深く読むようになるための」トレーニングを目的に作ったものです。まだその効果がはっきりと確かめられたわけではないので,ここでの公表は避けますが,そのうちこのトレーニングの効果が確認された時には,またここで紹介したいと思っています。 |