| 3月31日(土)晴れ 1440、銀座。テアトルシネマで「今宵、フィッジェラルド劇場で」。ロバート・アルトマン監督の遺作。自らの死を予感したかのような、死と終焉の物語。 1730。日本橋三越のクラブハリエでバウムクーヘンを。東京では日本橋三越にしか売っていないのだ。1800、SPACE早稲田に寄って、O路恵美に差し入れ。今日が楽日。「頑張ります」と笑顔。 1900、下北沢。「劇」小劇場で、椿組「なつのしま・はるのうた」。鄭義信の作品を松本祐子が演出。軍靴の足音が近づく南の島。戦時下でもたくましく生きていく理髪店の4姉妹の青春。月光舎出身の岡村多加江がいい役。 楽日前とあって、客席はびっしり。通路を取っ払って椅子席補充。出口なし。「なにかあったら怖いですね」と隣席の写真家・宮内氏と。 終演後、出口で松本祐子氏に挨拶して家路に。 ヴィレッジ・ヴァンガードで高橋葉介「夜姫さま」、星野之宣「神南火」。 3月30日(金)晴れ 朝のうち小雨。 JクリップのK谷氏と何度か電話連絡。 1830帰宅。 新聞夕刊の一面で「憲法改正の国民投票法案、今国会で可決の見通し」の大見出し。この期に及んでも日本のマスコミは「客観報道」。自民党の憲法改正の主眼が第9条にあることは明々白々。国民投票法案が可決されたら、憲法改正まで一瀉千里。それでも、「憲法擁護」の論陣を張らないのか。国民投票の前にはマスコミの報道も規制されるのだ。政権与党の憲法改正案が批判できないではないか。 「民主主義の多数決原理」と「裁判所の違憲立法審査権」は矛盾しないか。こんな問題が娘の短大の期末試験で出たとか。 国会の多数決で決まった法律なのに、なぜ憲法に違反したら無効になるのか。その答えは、「日本は立憲主義国家だから」というのが「正解」とのこと。 憲法はすべての法体系の上位に位置する。「多数決原理」がすべてなら、時の政府は国民を縛り付けるどんな法律だって作ることができる。それに歯止めをかけるのが憲法。だから憲法を変えるという事は、国家体制を変えるのと同じ。今の憲法の三大柱「主権在民」「平和主義」「基本的人権の尊重」。このどれもが欠けても、国民の自由と民主主義は崩壊する。自民党の狙いは「平和主義」の放棄にほかならない。平和主義が捨てられれば、基本的人権もそれに伴って棄てられる。「戦争ができる国」に「基本的人権」など不要だもの。 平和憲法はもはや風前の灯火なのか。恐ろしい時代が目前にある。 3月29日(木)晴れ 今週の週刊現代の記事で「ラジオは脳を活性化させる」に興味がひかれる。 音声だけのラジオが脳を活性化させるのは音という限られた情報からイメージを膨らませる力が自然と養える……ということは昔から言われていたことだが、脳神経的にもそれが実証されているという。 つまり、耳から入った音声は側頭葉の聴覚野で音として認識される。次に側頭葉の言語野で「言葉」として認識される。視覚的な創造をするために側頭葉連合野が働き、熱い冷たいの感覚を表す言語には頭頂連合野が反応する。 音声情報のみのラジオはこうして無意識のうちに脳を活性化させる。その中でも重要なのは前頭葉にある前頭前野という部分。人間にとってもっとも大切な意志や意欲を司る部位。記憶を司る「海馬」とも密接に関わっている。また他人の気持ちを理解するということもこの前頭前野の働きによるという。 要するにラジオを聴けば、自然と前頭前野が鍛えられ、モチベーションも上がり、コミュニケーション能力も上がるということらしい。 「ながら勉強」も実は脳を鍛えるのにいいとか。確かに、10代の頃はラジオの深夜放送を聴きながら勉強したものだが、「脳力」が落ちるにつれ、同時に二つのことをやるのはしんどくなる。いまやラジオのDJどころか、音楽を聴きながら日記を書くのもかなりきつくなっている。日記を書くときには音楽を止めなければ書けないということは「脳力」が低下している証拠だろう。 イヤホンで音楽を聴きながら勉強している娘を見て「本当に頭に入るのかな?」と思うのだが、まだ脳が若く、同時並行でも受け付けているのだろう。ウーム、うらやましい。 今でも幼児期に見た光景や会話を鮮明に思い出すことができるが、それはもしかしたら、5歳頃からラジオに親しんでいたからなのかもしれない。7歳の頃に聴いたラジオドラマのテーマソングや物語情景をはっきりと思い出すことができるし、昔住んでいた家の間取りや家の中の様子が写真で撮ったように思い描くことができる。これはラジオドラマ効果? 1900、新宿。紀伊國屋ホールでラッパ屋「妻の家族」。 「母危篤」の「メール」で駆けつけた5人の子供たち。母が2回再婚しているので、父親が違う兄弟姉妹の関係がややこしい。本人にもまして、夫や妻はなおさらのこと。2週間前に知り合って末娘(岩橋道子)とバタバタと結婚した引きこもり中学教師(福本伸一)にとっては、新妻の家族は複雑怪奇。ほかの兄弟姉妹にも様々な事情があり、生家を売り、遺産分けに与りたい様子。ところがある事件が起こり……。 大人数の登場人物を個性豊かに描き分ける鈴木聡の名人芸。珍しく、舞台で本水を使い、登場人物がザブンと飛び込むシーンが繰り返され、これがひとつのアクセントに。役者のアンサンブルは呆れるほどうまく、これだけ密度の濃い集団劇を演じられるのはラッパ屋くらいのものだろう。今回は特に岩橋道子が健闘。昔から華のある女優だが、他流試合が多いためか芝居の幅が広がっており、大化けの予感。 ほんわかと、あたたかなぬくもりを感じさせる人間喜劇。2125終演。広報の吉田さん、制作の山家さんに挨拶して家路に。 3月28日(水)晴れ 0730、起床。ゴミ出し。1100まで二度寝。 昼から家人と町を散歩。ペットショップでイモリのエサの冷凍赤虫を。40個で130円。 レゲエのRomieの動画を探しているうちに、音楽専門のYOU TUBEサイトを見つけたので、あれこれ検索。60年代の海外ポップス、ロックの動画もあり、これは宝の山。 思えば、1960年代に海外ロックの映像を見るということはほとんどできなかったわけで、1969年頃、北海道放送(HBC)の深夜番組「ロックンロール・エクスプロージョン」でレッド・ツェッペリンやディープパープルを見た時の衝撃は今も忘れられない。NHKで「ヤングミュージックショー」が始まる前のこと。当時、日本で海外ロックバンドの映像を見ることなんか不可能だったのだ。 で、YOU TUBE。なんとも嬉しいことに、60年代の歌姫、シルビー・バルタン、「ダウンタウン」のペトラ・クラーク、フランソワーズ・アルディの3人が60年代ポップスのメドレーを歌っているシーンなど涙もの。ロネッツ、ナンシー・シナトラ、ママス&パパス、シュープリームス、フランク・ザッパ……。すごい。夢を見ているような映像の数々。当分楽しめそう。 城山三郎氏に続いて、「気骨ある昭和の男」が亡くなった。植木等80歳。父親は浄土真宗大谷派の住職であり、水平社運動に参加、戦前戦中を通じて反差別・反戦を貫いた反骨の士。植木等もまた盟友・青島幸男とともに、戦後民主主義を体現した人であった。右傾化の流れに身を挺して抵抗した城山氏、そして植木の死……。 25日朝、能登地方地震を受けて、官邸は対策室を設置。塩崎官房長官と的場副長官が駆けつけたはいいが、記者団に発した第一声は「大したことないようだ」 溝手防災担当相にいたっては選挙区の広島市長選の応援に出かけ不在だった。その溝手大臣、慌てて26日、輪島市などの被災地へ視察に出かけたが、記者団に「人命(被害)は少なかった。1人だから」と述べた。地震の規模に比べて死者が少なかったことを強調したかったのだろうが、「一人の死者ですんだ」とはあまりにもデリカシーに欠ける発言。 で、安倍首相。この溝手発言について記者団から「不適切発言ではないか」と問われると、「死亡された方が1人でよかったという意味なんだろう」とフォローした。溝手発言の何が問題なのかわかっていないのだ。遺族への配慮もなければ、読解力もない。バカとしか言いようがない。 さらに、従軍慰安婦問題。 安倍は今月16日、1993年の河野官房長官談話について、「軍や官憲による強制連行を直接示すような記述は見当たらなかった」との政府答弁書を出した。記者とのやりとりでも「狭義の強制はなかった」などと言った。しかし、これにはアジアのみならず欧米も反発。 安倍は97年にとんでもない発言をしていることも発覚した。 『韓国にはキーセンハウスがたくさんあって、そういうことをたくさんの人たちが日常どんどんやっている。私はとんでもない行為ではなくて、かなり生活の中に溶け込んでいるのではないかとすら思っているんです』 自民党若手議員らが作った『歴史教科書への疑問』という本の中に出てくるから隠しようがない。韓国の国会議員、ウリ党のユ・キホン議員が来日し、外務省に抗議書を渡す騒ぎになっている。 米国では、慰安婦問題について下院で謝罪要求決議が議論されているだけでなく、ワシントン・ポスト紙は24日付の社説でこう書いた。 「拉致問題で国際的な支援を求めるなら、日本の犯した罪の責任を素直に認め、被害者に謝罪すべきだ」「安倍が日本の責任を軽くしようとしているのは奇妙で不愉快」 英エコノミスト誌もこう論評した。 「中国、韓国にたくみに接近した安倍はすべての善意を台無しにした。彼には聞こえていないのだろうか。1990年代になって、女性たちが沈黙を破り、勇敢に語り始めたことを。記憶喪失は現代の民主的な日本にはふさわしくない。恥を知れ、安倍氏よ」 26日夜、安倍首相は「拉致問題は現在進行形の人権の侵害だ。(慰安婦問題は)全く別の問題だ」とワシントン・ポスト報道に反論したが、夜郎自大とはこのこと。このトンチンカンな反論こそ国辱ものではないか。 3月27日(火)晴れ ヘンな夢を見ていた。 ぼんやりと空を見上げていると、雲の形が変わり、四角くなる。その雲がまた形を変えて、矢の束のようになる。その矢が上空から次々と落下する。その数秒後、ドーンという爆発音。そうか、あれは爆弾だったのか。 遠くのビルの壁が崩落する。会社の同僚に知らせなくてはと思い、会社に行く。エレベーターは危険なので、階段を上る。なぜか古いビルの螺旋階段。 ドアが開き、中に入ろうとすると、目の前に会社の先輩のSさんが立っている。Sさんは10年ほど前に亡くなったはず。しかし、その姿は実にリアル。「雨に打たれたら危ないから」と、放射能測定器を頭からかぶせようとする。しかし、「君は濡れていないからいいよ」と、列からはじかれる。見ると、同僚のMSさんらが頭からずぶぬれになって立ちすくんでいる。 「帰らなきゃ」と思い、螺旋階段を下り始める。フロアを一つ下りるたびに、自分が1歳ずつ若返るのがわかる。鏡に映った顔。しかも、会社を退職した人たちが次々と目の前に……。 先行きへの不安の表れか……。 電車の行き帰りにiPodで「マーダ」のリズム。しばらくははまりそう。 1745、茅場町で東西線に乗り換えようとしたらホームがごった返している。電車の架線にビニールが張り付いたため上下線ともストップしているとか。差し入れ用に、日本橋三越でハリエのバームクーヘンを買おうと思ったがこれでは時間がない。SPACE早稲田の電話番号がわからないので、橋本Mさんに電話すると、彼女も馬場で立ち往生とか。しばらくして電車が再開。時間ギリギリでSPACE早稲田に到着。 流山児★事務所「リターン」。舞台を挟んで両サイドに客席。 席を確保してから外に出てコンビニで買ったおにぎりを。 開演前に、M新聞のT橋さん、鄭義信と雑談。義信作の椿組公演は明日が初日。 電車事故の影響も加味して1908開演。 オーストラリアの戯曲だが、カナダ演劇「ハイライフ」とよく似ている。民族問題、同性愛問題も内包し、表現は暴力的。レグ・クリップのこの戯曲を初めに見つけたのは民芸の役者だそうだが、さすがに民芸では上演できず、流山児★事務所に持ち込まれた経緯があるらしい。 深夜最終電車に乗り合わせた5人の男女。刑務所から出てきた2人の男、劇作家、主婦、法律を学ぶ女子学生。 一見無関係の5人の間に張り巡らされた見えない糸。その糸が終幕になった顕在化する。そのスリリングな展開。芝居の終盤までほとんどセリフのない塩野谷正幸と、終始しゃべり続けの千葉哲也の息詰まる対決の迫力。今回の舞台を統べるのは千葉哲也の「官能」だ。 女子大生役の大路恵美も体当たり演技。千葉とのラブシーンもある。9年ぶりのリターンマッチは完勝か。 1時間35分。終演後、劇場で飲み会。高橋、西堂、義信、塩野谷らと歓談。「原田芳雄さんを何としてでも口説き落とし、昭和三部作をやりたい」という流山児。ぜひ実現してほしいものだ。原田さんが出るなら、毎日でも稽古場に通いたい。 お酒を飲めない大路さんは飲み会に参加せず早めに帰るので、しばし立話。9年前の初舞台はプレッシャーでほとんど記憶にないといってたが、「今回は大丈夫。記憶がありますから」と笑顔。気取らず飾らず。女優にしては実に性格がいい。2002年に有事法制反対アピールの賛同者43人の一人として、2003年にはイラク派兵反対アピールの賛同者50人の一人として、それぞれ名を連ねている。その平和と反戦意識の高さは吉永小百合と似ている。もっともっと活躍して欲しい女優さんだ。 2230、解散し、西堂、高橋さんと駅まで。 3月26日(月)晴れ 1800、新宿。タワーレコードでCDを物色。R&Bのディーバも食傷気味。しっとりとしたバラード「WITH U」が聴かせる「YU.KI.KO」の初フルアルバム「babyliclous」に食指が動くも、買うには至らず。 レゲエコーナーでminmi以来の強烈なディーバを発見。その名もRomie。女性二人組「HEMO+MOOFIRE」が強烈プッシュするダンスホール・シンガー。ハイトーン・ボイズとキュートなルックス、キャッチーなメロディーセンス。これは久しぶりに胸の高鳴り。 MURDA(マーダ)なるリズムをフィーチャーしたアルバム「MURDA V.A」に収録。ジャマイカ勢に加えて、ベテラン、ランキンタクシー、北海道出身の女性DJ、イロコマネチが参加する全編「MURDA」リズム・アルバム。まるでアフリカ原住民の太古のリズムを思わせる「マーダ」。これはクセになりそう。 合わせて、大瀧詠一のCMスペシャルを特集している「レコードコレクターズ」を買う。 1830、「信濃屋」でカレイ煮定食850円。 1900、紀伊國屋サザンシアターで「産隆大學応援団」。フジテレビの深夜番組を舞台化したもの。架空の産隆大學のつぶれかかった応援団員たちが織り成すドタバタコメディー。 幕が開いた瞬間、ありゃあ……。料理の仕方によっては面白くなる素材なのに、演出が……。盛り上がるべきオープニングの歌とダンスが……。演出は「THE WINDS OF GOD」の今井雅之。いい役者なのに……。セットなしのほとんど素の舞台。テレビの公開バラエティーを見ているよう。 アナクロだが憎めない。辞めたいという団員も、そのままヤキを入れることなく辞めさせるし、辞めた後のフォローも忘れない。ある意味で「民主的」な応援団員たち。各人の恋の悩みに全員で体当たり。最後は「気合い」で大団円という構成は悪くないのだが、いまひとつ物足りなさが……。 2110終演。 3月25日(日)雨 躰道稽古休み。 家人と買い物など。 午後から理容室で散髪。3カ月ぶりか。 能登半島で大地震。志賀原発が休止中だったことは不幸中の幸い。もし稼動中だったら……。 3月24日(土)晴れ いつものように0600の電車で出勤。昨日買ったPASMO定期で改札を通過。この便利さ。しかし、自分の一日の行動が捕捉されるという不気味さも……。 朝、伊野尾さんに電話。昼公演に行く旨連絡。「ちょうどよかった。今日はシーザーも来るって言ってましたよ」と伊野尾さん。 早めに仕事を終えて、1415、神楽坂へ。1500から万有引力の伊野尾さんが出演している「ダンス01」公演「デュオ〜2つの身体が出会う時〜」へ。もしかしたら01年に竹屋啓子CDCを改称して「ダンス01」になって以来初めて見ることになるのか。 会場はシアターIWATO。5分前に駆け込み。 後ろの席にシーザーと小林拓。見渡すと万有引力の役者や蘭妖子さんなど身内多数。懐かしや森脇希利子も。 笠井瑞丈+工藤丈輝、岡庭秀之+ケイタケイ、伊野尾理枝+関雅子それぞれの組み合わせによる実験的ダンス公演。舞踏の笠井叡の息子という笠井瑞丈のしなやかな肉体。工藤丈輝の極限まで鍛え抜いた肉体とのコラボレーション。研ぎ澄まされた岡庭の肉体と練熟のケイタケイ。 休憩15分。佐伯隆幸氏がシーザーに「珍しいとこで会うね」と笑顔で話しかける。シーザーは新宿で打ち合わせがあるため、中抜け。 第二部は伊野尾と関の「二人で一人」のツインズ。それぞれ片手で袱紗を開き、結ぶユーモラスなパフォーマンスから絶妙なツイン・ダンス。前二者の舞踏の緊張感から解放され、客席が暖まる。 1700終演。外で希利子や蘭さんと立話。「ふぐを食べにつれてってくれるって言ってからもう20年ですよ」と希利子。すっかり忘れてた。前に会ったのが川崎チッタで行われた、オートモッドのジュネのライブ。あれから10年? 伊野尾さんが出てきたので挨拶。次の予定があるので、急いで電車に。こんなとき、発券売り場に並ばずに済むパスモは確かに便利。 1750、初台。新国立劇場小劇場。1800開演にギリギリセーフ。遊座旗揚げ「いとしの儚」。さくら大戦シリーズの広井王子らが主体になったプロデュース公演。横内謙介の旧作を、声優の横山智佐が熱望して実現。主演はもちろん横山智佐。生まれてこの方バクチで負け知らずの鈴次郎(山中崇史)が、勝負に勝った鬼から、人間の死体を集めて作り上げた絶世の美女「儚」を手に入れる。しかし、生まれて100日目が来る前に儚が男を知れば、その体は水となって消え去る。 鬼との双六で勝利し、絶世の美女を得たものの、鬼と約束した百日を待たずに契ったため、美女は水となって流れ去ったという紀長谷雄(きのはせお)の「続教訓抄」を元にしたもの。 初演時は井川遥主演、杉田成道の演出だったが、今回は茅野イサム演出。 基本的には変わっていない。というか変わりようがない。 いかにも横内らしい戯曲で、生真面目な学級委員長が、ちょっとワルぶってみましたというような台本。 「右の浅田次郎、左の横内謙介」。そのメンタリティーは似ている。ハーレクインもどきで客を泣かせられると思う、そのタカをくくった大衆迎合主義が嫌い。 2時間15分。隣席の業界人らしい男の高笑いがカンにさわる。その男、途中で涙をぬぐっていたが、どうして泣けるのかまったく理解不能。 ただし、横山智佐はいい。カーテンコールで舞台にひざまづき、感無量の面持ちで客に感謝する。その意気やよし。 2015終演。家路に。 奥田英朗の「邪魔」読了。ある放火事件が発端となって、一人の主婦の生活が足元から崩壊していく。保身を図る企業、その犠牲となる一人のサラリーマン。そして警察と暴力団の対立。主人公の刑事・久野が実に魅力的。読み始めたら止まらない。さすがは奥田節。 2200〜2330、ETV「あしたのジョーの、あの時代」 37年前の伝説の「力石徹葬儀」が、いま講談社で蘇る!! 発見!梶原一騎 幻の原稿! 力石葬儀 44枚の写真! というわけで、1968年から73年まで少年マガジンに連載され、団塊世代の学生たちに大きな影響を与えた「あしたのジョー」を通して団塊の世代の心の軌跡を読み解いていこうというもの。 1970年3月24日、主人公・矢吹丈のライバル・力石徹の「葬式」が行われた講談社講堂に当時と同じリングを設置し、その上で司会の夏目房之介とゲストが語り合う。 しかし、このゲストが最悪。当時の民青ゲバルト部隊の宮崎学や格闘好きの夢枕獏はまだいいとして、残間里江子、猪瀬直樹はなんだ。体制の寄生虫に「あしたのジョー」を語って欲しくない。案の定、残間は「ジョーの立身出世主義は垢抜けない」と発言。その無知蒙昧ぶりを宮崎学にたしなめられ、赤っ恥。猪瀬に至っては当時の神田川同棲時代を臆面もなく話すだけ。元信州大全共闘議長が笑わせる。こういったウジ虫を出演させてバランスを取ろうというNHK。番組の程度がわかろうというもの。 わずかに収穫は、高石友也がステージ上で学生たちに吊るし上げられている映像を見たこと。反戦フォークの旗手たちが、反戦派学生の異議申し立てに苦慮する。メジャー化と反戦の整合性をめぐっての対立。まさしく「自己否定」の時代を如実に表わした映像。 1時間半もあるのに、中身は疑問符だらけ。寺山修司の「誰があしたのジョーを殺したか」もさらりと触れるだけ。 どうにもイラだちが募る番組。 折りよく、ちょうどこの日に合わせたかのように昭和精吾さんから1999年放映のCS放送、アニマックス「力石を殺したのは誰だ!?」が届く。さっそく拝見。 ETVと同じく「あしたのジョー」をモチーフに、時代を読み解こうとする構成。ちばてつや、内田勝ら出演者も同じ。ETVが参考にしたか。 しかし、志が違う。中心に寺山修司の「誰が力石を殺したか」をきっちりと据えており、昭和さんの朗読もおざなりな扱いではない。 東由多加さんもインタビューに答えている。そうか、このときはまだ存命だったのだ。 番組の締めくくりは寺山修司の弔辞「誰が力石を殺したか」の朗読。背中に電流が走る。 「誰が力石を殺したか」 寺山修司 力石はスーパーマンでも同時代の英雄でもなく、要するにスラムのゲリラだった矢吹丈の描いた仮想敵、幻想の体制権力だったのである。 丈の風来橋の下での生活、あの犯罪の日々、交番襲撃から集団窃盗、そしてじぶんの血を売って丈をボクサーにしようとした片目の丹下段平の父性への裏切りといったものが、しだいに「あしたのために1」といった紙片による学習へと綱領に組み込まれ、二流の技術のために一流の野性を失ってゆくことになったのである。 「あした」を破産させられたあしたのジョーはどうするか? また新しく幻想の敵を獲得し、水前寺清子のように♪東京でだめなら名古屋があるさ……と うそぶきながら、トレーニングにはげむか? それともスラムへ帰って昔の仲間たちと解放の夢からはなれて暴力団にでもはいるか? かつてのチャンピオン小林久雄のように浅草のなかを肩で風切りながら、ときにはテレビのボクシングを見て感傷するか? 力石は死んだのではなく、見失われたのであり、それは七〇年の時代感情の憎々しいまでの的確な反映であるというほかはないだろう。東大の安田講堂には今も消し残された落書きが「幻想打破」とチョークのあとを残しているが、耳をすましてもきこえてくるのはシュプレヒコールでもなければ時計台放送でもない。矢吹丈のシュッ、シュッというシャドウの息の音でもない。ただの二月の空っ風だけである。 (昭和精吾さんのHPから) この小気味良い寺山節! ああ、今この時代に寺山修司が生きていたなら……。 3月23日(金)晴れ 毎日新聞1面トップは「東電、78年に臨界事故」「7時間半停止せず 制御棒5本脱落」。78年に定期検査で停止していた福島第一原発3号機で臨界事故が起こったことを隠蔽していたという。29年前にすでに日本初の臨界事故が起こっていたのだ。 それをひた隠しにしてきた東電。原発事故の中でも臨界事故は炉心溶融につながりかねない重大事故。それを隠すとは。「原発事故は1万年に一回」とはよく言うよ。知らないうちに周辺住人は被爆していたかもしれないのだ。 1800。銀座。定期切れなので、PASMO定期に切り替え。JRと地下鉄を網羅しているわけで、今までのSUICAは不要になる。ウーム。便利? 1830、ル テアトル銀座で「セレブの資格」。 舞台は階級意識の残るイギリスの片田舎。前伯爵夫人フェリシティ(若尾文子)の息子ナイジェル(小林十市)がハリウッド女優のミランダ(愛華みれ)を婚約者として伴って戻ってくる。ところがミラ ンダはメイドのモクシー(柴田理恵)の絶縁状態にある実妹だった。ウソで塗り固めた妹の経歴。20年来屋敷に仕えるモクシーは二人の結婚に反対し、屋敷から出て行こうとするが……。さすがはノエル・カワードのコメディー。よくできている。ミランダが到着してからの展開は喜劇のお手本。前半は執事役の綾田俊樹のセリフがおぼつかなく、ハラハラするが、終わりよければすべてよし。若尾文子はやはり堂々たる大女優。どっしりと構えた風格ある演技。性悪女の愛華みれ、ナイジェルの従弟・小林高鹿もいい。学会信者の柴田理恵が「神の名において……」などとセリフを言うとき、どんな心情なのか……。 2135終演。帰り、ひまわりの林さんと立話。 3月22日(木)晴れ 1500、早めに退社。D議員会は欠席。 1620、K記念病院で鍼。 帰宅し、その足で、通夜へ。幼稚園の元園長が昨日亡くなったとのこと。タクシーに乗ると運転手さんが、「そうですか、一週間前に乗せたばかりですよ」と。高齢の妻を介護施設に預け、一人暮らしをしていたが、見舞いに行くときに駅までタクシ−を使ったのだそうだ。「1メーターですけど、足が不自由な方は駅まで歩くのも大変ですからね」 焼香の列は意外に短く、ものの5分で退席。帰りはバスで。子供たちが園児の頃の園長先生。いろんなことがあったが、すべては過去。今は冥福を祈るばかり。 3月21日(水)晴れ 祝日。0750起床。ゴミ出し。その後、夕方までウダウダと。なぜか眠くて眠くて……。1630、家人と買い物。この頃は日ものびて、暗くなるのが1700過ぎ。 休みの日はどうにも気力がなえてしまう。なぜだ? 3月20日(火)晴れ 1630、新宿。バルト9で「デジャブ」。新宿東映が「バルト9」なるシネマコンプレックスに生まれ変わっていたのを知らなかった。7階以上は今風のシネコン。 で、「デジャブ」。新機軸のサスペンスと思いきや、ビックリ仰天。なんとタイムパラドックスもの。しかも、この手の作品の古典ともいうべき「夏への扉」とほとんど同じ構造。まあ、確かに「デジャブ」ではあるけど、タイトルに使うか?普通。ウーン……。 1930、下北沢。スズナリでKudan project「美藝公」。筒井康隆の原作をもとに、天野天街が脚色・演出……となるはずだったが、台本ベタ遅れ。ついに、原作は概略だけを拝借。ほとんど無関係の舞台に。なにせ、名古屋公演10日前に台本があがったとのこと。 ヤジさん、キタさん2人が登場するのは「真夜中の……」と同じ。台本を書こうと苦吟するヤジさんは天野そのもの。いわば、同時進行ドキュメント。ただし、奇想天外な映像や、ループ感覚など天野ワールド全開。1時間30分。これはこれで十二分に楽しめる。 2110終演。ロビーで天野氏と雑談。帰りは伊藤氏と駅まで。 3月19日(月)晴れ 原発事故隠し、どこまで続くのか。 99年の北陸電力・志賀原発1号機の臨界事故で、当時の発電所幹部らが、「2号機の着工を数カ月後に控えていたため」などと、同社の事故調査対策委員会(委員長・永原功北陸電力社長)の聞き取りに対し隠蔽の動機を話したことが分かった。 事故2カ月前の99年4月に通産省(当時)が原子炉設置を許可。あとは、安全協定を結ぶ地元自治体の了解と通産省による工事計画認可の2つの必要な手続きが残っていた。要するに、事故を公表すれば住民が態度を硬化させるから、というわけだ。 住民の命よりも、会社が大事という動機。もしも、大惨事につながっていたら、と思うとゾッとする。どこが安全でクリーンなエネルギーなのか。ボロボロ出て来た事故隠しは原子力行政の最低限の自浄構造「情報公開」を踏みにじるものだ。 情報を隠蔽し、自分たちの都合のよい情報を垂れ流すことは、住民無視ということ。 今ごろになってタミフルの規制を始めた厚労省にしても、その副作用について以前から情報を集めていたはず。その情報の隠蔽が新たな犠牲者を生み出したのだ。薬害エイズと同じ。驚くことに、タミフルの中外製薬に厚労省から天下った元課長は薬害エイズ裁判でも名前が出て来たいわくつきの人物。00年にタミフルが認可され、03年に中外製薬に天下っている。 どうみても灰色な印象を受ける。 松岡「還元水」大臣の事務所費問題。19日の参院予算委員会で菅義偉総務大臣がこんな答弁をした。 「お茶やジュースは消耗品費だが、ミネラルウオーターは光熱水費。ミネラルウオーターはお茶やジュースとは明らかに違う」 政治資金収支報告書を所管する担当大臣がミネラルウオーターなら事務所の光熱水費に計上しても問題なし、との見解を示したのだ。これを牽強付会といわず、何をいうのだろう。それじゃ、ミネラルウオーターでお茶をいれた場合は消耗品なのか光熱水費なのか。 1600、上野「癒処」でマッサージ。アメ横で明太子などを。 1800帰宅。 3月18日(日)晴れ 0900〜1200、躰道稽古。審査や研修と重なり、参加者は10数人。高1の新人が見学。途中から稽古に参加。58歳のH崎先生がスクワット、腕立て臥せなど、体力訓練を。柔道部だったという高1生だが、さすがの10代も58歳のH崎先生の体力には遠く及ばず。H崎先生についていけずヘトヘト。「先生は何歳なんですか?」とバテバテ状態。さて、最初から絞られて、残れるかな? 1330帰宅。花粉症が出始め、全体に熱っぽく、不快感。「放課後」を見ようと思ったが、途中で断念。「やの雪」のCDを聴きながらベッドに。うつらうつらと仮眠。 1600、起きてから「放課後」を見始める。70年代に文芸坐で見たのだったか。16歳の高校生の少女の淡い恋心が、若い夫婦の間に微妙な波紋を投げかける。大人の世界の入口に立った少女の揺れ動く心情。少女役の栗田ひろみの清新さが印象的だった。そういえば、高校時代に定期入れの中には栗田ひろみの切り抜き入っていたっけ。 今見ると、栗田ひろみのなんと幼いこと。撮影時は中学生だったというから無理もないが、30年前は自分とさして変わらない年齢だったわけで、当時の栗田ひろみに「色気」を感じていたのは同世代の心情か。今はむしろ、当時はまったく関心がなかった宇都宮雅代と篠ひろこの妖艶な魅力にクラクラしてしまう。宇都宮雅代、神々しいまでに美しい。 そして、ラストの「いつのまにか少女は」。陽水はこの映画のために作ったという第二主題歌(第一主題歌は「夢の中へ」)。「いつのまに愛を使うことを知り……知らず知らず恋と遊ぶ人になる」。まさに栗田ひろみのためだけに作られた歌。しかし、自分が長い間勘違いしていたことに気付く。 「放課後」の中で、踏み切りの遮断機が上がったところを栗田ひろみが歩いてくるシーンがあると思っていたのに、それがないのだ。もしかすると他の映画? 「遮断機が上がり 振り向いた君はもう大人の顔をしてるだろう」という「白い一日」の歌詞が想像の中で一人歩きしていたのか? 森谷司郎監督は「栗田ひろみは自分が見つけた」と主張していたらしいが、それよりも早く、佐々木昭一郎さんが「さすらい」で起用しており、本名の「栗田裕美」の名前で出演しているわけで、佐々木氏の方が先。 最近のDVDは特典付が当たり前だが、この「放課後」はなんと、栗田ひろみ本人が副音声で地井武男と対談している。メディアに出ない栗田ひろみの声が聴けるという幸せ。06年収録だからまさに直近の栗田ひろみ。素晴らしい。 貫井徳郎「修羅の終わり」読了。文庫にしては800ページと分厚いが、読み始めると一気呵成。記憶をなくした少年、公安警察の暗闘、時間軸を超えて展開される複数のストーリー。最後まで結末読めず。しかし、叙述型ミステリーとはいえ、最後の1行には唖然呆然。いったいこの小説は……。 3月17日(土)晴れ 急に冬に戻ったような寒さ。 1500まで会社。K氏から電話。昨日の「お詫び」。「ジアンジアン時代から何十年もステージに携わってきたけど、本番で主役が意識をなくして前のめりに倒れるなんて初めての経験です」と恐縮しきり。テルミンという微妙な楽器を操るため、時々トランス状態になることもあるらしいが、まさか本番でそうなるとは。 1700、下北沢。本多劇場で加藤健一事務所「特急二十世紀」。 興行が立て続けに失敗――失意を胸にシカゴ発ニューヨーク行きの特急二十世紀号に乗り込んだ有名演劇プロデューサー、オスカー・ジャッフェ。奇しくも同じ 列車に、オスカーに愛想をつかし、ブロードウェイの舞台を捨て、映画界の華となったスター女優、リリー・ガーランドも乗車。降って湧いた偶然に、オスカー は演劇界の頂点へ返り咲くため、リリーと契約を結び、再び自分のステージに立たせることを思いつく。 乗り込んだら最後、特急列車はイチかバチかの運命をかけて一直線!「何としてでもリリーと出演契約を結びたい!」奮闘するオスカーが巻き起こす、抱腹絶倒劇の結末はいかに・・・?!(HP惹句) というわけで、カトケン得意の翻訳ものドタバタコメディー。いつもなら、爆笑につぐ爆笑……となるのだが、今回はちょっと……。俳優は宮島健、前田こうしん、さとうこうじ、小川輝晃、福島勝美と小劇場・アングラ系が多いのが特徴。これに無名塾の江間直子、文学座の浅野雅博、そして一柳みる、日下由美といった新劇系が加わる。役者のバランスもよく、セットは豪華。しかし、ケン・ラドウィッグのホンがいまいち面白くない。キーマンとなる男が「精神異常者」というのもなんだか……。で、カトケン芝居にしては珍しくクスリともできなかった舞台。隣席は次回出演の久野綾希子。十分に楽しんでいたようだ。 1908終演。A部さんに挨拶して家路に。 ヴィレッジヴァンガードで須賀原洋行「うああ 哲学事典 上巻」(講談社 714円)。 3月16日(金)晴れ 今年初の初雪を観測、というが、実態はなし。 1900、上野。文化会館小ホールで「やの雪」のテルミンコンサート。 世界でもテルミンを演奏する人はほとんどいないそうで、日本でもやの雪が唯一無二の演奏者。テルミンの愛好者自体は年々増えているというが、曲として演奏できる人はほとんどいないらしい。 1920年代にロシアの科学者によって作られた電子楽器テルミン。ラジオのチューニング時に出る「ウィーン」という電子音をヒントに、音楽的に使えるようにしたものとか。シンセサイザーの原型のようなもの。舞台にはトランジスタ製のテルミンと演奏者のやの雪さん。一見して、ただの木箱。演台のようなもの。アンテナがついていることで、「楽器」とわかる。左手で音量、右手で音階。手を握ったり開いたり、木箱の上でひらひらと動かすと、ビオラのような甘い音色が浮かび上がる。どうやって音階を刻むのか、まったくもって不思議な楽器だ。 ピアノの伴奏、ギターとの協奏。クラシックファンの殿堂・文化会館熱心な観客でほぼ満席。 手塚真の顔も。なんでも、CD総合プロデューサーだとか。あとで聞いたらやの雪の所属する事務所の社長とのこと。へぇー、タレント事務所もやってたんだ。 「やの雪」は、長い髪をたらし、スラリトした美形。どこか昔の石原真理子に似ていなくもない。楽器同様神秘的な雰囲気。トークゲストはサエキけんぞう。トークは得意ではなさそうな「やの雪」を絶妙のトークでカバー。それにしても、やの雪の受け答えはどこかしら神がかり的、教祖的。 テルミンの6重奏という試みも成功。一部終えて休憩。裏方をしているK氏と立話。 二部は、窪田晴男、赤城忠治とのコラボレーション。 しかし、思わぬハプニング。 1曲、2曲と続き、3曲目の途中で、やの雪の演奏がふっと止まったかと思うと、フラーッと体が前のめりに。「アアッ」という短い叫び声とともに、テルミンに覆いかぶさる形で舞台上に倒れてしまう。一瞬、何が起こったのかわからず、会場もシーンと静まりかえる。やや間があってバックでギターを弾いていた赤城氏が、駆け寄る。舞台袖からK氏も。その何十秒かの間。客席からようやく、ざわざわと心配そうな声。サエキもマイクを持って駆け寄るがなす術もない。懸命に場を取り繕うため、何か喋ろうとするが、言葉にならない。そのうち、やの雪の意識が戻ったようで、「急に何がなんだかわからなくなって……。本番で、ステージでこんなことは初めて……」と途切れ途切れの声をマイクが拾う。 さすがに会場は高齢のお客さんがほとんど。ざわつきはすぐに収まり、心配そうにステージを見守るだけ。なんとかステージを再開したいというアセリがスタッフに見えるので、”ゆっくりでいいよ”の声が会場からかかるとサエキ氏も「そういう声がありがたいんです。なんでもいいから皆さんの声を聞かせてください」と。 水が運ばれ、「甘いもの」がいいのか、チョコレートを持ってくるスタッフ。一度、再開の意思を見せるが、フラつく体。このまま、演奏中止か……。しかし、次第に落ち着きをみせ、15分ほどの中断の後、再開。再開の第1曲は、だれが聴いても弱々しい演奏。テルミンという楽器は演奏者と一体。その精神を如実に反映する。しかし、徐々に力を取り戻し、最後のハミング曲も無事に乗り切る。 通常ならアンコールだが、時間は予定を30分オーバー。観客も演奏者の体調を考えてアンコール要請はなし。会場販売していたCDを買って家路に。 2215帰宅。「花より男子2」の最終回。家族総出でテレビの前にかじりつき、途中入場を許さない。仕方なく、追いかけ再生で頭から見始め、一人で最後まで。お決まりのハッピーエンド。これで、来週から見るテレビドラマがなくなった。 注文したDVD「放課後」が届く。見るのは日曜日だ。20年ぶりに見る映画はどんなふうに受け止め方が変わるのだろう。 3月15日(木)晴れ 朝から熱っぽい。計測すると6度7分。微熱。「熱があるときは施術しないほうがいいですよ」とのことで、鍼は中止。 時間があいたので、銀座、シネカノンで「フラガール」を。 誰もが知っている炭鉱の町の「常磐ハワイアンセンター」。その設立の裏にはこんな秘話があったとは。途中から涙腺を刺激されっぱなし。松雪泰子、蒼井優がいい。豊川悦司も違和感なし。一番の感涙どころで山崎静代(南海キャンディーズ)が儲け役。そしてなによりも富司純子が素晴らしい。緋牡丹のお竜さんがそのまま歳をとったような、きりりと凛々しい炭鉱の女。そのタンカの口跡のよさ。「男の紋章」の轟夕起子か、東映任侠シリーズの清川虹子かというくらい、見事な「女傑」ぶり。冨士純子を見るだけでも「フラガール」を見たかいがあった。 途中、何度も嗚咽を抑えるが、花粉症のため息苦しくなり、呼吸困難に。映画館で嗚咽して呼吸が止まりそうになるとは思わなかった。 1810終映。階段を駆け下り、日生劇場に急行。 1820、セーフ。中川晃教主演の「ロックオペラ☆TOMMY」。劇団☆新感線のいのうえひでのり演出。ザ・フーの同名アルバムをもとにしたブロードウエイミュージカルがベース。父親の殺人を目撃したトラウマのために「見えない・聴こえない・話せない」の三重苦になった少年を主人公にしたロック・オペラ。 いのうえ演出は、地の芝居なし、すべて歌で表現する。しかし……。母親役の高岡早紀の歌は聴けたものじゃないし、映像を多用した「説明描写」は邪魔。わずかに、ROLLYの歌と山崎ちかの歌だけがグッと聴かせる。せっかくの中川も聴かせどころ少なく、消化不良。右近のブレスレス・シャウトに拍手が起こるに至っては、客はどこを見てるんだか……。 さすがのいのうえも、この難解なミュージカルは手にあまったのか。いいところなし。 休憩20分で2035まで。このコンパクトさだけが取りえか。 3月14日(水)晴れ 眠っている間中、ノドの痛みのためか熱っぽく、何度も目が覚め、イヤ〜な感じ。これでは仕事を休むことになる……と夢の中で悶々としている。 0730、いつものようにゴミ出しのために起こされるも、ノドが痛い。風邪だなこりゃ。しかし、起きると徐々にノドの違和感はひいていく。前にも病院に行って、結局クスリがムダになった。今回も病院に行くのは早計か。 で、病院には行かず、0930、税務署へ。住宅売買損金の還付申告。年間の税金が丸々戻ってくるのは嬉しい。それをそのまま貯蓄したら、住宅ローンは今の半分の期間で返せるのだが。結局、娘の学費に化けたりするわけで……。 1030帰宅。午後から家人の買い物に付き合い1600まで。ホワイトデーとやらで、投資額の数倍のプレゼントを返すことに。家人にはTシャツ2枚で8000円。痛い。商業主義に乗せられていることがわかっても、こればかりはなす術なし。 本屋で奥田英朗の「邪魔」(講談社文庫)2巻を買う。 帰宅後、やはりノドが痛む。熱っぽい。油断大敵。 3月13日(火)晴れ 仕事を終えて1550、銀座の「ギャラリー椿」へ。会社から歩いて10分ほど。先日、白石征さんに合田佐和子さんの個展が15日まで開催されていると聞いたので、寺山さんのCDを差し上げたら喜ぶかもしれないと思ったのだ。 合田さんの絵は100万円単位の値段。モンローの絵など、ちょっといいなと思うのは数百万円。 ちょうど、運良く合田さんがいらっしゃったので、係りの人に頼んで挨拶を。 「そうなんですか。それはありがとうございます。あのCMは当時欲しくて何度か担当者に頼んだけど、いただけなくて……。嬉しい。ちょうどノブヨ(出演していた二女)が5歳の時です。寺山さんに呼ばれて行って、いきなりぶっつけ本番。結構時間をかけて録った記憶があります」 「”お父さんとお母さんとどっちが好き?”というバージョンもあったんですけど。これには入ってない? そう、それは残念です」 合田さんの伴侶は「耳の彫刻」で知られる三木富雄氏(1937年〜1978年)。ノブヨさんが5歳の時(1977年)はまだ存命だったのだ。ということは、あのCMは1977年に録音したもの。放送まで7年間のブランクがあるわけだ。九條さんによれば「放送直前に、いわゆるのぞき事件(80年)が起きたためお蔵入りした」という。ちょうど時期的にピッタリ。 「寺山さんの声が実に若々しく力強い」という白石さんの印象は正しい。録音は1977年頃。寺山さんが病に倒れるずっと前なのだ。 当時を懐かしむ合田さんの顔。一本のCMが、また新たな記憶を呼び覚ました。死してなお生者に新たなナゾを投げかけ続ける寺山修司。 1620、「椿」を辞してマリオンへ。映画「ドリームガールズ」。客席はまばら。この傑作に客が入らないという不幸。 オープニングのオーディションシーンからしてすでにワクワク・ドキドキ。「ダイアナ・ロスとシュープリームス」がモデルというのはいわずもがな。聴くうちに次第にダイアナ・ロスの声にビヨンセが近づいていく。 ラジオのヒットチャート番組でシュープリームスの「ラブチャイルド」が連日一位だったのは1968年頃か。中学時代、学校から帰ると5球スーパーラジオに耳を傾けて聴いていた。 こんなにも人種差別がひどい時代だったとは当時は知るよしもない。 しかし、全編吹き替えなしっていうのがすごい。ジャニーズ事務所が君臨する日本のエンタメ界じゃまずムリ。成立しない。 ジェニファー・ハドソンの歌唱力は確かに拍手喝采ものだが、優等生っぽい「うまさ」というのは自分好みじゃない。やっぱりビヨンセだ。 2時間10分、ほとんどが歌唱シーン。なんという至福の時間。 1845終映。 駅に急ぎ、地下鉄乗り継いで神楽坂へ。シアターIWATOで龍昇企画「夢十夜」。食事する時間がなく、駅の売店でコーヒーロールとフェダインゼリーを買い、劇場のベンチで流し込む。初日のためか大入り満員。江森さん、七字氏、西堂氏、文学座の得丸伸二、流山児★事務所の小林七緒、燐光群の中山マリ……。客入れに手間取り10分押し。 本来のタイトルは「鏡と窓」なのだとか。死にゆく一人の男の末期の目に映った人生の断片。 漱石の「文鳥」を縦糸に、「夢十夜」の各エピソードをコラージュ。特に「百年待って」が主旋律。夢十夜の中でもっともロマンチシズムにあふれる第一夜「百年待って」は、大好きな作品。死んだ女の墓の前で百年が過ぎていく。自分に向ってのびてくる白い百合の花弁が暗喩する甘美なエロチシズム。 舞台の方は甘美に……とはいかず、どこかぎくしゃくとしか粗っぽさ。なによりも直井おさむのねばりつくようなセリフ回しが苦手。どうにも気どって聞こえるのでそれだけで興ざめなんだなあ。 2110終演。ノドに違和感があり、ノド飴をナメながら家路に。 3月12日(月)晴れ 夜、NHKで小椋桂の特集番組を見る。ふっくらとした顔。がんを克服し、精力的に活動している小椋佳。 小椋佳を初めて聴いたのは高校生の時。同じ寮の同級生が「青春」というアルバムを持っていた。私が買ったのは「雨」というアルバム。岡田裕介のジャケット写真。てっきり彼が歌っているのだとばかり思っていた。ナレーションと歌。淡い初恋の物語。小椋佳のほかに、素人っぽい女の子の歌もあったし、もう一人の男性の歌も入っていた。そのセンチメンタリズムが16歳の心にしみた。放送部だったので、昼休みの音楽放送で全曲かけたが、あの感傷的なアルバムが昼休みに全校に響き渡ったと思うと、ちょっと恥ずかしい。 「ミュージック・プロムナード」という昼の番組のひとつ。何曜日だったか。それまでイージリスニングしか許されなかったお昼の番組で、CCRや拓郎を流したのだった。「雨」もそのうちの一枚。 小椋佳のデビューは天井桟敷レコードの「初恋地獄篇」。寺山修司の主宰する詩のサロンに出入りしていたことから、歌うようになった。やはり、寺山修司は名伯楽だったのだ。その後、小椋佳がアルゴミュージカルを主宰するようになったのも、おそらく寺山修司の影響だろう。 「顔のない歌手」小椋佳の時代から30数年。「雨」のアルバムジャケットで岡田裕介が着ていた紺のシャツはJUNの製品。同じものを当時自分も着ていたっけ。田舎の高校生もあの頃はJUN&ROPEを着ていたのだ。 小椋佳のライブに井上陽水が出ているのを見たら、映画「放課後」を思い出す。栗田ひろみが一番可愛かった映画。すぐにネットで調べるとDVDが出ている。しかも、中古だと安く買える。さっそく注文。こんなときはネットはありがたい。 3月11日(日)雨 0830起床。稽古を休む旨、Y先生の携帯に連絡。腰痛が治まらず、今ムリすると長引くおそれがある。心配かけないように「風邪をひいて」とだけ話しておく。 花粉症の倦怠感か、うつらうつら。お昼には布団の中にもぐり、ラジオドラマを聴きながら惰眠をむさぼる。なんという自堕落な休日。夕方、家人の買い物に付き合い、ダイエーへ。500円プライスのDVD「オルフェ」を買ってきて鑑賞。コクトーの名作。鏡の中に吸い込まれていくシーンは30年後に「ミラーマン」に引き継がれた? 昨日、上野駅の売店で買ったヒバシャンプー。よく見たら製造元は大間。気がつかなかった。 PANTAの新譜発売全国ツアー最終日。ロフトでのライブが5時半から。しかし、行くことできず、残念無念。 3月10日(土)晴れ 相変わらずの花粉症。電車の中はマスク人間たちで異様な光景。 サラリと仕事を終えて、1530、新宿。京王プラザ「樹林」でO路恵美、事務所社長の橋本さんと待ち合わせ。流山児★事務所「リターン」に出演するO路さん。11年前の初出演時は毎日がパニックで、「当時の舞台のことはまったく思い出せない」という。初舞台=流山児演出作品という過酷さゆえの「記憶喪失」(?)。相変わらず美形。「赤旗日曜版」にエッセイーを連載しているとか。「ようやくペースがつかめたところで連載終了なんです」 結婚式が多いのか、「樹林」は満席。あちこちの席で記念写真のフラッシュ。 1630、早稲田の稽古場で次の取材があるとのことで、一緒に高田馬場まで。稽古場まで電車通いの恵美ちゃん、SUICAを持ってるのだからエライ。 馬場で別れて、上野まで。腰痛マッサージを、と思ったが、時間がないので大塚にリターン。駅前の本屋で貫井徳郎「修羅の終わり」(講談社文庫 1095円)を買う。奥田英朗の「邪魔」を読みたかったが品切れ。「マドンナ」が平積みに。半村良の「黄金の血脈」(天の巻 地の巻 人の巻)も読みたい。読みたい本ばかり。 1900、萬スタジオで万有引力「カフカの卵鐘」。冒頭から速射砲のようにカフカの小説のセリフ引用が炸裂。そのスピード感は特急列車。1時間45分、「城」から「変身」まで、俳優の肉体による作品のコラージュが展開する。「天井桟敷にて」「カフカとサーカス」など、初めて知ることばかり。カフカの人と作品を丹念に調べ上げたシーザー。 M紙のT橋さんは翌日があるので引き上げ、白石さん、市川さんらと駅前の「さくら水産」へ。白石さんに寺山ラジオCMの話をすると、「私も確か3本は持ってたと思います。それは貴重な音源ですね」と。 ダメ出しが長引いたか、シーザーほか役者陣は2200頃到着。今日の俳優の中では、森さんのセリフが実に明瞭で説得力があった。その旨話すとシーザーも同意。「一人芝居ができる声だと思う」とか。 2300、白石さんが終電なので、一緒に退出。 3月9日(金)晴れ 6日の時事電によれば、米紙サンノゼ・マーキュリーは6日付の紙面で、安倍首相が「(慰安婦問題で)強制性を裏付ける証拠はなかった」と発言したことに対し、「ホロコースト(ユダヤ人大虐殺)否定論者にも似た行為だ」と非難する専門家の声を紹介した。 日本の近代軍事史が専門のマーク・ピーティ・マサチューセッツ大学教授は同紙に「愚かさにあきれ、開いた口がふさがらない」と批判。首相発言を受け、米議会で審議中の慰安婦問題に絡む日本政府への決議案採択に向け、大きな弾みが付くだろうと予測した。 朝鮮併合は「朝鮮側から請われたもの」「南京虐殺もなかった」「朝鮮人強制連行もなかった」……そのうち、「真珠湾攻撃もなかった」となるのか。ま、相手が米英だと、右派の「修正史観」もおとなしくなるが。 チャップリンの「殺人狂時代」の中で、「ひとり殺せば悪党だが、100万人だと英雄になる。数が殺人を神聖化するのだ」というセリフがあるが、言い方を変えれば、数が多い方が「ウソ」とされやすい。100万人の朝鮮人を拉致・強制連行した歴史的事実さえ、修正主義者にとっては「まぼろし」になる。逆に「数十人の日本人拉致」のほうが重く……。 光熱費も水道代も無料の議員会館にしか事務所を置いていないのに、05年までの5年間に毎年400万〜800万円、計2880万円の光熱水費がかかったと報告していた松岡農水相。国会で疑惑を追及されると、「なんとか還元水のようなもの、暖房なりが含まれる」と釈明したが、議員会館には部屋ごとの電気メーターはないので、個別に料金を支払うことはあり得ない。今日、民主党の有志が松岡の議員会館事務所を直撃したが「還元水」を作る浄化器具もなかったという。あったとしても、月に40万以上も費用がかかる浄化器具って何だ?? どう考えたって「虚偽記載」だ。社民の辻元清美のどうでもいいような秘書給与問題を連日追及したテレビ、新聞。格段に悪質なこのウソつき男はどうするのか。「うるさい」と評判の議員だけに、ビビって追及の手を緩めるか。ここ数日が見もの。 インフルエンザ流行。同僚も一人ダウン。 1500、K條さんに電話。寺山修司のソニーCMのことを話すと、「それは偶然ね。ついこの前、地方で行った講演会に来てくれた女性が、そのCMを大学の担任から聴かせてもらったという話をしてくれたの。それで寺山に興味を持ったんですって」 K條さんのところにも、このCMの音源がないそうで、女性からの提供を待っているのだとか。偶然にびっくり。 1700帰宅。 きょうは朝から花粉症がひどかった。医者のクスリを飲んでも効かず、たまりかねて市販の鼻炎用カプセルを服用。イライラで仕事に集中できず。電車の中、街はマスクの群れ。知らず知らずのうちに、花粉症が常態化している。怖い。 3月9日(木)晴れ 朝起きるとき、腰に違和感。危険な兆候。 1620、K記念病院で鍼。美人の先生、腰痛と聞くと、「じゃあ……」と「気」を。「気」のせいか、痛みがやわらいだような……。しかし、鍼灸師「気」とは……。 1830、渋谷。パルコ劇場で「双頭の鷲」。祖父江氏と國井氏に挨拶。 満員の客席。美輪明宏と木村彰吾。二人のための舞台。休憩2回で終演2150。絢爛豪華な舞台美術と「たっぷり」の芝居。終演後はスタンディング・オベーション。休憩時間にS美也子さんとバッタリ。探検隊のメンバー、今は年に1回劇場ですれ違うだけ。劇場通いをしているはずなのに、ほとんど顔を合わせる事がない。それだけ、芝居の本数が多いからだろうけど。 駅までの帰り道、Sさんが「あれでスタンディング……周囲は誰も何も言えないんだろうけど……」 ……。 2300帰宅。 3月8日(水)晴れ 花粉症で一日、倦怠感。このもやもや感はちょっとした風邪と同じ。何かをしようという意欲がまったくない。一日ボーッと。それでも、録画しておいたラサール石井の「なかよし」を見る。テレビの舞台中継を見るのはめったにないこと。続いて、昨日買った「フェスティバル・エクスプレス」を。ジャニス・ジョプリンの「クライ・ベイビー」。コンパートメントでのセッション。移動フェスティバルに対し、「フリーコンサートにしろ」「おまえらは資本家のブタだ!」とののしる市長も。いかにも1970年の時代を反映している。 昨日届いたCD。寺山修司のソニーカセットテープのラジオCM。CM殿堂入りした作品だけのことはある。というか、いかにも寺山修司らしい作品。合田佐和子さんが娘さんと出演しているバージョンも。寺山さんの短歌朗読。胸が打ち震えるような思い。Mさんの好意に感謝。 1300〜1500、仮眠。 税務署に電話して、確定申告の相談。譲渡損の申告が今年も持ち越すのだとか。よかった。これで少しは還ってくる。 夕方、少し、持ち直して日記を。 中学の同級生のことでショックを。この世には神も仏もいないのか。 3月7日(火)晴れ なんという季節なのか。 1400〜1530、仮眠室で横になる。花粉症のため疲労感。 1700、下北沢。ヴィレッジヴァンガードでCD、本を。 ボッサ・ストーンズの第二集、「フェスティバル・エクスプレス」3990円。映画館で見逃したので。1970年のカナダ横断ロックフェスティバルの様子。ジャニス・ジョプリン、ザ・バンドら。 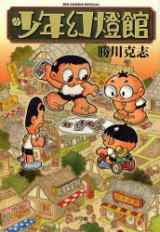 本は漫画。勝川克志「少年幻燈館」(小学館 900円)、かわかずお「パチ漫」(洋泉社 1400円)。 本は漫画。勝川克志「少年幻燈館」(小学館 900円)、かわかずお「パチ漫」(洋泉社 1400円)。1900〜2105、MODE「変身」。松本修のカフカシリーズの最新作。主人公グレゴール・ザムザの巨大虫への変身。ザムザの内部よりも、父母、妹など、周辺の人々の反応を書き込むことから、新たに「変身」を読み解こうというもの。高田恵篤が女中役。最初出てきたとき、背中のラインが20代の女性。まさか恵篤とは思わなかった。化けるものだ。しかし、全体に、松本流の美学とはちょっとずれている。唐十郎をやったことが大きいのか。いつもの演出よりも雑駁。意図してのことかどうかはわからないが。終演後も、何といっていいか困ってしまう。「〇〇さんは、つまらなかったら、そのまま帰ってしまうから」と松本さんが言ってたが、まさに……。今日は帰らないまでも、話が切り出しにくい。気配を察してか、松本氏も、あえて触れず。高田恵篤、客席にいた斎藤歩と立話をして家路に。 電車の中、そして帰宅してから、「少年幻燈館」「パチ漫」を一気読み。勝川の漫画の絵柄は、杉浦茂譲り。昭和30年代へのノスタルジーに満ちており、思わず遠い目。「パチ漫」、このセンスは大好き。作者自ら「好きな漫画家へのオマージュ」と言う通り、「はだしのゲン」「アストロ球団」「エースをねらえ」「三丁目の夕日」から「わたしは新吾」「恐怖新聞」まで、作者の絵を似せるだけでなく、いかにもその漫画家が書きそうな作品=思想の模倣。「火の鳥」のパチもん「画の鳥」など、手塚治虫に対する愛情と敬意に満ちた一編。単なるパロディーではない。この作者「かわかずお」のセンスと漫画への愛情がダイレクトに伝わってくる。久々のヒット。 3月6日(月)晴れ 全身筋肉痛。腰痛も。昨日の稽古が過重だったようだ。 1500、銀座・博品館劇場で中島啓江の記者会見&ゲネプロ。取材2社のみ。ちょっとさびしい。続くゲネは観客2人。ウーン。止めながら手探りのゲネ。1時間見るも、疲労感。帰宅途中で買い物。雨がぱらついたので、ストアまで傘を持ってくるよう、娘を呼んで、二人で夜道を歩いて帰宅。途中、内科に寄って花粉症のクスリを出してもらう。 2200就寝。 3月4日(日)晴れ 花粉症のためか、夜中に何度も目が覚める。1時、3時、4時。早く寝ても寝不足。 0900、躰道稽古。今日は0900ピッタリに稽古開始。これからは時間厳守。出欠のカードも作るとか。ファジーなところがよかったが、あまりにもルーズになりすぎるのも困りもの。これはこれで仕方ないか。 3時間たっぷり稽古。「強化合宿並みの稽古」とか。鼻炎用カプセルで花粉症を抑えているためか、ひっきりなしに水分補給。ただでさえ汗をかくのに、ノドが乾いて乾いて。 エビ蹴り、旋体の突きなど基本稽古もみっちり。1200、さすがに今日はグッタリ。 1300、帰宅。 WOWOWで「魚が出てきた日」を放送したので録画しておいたのだが、見る気力もなく、仮眠。 「魚が出てきた日」は1970年代に、名画座で「博士の異常な愛情」などと抱き合わせでよく上映されていた。「ぴあテン、もあテン」でも常に上位に選ばれていた作品。 マイケル・カコヤニス監督のブラックユーモアが秀逸。キャンディス・バーゲンも出ているのに、なぜか今までDVD化もされない。「核」の恐怖をテーマにした作品だからか、その不遇さには首をかしげてしまう。昔、テレビで放送したビデオを持っていたがカットが多く、日本語吹き替えも邪魔。今回、オリジナルが放送されるのは実に嬉しいこと。この日が来るのを待っていたのだ。しかし、全身疲労が激しい。見るのは後回し。 3月5日(土)晴れ 0630出勤。 1400、亀戸へ。カメリアホールで青年座「妻と社長と九ちゃんと」(鈴木聡・作、宮田慶子・演出)。亀戸と亀有はいまだに混同してしまう。亀有リリオホールと亀戸カメリオホール。紛らわしいことこの上ない。何度も行先が「亀戸」であることを確かめてから電車に。 受付で森、紫雲、水谷内各氏に挨拶。 2005年以来の再演。亀戸という「地方公演」のためか、客席の雰囲気がいつもと違う。幕が開くとすかさず拍手が巻き起こる。地方のお客さんならではの反応。本多劇場ではありえないこと。 さて、物語は……。 老舗企業「昭和文具」の社長宅(平屋、和室)が舞台。 社長・春日浩太郎(山野史人)は頑固一徹だが憎めない昭和の男。その妻・佐和子(増子倭文江)は、男を手の平で遊ばせるような器量の大きな昭和の妻。ホステスをしていたところを後妻に迎えられたのだった。 そして団塊世代の象徴のような男・森島三郎、通称・九ちゃん(岩崎ひろし)。会社では他の社員から疎んじられているが、なぜかワンマン社長にはかわいがられている総務課長。 社長宅の裏手には昭和文具の本社グラウンドがあり、春の花見、夏の盆踊り、秋の運動会、冬の餅つき。季節のたびに地域の人々に開放してきた昭和文具の象徴だ。 時代は昭和から平成に移り幾星霜。取締役の息子・昭一(横堀悦夫)は昭和文具の改革を強引に進める。外資系企業と手を組んで販路を世界に広げようというのだ。だが、社長・浩太郎は頑として譲らない。しかし、会社の幹部たちは昭一の意のまま。外堀も埋められ、やむなく社長交代へ。今まで続けてきた地域との交流も時代遅れと切り捨てられ、グラウンドは売却、その金で青山に本社ビルを建てて移転。社内にも外資の途中入社社員が続々と……。 そんな矢先に浩太郎が急死する。 通夜の夜。遺影選びで、新社長派と九ちゃんの総務部でひと悶着。しかし、部下の行く末を思って、グッとガマンの九ちゃん。しかし、亡き社長に対する心ない暴言にたまりかね、ついに爆発。新社長とその取り巻きにタンカを切ってしまう。 「古いと言われたっていいじゃないか。ムリして外国のやり方に合わせることはないじゃないか。なんでも外国流がいいのか。あんた、今すごいこと言ったぜ。憲法を変えて戦争ができる国になろうって。平和のどこがいけないんだ。みんなで言おうぜ、憲法9条改正反対!」 元は「憲法第9条改正に対する異議申し立て」の作品を作るということからスタートしたというが、鈴木聡の脚本は、それを見事に昇華し、密度の濃い人間ドラマとした。役者、特に九ちゃんの役の岩崎ひろしの大詰めのタンカに思わず涙。客席のあちこちから鼻をすする音。青年座らしい反骨のドラマ。この作品で地方公演。ぜひとも成功してほしいものだ。 初演より20分のびて休憩15分挟んで2時間45分。初演でやむなくカットしたセリフを生かしたり、役者の「たっぷり演技」のためとか。 初演の時間のつもりで行ったので、6時のトップスまで間がない。急いで帰社し、新宿へ。 1750、ぎりぎりシアタートップスにセーフ。慌てた……。 「悩み多き者よ」(作=水谷龍二、演出=田村孝裕) とある病院の更衣室。人間ドックの受診に来た3人のサラリーマン。小倉久寛、山口良一、ラサール石井。自分たちが51歳の同い歳だと知って意気投合。「バイアグラ」を仲立ちに、再会を約束する。次に出会った時には、互いの私生活もちらりほらり。気の合わない同士も出てきて……。それでも、なんとなく飲み会を重ねる3人。ひょんなことから、フォークソングライブを開くことに。 いやはや、笑った笑った。声を出して笑ってしまったのには自分でビックリ。水谷龍二の脚本は現場の3人に任せた部分が大きいだろうが、田村孝裕の演出が実に緻密。笑ったあとにホロリというコメディーの王道。 1時間40分。至福の時間。 間奏曲は「今日までそして明日から」「されど私の人生は」「教訓1」。3人で歌ったのは「自転車に乗って」など。小倉がリードギター、なかなかのもの。ラサールはリズムギター、ややおぼつかない。山口は淡々とベース。3人の生演奏&歌。心ウキウキ、いい感じ。 2050、人でひしめきあう新宿の雑踏へ。この雑踏になじめなくなって久しい。でも、今夜はいい芝居を見た後、心が弾む。 3月2日(金)晴れ 1800帰宅。 2200。「花より男子」。つくしと司の雨中の別れに思わず涙。「緋牡丹博徒 お竜参上」での藤純子と菅原文太の雪の別れ、「竜二」の肉屋の別れと並ぶ名場面……なわけないか。あと2回で終了。毎週心待ちにしていたドラマなのに、金曜日の楽しみがなくなる。 3月1日(木)晴れ 朝、目が覚めても、なお鮮明な夢。 飛行機が東京湾に墜落する。都知事も乗客の一人。グングンと迫ってくる海面。胴体着陸が成功したようで機体は爆発もせず、海に浮かび救助を待つ乗客たち。海の中に突き立った巨大なクレーン。その先から吊り下げられたロープ。手を伸ばそうとすると、それが急に巻き上げられる。と、そこにイルカの群れが現われる。1頭が自分の鼻先に海に浮かんでいる乗客を押し上げ、陸に向かってまっしぐら。1人、2人とイルカたちが救助してくれる。陸からイルカに手を振る人々。しかし、翌年、その海岸は助けられた乗客の一人、不動産屋によって買い占められる。そこを観光地にして一儲けしようというのだ。だが、イルカたちは翌年から姿を消す。 実家に立ち寄ると父が一人。壁のカレンダーは夏。各地から集まった伯母たちが帰り支度を……。 イルカに助けられる……何の暗示か。 1400、風のS崎さん来社。 1615、新宿歌舞伎町。コマ地下の映画館で「バブルへGo」。 1900、新宿。紀伊國屋ホールで文学座「初雷」。 |