| �T��31���i�j�����J �@1620�A�j�L�O�a�@���I�B�ŋ߂͌y���}�b�T�[�W�����Ă����̂ő̃X�b�L���B �@1900�A�Z�{�B�q���Y�����ɕ����ĂT���B���C�u�X�y�[�X�u�X�[�p�[�f���b�N�X�v�Łu�ÈłɃm�[�`���X�v�Ȃ�C�x���g�B����ȃC�x���g�ł��Ȃ���Α��ޓ���邱�Ƃ��Ȃ��A�[�N�q���Y�B�u�����g�v�̒��B �@���_����ɍL����A���ɂ��J���������Ă������ȋ�͗l�B�R���r�j�ŎP���������������A�킴�킴�����قǂł��Ȃ��Ǝv�������A���ցB�G���r���̒n���B30���O�ł��܂��J�ꂹ���B�������Ȃ��߂��̃R�[�q�[�V���b�v�ŃR�[�q�[�{�P�[�L�Z�b�g980�~�B �@�T���O�ɖ߂�ƁA�����ɗ�����̎p�B����̓�̗l�q�Ȃǂ𗧘b�B�J�ꂵ�Ă��邪�A�x�X�Ƃ��ċq���ꂪ�i�܂��B�Ȃ����낤�Ǝv������A�����ŎQ���҂̊����l�ЂƂ�r�f�I�ɎB���Ă���̂������B��őf�ނɎg���̂��낤�B �@���̐Ȃ��Ă���̂ŁA������ƍ��|���Ċό��B�J�����Ў�̕Η������B �@���C���̉��t�X�y�[�X������A���̉���Ɂu�тm�v�ɂ��r���E�c���[�̋�ԁB�V��Ɍ������ě�������������r����݂邵���}�t��������B�r���͂���������g���Ȏ���r���B�I�[�g���[�V�������Y�����ȑO�A���a20�N��ɍ��ꂽ�r�����Ƃ����B �@�������X���̉̂Ɖ��t�̊Ԓ��A���ɒu���ꂽ�r���Ǝ��ɐ����Ԃ�����a���̏����A���̎���ł̓��_���_���X�̃p�t�H�[�}�[�A���h��̕�����ȂǁB �@�����ǂɂ͂���Ȃ��̂ԂЂ뎁�̉f�������e����A�lj��Ƃ����̊G��\��t����B�u�́{���{���{�����{�f���v�̕����C���X�^���[�V�����B  �@�ϋq�͖�150�l�B�Ō�͂����܂�̃A���R�[���B���̂悤�ȃC�x���g�ɂ͂�����ƈ�a���B�Ƃ������A���炩���ߌ��߂�ꂽ�A���R�[�����ĉ��H�Ǝv���Ă��܂��B���ł͉��������炩���߃J�[�e���R�[�����g�ݍ��܂�Ă���B�̂Ɣ�ׂăJ�[�e���R�[���̑������ƁB �u���̒��ɃA���R�[���Ƃ����T�O�͂Ȃ��B���炩���߃��C�u�ɑg�ݍ��܂ꂽ�A���R�[�����ĉ��Ȃ́v�Ƃ������}�L����̂��Ƃ��ӂƎv���Ă��܂��B �@1930�J����2210�I���B�����������ߐl�ɂƂ��Ă͂炢�W�J�B������͓r���őޏ�B���]�Ԃŗ��Ă���Ƃ̂��ƂŁA�J�̒��A��ς����B �@�I����ĊO�ɏo��Ƒ嗱�̉J�B�w�܂ŋ삯�����A ������т������B�J�ɑł����̂͋v���Ԃ�B �@2330�A��B���������͑����A�낤�Ǝv�������A����Ɠ������ԁB��J���B �T��30���i���j�J �@�Ɛl�̊P���Ȃ��Ȃ��Ƃ܂�Ȃ��̂ŁA�厖���Ƃ��ċߏ��̕a�@�ցB���߂čs���l�a�@�B�h�A���J���������Ȃ̂ŁA�ҍ����܂Ŋ��҂ƈ�t�̉�b���������Ă���B�̂���̕a�@�ɂ��肪���ȃV�X�e���B�l���Ƃ����ϓ_����͂���͂��������Ȃ��B�a���A�Ǐق��̊��҂ɓ������Ȃ̂�����B �@�����Ƃ��A��t�͎��ɍ��ؒ��J�ȑΉ��B�ނ�݂Ɍ��������������������A��������Ɗ��҂ɁA�a��̐����Ɖ��P�̕��@�������������B���ʂ̈�҂Ȃ�u���ׂł��ˁB��o���Ă����܂��傤�v�ƂR���ŏI���Ƃ����30���ȏォ���āA�����K���̉��P��A�Ǐ�ɘa�̃P�A�ȂǁA���J�ɐ����B����ȁu�ԂЂ��v��t�Ԃ肪�A�t�ɑa�܂��̂��A�P���Ԃ̊ԂɊ��҂͂킸���R�l�B����ŕa�@������Ă�����̂��S�z�ɂȂ�B �@�@1830�A�ԍ�ցB�v���h�~�J�h�r���P�K�́uSUBIR Sea Blue Room�v�ŋ}�������H�t�Ȃ݂���̒Ǔ��ƕv�̓��T�i�����܂���B �@�x�������A���C���Ȃ̂łP���Ԃ��炢�Ŏ��炵�悤�Ǝv���čs�����̂����A�������������Ă��܂��A2200�̎U��܂ŁB��͉w�O�̋������B�����܂ōs�����A������2230�A����ł͗����̎d���ɋ����B�s�삳��A�Ђт��݂�����A�������X�������ɕʂ�������ĂP�K�ցB�����ɍ��{�A�������B�u����ł�������v�ƁA�G���x�[�^�[�ɉ������܂�ĂтT�K�ցB�������A��͂莞�Ԃ��x���B��l�A��Ɏ��炵�ēd�ԂɁB����ȂƂ��A�����̎d��������߂����B �@��͂S�O�O�l�ȏオ�W�������B���{�ƃu���W���̐e�P�ɐs�͂��A���{�����≹�y�����ɑ���ȍv���������v�Ȃ̌�F�̍L�����Q��҂̊�Ԃ�B��l�����w�W�ҁA�����E�����W�҂܂ő��m�ρX�B�㞊����A������A�V�[�U�[�A���{�A�^���A���A�s��A�O��A�c�V�q�A�k��A�Η��A���ё�c�c�Ƃ������V��V�~�E���L���͊W�A�쑺�B�A������q�v�ȁA�{���������� �@�쑺�B�ƕΗ����̖��k�ɓ��ȁB�����I�ɂ͂ǂ����������������i�H�j �@54�Ƃ����Ⴓ�ŖS���Ȃ����Ȃ݂���B�T�i����A��ꓰ�A�F�l��̋���ł����Ɏv�킸�ړ����M���Ȃ�B  �@�����̌�̃p�t�H�[�}���X�͉����o�I�q����A�������X������̉̂��� �@�����̌�̃p�t�H�[�}���X�͉����o�I�q����A�������X������̉̂��� �c�l�A�Ђт��݂��Ȃǂ̕����E�_���X�����X�ƁB�����o�I�q�͎d���̍��Ԃ�D���Ă������Ă��ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA�T�i����̌�������A�u�S���{�̃o���v�u�����I���t�F�v�A�����āu��̕��ɂ̂��āv�̂R�Ȃ�M���B�������X�����u�ԐF�G���W�[�v�u������ȁv�̂Q�Ȃ��B�I�������́A����������A�V�[�U�[�A���{�����ƋL�O�ʐ^�B �c�l�A�Ђт��݂��Ȃǂ̕����E�_���X�����X�ƁB�����o�I�q�͎d���̍��Ԃ�D���Ă������Ă��ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA�T�i����̌�������A�u�S���{�̃o���v�u�����I���t�F�v�A�����āu��̕��ɂ̂��āv�̂R�Ȃ�M���B�������X�����u�ԐF�G���W�[�v�u������ȁv�̂Q�Ȃ��B�I�������́A����������A�V�[�U�[�A���{�����ƋL�O�ʐ^�B�@ �@�������A�Ȃ݁E�T�i���̌𗬊W�������ɍL�����c�c�B �@54�͑��߂���B�ނ�ł����������F�肵�����B �T��29���i�j���� �@�������E�����閾���A��ʎ��̘_���́u�����̎��C�������~�߂����{�̐ӔC�v�ɏœ_�B���͂Ɂu�������߂����v�ƘR�炵�Ă����Ƃ��������B���ꂾ�����Ԃ̔��𗁂тĂ��J�G���̊�Ƀi���g�J�B���疳�p�Ȑl�c�c�Ǝv���Ă������A�{�l�ɂƂ��Ă͐j�̃��V���������̂��낤�B���߂����Ă��̋����Ȃ���Ύ��߂��Ȃ��̂��t���B�����̔C���ӔC�ɖ�肪�g�y����̂����₪���ď��������炵�҂ɂ������{�B���ʓI�ɂ́A���E�Œk���������̑����X���łɑ��苎����Ƃ�����A���{�́u�[�d�����v�Ƃ�������B �@����ɂ��Ă��A���{�́u�͜��ɑς��Ȃ��v�����̂������B �@���l�́u�߂����B���������v���ł��v�Ƃ���������Ŏg�����̂��낤���A�u���������{�v��ڎw���A�ꍑ�̎��u���������{��v�ɖ��m�Ƃ����̂́A�Ȃ�Ƃ��u�͜��ɑς��Ȃ��v�B �@�u�����̌����Ȃ��Ēp���������v�����Ɓv�ł���A�p��Έ�ڗđR�Bbe quite [deeply] ashamed of oneself �@�u�������g�ɐ[���p������v�킯�ŁA�ǂ������悤�Ƃ��A���{�����̌��t�̐������Ӗ���m�炸�Ɏg�����̂͗�R�B �@�����Ƃ��A�ߋ��ɂ͍�Ƃ̖��������A�o�ō����~�ߑi�ׂ̔s�i��Łu�͜��ɑς��Ȃ��v���g���A�����Ă��邩��A��p����₷�����t�Ƃ�����B �u�����́A���{�ɂ����镶�|��i�̉\���͂��Ƃ��A�\���̎��R��������������̂ƌ��킴��������A�͜��ɂ����܂���v �@�����f���ɓǂ߂A�u�͜��ɑς��Ȃ��v���u���Ɏc�O�v�Ɠ��`�Ŏg���Ă���͖̂����B��ɂȂ��āA�u�ٔ��ŏ��ĂȂ��������Ƃ͎����ɂ����������̂ł́v�Ƃ����Ӗ��Łu�͜��ɑς��Ȃ��v�ƕى������Ƃ������A�������������Ƃ��B��Ƃ����Č��t�̌�p�͂���B�f���Ɂu�ԈႢ�ł����v�Ƃ����悩�����̂ɁB �@1800�A�ߏ��̗V�Z��ŎГ��𗬏\���Y���B�ŏ��̓C���C���Q���g�����Z�ƂȂ�ƑR�ӎ����o�Ă��Đ^�������B�I�������̌𗬉���I�n�a�₩�B�Ȃɂ������G���C�����̐��ꐰ��Ƃ����\��B�X�s�[�`���j�R���J�B����̊��͑听���B���ȃX�R�A151�łU�ʏܕi�̃��C�����Q�b�g�B �@2200�A�e����ƃ^�N�V�[�ŋA�ЁB �T��28���i���j���� �@���Âœ��@���̂y�`�q�c�E�����c��a�@�Ŏ��S���Ă������Ƃ����炩�ɁB���K�i����]���A���̎��Ƃ̔��\�����c�c�B �@�Г����R������ɉ����������̂����ߋ߂��ɖ��炩�ɂȂ��������_�����̎��E�B�n���㉇�҂̎��E�̕���������B�Ύ����E�k�����߂����đߕߊԋ߂��\���ꂽ�����B�Q�@�I���T���Ă̏����ߕ߂͎����}�ɂƂ��đ傫�ȑŌ��ɂȂ�͂����������c�c�B���E�̈ŁB �@�`��}�L����r�c�O��������ŖS���Ȃ����Ƃ̒m�点�����������B���N�̕��̃s�b�g�C���łr�c���̎p�����������낤���B���R�Ƃ��Ȃ��B30�N�ȏ���}�L����̃p�[�g�i�[�Ƃ��āA�u���v������Ă����r�c���B�P�N�Ɉ�x����������킹�鎖�͂Ȃ��������A�����Ί�Őڂ��Ă��ꂽ�B�������N�A����тɁu���������Ȃ��̂�v�ƌ����Ă����}�L����B�Ƃ��Ƃ����̓��������̂��B�����������F�肵�����B�S�z�Ȃ̂́A�}�L������ŃK�b�N���Ɨ͂𗎂Ƃ��Ȃ����Ƃ������Ɓc�c�B�u���̉��͂r�c�������Ȃ��v�}�L����̌��ȁB �@1800�A��B�u�n���V���V�I�I�������A���N���u�v����������v���[���g�B �@���Ƃ�����͊k�t�E�j���N�[���ւŁB�������B �@����ɂ��Ă��Q��������������B �T��27���i���j���� �@0900�[���m�ÁB�{������Ƃ����āA�����N���X���s�݁B���l���ł̌m�ÁB �@�Ă̂悤�ȏ����ŏ��Ղ��������B �@�n�����ꂽ�u�[���j���[�X�v���z�z�����B���\�ꖇ�B�E�[���B�����̈ӗ~���h�������B �@1300�A��B�Ƒ��ŐH���B 1615�A��B �@�S������n�܂��Ă���m�`�b�T�Ɏ����X����B���l�ɌW�����̕X��ۂ��ނɂ����h�L�������g�ŁA�o�`�m�s�`���g�ɂ��C���^�r���[�A�̂ō\���B�X��ۂ́A�]�R�Ō�w�������o�`�m�s�`�̕�e���A�O�n������{�ɋA�鎞�ɏ�D�����a�@�D�B���Ă̓V�A�g���E�o���N�[�o�[�ɏA�q�������؋q�D���������A����ŌR�ɒ��p���ꂽ�̂��B �@�o���D�̓��}�ہA�����ۂ���v���钆�ŁA�R�x�@���ɐG����������҂��ʂ�������Ղ̑D�B �@�����҂�T�����ĂāA�،����o���̂����A�푈�ڑ̌������l�����̏،��͏Ռ��I���B �@�S�l�̐��_�a���҂����Ŋu���������������̏o�����A�����͂ɂP�T�Ԓǔ�����A�������o�債�����ƁA���̂͐����ɂ���Ɗ��������ȂǂŎ�ԂЂ܂������邽�߁A�D��ʼnΑ��ɂ������Ɓc�c�B�Ռ��I�Ȃ̂́A�o���܁A�q���|���Ȃǂ̂ق��ɁA�q��R����ς�ł������߁A���ۖ@�ᔽ�����o���邱�Ƃ�����A���ł��؋��B�ł��}���悤�ɁA�ꔭ�Ŏ����ł��鎩�����u������Ă����Ƃ������ƁB �@�u���X��ہv�i�I�����_�̃I�v�e���m�[������\�߂������{�C�R����m�C��ŕa�@�D�Ƃ��Ďg�p�j���A�������q��R�����^��ł������Ƃ����o���邱�Ƃ�����A�s�풼��̂W��19���ɁA���߉��Ŕ閧���Ɏ���������ꂽ����������B �@���{�������ɕa�@�D�̋U���ɐ_�o���g���Ă��������킩��B�a�@�D�����炱���U���ΏۂɂȂ�Ȃ��̂ɁA�ωׂ��q��R���ł́A��퍑�̝\�߂͔������Ȃ��B �@����ȋM�d�ȏ،��̐��X�B �@�v���A�X��ۂ��������Ă���o�`�m�s�`�����܂�Ă��Ȃ��킯�ŁA�u�p�b�`�M�I�v�̃v���f���[�T�[�A���P�F���̕��̒E���Ɠ����ŁA�^���̕s�v�c�����v���B �@�O�̂��߁A�l�c�ɘ^�����Ă����͂����A���s�B���̕������Ȃ������͎̂c�O�B �@�I�[�N�V�����Ŏ�ɓ��ꂽ1959�N���s�̊G�{���͂��B���R�C�i�̎����ڂ��Ă���̂��B �@���̎��́u����̂��݂Ɂ@�����܂��̂Ă��݂��Ȃ����Ă��܂����v�Ƃ����A�L���Ȏ��B�������A59�N�ł̊G�{�ł́A���̌㔭�s���ꂽ���W�Ɏ��߂��Ă��鎍�Ƃ͈قȂ�A��i�����̎������܂�Ă���B����͐V���������H �T��26���i�y�j���� �@0630�A�o�ЁB �@�ߌ�A1959�N�̒����V���k���ł߂Ă�����A�u�l�̉����v�Ȃ�A�ڃR�����ɖڂ��z�������B �@�Ȃ�ƁA�k�r�c������ŊG��`������ǂ��Ȃ邩�Ƃ����������s���Ă���̂��B�팱�҂́A�V�i��Ƃ̂s���B���吸�_��w�����̑�w�@���ł�����B�F�l�̐��_�Ȉ�̗���̌��A�k�r�c���p��12���Ԃ܂ł̕ω����Ԃ��Ɋώ@�B�L�^���Ƃ��Ă���B���f���̏����̊G������ɕω����A������ł͏b�l���A�I�Ղł͒������I�ȃf�b�T������l��������B �@�����A�ڂ��o�߂�ƁA�u����܂ŁA�`�����Ƃ��Ă��`���Ȃ������G���ڂ̑O�ɂ���v�ƏՌ�����s���B �@�����I�O�ɁA����ȁu�����v�X�ƐV���ɘA�ڂ��Ă����Ƃ̓r�b�N���V�B �@������B�����ʂ̃R�����B�u���ٌ��I���J��グ�āA�ꍏ���������ǂ����肳�������ݐM��ɐV���t�̐��k�o�钡�������u���͔��嗬�h�̑�\�̂悤�ɂ����邪�A�����̋C�����͂悭�킩�����v�ƒ��q�����킹���v�Ƃ̃R�����B �@���ꂩ�甼���I��A�݂̑��̈��{���A���k�̑��E�O�����⍲���Ă���̂�����A���{�̌��͎҂̍\�}�͉����ς���Ă��Ȃ��B �@1530�A���k��B�X��Η����̎ʐ^�W�����邽�߂ɒ���ʂ�̏�݃M�������[�u���E�J�����v�ցB �@����ʂ���O�������Ɍ������ĕ����B�t���[�}�[�P�b�g���J���Ă���X�A�Ó���A�������c�c�B�ǂ������������X�̌i�F�B�����͉��k��Ƃ����Ă��A�����ς�{���A�X�Y�i�����������������B���������O�ꂽ�����ł���Ȃɉ����������i�Əo���B���k�ĊJ���ɂȂ�A���̌i�F�͈�ς��Ă��܂��B70�N��I�ȁu���R�v�̑����������������鉺�k��̒����݁B�w�O�����ł͂Ȃ��A���̏����ȊX�̌i�F���ς��̂��B�X�̌i�F��D���ĊJ��.�B���~�ɂ��Ăق����B �@�M�������[�ɒ����ƁA���傤�ǂj�쎁�����ɗ��Ă����Ƃ���B�Lj�ʂ̕Η����̃Z���t�|�[�g���[�g�B�X�̒��A���i�ɗn�����Η����̃Z���t�E�|�[�g���[�g�B�E�[���A���̔��z�͂����ɂ����R�I�B10���قǎG�k���A�����グ�B �@1530�A�\�Q���w�B�R����Łu������I�����L�[�X�v�B �@�M���I�Ȗ싅�t�@���̒��N�j�������ƌ_��A���ƈ��������Ɏ�Ԃ�A�u���Ŏ҃W���[�v�ƂȂ��āA���V���g���E�Z�l�^�[�Y�ɓ��c�B�h�G�����L�[�X����ɉ��i���B�������A���ȉƂ̃W���[�́A�ȂƗ���Ă��邱�Ƃɑς��ꂸ�A�u�����̉Ɓv�ɉ��h���邱�ƂɁB����A�Q�l�̒����������߂ɁA�Ⴍ�������������[�������荞�܂��B�������A���[���͎���ɏ����ȃW���[�ɖ�����čs���B�Q�[�e�́u�t�@�E�X�g�v�����`�[�t�ɂ����~���[�W�J���ʼnf�扻��i���L���B �@�����̓{�u�E�t�H�b�V�[�̐U�t�̎a�V�����b��ɂȂ����Ƃ������A����͏����U�t�t���[���[�E���[�i�[�B�_���X�V�[���̌������̓{�u�E�t�H�b�V�[����������قǁB���ɁA�吟����ƌΌ��킽��̃y�A�_���X�͈����̈��B���܂Ō������Ƃ̂Ȃ��U�t�B �@��ˑޒc�㏉�o���ɂȂ�Ό��킽��̖��͂��S�J�B�A��ɂ߂Ă�̂��A�n�X�L�[�{�C�X�ƌċz�����C�ɂȂ������A�_���X�͌����B�R�P�e�B�b�V���Ȗ��͂��S�J�ŃJ�[�e���R�[�����m���m���B �@����^�������C�����ς��ʼn̂��鉉�Z�B �@�x�e20��������łQ����45���B��E�Ђ܂��̂x�c����t�s�{����Ɨ��b�B�_���X�V�[�������ł��J��Ԃ��������قǂ̏㎿�~���[�W�J���B 0930�A��B �T��25���i���j�J �@�p�X���ɂ��Ă���́A�P�J���ɂǂꂭ�炢��ʔ���g���Ă��邩����ڗđR�B������������āA��P��5000�~�B��͂茋�\�g���Ă�����̂��B �@1630�A���B�����Ń}�b�T�[�W�B �@1900�A�V�h�B�T�U���V�A�^�[�Ō��c�����u�V�g�����̗U�f To The Lonley Planet�v�B�V�����|�A�������I�ɂ��V�쏑�����낵�B �@�`�̂��̏����ȃz�e���u�g�`�y�`�l�`�v�B�D����~�肽�����������ē��𐿂��A���̃z�e�������̐��Ƃ��̐��̃n�U�}�B �g�����������ł���z���h ���⏑�ɂ������߂�ꏊ�B �@�o�̌��ǂ��Ă��Ă������������B�u�����ꏏ�ɘA��Ă��āv �@�ւ�j���āA��ӂ����o�Ɖ߂������ƂɂȂ閅�B������ߋ��ƁA�i���ɑ��������B���Ȃ����������Ԃ̐�c�c�B �@�ꐢ���r�����������n������33�N�B���g�������o�[���җ�ɋ߂��N��B�ŔN���������ߓ��m�q������Ȃ�̔N��ɁB����A�V���o�[���c�B���q����������オ�قƂ�ǂ̂悤�ŁA�����̌���̔N��w�Ƃ͎�Ⴄ�B �u�����ɂȂ��Ă��S���Ȃ�����e�̂��Ƃ��������Ă��܂�Ȃ��Ȃ�v�ƁA�������I���p���t�ɏ����Ă����悤�ɁA���ƌ�����������͔N����d�ˁA���؎��ɂȂ�B �@���Â߂�����������������O���̉��o�B�������A�K�オ��ɔM�C��тсA�Ō�͂�͂�����B�v���Ԃ�Ɍ���ɑI�B40��㔼�ɂȂ������낤�ɁA�����I�șz�X�����͌��݁B�������c�c�T�U���V�A�^�[�̋q�Ȃ������������܂�Ȃ��Ƃ����̂������̌������B �@2100�I���B �@�I�ɚ������X�P�K�łŔ������B�g�c�H���u�����@�[�Y�E�L�X�v�A��c���q�u�o�X�J�r���̖����v�A�����t��u���b�p�v�B�Í������̃~�X�e���A���k�����肰�Ȃ��D�荞��c���q��i�B�l�^�������Ƀj�����̊y���݁B�~���[�W�V����������Ƃ���͂菉���̍�i����ԗD��Ă���B�f�r���[�Ԃ��Ȃ����̍����t��͂܂������V�˓I�B�u���b�h�x���A���u�N���t�g���霂Ƃ�����r�e�A���|�t�@���^�W�[�̈�i�B�����āA�g�c�H���݂̂��݂��������n�[�h�Ȑt����B�ǂ݉����̂���}���K����B �@�f������C�J�A�i�}�R�A�^�R�ȂNJl�ꂽ�Ă̊C�Y�����͂��B���������̋��̖��B �T��24���i�j���� �@1900�A�Z�{�B�o�D������Ŗ؎R�������u���������v�B �@�ݓc���m���s���̑��������ɏ������Y�ȁB���̎��ォ���R�Ƃ��Ȃ����A�j���D�ʂ̎Љ�I�����A�����Љ�������Ă���A���鍑�̂��鋙���̏o�����B���̍��ł́A�����������E�o�ρE�Љ���������Ă���A�j�̓I�V����������A��˒[��c�ɂ����ʂ�������A�u�������̒���v�ł���Ζ����ۂ��[�܂��Ă���B���̑���A���͊C���Ƃ��Đ��Y�������s���A��Ƃ̎�Ƃ��ĉƌv��a�����Ă���B�x�@�����A���������A�Z�������B�܂�A�����j�ڂ̐��E�B �@���̋����ŌJ��L�����鏗�ƒj�̗��������B �@�펞���͑吭���^��̕��������Ƃ��Đ푈���́A���A���̂Ƃ��Ō��E�Ǖ��B�p���t�̒��Ŏ��������u���ł͊ݓc���m���吭���^��ɋ��͂����͎̂���������̖h�g��ɂ����c�c�v�]�X�ƁA�ݓc���m�̐푈���͂͂�ނ����Ȃ������Ɩƍ߂��邱�Ƃ��ʐ��ɂȂ��Ă���炵���B���̂��Ƃ͂悭�킩��Ȃ��B�����A�ݓc���m�����A���{�Ɠ��{�l�ɑ��āA�����I�Ƃ������镡�G�Ȏv������������Ƃ͂��̎ŋ������Ă��悭�킩��B �@�V�c���t�@�V�Y�������]���Ė����`�o���U�C�̐��̒��ɓ]���������̓��{�B�������A���{�l�̐S���͍��{�I�ȂƂ���ł͂܂������ς���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�u�����j�ځv�̖������E���A�������ɂ������ɕ��Ă����\����Y�킹�Ȃ��畨���͖������B�풆����ʂ�������̑̌�����A�ݓc���m�́A���͂���{�l�Ƃ������̂ɁA�[���������������Ă��Ȃ������c�c�H �@����ɂ��Ă��A�i�s����t�@�V�Y���̖h�g��H�@���ꂪ�L���Ȃ̂��^�킵���B�u�����̖\���𐧌䂷��v�Ƃ����u����ځv�̌����}������Ɏ����}�̖\�������������Ă���̂Ɠ����ŁA���͂ɓ�����A���͂ɂȂ�B�u���̎��v�́u�吭���^��v�̕��������ɂȂ�̂́c�c�B �T��23���i���j���� �@0730�N���B �@����C������߂����c�u�c���R�[�_�[�𐘂����B��ؐ������W���_�r���O�B �@1230�A�߂��̂j�N���j�b�N�ցB��T�s�����������\�B���ʂ��܂ł͕s�����������A���S�N���A�B����̉_�����������A�L�������v���B �@���N�ł��肳������ΐl���̂X�O���͍K���Ȃ̂��B �@�@�A���ƁA�̒�������Ċw�Z���x�؎����m����߂����ƌ����Ă���B�����Ă܂����B 1500�A�q����d�b�B���̌�AM����Ɠd�b�łЂƂ����肨�b���B �����̂m�{����A�ʐ^�ƁE���T�i���v�l�̏H�t�Ȃ݂��P���ɖS���Ȃ�A30���ɗ�܂������Ƃ̒m�点�B�H�t����ɂ͕��̖݂��ʼn��x��������Ă���B�܂��Ⴂ�̂Ɂc�c�B �T��22���i�j���� �@1530�`1630�A��c�B �@1930�B�ю����B�w����15���B���݂��p�[�N�X�^�W�I�̕~�n�ɂ����؋��Y������ЂQ���q�ɓ�������Ō��c�V�~���q�u�R�{�R�O�V�v�B �@�J���O�Ɍ��V���̕ҏW���E�~�{����Ƃ�����ׂ�B �@���̐Ȃ���u�Z�Z���[��v�Ɛ���������ꂽ�̂ŐU��Ԃ�ƁA�h��ЂƂ݂Ƃl�����q�B�q�Ȃɂ͔����̂`�n���R�Ƒ��c����̊���B �@������ȁB�J�����ԂT�������ŃX�^�[�g�B �@����͔s�풼��̔����`���牓���u�Ă�����R�̒��̏W���B�s��̂ǂ������Ŗ]�܂ʎq�����h�����������̋삯���ݎ��̂悤�ȕa�@������B�����ɁA�u�߂�ǂ肳��v�ƌĂ���l�̋����������Ă���B�ޏ��͐펞���Ɉ�l���q���Ɏ���Ȃ��悤�A�͔͓I�Ȉ����w�l����������A����̒S���҂Ɏ��������肵�����̂́A���W�ߏ������݁A���q�͉����B�A���ė����̂́A��̍����ɉp��̕������������������B�u�����̃o�J�����[�A�V�c�̃o�J�����[�v���Ԕޏ��͋��C�̐��E�Ɂc�c�B �@���̔ޏ����ĕ��ɖ_�ʼn��肩�������Ƃ����̂ŁA�i���R�̈ӂ����n�����N�U�̎��Ƃ��ĕ���������荞��ł���B �@�������A�]�R�Ō�w�̋��E�؍����E�����߂ĕa�@�ɂ���Ă���B �@�u�߂�ǂ肳��v���߂���A�������ƁA��t�A���@���҂����̍j�����B �@�푈�Ƃ�����ƃ��N�U�ɑ����镜���������̏��𗍂߂āA�u�E�����ȁv�u�������т�v����̃e�[�}�ɂ�������B �@�܂�Łu�p�b�`�M�I�v�Ɠ����e�[�}�B �@��Ə��������N�����悤�Ƃ��������i�̋r�{�́A���疟�ŁA���܂����ݍ���Ȃ��������ڗ������̈ӗ~�Ǝu�͔����B �@�L�����݉��B�C���g���̃Z�b�g���c�����s�ɓ������A�č\�z����͈̂ېV�h�̕���Ɏ��Ă���B �@���ӂ̃X�y�N�^�N�����o�͑z����Ƃ͂����A��͂������������Ȃ点��B �@��P����50���B �@�J�[�e���R�[���̈��A�ŗ�߂��݂��܂��݂Ȃ��炨�l�т̌��t�B �@�Q�l�v���Ŏ��̂�����A�V�l�̔o�D���P�K�����R�B��T�̖ؗj���ɓd�b�ŕ����Ă������A�ڂ������Ƃ͍������߂ĕ����B �@���ɂ��A�V�l�̓Q�l�v�����ɁA�C���g�����痎�����A���W���܁B�x�@�̎������A�u�������~�A���c���U�v���l�����Ƃ̂��ƁB�������A�P�K���������҂��A���c���������肵�A�P�K����ՓI�ɒZ���Ԃʼn������Ƃ�����A���c�̘b�������Ō������~�ɂ͎���Ȃ������ƁB �@���c���̃P�K�ʼn��U�܂ōl���ɓ����̂͂ǂ��Ȃ̂��Ǝv�������A���c�̐���҂ɕ����u���c�̕s�ˎ��Ƃ������ƂŁA����͓��R�l����ł��傤�v�Ƃ̂��ƁB�Ȃ�قǁA���c�^�c�Ƃ͓�����̂��B �@�I����A�Έ��Ɨ��b�B�@�~�{����͗����A������f�Ƃ̂��Ƃň��݉�͎��ށB�N���̐X����A�X�^�b�t�̂m���A���D�̏��F����Ɖw�Ɍ����r���̒��؉��Ōy����t�B�r�[���t���P�_��500�~�Ƃ₽��ƈ����X�B �@���F���q����͐N���̒������D�B�����o�g�B�n�������������Ƃ̂��ƂŁA�܂��͂��������H�ו��̘b�ȂǁB�u�����q�͂���ς�n���Ɍ���܂��v�Ƃ��B �@�Ί炪�f�G�ȏ��D����ŁA�悭����ƈ��^���Ǝ��Ă���B�u�Ⴂ�R�Ǝ��Ă�Ƃ�����̂͊������I�v �@���D�炵���A�j���ۂ������C���B�C������Ȃ��Řb����^�C�v�̂悤�B �@�H�̒�����i�ɏo���ł���������B�A��ɁA���A���N����������ł��A�ƁB�R�N�O�ɖS���Ȃ������e�̖��O��������āu���F�鏼�v�ɂ����̂��Ƃ��B �@2300�A�ю����w�ŕʂ�Ēn���S�ʼnƘH�ɁB �T��21���i���j���� �@1545�A�d�����I���ċ���ցB�V�l�J�m���Łu�p�b�`�M�I�@�k�n�u�d���o�d�`�b�d�v�B�q�Ȃ͒����N�������A40�l��̓���B �@����̕���͓����E�]����̍ݓ����Z��E�}��B�A���\���̑��q�E�`�����X����a�E�W�X�g���t�B�[�Ƃ킩��A���̎��Â̂��߂ɓ����̏f���v�w�̌��ɐg���Ă���B��Ɩ����ꏏ�B ���L�����W���̓`�����X�̓��a��p���҂����߂Ɍ|�\�E��������ӂ���B�A���\���͍ݓ��̃S�b�h�}�U�[�̏����ŁA���E���ɋ���ƕăh���̌���������@�̎d���Ɏ�����߂�B �@�O�삪�A1968�N�Ƃ����A�����Ɋ�]�����������{�̐t����Ȃ�A����̕���1974�N�́u�t�v����������A���̒�������ɑ��ꂵ���Ȃ�r�j�[�����̃t�@�V�Y�����䓪���Ă��鎞��B �@�ݓ��̈�Ƃɂ����̎��オ�d���̂�������B �@������A�O��̂悤�ɁA�n�`�����`���œ˂��������t����ł͂Ȃ��A�g�[���͂��A�T�ɂȂ�B �@�������A���̒�ɗ����F��͓����B�u���v�Ɓu�푈�v������̃e�[�}�B �@�|�\�E���肵���L�����W���ɗ����͂�����u���ʂ̖��v�B���̍�����錾���ꂽ�`�����X��K���Ɏ�낤�Ƃ���A���\���B �@�p�������ŕ`�����̂́A�A���\���ƃL�����W���̕��e�W���\���̐t�B���{�R�ɒ�������A����̓��ɓ��S����W���\���B�ߋ��̐푈�ƁA�L�����W�����o�����錻�݂̐푈�f�悪��������B �u�푈���������f��̓A�J���B��҂��E�Ȃ炦�������������v�ƐΌ��T���Y���w���́u�E���푈�f��v��ᔻ�����䓛�ēB����قǒ��ځA�f��̒��ŁA�푈�����f���ᔻ���Ă���Ƃ͎v��Ȃ������B �@���ꂱ���䓛�߁B �@��҂̉E�X���ɂ́A�퓬�I�ɑR���ׂ��B �u�����͂����炱��Ȃɂ��ƂȂ����A��i�ɂȂ����̂��B���ꂩ��̃t�@�V�Y���ɑR����ɂ́A������������g���Ăł����܂�Ȃ��B�X�L�����_���X�Ȏ�i���g���Ăł��c�c�v�ƌ������͍̂����M���������B �@�C���^�[�l�b�g�ł́A��ɂ���āA�l�b�g�E���E�t�a�������m�����ɂ��䓛�ēᔻ�������y�[�W�̃g�b�v�ɕ\�������悤��삪�s���Ă���B�f����q�b�g�����邱�ƂŁA������̕@���������Ă�肽�����̂��B �@��K�G���J�̏o�����ނŎ���ɔ��F���ꂽ������肪���ɑf���炵���B�������L���b�ƌ��Ԏd���̉��Ȃ��ƁB1960�N��̓����f��̃q���C���̂悤�Ȑ��^�Ȗʗ����B�ǂ��ƂȂ����삢�Â݂ɂ����Ă�B����ŁA�����R�n��ł͋C�̋������������B�v�X�̃q�b�g�B���̏��D�͐L�т�B�䓛�ē̖ڂ͊m�����B �@�����A�A���\�����̈��r�Ƃ̋����̎ŋ��̓c�����Â��B�����炪���Ă�悤�Ɍ�����̂���_�B �@�O��͌㔼�A�����̘A�����������A������̂͑�l�߂̃V�[�������B�������A���ꂾ�������̉f��͍��̉f��E�ł͂Ȃ��Ȃ����Ȃ��B �@����ɓ��S�������N�l�̃��f���̓v���f���[�T�[�̗��P�F���̕��B�푈�Ŏ���ł���Η��������̐��ɐ��܂ꂸ�A�u�p�b�`�M�I�v���a�����Ȃ������B�u���ʂȁB�������т�v�B���ꂪ����̃e�[�}���B �@����ɂ��Ă��A�T���Y�f��ɐ��@�i���o�����Ă���Ƃ́B�ǂ�ȗ��������悤�Ƃ��A�푈���������A���U���������f��ɏo��Ƃ������Ƃ́A�o�D�Ƃ��Ă��̉f��̕�����F�߂Ă���Ƃ������ƁB�b�q��������B���{�̓��U���ƃC�X�����̎����e�����ꏏ�ɂ���ȂƂ������A���ꂱ���C�X�������ʁA���U�����ɂق��Ȃ�Ȃ��B���U���͖��Ԑl���������܂Ȃ������Ƃ������A�P�Ɏ˒����Ȃ����������ł͂Ȃ����B�A�����J�{�y�Ɍ����ĕ��D���e���������{�B���炩�ɖ��Ԑl�����W�I�ɂ��Ă���B�b�q�̌������͏�E���Ɠ����B�t�����X�d���݂̃��x�����X�g���������̂��B 1900�A��B �T��20���i���j���� �@0900�A�[���m�ÁB10.00�`�x������B�V��̏Љ�B�܂�30��B�����炵�����Ă邪�A�{���I�ɂ͍ʼnE�h�c���B�^�c�Ɍ��o�����邱�Ƃ͂Ȃ����낤���c�c�B �@1300�A�A��B �@�Ƒ��Œ��H�B���̌�A�������ƂŎg���Ƃ����̂ŁA�c�������ɔ��A�X�`���[�����ɁB�������͂c�������B�Ȃ�ł��u���Ă���B�P�b�~�P�E�W�b�łQ�W�O�~�B�������A�����A�肪��ρB���������A�^�Ԃ̂�����V�B�d�Ԃɏ��O�ɁA���ɕ��Ő^����B �@�C��������Ԃ��Ǝv���A���������ɍs������A�[���܂ő�ԗցB �T��19���i�y�j���� �@1600�܂ʼn�ЁB �@�H�t���Ń��h�o�V�J�������ꏄ�B���܂ǂ��̂c�u�c���R�[�_�[���ǂ�Ȃ��̂����邽�߁B�������q�ł������Ԃ��X���B��^�e���r�̃R�[�i�[������킢�B50�^�A62�^�Ȃ�Ă�������e���r��ʂ𐘂�������Ƃ��Ăǂ�ȉƁH�@�Ɠd���i�F���锃�����q�̎p�����Ă���ƁA�s�����̒����J�b�g���́A���[�L���O�v�A���́A�Ƃ��������͂ǂ��̍��̘b�Ǝv���Ă���B �@1800�A�O��B�����Z���^�[���̃z�[���łf�Q�v���f���[�X�u�c�O�m�t�̐X�v�B �@��n�k�ɂ��n�\�ړ��ł��ׂĂ̋��E�����B���ɂȂ��Ă��܂��A������ԂƂȂ����ߖ����̓��{�B �@���葱����u���l�v����������o�߂�̂�҂�Ƃ̓@��ɁA��x���߂����̎��̂��@��Ԃ����Ƃ���Z���A�܂��낢���N�U�c�c���܂��܂Ȑl�Ԃ��W�܂��Ă���B�u���l�v�����肩��o�߂��Ƃ��A�ނ�ɉ����N����̂��B �@�f�Q��E���o�ِ̈F�̃t�@���^�W�[�B���X�g�V�[���ŁA�o��l���������������鋐��ȉ~�ՁB�납���ї����́u������ȁv�~�Ղ́A�����ւ̕s���̏ے����B�������߂Č���ɗ������q����ɂƂ��Ă̓L�c�l�ɂ܂܂ꂽ�悤�ȕ���H �@�剉�̕Ћːm���������A�⋴���q�������̎����������Č����B �@2010�I���B �@�����ĎO��w�܂ŁB �@2200�A��B �@���m�̗��Ă����莖���Ɖ���̎��q���o���̊֘A�B �@���Ɨ\�Z�Řd���Ă���ȏ�A�r�`�s�͊e���x�ɏ�������`�����A�����I�ɂ͌x�@�����g�D���Ă�����ꕔ���B�����x�@���̃g�b�v�A���Ԋޒ����͌����m���x�{�����B���{�Ɲ፧�̊ԕ��B�ߋ��̖k���N����݂̎����������o���āA�u�f�v�Ɛl�v�����ێ�z����ȂǁA���{�̊��U����������Ă���B �@����A���V�Ԋ�n�ڐݐ�̕Ӗ�Í���ӊC��̊������ɊC�㎩�q�����o���������Ƃ̈Ӗ��B �@���q���������ێ��̂��߂ɏo���ł���̂́A��K�͂Ȗ\���̂Ƃ��Ȃǂ̏ꍇ�ɁA���t������b�̖��߂�����ꍇ���m���̗v��������ꍇ�Ɍ����Ă���B �@����̏ꍇ�A�s���������ȍ��荞�݂�R�c�������s���Ă���킯�ŁA���Ɠ]���́u�\���v�ɂ�����͂����Ȃ��B�������A���ꌧ�m���͋L�Ғc�ɑ��A�u���̂��߂ɂ���̂�������Ȃ��v�ƕs�����������ɂ��Ă���B�m���̗v���ł��Ȃ��B �@�������A���q�����g���u�h�q���̖��߂ɏ]�������Ȃ����A���q���ɖ��ԋƎ҂̂悤�Ȋ������̌o���͂Ȃ��B�C��ۈ������s���x�����ł��Ȃ��v�ƌ˘f���Ă���B �@���ꂶ�Ⴀ�A�N�����q���̎����o����v���������B���ړI�ɂ͋v�Ԗh�q���̖��߂��낤���A���q���́u�ō��i�ߊ��v�͈��{�B �@���{�������o����v���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@�h�����ꂽ�C���̑|�C��́u�Ԃv�ɂ͑�C����������Ă���B�ʏ�A���̂悤�ȊC��x���͊C��ۈ����̖�ځB������u��C�v��ς��q�͂��o������Ƃ́B �@�u�ō��i�ߊ��v������{�������̗͂��֎����Ă���Ƃ����v���Ȃ��B����ɑ��A���ق𑱂����V�����ُ�B �@�킸���ɁA�����V���������u��\�͂ɓO���镽�a�I�ȍ��荞�ݍR�c�s���ɑ��āA�@�����Ȃǂ̌x�@�����ł͂Ȃ��A�����Ȃ�R���𓊓�����Ƃ����̂͐�i���ł͂���߂Ĉٗ�B���̏ꍇ�A����̐��_�݂̂Ȃ炸�A���ې��_�̔����������N�����\��������v�Ƃ̋L�����ڂ����B �@���m�E���v��̎����ƁA����̎��q���o���B �@����́A��������l�̑e�\���N�U�ґ���ɁA29���Ԃ������𑱂��A����́A������邽�߂̎s���̍R�c�s���ɑ�C��������|�C��͂�h������B��ɑ��֊W�͂Ȃ��Ƃ�����������Ȃ����A�w�����ߌn���͓����B �@�u��ヌ�W���[������̒E�p�v�Ƃ����Ε��������������A�v����Ɂu��O��A�v�B���͂�u��O�v�͔�щz���āA�u�J��O��v�܂ők�����Ƃ����Ă������B �@���Ɂu���a�v�̂��肪�������g�ɟ��݂Ă킩�鎞�オ����B���̂Ƃ��͂����x�����ǁB �@���N�ł���Ƃ��͌��N�̂��肪������������Ȃ��B�a�C�ɂȂ��Ă͂��߂Č��N�̂��肪���݂��킩��B �@���a���@�������ꂽ�Ƃ��ɂ͂��߂Ď��������������ɕ��a�����Ă��������킩�邾�낤�B �T��18���i���j���� �@��[�����������m�E���v��̘U�鎖���́A���ɂȂ��Ă��P����ԁB �@�ߌ�ɂ͐l�����E�o���A�Ɛl��l�������Ƃ����̂ɁA���x�͂����Ɖ䖝�̎q�B�f�l�l���ł͕s�v�c�Ȃ��ƁB�ق��Ɏ藧�Ă͂Ȃ��̂��B �@���N�U�E�E���ɊÂ��x�@�B�܂����A���肪�����N�U������A��������Ă�Ƃ����킯�ł�����܂����B�����A���ꂪ�Z�N�g�̊����Ƃ�������A�S�O���邱�ƂȂ��˓��E�ˎE�ƂȂ��Ă��������B �@���Ƃ��玖���������Ă���悤�Ɍ����錧�x�B �@������������������A����̃L�����v�E�V�����u�ł̕ČR���V�Ԕ�s�ꌚ�ݒ����ŁA�C�㎩�q�������Δh�s���ƑΛ����Ă��邱�Ƃ��ߏ����邽�߂̗z���Ƃ������Ȃ����Ȃ��B �@�ČR�́u�Ԍ����v�Ƃ��ĊC�㎩�q�����O�ʂɏo�āA���ځA����s���ƑΌ�����̂́A���j�I�Ȏ����B�u�����o���v�Ƃ�����B�{���Ȃ�A�V���̂P�ʃg�b�v���B���ꂪ�A���v��̎����ł�����ł��܂����B �@���N�U����ɐT�d������{���B�s�v�c�Ƃ����Εs�v�c�B �@0830�A�Ɛl���O�ɏo�Ă��đߕ߁B �T��17���i�j���� �@1430�A���c�q�̂s�����ЁB���m�̏��D�E�j����s�B�U�������u�T�����v�̏��B���������������Ɂu�T�����v�Ƃ͂܂��c�c�B �@1620�A�j�L�O�a�@���I�B �@1800�A��B �@�R�I���ʂ������r�[�A�S�[�}����Y�ɖ߂����Ό��T���Y�s�m���B�ᔻ�̓I�������u���؊C�O���@�v�����ւ����Ƃ��B �@���T14���Ƀj���[���[�N�֏o���B�s�E��10�l�������A��Ă̑喼���s�B�h����̓}���n�b�^���̂T���z�e���B�S���U���ɁA�s�̗\�Z���z��1900���~�B �@��s�s�ɂ������_���Y�f�팸�v���W�F�N�g��b�������u��Q�E��s�s�C��ϓ��T�~�b�g�v�Ƀp�l���X�g�Ƃ��ĎQ�����邽�߂Ƃ������c�c�B���̊��ɂ͑؍݃X�P�W���[�����X�J�X�J�B �@���������̃E�G���J�����Z�v�V�����͑̒��s�ǂŌ��ȁB�؍݂Q�A�R���ڂ͓����P�A�Q���ԂقǃZ�~�i�[�ɏo�Ȃ��A��͗[�H��܂ŗ\��Ȃ��B�S���ڌߑO�ɋL�҉���ς܂�����A�c��͊��S�Ƀt���[�^�C���Ƃ����B �@����ł͉��̂��߂ɍs���̂��킩��Ȃ��B �@����ɂ��Ă��B�S���U����1900���~�I �@�f�v�ɉƑ��S�l�łP���Q��10���~�i�����^�J�[���݁j���A�u����Ȃɒ��ґ�ȗ��s�����āA�o�`��������Ȃ����v�Ǝv���Ă��܂������ɂ͑z�������Ȃ��o��B�Ό��̏ꍇ�A�S���ŋ�������A�ӂƂ���͒ɂ܂Ȃ����c�c�B�܁A�I�s���͂������ƐΌ��Ƃɐŋ������サ�Ă��������ȁB �@�A���ƁA�e���r����ٔ��������B���m�E���v��Ō��\�͒c���ɂ��l���E�ď鎖���������B �@�Ɛl�ɏe������A���������x�������֘e�ɓ|��Ă���l�q�����X�Ɖf���Ă���B�~�o�ł����A���̌�A�T���Ԃ����u���ꂽ�̂ɂ͎���Ђ˂������A����̏��s���ł͉��������Ȃ��B�Ɛl�����������x�����u�l���v�Ǝ˒��ɓ���Ă����̂�������Ȃ����B �@�x���~�o�̍ۂɂr�`�s��������e�����S�B�܂�23�B�Ԃ�V�����܂ꂽ����Ƃ��B�ɂ܂����B�}�E�̃��X�N���傫�����߁A�r�`�s�����͑S���Ɛg�Œ��j�͊O���Ƃ����K�肪����Ƃ����̂̓K�Z���H �@�����̕�e�S�E���N���u�푈������ΐl�E�����ł���̂ɁA�푈���N���Ȃ����獡�l���E���Ă��܂����Ǝv�����v�Ƌ��q�����Ƃ����B �@ �T��16���i���j �@0730�N���B �@1130�A�s���֗����ׂċߏ��̃N���j�b�N�ɁB �@1300�A��B�Ɛl�ƎU�����Ă�A�w�O�̃V�������i���X�ł����B �@�Q�T�ԂقǑO����c�u�c���R�[�_�[���_�r���O�ł��Ȃ��Ȃ����B�n�[�h�f�B�X�N�ɘ^��͂ł���̂�����܂��������ƕ��u���Ă��������A�������̂c�u�c���R�[�_�[���Q�`�R���O���瓯���Ǐ�B�^��͂ł���̂ɁA���f�B�A�Ƀ_�r���O�ł��Ȃ��B����͑傲�ƁB�c�u�c���R�[�_�[�������̘^��@�ɂȂ��ẮA�厖�Ȕԑg���i���ɂg�c�c�̒��ɕ���Ă��܂��B �@�قړ������ɔ������p�C�I�j�A�̋@��B�u�c�u�q�|�T�P�O�g�r�v�Ɓu�U�P�O�|�g�r�v�B�S�N�O�A�o�n�߂̍�������10���������̂����͓������\�Ŕ��l�B����̓f�W�^�������ɍ��킹�ĉq��������^��ł���@��ɃV�t�g������B������Ƃ����Ĕ���������̂͋ƕ��B �@�T�|�[�g�Z���^�[�ɓd�b����ƁA���ɒ��J�ȉ��B�u�T�|�[�g�Z���^�[�Ƃ����Ζ����z�Ŗ��f��v�͍��͐̂��B �u�Q����������グ�����������̂ɁA�ǂ����\����܂���v�ƒ�p���B �@�������A�P��ɂ��Q������~�̏C���������Ƃ����B�Y�������A�P�䂾���C���ɏo�����ƂɁB�Q��łU���~�̏C������Ȃ�^���������ق��������B �@����ɂ��Ă��A�f�W�^�����͕̂s����o��ƁA�I�[���E�I�A�E�i�b�V���O������|���B120�M�K�̂g�c�c�ɂ��ߍ��ԑg�������邩������Ȃ��̂�����炢�B �u�f�B�X�N�����̏C���ōς߂A�g�c�c�͏��������܂���v�Ƃ͂������̂́A�m���͒Ⴂ�B �@�����Ȃ�ƁA�p�\�R���W�̃N���b�V�����C�ɂ�����Ƃ���B���̂Ƃ���A�����オ�肪�x���A���삪�݂��B�g�c�c���I�V���J�ɂȂ�����ڂ����Ă��Ȃ��B�c��ȃf�[�^���ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��B �@�U���ɍs���r���ŁA�u�R�W�}�v�Ɋ��A�O�t���̂g�c�c400�M�K���w���B�Q���~�B�n�[�h�f�B�X�N�������Ȃ����B �@�Q�J���Ԃ�ɏ����ɍs���ăT�b�p���B �@1830�A��B �@�l�E�s������A�v��ʃv���[���g�B���R�C�i���S���Ȃ�O�̐����ɂl���̉�����ɏo�����N���̃R�s�[�B�̒���������Ȃ��ɂ��ւ�炸�A���M�̔N�����������R����̗��V���B �T��15���i�j���� �@�����ŕ�e�S�E�A�������x�@�Ɏ��Q����17�Ώ��N�̎��������B�������A�������̂��̂����A�l�b�g�Ɂu����Ȏ����͂����H���C���v�Ə������ގ�҂̕����s�C���B�@ 1700�A�O�������B �@�L�����b�g�^���[�̂Q�K���X�ŁA�����c���́u�]�݂��̌����v�i���t���Ɂj�A�ƃ��b�N�{�u�d���l�ԃx����S�v�i�o�t�Ёj�B �@�����c���̒Z�҂�ǂނ̂͋v���Ԃ�B�u�i�|���I�����v�ȗ��A�قƂ�ǂ̍�i�͓ǂ�ł������A�ŋ߂͂Ƃ�Ƃ��������B 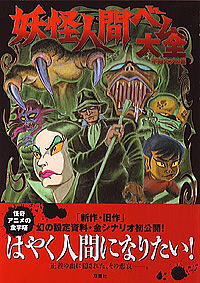 �u�d���l�ԃx���v��1968�N�ɕ������ꂽ��i�B���x���ĕ�������Ă���A������č������l�C���ւ����A�j���B �u�d���l�ԃx���v��1968�N�ɕ������ꂽ��i�B���x���ĕ�������Ă���A������č������l�C���ւ����A�j���B�@�������A���o�C�o���u�[���������Ă��A���̍�i�Ɋւ��Ă͍�҂Ɋւ��Ă��A�����ЂɊւ��Ă��قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��B�����ƋC�ɂȂ��Ă����̂����A�{����ǂ炻�̃i�]���������B �@���̗��ɂ�1965�N�ɒ������ꂽ���؊�{��������Ƃ����B�܂�A���̏��ɂ��A�؍��Ƃ̕����𗬂��ϋɓI�ɐi�߂��A���̎�i�Ƃ��āA�����A���E�I�ɔF�߂��Ă������{�̃A�j���ɔ��H�̖�������Ƃ����̂��B���{���G�[�W�F���g���L���㗝�X�u�����B��v�����o�[�͓����A����ŃA�j���X�^�W�I���o�c���Ă����X��M�p���B �@2001�N�ɍs��ꂽ�u���̗v�f�ڂ���Ă���B �@�X�쎁�͉Ƒ�������A�ŏ��Ŏ�������A�����������A�؍��ɃA�j���w�����邽�߂ɓn��B �u�펞���A�Ô����F�̌��A���f�Œ����l�ɓ���������Ă���A���{�R�̒����E���N�����ւ̎c�s�s�ׂ�ڂ̓�����ɂ��Ă������߁A���̊؍��ւ̏����̋C�������������v�Ƃ����B �@�������āA�؍��ɓn�����X�쎁��̋��̖��ɍ��ꂽ�̂��u�����o�b�g�v�Ɓu�d���l�ԃx���v�Ȃ̂��B���{����G�R���e��V�i���I����A���A�؍��ō��A���F�A�Z��������B�f�l����A�j���[�^�[����Ă��J�͕����ł͂Ȃ��A���ɂ͏o���オ������i���m�f�ɂ��A�����ňꂩ���������Ƃ��������Ƃ����B �@�������A���؋��͂́u�x���v�ȍ~�ڍ�����B���؋��͂̔����̂��ƁA���̂Ƃ���A���{���̑_���͊؍��̈����J���͂��ړ��Ă������̂��B��A�ɂ������p�A�r���̕������̂Ȃǂ��l����ƁA��p�Ό��ʂ͂Ȃ��A���{�ō�����ق��������オ�錋�ʂɂȂ����B �@�������āA�؍����̐��ӂ𗠐�`�ŁA���{�ɖ߂����X�쎁�͈ȍ~�A�Ăъ؍��ɓn�邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B�u��Ж��߂Ƃ͂����A�ꏏ�ɃA�j������ɂ������ޓ������̂Ă����ƂŁA��x�Ƃ��킹��炪�Ȃ������v�ƁB�����Ė����Ȃ��؍��̐l�����̌��̂ɂ��ނ悤�ȓw�͂��琶�܂ꂽ�A�j���u�d���l�ԃx���v���������{�̎q���Ɉ����p����l�C�̂��邱�Ƃ������B��̐S�̋~���c�c�ƁB �@�����Е��̊G�A�Ɠ��̃^�b�`�A���ꂪ���͊؍��̖����̃A�j���[�^�[�Ƃ̋�����Ƃ��琶�܂ꂽ�ƒm���āA���߂Ĕ[�����������B�u��O�̉߂����J��Ԃ����A���a�����A���ʂ��Ȃ����A���E���̐l�X�ƂȂ��悭���Ăق����v�ƌ��X�쎁�́A�u������82�B�����Ȃ�88�B �@��{�̃e���r�A�j���ɂ܂��l�X�ȃi�]�Ɛ^���B�u�x���̐V��c�u�c�̃v�����[�V�����v�Ƃ����w�i�͂���ɂ���A���̂悤�ȗ��ʎj�@���A����̖{�ɂ����X�^�b�t�̔M�ӂ͑f���炵���B����26�b�A�V��26�b�̊G�ƃX�g�[���[���f�ځB �@1900�`2035�A�V�A�^�[�g�����Łu���̃o���G�[�V�����v�B�C�v�Z���̍ė��v�ƕ]���������m���E�F�[�̋S�˃����E�t�H�b�Z��01�N�Ɏ����ŏ��������Y�Ȃ��t�����X�̉��o�ƃA���g���[�k�E�R�[�x�����o�B���̎�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��u�N�Ƃ����j�v�i���ˋ��O�j�Ɓu�N�Ƃ������v�i�������q�j�A�����āA�Q�l���P���Ă�������́u�Ⴂ�j�v�u�Ⴂ���v������Ō�������B �@�Ɩ��͗��Ƃ���A�قƂ�ǔ����̒��ŁA�����Ԃ₭�悤�ɐi�ޕ���B�E�[���c�c�B �@�q�ȂŐΈ�ЂƂ݁A���c�b�ĂƗ��b�B�Έ�͂P������i���X�ň�l�ŋ������Ƃ��B���t�Ƃ��g���ƂȂ�ƁA����Ȃ�ɔ�p��������B�ŁA�u����͎��ЂƂ�Ȃ�ł��c�c�v�ƁB �@�i�c���܂łl���̂s������ƁB��T�܂łP�T�ԁA�j���[���[�N�������Ƃ��B�u���[�h�E�G�[�~���[�W�J���O���Ƃ͂����܂����B �@���{�̐l�C��萭��Ƃ������ׂ��u�ӂ邳�Ɣ[�Łv�B�l�������Z���ł̈ꕔ���̋��̎����̂ɔ[�߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �@�l�������n���ł́A���N�U������ېŏ����̈ꗥ10���ɕς��B�u�ӂ邳�Ɣ[�Łv�́A���̂P��������ɁA�̋���A�����̍D���Ȏ����̂ɔ[�߂��鐧�x���B �@�u�����A����͂�����Ȃ��I�v�Ƃ����l�����邩������Ȃ����A�[�t���I���ł���͉̂ېŏ����̂킸���P���B �@07�N�x�̌l�Z���ł̐Ŏ��͖�12���~�B�����S�����P�����̋��Ɉڂ����Ƃ��Ă��P��2000���~�A�n�������̂̍Γ����z�͖�83���~������R���}�ȉ��̃p�[�Z���e�[�W�B�������A�T�����[�}���͌���������A�ӂ邳�Ɣ[�ł��邽�߂ɁA�Ŗ����ɍs���Đ\���葱������l�����l���邩�B �@���ǁA�ŋ���n���ɐU�蕪���邽�߂̎��������Z���^�[������āA�����ɖ�l��V���肳���Đŋ���H���ׂ������B �@�u�ӂ邳�Ɣ[�Łv�ȂǁA�c�����l�̐V��̐ŋ������܂�����i�ɂȂ邾�����B �@�A�z�炵���B �T��14���i���j���� �@�l�ԃh�b�N�B0700�o�Ђ��A�d���B0900�A�r���ەa�@�ցB0920�Ɏ�t���������A�ҍ����͐l�ł������Ԃ��Ă���B�R���s���[�^�[�V�X�e�����_�E�����A��t���ł��Ȃ��̂��Ƃ����B�u�����̌��ʂ��������Ȃ��̂ŁA���ɂ���ς�����͂��\���o���������v�ƃA�i�E���X�B�������A���Ԃ�����Ĕ����h�b�N�ɗ����l����B�����ȒP�ɃX�P�W���[���͕ς����Ȃ��B�������ɐH���Ċ|����s�N���B������́A�ǂ����d���̖ڕ@�����Ă邵�A�Ƃ������đ�g�B0940�ɂ͕������邪�A�O���l�܂�����ԁB�����Ȃ�X�C�X�C�ƌ������i�ނ̂ɁA�����͂Ȃ��Ȃ��i�܂��B�Ō�݂̈̂w���������I������̂�1230�B�H�������ĉ�ЂɈ����g�����̂�1300�B�������ʂ��ɍĂѕa�@�ɖ߂�����A�Q��������B 1600�ގЁB �@�������[�@�Đ����B���̓��������{�̓]��_�ɂȂ�B�u����60�N�ɋy�ԕ��a�Ɓi���肻�߂́j�����`�̎��オ�������v�ƁA�ߖ����̗��j�ɋL����邾�낤�B �@ �@�u�L�����[�����̉ߔ����v�Ō��@�����������B���@����������ꂽ���̂��B �@���@��ς���Ƃ����͍̂��Ƒ̐���ς���̂Ɠ������ƁB�A�����J�́u���@�C���v�Ƃ͔�r�ɂ��Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�u�L�����[�����̉ߔ����v�Ō��܂�Ƃ́B�������A�Œᓊ�[���̋K����Ȃ��B��Ђ̎Ј�������āA�葫���ɖ����Ȃ���Εs�����ɂȂ�B���@�����Ȃ�A�u�S�����̉ߔ����v�ɋ߂��A�������L���[���̋K�肪�����ē�����O�Ȃ̂ɁA�����E�����i���̃k�G���}���I�j�̃S�������B�������A�������E�����̔��Ή^�����֎~����Ƃ́B �@�u��]�͋����҂̌��_�v�Ƃ����Ă��A�����܂ŃR�P�ɂ���Ă��A���r�����̍����ɂ͂قƂقƃA�C�\���s����B �@��ɂ���āA��V���́A�@�����������Ă���A�u�������[�@�̖��_�v�����҂Ɍ�点�A�}�X�R�~�̗ǎ��̃A���o�C���B��������A�@���R�c����Ă���Ƃ��ɁA������ƕ����A�Љ�ʂŁA�Ƃ��������Ȃ�B����̍����͔ԑg���ƎЉ�ʂ������Ȃ�����B�߂������̓��{�^�t�@�V�Y���i�i�E�t�@�V�Y���H�j�̐ӔC�̈�[�̓}�X�R�~�ɂ���B �@�����A���R�Ƀ��m��������̂͂��ƂR�N�B���̌�́c�c�B �@����ɂ��Ă��A��ԕq���Ȃ͂��̊w�����҂������܂Ŗ��S�Ƃ́B��������]�̐F�Ȃ�A����͂��̂܂��������ɒ��˕Ԃ��Ă���B�Ȃ̂ɁA�U���̖���́A�ێ�h�ł͂Ȃ��A�u���E�ێ�h�v�Ƃ́B���Ȃ��Ƃ��A�t�����X�ł��A�����J�ł��A�w�����҂͗����������ׂ��u�G�v�͌������Ă��Ȃ��B�Ȃ̂ɓ��{�������ˏo���ĕێ�I�Ȏ�҂ł��ӂ�Ă���B�����Ŏ����̑̂������Ă���悤�Ȃ��́B�����܂ŃA�u�m�[�}���Ɏ�҂̐S��c�܂����̂����ׂė�㎩���}�����̐��ʂ��B���͂ɒ�������Ċ�Ԃr�l�j�b�|���B�킩���B �T��13���i���j���� �@���ɂ̂��߁A�[���m�Ëx�݁B �@���W�I�h���}�̐����B��ƁE���{�������́u�J�����̉w����v���f�W�^�����B���{�����������R�C�i�Ɏt�������Ƃ������Ƃ͒m���Ă������A�c�����m����̖{�̒��ɁA�u�Ŋ��̎��R���x���鏗�����v�̈�l�Ƃ��āA�����A������o������ŁA�y���l�[���A���t�̂��g���Ă������{���̖��O���o�Ă���B���̃y���l�[������u�J�����v�ƌĂ�Ă����Ƃ����B�����m��ƁA�o����ƂȂ����u�J�����̉w����v�̃^�C�g�����Ӗ��[�Ɍ�����B��l���̏����̖��O�́u�݂����v�B���R�C�i�̏����������W�ɂ悭�o�Ă��閼�O���B �@����̎��R�w��B���O�́u�A�J�f�~�Y���Ƃ͖����̎��R�v�Ə��������A�v���A�V��V�~�⎛�R���͂ނ̃X�^�b�t����́A���̌�A��w���������o���Ă���̂������B�|�{����A��������A����p�A�����h���A���|�M�߁c�c�B����ɓ��\�Y�܂ŁB�����m������A���R�C�i�͌��\�A�ʔ����������낤�Ȃ��B �@�c�����m����̒����ɂ��A���R�C�i�̍Ŋ��́u�ӎv�I�ȁv���t�́u���̈�҂������̂́A�O��I�ɔM��������Ƃ������ƂȂˁv�������Ƃ̂��ƁB �@�S��21���A���M���o�����߁A��M�܂��g�������������Ă��܂����߁A�됣��t�ɓd�b���ď��������߂����A��������ƁA�Ăщ�M�܂��g�����Ƃ��w�����ꂽ������B�钆�̂Q�����A�g�C���ɂ��������R���A���m�̕����̑O�ɐm�������ɂȂ�A�����������̂��Ƃ����B �u���̈�ҁv�Ƃ������Ԃ�͎��R�炵����ʂ��̌����B���̎��_�ŁA�됣��t�ɑ���s�M�������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B����ɂ��Ă��A�u�O��I�ɔM��������c�c�v�Ƃ́B �@�ǂ݉߂������̂܂܂����A�u�O��I�ɔM��������v�Ƃ������Ƃ́A�̉����Ȃ��Ȃ�Ƃ������ƁB�u���v���Î����Ă���Ƃ�����B���R�́u�������������v��\�����Ă����̂�������Ȃ��B�c�����m����ł͂Ȃ����A�Ԃ��Ԃ����A���̈�҂Əo���Ȃ���c�c�Ƃ����������v���Ɏ�����B�܂��܂����R�C�i�͐������͂��Ȃ̂ɁB �@���͐��܂ꂽ�c�ɂ����q���Ɖߑa���ŁA�����w�Z�̎�������40�N�O��10���̂P�ɂȂ��Ă���B �@���������w���̍��́A���̐l����8000�l�B���������łł������䂦�A�V���������ւ̋A���ӎ��͔����A���ł��u�n�Z���v�o�g�ƌ�������ɂ͈�a��������B�����܂ŁA�o�g�͂����ЂƂ̒n�於�u�Z�Z�v�Ȃ̂��B���́A�킪�n����ߑa���������݁A���ɁA�c�t�����u�ׂ�n��v�Ɠ��������Ƃ��B���܂ꂽ�Ƃ�����A�u�גn��v�̗c�t���Łu�ׂ�n��v�̎q�������Ɖ߂����A���Ԃ�A�����̃I���W�����B���ɂȂ�낤�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B�m��Ȃ��l���ǂ�ł��Ӗ��s�����Ƃ͎v�����B �@����͂����Ƃ��āA����ł������͂P�w�N72�l�B�S�Z�łS�O�O�l�͂����킯���B�u�Z�O�ǁv�������āA�e�����ƂɁA���Ԃ̉Ƃɔ��q���u���Ă������B�����Ă��͌��֘e�̒��ɂ����Ă������Ǝv���B �@������v���ƁA�N�Ԃ�ʂ��Ă�����̂��A����Ƃ��~�̎��������������̂��A�ǂ������R�Ƃ��Ȃ����A�Z�O�ǂŁu����v������悤���߂��Ă����B�[���U�������������A�N���̊w�N�̌ォ���w�N�����Ă����āA�u�̗p�S�v������B �u�̗p�S�I�v�i�J�`�J�`�����q�̉��j�u��l�͉����@�q���̓}�b�`�A��Ƃ�����ĉ̗p�S�v�i�J�`�J�`�j�B �u�̗p�S�v�i�J�`�J�`�j�u�|���v�S���p�S�ЂƂA�݂Ȃ��݂��ɋC�����܂��傤�v�i�J�`�J�`�j �@����ȕW����̂��Ȃ��璬�����������킯�����A�l�b�g�ł��߂��Ɍ���������u�|���v�S���p�S�ЂƂv�͖�������Ɏg���͂��߂��W��Ȃ̂��Ƃ��B�u�|���v�v�Ƃ͔n�������C�|���v�B�����͔��R�ƁA���h�|���v���C���[�W���āA�̂��Ă������A���͔n�����|���v�̂��Ƃ������Ƃ́B�E�[���A40�N��ɒm��u����̗p�S�v�̐^���B�������A�Z�O�ǂ��̗p�S���Ȃ��Ȃ����c�ɂ̎q�������B���茸���ĕ��i�̂��������̔��q�����͂ǂ��ɂ������̂��낤�c�c�B �T��12���i�y�j���� �@�T�N�T�N�Ǝd����Еt���A1113�̐V�����u�̂��݁v�ɔ�я�薼�É��ցB�M���M���Z�[�t���������A�ԓ��͂����Ă���A�����̐Ȃɐw���A�܂��͎ԓ��̔��̖��̓��ٓ�1300�~���B���o�����ŕ��i���F�́u�R�̂�����v���Ă��邤���ɂ��Ƃ��Ƃ��͂��߁A�C�����Ɩ��É��w�B0055�B���܂ł̓����̃R�s�[�������炸�A�e�J����ɓd�b�Ŋm�F�B�n���S�Ŗ{�R�w�܂ŁB�w����10�������A�����ԈႦ�A�T�����X�B�ŁA���ǁA�㞊����̍u���̏I��荠�ɉ�ꓞ���B �@��S��u���ێ��R�C�i�w��v�B���m�w�@��̐��������̊̂���őn�݂��ꂽ�u���ۊw��v�B�A�J�f�~�Y���Ƃ����Ƃ������ꏊ�ɐg��u���A����������������R�B����Ɋ�����ꂽ�u�����v��u�w��v�Ƃ������t�ɐ̎��R�C�i�͋���Ă��邩������Ȃ����c�c�B�v��24�N�B�u�����v��ʂ��āA���R���㐢�Ɉ����p�����Ƃ����w�҂����̈ӎu�ƁA���̏�M�ɂ͌h������B �@�����̃v���O�����́A�㞊�����q����̍u���A����p�Ƃi�E�`�E�V�[�U�[�̑Βk�A�|�{����E�쓇���q�́u���J���œǂގ��R�C�i�̔o��v�B�����āA��w�W�҂�̌������\�B �@ �@���Ńl�b�g���Ԃ̂g����ɐ����������т�����B�Ƃ��߂��Ȃ̂��Ƃ��B���݂₰�܂ł����������k�B�u���̂��ƁA�\�ʍ��̐搶�̂Ƃ���ɍs���v�̂��Ƃ��B�����Ă���������ނ��̃m�~�B���������A�����Ԃ��ԁA���m������Ă��Ȃ��Ȃ��B�f�W�^���ł͂Ȃ��A��ł����郂�m���̊y������Y��ċv�����B�O�̃}���V�����ɉz�������A�L�荇���̖ؕЂŒ��̑�����������̂�10���N�O���B�}���V�����Z�܂��ł̓g���e�����킯�ɂ͂����Ȃ����B���߂āA�ؒ���ł����������̂����B  �@����E�V�[�U�[�̑Βk�ł͍��悪�������ɂȂ��āA�V�[�U�[�Ǝ��R�C�i�Ƃ̏o��A���y��S���������������ȂǁB�V��V�~�̊M�������u�@��v�ł̗��������Ȃǂɂ��b���y�сA�����Ǝv������A���͈ӊO�ƐÂ��B�����N���قƂ�ǂŁA20��͂킸���B��͂�u�w��v�����ɁA������̋����͌ł��b�H �@�����Ẳ|�{�E�쓇�̌������\�B�쓇����1957�N���܂�B���_���͂̃W���b�N�E���J�������҂ł���A���R�̔o������J���́u�����i�K�_�v�Ȃǂœǂ݉������Ƃ���B���R�̔o�����i�N��ʂɐ������A���͂������͑N�₩�B�����A�o��̉��߂͊�悤�ɂ��ł���B���߂�ς��������ŁA���_�����{�������ꍇ������킯�ŁB���ς�炸�̃_�W��������g�����|�{����̐i�s�ŔM��тт���B �@��l�̋����[�����\���I�������͌ʌ������\�B�A�H�ɂ��O�ɁA�����L���͐���̋v�ۂ���i�����̐����w�@�j�́u�є�̃}���[��60�N��v�̖`���������V�[�U�[�Ɠ����ŕ����B �@�|�{����͎d���̊W�łs�s�ցB �@�e�J����Ɍ������A�^�N�V�[�ɕ��悵�A�㞊����A�R�`����A�V�[�U�[�A�Η��A����A���̂U�l�ʼnh���ցB �@��H��́u�ޖ��сv�ŐH���B�Ē��u���X�v���P�{���Ă��܂��i�c��͐V�����̒��Łj�B���̏Ē��́u�S�N�̌ǓƁv�̌����Ȃ̂��Ƃ��B���R�C�i�́u�q�r�_�v����̗F�l�E�R�`����͎Ⴉ�肵���̎��R�̃G�s�\�[�h���B���߂Ď��ɂ���b���B �@1900�A���É��w�B���Ԑ����O�̋삯���݁B�U�l���̐Ȃ��m�ۂ��A���������킹�ň��݉�̑����B�V�[�U�[�͓r���ʼn��ԁA���ƂցB �@2100�A�����w�ʼn��U�B���ŎR�`���ƕʂ�A�n���S�ցB �@2200�A��B���݂������̂����ɁB �@ �T��11���i���j���� �@��邩�璩�ɂ����Ă��̂����������B���ő�������ςȂ��B�d�Ԃ��~�܂邩�Ǝv�������A0544�A�w�ُ͈�Ȃ��B�ʏ�ʂ�̏o�ЁB �@�����O�A���̏�ɏ��Џ���B�c�����m����̐V�����B�킴�킴�����Ă��ꂽ�̂��B�������B����̑����͂�����ŁB���H��A�������ō��̑�����ǂށB���ꎞ�ԂœǗ��B����ȃX�s�[�h�œǂ{�͋v���Ԃ�B�ŏI�͂̎��R�Ƃ̕ʂ�̏�ʂŎv�킸�܁B�K���A�ׂ�̃x�b�h�͂��т��������ĐQ�Ă��铯������l�B�����A�������Ŗ{��ǂ�ŗ܂���Ȃǒp���������āB �@���m������͂��߁A�V��V�~�̐l�����͖{���Ɏ��R�C�i����D���������̂��B �@�����炱���A�u���I�Ȍ�f�v�Ŗ����k�߂Ă��܂������R�̍Ŋ��͉����ł�����݂���Ȃ��͓̂��R���B�u���߂Ċ̍d�ςŎ���ŗ~���������v�Ɩ��m�������̂�������B���c�����߁A�d���̗ʂ����炵�A�̗͂��������Ȃ���A�Â��Ƀt�F�C�h�A�E�g���Ă������R�̎p�A���v�������ׂĂ������m����B�u���ƂR�N��������A�̑��ڐA�̓������Ă������͂��v�ƁB �@���̉������́A�厡��ł������됣���́u�������v�Ɍ�������B���̈�t�̓��ِ��͎��R�ɂƂ��ĕs�K�Ȉ������킹�������Ƃ��������悤���Ȃ��B�����A�Ⴄ��t��������c�c�B�ߋ��ɑ��A�������A�������Ƃ����͕̂s�т����A��͂�ň��̐l�̎��ɑ��Ắu�������v�Ǝv�������Ȃ�B �@�R�N�O�A��a�̕����S���Ȃ����̂́A���l���Ă���Éߌ�Ƃ����v���Ȃ��B����܂ł̓o�C�N�ɏ��قnj��C�������̂ɁA���ݖ��ς��Ă���}�ρB���̌��ǂ͂ǂ��l���Ă�����~�X���B�Â��ɐÂ��ɐ����I����͂������������ˑR�̎��Ɍ�����ꂽ�A���̂Ƃ��̃V���b�N�B�Â��Ɏ��R�C�i�̎����Ŏ��o������Ă����c�����m���P�����u���I��f�v�ւ̌���́A�悭�킩��B �@�u�~�߂�A�ɂ�����Ȃ����B�ق�Ƃ��ɓ{���v �@���A����낤�ƁA�A���ɃJ�e�[�e����}�������Ƃ��A�����̂��N�����Č������Ƃ������R�B �@ �@��������Ă��������ЂƂ݂́A���́u�ق�Ƃ��ɓ{���v�Ƃ������R�̌��t�ɋ�����������̂��������Ƃ����B�u�Ō�܂Ől�ɋC�������āc�c�v�ƁB �@�قƂ�Ljӎ����Ȃ������͂��Ȃ̂ɁA�u�ق�Ƃ��Ɂc�c�v�ȂǂƔO�����������肪�����ɂ����R�̂₳�������ے����Ă����Ƃ����B�����āA���́u���l�ւ̂₳�������܂��t�v���Ŋ��̌��t�ɂȂ����B �@���̖{��ǂ݂Ȃ���A���Č����V��V�~�̕�����v���o���Ă����B�u�g�Ŋہv�u���~���O�v�u�z�X�P�v�u�S�N�̌ǓƁv�B�ӔN�̍�i�̂ق�̂킸���������Ă��Ȃ����A���܂�Ĉȗ��A��ɂ���ɂ����̂悤�Ȕ������A�\�͓I�ŁA�h���Ƒz���ɖ�������������͌������Ƃ��Ȃ��B�����ȕ��䂪����Ƃ�����A���R�C�i�̉��o�����V��V�~�̕���ȊO�Ȃ��B���ꂩ�牽�S����̕�����������Ƃ��B�������A���܂��ɓV��V�~���镑��͂Ȃ��B���Ԃ�A���ꂩ����Ȃ����낤�B �@ �@1700�A��B�Ɛl�A���ɂƕ��ׁB�؎��A���ɔ����B���₢��m�ցB �T��10���i�j���� �@���������A�����A�c�����m����̐V���{���o�Ă���͂��B�l�b�g�Œ��ׂ���X���ɔ�������Ă���B1600�A����E�R�����X�œc�����m���u���R�C�i�Ɛ����āv�i�V���فj���w���B�i���X�ɗ��������̂��҂����ꂸ�ɕ����Ȃ���ǂ݂͂��߂�B�d�Ԃ̒��A�Z�{�̃��[�������A�o�D�����̋i���X�Ɠǂݑ����A�ŋ����n�܂�O�ɂR���̂P��Ǘ��B 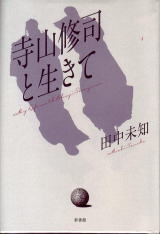 �@16�N�]�����R�Ɖ߂����A�����ʂ�A������l�́u�E�Ǝ��R�C�i�v���������m����B24�N�Ԃ̒��ق�j���ď��߂Ď��R�C�i�Ƃ̓��X���������B�������ق�]�V�Ȃ����ꂽ���A���̃}�O�}�̕��o�͐��܂����B�����̎v���̂����������܂ŃX�g���[�g�ɕ����ɂ����{�͂ق��ɒm��Ȃ��B �@�`�������ł́A�u�����I���o�����݂ɂ����Ă����A�𓊂��A���R�C�i���������Ƃ��Ă���Ƃ����v���Ȃ����R�]�`�v�Ƃ��āA�����O�Y�u���\�n���@���R�C�i�v�A�c�V���u���l�@���R�C�i�v�A���R�����u���R�C�i�@�V�Y�̐l�v�𖼎w���ŁA�O��I�Ɏw�e����B �u���̉����́A�������A����炪��i�ւ̔ᔻ�ł͂Ȃ��A���R�C�i�Ƃ����l�Ԃւ̔��ɃW�����v���Ă��邱�Ƃł���B�܂�ŁA�ނ炪���R��l�ԂƂ����Ȃ߂悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ɂ܂Ŋ�������̂��v�A�ƁB �@�����āA�o�l�̑�H��s�́u�ޑz�����ꂽ��������肵�Ă͋�͂ł��Ȃ��B�ނ���A�ϋɓI�ɗޑz�̉��ɂЂ��ސl�ԋ��ʂ̊���ɐ[���˂����݂����v�Ƃ̌��A�����āA�H�q�Ƒ��c�j�́u�ڍՊ��@�����͉����Ȃ�ɂ���v�u�~����@�����͉����Ȃ�ɂ���v���r������H�̊��z�������Ȃ���A���R��͕�ƌ��ߕt����O�R�҂̋\�Ԃ�˂��B �u�悭�A�ޑz�Ɨދ���悤�ɍl���A�ދ�Ƃ�������̂̒��ɂ�����A�G�傪����ɂ�������炸�A�ދ�͂��ׂĈ����E���Ǝv���₷�����A����͌�肾�낤�B�ޑz�͔������ʏꍇ������A���ׂėޑz�͈����Ƃ͂�������Ȃ��B������ދ���A�ޑz����o�����Ĕ�ނ̂Ȃ��V����������������̂ł���A���̋�͗��h�ȑn��ł͂���܂����v�i��H��s�j �@�܂��A����̋��ς����������R��ϋɓI�ɕ]�������ѓc�����̎��R�ւ̗����������A���R���u�͕폭�N�v�Ƃ����Ȃ߂�l�X�ɓS�Ƃ�������B���̈��p�̑N�₩���͎��ɒɉ��B �@�A��̓d�ԁA�����āA�z�c�ɓ����Ă�����A�܂�łނ��ڂ�悤�ɓǂݑ����A�ߑO�O��30���A�������ɗ����̎d���ɍ��x��������̂Ŗ{����Ėڂ��ނ�B����ɏA���O�ɓǂu���R�C�i�̕�̏́v�̉����Ɏc��Ȃ��Ȃ��Q�t�����B��n�c�̃G�L�Z���g���b�N���͑����ɉߑ�ɕ��Ă���̂��낤�Ǝv���Ă������A���m����ƃn�c����̑�����m��ƁA�����������R�B���߂ēǂރn�c����̎��R�ւ̎莆�̌��z���ɂ͐����Ȃ��B �@1900�`2115�A�o�D������Ō��c�o�D���u���r�G�[���̉Ă̍Ղ�v�B�l�E�f�����X�́u�����������s�݁v����ɁA�g�i�m�Y���r�{���A�x�e�����o�D�E���쐽�炪�����o�������́B����͐ɗאڂ��钹�z�B�����ŁA��l�̏������u���r�G�[���v�Ƃ����i���X���c��ł���B�ޏ��͐펞���A�v�Ƃ����œX���o�c���Ă������A�v�͏o���B���B�Ŕs����}���邪�A���܂��ɐ����͕s���B�Ȃ͏I���Ă���Ȃ������X����l�ōĊJ�A16�N�̍Ό������ꂽ�̂������B���z�Ղ肪�߂Â���������A�X�̋߂��ŕv�Ɏ����j��ڌ����邱�ƂɂȂ�B���������ĕv�ł́c�c�B�������A�j�͋L���������Ă����B �@���C���̕���͋i���X�B�j�̏Z�ސ쌴�̂���Ƃ̃Z�b�g����蕑��œ]���B���쐽��ƍȖ��̐���֎q�B�����āA�ޏ��ɗ������҂́A�푈�ň����ꂽ�O�҂̐l���������h���}���ɓW�J����B �@����̏����o�����A�Ó]�ŏ�ʂ̐�ւ����J��Ԃ����̂͂킸��킵���B��͂艉�o�͓�����̂��B�������ʂɈ�a���Ȃ����䂪�i�s���Ă��邱�Ƃ��ǂꂾ����ςȂ��ƂȂ̂��B �@���ԂɁA��Ђ̂n�a�A�e���ɋg�i������Љ���B���E�̖��ȋi���~�j�����̏�A���m�Ƃ̂��ƁB �@ �@ �T���X���i���j���� �@�X�M�ԕ��̂��Ƃ̃q�m�L�ԕ��Ƀ_�E���B������@���~�܂炸�A�����s�̖�p�B���ꂪ�Ȃ��Ȃ��������A�����n�߂��̂��^�������䂪�n�܂钼�O�B �@�x�݂����A�T���͗\�肪����̂ŁA�d���Ȃ��A�O���[�u���ł́u���̍���v�������̒��Ɍ��邱�Ƃɂ���B1400�A�V��v�ہB�i�������̎������ɂȂ��Ă���͂߂����ɑ��ݓ���邱�Ƃ̂Ȃ��O���[�u���B �@�X�^�C���b�V���ōd���E���������锒��W���o�͔ӔN�̎��R�C�i���o�Ƃ悭���Ă���B����͑���̌�������ɓV��V�~�́u�ϋq�ȁv�ɏo�����Ă���킯�ŁA���R�C�i�̕���͂悭���Ă���͂��B�t�����X�̃V���[�����A���Y���I�ȕ�����͎��R�̉e��������̂�������Ȃ����A���̂ւ�͈�x�m���߂������́B �@����͓n�Ӎ��Ô��̃t�������R�M�^�[�����Œ����Ȃ���A���o�͖��ł�������̂悤�ɋL���̒�ɁB���������x�݂ɏo�������Ƃ����̂ɁA��ɂ�鐇���͂�����Ƃ����������B�s�o�I �@1550�I���B�J�[�e���R�[���ŐX�R�A�\�j���̃t�������R�_���X�B �@�A��A�Ђ܂��̂r������Ɉ��A�B�u�͂��͂��v�̂s������Ɨ��b�B�ŋ߁A�_���J���W�̃p���t���肪���Ă���̂��Ƃ��B 1700�A��B�Ăщԕ��Lj����B�ǂ��Ȃ��Ă�̂��c�c�B�炢�B �@�����_�Џt�G���Ղň��{�W�O���u���t������b�v���Łu�^��i�܂������j�v���[���Ă����Ƃ����B�T���~���|�P�b�g�}�l�[�ŏo�����Ƃ������A�u���t������b�v�̖؎D�����Ă���̂�����u���l�v���ƌ��������Ă�����������B������A�I�n�m�[�R�����g�B�u�v�z�E�M���Ɋւ����肾����v�R�����g���Ȃ��Ƃ͋V�B�N����E���̊ہA�]�R�Ԉ��w�Łu�v�z�E�M���v�������t���Ă����̂͂ǂ��̒N���������B�����ɓs�����������Ƃɂ̓_���}�������ߍ��ނƂ����͎̂q���Ɠ����B���������Ă����}�X�R�~�����邩��A���オ��̂��B �T���W���i�j���� �@1800�A�V�h�B�M�Z���Ŏh�g��H1000�~�B�����V���̗[���ɖk���a�v���𓉂ޕ��́B�����A���S���Ȃ����́H�@�U���H�m��Ȃ������B�܂����c�c�B������A�a�r�̐����t�q���W�ɏo�Ă���k��������������B���^�͍ŋ߂��낤�B80�B�����t�q�Ɍ��y���邽�тɗ܂���ł����p����ۓI�������B�S��A�����t�q�����Ă����̂��낤�B�Ō�Ɍ�������́u���̒��̒������v���������B�Z���t�ɋl�܂�V�[�������X�������B���҂Ƃ��ăZ���t���o�����Ȃ��̂͐h�������ɈႢ�Ȃ��B�����オ�����݁A�u�k���a�v�ł����������Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����b�����̂͋��N���������B�k���L�N�Ƃ����҂Ƃ��ĉԊJ�������ƂŎv���c�����Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ����c�c�B 1900�A�I�ɚ����T�U���V�A�^�[�ŕ��w���u�ʂ�����v�̏����B �@�ϓT�F�̊ݓc�Y�ȏ�܍�B�s�ς���A��ʎ��̂��N�����X�ǂ���ɂȂ�A�ꂪ�}���A�ǂ�������������悤�ɍȂɗ�����˂������Ă���l���ň��̒j�B80�߂��̕��e�Ɠ�l��炵���n�߂���̂́A���͔F�m�ǁB������A�I�V�b�R�����炵�����e���g�C���ɉ������߂�B���炭���Ĕ`�����j���������̂͒E�炵�����B�Ȃ��80�ォ��20�N����Ԃ�A60��̌��C�ȕ��ɕϐg����B�����ɁA���̕����ĂђE�炵�A40��ɁB�������ĕ����̒��͕��̔����k�ƁA�Ⴂ�������B���Ă����B �@�₪�āA�N���̌J���Ƃ��Ă������ꂽ�u�a29���}�����闋�d�ŋ㎀�Ɉꐶ���푈���̘b�v�̎���ɂ܂ŕ��͑k��B���ꂱ�������̎����̒a���ɂȂ���A��Ƃ̏o��ł���c�c�B�①�ɂ��猻�����e�̌��e�A�ʂ����炽���̃t���_���X�A���V�Ђ̏����́u�̓�����v���U�A�w������̉f�挤����̗��l�̒���ȂǁA���܂��܂ȃG�s�\�[�h�𗍂܂��Ȃ���̓W�J�ŁA���o�I�ɂ��_����Ȃ��B���ɖ��x�̔Z���ŋ���ԁB�����ƌ��z�̐�ւ����▭�B�������͏��{�S�q�B�����A���ꂪ�傫�ȕ��A���䂪�������ăA�g���G��Ԃ̗Տꊴ�ɂ͋y�Ȃ��B�ᏼ�O�̋����E����C���݂ŋq�Ȃ��甏�肪�N����̂��قق��܂����B �@2115�I���B�q�Ȃɗ��R���B�N���̐X����Ɖw�܂ŁB�S���Ȃ����k���a�v���̂��ƂȂǂ�b���Ȃ���B�u���N�U���̐X�˂̑��V�Œ�����ǂ�ł��ꂽ��ł����ǂˁc�c�v�ƁB �@�A�g���G���� �T��7���i���j���� �@�������30�������d�Ԃŏo�B0630���B�m����Ђ̌��đւ��H���ɔ����A��������V�X�e���ύX�B�u���^�]�v�̓g���u�����X�B �@1645�A�V�h�B�̕��꒬�̉f��قŁu�Q�Q�Q�̋S���Y�v�B�O��`�ł͖ʔ������c�c���������A����قNJ��҂ƌ����̗���������f��͒������B �@�E�G���c�l�m�̋S���Y�̓r�W���A���I�ɂ͂܂��܂������A�Ƃ肷�܂�����Ǝŋ��B���[���A�Ɍ�����̂��v���I�B���^�����u�����v�̎ŋ����甲����ꂸ�B�L���E�c����ނƂ̗��̂��ⓖ�Ăł����邩�Ǝv������A��l�̗��݂͂Ȃ��B��l�A���m�̂˂��ݒj����������̂������킵����̌����Ă��Đ▭�B���䎠�̍������k��������B�������A����I�ɋr�{���ʔ����Ȃ��B������Ȃ��邾���̉��o�����^���^�B�X�s�[�h���[���B�r���ł����т��o�����Ȃ��炢�ދ��ȓW�J�B�S���Y�̖ѐj�U���Ŗѐj���o�s�����ċS���Y�̓����c���c�c�ɂȂ�Ƃ����̂����[���A�Ɗ��Ⴂ���Ă���ē̊��o����A�f�悪�܂�Ȃ��Ȃ�͓̂��R���B �@�������A�r���ŋS���Y�̔��̖т����Ő����グ���A�����Ȃ��͂��̍��ڂ��o�b�`���������̂ɂ͈��R�B�S���Y�̍��ڂ͐��܂�Ă����ɕ�ɂԂ��莸���B���̊��|�ɖڋʂ��₶������ł���Ƃ����ݒ�ł͂Ȃ��������B���ڂ�������S���Y�Ȃǂ��肦�Ȃ��B�ȂႱ���B���ғx100�Ō��I����ă}�C�i�X10�B �@1845�I�f�B �@���ɍs���O�ɕ������炦���A�Ǝv���ē�������]���i�B�l�^���₽��ƍ����B500�~�M�A600�~�M���O���O���B�����M�͒������Ă���A�Ƃ������ԓx�B������ċt����Ȃ��́H �@0930�A�V�A�^�[�g�b�v�X�Ō��c���w�搶�u�����炵���o�J������̂͌Â��o�J����Ȃ����낤�v�B �@�����~�F�̋����R�����o�ōĉ��B�����1970�N��n�߂̋�B�̏����ȍ`���B���R�[�h����Ẫt�H�[�N�t�F�X�e�B�o���ɋg�c��Y������Ă���Ƃ����̂Œ��͊��}���[�h��F�B�Ƃ��낪�A����Ă����̂́u����x��v�̃t�H�[�N�̎肽���B�`���̑啨�t�H�[�N�̎�i���тƍ��ΗF��H�j�ŁA���͉��y���������o�c����j�i�R���j�ƕ��ʂ��Ă������q�����́u���蕿�v����]���Ĕ��̓I�ɁB��Y�����Ȃ���A�R���T�[�g�͒��~�ɂȂ�B�����łƂ������]�̍�Ƃ́c�c�B���Z�̕����ɏW�܂����t�H�[�N�V���K�[�����̂����������Ȃ��l�Ԗ͗l�B �@�������킵�����G�ɕ`�����悤�ȐR���́u�`���̃t�H�[�N�V���K�[�v�A�J���b�W�t�H�[�N�A�f���I�̕Њ���i����V�㗲�u�j�A�Ìy�̏�O�́i���Z�p�����j�A�u���܂݂�̃J���X���̂��v����f���I�u���J���X�v�i�������r�F������̂ЂƂ݁j�A�R���T�[�g�̓r���ŐQ�Ă��܂����������t�H�[�N�V���K�[�i���ۑ���a�j�B����ɁA�Ԍ��i�����������j�̑��q�œ����ɏo�ăt�H�[�N�V���K�[�ɂȂ肽���Ƃ�����ҁi�����������j�̐e�q�̑����A�����邳�����Z�̉��y�ږ⋳�t�i������O�j�A���R�[�h���̓X��i�C���i�j�A����̐E���i���C�ю����j�炪����Ńh�^�o�^�̑呛���ɁB �@�^�C�g���͂������A��Y�̍L���t�H�[�N���f�r���[���R�[�h�u�Â����D������̂͌Â����v����Ȃ����낤�v���炫�Ă���킯�ŁA�����~�F�̃��`�[�t�ɂȂ����̂́A��Y�o��ŃK�����ƕς�����t�H�[�N�n�}�B�o��l���́A���ꂼ��O�㊰�A���c�n�A�T�̐Ԃ����D�A�r���[�E�o���o���i���ꂾ���J���b�W�t�H�[�N�j���霂Ƃ�����ݒ�B�p���f�B�[�ɂ���̂́u�Ώۂւ̈�����邩��v�Ƃ͂������̂́A������z�N��������ǂ��낾���ɁA�Ȃ��Ȃ��c�c�̎v�����B �@����Ȃ���Ȃ�ʂɂ���A�����̂悤�ɂ悭�ł��������~�F�̐l��t�쌀�B�قǂ悭���Ăقǂ悭����݂�B�o��l����l�ЂƂ�ւ̃X�|�b�g�̓��ĕ������܂��B�Z�����Ԃł��ꂼ��̌����ꂪ�L�b�`������̂����炳�����̎肾��B �@2130�I���B�q�ȂɃA�g���G�_���J���̒r�c���F���̊���B�i�N���b�v�̏�J���Ɉ��A���ĉƘH�ɁB�u�p�������Ȃ���O�b�o�C�v�͓������܂����ŏI������悤���B �@ 5���U���i���j�J �@�A�x�Ō�̓��B�J���������ƂɏI��孋��B�[���̌m�Â��x�݁B�ߌ�ɂȂ��ă��W�I�h���}�̐����B �@�O�ɏo�Ȃ��̂ŁA�^�悵�Ă��قƂ�nj���@��̂Ȃ��e���r�h���}�����炾��ƌ��Ă��܂��B�m�g�j�̂a�r�Ő[��ɕ��������u�������@�Z�J���h�t�@�C���v�B�V��Ƌ���R�{�B�V��u�l���v�͊��j����e�[�}�ɂ�����i�B���ی�^�������X�Ɛ������A�Ō�̈�l�ƂȂ��ČǗ����A���E�����N�̍��݂��u�l�Ԃ�łڂ��A���ƈ�̉�������ԕ��E�C���X�v�����o���B60�N�ォ�猰�݉��������j���21���I�ɂȂ��Ă��Ȃ��~�܂��A���̂܂܂ł͐l�ނ̖ŖS���G�ł͂Ȃ��Ƃ����̂ɁA�]���̓������ǂ葱����l�ށB�������A�����������e�[�}�ł����A���͂�^���Ɏ~�߂�l�Ԃ��}�C�m���e�B�[�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��s�C���B����́u����Ȃ��ƁA����������v���낤�B �@�����āA�A�j���u�������̃W���[�v�A���������S�b�܂ŁB �T���T���i�y�j���� �@�O�V�R�O�N���B  �P�P�O�O�A�Ɛl�Ɠ�l�A�r�R�̎ō������邽�߂ɓd�ԂŒ����ցB�H����ƕГ���Q���ԁB�������A����̓��}���͂��ׂĔ����B�e�w��ԂŒ����܂ōs�����̉�����B����̉w�z�[���ŋ��R�A�]�Z�̂l����v�w�Ɩ��̂l������ƂƂ�����B�Ȃ�ƁA�����Ƃ���ɍs���̂��Ƃ��B����ȋ��R������c�c�B�����A�l����t�@�~���[�Ǝō����������邱�ƂɁB�����w����k���Q�O���B�u�˒n�тɍ��R�ƌ���ꂽ�s���N�A�ԁA���Ȃǂ̎ō��J�[�y�b�g�B���ꌔ�R�O�O�~�B�����l�������A�J�[�y�b�g�ɌQ����A���̂悤�B�A��͒����w�܂ŁB�P�T�S�O�A�l�����Ƃƕʂ�āA�ƘH�ɁB�������ɂR�A�`�����͔���B�̂��������B�P�W�Q�O�A��B �P�P�O�O�A�Ɛl�Ɠ�l�A�r�R�̎ō������邽�߂ɓd�ԂŒ����ցB�H����ƕГ���Q���ԁB�������A����̓��}���͂��ׂĔ����B�e�w��ԂŒ����܂ōs�����̉�����B����̉w�z�[���ŋ��R�A�]�Z�̂l����v�w�Ɩ��̂l������ƂƂ�����B�Ȃ�ƁA�����Ƃ���ɍs���̂��Ƃ��B����ȋ��R������c�c�B�����A�l����t�@�~���[�Ǝō����������邱�ƂɁB�����w����k���Q�O���B�u�˒n�тɍ��R�ƌ���ꂽ�s���N�A�ԁA���Ȃǂ̎ō��J�[�y�b�g�B���ꌔ�R�O�O�~�B�����l�������A�J�[�y�b�g�ɌQ����A���̂悤�B�A��͒����w�܂ŁB�P�T�S�O�A�l�����Ƃƕʂ�āA�ƘH�ɁB�������ɂR�A�`�����͔���B�̂��������B�P�W�Q�O�A��B
�T���S���i���j���� �@0900�N���B�����C�ɓ���A�����A���낢�ł���O�o�B �@���R�C�i�̖�����Q�B���N�A���̓��͉Ƒ����s�̂��߁A����v���Ԃ�̎Q���B �@�d�Ԃɏ���ĂP���Ԓ��B�V��Ɍb�܂�A�t��t�������������������R�B�w�O�ʼnԂ��āA��l�A�Ă��Ă��ƍ⓹���B1140�A���掛���B  �@�T�����ɑ傫���u���R�Ƒݐv�̕����B�u�Z�Z�����I�v�ƌĂꂽ�̂ŐU������Ɨ��d�q����B�������C�ȗ�����B���̏Ί�ƋC�����ɔ���������ԁB���ɁA�����E�~����A�ꂽ�ᏼ���j����A���ڂ������B�e�����}�V���̈�t����̓o�X����~��Ă����Ƃ���B �@�܂��͎��R����̂���Q��B���N��24�N�B��̑O�ŎႢ�����ɐ���������ꂽ�̂ł悭����Ɩ��L���͂̐�������Ă����j�ۂ���B�u���c�͑O������Ŏ��߂Č����ɐ�O���邱�Ƃɂ��܂����v�Ƃ̂��ƁB�ޏ��͂����̐����q��̑�w�@���B���m�ے��ɐi�݁A���R�����𑱂���̂��Ƃ��B�Ȃ�قǁB�����ŕ�������̃����[�X�̕��͂��������肵�Ă����͂����B �@����̑O�ɂ͉ԂƐ����B�Ă��������̕揊�ɐ^�V���������������Ă���B���f��̃C���X�g�������Ă����͂���҂���̂���B���ꂩ��A���R�C�i�̏����^��̂悤�Ƀ��j�[�N�ȕ�������Ă����̂��낤�B �@���ڂ����̑��q�E�����N���̃��`���`�����ɖڂ��ׂ߂�㞊����ƕΗ��B �@�T�����ɖ߂�A�r�[���Łu���t�v�B���ΐ��A���c���j�A�c�����m�A���n����A�ь瓶�q�A�O��G�N�v�A���c�`���o���a�[�s�n�j�x�n�̍�����R�I�A���j�Îq�A�q������A���엘�F�A�}�[�N�E�Z�o�X�`�����A�����Ďᏼ��ƁB�ߌォ��̓V�[�U�[�Ə��ё�疜�L���̖͂ʁX�A�s�쐳�A�������獪�{�L�A3���߂��ɍ���p�Ƃo�`�m�s�`�A��m���߂��݁A�X�M�E�����J�ق����I�̌��c�̏��D�w�B���悳��ɓ��s���Ă����|�\�v���В��̊p�삳��B�p�쎁�͋㞊����̋��F�łj�炳��Ƃ�40�N���̕t�������Ƃ��B�u�A�x�����ɂ݂�ȂŏW�܂邱�Ƃɂ��Ă�v�Ɗ��������B �@�S���߂��ɂ��J���B��ցB�s��d�q����Ƃo�`�m�s�`�̃N���}�ɓ��悵�A�ӂ��Ƃ̋������Ōy���H���B �@�́A�s�a�r�̃��W�I�Łu�������̃W���[�v�̎��̂��̂��Ă����i�o�`�m�s�`���g�`�k����j�Ƃ������Ƃ��o�`�m�s�`���畷���B����H�@���̘b�͊m���O�ɕ������悤�ȁc�c�Ǝv���Čォ��L�����Ђ�����Ԃ������A�L�ڂ��Ȃ��B�ǂ��ŕ������낤�B��͂�o�`�m�s�`�{�l���炩�H�@�����C�T�I�̉̎����̂܂܂������Ƃ��B��x�����Ă݂������̂��B �@�o�`�m�s�`�͍��A�d�M�[�q�̏��������ɋȂ����b�c���A�߁X�����[�X����\��B�u���܂���ˁv�Ƃ����d�M���C����̉̐��������邩������Ȃ��B �@���������o�āA�o�`�m�s�`�A����g�̓N���}�œs���ցB�p�삳��͋������B�s�삳��Ɠ�l�ʼnw�O�̋������Ɉړ��B����s���B�����Ȃ瑁�߂ɔ����o���㞊���x���܂ŕt�������Ă���̂ɂт�����B�V�[�U�[�A�c�����m�����Ɗ��k���B �@����������ꂽ�u�z���b�c�e�����}�v�Ɋւ��Ă͓��R�Ȃ���A�F�����B�K���ɐ����Ђ��ς��Ă����Ɏ��R�C�i�Ă͂߂������A�ƁB �u�v��T�N�A�P�O�N�ڂ��炢�܂ł́A���̌��Ƃ��Ď��R�C�i��U�O�N��Œm���Ă��鐢�オ�e���r�ǂɂ������B�������A�������̐���͌���𗣂�Ă��܂��ċv�����B���R���܂������m��Ȃ����オ���T�ɓ����炸�A���A�O���������Ƃɍ��A�����Ȃ邩������Ȃ��v�Ƃl����B �@�r����́u���\�Y�A���֖��G�̃C���^�r���[�������^�[�W��������@�ɋ^��v�ƁB�m���ɁA�ʂ̔ԑg�p�̃C���^�r���[�����p�����͖̂�肾�B���̔������Ӑ}�I�ɋȉ������ꍇ���o�Ă���B�u�����ԑg�𓂂����Ă�����{��ɈႢ�Ȃ��v�Ƃs���B�c����\�H�ꂩ�炰�ɂ��A�����������R�C�i�̐�Ŋw���^�����n�܂������̂悤�ȃ����^�[�W��������̂����c�c�B���R�Ƃ��̎����m��l�ɂƂ��ẮA���̔ԑg�͂��܂�ɂ����x���Ђǂ������Ƃ������ƁB �@���c��Y�̍Ĕ��b�c�u�⌾�́v�ɓ����Ă闖����́u�O���q��S�v�B������ɂ��u�V��V�~�̃��[���b�p�c�A�[�ł߂���߂���Z���������B���ʂ�n����ď��ꎞ�ԂŊo���Đ������́v�Ȃ̂��Ƃ��B�����̓V��V�~�ŗ�����͈ߑ��W�����Ă������炩�Ȃ�Z���������悤���B���܂�ɑ��Z�ŁA�X�c���q�̃R���T�[�g�Q�X�g���f��A�u����ɏ��a���Ⴓ�s�����v�Ƃ̂��ƁB�V��V�~�̐��������E�����m������ЂƂ̓V��V�~����B���ЁA�����Ɏc���Ăق����B �@�Q�O�O�O�A�㞊����A�c�����m����A�����A��̂ŁA�ꏏ�ɉw�܂ŁB�R�l�͋������B���͂i�q�ʼnƘH�ɁB �@�������A���R�C�i�͕s�v�c�Ȑl���B�v��Q�S�N���������܂ł��A�s�݂̎��R�C�i��炢�A�l�X���W���B�����̊W�҂݂̂Ȃ炸�A�܂����܂�Ă��Ȃ���������܂łЂ����鎛�R�C�i�̎���B 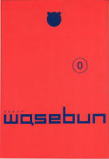 �@����ŁA�����a���̂悤�Ɏ���̒��őN��ɐ����Ȃ���A���܂ł͎���ƂƂ��ɖY�ꋎ��ꂽ���w�҂�����B�����镶�w�҂̒��ʼnʂ����Ėv��Q�O�N�����Ă��A����ʂꂽ�F�ƍĉ��悤�ɂ��̕��w��l����肠�����Ƃ��ł���l�͂��邾�낤���B�u���X�v���o�����l�ł͂Ȃ��A�Y����Ȃ��l�ԂɂȂ肽���v�ƋL�������R�C�i�B���̎v���͍����m���ɑ��Â��Ă���B �@����ŁA�����a���̂悤�Ɏ���̒��őN��ɐ����Ȃ���A���܂ł͎���ƂƂ��ɖY�ꋎ��ꂽ���w�҂�����B�����镶�w�҂̒��ʼnʂ����Ėv��Q�O�N�����Ă��A����ʂꂽ�F�ƍĉ��悤�ɂ��̕��w��l����肠�����Ƃ��ł���l�͂��邾�낤���B�u���X�v���o�����l�ł͂Ȃ��A�Y����Ȃ��l�ԂɂȂ肽���v�ƋL�������R�C�i�B���̎v���͍����m���ɑ��Â��Ă���B�@�A���ƁA���q����B����L�������瑁��c���w�����������B�S������V���Ȃ�������c���w�B���䎁�̏������y���݁B���R�C�i�̖����^�����u�ƒ{�����сv���f�ڂ���Ă���B������Ɓu�܂����R��i�ŒP�s�{�����^�̍�i�͂�������͂��v�Ƙb�������肾�����B �T���R���i�j���� �@0700�N���B���H�̂��ɂ���o���ɃR���r�j�ցB���S���̂͂��������Ƀt�@�~���[�}�[�g���I�[�v���B�X�̑O�ɉԗւ�����Ƃ������Ƃ́A�J�X�z���z���B�X���̉������X�����c�c�Ƃ������A�������Ȃ��B �@1000�A�\�Ă������z�e���̃e�j�X�R�[�g�ցB20���ʂ��邪�A�قƂ�ǎg���Ă��Ȃ��l�q�B��^�A�x�ɂ��ւ�炸�A�ՎU�Ƃ����e�j�X�R�[�g�B�Ƒ��Ńe�j�X�ɋ�����̂͏��߂āB�����̓h���C�u�A�������A�H���ŏI���̂ŁA���N�͓؎��̈ӌ�������ĉ^�����B�Q���ԁA�����Ղ芾�������ăX�b�L������₩�B�؎��Ƃ̃Q�[�����S�[�R�̃Z�b�g�������B�����͕��̈Ќ����ۂ��ꂽ���H �@1430�A�K���i�ցB�����ɗ���x�ɍs���X�B����͂P���Ȃ̂Œ��̐H���B����ł��S�l�ŐH�ׂ�A���D���q�����Ɣ��ł����B �@�����̓n�[�u���B�n�[�u�̒����U���c�c����������l�͔������O���B�����ł����D�q�����`�`�B �@1600�A�������̃I�[�V�����X�p�u���z�̗��v�ցB�����̓X�p�̊e����e�}�b�T�[�W�Ŗ����ꂽ���Ƃ��B �@���ٗ�2200�~�B�A�x�Ƃ����đ吷���B����E�X�p�Őg���S�����t���b�V���B�G�X�e�R�[�i�[���\�����ς��B�Q���ԑ҂��̂��߁A�Ɛl�̊�]�ŋA��̎��Ԃ�x�点�邱�ƂɁB�J���I�P�A�Q�[���c�c�ƉƑ��T�[�r�X�B �@�G�X�e�A�}�b�T�[�W�������ς��Ȃ̂ŁA���ƕ���Ń}�b�T�[�W�`�F�A�ɁB300�~�B���ꂪ�Ő�[�̃}�b�T�[�W�`�F�A�B�y���Ƃ���Ɏ肪�͂��Ƃ������A�l�ԍH�w�e�N�m���W�[�����炵���B�葫���ݍ��݁A�M���b�ƈ��銴�o�̓}�b�T�[�W�t���̂��́B�n�C�e�N�E�}�b�T�[�W��Ɋ��Q�B����Ȃ�300�~�͈����B �@2030�B�ފق��A�ƘH�ɁB���t���H�ł��a�Ɋ������܂����A�a�؎��̃X�s�[�h��50�`���ςȂ�a�Ƃ͂����Ȃ����B�X�g���X���Ȃ��A�����h�b�����֎����ԓ��A�O�B �@�Ƃ��낪�A�O�ł܂����ԈႦ�B�d���Ȃ��A��ʓ��ɁB�ǂ��Ȃ��Ă�̂��c�c�B�d���Ȃ��̂Ńi�r�̎w���ʂ�ɖړI�n�����ցB�c�c�������A���낵�����ƂɁA�i�r�̐��ɏ]���ĉ^�]���Ă�����A�ׂ������炢���Ȃ��ʂ�ɁB�������O���̔��ΎԐ����ƋC�������Ƃ��͑̂��猌�̋C���X�|�b�ƈ����Ă����̂��킩�����B�Ȃ�ƁA�ڂ̑O�ɐM���҂��Œ�Ԃ����ԗY�����B�O�Ԑ��̃N���}�����ׂĂ�����������Ē�Ԃ��Ă���̂��B�Ƃ������Ƃ́A������͎Ԑ��̔��ɒ�Ԃ��Ă���Ƃ������ƁB�M���ɂȂ�����A���������ɃN���}�����ʂ���P���Ă���B�n���@�l���@�f�n�c�I�@�܂�ŁA��ԑ��̑O�ɔ�яo�����Ԃ�V���B �@����Ăăn���h�����A�H���̑ޔ��G���A�ɁB�N���}�̗��ꂪ�r�₦���̂����v����Ăt�^�[���B �@��@��E������A�o�s�r�c��ԁB�ߋ��ɁA�O��ǂ����������悤�Ƃ��Ė{���ɖ߂ꂸ�A�Ό��ԂƐ��ʏՓ˂����������Ƃ����������A���̉A�ɉB�ꂽ���ݐ�ɋC�t�����A����100�L���œ��ݐ��ʉ߂������Ƃ��������B���ł����̗l�q���v���o���ƐS�����h�L�h�L���Ċ���ł��܂��قǁB�J�̓��̎�s���Ń��C�p�[���O�ꂽ���Ƃ��������B�X�s�[�h���グ��ƃG���W�����~�܂�N���}�ɓ����������Ƃ��B100�L�������Ƃ���G���W���X�g�b�v�Ȃ�āA�����ɂ��Ȃ�Ȃ��N���}�ɂ悭����Ă������B��̋��t���H�ł����Ȃ�G���W�����~�܂����Ƃ��ɂ͎��ʂ��Ǝv���������B�������čl����ƁA�����Ă���̂��t�V�M�Ȃ��炢�B �@�@ �@�܂��A�V���ȁu�`���v������Ă��܂����B�����A���낵���B �@�Ȃ��ŁA2200�A��B�f�r���J���ĂȂ��̂ŁA���[�^�[�ŃK�\�����������5600�~�B�G�b�A4400�~�Ŗ��^���Ԃ��ɂ��Ȃ����Ă������ƌ���ꂽ�̂�f�����̂��s���B�������K�\�������g���Ă��Ȃ��̂ɁA5000�~�ȏ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�āc�c�s�𗝁B �@�����͌��@�L�O���B���A�t�W�e���r�́u�Ƃ��_�l�I�v�ō��Z�싅�̓��Ґ����������Ă������A���̗���ŁA�R�����e�[�^�[�̎O����Ƃ��u���Z�싅���͂����@�����̎��Ԃɍ���Ȃ��Ȃ��Ă邱�Ƃł͓����B����ɍ���Ȃ����@�͕ς���ׂ����v�ƌ������̂ɂ̓r�b�N���B���Ґ��������������ɁA�������A�s�[������ȂǁA�R�����g�̈�E�������Ƃ��B����ȂƂ��A�i��̏��q�q���������Ȃ߂�ׂ����낤�ɁA���̂܂܃X���[�B�t���̋�������B �@�����V���̒����ʼn����^����51���A����19���B�����^���̗��R�ň�ԑ����̂��u����ɍ����ĂȂ��v�u��x����������Ă��Ȃ�����v�Ƃ������́B���Ɂu�A�����J���牟���t����ꂽ�v�u���q���̊����ƂX���ɘ���������v�u�l�̌����d�������Ă���v�Ƒ����B �@�ǂ�����ɂƂ��Ă͂܂����������ł��Ȃ����R���B �@�u60�N��������Ă��Ȃ�������������ق��������v�Ƃ͂Ȃ�H�@�l�Ԃɂ��җ���邩�猛�@���ꏄ�肵���Ƃ���ʼn������H�H�@�s�v�c�ȗ��R�Ƃ����ق��Ȃ��B�l�ނ����s�����ĉ����N�B���Ⴀ���낻����s����߂āA�P���P�����тŕ������Ƃɂ��悤�c�c���ĂȂ��́B �@�����t�����@�_�͂����Ƃ킩��Ȃ��B�푈�ɕ����Đ�̉��ɂ��������{���V�������@�����ďo������͓̂��R�̂��ƁB�A�����J�̐�̉��ɂ��������炻�̎w�����Ɍ��@���z�������߂�ꂽ�͓̂�����O�̂��ƂŁA���@���ĂɊւ��ẮA���{�̊w�ҁE�����҂ɂ��u���@������v���A�J���I�Ȍ��@�v�z�荞�݁A���̑��Ă��f�g�p�̌��@���Ăɉe����^�������Ƃ͗��j�I�����B �@�܂�A���@�̍��{���_�͓��{�l����������̂Ƃ�����B�u�����t���v�Ƃ������t�Ƀi�V���i���Y�������������A�u�����t���Ȃ���{�l�̎�ŐV���Ȍ��@���v�Ƃ�����I�ȌQ�W�S���Ɋׂ�j�b�|���l�B���͂̈ӂ̂܂܁B �u�����t���v�Ƃ����̂Ȃ�A���Ĉ��ۂ����́u�����t���v�̍ł�����́B���{�̒��ɃA�����J�̊�n������A�����A�����̔�Q�͐r��B����Ȃ��ɁA�t�ɃA�����J�R�ɖ��N����ȍv�������Ă��邱�Ƃ����p�Ǝv��Ȃ��̂��낤���B �@�ߍ��ł́u�N�����v�v�]���v�Ȃ霘����˂����A����������A�����J�B�X�����c���Ȃǂ�v�����A������Ԏ��Ŏ���A���{�̍��Y����n����������t�B�R�T�O���~�̗X�����Y���A�����J�Ɍ��サ�������R�B���̎����}���{���A�A�����J�ׂ�����ŁA���������Ȃ̂ɁA���@�����́u�����t���v�ƌ����o�������B �@�u���q���̊����ƂX���̕s������̊Ԃɘ��������邩��v�Ƃ������R�ɂ������Ă͈��R��R�B �@�X�����������ꂽ��A�W�c�I���q����F�߂邱�ƂɂȂ�B �w�W�c�I���q���x�Ƃ́A�u�����Ɩ��ڂȊW�ɂ���O���ɑ��镐�͍U�����A���������ڍU������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A���͂������đj�~���錠���v�̂��ƁB �@���Ĉ��ۂ̘g���ɂ�����{�́A�C���N�ł��낤���C�����ł��낤���k���N�ł��낤���A�A�����J����킵���u�ԁA�������Ƃ��Đ푈�ɎQ�����邱�ƂɂȂ�B�A�����J�̓G��G�Ƃ��ĎQ�킷��̂��B�t�Ɍ����A���{�����荑�̕W�I�ɂȂ�Ƃ������ƁB���{�����ڐ��ɂȂ�̂��B�������{�A�Q������X�p�C�����s����B���R�A�����̊�{�I�l���𐧌�����펞�̐��ɂȂ�B���̎��Ɏז��ɂȂ�̂����@�̐l���K��╽�a��`�B������P�p����܂��ɐ�O�̈Í�����̍ė��ƂȂ�B�����}���A���X�Ɛi�߂�u�펞�̐��v�B����͂��łɁu�L���O�@�v�ŊO�x�͖��߂�ꂽ�B�푈�ɂȂ����獑���̍��Y�ł���y�n�������ڎ��ł���B�푈���ł���̐��𒅁X�Ɛi�߂Ă��Ƃ͖{�ۂ́u���@��X���v���U�ߗ��Ƃ��ΐ푈�̐��͊�������B�C�����t�@�V�Y�����ƂցB �u����ɍ����ĂȂ��v�ȂǂƂ����C���`�L�Ȑݖ�ɃC�G�X�Ɠ����Č��@�����Ɏ^���ȂǂƂ���51���̍����B����ׂ������͂��Ȃ����̂������Ŏ��ɂ��炵���Í����E�ɂȂ肻���ł������܂��B �@ �T���Q���i���j���� �@0730�N���B�S�~�o���B �@�[���܂Ń��W�I�h���}�̐����B������������m�g�j�E�a�r�̐����t�q���W�����Ă��܂��B���̓O�ꂵ�������Ԃ�Ɋ��Q�B���M�����ނ������R���悭�킩��B �@�؎����e�j�X�̎���������Ƃ����̂ŁA�O��������Z�k�B 1930�A�����^�J�[�i�P���U000�~�j����Ă��ă}���V�������ɒu�����A�H�㒓�Ԍ������܁A�Ƒ��̏����������܂ŋߏ��𗬂��^�]�B �@2030�o���B�O���獂�����Ɉڂ鎞�_�ł܂����Ă������I�[�o�[�B�i�r�̐��ɘf�킳��āA�ʂȕ����ցB�J�[�i�r���Ȃ����ɂ͊ԈႦ�����Ƃ��Ȃ��̂ɁA�i�r��M���Ďw�����������B�Ȃ�̂�������B�����Ԃ��čĂю�s���ցB�r���A�قƂ�Ǐa���Ȃ��܂܋��t�A�����A��\�㗢�̗L�����H�Ə����ȃh���C�u�B���A�܂����Ă��L�����H�œ�҂ɕʂꂽ�ꏊ�őI���~�X�B���������A���������ǂ��Ȃ��Ă�́H�@�u�l���̕����ꓹ�őI������葱���Ă������炵�傤���Ȃ����v�ƉƐl�ɏ�k����������A�u�ǂ������Ӗ���v�Ǝ����Ă��܂��B �@2230�A�Ȃ�Ƃ��A�ۗ{���ɓ����B���܂�̂͂킪�Ƒ������B�����̌�������q�͕��u�����ςȂ��B�o��팸�Ƃ͂����B�E�[���c�c�B �@ �@�T���P���i�j���� �@0700�o�ЁB�A�x�̒J�ԁB���������Ǝd����Еt���A1530�ގЁB�ƘH�ɁB �@�j���[�Y�E�B�[�N���A�E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�����A�b�m�m�e���r�ƑS�Ă��J�o�[����R�}�̂��w�����P�ƃC���^�r���[�ɉ��������{�����c�c�B �@�j���[�Y�E�B�[�N�ŐV���́A���{�C���^�r���[���f�ڂ��Ă��邪�A�uastaunch nationalist�v�i�؋�����̍�����`�ҁj�ƏЉ�B�]�R�Ԉ��w�̎ʐ^���f�J�f�J�ƍڂ��Ă��邩��A�ă}�X�R�~���_��͎��s�������悤���B���{�̃}�X�R�~�ƈ���āA�ă}�X�R�~�͐h煁B �@�j���[���[�N�E�^�C���Y���Ɏ����ẮA�u�u�b�V�����J�����߂悤�Ƃ��A�����������z��iSex�@Slave���]�R�Ԉ��w�̂��Ɓj���͈��{�ɂ��܂Ƃ��v�i�S��29���t�j�ƃo�b�T���B�u���z����Ɋւ��鉺�@���c�����킷�Ƃ����ړI���ʂ��������ǂ����͋^�킵���v�Ə����B �@���{�̓x�Z�X�_�C�R�a�@�ŃC���N�푈���������Ԗ₵�A�A�[�����g��������n�Ō��ԁB�u���{�����q����h�����C���N�����ɋ��͂��Ă���v�ƃA�s�[�������B�Ƃ��낪�A���̈���ŁA�u�b�V���哝�̂Ɂu���{�ƃS���t�����܂��v�Ǝ��������Ă����Ƃ�������A�������̖B�O����V���]�E�B �@���̐́A���{�̑c���ł���ݐM��ƃu�b�V���哝�̂̑c�������V���g���x�O�̃S���t��ňꏏ�Ƀv���[�������Ƃ�����B�c�����m���v���[�����S���t��ŁA�ꏏ�ɃN���u������B�u����̓}�X�R�~����т��B�C�P��I�@�v�Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B�����u�b�V���哝�̂͂����Ȃ��\���o��f��B�u�����̓C���N�푈�������Ă���Ԃ̓S���t�����Ȃ��ƌ��߂Ă���v�ƁB �@�܂��ɒp���炵�B �@����Ȉ��{�Ȃ̂ɁA�����̖����V���̐��_�����ł́A���t�x������43�p�[�Z���g�ŕs�x���i33�p�[�Z���g�j�Ƌt�]�����Ƃ����B���̗��R���u�w���͂̔����v���Ƃ��B����Ȃɂ܂Œ�x���ȍ������Ƃ́A��Ȃ��ė܂��o�Ȃ��B �@���̂Ƃ���A60�N��̐V���̏k���łׂ邱�Ƃ������A���\�V�������������邱�Ƃ������B�܂��ɉ��̒m�V�H �@���w���̍��Ɍ����������Ă����e���r�h���}�u�����炢�v�i1969�N�j�B�V�m�Ύ剉�B  �@��������n��Ƃɖ��߂�n�k�����u�z�e���̉Ύ��ŕs�R���𐋂������Ƃ���A������Njy����Z�́u�����炢�v���n�܂�B���͖��͐����Ă���A����p���B���Ȃ�������Ȃ����R���������̂��B�l�X�ȃi�]���Q�����~�X�e���[�Ȃ̂����A���̋߂��Ђ̃g�b�v����ؐ���Ƃ������Ƃ����͋L�����Ă����B �@�������A���̂ق��ɖ�ۗz�q��吐�K�Y�A�����ĉe�̉�Ƃ��ĒC�Ȗ����Y���o�����Ă������Ƃ͋L�����犮�S�Ɍ������Ă����B����́A�I���ɂȂ��āA�����n��Ƃ��j�������Ђ����ɖ��A���A����𐭕{�̍���������ɓ]�p�����]�������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�B �@69�N�Ƃ������R�Ƃ�������̕����B�����A��ȃ��A���e�B�[�����������A���ꂩ��40�N�A���{�̎�]���u�j�����v�����Ԍ��݁A�u�r�����m�v�Ƃ͂����Ȃ��Ȃ����B �@���̋r�{�����X�؎炾�����Ƃ������Ƃ����߂Ēm�����B�����A���X�؎�́u���l�̌Y���v�ȂǎЉ�h��i�𑽂��肪�������A�u�E���g���}���v�̋r�{�������Ă����͂��B�f��]�_�Ƃ̏��c���j�A�f��ē̑��������Ƃ�1968�N�ɉf��u���́E�A���ˎE���v�𐧍삵�Ă���B���V�c�������q�ɐ������u�E���g���}���v�f��̋r�{�����������R�Ȃ���{�c�ɂȂ����Ƃ����B�L���Ɏc��h���}�̏����肪���X�؎炾�����Ƃ������Ƃ�m���Ċ����ʁB �@��̐V���̃R�����́u���l�̌Y���v�̊X�����P���Љ�����́B���́u�ӂ��肾���̋���v�́A�t�B�����ŎB�e���ꂽ���߁A������Ƃ�A�Q�삾����������u���l�̌Y���v�̈�{�B�g�c���o�q���o�����Ă����͂��B �@��ˎ����́u���̑�`���v�����w���̍����T�y���݂Ɍ������̂����A�p�C���b�g�ł̃L�����N�^�[�͑�l�тĂ������߁i��̃L�����N�^�[�j�A�����ւ��ɂȂ������Ƃ����߂Ēm�����B1966�N�̐V�����Ă���B����͂܂������m��Ȃ��������ƁB�^�C�g�����u��������`���v�ƂȂ��Ă���B�q�������̔��������Ƃ����̂�����Ă��c�c�B 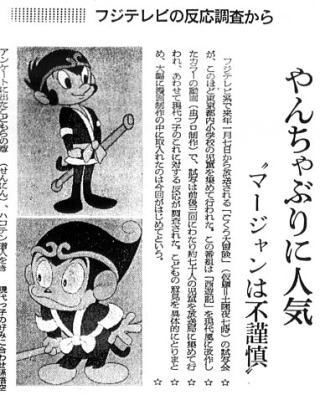 |