| �W��31���i���j���ꎞ�X���J �@�ߑO���A����Q��B �@�ߌォ�珬�J���p�����B���q�ƈ��ނ�ɁB�Ƃ����Ă��㗬�ł͂Ȃ��͌��̌Q�ꈼ���ړ��āB�������̂r�̒ދ�X�Ŗт���B�Q�{900�~�B���傤�ǒ��x�݂ŋA����r�Ɨ��b�B�u�ݕǂɍs���Α傫�ȃA�W���ނ��v�Ƃ���ꂽ���A�܂��͈��ނ�B������Ő��O�́u�w�A�l�b�g�v���g�������d���B���Y���~�̃l�b�g���r�������Ă���Ƃ̂��ƂłP�������Ă��炤�B�l�b�g�Ɩт�̓�{���āB �@���A�������c�c�B���J�ς�����A�Q��鈼�ɖт�𓊂��Ă������������Ȃ��B���N�̈��͑�^�ŁA�⋛���������Ă���B��ނȂ��A�l�b�g�ɐ�ւ�����A��������������Ȃ��B�͌��Ȃ̂ŃN�T�t�O����э���ł���̂��ƕ��B �@�����₽���A�������������q�Ƒ��X�Ɉ����グ�B �@���߂ĂP�C�ł��ނ�グ�ė[�H�̂������ɂ����������̂����B �@�[���A�{���ɍs�������Ƃ����̂ŁA�ג��ցB�Ŗk�[�ŋL�O�B�e�B�C���͉�����A�����Đk����قǁB�������A�[�Ă����������B�Q�F�̊C�ƃI�����W�̗[�₯�A��̑����Ɖ_���Ȃ�B����Ȃɂ��ꂢ�ȕ��i�Ȃ̂Ɂc�c�B �W��30���i�j���� �@�e�ʂ̂���Q��B���̌�A�����Y�ցB�Ɛl���K���̂͏��߂ĂƂ��B���܂ł͋A�Ȃ���Ƃ��~�̎d�x��Ƒ��̐��b�łقƂ�NJό��炵���ό������Ă��Ȃ������Ƃ����B�����Ă݂�A�m���ɖ��N�̂��~�A�Ȃł͊O�o���܂܂Ȃ�Ȃ��������낤�B�s���Ɏv���B  �@�����Y�͊C�ݐ��ɗ������Ԋ���̒n�B�N���}��40���B�r���̂Â�܂̍⓹������҂ɂƂ��Ă̓L�c�C�̂����B �@�����Y�͊C�ݐ��ɗ������Ԋ���̒n�B�N���}��40���B�r���̂Â�܂̍⓹������҂ɂƂ��Ă̓L�c�C�̂����B�@����n������B��ɔ����_�B���̒��Ȍ`�e�ȊO�Ɍ��t��������Ȃ��B���܂ʼn��C�Ȃ����Ă����c�ɂ̕��i�B���߂āA�悭����ƂȂ�Ƒf���炵�����i�Ȃ̂��B��͂����܂ł����A�_�͂����܂ł������B�ꕝ�̊G�������悤�Ȕ������R���g���X�g�B���̕��i������������O�̂��ƂƂ��Č��߂����Ă��������B���܂�̋��̕��i�͂���Ȃɂ������������̂��B �@���ԏ�ɂ͒������o�C�N��Y��ό��q�̃N���}������B �@�����K�i���~���Ɩڂ̑O�Ɋ���L����B �@����̌��Ԃɓ��荞��A�����܂�̏�����`�����ޑ��q�B�ʃ��[���O���̉Ɛl�Ɩ��B�̋��̉Ă�����Ȃ�ɖ��i���Ă���Ċ������B �@�A��̂Â�܂蓹�͂����C���Ƃ̂��ƂŁA�V���D�ňꑫ��ɉƑ��͋A���A��l�A�N���}�ō���܂ŁB�A���T�X�Ŕ����B���̎��ԁA�H���͗[���܂ł��x�݁B�e�ɂ킴�킴�����J���Ă��ꂽ�u���v�Ƃ����X�ŐH���B �@�[���A��B�]�o�v�w���K�˂Ă��Ă����B�]���v�w���B�Q�P�O�O�߂��܂ł݂�ȂŊ��k�B�y�����ЂƂƂ��B �W��29���i���j���� �@0630�N���B �@�L���������u�����R�������A�����V�[�g�����Ԃ����s�R�ȏ��^�D���C�����q�C���Ă����̂������l�͑g���܂ł��m�点���������v �@�s�R�D�H�@�����D�Ȃ̂��B����ȕ������̂͏��߂āB���a�ȓc�ɒ��������Ȑ��̒��̓����Ɩ��W�ł͂����Ȃ��B �@0800�A�Ƒ����V�����ɏ�鎞�ԁB���v�Ȃ̂��H�ƐS�z���Ă�����A���ꂪ�����ɓI���B�o���ԍۂ̑�g���u�������B�d���Ȃ��A�\���葁���}���ɏo�邱�ƂɁB �@1100�A�s�s���B�s������̉Ƃɍs���ƕs�݁B���炭�҂ƁA�u����҂ɍs���Ă����v�Ƃ����s�����A���B�ē�����A�j�q������̈ʔv��a����s����̉ƂɁB���ވ�e�Ɏ�����킹��B�Ƒ��̂��Ȃ��j�q������͒�̂s���������ƂɂȂ����������B��̑��ނ�������Ă����s����v�w�B�u�����Ɉʔv�����邩��A���ł����Ă��������ˁv �@���Ƃ͏]��ɂ�����s����B���̑��V�ȗ����B �@���Ԃ��Ȃ��̂ŁA�����Ɏ����B�N���}�łm�w�܂ŁB�߂��悤�ł��Č��\�����B�r���ɂ���u�X�q��v�̊Ŕ��ʂ̖��O�ɏ����ς���Ă���B�������Ƃ����͖̂{���������̂��B �@1300�A�w�ɓ����B�R���Ԃ�̉Ƒ��Ƃ̍ĉ�B �@�؍ݓ��������Ȃ��̂ŁA�Ȃ�ׂ��X�P�W���[���ٖ͋��ɁB  �@�A�H�A���R�ɗ������B�q��������10�N�Ԃ肭�炢���B���̎q�͂قƂ�NjL���ɂȂ��Ƃ����B �@�A�H�A���R�ɗ������B�q��������10�N�Ԃ肭�炢���B���̎q�͂قƂ�NjL���ɂȂ��Ƃ����B�@�V�[�Y������Y���Ă���̂Ŋό��o�X���P�䂾���B�O�r�̐�̐Ԃ����ۋ��̉��̐�ɁA�����ۂ����̌Q��B��ʂ����̋��B�����C�͂��邾�낤�BpH 3.5�Ƃ��������_�����̒��œK�����Ă������R�̃E�O�C�ɈႢ�Ȃ��B �@�ΎR�̂悤�ɔ����ۂ���ꂪ�����Č�����u���̐�v�Ƀr�b�V���Ɖj���E�O�C�̌Q��͈ٗl�Ȍ��i�B �u����͎��l�Ȃ̂����v�ƉƐl�B�m���ɁA���҂̌Q��̂悤�Ɍ����Ȃ����Ȃ��B���Œނ������l������͂����Ȃ��A�ɐB������Ȃ̂��낤���ǁB �@  �q�ϗ�500�~���ĎQ�q�B�P���Ԃ��܂�̒n���߂���̗��B���{�̂��߂ɏ���ςݏグ��Q�q�q�B �q�ϗ�500�~���ĎQ�q�B�P���Ԃ��܂�̒n���߂���̗��B���{�̂��߂ɏ���ςݏグ��Q�q�q�B�@�q���̗���Ԃ߂镗�Ԃ������炱����ŃN���N�����B�u����ŗV��ŁA�����ɋ��Ȃ����B������i�����j�Ɋ҂��Ă��Ă͂����܂���v�Ƃ����Ӗ�������A�Ɩ�m���̊ό��q�B �@�r���Ƃ����厩�R�̒��ɕ����яオ��l�H�̑傫�Ȓn���B���̃V���[���ȕ��i�B �@����ɂ���n�����̒��ɓ���ƁA�����͂܂��Ɂu���̋C�z�v���[�����Ă���B �@�S���Ȃ����Ƒ��̈�e��ߗށA�l�`�A�����Ȃǂ��������ƒ�A���[����Ă���B�Ⴍ���ĖS���Ȃ��������̂��߂Ȃ̂��낤�A�����̉ԉŐl�`���ЂƂ���ڂ��Ђ��B���̐l�`�ɍ��߂�ꂽ�v�O�ɁA�߂܂����������ɂȂ�B���҂ւ́u�v���v���[�����Ă���ꏊ�B�r���Ƃ����O�E�̒n���̕��i�����A���̂����̒��ɏ[������u���ҁv�ւ́u�v���v�̔Z�����Ɉ��|����Ă��܂����B �@16.45�A�n���߂�����I���ĎR��܂Ŗ߂�ƁA���łɂ݂₰���̓X�͕X�B�u�T���܂ŊJ���Ă܂�����ˁv�ƌ������ɂ��ւ�炸�A0450�ɂ͓X���܂����ĉ��R���Ă��܂����݂₰���̓X�̂������B���̂�����u���k���o�v�Ȃ̂��B�����ł͂T���̑ޒ����ԂɂȂ�ƁA�قƂ�ǂ̐l���T�T�b�Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ƃ������B �@�Ƃɓ�����1830�B�����Ă������z�c����荞�݁A��Q��B 2000�`2100�A���w����̓������f�̉ƂɁB���N�̂R���ɓ��@���A�S�z���������͊�̐F���������B�����̂l�Ɠ�l�A�d���O�ɃR���u���ɂ��o�Ă�Ƃ��B �@�T�ɂP�x�A�N���}�ŕГ��S���Ԃ����ĐX�̕a�@�܂Œʂ��Ă���Ƃ������A�̂ɕ��S���|���肻���B�����A�o�X�A�S�������p���Ƃ����Ǝ��Ԃ�������B��ʂ̕ւ̈������l�b�N���B���܂ꂽ����̑����P�B���c�c����ȃg�V�ɂȂ�̂��B�����w����̃����K�L���c�c�B �W��28���i�j���� �@�֓��ƕς�炸�A��͐Q�ꂵ���قǂ̏����B�u����Ȃɏ����Ă͕��������Ƃ��Ȃ��v�ƒn���̐l�������قǁB �@0600�A�������狙���̗L�������ŊC�����i�̂��m�点�𗬂��Ă���B��������ƒ�͂S���߂��ɂ͋N���o���A�T������̃R���u���B��������L�������Ƃ����̂��u���߂���v�Ƃ������o�ł͂Ȃ��̂��낤���ǁc�c�B ���W���́u���̐�v�̃e�[�}�ȁA�[���U���ɂ́u���[�����o�[�v���L�������ŗ����B�Ȃ��u���[�����o�[�v�Ȃ̂��̓i�]�B �@�����A�Ŗk�[�̐H���ł��������[����900�~�B���ʂ̉����[�����ɃE�j���悹�������̃V���v�����B�����ʂ��痈���炵���V�e�Ƒ��q�炵���ό��q����g�B�X�̎�l�������ȁi�H�j���ʌ�œ�l�Ɋό��ē��B�J���i�N�Y�݂����Ƀy���y���Ƃ悭����ׂ�B�����ɂ��u�����͓̂s��Ŗ炵�����̂ł��v�Ƃ������Ԃ�B���������l��n���ł́u�����ӂ肱���v�u�����Ȃ���v�Ƃ����B�����l�ł͂Ȃ���������ƕ@���ށB �@�ߌ�A�{�Ƃɍs�������łɁA�Ăы����@���M�̕�ցB�u����]�ފC���B���̕��i�������ς���Ă��܂��̂��낤�B �@�d�b�@�̈����o���ɂ��������̎蒠���B�ׂ��ɖ����̋C�ہA���̌����₻�̓��̗\����������Ă���B�ȑO�����̂�89�N�B�����87�N�B10��27���̗�������ƁA�u���̎q�����܂ꂽ�Ƃ̓d�b�B���߂łƂ��v�̕����B�����a���̓����B12��10���́u�R�̐_�̒������āv�̋L�q�B���N���������͂��̓����Ă�ꂽ�̂��B�X��27���A�u�����A�P�R�`�̑啨�̂�v�B�ʐ^�Ɏc���Ă���傫�ȕ����̊��͂��̓��̂������́B�c�я��Œc���A�n�{�i�I���O�j�̕������B�U���Q�O���A�u�Z�Z��蕃�̓��̃V���c�����Ă���v�Ɏv�킸�ړ����M���Ȃ�B�ꏏ�ɂ��Ă�邱�Ƃ̂ł��Ȃ������e�s�F�҂̌���c�c�B �@�A��ĎG���B�[���A�F�l�c���K�˂Ă��Ă����B�A���Q�N�ځB����₱���̐ς���b�B�C�����Ǝ��v�̐j��2300�B �W��2�V���i���j���� �@  ������y���L�h��̑����B�����Ɣ�J�ŁA�ߌ�̒��Q���[���܂ʼn����B ������y���L�h��̑����B�����Ɣ�J�ŁA�ߌ�̒��Q���[���܂ʼn����B�@�I�[�N�V�����Ŕ������I�[�v�����[���̃e���R�Ő̂̃e�[�v���Ă݂悤�ƁA��30�N�Ԃ�Ƀe�[�v�Z�b�g�B�w�b�h�̖��ՁE�T�r�̂��߁A�m�C�Y���傫���A�g�����̂ɂȂ炸�B�c�O�B���̃A�i���O���o�������̂����ǁB �@���A�e�ʉ��B �@�F�l�̂l�c����A�ȑO�ɏo���ꂽ�h���u�����@���M�̕�v�̃i�]�𖾁B���j�ɍڂ��Ă���300�N�O�̘̐b�B�����@���M�Ƃ����s�v�c�Ȗ@�͂��������C���҂����l�Ɋ�Ղ������炵���Ƃ����b�B���l�̕a�������A���̒��ő�������ȏ��D����Ɉ�������A���邢�͋��ԃJ�����������ŗ��Ƃ����Ƃ����B���̋����@�̕�̎ʐ^�����j�ɂ͍ڂ��Ă���̂����A�ꏊ������ł��Ȃ��B�ǂ��ɂ���̂ł��傤�H�Ƃ����̂��l�c����̖₢�B  �@���̎ʐ^���ǂ����Ō����悤�ȋC�����Ă����̂����A�����̐��Ƃ̂����߂��́u�ԍ�v�Ƃ�����̏�ɂ���̂������̂��B �@�q���̍�����A���̕���u����͈�̂Ȃ낤�v�Ǝv���Ă����B�R�̏�ɂ���A�ꌩ���ĕ��ʂ̂���ł͂Ȃ��B�L���̕Ћ��ɂ��̃i�]�̕�������Ǝc���Ă��āA�������N�A�A�Ȃ�����A���̕�����ɍs���Ă݂悤�ƍl���Ă����Ƃ��낾�����B�������A�n�`���ς��A���T�C�h�������R�ŁA�Ⴊ�~��Ƃ��̋}�Ζʂ��\���Ŋ����������̂����A���͂��̊R���Е��͐������Ռ`���Ȃ��B �@�����A�C���̊R�͎c���Ă���A���̏�ɁA�̂���̏����ȕ���������B�s�����������ƕ�̃y�A�B���̕�̕��������ǂ�ƁA�u�����@���M�v�̕����B��͂�A�����������I �@�����I�O���炭���Ԃ��Ă����u���̕�͂����������H�v�Ƃ����^�₪�X�������u�ԁB �@���j�ɂ́u��ԁv�Ƃ��邩��A�܂���킵���B�܂������ʂ̏ꏊ�������̂��B  �@���̂��Ƃ��l�c����Ɍg�тő��U�A���B�����̉Ƃŗ[�H���ɘb���ƁA�u�̂͐����ɂȂ�ƁA���̕�ɒ��A���͂������̂��v�Ƃ����B�n���̐l�ł��A���̉��N��m��Ȃ��l�������Ƃ����B�u�t���_�Ђ̐_���̖��Ⴊ�Ǘ����Ă���v�̂��Ƃ��B�Ȃ�قǁA�����͂��B �@�v��ʔ����ɏ���肷�鎩���B���Ȃ炻��Șb���悭�m���Ă������낤�Ɂc�c�B �@�[�H��A����̉ƂɁB�]�Z�Ǝ����ނ��킷�B�C�����Ɛ[��O���B����Ȃɒ������ԁA�]�Z�Ƙb���������Ƃ͂Ȃ������B �@�ނ͌����ɂ͎^���̗��ꂾ���A�u�{�H���͑��[�l�R������邩��A�n���̌��݉�Ђ͏����H�������B������A���݂����肵�����̂Ђ��Ԃ����悤�ɁA�n���Ǝ҂ɂ͗₽���B���������ΐ������������Ԏ��ɂȂ�悤�Ȃ��́B�o�J�炵���Ă���Ă��Ȃ��v �@���܂��ꂽ�c�c�Ƃ͌���Ȃ��������A�����悤�Ȃ��́B�U�X�I�C�V�C�b�Œn���ɗ��v�U������ƌ��������Ă����āA�Ō�͑��[�l�R���������ׂ����z���グ��B�d�����ΐԎ��ɂȂ��Ă��A�n���Ǝ҂͎��ꂴ��Ȃ��B�d���Ȃ��̂��߂ɁB �@�����炷��A���܂������������A���܂��ꂽ�ق��������B �@�R���u�������Ă��锌���������������B �u���N�A�R���u���̎��A�R���u���グ����D���т�������āA�C�Ő��Ȃ��Ɗ����Ȃ����炢�B���ׂ���A�������ݍH���̃g���b�N���C�ɉ��\����y����s�@�������Ă����v �@�R���u���͒��̐l�̈�N�̎����̑傫�Ȕ�d���߂�B�s�@�����͋��ƕ⏞����ᔽ�ȑO�́u�s�@�s�ׁv�ł���A�������d���J���ɕ⏞����v������͓̂��R�̂��ƁB �@�ŏ��̗v���z30�������ʓI�ɂR��7000���~�ɂȂ����̂����A�Ԃɓ�����������5000���~��悹���Ď��ł����Ƃ����̂��A�������Șb�B�ŏ����猴����ЂƋ����g�����ƒ����̗�������������Ǝv���Ă����傤���Ȃ��B �@�s�s���Ȃ�X��E�����o�Ă��Ă��̏\�{�̕⏞���������o���Ă���͂��B�����Ƃ��A�J�l���E���͌����̂���_��S�����낤���B �@�����J���Δ����������̓`������ꂾ�̂ƌ����u�E���v��u���Ǝ�`�ҁv�����B�������C�l��`�����镃�c�̓y�n����˔\���ꗬ���̌����̉��ɖ��߂Ă��܂����Ƃ��u�������v���ƂȂ̂��B�_�Ђ̌�_�����������ăX�J�X�J�̌����ɂ��Ă��܂��̂��u�h�_�v�Ȃ̂��B��k����Ȃ��B���������S���Đ����ł���������A�×��̓`�������A���������{�̎��R�����B���ꂾ���ł����̕�����قǁu�������E���v�̎��i������Ǝv�����c�c�i���j �W��26���i���j���� �@�n�{��0802�̐V�����Ŗk��B1119�A���˂���́u���炫��݂��̂����v�B�喩�w1310���B �@�֓��ƂقƂ�Ǖς�肪�Ȃ������B�w�O�Ń����^�J�[�ɏ�芷���A�c�������ʂցB�܂��A��N�S���Ȃ������̏]���E�j�q������̉ƂɁB�ׂ�̂r������͕s�݁B�j�q������̉Ƃ̑O�ɂ͎q���p���]�Ԃ⍻�ꓹ��Ȃǂ��G�R�ƒu���Ă���A�q���̂���Ƒ����Z��ł���l�q�B�q���̂��Ȃ������Ƃ��炵�̂j�q������̉Ƃ͂��s���Ă�������ƕЕt�����A�[���Ȃ������܂��̉Ƃ��������A�܂�ŕʂ̉Ƃ̂悤�B�Ƃ̎傪�ς��ƉƂ܂ŕς���Ă��܂��B��K�̏��ւɂ����������S�W�͂ǂ��Ȃ������낤�B���Z�ɓ��w�����Ƃ��A��ƈꏏ�ɂj�q������̉Ƃɏ��߂Ă��ז��������A�莝���������ŁA��K�ɂ����������S�W����Ɏ��A�����ǂ݂ӂ����Ă��܂������̂��B �@�r������̉ƂɎ�y�Y��u���āA�a���̎������ցB���A�ނ��s�݁B�g��O�̃��C�u�R���T�[�g������A�㉇��Ƃ��āA������قɋl�߂Ă���Ƃ̂��ƁB �@�c�����𗣂�A��H�A�䂪�ƂցB �@�ߌ�Q���߂��A�܂��s�[�J���Ƃ�B�ؖ암���ł�29�x�I �@��ꎞ�ԂŐ��܂ꂽ���ցB �@�ϐk�v�̍Č����̂��߁A�H�������т������B�������A���łɔ����C�݂͕����B��ʎԗ��͉I�H���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ�E��ɊC����Ղ݂Ȃ��瑖�点��N���}���A���ꂩ��͎R���𑖂邱�ƂɁB���ƂƎ���ƂɊC�ƊC�ݐ���n�����킪���B���c������Ă����y�n�����c�P�͂����K������B�����Ȃ��C���ɂ�݂Ȃ���A���̒��ւ̈������ӂӂƂ������Ă���B �@�����ʼn䂪�Ƃɓ����B�����̑O��������Ƃ������o�Ȃ̂����A�����P�N�����Ă���̂��B����A�]���v�w�������{�C���[�����ւ��Ă��ꂽ��A�|�������Ă��ꂽ�̂ŁA���ʂ����悭�A�����Ƃ���L�C���Ȃ��B���d���J���āA�����𗧂ĂĂ���A��Q��B���傤�ǁA�Z�E�̖����F�l��Ƌ����Ńo�[�x�L���[������Ă����̂ŁA�h�Ɨ��̎x�����B�P�N�łR��3600�~�B��N���[�������̂łQ�N���U��7200�~�B�����ɕ����������o�J�ɂȂ�Ȃ��B�����A����������ǂ��Ȃ�̂��B�q�������ɂ���ȕ��S��������͔̂E�тȂ��B������ێ�����̂���ς��B�c�c�ȂǂƓƂ育���B �@ �@��ʂ�A�Ƃ̒���|���B�܂��z�������̂Ńx�����_�̃y���L�h������邱�ƂɁB�y���L���͂��ă{���{���Ȃ̂��C�ɂȂ��Ă����̂��B���N�̋A�Ȃ̍ŏd�v�ۑ�B�x�����_�̃y���L�h��B �@�ŁA�Ԃ�����āA�u���v�ցB�����y���L����ꎮ�B�Ԓd�̃u���b�N380�~�~�T�B���ꂪ�O�����߂Ĉ�Ă������ʂ̖�����ꂽ���Ƃ����܂��Ɍ��ɂ����B�킸���Ɏc���Ă����̖����Ȃ���B�s�݂��������ƂɁA�݂��������݂̂Ȃ炸�u�ꉮ�������v���ƂɂȂ����畃��ɐ\����Ȃ��B �@�[���܂Ńy���L�h��B�����ɂȂ��ė����������̂ŁA�I���Ƌؓ��ɂƍ��ɁB�Ƃ肠�����͕Е��̃x�����_�̂݁B�y���L�̐F���d�オ������Ȃ��ƐF�������悭�킩��Ȃ��B�Ⴄ�F�̃y���L������������A�Ă�Ă������B �@�[�H�͏]�o�̉Ƃł��Ă�B�c�ɂɋA���Ă��C�����悭�߂�����̂͏]�o��e�ʂ̂������B���ɏ]�o�v�w�ɂ͑��������Ă͐Q���Ȃ��B���̎o��̂悤�ɋC�����Ă����̂�����B�Ƃ̏]���v�w���������A���k�B �@2000�A��B �@���Ƃɔ��܂鏉���ْ͋����Ă��܂��B�܂��Ƃ��Ȃ���ł���Ȃ��̂��A�ǂ��ɂ��S�ׂ��̂��B����V�����߂���ƁA������͐^���ÁB�o�����l�����Ȃ���ΊX�����قƂ�ǂȂ�����A�X�͈łɕ�܂��B�P�K�̓d���������ςȂ��ɂ��ĂQ�K�ŐQ��̂����A���������Ȃ��ȁA���ꂪ�B�����ɂȂ��Ă��A��̈ł͕|���B �@ �W��25���i�y�j���� 1400�A�V�h�B�V�A�^�[�g�b�v�X�ŃW�F�b�g���O�E�v���f���[�X�u����v�B�V�~���q�̓����i��E���o�B���c�ł̑�d�|����s��ȃ��}�����������A����̂悤�Ȑl�Ԃ̋@����`�������i�ɂ����킢������B���߂Ă��̍˔\���������B 1545�I���B�ׂ�̋I�ɚ����z�[���ցB���I�̃}�`�l�B�I���̖�45���Ԃ����r�[�̃��j�^�[�Ō���B���R���̖��҂��Ó]�œ]�|�B�z���A�]�kṂ��N�������Ƃ����B�~�}�Ԃ��Ăڂ����Ƃ��������ɂȂ���A���̂܂ܑ��s�B���j�^�[�Ō������̓Z���t�����v�B �@�T�W�F�X�`������������p�v�̉��o��ύX�����͗l�B�I����̃��r�[�ɂ͋㞊����A�Η��A���V����A�����߂Ƃ������V�~�g�B�X���痈����������͗p��������Ƃ̂��Ƃő��X�Ɉ����g�����Ƃ̂��ƁB �ߏ��̋i���X�ł����B���ꐅ��̗�ؖM�j�A��v�ۑ�A����A�R��N�̊�Ԃ�B �@1900�A�������͂ŗє��Y�������A���N���u�̃I�t��B10�l�قǂ̉���Ə��獇�킹�B��͒��엜�G����̓X�B�s�������������A�����̂��Ƃ��l���ĒE���B2230�A��B���͍Ղ�̗]�C�B �W��24���i�j���� �@1400�A����B�|�P�b�g�Ō��cPATHOS PACK�̊��g�������uVACANCY? NO VACANCY!�v�B �@�F�����m������ǐM�A����M���Ɗ��g���������c�B���̐́A�u�ŁX�ŋ��v�Ƃ����v���f���[�X���c����Ɂi���̌�u�����������v�Ɉڍs�j���Ă����F���B�}�X�R�~�Ńu���C�N���A�Љ�l�싅�̊ēȂǂɊ���̏���L���Ă��A�ŋ��ւ̏�M�͐����邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ԏ��K���̏����c�����g�����邻�̐S�ӋC��悵�B����́A�n�ӂ���q����̌����ƌ��z����������u����v�l�������B �@�������A�ŋ������܂��]���炸�����Ƃ���ő����݁B���ᒲ�B�q�Ȃ͂R���̓���B �@15.35�I���B �@�ӂƁA�[���{�����ߏ��ɂ��邱�Ƃ��v���o���A�[���T�_�����߁A�d�b����ƁA�����ڂ̑O�̃r���̂Q�K�B�d�b�ɏo�������́A���Ȃǂł悭��������X�^�b�t�B�����������m���Ă���悤�ŁA�u���Z�x���̂́�������ł���ˁB�Љ�l���ł����O�́c�c�B���̑O�A�����q�����܂����v�ƁB�����ƁA��s���͂��Ă���H�@�т�����B �@�V�h�Ɉړ��B�I�ɚ����z�[���ցB1600�A���傤�ǃQ�l�v���̏I���B���悳��ƃV�[�U�[�����o�ȂɁB �@���I�̌��c�͏��߂Ă̋I�ɚ����z�[���B�V�[�U�[�́u���~���O�v�ȗ��A24�N�Ԃ�̋I�ɚ����z�[���B���̂Ƃ��͂܂����R����͐����Ă����̂��B�����āA���A�u���R�C�i�̐��U�v�䉻����B�s�v�c�Ȃ߂��荇�킹�B �@�_���o�������Ȃ��炻��Ȋ��S�Ɂc�c�B �@�o�`�m�s�`�̓M�v�X�͏������Ȃ������̂̂܂����t��B���r�[�ő�v�ۑ邳���ƒk�B�J�[�e���R�[���Łu�є�̃}���[�c�c�ł͂Ȃ��A�P�K�̃}���[�v�Ƃo�`�m�s�`���Љ�����Ƃ����邳��B�A�h���u�͔����B�E�P�_���̏Փ����y���܂ŗ}�����邩�B �@�q����̂U.30�܂ŁA���r�[�Ŋώ@�B�������A�j��В����o�Ȃ̂e�`�w�������Ƃ����̂ŁA�N�F�v���Ɠ����őҋ@������A���Ɍ��ꂸ�B �@���悳��̌�F�W�̍L����\���悤�ɋq�Ȃɂِ͈F�̊�Ԃ�B���������A�ѐÈ�A�H�R�S�����q�A�̊�����R�v�l�̍��X�Ďq�A���u���g�����h�̎O��i�����j���������B�]�_�Ƃł́A��c���F�A�����L�A�]�X���v�A�����p��A�����s�l������ �@���I���ӂ̈Ó]����X�^�[�g�B �@�I�ɚ����z�[���̓}�b�`���g���Ȃ����߁A�����d�����g���Ắu��ŖS�v����B����͎c�O�B�}�b�`���邻�̉��̂��߂��������R�C�i�Ȃ̂Ɂc�c�B �@��Q����15���B�J�����Ԃ��������̂�2125�I���B �@�I����A�u���t�v�Ŋ��t�B�N����A�ѐÈꎁ�炪��s�B�����ŁA���X����A���R���̎O�Y�L�q����A��v�ۑ�A��������A�]�X����B �@�邳��͊��g�������̓V��V�~�����Ă���Ƃ����B�u�V��V�~�̎ŋ��͍D����������B���̍��A���҂����c�����R�Ɉړ��ł��鐧�x����������A�Ȃ�čl���Ă����v�ƁB�g�e���g�̐\���q�̂悤�ȑ�v�ۑ邪����Ȃ��Ƃ��l���Ă����Ƃ́B�Ȃ��Ȃ��ʔ������z���B�����͍g�A�����͍��A���̎��͎V�~�c�c�B �@�V��V�~�Ə���̗��������̎��ɂ́A�邳��������ɉ�����čS�u������B�u�Q�K���I�������g�ŁA�P�K�Ɏ��R�������Ă��B�Q�K�ɏオ��Ƃ��A�����玛�R���j���b�Ə��Ď���グ�ĂˁB���i�\�Y�j����ɂƂ��Ă͌Z�M�������A����Ȏ��R���������悭�������ˁv �@���X����́A������R�̈ӊO�Ȗʂ��B�ߏ��ʼnΎ����N����A�ޏĂ��邩������Ȃ��ƁA�݂�Ȃ������悤�Ƃ��Ă��Ă��A�בR�Ƃ��Ē��ߐ�̌��e�������Ă����Ƃ��B�ѕz����������Ȃ��̂ŁA�Ƃɖ߂����炻�̖ѕz�Ō��e�p���������ł����c�c�ȂǁB1950�N��́u�`�����s�I�����v�̌�A���炭�s�����オ�����A�u�k�Ђ̎G���ꎏ�����̒��������Ȃ������B����ł��A���炻���ɂӂ�Ԃ��Ă����Ƃ��B�u�L���ɂȂ��āA�����������Ăӂ�Ԃ�̂ł͂Ȃ��A�n�R�ȂƂ����ς�炸�A���ݕs���ȑԓx�ł�������B���̓_�͎����т��Ă��āA���炢�ł���ˁv�ƕv�l�B �@2330�A�I�d�ɊԂɍ����悤�ɁA�]�X����Ɛ�Ɏ��炷��B �u�Ԕ��Ԃǂ��܂ʼn����Ǖ�n���v �@���̎��R�̔o����A�u�͂Ȃ�����@�ǂ��܂Łc�c�v�Ɩ��҂��ǂ̂ŁA�I���b�Ǝ���Ђ˂����̂����A�h�͂Ȃ��肮��܁h�ł͌��܂���͂ݏo���Ă��܂��B�������A�u�͂Ȃ�����v�͂Ȃ����낤�ƁA�����A�_�c�B���āA���R����͂ǂ��ǂ܂����̂��H�@�i�]�ЂƂB �@����̕���B���R�C�i�̐��U��`���Ȃ���A�ނ̕����i�̓o��l���A�i���q�T��A���N�T��c�A�є�̃}���[�������j���������邱�Ƃɂ���āA���R�_�����������Ă���B����������A����j�ςɂ�鎛�R�_�B �@����G�i���E���ǐ�t�j�����t�B�X�g�Ƃ��āA���R�C�i�̖��ƈ����ւ��ɍ���D���Ƃ����V�[���͂������u�t�@�E�X�g�v�ł���A���I�̌��c���㉉������ˎ����Ńt�@�E�X�g���p���f�B�[�ɂ������́B���̎ŋ��ɏo�Ă�������G��������͓̂�d�̃p���f�B�[�B �u�݂�Ȃ��s���Ă��܂�����@���̐��ōŌ�̉������z�����c�c�v�Ƃ����V��V�~�Ō�̌����u���~���O�v�̎��́u���E�̊U�Ă֘A��Ă��āv�̍����Ɏv�킸�܁B �@�������A�s���Ȃ̂́A���R�̔ӔN�����������҂̑��`�B�X�^�C���b�V���ŁA�D�u�Ƃ��Ă������R���A�u��e�̉e�ɋ������Ȃ����N�j�v�ɂ��������Ȃ��B�J�b�R�����̂��B���R����͂߂��Ⴍ����J�b�R�悩�����B���ꂾ���͕s���B���݂���l����������͓̂�����A���܂�ɂ��f�t�H�����������āA���̐l�������j���̂͂ǂ�Ȃ��̂��B�u�ҏW���v���ƒ���p�v���������̂̓X�M�E�����J�B����͂Ȃ����낤�A�Ƃ����f�t�H�����Ԃ�B�R�c����������B����Ɋւ��Ă����A�z���N�Z�N�V�����ł��邱�Ƃ݂̂��N���[�Y�A�b�v�����B�N�l�N�l�Ɛg���悶�点��̂́c�c�B���O�̒��䎁�͎��R���l�A�X�^�C���b�V���ŋB�R�Ƃ��Ă����B�p�^�[�������ꂽ���Z�͂��̏ꍇ�A�}�����Ăق��������Ǝv���̂��B �@ �@2430�A��B�������Ԃ��Ȃ��c�c�B �W��22���i���j���� �@�������܂��ҏ����B �@�e���r�̐����t�����@�ɁA�����̑�|���B�^��ǃe���R�Ȃǂ͓c�ɂɔ����B�����w�肪�ł���̂��������B�[���ɂ͈�ʂ�Еt���B�{�ƃr�f�I�A�������͏ꏊ������Ăǂ����悤���Ȃ��B�ꕔ�̓����^���̕��u�ɁB �@�[���A�Ɛl�ɕt���Y���A���Ȉ�ɁB�A�Ȃ̐ؕ�����z�B�����^�J�[�U���ԂłS���~��B �@2000�A�l�䂳��̃��[���ō����̒����V���[���ɍ��X�؏���Y�����u�V����B��v�Ƃ����L�����ڂ��Ă���Ƃ̒m�点�B���ꂪ�{���Ȃ�d�厖���B�Q�Ăė[�������߂ăR���r�j���n�V�S���邪�ǂ��ɂ��Ȃ��B��ʎ��̗[�����R���r�j�ł����ɏ��Ȃ����B�g�т�Y�ꂽ�̂ŁA���O�d�b����Ƃɓd�b���āA�����̐ꔄ���̓d�b���B�ŁA������ꂽ�̔����Ɏ��]�Ԃŋ삯����ƁA�̔����͖��l�B�d�b���悤�ƌ��O�d�b����T�����A�Ȃ��Ȃ������炸�B�悤�₭�����ēd�b����Ɓu���݂܂���A��K�ɂ����̂ŋC�����Ȃ��āv�B�ŁA�̔��X�ɍĂы}�s�B�悤�₭�[�����ꕔ��ɓ���邱�Ƃ��ł���B �@�������A���̎���A�V���̗[�����ꕔ��ɓ����̂ɂ���Ȃɋ�J����Ƃ́B�܂��A�g�т̕��y�Ō��O�d�b���p����������̂��A����̔s���B�֗��ɂȂ����悤�ŁA���͈���O���ƕs�ɂ܂�Ȃ��B �@�̐S�̋L���́A���X����ꗬ�̃��b�v�T�[�r�X�H�@�������A����Ɂu����c�̏��w���v�Ƃ�����̓I�ȋL�q�B�����A��������A�������B �@�c�ɂŒn�k���������Ƃ̃e���r���������̂ŁA�]���ɓd�b�B���łɁA�{�C���[�̌��A�v���p���K�X�̌������肢����B�n�k�́u�C�����Ȃ������v�Ƃ��B �W��21���i�j���� �@1600�ގЁB�ŋ������ɍs���܂ł̎��ԑ҂�����������B�H�t���ʼn��Ԃ��A�u����v�ɁB �@���܂�ɂ��������ēǏ��ӗ~���N���Ȃ��̂����A��������Ǝ��Ԃ������ĂP�K����U�K�܂œX��������B�y�b�g�{�A�I�[�f�B�I�{�A�i���Z�{�A�f��{�ȂǁA���i�͒ʂ�߂���R�[�i�[�܂ŒO�O�ɁB �@���D�E�V���p�q�́u���̗������@�g���ŗ�v�i����o�Łj���������̂ŗ����ǂ݁B���g�̗c�N���̎ʐ^�Ⓑ���E�G������̎q���̍��̎ʐ^�Ȃǐ}�ő����B�����ʂƔ����͂ɔ���������A��_�̃u�����Ȃ����D�̐������B���������Ǝv�������A�A�}�]���̒��Ï����Ƃ����炾�낤�ƁA���l�b�g�l�i���l���Ă��܂��B�����������炻�������c�c�B���ꂶ�Ⴀ�{������Ȃ���Ȃ��B �@���ǂP�K�̃��b�N�A�G���{�̃R�[�i�[�ŁA�O���A���Y���u���������ɂ��܁v�i�j�j�����O�Z���[�Y�j�A�u�h�镕��f���@���̓��B���A�j���O��K�C�h�v�i�O�˃u�b�N�X�j���B�����̃��[�c���퍷�ʕ����ɂ��邱�Ƃ����\���A���ʂ܂ŋ����̗��𑱂���O���A���Y�̔����L�B�퍷�ʂ̋�Y��w�����Ă������߂��A�O�ꂵ�č��Ƃ₻��ɕt�����錠�͂Ƃ������e�B���܂ɓ��������ɗ��Ă������_�Ђɂ͌������������A�R�l�ɗ^����ꂽ�]�R�L�͂��㐶�厖�ɂ��܂�����ł����ǂ��납�A���̎�֑���ɂ��Ă����Ƃ����B����ȋC���̂��镃�e���A�Ō�܂Ŏ����̏o���𑧎q�Ɍ�鎖�͂Ȃ������B�Ō�̎��̏��ŁA�܂Ȃ���ɐ��Ȃ����ői�������͉̂����������B�퍷�ʂ��O���A���Y�̔����͂̌��_�B84�B�v���Ԃ�Ɂu�ٕ�Z��v�����悤���B34�̎��ɁA�V���������邽�߂ɁA��̑O�����Ȃ��ł��ׂĔ������Ƃ����A���̉f��B���傤�ǁA�����A�a�r�ŕ��������̂������B �@�@�{�����o�āA�n���S�ɏ��p���A�X���ցB���[�������Œ��ؘ�780�~�B �@�����ł����������ƃx�j�T���ɋi���X�Ɍ����ĕ����ƁA���̋@�O�Ŏ������ĂԐ��B�N���Ǝv�����◬�R�����B�������A�x�j�T���X�^�W�I�Łu�I�b�y�P�y�v�̌m�Ò����B�u�����͂��ꂩ��U�t���܂�����v�Ƃ����̂ŁA�m�Ïꌩ�w�B�v���Ԃ�̒��c�}���[�A����J����B����30�l��̏W�c���B�U�t�V�[�����唗�́B6�E45�܂Ō��w�B�R������q����̋}���̘b������Ɨ��R�����m��Ȃ������悤�ŋ�������B�u����Ⴀ�A�M�i�����j����A�V���b�N���낤�B�i�ϐ��h�v����Ƃ����j���đ����ɑ厖�Ȑl���S���Ȃ����c�c�v�ƁB�����M���o�A������11���I�y���u�V���ƒn���v�̈ߏւ��R������q���S�����Ă����Ƃ̂��ƁB 1900�A�x�j�T���s�b�g�Łu��������̋����\The Distance from Here�v�B�A�����J�̍�ƁA�j�[���E���r���[�g�̋r�{���t�N�炪���o�B �@���e���N�Ƃ��킩��Ȃ��Ԃ�V����Ă鏭���B���̌��̂Ȃ���Ȃ���ƌZ�A��̈��l�B16�̏��N�����̖��O���ȓ{��Ɛ�]�B������Z���Ȑ��Ɩ\�́B�����ɂ���t�N��炵���������Y���B �@��t�A�A��t�q�ȊO�͖����̎�҂����B�剉�̃_�������������y�c�S���A���J�^��A�����ď��щĎq���s����Ȏ�ҌQ����̓�����ʼn����Ă��Ă������������B���ł��_���T�[�o�g�̍��q�͒��ڊ��B �Q����10���B�w�܂łs���L����ƁB�u�r�[���ł�����ł����܂��v�ƗU���邪�A�u�n�Q�^�J�v���҂��Ă���B�R��ڂ��������킯�ɂ͂����Ȃ��B�^��������ς��ŁA���A���^�C���Ō��邵���Ȃ��B�₽���r�[���f�O�B�s���������B�n���S�ŕʂ�Ĉ�U�ɉƂ܂ŁB2210�����B�Ȃ�Ƃ��Ԃɍ������c�c�B �@���������t���e���r���͂��B �W��20���i���j�����[���J �@�ߌ�A�c�ɂ̋����ɓd�b�B�A�Ȃ̍ۂɋ��ƌ��̑������A�Ǝv�����̂����A�u�Z�������n�łȂ���Α����ł��Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��B���N�́A�u�����I�ɕs�s��������Ƃ����ɂ��邩�獡�̂����ɑ������v�ƌ����Ă����̂ɁA���́u��̂Ђ�Ԃ��v�B�m���ɁA�c�ɂɋ��Z���Ȃ��҂ɋ��ƌ�������Ƃ����̂��s���R���Ǝv�����A�������Ƃ͕ʖ��B �@�������A�S���҂̂��̌��t�̃E���ɉ����s�R�Ȃ��̂���������B �@�v���ɁA�����̕⏞�����V���ɕ��z����邱�Ƃ����܂����̂ŁA�Ȃ�ׂ��u���O�ҁv�̓I�~�b�g���悤�Ƃ����Ӑ}������̂ł́B�����Ƃ�A�⏞���ȂNJᒆ�ɂȂ��B�����A���c�̋��ƌ����A���ł��������Ȃ��Ƃ������Ƃ����B�����͓c�ɂɖ߂邩������Ȃ��B���̎��ɁA���ƌ�������ΊC���̂肾���Ăł���킯�ŁB������u�⏞���ړ��Ă̑����v�Ǝv��ꂽ�Ƃ�����S�O���̏�Ȃ��B �@�̋��Ƃ̂Ȃ��肪�܂��ЂƂf����ꂽ�悤�ȋƂ����C�����c�c�B �@�̘^�悵����f�f��u��̒��v�i1957�N�j������B �@���}�`�q�ƎR�{�x�m�q�̓��X�^�[�̋����B����̍����o�[�̏����ƁA���s����i�o���Ă����o�[�̏����̉ߋ��ƃ����c�������������܂����o�g���B�������A�������̕i�i�̂Ȃ��o�g���ł͂Ȃ����B�`���̕��d�o�[�u�����߁v�����f���ɂ������̂Ƃ��B�D�z�p��A���h�O�A�H���C�u ����h���Y�A�R�����A�����L�Y�c�c�B�X���閼�D���݂�ȎႢ�B�����E�g�����O�Y�ē̗���ȃ^�b�`�B �@1957�N�Ƃ����ΐ��܂ꂽ����B���R�Ȃ���A�R�{�x�m�q�Ȃǂ́A���{��̔��l���D�Ƃ��Č��`����Ă���̂����������B�����ɂƂ��Ă͂͂邩�ɔN��ŁA�����Ă�����u�����D�v�Ƃ��Ă������Ă��Ȃ������̂����A������ƁA�B�e���͍��̎��������N���Ȃ킯�ŁA�u�Ȃ�Ă��ꂢ�ȏ��D����v�Ɠ��R�Ƃ��Ă��܂��B���̕s�v�c�Ȋ��o�B�q���̍��̋��t��������������u�N���v�ɂȂ�A�u�����̋��t�̋C��������Ɏ��悤�ɂ킩�����u�ԁv�̂悤�Ȃ��́H �@����ɂ��Ă��A�̂̉f��͕i�i������B���݂̂Ȉ����ɗ�����錻�ォ�猩��c�c�B �@�R������q����}���̕�ɋ����B����œ|��Ă���̂�K�˂Ă����F�l�����������Ƃ����B���łɎ���Q�`�R���B�}���x���Ƃ������A��l��炵���������߂̔ߌ��B���P�J�����炢�O�ɐV�h�̃X�y�[�X�[���̋q�ȂŎp��������������B���ς�炸�̔������B���̉e�Ȃǂ���킯�͂Ȃ��B���R�C�i�̕���u�����̕s�v�c�Ȗ�l�v�A�f��u��C�ِl���فv�ł����̗d�������͂��ۗ������B�꒷�̖ځA�Ɠ��̉��ρA�t�@�b�V�����E�����łȂ��A70�N��̓��{�̔��̏ے��������B���l�����Ƃ͂������c�c�B �@ �W��19���i���j���� �@���傤���܂��ҏ��B0900�`1200�A�[���m�ÁB�q���͂R�l�B�c��͑s�N�g�B���̎����A�s�N�̏o�ȗ��͔��Q�B9���̎Љ�l���̒c�̐���܂�ڎw���Čm�ÎO���B�X�|�[�c�h�����N�Q���b�g���͂����Ƃ����ԁB �@1300�A��B���H�͉Ƒ��Łu�؉��^���q�v�B �@�ƂɋA��ƁA���̃r�[���̂����������ɏP���A�O��s�o�B�C������1900�D�����ƁA�������t�C�ɁB �@��������A���R�[�����������u�n�Q�^�J�v�����Ă���A�Q�B�Ȃ�قnj��������̂���h���}�B �@���ԙZ�̑��q�̑�X����B�e�Ƃ��Ă͂���Ȃ����o�D�Ɉ���Ă���Ċ��������낤�Ȃ��B�c�c�ȂǂƁA�ŋ߂ł͑��q�ƕ��e�̊W�ɂ��ڂ������Ă��܂��B�킪�؎��A10�N��́c�c�B �W��18���i�y�j���� �@���ɑ�䋣�n�܂Œ��~�ɁB�������܂ő����B 1500�A��������ŕ��w���u�ᑐ����v�B��k�푈����A�]�R�q�t�Ƃ��ĕs�݂̕��e�ɑ���A�}�[�`�Ƃ̎l�l�o�����O�A�W���[�A�x�X�A�G�C�~�[���������݈�Ă��B�T���ł͂Ȃ��Ƃ����邭���r�܂�����炷�Ƒ��̎p�B�~�肩���邳�܂��܂Ȏ������ޏ��������u���g���E�E�B�����v�i����j�Ɛ��������Ă����B���͒p�������Ȃ���A���̖����ǂ��Ƃ��Ȃ��B��������ď��߂đS�̑���͂���B �@��҂̃��C�[�U�E���C�E�I���R�b�g�̕��͏@���I�ɂ��Љ�I�ɂ��}�i�I�ȍl�����̎�����ł���A����A���c�u�C���e���A�q�b�s�[�A�x�W�^���A���v�B�����`�i���R��S���Ȃǂ̐_�I�T�O�͐l�Ԃ̍��ɓ��݂���ƍl����v�z�j��M�A������v�ɐg������鐶�U�𑗂����Ƃ����B�������A���̂悤�ȗ��z��`���A�����J�Љ�Ɏ���邱�Ƃ͕s�\�B �@�����Ȃ��u�˒n�Ɂu�t���[�g�����Y�v�Ƃ��������I�ȉƑ������̂𗧂��グ�A���Ɩ�A�p���A�ʎ��݂̂̐H���ň�����A�k��ɂ������݁A���v�ƂƂ��ɋx�ދ֗~�I�Ȑ�����������ꂽ�B�������A�v���C�o�V�[���Ȃ��A�j�����S�̐����͂P�N���������ɕ����Ƃ����B70�N��̓����L�b�h�u���U�[�Y�́u�������ڋ��a���v�̎����Ǝ��Ă��Ȃ����Ȃ����B �@���̕��e�̉e�������I���R�b�g���܂��A�����̎Q������������x�����X�g�ł���A�z�ꐧ�x�ɂ����̗����������B �@����́A��҂𓊉e�����W���[�̖ڂ�ʂ��āA�S�o���ƉƑ��̕��ꂪ�Ԃ���B�W���[���������������ߎq���͂�Ƃ������Z�B�x�X���̔��舤���܂��A���K�̏����̑��`���҂�����B���ɂ͎��܂�q�������̛g�����������A�q���̍��ɁA���̂悤�ȊȌ��Ő��V�ȕ����������̂͏����ɂ��Ȃ邾�낤�B�Ӗ��͂킩��Ȃ��Ă���ł����Ƃ����z���o�ɂȂ�B 1730�A�I���B15���̋x�e������łQ����30���B�ׂ�̍]�X����ƊJ���O�ɂ�����ׂ�B�u���c����A�ŋߌ��Ȃ��ˁv�ƁB �@1830�A��B�}���V�����̎�����̉�B�čՂ�̑ł����킹�B���A�����͏o�Ȃł��Ȃ��̂ŁA���X�Ɉ����グ�B �W��17���i���j���� �@�i�q�`�̓y���J�Ò��~�ő卬���B�n�C���t���G���U�ŋ��n�J�Â����~�ɂȂ�̂�36�N�Ԃ�B�I���Г������B�������H����1700�܂őҋ@�B �@�p�\�R���̃��j�^�[���e���r����ɗ��p���Ă������A�R���o�[�^�[��������Ă��܂��A��ނȂ��t���e���r�����ƂɁB15�C���`�łQ���T�O�O�O�~�B���łɁA���u���Ă����c�u�c���R�[�_�[���C���ɏo���B������͏C����Q��6400�~�B������Ȃ��Ɓc�c�B �W��16���i�j�ҏ��� �@40�x���ҏ��B�O�o����ƌ��t�������������B �@�ߌ�A�������Œ��Q�B �@�j��������̉�����ɓd�b�B�G���Ђ���̒��p�B �@1700�A����E�R�����X�ʼn��R�G�v�u�^���v�B�����ŁA���X�ׂ̗�̉�]���i�ցB�ď�̂��߂��A�߂��Ⴍ����V�����ɉ����������Ă��āA�|�̖��ȂǂȂ��B�����V�H�@�Ђǂ��X�B �@1730�A�a�J�B�g�l�u�łb�c���F�B �@1800�A���̃W�A���W�A���Ղ̋i���X�ցB���m���[������V�����X�Ɉߑւ��B �@1900�A�p���R����Łu�k�n�u�d30�@�u�����Q�v�B �@�{�c�c�q���o�ŁA�R�l�̋C�s�̍�Ƃ��������낵�B�j���̃J�b�v���R�g�̃I���j�o�X�h���}�B �@��g�ڂ͓��c���{�����肳�u�k�����̏��v�i�؍��E��j�B�Q�l�͕s���Y��Ђ̐�y��y�̊W�B��y���q�Ј��͎В��ƕs�ς��Ă���炵���B�Q�l����̔ނ�ɔ����ȕ��͋C���c�c�B �u�A���[���`���ɂāv�i�쁁�Ԗx��H�A��؍��H�{�����Ƃ��̂�j�͓c�ɂ̍��Z������̂Q����A�J���I�P�{�b�N�X�łQ�l����ɂȂ��������l���m��`�������́B�J�����}���ɂȂ閲�������Ă��̒����o�čs�����j�B�ނɂ��čs���Ȃ��������B10�N�̎��Ԃ����߂����Ƃ���j�Ə��B�₦�ԂȂ��~�葱���O�̉J�̂悤�ɁA�ʂꂽ�j�Ə��̐S�����B �u�\�y�̍s���v�i�쁁�c���F�T�A���������{�H��T��j�͂R�N�Ԃ̓������������A�����z���̍Œ��̂Q�l�B�^���X�̏��L�����߂����ď������y�����c�c�B���S�ɓ݊��Ȏl�\�j���H�ꂪ�▭�ɉ����āA�R��̒��ł����Ƃ��y�₩�ŃV���������b�B���������́A�u����ȗ��l��������c�c�v�Ǝv�킹�邿����҂�C���������ǁA���邭�y�������̎q���D���B �@�R��i�łP����45���B���ꂭ�炢�����傤�ǂ����B �@�A�Ԗx�A�c���[�[���̂R�l�͎������ł����������Ƃ��B�͂����A������ƂR�l�̌��Ɨ͗ʂ��o��������B���̎�̃I���j�o�X�ɂ��Ă͒������[�����Ă����B �@�i�q�o�R�ŋA��̓r�B��P���ԁB �W��15���i���j�ҏ� �@���A�F�����̉ƂɗV�тɍs�����؎������A���Ă���B���߂Ă̊O���B���w���ɂƂ��Ă͖`���̂ЂƂB �@���āA�����̒��w����͂ǂ��������낤�B �@���̈�ԌÂ����L�͂X�̎��̓��L�B�w�K�G�������掏�Łu�Í��œ��L���������v�Ƃ����L���Ɏh�����ꂽ�̂��A�Í��œ��L�������Ă���B�������ǂ���ƁA 10��17���A�J�B �ƂȂ��q�ɂ��āB������������l�B�G�N�g�[���E�}���[�B�t�����X�̏����ƁB1830�N5��20���A���Z�[�k���̃��E�u�[���ɐ��܂��B1907�N7��19���A�Z�[�k���t�H���g�l�[�E�X�[�E�{�A��79�Ŏ��B���̕����ǂ�Ő[�����������B 10���@���@������ǂ�Ŋ��������B �@���ꂶ��Ǐ��̊��z���H �@���w�Z�R�N���̍��B�P�T�ԂɂP�x�݂��o���̂���w�Z�̐}���ق��J���̂�҂����ꂸ�A�E�����ɍs���āA�S���̐����搶�i�����́A���������搶���Ǝv���Ă������ǁA��N�O������܂�50��̐搶�������I�j�ɃJ�M����Đ}�������J�������̂��B����Ȃɑ����̑����Ȃ��}���ق̕���{�́A�����ɂ��ׂēǂ�ł��܂����B�`�L���͍̂D������Ȃ��A�����A�M���V���_�b�Ȃǐ��E�e���̖��b�E���ꂪ��D���B�s��̂悤�ɑ傫�Ȑ}���ق��������Ȃ�A���̍��̎����Ȃ炫���Ɩ����ł��ʂ��ēǂݐs��������������Ȃ��B �@�s��̎q���������܂��������B�Ȋw�̎����Ŏg���n�t��t���X�R�A�r�[�J�[�A����Ȃ̂��Ă�f�p�[�g������łȂ��B����̎��A�g�ݗ��Ď��̓V�̖]�������悤�₭���������ɂ́A�O�r�����肵���B�w�Z�̗��Ȏ��ɂ���V�̖]�����̎O�r�����f���Ɍ��悤���^���ŁA���̏����ɂ���؍ނ̐�b�[���g���āB�����A�̂́A���m���Ȃ����A�����ō�����̂������B�����s�̃u�[�g�L�����v�ł͂Ȃ����A�u�����[�J�[�Ȃ�̗͑����������I�ɗ��s���������A�P���~�i�m������Ȓl�i�j�Ȃ�ĕ�����킯�͂Ȃ��A�Ɛ��[�v���g���ău�����[�J�[����B�L�k���Ȃ��Ă����C��������u�u�����[�J�[�v�ɂȂ�B���\�A�����^���ɂȂ����悤�ȋC�����邯�ǁc�c�B �@�d�Ԃ̒��ł��g�т�d�q�Q�[���ɖ����̍��̒��w�������B �@�����͂ǂ��������낤�B 12�i���w�U�N�j�̎��̓��L�B 7��30���i���j���� �@�ċx�݂ɓ������B�����̓R���u�̐ԗt��ŖZ���������B�ċx�݂ɓ���C�����������������ɐg������Ȃ������B�ċx�݂̏h��͌v��ʂ�i��ł���B �V��31���i���j���� �@�ߑO9�����ߌ�R���܂ŁZ�Z�Ńu���X�o���h�̍u�K��B�������Z�Z����A��A�����R���u�̐ԗt��B�ߌ�X���܂ŁB������11���܂ŕ��B 8���P���i�j�J �@�������܂��R���u�̐ԗt��B�R���܂łȂ̂ŁA����������Ȃ����Ƃɂ����B�������烉�W�I�̑��B�̑��I����A�~�x��̗��K�B �W���R���i�j���� �@����ŃR���u���I������̂ō����͂������ɗV�B���C�g�v���[�������ɂ݂�ȂŒ��w�Z�̃O���E���h�ɍs�����B11�����U�B �W���S���i���j���� �@���A���W�I�̑��̎��A�Z�Z�ƃP���J�������B���A�������ǂ��Ȃ����B���A���j���ɍs�����B�܂��j���Ȃ��l���Z�Z�������w�����Ă��ꂽ�B�������Ō��������炢�͂ł���悤�ɂȂ����B���̎��̊�т͖Y����Ȃ��B �W���X���i���j����̂������� �@�R���u�����B��A�R���u�̐ԗt����ꎞ�ԁB����������ɐg�����悤�Ǝv���B����14���ʼnċx�ݏI���B�v��I�ɐ����������낤�B�F����푈�������B12�`�����l���A�R��35������B �@���ł����������A�R���u���͊e�ƒ�̂P�N�̑傫�Ȏ������B���t�łȂ��Ă��A���ƌ�������A�Ă̓R���u���ɏo���B�R���u���͈�Ƒ��o�ōs���Ă̕������B�q���������܂��M�d�ȘJ���͂ɂȂ�B �@�����c���A���ƈꏏ�ɊC�ɏo�āA��`�����B���w����������`�����Ƃ����A�܂��A�̂��ė����R���u���C�݂̐Ώ�Ɋ����B���ꂪ�����Ɨ[���Ɏ������B������J��Ԃ��A������x�R���u������������A�R���u�̒[�ŐԂ��ϐF���Ă���u�ԗt�v��藎�Ƃ��̂��B���疇������R���u�̐ԗt��͏d�J���B �@����ȊO�ɂ��A���ۂɕ��e�����Ɖ��ɏo�āA�C�̎d������`�����Ƃ������B �@���̕��́A���t�ł͂Ȃ��̂Łu�`���b�J�v�ƌĂ��傫�ȑD�ł͂Ȃ��A�����ȁu��M�v�ŃR���u�������Ă����B����Ɉꏏ�ɏ�荞�݁A�u���₹�v�ƌĂ��D���������̂��B���̎w���ɏ]���đD�𑀂�A�R���u�̔ɖ���ꏊ�Ɉړ�����B�������ŁA�̂͂����܂����Ȃ������A�D���������͂炩�����B�Ƃ��ɂ̓Q�[�Q�[�f���Ȃ���K���ɟD�𑀂�B���S����ɋN���āA�T�����o�q�B�X���ɑ��ƒ�~�B���A�V�����Ɓu�����̓R���u�������~�B�悩�����v�ƐS��v�������̂��B�V������āA�����킹�́A�����ɔ��ƍ��́u�����v�ƌĂ������オ��B�S�[�T�C���͐Ԋ��B���ƒ�~�͍����B�������f�����D���D�c�̒����삯�ė���̂�����ƃz�b�Ƃ����B����ŗ��ɋA���c�c�ƁB���ɏオ���āA���𗁂тċ����ƃp����H�ׂĂ��ꂩ��w�Z�ցB�P�����̓r������B�����̃R���u���Ɛ��k�̒x���͌�����ψ���Ŗ��ɂȂ��Ă������c�c�B �@���Ƃقǂ��悤�Ɏq���̍��̉Ă̎v���o�̓R���u����F�B���ꂪ�c�ɂ𗣂��܂ő������B������R���u������ƁA���ł��R���u���̒����Ă��v���o���Ă��܂��A�Ȃ��C�����ɏP����B �@���v���A�������w�܂ł�����̂ɁA���e�͂ǂ�Ȃɋ�J�������낤�B���̍̂����R���u�ꖇ�ꖇ�������̍��̐����ɂȂ����Ă���̂��B�炢�Ƃ��ꂵ���Ƃ�������o�`��������B �@���~�����傤�ŏI���B����Ȃ��Ƃ��ӂƎv���Ă��܂����̂��A���~�ŋA���Ă��Ă��镃��̍������ɂ��邽�߂�������Ȃ��B �@���~�ɂ͋A��Ȃ����A��������������c�c�B �W��14���i�j���� �@�ҏ��B�p�\�R���ōŖk�[�̃��C�u�f��������ƁA�吨�̊ό��E�A�ȋq�B���S���h�������B �@1900�A�k��Z�B�V�A�^�[�P�O�P�O�Łu���Ƃ₩�ȏb�v�B�쓇�Y�O�̉f���i�������N�Y�����o�B�r�{���V�����l�B�J���O�ɗאȂ̎����p�㎁�Ƃ�����ׂ�B��e����B�o�g�ŁA�S�܂ŋ�B�ň������������͒��N�푈�̎��ɓ����ɏo�Ă����̂��Ƃ����B�F�X���ׂ����A�����Ƃ����c���͐��˂ɂ����Ȃ��A�Ƃ����b�B���Z����ɁA�u����w�v�����ԍ��Z�������������������n�̓V�ˁE��������B�u�쓇�Y�O����D���ŁA�ނ��S���Ȃ����Ƃ��A���V�ɍs�������čs�������āc�c�v�ƁB �@���́u���Ƃ₩�ȏb�v�͐쓇�Y�O�̑�\��B�o��l���݂͂ȏ����}����B���������Ƃ̈��l�ɂ��Ă��̂��蓖�ĂŗD��ȕ�炵�����Ă���v�w�B�������A�|�\�v���_�N�V�����ɋ߂鑧�q�ɉ��̂����A���̃J�l���������グ�Ă���B�|�\�v���̔��l�o�����s�����A�݂�Ȃ��K�ɌQ���鈫�}�B���̈��}�B�̉E���������R�~�J���ɁA�V�j�J���ɕ`�����̂͐쓇�Y�O�̉f��B �@�������A����͎S�邽����́B����̂��Ȃ�����1960�N��̒c�n�̈ꎺ�̃Z�b�g���g�܂�A���̃Z�b�g�ɔ������ăZ���t�ɃG�R�[��������A�قƂ�Ǖ��C��̎ŋ��B�������̃g�[���𗎂Ƃ��ƁA�v�����v�^�[�̐��ƕ����ԈႦ�����Ȃ��炢�B�Z���t���������Ȃ��Ƃ����̂͒v���I�B����ɗւ������āA���o�����B�e���|�͒x���A�ԉ��т��Ă���A���Y�����Ȃ��B�قƂ�Ǖ���Ƃ��Đ������Ȃ��B�����N�Y�̉��o�͉��x�����Ă��邪�A���������B�ԉ��т��Ă��ĕ���ɖ��������Ȃ��B��ˏo�g�̐^�Ղ��i��Ђ̌o���S���j�͂��̂܂�܁A��˂̒j�������B��萺�������ꂵ���B���ꂼ��̉��Z���o���o���B�B��A���l���̎R�c�܂�₾�������������Ƃ������Z�ŏ���~���Ă���B �@�킯�̂킩��Ȃ��Ó]��і��̏グ�������킸��킵���B�q�Ȃ͏I�n�Â܂�Ԃ�A���܂�A�������˓I�ɏ����R��邾���B�Ȃ�Ƃ����ᒲ�ȕ���B2100�I���B��������Q���ԁB 2130�A��B�����A�c�ɂ͂��~�̓��킢���c���Ă��邾�낤�B �@ �W��13���i���j���� �@�O�ɏo��ƔM�˕a�ɂȂ肻���ȏ����B �@1600�A�S�e�ŏd�唭�\�B����Ă������Ƃ��B���̓�������̂͊o�債�Ă������c�c�B �@1700�A�r�܁B�u�E�C���U�[�v�œ؎��̗~�������Ă������l�b�N�X�̃e�j�X�L���b�v���w���B�ĊO�A�e�j�X�X�Ƃ����̂̓V���b�v�ɒu���ĂȂ����̂��B�s���̗L���X�܂�T���Ă悤�₭�������̂�����B�u�ɂ��Ȃ��āA���ɂȂ�܂��B���~�����Ȃ̂Ń��[�J�[�͋x�݁B20���߂��ɂ́c�c�v�Ƃ̕ԓ����������������B �@1800�A��X�B�u��X�؈��v�ō��Z������́u������v�B������́u������v�̘b�B�g�D�͂ǂ��ł���������B�����̓o�g���^�b�`���Ȃ���B��Ђł̓o�g����n���ق������A������ł̓o�g���������H �@�Q�s���C���Ȃ̂ŁA���߂ɑގU�������������A����2130�܂ŁB�o�e�o�e�ŋA��B2400�A�Q�B �@�������A�܂����Ă��A�����ɋ����Z�~�̐��Ŗڂ��o�߂�B�}���V�����̕ǂ�т̖̎}�Ɗ��Ⴂ����Z�~�∣��B �@�x�ؓލ]�����Ƀ����[���B �W��12���i���j���� �@0900�`1245�A�[���m�ÁB�������ɂ��~�O�Ƃ����Đl���͏��Ȃ��B�q���͂P�l�����B��ԑ����̂͑s�N�g�̂T�l�B�����J���Ă����͓��炸�B�����Ƃ̓����B �@1300�A�A��B�����B �@�c�ɂɋA�����F�l����̎ʃ��[���ɖ]���̔O���B�������炨�~�B��N�Ɉ�x�̃n���̓��B���A�����ɋ����킹�Ȃ������B �@ �@�e���r��100�b�̃��[���[���\���ǂ����A�Ƃ����q���̖�����������ԑg���Ƒ��Ō���B�ǂ����ĊO���܂ōs���Ď�������́H�@�Ƃ����b�ɂȂ������A�u100�b�̒f�R�����{�ɂ͂Ȃ�����v�ƁA�݂�Ȃ������Ă邻����A�ӂƁA�����̓����ƌ��킷��k�̂���ŁA�u�X�^�b�t���C�O���s���������炾��v�ƌ������Ƃ���A�؎����L�b�ƂȂ��āu�������c�c�v�ƈꌾ�B�q���̖���������ԑg����M�����Ǝ�����炵���B�I�g�i�̍l���͉����c�c���B���Q�̓؎��̏��^���ɋ����Ɠ����Ɋ������Ȃ�B���тȂǂ��ł������B����ȏ��ȋC���������������Ă����B �W��11���i�y�j���� �@����������s���̊e�w�ɏ������A�n�����Ă��܂��A�C�����Ƃ͂邩�ɃI�[�o�[�����B�����Ԃ��ď�芷������A���ǁA���߂ɉƂ��o�Ă��Ӗ��Ȃ��B0710�o�ЁB 1400�A�x�j�T���E�s�b�g�ŃV���N���i�C�Y�E�v���f���[�X�u���������v�i��E���o���v���Č����Y�j�B�^�C�g���͒J��r���Y�̓���������̈��p�B������̂߂����^�C�g�������A���N��������̒��ł����w�̍D����B �@�ދ��ȓ��킩�甲���������ƁA�Ƒ��̔���������A���l�Ƃ��ʂ�A�C�O���������u�����T���v�̐N�B�����A�ނ����������̂͏e�e��ь��������̐�n�B�킯���킩�炸���܂悤�ނ��o��̂́c�c�B �@��l�̐N�̐S�̗���ʂ��āA�u����v���f���o���i���Z���X�ŃV�j�J���ȕ���B�p�t�H�[�}���X��́A�_���X�������ꂽ�u�E�E����v�B��ǂ݂Ȃ����o�A���҂̉��Z�A����قǃ��x���̍�������͋v���Ԃ�B��c�G���́u�a�����v�̏���s���Ă�B�v���Č����Y�͊��̉��o�Ƃ炵�����A���O���̂͏��߂āB�����E�͍L���B����ȉ��o�Ƃ������Ƃ́B �@���Ȃ݂ɒJ��r���Y�̎��͈ȉ��̒ʂ�B �������� �@�J��r���Y �哝�̂������������Ă� �����������Ȃ���l���Ă��� �푈�Ȃ������Ȃ��� �Ζ��������Ղ肠�肳������� �e�����X�g�������������Ă� �����������Ȃ���l���Ă��� �����Ȃ������Ȃ��� ���l�c���Ď��ɂ����Ȃ����� ��������������������Ă� �����������Ȃ���l���Ă��� �E���̂��Ă���Ȃ��� �E�����̂͂����Ƃ��₾�� �j�̎q�������������Ă� �����������Ȃ���l���Ă��� �}�V���K���������Ă݂����� �����ƋC�������������肷�邩�� ���폤�l�������������Ă� �����������Ȃ���l���Ă��� �e���Ȃ���Ε��a�͎��� �����Ȃ���Ύ��R�������� ���Ŗ�nj������������Ă� �����������Ȃ���l���Ă��� �G�����Ȃ���□�������Ȃ� �����̖����Ă��邾�� 1545�I���B�P����45���B���̉����E�ł́u�Z���㉉���ԁv�B�������ϋq�Ɏ��������̎v����`����ɂ͏\���Ȏ��ԂȂ̂��B �@�n���S�Ŋ�{�����H�t���B���X��500�~�r�f�I���S�{�B�u�܂ڂ낵�T��v�̂c�u�c�P���Q���A�u����\�O��v�A�Ζ��q�剉�̉�Ɠ�v���q�E������剉�̉���B���h�o�V�łc�u�c�P�[�X�w���B���ς�炸�������Ԃ��X���B���ʃe���r����l�������āc�c�B 1800�A�A��B �W��10���i���j���� �@1540�A�V�h�E�̕��꒬�B�R�}����Łu���������v�㉉���̊Ŕ����ڂɁA�u�g�����X�t�H�[�}�[�v���ς邽�߉f��قցB�u���������v�͏��Ɖ����ɐc���肳�ꂽ�u���c���E���v�̊۔��ۈ�Y�{�،��`���r�̋r�{�������r�ꂪ���o���Ă���B�]�����悭�Ȃ��̂̓A�C�h�����Y������剉�ɂ����C�[�W�[�������邾�낤���A�����l�C���o��ƃW���j�[�Y�������⏤�Ɖ����p�ɏ����c�̍˔\��c���肷�鐧���Ђ̐ӔC������B����������䂪�o��܂ő҂Ă����̂ɁA���������犠�����ă_���ɂ���B �u�g�����X�t�H�[�}�[�v�͂u�e�w���������Ƃ��������̉f��B�\�f�Ȃ��Ō������A�����A�j�������}���K�Ȃ̂ŁA���ꂠ��c�c�Ƃ����W�J�B�������A�f��̓��B���s�������������B�������B 1730�A�f��ق��o�āA�̕��꒬����V��v�ە��ʂցB�����ɗ���35�N�A�V�h����V��v�ۂ܂ŕ������̂͏��߂āB����Ȃɋ߂��Ƃ́B�����u�_�v���ړ����邾��������A�u�ʁv���킩��Ȃ��B �@�V��v�ۂ̗��ʂ��������Ƃ͂߂����ɂȂ��̂ŁA�������u�ٍ��v�ɂȂ��Ă���̂������B�n���O������������A�ˁA�Ă��ՈŎs�̂悤�ȁu������ځv�܂ł���B�G�l���M�b�V���Ȓ��B �@1830�A���C�u�n�E�X�u�maked �koft�v�B1900����PANTA�Ƌe�r��Ȃ̃��j�b�g�u���v�̃��C�u�B���A���o���u�I���[�u�̎��̉��Łv�̔������L�O���Ẵc�A�[�r��B�A���o���͓����S�u�����̏d�M�[�q��PANATA�̌𗬂��琶�܂ꂽ���́B�d�M�[�q�̏����������삵�APANTA���̂��B�u��ւ̉ԑ��v�u���C���̃o���[�h�@�p�ꎌ�v�͏d�M���C���̂��Ă���B �@1900���炾���A�I�[���X�^���f�B���O���낤�Ǝv����30���O�ɉ��ɓ���Ƃ��łɑ吨�̊ϋq�B�R���̂Q���֎q�ȂŁA���łɖ��ȁB�ォ�痈�����q����͈֎q�̌��ŃX�^���f�B���O�B�������̐X����ɃT���v���Ղƃp���t���b�g���B 1900�APANTA�o��B�M�v�X�A���t��p�B���É������ŁA�A���R�[���̍ہA�Èł̒��A�K�i���瑫�݊O�����Ƃ������R�����ɉ�ꂩ������B �@�M�^�[�Q�{�̃A�R�[�X�e�B�b�N��̃��C�u�����A�c�A�[���o�āA�Q�l�̑����s�b�^���B�܂��̓G���L�M�^�[������āuP.I.S.S.�v����B�f���I�Ƃ͎v���Ȃ����́B�u�v���n����̎莆�v�u�l�t�[�h�̕��v�ȂNj����������ĂQ����10�������Ղ�̃��C�u�B�A���R�[���͏��t����l�����āu�o�[�`�����v�ŁB���R�C�i���́u����̓T�[�J�X�̔w���ɏ���āv�ȂǁB �@����̃A���o���͂��t�H�[�N�A���邢�̓t�H�[�N�E���b�N���̉̂������B�u�莆�v�̃����f�B�[���C���A���Y���ȂǁA�ɐ����O�́u22�̕ʂ�v���B���ҁu���C���̃o���[�h�v�͒��������\���B �u���b�N�͓{�肾�I�v���v���o�������̂́u�����̃��X�^�[�t�@�v�B�C���N�푈�̎��A�t�Z�C���̂Q�l�̑��q�A�E�_�C���A�N�T�C�����ċ���ɋ}�P����A�ˎE���ꂽ���A���̂Ƃ��A�{�f�B�[�K�[�h�Ƌ��ɂQ�l�̂��ɂ����̂��N�T�C���̑��q��14�̃��X�^�[�t�@�B�R�l���ˎE���ꂽ����P���Ԃɂ킽���ĕĕ��Əe������J��L�����̂��B�u�ے�ł��m��ł��Ȃ��A14�̏��N����������l�ŃA�����J�ƑΛ����������B�����m���Ăق����v�Ƃo�`�m�s�`�B���͎����m��Ȃ������B�䂪�؎��Ɠ����B�������A�؎����c�c�Ǝv���ƁA�@������悤�Ȉ�����܂�̂��Ȃ���A�ړ����M���Ȃ�B �@2210�A�������ɂQ���Ԉȏ�̃X�^���f�B���O�ō����c�c�B�y���ɍs���Ăo�`�m�s�`�Ɉ��A�B�����A��s�@�Ō����n�̐X�ɍs���Ƃ����B�M�v�X�͍��������ς��B23������̌��I�����͑�{�����������Ă̏o���B�u���T����͎ŋ��̌m�ÂɏW���ł���v�Ƃ��B �@2330�A��B �W���X���i�j���� �@�l�b�g�Ŕ������u���k�Ɠs��v���͂��B1962�N�̏o�ŁB���҂͌ː�K�v�B�������w�̌ː쎁������Ȗ{���o���Ă����Ƃ́B�́A�ǂ����ŕ������悤�ȋL�������邪�A��������ɂ����̂͏��߂āB�{�B�̖k�[�Ɠ�[�̖��̋L�^�B �@���ܑ��̓��A�����̖��ƁB�����������i�B�q���̍��̎ʐ^�͂����������l�����S�B���̗l�q���ʂ����ʐ^�͂��܂茩�����Ƃ��Ȃ��B���Ԃ��щz���A�c�N���̕��i�ɓ��荞�ށB �W���W���i���j���� �@����o�������[���ɂx�ؓލ]���烊���[���B�����A�����J�ɋA���Ă���Ƃ̂��ƁB �@�I�[�N�V�����ŗ��D�����u���k�����������v�㉺�����͂��B�������c�c��Ԓ��j�͍ڂ��ĂȂ��Ȃ��B�Ȃ����H�@�����ƓǂނƋC�ɂȂ���B�ꎞ�A��Z���E�ڈΉ��l���ɑ��Ė��˂��}�{����^���Ă������A���ꂪ��������A���̒��̈�l�͂n�ˑ��ɈڏZ�����Ƃ������Ă���B���̐l���́u�����v�Ə̂����Ƃ��B��c�Ɂu�����v�̖��O�͂��邪�A����͂����Ԏ���������Ă���B�����ِl���낤���c�c�B�Õ����ɐV�������������邩������Ȃ��B �@�g�i���S���̉f����{����B�u���ł������v�u�K���X�̒��̏����v�B �u���ł������v�͂���ȉf��B �@��l���͒莞�����Z�ɒʂ��Ō�w�E�Ђ���i�g�i���S�������z�̂悤�ɖ��邭�͂�Ƃ��������ň��̃s�J�����j�ƁA�ޏ��Ɏv������Q�l�̐N�Ƃ̗����厲�ɁA�n�����̒��ł��K���ɐ�����t�Q����`�������́B�Ђ���ɗ������l�́A�����莞�����Z�ɒʂ������i�l�c���v�j�B���͏����A���E�����e�ƒ�̂R�l��炵�B�n�������甲���o�����ƁA���͒��H��œ����A��͒莞�����Z�ŕ��B���Ƃ�����傫�ȕ��Y��Ђɓ���̂����B������l�͒������g���b�N�^�]��̗����i���K�v�j�B���R�o������Ђ���Ɉ�ڂڂ�B�����Ɨ��̏ⓖ�Ă������邱�ƂɂȂ�B �@�Ə����A�Ȃ��ʂ̗����f�悩�Ǝv���̂����A�f�悪����ꂽ�̂�1963�N�B�܂��A��オ�F�Z���c�鎞��B����ɁA��㖯���`���t��t���n�߂鍠�ł�����B���C�o���Q�l���u����I�Ɂ������ɂ���������Ȃ����B�o�������͂�߂悤���v�ƌ݂���������B�������A���x�o�ϐ����O�A�܂��܂������͕n�����B�r��̓y��t�߂ɂ͒������������сA���i�ɍH��X�̉��B�i���͌��R�Ƒ��݂���B �@�f��̖`���͍r��̕n����������w�i�ɁA�͐�~�ŃS���t�ɋ����钆�E�㗬�K���̐l�����̎p�B���̖`���̕n�x�̍��̃V���b�g���f��̃e�[�}�����킵�Ă���B �@���тł��f�s�ł��Ȃ����͂Ȃ��̂ɁA���Ђ̎����ɗ����Ă��܂��������̋C�������ق��A�S�C���t����ЂƊ|�������ƁA��Б��̓����́u�莞���̐��k�͎Љ�Y�����Ă��邩��ˁB�����͂���ς�܂�����Ȑ��k����肽����ł���v�Ƃ̓����B�u�ꑫ��ɎЉ�ɏo�āA�d���ł��܂�Ȃ���A�^�ʖڂɕw�ɗ�ނ��Ɓv���A��Ƃ̘_���ł́A�u���ꂪ���Ă���A�Љ�Y�����Ă���B����Ȑl�Ԃɑg���^���ł����ꂿ�።��Ɓv�Ȃ�̂��B �@���P�ɂȂ��Đ��Ԃޏ����B�R�l�̗F��͂ǂ��Ȃ�̂��c�c�B �@���̎����̓����f��͂܂�������㖯���`��������悤�Ƃ����ӗ~�ɂ��ӂ�Ă����B�Ђ���̗F�l�i�����q�b�q�j���A�����Ȃ���w�Z�ɒʂ��Ă��邪�A�x�a�ɖ`����A�g�̕s�^��Q���B�n���ƎЉ���B�����āA��������z���ĐV�����Љ��z�����Ƃ�����]�B�Ȃ�ƁA�����t�f��͊K�������f�悾�����̂��B �@�莞���̎��Ƃ��I���ĉ��Z���鐶�k�������A�蓹�ʼn̂��u�������v�B �@�q���̍����玨�ɐe����ł������K�v�Ƌg�i���S���̂��̉̂����͂���ȏ�ʂŎg���Ă����̂��ƋC�Â�����A���������ς��ɂȂ�B �u�k�������ʂ��@���������@�S�ЂƂŁ@�g�����Ȃ�@���炩�ɍ炢���@���ȉԂ��@�݂ǂ�̔��Ɂ@�������č������@�����@�k���̒��Ɂ@��������t���v �@�n��������Ȏ�҂����̎Љ�̕��ɗ�����������]�̉̂������Ƃ́B �@����ɂ��Ă��A�g�i���S���̉��Ȃ��ƁB �@1945�N���܂�̋g�i���S��������㖯���`�̑̌��҂��Ƃ������ƂɋC�Â������B �@�g�i���S���̎p���͈�т��Ă���B�����u���邱�Ƃ͂Ȃ��B�������̘N�ǂ𑱂��A����E���j�^�������C�t���[�N�Ƃ���g�i���S���B���̒ꗬ�ɂ́u�L���[�|���̂��钬�v���瑱���u��㖯���`�̎q�v�����Â��Ă���B�������\�N���͂����ċC�ɂ����߂Ă��Ȃ��������A�Ȃ�Ƌg�i���S���͑f���炵�����D�Ȃ̂��B �@�u�K���X�̒��̏����v�́A��w�����̖��i���e�͐펀���A�ꂪ�č��j�ƁA�n�����E�H�i�l�c���v�j�Ƃ̏�����`�������̂ŁA��l�̕Ό��Ɩ������������̂܂܂̎���I����B15�̋g�i���S���̂Ȃ�Ɖ��Ȃ��ƁB����Ȃɏ������C�ȍ��Z����21���I�ɂ͐�ł��āA���Ȃ��B �W���V���i�j���� �@�^�钆�Q���߂��܂ŃZ�~�̑升���B�Z�~���钆�܂Ŗ��Ƃ����ُ͈̂�ł͂Ȃ��̂��H �@1500�A�V�h�B�X�y�[�X�[���Łu�P���R�[�S���n���j���E�~�V���[�v�B�얾�ށA��t�ށA����䂸�G�A�`�݂��فA�������q�A�쑺����ȂƂ������A�C�h�������i�S�R�m��Ȃ����ǁj�������p�ŕ���̃v�[���ɔ�э��ށc�c�Ƃ��B�r�{�E���o�͐����u�B�n�C���O�W�[�U�X�̏�A�ō��͓����d�C�̎�ɁB�Ȃɂ��ʔ������Ƃ�����Ă���邾�낤�Ɗ��҂��ό��B�������c�c�B�w�|��ȉ��Ƃ����\��������قǎ�����������Ȃ��B�A�C�h�������܂��g���Ă���Ȃ�ɖ�����̂̓��T�[���Έ䂪���ӂ����A�����ɂ͕З��Ȃ��B�_���_���Ɠo��l���̃Z���t�����ꗬ���ɂȂ邾���B�r�{�\���[���B���Ƃ����Ė��҂̓��ӑ����̃A�h���u������킯�ł��Ȃ��B�q�Ȃ̓V�[���ƐÂ܂�Ԃ����܂܁B�킸���ɏ��ь��ꂪ������邾���B���������B�����|�l���O�X�e�[�W�ɗ�������悤�Ȃ��̂ŁA�����d�C�ƃA�C�h���V���[�͐��Ɩ��B����Ȃɒᒲ�őދ��Ȃ̂ɁA�x�e15���łQ����35���B��������B�q�̓A�C�h���I�^�N�ƌ|�\�v���̃}�l�W���[��W�ҁA�����ďo���҂̉Ƒ��B�얾�ނ��g�b�v�A�C�h���̂悤�����A��t�ނ̕������D�Ƃ��Ē������������B 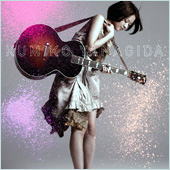 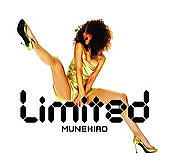 ����^���[���R�[�h�ŁA���c�v���q�u�t�̋P���v�A�������Q�G�{�[�J���X�g�l�t�m�d�g�h�q�n�́u�k�h�l�h�s�d�c�v�B�X�^���v�J�[�h���o������u�S���O�Ɋ�������Ă܂��v���ƁB�V���b�N�B����^���[�Ŕ����ĂȂ��������H �@1900�A�a�J�B�V�A�^�[�R�N�[���Œn���S�[�W���Y�u�����₫�F�̂��̓������v�i��E���o�E�o�����ݒJ�ܘN�j�B���Ȃ̂��ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��A䩔��Ƃ�����Ԃœ�l�̒j���o��B�������A�ނ�͎��������������̘b�����n�߂�B��l�̈�������l�̏��B�S�l�͐l���̒��Ō������Ă����c�c�B �@�킩��₷���G���^�[�e�C�������g��ڎw���Ă����n���S�[�W���X�ɂ��ẮA�����������������A���Ԃ����҂�������A�\�����d�w�I�ł��܂܂łɂȂ��`���B�������A�́E�_���X�E�E�w�Ȃǂ���g�����G���^�[�e�C�������g���͏\���B���ɍׂ����Ƃ���܂Ōv�Z���A�������Ă���r�{�B�ݒJ�ܘN�̃R���f�B�[�Z���X�͂��Ȃ�Ȃ��́B�k����������䏉�ɂ��Ă͗����������ŋ��B �@�������͎̂R���і���̉̂̂��܂����ƁB������M���M���̃��b�N�{�[�J���B���o���h���o�b�N�ɃZ�N�V�[�ɗ͋����̂��グ��̂�����A����������B����ȍ˔\���������Ƃ͒m��Ȃ������B�{�����ʂ͏o�Y�����̏o���B�R���f�B�[�����[�t�Ƃ��āA�ݒJ�Ɍނ����Z�B��D���ȉ���G�Ƃr�g�t�m�̃_���X�V�[���͑̂��k����قǁB�������̓_���X�E�̎��͔h���m�B�������ƊݒJ�̃_���X�B���ꂪ43�Ƃ͎v���Ȃ��̂̐�B���₠�A��������������Ă�������B�����G���^�[�e�C�������g�ł��E�~�V���[�Ƃ͓V�ƒn�̊J���B2105�I���B�㉉���Ԃ����傤�ǂ����B 2230�A��B�ǂ����f�����s���B�d���Ȃ��A�V�����f����ݒu�B �W���U���i���j���� �@���ɑN���Ȗ������Ă����B�ǂ����x�O�̉w�B�A��̓d�Ԃ��Ȃ��B���āA�ǂ����悤���A������������\���c�c�B�����A���Ė��肽���B�����c�c�B���̒��Łu�������Ɩ����������v�Ǝv���Ă���B����Ȃ͂�����Ƃ����u�Ӓ��̖��v�͏��߂āB �S���ɖS���Ȃ�����ƁA�J�[�g�E���H�l�K�b�g�̈��G�b�Z�C�ɂ���Ȉ�߂�����B �u�P���A���ɏ��ĂȂ����Ƃ��Ȃ��B�����͑S�đg�D�̖͂�肾�B�����A�V�g�Ƃ����悤�Ȃ��̂����݂���Ȃ�A���߂ă}�t�B�A���x�̑g�D�͂����K�v�͂���v �u���܁A���̒n����ł����Ƃ��傫�Ȍ��͂������Ă���̂̓u�b�V�����A�сA�f�B�b�N�i�f�B�b�N�E�`�F�C�j�[�j���j���A�R�����i�R�����E�p�E�G���j���K�̂R�l���B�������₾�Ƃ����āA����Ȑ��E�Ő����邱�Ƃقǂ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v �u�V�g���}�t�B�A���݂̑g�D�͂�Έ��ɏ��ĂȂ����Ȃ��v�Ƃ������t�͐؎����B �@���͎��Ȃ̗��Q�̂��߂ɁA�����ɑg�D�����A��剻����B�������A�P���V�g�͂ǂ����B�Ȃ̐������ɂ������A�����̓�������B���̌��ʁA�e���j������ł���B�������u���@��X���v�݂̂���v�_�ɁA���ׂẮu�V�g�v�������ł��Ȃ����̂��B �@���{�����߂Ȃ��͉̂E�����͂́u���{���g���ĂX�������𐬗�������v�Ƃ̈��͂����邩�炾�Ƃ����B�قƂ�Nj��C�̗̈�ɋ߂Â��Ă��鑀��l�`�̋��菊�͋ɉE���͂̂݁B���̗v���ɉ�����̂������̎g���ƐM������ł���B������㉟������u��v���ݐM��̖��B���j�̗��ɂ����߂�鳖��鲂����ɂ�鐭�ǂ̒�c�c�Ȃ�Ƃ����s�K�B �@1500�A���h�BI�a�@�Ō������ʁB�u�ǐ��ł��v�Ƃ̂��ƂŃz�b�Ƃ���B�f�@�҂������Ă���Q���ԂŁu�����g��v��Ǘ��B��ؗ��́u�����ꂶ���v���霂Ƃ�����A���N�������w�̌���B�ɂ����B���ꂪ�������P���ŏI������Ƃ́B �@1900�A��B���A�؎��̎��]�Ԃ̌�փ^�C�����E���B�傫�Ȏ��̂ɂȂ�Ȃ��������炢���悤�Ȃ��́A�킸���Q�J���łQ��ڂƂ́B����͏d��Ȍ��ׂł͂Ȃ����B �u���Č�������v����̃u���O������p�B ���{���푈�Ɋ������܂ꂽ��A�푈�ɍs�����H���� �s�� �ǂ����Ăł����H�������{����邽�߁B �����̑�Ȑl���푈�ɍs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�����A�ǂ����܂����H ��l�j�ŁA�������F��A�������s���B(���P �j �F�{��) ���푈�ɍs���� �u�푈�ɂ͍s���Ȃ��v�Ƃ����ӌ������\�����悤�ł����A���͂�����������s����������܂���B ������邽�߁A��Ȑl����邽�߁A�܂����R�͕�����܂��A�s���ƂȂ�����s���ł��傤�ˁB �����č��ɂ��Ă��A���ɂ��Ă��A�ǂ����ɂ���ꂵ�ނ��Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��̂����B �푈���ǂ�Ȃ��̂����A�l������{��ǂ肷������A���ۍs����������ق����悭������悤�Ɏv���܂��H (���R �� �_�ސ쌧) 60�N�Ԓ� �@���Ԑl���P�����Ȃ��O�[�^���������Ă��鍑�푈���Ԍo�����Ă��Ȃ����o�������l�͘V�l�̍��ł��B����ɐ�͂����鎖���ł��Ȃ������̓��{���������̍��͂Ȃ��ł��A�P�������Ă��Ȃ�����e���낭�ɂ��ĂȂ��B�푈���|��������ēG�O���S���镺�m������������͖̂ڂɌ����Ă��܂��B�U�ߍ��܂�Ă����������͂Ȃ��ł�(�R�̃W���E�z�E�𗬂��ꑱ���č��܂��Ƃ������킢�����ȍ��ł�����܂���) �@�푈�ɍs�������Č���ꂽ��s���܂� �����c�����S�ł��傤�� ���̍����D���ł���Q�����E���ł��̍�������Ă��ꂽ�p�Y���������̍��������ł� �푈�͂����Ȃ����Ă������Ǐ��F�͌������A�����͐₦������ ����ɂX��������(�������������ł����c)���m�ȕ��������ł� �O�ɂ̓f�������Ă�l���܂������H ������Ƃ͒��ׂĂ��炢���ė~�������̂ł��c ����ȍU�ߍ��܂��悤�Ȃ��Ƃ���킯���Ȃ�����Ȃ��ł��� (���Q �j ���m��) �����푈�Ɋ������܂ꂽ��A���͐푈�ɍs���h�ł��B �݂Ȃ���̈ӌ���ǂ�ł��āu�s�������Ȃ��v���ĕ�����R����ȁA�Ƃ�����ۂł����B �������݂�Ȏ��ɂ����͂Ȃ����낤���A�������Ăł���Ύ��ɂ����͂���܂���B���R�ł���ˁB �ł����͂��̍�����肽���A�Ƃ��v����ł��B �u�푈�ɂ͍s�������Ȃ��B���ɂ����Ȃ��B�v�ƌ����l�B����邽�߂ɁB��邽�߂ɁA�킢�܂��B�����g�����̐��E�Ő����Ă��čK�����Ǝv������A���̐������ɂ��Ă���l�B�̍K���������Ȃ��Ǝv���܂��B ���̑��ɋ���l���A�ꐶ����Ƃ̂Ȃ��l���������B ���ׂ̈ɑ����̐l�̖���D���͈̂���������ǁE�E�E ����ł��U�߂���A��邽�߂ɒ�R�͂��܂��B ������u�푈�ɍs�������Ȃ��B���ɂ����Ȃ��B�v���Č����l�����邱�Ƃ͑�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B����͂܂�u���̐��E�Ő����Ă������B�v���Ă��Ƃł��傤�H ���������l����邽�߂ɐ키�l�͂���Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ����͂����ł��B (���R �� �����s) �����������{���푈�Ɋ������܂ꂽ��A�푈�ɍs���H �o����s�������Ȃ��ł��B ���ǁA����ύs�����Ȃ��B�B�B ��Ȑl����邽�߂Ȃ�s�������ł��B(���Q �� ��ʌ�) �ȏ�̏������݂�NHK�u�y�j�������݂s�u�v����̈��p�B �@���̏����w���������܂Łu�����ҁv�ɐ��]����Ă���Ƃ̓I�h���L��ʂ�z���Ĕw�������Ȃ�B�����{�@���������Ȃ��Ă��A�������̍��̋���͏\����O�ɉ�A���Ă����̂��B �B �W���T���i���j���� �@0900�`1200�A�[���m�ÁB��ʐ^����̖�����쐬�B�z�z�B �@���̏����̂��߂��Q���҂͏\���l�B�q���Ƒs�N���قƂ�ǁB�₦��������⋋���Ȃ��Ɠ|�ꂻ���B�Q���b�g���������B���ꂪ���ׂĊ��ɁB�������ɍŌ�͔��ă{���{���B 1300�A�A��Ē��H�̌�A�x�b�h�ɉ��ɂȂ��n���B�ڂ��o�߂��1830�B������I����Ă��܂��B �@���傤�AI���搶���炢���������A�u�[���V���v�A�j�䐳�����u�V��蓹���́v�A���i�͒��u�����g��v�������ƂȂ��߂�B�u�V��蓹���́v�͂U�O�N��ɋ��E��Ȋ����������B���̐��藧������A���̐��_�A���a�ւ̊ȂǁA�P�Ȃ���Z�p���͂ł͂Ȃ��A�j�䐳�����̐l�Ԃ̑傫�������������閼���B�������Ȃ�A�����E���ς�������낤�ɁB�u�����g��v�́A���̏j�䐳�����̔����������ɂ������́B�Ȃ����P���ŗ��������ɂȂ������A���ɒɉ��ȕ��������B���������Ăق��������B��쎁�͐���N�͂̒�q�ɓ�������Ƃ��B �@����͂����Ö{�u�q���̉Ȋw�v�B1957�N�̏����w���̉Ȋw�ɑ���m���~�̍����ɋ��Q����B���W�I�̑g�ݗ��Ă���A���܂��܂ȓd�q�@��̑g�ݗ��Đ}�B���������Ƌ����B �@��A�^�悵�Ă�����NHK�́u�V�}�`�x���v������B�Z���]���������̌�ҁB���݂��������k�������Đg����ɑߕ߂��ꂽ�������t�B���[�̊w�Z���j�\�������i�C���^�[�l�b�g�J�t�F���瑼�l�̃A�h���X�Ŕ��M����Ƃ������肦�Ȃ��ݒ�j�ɂ��Ă����A���e�B�[�[�������A�����L�[�搶�����������������Ă��ꂽ�Z���̓]�����ŁA���k�������Ƃ�����d�\�����}���I�B�ٔ����̖@��̐����O�L���܂ŕ������Ă��āA������Đ��k�����S����Ƃ����̂��u�Ȃ��Ȃ��v�B����ɂ����A�Z���]���͎��̂ł����Ď�������Ȃ��B�O��̃z�[�����X���Q���������������ǁA�u���̒��ōl�����r�{�v�ɉ߂��Ȃ��B���R���q�B����ȂɎ����グ�Ă����Ƃł͂Ȃ���Ȃ��́B����ȒP���ȁu�q���[�}�j�Y���h���}�v�A�̂�NHK�h���}�Ȃ�O���B���ꂾ���A�r�{�Ƃ̎��������Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B�u�j�����̗��H�v�̓y�j�h���}�����������B �W���S���i�y�j���� �@�I����ЂŎd���B 1830�A���c�J�p�u���b�N�V�A�^�[�B���܂��{SIS�J���p�j�[�u���}���X�v�B �@���Ђ����̐V�삪�����������}�����̂͊�ՓI�B�q�Ȃ͓��R�Ȃ��疞�ȁB�ЂƂu�������ׂ̐Ȃ̘V�a�m�v�ȂɈ��Ђ������b�������Ă���̂ŁA�N���Ǝv�������]���O�Y���B�ŋ��̐Ȃő�]��������̂͒������B�ڂ���ׂ͗ɏ������B �@�`�F�[�z�t���߂��鈤�Ɛl���̕���B�`�F�[�z�t���́A�N��ƂɈ��F�Y�A�������v�A�i�c�����A�؏ꏟ�Ȃ��B���}�����͏������q�A�ȂƂȂ��l���I���K���|���̂Ԃ��B�܂��A�����̂��܂��܂Ȗ���o�D��������ʼn�����B�Q���x�e15���łR����10���B �u���̍�i���������Ȏ����ɂ����̂́A�X�^�j�t���t�X�L�[�A�N�̂������v �I���A�`�F�[�z�t�������Z���t�B�u�̂���x�肠��y�Ƃ���̃{�[�h�r�����������̍�i�̌��_�Ȃ̂��A�����N���������Ă���Ȃ��v�ƌ�����`�F�[�z�t�B�X�^�j�t���t�X�L�[�̉��o���郊�A���Y�������Ƃ͍Ō�܂ő��e��Ȃ������`�F�[�z�t�B���Ђ����̉����_�Ƃ�������B �@2145�A���s����Ɉ��A���ĉƘH�ɁB �W���R���i���j���� �@1400�A�j�`�y�d�̂r�肳�ЁB 1600�A�j�쎁�Ƃ̖�����A���Ԃ��ꍞ�݁A1700�A�s���̂��ݏ�ƂQ�l�A���ЁB �@1800�A��B���ݏZ�̂j�����c�u�c�͂��B���W�I�h���}�̃i�]�̎��̂̌��B�������������B�j���͂قړ�����B�W�؉f��̃��m�N����ʂ͎����̍��Z����Ƀ^�C���X���b�v�����悤�ɉ�������������A���Ȃ�������B�J�������������A�͂ɂ��ޏ��������B�u�͂ɂ��ށv�Ƃ������{��͂��͂⎀��ɋ߂��̂�������Ȃ����A�����̏��q�����ɂ́A���̌��t���悭�������B �@�ŁA�̐S�̉̂����A ���O��S���@������̐��Ⴍ���@���g�ɂ�����Ō�����@���ꂪ�������̈��̊w�Z�@�Â��Âт����֏��͂������̖��̔������u�@�G�����R�@�K�����l�@�f���[�V�@������������ă����c��x���ā@�G�����R�����������������ā@������Ă��������ɂȂ�@���ɂȂ����ԁ@�v�킸�������}�b�`���C�����@�������̃}�b�`�̂ЂƎC��ɕ�����ŏ�����ꂳ��̊�@�{�[���ɓ������Ď��F�B�@�����Ă������̈Â��Ί� �@���O��l���@���ӂԂ��̂ӂԂ����@�I�����W�F�Ƀ��������R���邠�ꂪ�������̊w�Z �@�ѐÈ�{�������X����A�z������A���O���t�H�[�N���B�u���L�̎����c�̋╲���̂悤�ȉ̂����B �@�c�O�Ȃ��璮�������Ƃ��Ȃ��B �@�������A��肩�������D�B����Ƃ̂s�J�M�V�����Ƀ��[���Ŗ₢���킹�B�s�J����Ȃ�m�g�j�̃��W�I�h���}�ւ̑��w���[���B��������l�тȂ����[���B �@�s�v�c�ȉ̂��߂���`���̗ւ��L����B �W���Q���i�j���� �@1900�A�r�܁B�����|�p���ꏬ�z�[���P�Łu���Ƃ����u�v�B���m��̍�E���o�B�܂��Ǝs���|�p�قŊ�搧�삳�ꂽ��i�ł���A����A�����z�[����������l�b�g���[�N���Ƃ̈�тƂ��āA�S���X�J���̌���ŏ㉉�����B �@�����ł͔w�L�p�̌���W�҂����o�ŏo�}��������B���̕��X�����͂ȂA�Ǝv�����炻���������Ƃ������B���z�[���ōs����ŋ��ɂ͒������A����ł����Ԃ̋q�Ȃ̃Z�b�g����������Ƒg�܂�Ă���A�����Ԃ����������Ă���悤���B �@�o��l���͂S�l�B�n�Ӕ����q�{����j�Y�A����F���{�{�{�T�q�B �@��s��Ԃ̈֎q�Ȃɍ���T���O���X�̏��B�ʘH������Ă���j�B�����ŏ��̑O�̐Ȃɍ���j�B �@����40�N�O���炢�Ƃ�����l���ɂ����n�[�h�{�C���h�����������Ă���B��w�����̎���A�����̎���c�c�B���Ƃ��͎���̈łɂ܂���A���Ƃ̗��ňÖ�B�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ���Ƃ��͎��݂���̂��A����Ƃ����z���B �@40�N�̎��Ԃ��Q�l�̑z�O�����҂���B �@�����Ă����P�g�B���̎Y���ƁA���̂��Ƃ��̒j���̗����B �@��g�̒j���̍s�������I���w�́c�c�B �@��������҂����Ȃ���A�ӂ��̐l��������ɂ��Ă����B���m�������N���݂Ă��������I�����̐��ʂ��\�ꂽ��i�B�n�Ӕ����q�ƍ���j�Y�̂����������G��B�{�{�T�q�̃G���`�V�Y���Y�����Z���B �@�����A�����Ēʂ肽���A��������ȃe�[�}���܂�ł��邽�߁A�ǂ��ɂ��c�c�B �@2100�I���B�|�X�g�g�[�N������A���̂܂܉ƘH�ɁB �@�J���O�ɗאȂ̑��䎁�ƎG�k�B�����P��̃p���X�`�i���������̘b�ȂǁB �X�����̌��������A���͂��܂ЂƂ̂悤�B �W���P���i���j���� �@�Z�~�̍������܂т��������ƁB�}���V�����̒��L���ɃZ�~���]�����Ă���̂�����ƉĂ��Ȃ��Ǝv���B�}���V�����̕ǂ�ؗ��Ɗ��Ⴂ����Z�~�₠���B �@�C�ӂ̊�A�ʼnj���������Ă���B�����������傫�ȋ��B�J�S�ɓ��ꂽ�c�u�L�������o���A��Â��݂���Ƌz���t���Ă���B���̒ɂ��ɖڂ��o�߂�B�w���Ȗ��B �@ �@�ߌ�AK�삳��d�b�B�ƊE�l�̃p���[�Ɉ��|�B�����ɂ͂ƂĂ��}�l�ł��Ȃ��B �@�[���A�U�����Ă�A�Ɛl�̔������ɕt�������_�C�G�[�ցB �@�~�P�����W�F���E�A���g�j�I�[�j�ē����B�x���C�}���ē��B���e���g�̕�����b����͂���̂��߁B�Ō�̕���u�S�C�ʁv�����Ȃ��������Ƃ��S�c��B�X�s�o�g�������Ƃ͒m��Ȃ������B���v�I���܂ŁB�]�������B �@ �@���͒N�ɂł��A������ˑR����Ă���B���̂��Ƃ́c�c���B���̐��͐��҂̖ڂ���Ȃ��߂����E�ɂ����Ȃ��B���͐��E�����ł�����B���҂Ɛ��҂��Z�a�ł��鐢�E�Ƃ́c�c�B �@ |