�X��30���i���j�J �@0900�`1200�A�[���m�ÁB����~��̉J�B�����e�w�̒ɂݕς�炸�B���̍��͕����̂������ɂȂ�B �@1300�A��B�Ƒ��ŊO�H�B�P��3000�~�B �@1500�A�����ɑς��ꂸ�B�ڂ��o�߂��1730�B������e�A���ƂR�{��҂����B����10���ōZ���B�l���Ă݂�ƍj�n��̂悤�Ȃ��ƂN�J��Ԃ��Ă���킯�Łc�c�B �X��29���i�y�j�J �@�ߌォ������B1730�܂ŁB�u���t�v�Ƃ̃W�����Z�b�V�����̂悤�Ȃ��́B�������t������A�r�r�b�Ɗ�������B�茳�Ŏ��݂ɕω����Ă���������B���ꂪ�ҏW�̑�햡�B 1900�A�r�܁B�T���V���C������Ŕ����u�h�������v�B�O��ƊԊu�������Ȃ��ĉ��B�����~���[�W�J���Ƃ��Ď��M�̕\�ꂩ�B�����Ƃ��A���Ƃ��ẮA�n�c�p�[�N�ł̎�����ɏ�����̂͂Ȃ��̂����c�c�B �@�G�A���A���̕O�R�G�q���̒��s�ǂŌ��Ƃ����A�N�V�f���g�ɉ����A23���Ƀ��C���o�D�̌����~�����P�K�B�T���V���C���������~����Ƃ����ň��̓W�J�B���̂��߁A�J�[�e���R�[���ŁA��ؗ����͊��ɂ܂��ėܗ܁B �X��28���i���j���� �@1400�A�e�n���Ƃm���܂�q����Ƃ����B�p�j�b�N�V�A�^�[10�������̏��B�����k�[�h���߂����ĂR�l�ő���B�r�a�@�ɍČ����ɗ����Ƃ����e����Ƌv���Ԃ�ɉ�B���̂Ƃ���̐l���ɂ��āu�▭�Ȕz�u�v�Ɣ�������H 1830�A�V��v�ہB�O���[�u���Łu�X�֔z�B�v�̗��v�B���쁁�^�Ă������i�����W�c�L���������{�b�N�X�j�A���āE�r�{�����{�ʁB���o���g��O�B�����m�q(�I�Z��)�A����_�K(�����W�c�L���������{�b�N�X)�A�t�،\��Y�i���c���V�����j�A�C�����Y�B �@�c�����Z�ތ̋��̗����ɖ߂�������Ȃ��A�C�h���̎�ɓ͂����l����̎莆�B�ޏ����C�����A�p�ɂɖK���}�l�W���[�B�莆��z�B����X�Lj��B�S�l���D�萬���l�Ԗ͗l�B����Łu�V���m�v�B�q�Ȃ͒����N�����B�W�X�Ƃ����ؗ��āA�N���̂Ȃ�����W�J�ɁA�Q���̉��������炱���炩��B0830�I���B �X��27���i�j���� �@1620�A�j�L�O�a�@���I�B�P�J���ȏ���x���A�Ǐ�͂������ĕς��Ȃ��B�I�̌��ʂ́H �@1800�A��B �X��26���i���j���� �@0730�N���B�������̌��e�������Ă����ɂe�`�w�B �@�f������悤�Ǝv���������̎��Ԃ��Ȃ��B���[�A��������o�Ȃł����B �@ �X��25���i�j���� �@�[���A�������ɒ���B�܂��͑S�̂̓����肩��B �@1930�A���c�ցB�~���~�w����k��15���̏Z��n��ɂ��銗�c�����H��Ō��c��@�U�E�T�[�h�X�e�[�W�k�`�a�n�����u�����v�B �@���Ԃ����������̂ʼnw�O�̋������ŁA������ǂ�850�~�B�ߏ��ɋi���X�����邾�낤�Ǝv�������A�Z��X�B�����Ȃ��B�����Ԃ��āu�W���i�T���v�Ńn�[�u�e�B�[���P�[�L�Z�b�g661�~�B �@���߂ĖK���X�͐V�N�B�̏Z�ߌ��̉����Ɠ������͋C�B��͂�A���l�H�ƒn�т��B �@15���O�Ɍ���ɁB�����ʘH��ʂ��Ē��ɓ���Ɨ��T�C�h�ɊK�i�q�ȁB���˃t�@�N�g���[�Ɠ������B�~�`�̕��䑕�u�B���������ɂ��Ă͂������肵�����u�B �@��҂͐X�Ō��c����ɂ����ƁE���V����i���c�u�n�ӌ��l�Y���X�v�j�B���o�͉͓c���q�i�������i�n�j�n�j�B �@����͋ߖ����i�Ƃ����Ă����݂ł��ʂ��邩������Ȃ��j�B �@�w�Z�r�p�͐i�݁A���S�͂������������Ȋw�Ȃ́A�w�Z�ɂ�����u�Z���v�̐E�����E���̌ݑI�ɂ���đI�яo�����x������B�w�Z�ŋN����܂����̎����A�܂����̕s�ˎ��̑����ŁA�ӔC�����Z�����s�����Ă���̂��B �@�Ƃ���n���s�s�̌������w�ł́A���E�����O�Z���̌�C�E�V�Z���̖�I���n�܂�B�Z�����ɏW�܂鋳�t�����B�b�������Ō��߂悤�Ƃ��邪�N�����������l�����Ȃ��B�ӔC�]�ŁA���߁A�܂��b�������c�c�B�Ō�ɂ̓N�W�őI�ڂ��Ƃ܂Łc�c�B�w�N��C�A�x�e�������ꋳ���A�V�j�J���Ȏ�苳���A�|�����̃i�V�̂�������A�V�̗p�̏��q�����A���Z�𑲋Ƃ��ĊԂ��Ȃ��Z�����A�{�싳���A�Љ�l���ʌٗp���x�K���̊��Ԍ��苳���c�c�B �@�W�l�̋��t�ɂ�锒�M�����c�_�́A�u�\��l�̓{���j�v��̔��́B�����̋��t�ł��锨�V���������t���m�̉�b�̓��A���B �@�`���́A�����s�A�X�𒍈ӂ��ꂽ���Ƃŏ�荞��ł�����e�Ƌ��t�Ƃ̑Ό��B�����̎q�ǂ��̐ӔC�͒I�ɏグ�A���t�ɂ��ׂĂ̐ӔC��]�ł��悤�Ƃ���N���C�}�[��e�B�펯�O��̕��Z�ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̎���̋��t�͑�ς��B �@�ǂɂ́A�Y�����Ə}�E�����Z���̎ʐ^�B�قƂ�ǂ���Ɖ��̔��݂ɂ��Ă̎��E�B �@�C�O�h���̎��q�����������}�E���B �@�p���t���b�g�ŏ����Ă���悤�ɁA�������Y�̖���u�ٖ��i�b�E����j�v�Ɓu���̎��v�����p������i�B���c���j�́u���ј_�v�̑��������B �@���̊w�Z�ł͐_�ɕ����鐶�т��v�������B�N�����тɂȂ�̂��B �@�P����45���B�^�C�g�ȉ��o�A���҂̒B�҂��������āA�A�b�Ƃ����ԁB �@�Z���ݑI���B�G�ł͂Ȃ��B���͂₻���܂ōr�p���i��ł���Ƃ������ƁB �u����ɕی����ɂ���Ă��锼���a���k��60�l�v�͂����炭��Q�T�Ȑ����ł͂Ȃ��B �@�͂�銗�c�܂ŗ��������n�͂������B �X��24���i���j���� �@��T�����ĘA�x�Ƃ�����������B �@�J�ł́A�c�����Ɏ�����������蓊������A�c�����̋c���ƁA�����̋c�����̍��������đ����A���E�h�������B�����́A�u�O�v����Łu���C�̗��R�͑̒��v�ƕٖ��B�A�z�炵���B �@���P����c���͂R���P�ɏ��Ƃ̒���������B�O���̋c���ɏ����������킩��͂����Ȃ��B�������ォ��A�ȂƑ����F�������B���̎F��联��Ɏx�z����Ă���j�b�|���B �@�ǂ����̍��̐��P�ȂǏ�����̂��B���͂⍑��c���͍]�ˎ���̔ˎ�Ɠ����B�ǂ����ߑ㍑�ƂȂ̂��c�c�B �@�����߂��A�]�o�̑��q�̂j�N���V�тɗ����̂ʼnƑ��Ŋ��ҁB�c�ɂ̂����ō���Ă���u���r�[���v�̕�����Ď����B �@�j�N���A������A���������A�����n���B �@��ƁE����L��������菑���l���u�l�n�q�s�n�r�v�n�������͂��B�G�X�y�����g��Łu������v�Ƃ����Ӗ��Ƃ̂��ƁB�����Ɍ}�����Ȃ����w�̎u�A�����������B���{��`���w�Ƃ͎������قȂ�B �X��23���i���j���� �@�`���̕�Q��Ŗ[���ցB�����O�ɂ��łɋS�Ђɓ����Ă���A�ʐ^�ł����m��Ȃ��`���B�e���r�ł悭����Ȃ̕��Ƃ̉�b�Ƃ��������x�͂���Ă݂��������c�c�ƍŋߎv���B �@�����O�ɒ����A�^�N�V�[�Ŏs�c�쉀�ցB�A��ɋ`��ƐH��������Ƃ������N�̊��킵�B �@1730�A��B�J�͗l�̂��ߎ����čs�����P�͂��Ɏg�킸�B �@�Ƃɖ߂�Ɣ�ꂪ�h�b�Əo��B �@����͂����A���Z������̌��e�Ǝ������茳�ɁA�s�X�搶�ɓd�b�B�ސE�������t�����̉�u�V���o�[���E�G�̉�v�̌����Ȃǂ��f���B�e�g�ɂȂ��đ��k�ɂ̂��Ă�������s�X�搶�B �@�������A���E�G�̉���܂��A�ݔC���̕����傫���Ȃ�ɂ�A�e�r�c�̂Ƃ��Ă̑�����Ղ���炢�ł���Ƃ����B�������Z�ɍݐЂ��Ă��A�ݔC�����Ⴆ�u���m��ʐl���m�v�B����́A������ɂ������邱�ƁB40�N�ȏ���w�N�����Ⴆ�A�����n�a�Ƃ����Ă��A��Z�ւ̎v��������A���ꂼ�ꂪ�������i���Ⴄ�B�^�c���Ă���搶����������B�u���̂Q�A�R�N����̑����̋Ȃ���p�ł��v�Ƃs�X�搶�B�Ȃ�Ƃ��A��𑱂��ė~�������̂����c�c�B �X��22���i�y�j���� �@�@�����풘�u���̒f���v��Ǘ��B���R�����������u�I�b�y�P�y�v�ʼn���J���K�����������R�����̑s�m�B�u�ނɊւ��鎑�����܂������Ȃ��B��̐l���ł��v�Ƃ�������J����̌��t���Ȃ���������Ђ���邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�B �@�y���ˏo�g�B���m�̗��u�Ђ������R�����̑s�m�ł���A�v���I��ƁB�ԕv��g�D�����u�ԉ�}�v�̃��[�_�[�B1884�N�̎��R�}�̖��É������i�x���E�Q�����j�ɘA�����A13�N�Ԃ̍��������B���x�̒E���v��B�V���o�ɏo�Ă������ɂ͐��̒��͈�ρB�������R�����h�͓������I�푈�����ɑ��]���B���g���������R�}�����������B �@����Ɏ��c���ꂽ���v���Ƃ͂���ł������̎v�z���̂Đꂸ�A�V�����v�z�A�Љ��`�̌����B�p�������ł͓��{�̌|�W��s�������A��ʖ}�l�W���[���B �@�₪�āA�K���H����̎Љ��`�A�����{��`�ɋ߂Â����̂��A�����́u����x��v�����߂����Ƃ������߁B�������A���{�̃��i�ɗ����A��t�����ɘA�������Y�����B �@�����ȁu�N�勤�a���v�𗝑z�Ƃ��Ă������{����t�߂ɘA������킯���Ȃ��B���{���ł����グ����t�����̋]���҂ɘA�Ȃ����͉̂��{�ɂƂ��ĕʂ̈Ӗ��ŕs�{�ӂ������̂ł́B �@����ɂ��Ă��A�����̌Y�@�K�͂��炷��A�u�V�c�A�c�@�A�c���q����_���Ċ�Q����������A�����悤�Ƃ���߁v�A�������t�߂̔���B�u���s�v�ł͂Ȃ��A�u���ʂ̎v�z�v�������Ď��Y�ɂ��邱�Ƃ����X�ƍs���Ă����킯�ŁA�܂��ɋ��|�����B �@�������A���́u�N����E���̊ہv�̋����́u�v�z�v�������܂�@���Ƃ�������킯�ŁA�K���H���̑�t��������100�N�����Ă����{�̒ꗬ�͕ς���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B �@�����ɂ͎Љ��`�ҁA�r���������o�ꂷ��B���̂Ƃ��A�Ԋ������ō����ɂȂ���A�ނ��܂���t�����Ŏ��Y�ɂȂ��Ă����͂��B �@1976�N�A����E�{���ʼnF�䏃���̏����ōu�������r�������B89�̍���ɂ��ւ�炸�A�u���{��`�͐l�Ԃ�{���Ȃ������łȂ��A�Q�ł��T���U�炵�Ă����v�ƁA����@�����V���Ă����p������̂悤�Ɏv���o�����B�����̎Љ��`�҂ɂƂ��āA�^�u�[�͉����Ȃ��B�����V�c���̎����ɐg�����ł��Ȃ����{�l���͂邩�Ɏ��R�l�������B �@�܂�ʼnĂɖ߂������̂悤�ɏƂ���鑾�z�B��������B �@1400�A����E���i�ٌ���łm�k�s�u�}�O�m���A�̉Ԃ����v�B �@�f�扻��i�͕��؎��Ɍ��ɍs�������A�r���ŐQ�Ă��܂������A�قƂ�NjL���ɂȂ��B�����炫����Ɓu����v�̕��������̂͏��߂āB �@����̓��o�[�g�E�n�[�����O�B���A�a�ɂ�鍇���ǂŖ���S���������̌������ɂ��ď��߂ď������Y�ȁB���o�͖k��G�l�B �@����̕���̓��C�W�A�i�B�̏����Ȓ��̔��e���B �@�����V�F���r�[�̌������̏����̂��߁A�V�F���r�[�ƕ�̃}���������e���ɂ���Ă��邪�A�V�F���r�[�͓��A�a�̔���ɏP����B�ޏ��͂��̕a�C�̂��߁A��҂��猋�����Ă��q�����Y�܂Ȃ��ق��������ƌ����Ă����̂������B�������A�P�N��A���͂̔��ɂ�������炸�A�D�P�o�Y�B�����A������A�V�F���r�[�̕a�C����������c�c�B �@���e���ɏW���U�l�̏����m�̗F���ʂ��āA�l���Ƃ͉����A������Ƃ͉�����i����㎿�̐l�ԃh���}�B �@�������ȕ��䂩�Ǝv������A�Ƃ�ł��Ȃ��B���X���~�̃Z���t�̉��V�A���I�ȓo��l���̑��`�A��b�̖��B���ׂĂ��ꋉ�i�B���������ɂ悩�����B�I���͎v�킸�܁B�m�k�s�̎ŋ��ŋ������̂͏��߂Ă��H �@�o���͖ؑ��L���A���m�g����A��㒩�q�A�x�]�^���q�A�^�����A����b���B �@�����\�肵�Ă����o���҂̍~�ȂǂŁA�o�^�o�^�����炵�����A������������ł͂��ꂪ�x�X�g�̑I���B���ł��V�F���r�[���̐^�����i����ǂ��E���j�̓L���[�g�Ȋ痧���A���邭��Ƃ悭�ω�����\��A�X�����ȑ̌^�A�D�݂̏��D�̃h���s�V���ǐ^�B�́A�u�L�C�n���^�[�v�ɏo�Ă������h�q�Ƃ�������B�����Ƃ��Ă����������Ȃ��B���o�g������Ⴄ���낤���ǁB �u�K���̔w��ׁv�ɏo�Ă����Ƃ������A�L���Ɏc���Ă��Ȃ��B��͂菗�D�͂��̖��ɕ����Ƃ����B����̃V�F���r�[���͐^�����ɂ҂�����̖������悤���B���ꂩ��̒��ڊ��B �@�x�e10�����݂Q���Ԕ��B�x�e���Ԃɐ���̂n�V����A�l���̂s������Ɨ��b�B�n�V����̓o�X�P�b�g�̑I�肾�����Ƃ��B�u�����Ƃ͖�����������ł���v�B �@��Ђɖ߂�A�������̍L���𐔓_�쐬�B �@1800�A���k��B�{������Ńg���E�v���W�F�N�g�u�Ă�����Ȃv�i��E���o���ӂ������悵�j�B �@�R�{�Ƃ̂���Ă̓��̏T���B��w�A�I�q�����H�̌�Еt����|���ɗ]�O���Ȃ��B�����͖����Ɛg�̖��̔������u�厖�Ȑl�v��A��ė�����Ȃ̂��B�������A�����Ƃ��ς��Ȃ��x���̒����}�������̉Ƃ̎�l���v���l���̑��c�̓}�C�y�[�X�ŋI�q�����炾������B����Ȓ��A��������l�ł���ė���B���Ԃ����ދI�q�ɔ����́A���͍����A��ė���l�͎������ݑ�P�A�[�ʼn���Ă����l��炵�̘V�l�Ȃ̂��Ƒł�������B���̐l�ɁA�Ƒ��̒g���ȕ��͋C�����킹�����Ƃ����̂��B������I�q���A�����Ƒ��c�A�����Đ��v��������Đ������A���̂����̘V�l�𐳕v�̕��e�Ɏd���ďグ�A�Ƒ��̈���Ƃ��Č}���悤�Ƃ̌v��Ő���オ��B �����āA���悢�悻�̘V�l������ė����̂����c�c�B�i�g�o���炷���j �@�I�q�ɂ͐m�Ȉ��G�q�B�ǂ����Ă����Ă̐����h���D�Ƃ����C���[�W�������A��e���͑z���ł��Ȃ��B�l���Ă݂�A����54�B�s�v�c�͂Ȃ��̂����A�L���̒��̏��D�͂��̂܂��Ԃ��~�܂����܂܁B�������A30�N�ȏ�̎��Ԃ��щz���Č���ꂽ�m�Ȉ���q�́A�܂��������䏗�D���̂��́B�h�ꓮ���v���A�S�̋@�����ׂ₩�ɕ\���B�������N����d�˂Ă���B �@�ؗE��A���є��]�������B�ŋ߂̎ŋ��ɕK���Ƃ����Ă����قǓo�ꂷ��P�C�^�C����x���g���Ȃ��̂��D�������Ă�B�S�ɂ��݂�ӂ������Łu���A��v�B�v���Ԃ�ɏI���̗]�C�ɂЂ����Ă��܂��B �@�P����50���B �@�@�[�H��H�ׂĂ��Ȃ������̂ŁA�����[�����ł��c�c�Ǝv������A�Ȃ�ƓX���܂��B����ɕʂ̃��[�����X���B���܂͂��ׂ̍߂�ɂƂX�[�v�B�C���X�^���g�̖��ł��̎�̃��[�������͎t���Ȃ��B�����[�����͂Ȃ��P�ނ����̂��H �X��21���i���j���� �@�\������ĂȂ������̂ŁA���߂ɋA��B �@�]���̖��̂r����A�u�d���ŋ߂��ɗ�������v�ƁA�ƂɊ���Ă����B�؎���l�͏m�ƃf�[�g�B�r�����Ɗ؍������̓X�ŐH���B2100�܂ŁB �X��20���i�j���� �@1500�A���k��B�u���v������ŐA�g����u���ڂ�����v�i�쁁�É����j�A���o�����j�B �@�A�ؐE�l�ł�����o�D�̍����L�g�����g���������j�b�g�ŁA�A�؉��̐e������l���ɂ����l��쌀�B �@����������A�؉��̐e���͖��Ƃ��̖��̎O�l��炵�B���̒U�߂͓����A�ؐE�l�����������łɑ��E�B�Y��`�������̖��̂悤�Ɉ�ĂĂ������A���ɂ��̓�������Ă���B�u���̐l�ƌ������܂��v�Ƃ����錾�B�������A���̑���͊؍��l�B���ӂ͌ł��A�؍����畃�e�i�O�c�����O�j�����A�ɂ���Ă���B��ȂȐe�����A����ɐS���J���A����̕��e�ƈӋC�����c�c�B �@�؏����ʂ�̐l��쌀�B�E�l�����̂�����Ƃ����g���u���͕���̖��t���B�z���ȏ�̓W�J�͂Ȃ��B���܂ɂ͖��҂̉��Z�����Ō�����t���b�g�Ȏŋ����������B���T�킪�C�������ς�A�Z�v���̖������D���B�E�l���̗���F�a�����I�ȉ��Z�ƕ��e�ōD���B �@�P����35���B���B���b�W���@���K�[�h���U�Ă���ƘH�ɁB �X��19���i���j���� �@�˗������������̌��e���͂��B�l�s�ɍݏZ�̂s�v��搶����B�ސE���Ă���A����ŋ��ڂ������Ă����Ƃ����s�v��搶�B���̐����ɂ��`�N���ƈًc�\�����āB �X��18���i�j���ꎞ�X�J ���c���Ăs�c����̎��ʍ��B �@1800�A�V�h�䉑�O�B��H���łق����Ē�H�B 1930�A�V�h�ցB�V�A�^�[�u���b�c�ŐV�h�|�\�Ёu�ւ��̂͂Ȃ��v�B�u�p�b�`�M�I�v�u�t���K�[���v�̉H������ɂ��錀�c�̌����B �@���{�̊e�n�ɂ���u���{�̒��S�v�i���{�̃w�\�j���ނɂ����R���f�B�[�B���d�������݂���A�_���H���Ő��v����^���̏����ȑ��B���l�͊�z�V�O�Ȏ�i�ŁA���̃_���H���𒆎~�����悤�Ƃ���B����́A�����u���{�̃w�\�v�Ƃ��Ēn�}�ɍڂ��邱�ƁB���̂��߂ɁA���y�n���@�̖�l�ɂ��̎肱�̎�Œ�����d�|����c�c�B �@�F�d�|���ŁA���̖�l��U�����悤�Ƃ���̂��A�����̖��i�����b���j�B�������A�ޏ��ɂ͗c�Ȃ��݂̗��l������B���̎O�p�W������ő��͑呛���B �@�c�c�ƁA�R�e�R�e�̊쌀�ł͂��邪�A�ˑR�_���X���n�܂�����A������������ɂ����A�U���I�ȃZ���t�̉��V�ȂǁA�����ɂ��A�������ւ��d���݂̕���B �@�������A�I�[�v�j���O���}�C�P���E�W���N�\���́u�X�����[�v��������A80�N��̃_���X�~���[�W�b�N��������A�f�ނ������ɂ��ÐF���R�B���̎����̏{�̑f�ނ��g���̂�������̃Z�I���[�B�N�㗎���̉��y���g���Ӗ����悭�킩��Ȃ��B �@������u�����͂ł��邵�A�����͂ł���v���A����Ƃ��Č����ꍇ�ɖʔ��݂��Ȃ��B�P�Ȃ���ŋ��̈����Ɍ����Ă��܂��̂��B �@�I����A��������ɓc�ɂ̒n�r�[������������B��̃r�[���D���ƌ����Ă��̂ŁB �@�q�t�o�̂g�{����Ɉ��A���ĉƘH�ɁB �X��17���i���j���� �@�x���B�C��35�x�B�Ă͏I���Ȃ��B �@����A���炾��ƉƂʼn߂����B �@1900���瓌���`�����l���ʼn��������W�B���̎�̔ԑg�͐̂͌h�����Ă������A�ŋ߂̓r�[����Ў�ɂ��������Ă��܂��B�����ĉS���B�g�V���Ȃ��H �@���ł��u�u���[���C�g�E���R�n�}�v�Ɓu�閾���̃X�L���b�g�v�����ɃY���Ƌ����B���w����A�w�Z����A���ė[���T���ɂg�a�b�i�k�C�����W�I�j�ŁA�y���ȃh���~���O�ƈꏏ�Ɂu�g�a�b�g�b�v�g�E�F���G�e�B�I�I�v�v�̔��n�������A�i�̐��B���̔ԑg�͓��{�̋ȂƊO���Ȃ̃g�b�v20���Љ�Ă����̂��B��Ԉ�ۂɎc���Ă���̂́u�閾���̃X�L���b�g�v�����T���g�b�v�P���l���������ƁB�����āu�u���[���C�g�E���R�n�}�v�B����̓m�X�^���W�[�Ɏv����Ђ���Ȃ���Ђ�����̂��S���B�����������ɉߋ��ɂȂ�B���܂ɉߋ��ɂЂ��������Ă����B �@�@�E�j���̃u���O�Ŏ��̋L���ɋ������Ђ����B �@�C���h�l�V�A�Ō��q�͔��d���̌��v�悪�i��ł��邱�ƂɊւ��A�������߁A�n���̃C�X�����w�҂炪�A���q�͔��d�́A���ꂪ�����炷���v�����j�p�����Ȃǂ������炷�ЊQ�̉\���̂ق����傫���A�n�����iharam=forbidden ���X�����ɋ�����Ă��Ȃ����́j�ł���A�Ƃ����@�������i�t�@�g���Afatwa�j���o�����Ƃ����BGreenpeace �̋L���ɂ��A�ȉ��̒ʂ�B �u�C���h�l�V�A���{�������W�����̃����A�����Ői�߂Ă��鏉�̌��q�͔��d�����v��ɑ��A�����ő�̃C�X�����n�c�̃i�t�_�g�D�[����E���}�[�iNU�j�̃W���p�����x����9��3���A�����A�����̌��֎~��錾���܂����BNU�̓C���h�l�V�A�Љ�ő傫�ȉe���͂������Ă��܂��B���q�͓������~�߂邤���ŁA���̐錾�͂���߂ďd�v�ȃX�e�b�v�ƂȂ�ł��傤�v �@�u���v�����j�p�����������炷��Q�̂ق����傫���v�Ƃ������X�����̌��������E�̒����ɂȂ�A���E�͕ς���Ă������낤�B���āA���{�̕����E�́c�c�B �X��16���i���j���� �@���͐Q���̂��P�����B�N��0630�D�����s���B�������[���S���Љ�l�D�����B �@0800�A�����̓��������فB��D�n�s�̐E���E�j�삳�����̂ŗ��b�B���ƂƂ�����㋞���Ă�Ƃ��B �@0815�A�J��B���ւ��ď����^���B�J��̗��K�B 0915�\�I�X�^�[�g�B�܂��͒c�̂ŏo��B�m�Â̎��Ɠ����ŁA�T�l�̌ċz���Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B����20�E5�ő����T�ʁB�����i�o���Ȃ킸�B �@��͂ق��̎��������Ȃ���ߌ�̌����܂ŁB �@1330�A�J��B�O�N�x�D���҂̃g���t�B�[�ԊҁB�ʉf���B �@1450�A�����B�\�����łȂ������B���N�̓Q�܂Ȃ���c�c�B���̃v���b�V���[���������̂��B�E���̓r���Ő��b�B�u�ԈႦ���I�v�Ǝv�����̂����A���̂܂ܑ��s�B���Ƃŕ�������u�ԈႦ�ĂȂ�������v�ƌ���ꂽ�̂����c�c�B�������Ɗo�債�����A���͂R�{�B�z�b�Ƃ������A�����̒��ł͖����̂����f�L�ł͂Ȃ������̂Ŋ�т����܂ЂƂB �@1600��B�����č��e��B���N�A���̍��e����[���̂悳����������B��������ʉ���������ȁB���ꂵ�����Ƃ͈�Ȃ��A����ŐH�ׂď��āA���e��[�߂�B�e���ꂪ�d��ŗ]���̃o�b�N�����I����̂����Ȃ��݁B �@�Ō�͏o�Ȏ�68�l���c���67�l��67��̓��X����̈�������ĕʂ�̃Z�����j�[�B����̑�w�����E�s���E�x���̍I�݂Ȏi������B �@�j���t�͂��u�f���̃t�@���ł���v�Ɗ��������Ɉ���B�����̐l�E�j�t�́B �@1930�A�ꑫ��ɉƘH�ɁB �X��15���i�y�j���� �@0630�o�ЁB�t���͉ċx�݁A�r�����x�݁B���Ԃ����Ղ�Ŏd���������B 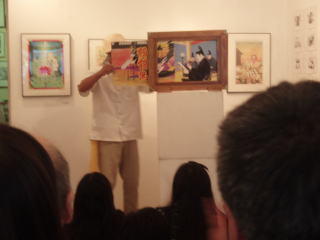 �@1530�A����X�p���A�[�g�M�������[�i�r�`�M�������[�j�ցB�C���X�g���[�^�[�A�g�c���F����̌W�B�������Â��ŁA���₩�ȏΊ�̋g�c����A�t�@���������A�W�����ꂽ����͂��炩�����D����Ă���B�g�c����̊G���ꖇ�͗~�����ȂƎv���Ă����̂ŁA�s�v�c�̍��̃A���X���C���[�W�����G�����ƂɁB15�����̂P���B�z�t���P��6000�~�͈����B �@1530�A����X�p���A�[�g�M�������[�i�r�`�M�������[�j�ցB�C���X�g���[�^�[�A�g�c���F����̌W�B�������Â��ŁA���₩�ȏΊ�̋g�c����A�t�@���������A�W�����ꂽ����͂��炩�����D����Ă���B�g�c����̊G���ꖇ�͗~�����ȂƎv���Ă����̂ŁA�s�v�c�̍��̃A���X���C���[�W�����G�����ƂɁB15�����̂P���B�z�t���P��6000�~�͈����B�@������1600��1800�̓��A�������F����́u�鐋S�v�̎��ŋ�������B������ɃL���������A�����t����500�~�B�Η��������ɗ���B���̂Ƃ���悭��B �@30�l�قǂ̑�l���M�S�Ɏ��ŋ��Ɍ�����}�B�ʔ����B �@�c�t���̎��ɁA���ŋ��̎��Ԃ���D���������B �@���ł��u�t�̂����v�Ƃ������ŋ��B�����Ȓ��������A�v���v���̏�蕨�ɏ���Ă��Ԕ��ɔ��ł���B�ׂ��ȓ��e�͖Y�ꂽ���A�\���̎�j�������悤�Ȓ������̏�蕨�ɋ������Ђ��ꂽ�̂��B �@1630�A�M�������[�������Ē������ɁB�������J�ō~��āA�u�]�˒|�v�ŗ[�H�B�n���̗L�Ղ��������������~�ɐw����ĉ���B�₩�܂����̂͂������ǁA�H�����ɃQ�e���m�̘b������̂͂�߂ė~�����B�w�r�̐��������ޘb�A�Q���̘b�B���������Ő���オ���Ă���B���������̎h�g��H1000�~���䖳���B �@1800�A�O��ցB�����������Ė�20���B�W�u���̐X���p�ق̗���̋n�Ŏ��̗��R���e���g�B�V�h���R���́u���̖��O�Y2007�v�B���\�Y�v���f���[�X�ɂ��O�F�e���g�����̑��e�B  �@�J����҂l�̌Q��B��350�l�B�i�N���b�v�̏�J����A�����s�l����Ɨ��b�B �@����́u�����v�́A�ߓ����G�Ԃɑ����āA�剉�ɉ�����q�B�g�̂��Ȃ����V���[�v�ł��ꂢ�Ȗʗ������q���C�����ɂ͂����Ă��B���o�����ʂȕ������������Ƃ��A�X�s�[�f�B�[�ɁB�����E�V���h�C�Ƃ�����ۂ����������A����͋x�e�Q��i�e10���j�����݂Q���Ԕ��i���ۂɂ͂Q����45�����������j�A���Ԃ̒��������������Ȃ��I�݂ȉ��o�B�O���ڂ̎O�Y�L�q�́u�ЂƂ�ŋ��v�͂����Ă��唚�B�L�q�͎ŋ������܂��B �@�Ō�w���̑��ŏo���̑�ߔ��m�������X�̎ŋ��B�A�h���u�����ȂǁA�������͓��\�Y�̂c�m�`�B�R�r���}�m��̉����ɗN������B���l��̃_���X������܂ł̗��R���ɂ͂Ȃ��J���[�B�e���g�ŋ��̍r�X�����ɍʂ�Y����B �@���X�g�V�[���́u��s�v�̃X�y�N�^�N��������܂łōō��̃f�L�B�u�����v�͍��ŏ�̎d�オ��ɂȂ����B �@�I����A�e���g�Ŋ��t�B���Γ��������A�ɑ����ĉ����B���璿�ɘQ���̉S�����l�p�M����┎�����Љ���B�}���Z���Y����Ɏt�����A�f��܂邲�ƌ��|��W�J���Ă���Ƃ����B29���ɍ]����ÐΏꕶ���Z���^�[�ŕ��䂪����Ƃ̂��ƁB�P�ΔN���B���ɐ^���ōD�������Ă�B�L���j�͂T�̑��q�ƈꏏ�B�b��������ƒp�����������Ƀ\�b�|�������B���e�Ɏ��Ȃ��ŃV���C�ȁc�c�B�Q�̖��͋�����������B �@�����ƈ���ł��������A�����A����������̂ŁA�R�r���}�A�n��A�O�Y�����Ɉ��A���ĉƘH�ɁB �@�W�u���̐X�B�����Ƃ��낾�B�߂��ł͎R�{�L�O�W�B���j�ƕ����̒��B �@���܂��烀��������A���܂�ς�邱�Ƃ��ł����Ȃ������x�����������ɏZ�݂������̂��B �X��14���i���j���� �@�ߌ�A���c�n��ցB�s�������w�������̎p���܂Ԃ����B����邱�Ƃ������Ȃ��N��B�����ɂ͂��܂͂��̑�^�J���I�P�X�Ȃǂ������A�X���l�ς��B �@����c���|�Łu�P���l�̂��߂̃\�i�^�v�u�u���b�N�u�b�N�v�̓�{���āB����ւ��Ȃ��̓�{���ĂƂ����͖̂�����Ȃ�ł́B�����X�^�b�t���ē��A�U������B�q�Ȃ̈֎q���N�b�V�����������A�g�C�������ꂢ�B�w������ɒʂ���������̖ʉe�͂Ȃ��B �@�������A�̂ƕς��Ȃ��A�f��D�����K���f��فB�q�ȂŃI�V���x�����邨�����l�A��͂��Ȃ����A�|�b�v�R�[���̓������Ȃ��B���ɉ��K�B����Ȃɉf��قŐS�n�悭�f��������̂͋v���Ԃ肾�B�ŋ߂͉f��قɍs�����тɃC���[�ȋC���ɂȂ邱�Ƃ������B�����̕����Ńe���r�����Ă���悤�ȕ����O���Ȑl�̑������ƁB����Ȃ�ƂŃr�f�I�������ق����܂��}�V�Ǝv�����Ƃ���B �@�����́A�Èłɐg�߁A�傫�ȃX�N���[���ʼnf����y���ނƂ��������̎��Ԃ��߂������B���̓�{���Ă������Ă��ꂽ�n���V���V�I�I�������A���N���u�̂l����Ɋ��ӂ������B 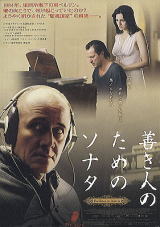 �u�P���l�̂��߂̃\�i�^�v�́A�x�������̕Ǖ��O�̓��h�C�c������B���̐��������Ď����鍑�ƕۈ��ȁi�V���^�[�W�j�̓����\���Ȃ���A���Ƃɖ|�M���ꂽ�|�p�Ƃ����̋�Y��`�������́B �@�V���^�[�W�Lj��̃��B�X���[�i�E�����b�q�E�~���[�G�j�́A����Ƃ̃h���C�}���i�Z�o���`�����E�R�b�z�j�ƕ��䏗�D�ł�����l�̃N���X�^�i�}���e�B�i�E�Q�f�b�N�j�����̐��ł���؋������ނ悤�ɖ������A�h���C�}���̏Z�ރA�p�[�g�̂�����ꏊ�ɓ�������d�|���ĊĎ����n�߂�B �@������A���̓����킩�璮�����Ă����̂́A���o�Ƃ���h���C�}���ɑ���ꂽ�s�A�m�ȁA�u�P���l�̂��߂Ƀ\�i�^�v�������B�u���̋Ȃ�{�C�Œ������҂͈��l�ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����ȁB���B�X���[�́A���̋Ȃƃu���q�g�̎��W�A�����āA�h���C�}���Ď������͐��{�������N���X�^���䂪���ɂ��悤�Ƃ���l�I�ȗ��R�ł��邱�Ƃ�m�������Ƃ���A��l�ɓ���Ƌ������Ă����B �@���B�X���[��т��������E�����b�q�E�~���[�G�́A�������ŏ\���N�ԁA���g�̍Ȃɖ������ꑱ���A�V���^�[�W�̊Ď����ɂ������Ƃ����B �@���Ƃɒ����𐾂��������̓����҂��A���Ɖ��y�A�����āu���v�ɂ��A����ɐl�Ԃ炵�������߂��Ă����B�c�c����ȊÂ��b����킯���Ȃ��A�Ǝv����������Ȃ����A�����ł���ȃZ���t���o������B �@���[�j�����u�x�[�g�[�x���̏�M�̃\�i�^���Ă��܂��ƁA�v�����Ŋ��܂ł�肨�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�ƌ������B �@�|�p�������ɐ����ɑ��đ傫�ȉe����^���邩��������b���낤�B �@������A�f��Ƃ��Ă͂���ł����B �@������`�҂͂��̉f����u���R�̂Ȃ��Ǘ����Y��`�Љ�̐�]�v�ƌĂԂ̂�������Ȃ����A���݂̃j�b�|���͂ǂ����B �@���̋��X�Ɂu�����v�̂��߂̊Ď��J���������������A�X�[�p�[�E�R���r�j�E�f�p�[�g�̊Ď��J�����A���C��Ԍ��A�N���W�b�g�J�[�h�c�c�B����Ƃ��o����A����̂����Ď��J�����ɉf��Ȃ��ʼn߂�����l�͂܂��A���Ȃ��B���܂��ɏZ����{�䒠�A�������w�ԍ����c�c�B �@���h�C�c�̃V���^�[�W���S�̃t�@�V�Y���Ȃ�A���̓��{�̓v���X�`�b�N�̊Ǘ��Љ�B�₪�ēS�̊Ǘ��Љ�Ɉڍs����͖̂ڂɌ����Ă���B���h�C�c�̗⍓�ȊǗ��Љ�͑��l���Ƃł͂Ȃ��B �@���̎��A�u�P���l�̂��߂̃\�i�^�v�͒������Ă���̂��낤���B �@�Q�{�ڂ́u�u���b�N�u�b�N�v�B�I�����_���h�C�c���C�M���X���x���M�[��������B �@  ���؎��ɉf��ق̗\�������ċ������������A���������Ă��܂����B�����͖��̈ꎞ�A����B�r�f�I�Ō����邩��A���߂ɋA���Ă����悤���ȂƎv�������A���[��������u�f�[�g���v�B�ӂ������čŌ�܂Ō��Ă悩�����B ���؎��ɉf��ق̗\�������ċ������������A���������Ă��܂����B�����͖��̈ꎞ�A����B�r�f�I�Ō����邩��A���߂ɋA���Ă����悤���ȂƎv�������A���[��������u�f�[�g���v�B�ӂ������čŌ�܂Ō��Ă悩�����B�@����Ȃɂ��N���ɕx��y��Ƃ͎v��Ȃ������B �@�����1944�N�A�i�`�X��̉��̃I�����_�B���������_���l�̎�̃��w���́A��l�̒j�̎�����ŁA�암�֓��S����r���A�҂����������h�C�c�R�ɂ��Ƒ����E����Ă��܂��B���W�X�^���X�ɋ~��ꂽ���w���́A�G���X�Ɩ���ς��A�����u�����h�ɐ��߁A���W�X�^���X�^���ɎQ������B���̔��e��ɃX�p�C�Ƃ��ăh�C�c�l���Z�����c�F�ɋ߂Â��Ă������A���̗D�����ɐG��A����Ƀ����c�F��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B����A�߂��ꂽ���W�X�^���X�̒��Ԃ������邽�߁A�h�C�c�R���P�������W�X�^���X�͋t�ɑ҂������ɂ����Ă��܂��B�ʕ�����҂̑��݂������яオ��B �@��]�O�]�A�Ō�܂ŗ���҂��N�Ȃ̂��킩��Ȃ��S�����r�{�B�|�[���E�o�[�z�[�x���ē̃V���[�v�ȉ��o�B�Q����24���̒�����Ȃ���A�܂������_�����Ƃ���Ȃ��Ō�܂ň�C�B����A�������[�����B �@���w�����̃J���X�E�t�@���E�n�E�e���̃L���[�g�Ȃ��ƁB�ǂ��ƂȂ��̂̉���܂肱�Ǝ����A���f�I�ȕ\��B�i�`�X�ɂ�郆�_���l���Q�Ƃ����A���肪���ȃe�[�}�ɐH���C���̕��ɂ��������߁B�Љ�ƌ�y������̂ƂȂ����ꋉ�G���^�[�e�C�������g�B �@�f��̖`���ƍŌ�ɁA�����ɍ��ƂȂ����_���l�����A�����p���X�`�i�̒n��������B�I���͑�����푈�̔����B�f��̒��ł̓I�����_�l���W�X�^���X�ɂ��y���郆�_���l�B���̃��_���l�����A���������ɂ̓p���X�`�i�l���������Ă����B�ނ��ǂ��o���Ă̍��ƌ��݁B �@�f��ł̓h�C�c���s�k������A�h�C�c�R�������I���ɍ߂�A�I�����_�R�Ɏ�����A�푈�ƍ߂̏؋��B�ł�}���ʂ�A�M�������s�����i�`�X�̋��͎҂��s�҂����ʂ��`�����B�܂����������̘A���B �u��Q�ҁv�̃��_���l���p���X�`�i�l�𔗊Q���A���x�́A�p���X�`�i�l�ɑ��������B�����̘A���̌���j�B �u�X�̔��v�̊ē炵���G���`�V�Y���ƃT�X�y���X�t���Ń~�X�e���A�X�Ȍ�y���Ȃ���A�o�[�z�[�x���ē̊�ڂ́u�X�D�P�P�v�ȍ~�̕č��哱�́u�����̘A���v�ւً̈c�\�����Ă��������̂ł́B�n���E�b�h�̋�a�ȑ������͂邩�ɖʔ����u�u���b�N�u�b�N�v�B�܂��f��قŌ��������̂��B �@�f�悪�I���A�}���ŋA�낤�Ƃ��Ă�����A���r�[�łl�c���ƃo�b�^���B���R�Ƃ͋��낵���B�l���܂�݂�����ꏏ�B�C���X�g���C�^�[�̂l������A�w�����ォ�當�|���̃C���X�g��L�l�{�̃R�����œǂ�ł���̂ŁA�u�����v�Ɖ�̂͏��߂Ă����A�܂�ŗ��j��̐l���ɉ�悤�ȕs�v�c�Ȋ��o�B�u�P���l�̂��߂̃\�i�^�v�����邽�߂ɗ����Ƃ��B �@����ɂ��Ă��A��͂薼����͂����B �@2100�A��B �@�v���Ԃ�ɉ���B���߂ĉƂ𗣂�Ă̕�炵�B���S�����邩�Ǝv������A�ӂ���ƕς��Ȃ��c�c�B �X��13���i�j���� �@1530�`1630�A�c����B�j�a����Ō�̈��A�B����o�Ȃ����B �@1900�A�ԍ�B�����z�[���Łu�˓c�b�q�@�A�N�g���X�v�B���r�[�ɏ���ꂽ�e�E����̍��ȉԁX�B���Ȃ̏���B�u�����{�ň�ԖZ�������D�v�c�c�B��тƓ����Ɉꖕ�̂��т����B  �@���A�g���G�_���J���̗����ɐ���������ꂽ�̂ŁA�J���O�ɗ��b�B�V�������쎖�����𗧂��グ���Ƃ̂��ƁB��t�ɂ͂x�c�R�I�q����B �@���A�g���G�_���J���̗����ɐ���������ꂽ�̂ŁA�J���O�ɗ��b�B�V�������쎖�����𗧂��グ���Ƃ̂��ƁB��t�ɂ͂x�c�R�I�q����B�@��ꕔ�͂��̓����̉̂łÂ�˓c�b�q�X�g�[���[�B��̗����ɂ��ꖺ�ƒ�̐����A�����̂Q�x�̗������B�����ƂȂ������Ɍ��Ƃ���͌˓c����炵���B���[���A�Ƃ�����҂�Z���`�����^���ȐF�Œ��F���ꂽ�����L�B�u��ԍD���ȉ́v�Ƃ����u���̏H�v���̂��Ă���r���A�����l�܂点���ʂ��B�v���Ƃ��Č����ĕ���̓r���Ŏ����̊���ɗ����ꂽ��A���ꂽ�肷�邱�Ƃ��Ȃ������˓c����ɂ��Ă͒������B�u�Â��ȐÂ��ȗ��̏H�@�c�c�����A�ꂳ��Ƃ����Q�l�@�I�̎��ςĂ܂��͘F���[�v �@�Q�N�O�ɍň��̕��S�������˓c����B��ւ̎v�����ˑR��������̂��B��Ò����A������`�҂̌˓c����ł��A�コ�������邱�Ƃ�����̂��c�c�B �@�����̂S�l�i�������ٗ��A���G���ގq�A���V�q�A�ē������j�͂��킸�ƒm�ꂽ�G�����^�[�e�C�i�[�B�_���X�A�́A�R���g�̑�ԗցB�q�Ȃ͏��Ɍp�����B �@��͐V���u�A�N�g���X�v�̃i���o�[�𒆐S�ɂ����V���[�B�^�g�̃h���X�œo�ꂵ�A���F�����ŏ����̃h���X�ɁB �@�������̍쎌��Ȃɂ��u������v�͂����ȁB�q�b�g�̗\���B����Łu�g���v�ɂł��o��A�����������ƂȂ����B �@�A���R�[���Q�ȁB�\����20���I�[�o�[��2145�I���B �@�w�܂łl���̂s������ƁB �@�˓c���o�Ă����u���w���Q���v�̃e�[�}���y�����̒��������߂���B�M�^�[�̉��t�ƁA�`���ŗ����u���w���Ƃ́A���n�ȔN��ł��邪�c�c�v�Ƃ����i���[�V�����B40�N�O�ɘ^�����āA�e�[�v���������͂��Ȃ̂ɁA������ǂ����ɍs���Ă��܂����B�m�g�j�ɂ͒��w���Q���̃e�[�}�����͎c���Ă���̂��낤���B �X��12���i���j���� �@���A�h�c�M�V����d�b�B�����̏o�ł�10��15���Ɍ��肵���Ƃ̂��ƁB �@�����A�Ɛl���u���{���C�������v�ƁB�����ăe���r������ƁA�܂������B �@���M�\�����s���A�������獑��ő�\����B���̒��O�Ɏ��C�\���Ƃ́B�Q������̎��C�\���L�҉�����邪�A�L�҂̎���ɂ͑��āA�������ЂƂ̂��Ƃ��J��Ԃ������B�u�ǖʂ�ŊJ���邽�߁v�B������Ă��A���̌J��Ԃ��B �@�V�w�����n�܂��āA�o�Z���ɂȂ������̂́A�����ɉۂ���ꂽ�h��͎R�ς��A�ǂ�ɂ���������Ȃ��B����Ȃ̂ɁA�e�ʂ̂�������ɂ́u�h��͍ς�v�Ƌ���A�����Ƃ��݂��悤�Ƃ���B�ŁA�����A�����ɍs�����Ƃ����瑫��������œ���Ȃ����w���̂悤�Ȃ��́B �u�w�Z���߂�Ƃ肠�����h�������瓦������v�Ƃ��������s���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B�u����������̖����ɂȂ��Ă���Ȃ����A����ɂ��Ă���Ȃ��B���[�A��[�߂��v�Ƃ����S���Ȃ̂��낤�B�܂�Ŏq�������������˂Ă���悤�Ȃ��́B�Ō�܂ł��q����������B���ꂩ��w���ψ��������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������͂����c���̔�B 1800�`2000�A�[���m�ÁB���O�̍Ō�̌m�ÁB�������邽�߁B �X��11���i�j�J �@�h�C�c�k���̃e���r�ǂm�c�q�Ŕԑg�̏����i��҂��A�u�i�`�X�x���v�̔������Ƃ��߂��ĉ��ق��ꂽ�Ƃ����O�d�B �@�V���s�[�Q�����̉p���L���ɂ��A���̔����͂������B "It was a gruesome time with a totally crazy and highly dangerous leader who led the Germans into ruin as we all know. But there was at the time also something good, and that is the values, that is the children, that is the families, that is a togetherness -- it was all abolished, there was nothing left," Herman said. �u�݂Ȃ�����悭�m���Ă̒ʂ�A�S�������������݂Ĕ��Ɋ댯�Ȏw���҂��A�h�C�c�l�ɑ傫�Ȕ�Q�������炵�����낵������ł����B�������A���̎���ɂ́A�悢���Ƃ��������̂ł��B����͉��l�ςł��B�q�ǂ����������āA�Ƒ�������A�c�R������Ƃ����l���B����́i����ɂ����āj���ׂĉ�Ă��܂��A�����c���Ă��܂���v �@�܂�A�u�i�`�X�̎���ɂ́w�Ƒ����J�x�Ƃ����������������B���܂͂��ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����v�ƌ����Ă���킯���B���̎i��ҁA���i����u���͊O�Ŏd��������A�Ƃ̒��Ŏq��Ă����A�v�̋A���҂ׂ����v�Ƃ����咣�����Ă����B���̐M���̉�������ɂ��锭���Ƃ�����B �@���{�Ȃ炱�̒��x�̔����͖��ɂ����ǂ��납�̗g����邩������Ȃ��B�e�ĕێ�̍���悵����̃^�J�h��������݂���킢�����́B����ł��A���̔��������Q�X�g�w�͎��X�Ɣԑg�L�����Z���������B�h�C�c�����������Ƀi�`�X�ɑ��ĕq�����Ƃ������ƁB�`����Ƃ̑��������̑c���̔Ƃ����푈�ƍ߂�i�삵�A���X�ƑI���ɏo����{�Ƃ͑�Ⴂ�B���{�l�ɂ́u���ȁv�Ƃ������t���Ȃ��Ƃ����Ă����傤���Ȃ��B �@1600�A�a�J�B�V�l�}���F�[���a�J�ŊJ�Ò��́u�ώ��A�ٌ`�̐l�X�h�h�v�B�����́u��������O�v�Ɓu���k���ނ��j�v�̓�{���āB�u�����v�͓r������B�O�Ƀr�f�I����Č������Ƃ����邪�r���ŃM�u�A�b�v�����L��������B�O����X�v���b�^�͋��B�u���D��v�̍����m�̋r�{�����A�Ȃ��߂Ȃ��B�O�ւЂƂ݂̐��������~���B���{�L�A�~��q�i���̍��͑����������c�c�j��̊���B�u���́����L���́v�ƃN���W�b�g�B �@�����ł��ړ��Ắu���k���ނ��j�v�B65�N���f��i�B�ē͍������B �@�����ɂ��Ȃ����ȁB�d�b�ŕv�̔��������m�炳���B�Ȃ͕v���c�����ʑ��������A���������Ƃ߂悤�Ƃ���̂����c�c�B �@�������������āA�L���X�g���B�X�����Ԃ�B�u���ނ��j�v�ƌZ�̒j�݂̓���Ő����W�A�ȁE��Ўq�A�`�Z���������A�v�̓������]���^��Y�A�|�b�q�A�t�R�t�q�A�t��܂��݁A�K���K�q������ �@�K���K�q�́u�v���C�K�[���v�̏����O���B�C�̂ӂꂽ���ŁA�܂������̖ʉe���c���Ă���B �@�����W�̉��Z�͂�������A���~�̑O��ʂ肩�����āu����̂������Ŏ��ȗ���P���ɗ����v�Ƃ�����}�t����،��}�B���ڂ��ނ��āA�⋩���锗�^�̉��Z�B�ǂ�Ȗ��ł��S�g�S��B�������ɖ��D�͈Ⴄ�B �@�펞���̐��̎����⏫�Z�ɂ�闪�D������̔w�i�ɂȂ��Ă���A�m�ق�ɂ������d�ȉ���삾���A���̃z���[�e�C�X�g�͍����Ă��F�Ȃ��B���̘I�o�͂قƂ�ǂȂ��ɂ��ւ�炸�A�ӂƂ������D�̂����������ɉ�������������̂��V�N�B �@�������A�ǂ̔o�D���A�u������e���r�Ō����悤�ȁc�c�v�C������̂́A�s�v�c�Ȋ��o�B�f��̒��̔o�D�͍��Ƃ�Ȃ����炩�B �@1830�I�f�B��]���i�ŕ������炦���Ă���V�h�ցB 1930�A�X�y�[�X�[���Ō��c���E���u�E�@�q�n�b�j�@�l�d�I�@�`�T�����v�B �@ �@�I�[�v�j���O�̃��b�N�{�[�J���A�n�f�ȃp�t�H�[�}���X�A�Z���X�̂������c�c�n�C���O�W�[�U�X�Ƃ��������c���V�����̃��C�����B�q�Ȃɂ͈��Ђł̂�B �@���ւ��Q�X�g�͉ԑg�ŋ��̐A�{���B�������ɖ��҂��ꖇ���B������A����ׂ�͂��܂��A���ӑ����̃A�h���u�������B�|�b�Əo�̖��҂͑����ɂ��y�Ȃ��B �@�Q����15���B�ׂ�̏��ҋq�͓r���őސȁB����Ȃ������̂��B �@�I����A�l�����g�����̂x�Ƃ���ɐ�����������B�H�͉�����Ƃ��B�P���Ȃ��Ƃ����c����a�q����Ɖw�܂ŁB11������C�O���C�Ƃ̂��ƁB 2300�A��B �X��10���i���j���ꎞ�X�J �@1630�A��B�������̊�e�҂��邽�߁A�l�s�ݏZ�̌����t�x�搶�ɓd�b�B�A�h�o�C�X�����������B���̏������ƂɁA���l���̋��t�ɓd�b�B�֓��쎡�搶�A���X�搶�ق������B���̎����͖��N�A�������ҏW�Ƃ�����N�̃C�x���g���҂��Ă���B���N�͂������̂���肽���B �@�ȉ��́A�E�j���̃u���O����̈��p�ɂ��A�u���Ԑl�̐푈�]���҂̋L�^�v�B Documents received from the Department of the Army in response to ACLU Freedom of Information Act Request - ���ꂪ�A�����J�̐l���c�� American Civil Liberties Union (ACLU) ���X���S���Ɍ��J�������X�g�B�C���N����уA�t�K�j�X�^���ŃA�����J�R�i���R�j�����Ԑl���E�������������Ɋւ���R�̑{���L�^�A�R�@��c�̋L�^�ȂǁB�����J�@�Ɋ�Â������ɂ��J�����ꂽ���̂��B �@�����J�ɉ������̂͗��R�����������͗l�B���������C������b���̎����͑ΏۊO�B �u���m�������A�܂���������@��Ȃ��ƕs�����q�ׂĂ����Ƃ���A���сm���O�����͕����n���w���Ⴀ�A�E�����Ă���x�ƌ����A�ނ�͉��̗��R���Ȃ����k����Ƃ��ꂳ����E���܂����v�ȂǂƂ�������������Ƃ����B �@�푈�͌Ñ���ߑ���l���E�����Ƃ��ŏI�ړI�B���̎�i����Ⴄ�����B62�N�ԁA���{�������̍����ڎE���Ȃ������Ƃ����̂��ǂ�قǑf���炵�����Ƃ��B �@���J�Ɋւ���ڍׂ́A���� "ACLU Releases U.S. Army Documents That Depict American Troops' Involvement in Civilian Casualties in Iraq and Afghanistan" �@�p��Ɋ��\�ȕ��͂ǂ����B �X���X���i���j���� �@0900�`1200�A�[���m�ÁB���1�T�ԑO�̋����m�ÁB�킸��10���̉��Z�����A���N����Ă������Ƃ͂����Ȃ��B�[���͉����[���B �@�d�Ԃ̒��ł��o�����B�S�n�悢���Q�G�̃T�E���h�̌�ɓˑR�A���o�B�u�v���C���X�g�v�ɍ��������͗l�B�������A���ꂪ���Ɍ��ʓI�B���Q�G�����o���q���a�����o�c�c�B�܂�ŋȊԂ̂l�b�B�s�v�c�Ȍ��ʁB���o�ƃ|�b�v�T�E���h�͍����B 1300�A��B�V�����[�𗁂тāA�����̕Еt���ł��c�c�Ǝv���Ă������A�x�b�h�ɃS�����Ɖ��ɂȂ����Ƃ����ɏP���1700�܂ŁB���Ă�̂��B �@ �ӂ��X�������̂��Ȃ��Ƃ͉̋C���������悤�B�����A�����Ƃ��o�čs����������Ă���B���̐S�\���̂��߂̃g���[�j���O�Ȃ̂����B �@���R�����������u�I�b�y�P�y�v�ɓo�ꂷ�钆�N�s�m�E���{���V�i�����݂̂�E���j�̂��Ƃ��C�ɂ�����A�l�b�g�Ō�������Ǝ��R�����^���̑דl�E�F���g���ق������y���Ă���B�N�����Y���u���{���V�@�������R��������Љ��`�ցv���Ï��ŏo����Ă���̂Œ����B�����ɂ͓͂��B���ꂪ�l�b�g�̂����Ƃ���B�u�قƂ�ǎ������Ȃ���ł��v�ƁA���{���̉���J����͌����Ă������A�]�`�A�S�W�ȂǁA���\�����͎c����Ă���B �u��t�����v�ɘA�����A�K���H���̌�A�O�Ԗڂɍi��Y�ɂ��ꂽ���{�B�Y�����Ȃ�����A���{�̃X�p�C�ł͂Ȃ��������Ɖ\������̑����l���B���R�����^���Ƃł���A���̎咣��ǂނƁA�V�c����ے肵���K���H����ƈ���āA�u�N�吧���a��`�v�Ƃ������ׂ����{��`�N��ς��瓦��邱�Ƃ̂ł��Ȃ������悤���B�u��t�����v�ɘA������l���Ƃ͎v���Ȃ��B �@����͂��Ă����A�����l�̋���A���{�A�m���~�̍����ɂ͋��Q����B23�̂Ƃ��ɁA���{�͂��łɁA�p�w�A���w�A�m�Z�ɐ��ʂ��A���w�Z�ł���ȋ��ނ��g���Ĉ�l�ŋ����Ă���̂��B �@�O�[�h���b�`�p���j�A�z�[�Z�b�g�o�ώj�A�M�]�[�J���j�A�[�{���_���w�A�x�C���C�g�_�A�~���o�Ϗ��A�x���T�����@�_�A�O�[�h���b�`���n�i���[�}�j�j������ �@���ł��x���T���́u�ő命���̍ő�K���v�����{�̏I���̎j�z�̃o�b�N�{�[���ɂȂ����B �@�|���āA���̓��{�͂ǂ����B���{�͂��q����ܒ��ǂ����t�B�}���K���D��������Ƃ������R�ŃI�^�N�ɐl�C�̂��鐭���ƁB���z���v�z���Ȃ��A�n�V�ɂ��_�ɂ�������Ȃ��c�������B�����̒m���l���猩����Ԏq�̂悤�Ȃ��̂��B�j�āB �X���W���i�y�j���� �@0630�o�ЁB�[���܂Ŏd���B�������茳�̃y�[�X�ɖ߂��Ă��܂��B�������ł����Ă��A�ڂ̑O�Ɏd��������ƁA������o���Ă��܂��B���ʓI�Ƀn�[�h�Ȉ���ɁB���Ȑ����B �@���傤���疺�����C���h�B12���Ԃ��Ƃ���̂͐��܂�ď��߂āB �@1700�A�ѓc���B�u�g���m�v�ō��Z���������B����O�̍Ō�̑ł����킹�B�X�̃I�[�i�[�͂n�ԏo�g�B������ɂ��Ȃɂ��ƕX���͂����Ă����B �@��������̐�y�E�r����B���j�ŁA���e�͍���B�ŋ߁A������ɗ��e���Ă��A���N�ň����g���Ă��܂����Ƃ��B�c�ɂŕ�炵�Ă����l�ɂ͓s���炵�͂������Ȃ̂��낤�B�r����̐S�z�́A����̗��e�̂��ƁB����̂��Ƃ������ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��c�c�ƁB �@�ŁA��������k�`�B���܂��o�Ȃ��Ă���20���̕����쉀�W�̎d�������Ă���Ƃ��ŁA���̕��ʂ͏ڂ����B �@���܂Łu�i�㋟�{�v��������Ă����B�ŏ��ɋ��{�����A�i�v�ɂ��悪����������̂��Ƃ���v���Ă������A�u�オ�r���Ƃ��̎��_�ł���͑ł����A����͍X�n�ɁA�����͖������Ɉڂ����v�̂��Ƃ��B�m��Ȃ������B �@�����̏ꍇ���A���N�h�Ɨ������������́A������g���邪�A���ꂪ�r�₦���玛�ɂ����Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B �@����͗\�z�O�B���R�ƁA�u�N���K���l���Ȃ��Ă�����͉i���ɑ������́v���Ƃ���v���Ă����B �@����������ŁA���e�̂���ɓ���A���̂��ƁA800�`���ꂽ�s��ɏZ�ގq������������Q��ɗ��Ȃ��Ă��A�����Ɨ��e�̌��ŁA����ɂ�������̂��Ƃ���v���Ă����̂������B �@�܂����A�u�h�Ɣ�̑��v���r�ꂽ�炨���ǂ��o�����Ƃ͎v���Ă��݂Ȃ������B �@�m���ɁA����Ȃ������ł͂������ێ��ł��Ȃ����낤���B �@�ŋ߁A�A�����J�̕x���������̂���Q�������������邱�Ƃ������ɔ���Ȉ�Y��e���ɑ������Ƃ����j���[�X�����悤�ȋC�����邪�A�u�Ȃ�Ŏ���������̂���Q����C�ɂ���̂��낤�v�ƁA�����ł��Ȃ������̂����A�����A�����̐g�ɒu��������ƁA���̕x���̐S�z���킩��悤�ȋC������B �@10���70�N���ۂ̐�����A�u�@���v�I�Ȃ��̂ɂ͒����ԁA���⊴���������B���ɁA�������ƌ������킸�A���Տ@���Ɖ��������{�̑����̏@�h�ɂ́B���ꂪ�A���́u���Տ@���v���߂��銋�����킪�g�ɍ~�肩����Ƃ́B �@�ꂪ�S���Ȃ肻�̂X�N��ɕ����B���̌��Ă����h�Ȃ���ƕ��d�B�u����ȗ��h�Ȃ̂�����Ă��܂��āc�c�v�ƁA���̐e���̈�l��������ݒׂ����悤�ɂԂ₢�����Ƃ��������B���̈Ӗ������߂Ēm�邱�ƂɂȂ�B �@����Ƃ́A���̓y�n�ɏZ�ݑ����邱�Ƃ�O��ɂ������́B���e����p��������͎����̎q��Ɉ����p�����Ƃ��ł��邩�Ƃ����c�c�B �@��̂��߂ɕ�����������h�Ȃ���B���߂�33������I���܂ł͑��������������́B�������Ă݂�ƁA�����́u33����ň���B����ȍ~�͋��{��ł��邱�Ƃ��v�Ƃ����@���̂�������ɂ͗��R���������̂��B�u�̐l�̋��{�͂��̌̐l��m��e���̈ꐢ��ōs���v�Ƃ����B �@�����@���M����n�܂��āu�e�a�v�̎O���A���Y�A�u�։�v�̔��֖��G�ƁA�����ē�����̂���k�`�ƁA���̂Ƃ��둱���������L������B �@�u���v�ƌ��������N��ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B �@��͐_�y��́u�M���v�B���X�ؔ~������͕s�݁B�����́u�g���m�v�̃I�[�i�[�̖��B �@�r���A�x�c�A�x�c�e�q�A�v�сA�g�c�A�s����̂V�l��2230�܂ŁB�̋��k�`�₢���Șb�ɉԂ��炭�B�̂Ă�ꂽ���L20�C�]�����炵�Ă���Ƃ����x�c����̃{�����e�B�A�����ɂ͋�������B�u���L�́A�l�Ԃ̎q���Ɠ����B�ڂ���S���`����ł��v�B���X�̂�����T���~�B���s�ȂljƂ��邱�Ƃ��Ƒ��Œ������Ă���Ƃ����B�ƂĂ��܂˂͂ł��Ȃ��B�G�X�Ƃ����x�c��������Ȃ��Ƃ����Ă���Ƃ͏��߂Ēm��B �@2330�A��B �X���V���i���j�J �@�d�Ԃ��������S�z���������A�_�C���̗���͂�����̂̒ʏ�^�]�B0630�o�ЁB �@���̂����͕��J�B�ߌ�ɂ͑䕗��߂ŋC���㏸�B �@1900�A����x�m�����ɂ���m�Ï�ցB�w����15���B�u�p�b�`�M�I�v�̋r�{�ƁE�H������ɂ���V�h�|�\�Ђ̌m�Ò��B���m�̐����ЎЈ��E�g�{����ɗ��܂�A�O���r�A�E�^�����g�̕����b�������ɓ˓��B��l�ł͊댯�Ǝv�������A�H���������ȁB�܂�Ŗ����������e�i�H�j �@14������n�܂�u�ւ��̂͂Ȃ��v�ŏ�����̕��������A�C�����Ŗ��邢23�B���̕��䂪���������Łu���D�v�ɖڊo�߂邩�B �@2000�A��B �X���U���i�j�J�@�䕗 �@�P�U�R�O�A�\�j�[�l�`�̂v�ӎ��Ƃg�䎁���ЁB���_���͈���}�l�W�����g���邱�ƂɂȂ����Ƃ��ŁA���̏��B �@1800�A����B�R��y��B���y�b�c�F���Ă������A�ӂƖڂɂ����@���b�c����ɂƂ��Ă݂�B�e�@�h�̂��o�b�c�B���i�Ȃ��Ό����������Ȃ��̂ɁA�����̗��ꂩ��A���������ɂ����A�����Ă��܂��B�u��y�@�v�̂��o�b�c�B���āA�u�̂��܂��@����@�������@����Ă��v�́A�����Ă��邩�B �P�W�R�O�A���@�e�A�g������Łu���֖��G���y������v�B �@��ꕔ�͏���̂��A��̓V�����\���B �u�t�͂��ŋ��A�H�̓R���T�[�g�B���̊Ԃɍu�����������āA���̕��������{���ǂ��ɂ��������Ƒi���Ă��܂����B���N�A�悤�₭���̊������Q�@�I�Ŏ������т܂��āc�c�i���j�B�ł��A�܂��O�@�I������܂����v �u���{�̕������A�ǂ����ċʍӂ�I��A�ߗ��ɂȂ邱�Ƃ����ꂽ���B����́A���n�Ɏc���ꂽ�Ƒ���e�ʂ̂��Ƃ��v���ĂȂ̂ł��B�ߗ��ɂȂ����g�����������瑺�����ɂ���܂��B���{�̕����͗E�҂Ŏ�������Ȃ������̂ł͂Ȃ��A�����Љ�̒��ʼnƑ������Q����Ȃ��悤�Ɏ���I�����v �@�̂̍��ԂɁA�ۂ�ۂ�Ɣ�яo���A�푈�ƃt�@�V�Y���ւ̕���B �u�j�Ə��A���Ə��A�j�ƒj�c�c���ɋ�ʂ͂Ȃ��B����������Ȃ��Љ�̋]���ɂȂ��Ď���ł������F�l�̖��O���v���v�Ƃ��B �@�@���ʂƕn���̎��g�̔����B���֖��G���u�Ō�̐�㖯���`�ҁv�ƌ������̂͒N���������B�ĂьR�C�̋������������Ă��鍡�̎�������֖��G�̔����̍��ɋ�������B �@�I����A���j�Îq�Ɨ��b�B�ΐX�j�Y������l�ŋ��������Ă��ꂽ�Ƃ̂��ƁB�u���v�㉉�ł��邩�c�c�v�Ɛ��B�ŋ߂͗��������Ă�悤���B �@���R������X��Η����ƈꏏ�Ɋy���ցB�]�����ق��K��q�������A�ʉ�܂łQ�O���ȏォ�����Ă��܂��B �@�y���̔��ւ���B�u�Ȃ��N���Ƃ�x�ɁA�s�v�c�ƃp���[�A�b�v���Ă����݂����v�Ƃɂ�����B�m���ɁA���ʂƂ����g�[�N�Ƃ�����D���B �@�Q�Q�Q�O�A�w�ցB�䕗�ŎP���܂��قǂ̋����B�r���A�M���̏�⋭�����ӂʼn��x���X�g�b�v�B�Q�R�D�R�O�悤�₭�A��B �X���T���i���j����̂��J �@�O�V�O�O�N���B�S�~�o���B �A�Ȏ��̓��L���܂Ƃߏ����B �@�O�U�O�O�A�C�����I�����c�u�c���R�[�_�[�̍�i���c�u�c�Ƀ_�r���O�B�r���ŁA���̉f���̋����Ɏ䂩��āA���̂܂܌��n�߂Ă��܂����ԑg������B�X���q����e���ŏo�Ă�����j�v���X�e�[�W�u���ꂳ��@�ڂ������܂�Ă��߂�Ȃ����v�i�V�������j�B�Ƃɂ��Ă��h���}�����邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��̂ɁA�������܂�Ă��܂����̂́A��V�����������Ȃ���A�ɗ́u�����Ƃ��v��r���A�W�X�Ƃ����M�v�ŕ`�������o�ƁA�r�{�̂悳�A���c���I�A�ɓ��������A�ߌ��C���̉��Z�ɕ����Ƃ��둽���B�]���}�q�̏��N���������n�Ӓ����̉��Z�͂܂��ɐ_�Z�B�X���q�����Z�������Z�B�P�Ȃ邨�ܒ��Ղ��̂ł͂Ȃ��B�P�T�Ŏ��S������l�̎�҂̐������������ɂ���B���炦���ꂸ�ɉ��x���j��B �u���߂�Ȃ����ˁ@����������^���߂�Ȃ����ˁ@����������^�ڂ������܂�ā@���߂�Ȃ����^�ڂ���w�����@��������́@�ׂ����Ȃ��Ɂ@�ڂ��͂����^�ڂ������@���܂�Ȃ�������@��������́@���炪���Ȃ������낤�ˁ^�傫���Ȃ����@���̂ڂ���w�����ĕ����@�߂��݂��@�u������Ȏq���ˁv�Ƃӂ肩����߂��������Ɂ@�������Ƃ��^�ڂ������@���܂�Ȃ�������v �@�����ɒ����Ɂu������v�Ƃ����u���ʕ\���v�������Ďg���A���̐���p���͂����B �@ �X���S���i�j���� �@���́A�l�Ԃ�����������Y��Ă�������ՂɂȂ��Ă��܂������̂悤�ɓ��퐶�����삯����Ă��鎩���c�c�B 1400�A�a�J�p���R����ŃV�A�^�[�i�C���X�u�V�F�C�N�X�s�A�\�i�^�v�B�n���������̂������̍����Ɣނ���芪���l�X�̐S���Ɛ�����`���⏼���̐V��B���G�Ȑl�ԊW�A�����Ȃ��̒E�E����B���l�ɂ̓E�P�邾�낤���A���{�K�l�Y�ړ��Ă̈�ʂ̂��q����͂Ƃ܂ǂ�����B�p���R�ŁA�K�l�Y���⏼�������Ƃ����̂͂��Ȃ�̖`���B�q�̓�����L�тĂ��Ȃ��Ƃ������c�c�B�ɓ����A���������A���삽�܂��A���{�I�ۂق��B �@�]�X����Ɖw�܂ŁB�u�ڂ��͊⏼����D��������B�ł��A�K�l�Y�t�@���͂ǂ��Ȃ낤�H�v�ƁB 1800�A�X���B���؉��œ��j�����C�X�B 1900�A�x�j�T���E�s�b�g�ŗ��R�����������u�I�b�y�P�y�v�B�}�������ϐ��h�v�V���Z���N�V�������e�B�ϐ��h�v���o�E�o���̗\�肾�������A��������Ȃ킸�B �@�����E�吳��w�i�ɁA�I�b�y�P�y�߂ňꐢ���r������㉹��Y�����f���ɂ����v���Ɣs�k�̕���B1962�N�A60�N���ۂ̔s�k�ƍ��܂��Q���~���[�W�J���u�^�c���_�^�v�ɑ��������c�P�V�B���̑��e�Ƃ��ď����ꂽ�Q�����B �@���A�}�_����z�A�K���H��������f���ɂ��Ă��邪�A�j�q���X�g�Ƃ��ĈÖ�A�v�������鉜���Ԏ��݂̂��َ��B����J���K�����鉜���͉��{���V�Ƃ�����t�����ɘA�����A�O�Ԗڂɍi��Y�ɂ��ꂽ�l�������f���B�����ł́A���łɏ{���߂��A�ߋ��̉h���Őg�߂����߂����Ă�����d�ƂƂ��ĕ`�����B��ɂ���Ė����ɋÂ鉖��J�A�����s���R���Ƃ����ݒ�ŁA���ʂȂ������ēo�ꂷ��Ƃ�����A���ɖؘg���͂߂ăK�c�b�K�c�b�Ɖ��������Ȃ���̓o��B �@�I�b�y�P�y�Ō��͂h���A�v������������A����Ɍ��͂Ɏ�荞�܂�A�������I�푈���@�ɁA��Ӎ��g�����㉉����悤�ɂȂ�E�]�����Ă�������Y�B���X�g�V�[���͋������̈��b�C�炪�A�I�b�y�P�y�߂Ő푈���ɗ������Ă����B�������̊ϋq�����藐��Ă̋��에���B �@�����ŌJ��Ԃ���铌�m����{�������āB����15�N�ɉ����炪�Q�悵�č�������@���āB���ɗz�̖ڂ����邱�Ƃ͂Ȃ��������A���̑�70���� �u���{�����Ɉᔽ�X���g�L�n���{�l���n�V�ɏ]���U���R�g�����v ��71���u���{�����������׃X�g�L�n���{�l���n�V���r�˃X���R�g�����v 72���u���{���j�����j�w�L�l���m���R�������c�Q�V�����m��|���W�O�����n���{�l���n�V�����ŃV�V���{�����݃X�������v �@�v��A70���́u���̐��{�����@�Ɉᔽ����s�ׂ��s�����Ƃ��͍����͂���ɏ]��Ȃ��Ă������v�B71���u���{�y�ъ������s���Ȑ������s���A��������������Ƃ��͍����͐��{�E������r�˂ł���B 72���u���{�����@�ɔw���č����̎��R�⌠����D�����A�����͐��{��]�������A�V�������{�����邱�Ƃ��ł���v�Ƃ������ƁB �@�܂�u�v�����v������Ƃ����B�吳����̌��@���Ă̊v�V�I�Ȃ��ƁB �@���̑吳�̌��@���ĂƑΔ䂷�邩�̂悤�Ɍ���̓��{�����@�O�����Ō�ɌQ�ǂ����B�������A�m�C�Y�Ɖf���ŁA�R���[�W���B �@����J���͂��̌��@�N�ǂɍŌ�܂Œ�R�����Ƃ����B�u�����łł��Ȃ����Ƃ������ł���Ă���̂��B����܂ł���Ă����̂͂Ȃ����̂��B�����ɉ����������Ă͂����Ȃ��v�ƁB���̕ق������ł��邪�A���R���̎v�����킩��B�吳����̊v���I�Ȍ��@���ĂƍŌ�Ɍ���̌��@�O���̊i���������t��Δ䂳���邱�ƂŁA����̏����Ԃ肾�����Ƃ��܂���̉��o�B �@�X��25���I���B�Q����25���B �@�V��V�X�A�����i�A�ᐙ�G���Ɨ��b�B�ᐙ�W���j�A��11�J���B�u���������Ă܂���A�����������݂����ł��ˁv�ƏΊ�B������̎����Ȃ݂͐V�����Ŏŋ��B�u�ڂ������x������B��l�Ƃ��d�����Ă܂��v�B �u����v���悩����������ƃ~�c�o�`�k�`�B�u�ŋ߈ُ�C�ۂȂ̂��A���m�~�c�o�`�ł��������p�ɂɂ��邻���ł��v�ƁB�������ĂɃn�`�������瓦���o���u�����v�̓j�z���~�c�o�`�����Ƃ����̂�������������B �@�A��ہA���É��̂g������Ƒ����B�҂����킹������炵���}���ł����l�q�B���b���ł����B�c�O�B �@2130�B�i�����ŏ������t�B���c�}���[�A�`�۔��q�b�A����̖�������Ɨ��b�B10�������̑�{�͂܂��[���Ƃ��B���ƂP�J���c�c�B����J����Ǝŋ��̘b����������ƁB �@2200�A�ޏo���ԂȂ̂ň����グ�B �X���R���i���j���� �@0630�o�ЁB�܂��S�͉��ʂ����Ԃ��Ă���B�y���}����ԁB�����Ƃ̂����̃W���[�N�̃W���u�̉��V�Ŏ���ɋC����������Ă����B���N�̂��ƁB�ߌ�ɂ͉��邾�낤�B �@1700�ގЁB���˃t�@�N�g���[�ŗӌ��Q+�t�B���s�����ی𗬃v���O�����u�����̖[�v�i�쁁���l�EO�E���B���k�G���@�A���o���|����Y�j�A�u����\�y�W�@�O�l�o���v�i�쁁���m��A���o�������T�h�j�B �@�x�ݖ����̓��ɂ́u�����̖[�v�̃Z���t�͂قƂ�Ǔ͂����B�O�Ȃ̂r�������������Ƌ�����B�u�O�l�o���v�͎h���I�Ŗʔ����B�^�钆�A���A���l�̌���ɖ��������m�����B�����ŏ㉉�����u�O�l�o���v�������鏗�D�����B�ޏ������͗H�E�̎҂Ȃ̂��A����Ƃ��A���m�������c�c�B�����T�h�̉��o���ΎG����}���A�H���������������B 2100�I���B�d�Ԃ̒��œ����ƃo�b�^���B�������B �X���Q���i���j���� �@�c�ɂ���A���Ă��������͂܂��זE�̔����͓c�ɂ̂܂܁B�c�ɂʼn߂������P�T�ԂŃn�����Ɨ��Ƃ����A�x���A�˂��݁A�~�]�A���ȁA�����Ƃ��������Ȗh�q�̃g�Q���Ăё̂̂����������琶���ė��āA�܂��s��ɓK�����Ă����̂��킩��B�u�R���L�v�́A�ՂɂȂ��������̂悤�ɁA�c�ɂł̎����Ɠs��ł̎������������A����ɓs��̎����ɕϐg���Ă����B���ȕ��B�����̊ό����s�Ƃ͈Ⴄ�A�c�ɂɂ���̂͂�����l�̕ʂ̎����Ȃ̂��B�זE���L�V�~�������āA�s��ɓK�����悤�Ƃ��Ă���B�����̂��ƁB���ƂQ��������A�u�c�ɂ̎����v�͂�������Y��邾�낤�B�������A���̊����B������15�N�A�l���̂ق�̃g�o�����߂����������̌̋����Ȃ�����قǗ��炤�̂��A���邢�͑��ނ̂��B �@0900�`1200�A�[���m�ÁB���ʂ͐R�����ɁB���̂��߁A�����̏o�Ȃ͑s�N�U�l�ƈ�ʂQ�l�����B �@�m�Â����Ă��邤���ɁA���X�ɐS������ɉ�A���Ă���B �@1300�A��B�P�T�ԕ��̐V�����܂Ƃߓǂ݁B���ς�炸�E���Ƃ������̒��B �X���P���i�y�j���� �@0600�N���B0900�A�R���u�����I�����r�g�f�����J�j��C�J���l�߂����A�X�`���[�������o�C�N�ɐς�Ŏ����Ă��Ă����B�e�ʂ��炢�����������݂₰�ő�}�ւ����Ȃ�̐��ɁB���肪�������Ƃ��B�������A���ׂĂ͍��܂ł̕���̐l���̂������Ȃ̂����B �@0930�A�˒�������ĉƂ��o��B��͏]���̒U�߂���̂j��������d�C��������Ă����B��������肪�������ƁB �@���Ԃɐe�ʂ̉Ƃ��܂���Ĉ��A�B�Ō�͂r�g��������B��̌Z��̒��ł��Ƃ�킯�C�������D�����܂��낢�B�q���̍��͂悭�u�����肵�Ă����߂����B�w�Z���Ƃ�������ƂɋA���Đe�F�s���Ȃ����ȁv�ƌ����A�����������̂����A����͔�������̗��e���C�����D��������o�����t�B���ɂ��Ă����|���̏d�����킩��B �@1200�A�l�s�����B�܂�����v���U�ŐH���B���Ԃ�����̂Ńm���r�����Ă������A�Ό������Ɂu�����܂��فv�Ȃ鋽�y�����ق��ł����̂ɍs�������Ƃ��Ȃ������B���v������Ɨ�Ԃ̎��ԃM���M���B���킽�������ٓ��������蔲���A�n���w�ցB�������邽�߂̎��Ԃ��M���M���B�a���̂Ƃ���Ɋ�낤�Ǝv�������f�O�B �@���N�����͒��w�̉��t�g�搶�̏��ɂ����ז����悤�Ǝv������������A�E�g�B���Z�̌������搶��97�B�����C�Ȃ�Ή���čs�����Ǝv�����̂Ɂc�c�B�\��͂قƂ�ǃ_���ɁB �@1415�A�n�����̗�ԂŋA���̓r�ɁB �r���������Ȃ��A1930�A�A��B |