|
望遠鏡の対物レンズがどのように設計されていくかを、自分なりにいろいろやってみて、まともな結果が出たみたいなので、手順を公開しちゃいますっ! 光学設計テクニックは、光学メーカーの企業秘密(?)らしく、どんな本を見ても、「このままでは十分な補正が行われていません。そこで、何回かベンディングを繰り返した後の結果を次に示します」などと、うやむやにされています。計算量が膨大で、苦労するのはわかりますが、設計をどうやって追いつめるのかも興味のある部分ですからね。 |
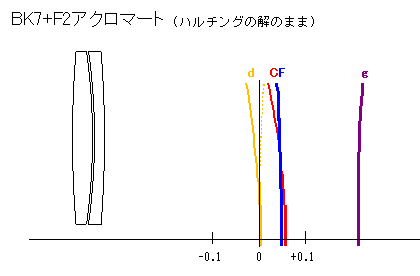
|
ハルチングの公式とは、使用する2つのガラスの屈折率とアッベ数を与えると、2つの色で色消し、1つの色で球面収差とコマ収差がゼロ(=アクロマートという)というレンズの曲率半径を求めることができるという便利な公式です。16個の式を順次解いていくだけですし、一番難しい計算が平方根なので、パソコンに式を入れておけば、すぐに結果が出ます。(*1) 例としてBK7(n=1.516330、ν=64.14)とF2(n=1.620041、ν=36.26)の解を示します。ハルチングの公式では、解が2つ出てきます。 解1 r1=+0.60610 r2=-0.35642 r3=-0.36063 r4=-1.48053 解2 r1=+0.15906 r2=+0.54597 r3=+0.17718 r4=+0.12917 この曲率半径は、焦点距離=1の場合なので、数字が非常に小さくなっています。 解2の方が曲率半径が深くなるので捨てます。実際に解2を活かして計算を進めると、ガウス型のような形になりますが、あまり収差補正状況は良くないようです。 また、ガラスを逆に指定すると、スタインハイル型(前が凹、後ろが凸)というタイプになります。 |
(*1)実は、もっと簡単な方法もあります。これは後述。 |
|
ハルチングの公式で求めた解は、焦点距離=1のときの曲率半径です。これを実際に使える大きさまで引き延ばします。光学では焦点距離=100にして評価しますが、実物の望遠鏡としての評価なら、口径70mm〜100mm、F6〜F15ぐらい(焦点距離400mm〜1500mm)の望遠鏡を想定した方が現実的です。。 ここでは口径100mmF10としましょう。口径100mmF10なら、焦点距離=1000mmですから、曲率半径も1000倍に拡大します。 拡大したR r1= +606.10 r2= -356.42 r3= -360.63 r4=-1480.53 (単位:mm) |
|
厚さのないレンズは存在しませんから、厚みを与えます。もちろん、レンズに厚みが加わることで収差や焦点距離などが変動しますが、後で調整するので今は気にしません。 レンズは、薄いほど材料費がかからなくて済み、かつ、(一般に)収差補正に対して有利に働くのですが、自重で歪むのも困ります。このような理由から、 凸レンズ=コバ(レンズのフチ)の厚さが直径の5% 凹レンズ=中心部の厚さが直径の3〜4% また、量産するときの検査上の理由から0.05mm単位に丸めます。 レンズの直径も、光が通る部分の直径が100mmなので、レンズをおさえる部分も含めて外径を4%増しにします。この直径から中心肉厚を求め、曲率半径の出っ張り・凹みを考慮して中心間隔を決定します。 レンズ間隔 d1= 11.25(BK7の肉厚) d2= 0.10(レンズ間隔) d3= 6.25(F2の肉厚) (単位:mm) これで必要なデータはそろいました。ここから先がテクニックです。 |
|
焦点距離を求めるにあたって、レンズの肉厚・間隔を一度 焦点距離=1相当に縮小します。現在、焦点距離=1000mmを想定しているので、間隔も一旦1/1000に縮小します。 これで、最初に求めた焦点距離=1相当の曲率半径と、1/1000に縮小したレンズ間隔を使って焦点距離を求めます。ハルチングの公式で求めた場合と異なり、今度は肉厚がありますから、焦点距離は1になりません。厚みを含めて再計算すると、次のようになります。 焦点距離=1.00158 |
|
焦点距離の再計算で、実寸での焦点距離が1001.58mm相当になることがわかりました。自作ならばこれで納得して使えばいいのですが、工業製品となると、そうはいきません。せめて設計ぐらいは希望通りに1000mmにしたいところです。 そこで、焦点距離=1.00158が実寸の焦点距離=1000mmになるように、曲率半径の拡大率を998.42倍に変更して拡大しなおします。 再拡大したR r1= +605.1379 r2= -355.8613 r3= -360.0596 r4=-1478.1886 (単位:mm) この曲率半径を使って、再度肉厚を求め、焦点距離を求め直します。 拡大→肉厚計算→縮小→焦点距離計算→再拡大の処理を数回繰り返すと、焦点距離=1000mmちょうどのレンズデータが得られます。F10ぐらいの暗い光学系ならば、4〜5回ほど繰り返すだけで、ほぼ数字が収束します。 収束後のR r1= +605.1338 r2= -355.8589 r3= -360.0572 r4=-1478.1787 (単位:mm) |
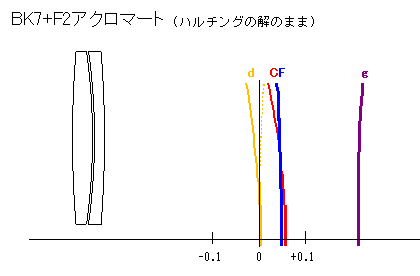
|
現段階でどこまで補正できているかを、球面収差図でチェックします。 d線(黄色い実線)のカーブが前倒しになっているので、球面収差が負修正、OSC(正弦条件不満足量。黄色い点線)もd線に対して開いているので、コマ収差も多そうです。これらの収差は、レンズに厚みが出たために発生した収差です。 BK7-F2ペアでは、そのままでも結構いい所まで補正されているのですが、設計図ぐらいきっちり補正しておきましょう。 |
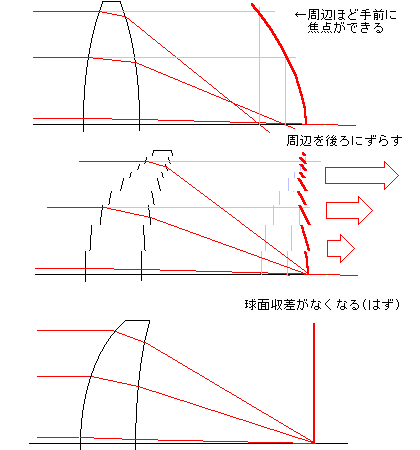
|
球面収差図というのは、光軸に平行な光が、屈折したあと光軸のどこを横切っていくかを示したグラフです。線が前に倒れるということは、周辺の光が手前に焦点を結んでいるということになります。 原理がわかれば、補正は簡単。理屈としては屈折する場所を収差量に応じて後ろにずらしてしまえばいいのです。周辺ほど手前に焦点を結んでいるのですから、全体を「( (」のように弓なりに曲げてやれば、簡単に補正できます。この辺は、単レンズでも2枚以上のレンズでも同じです。 |
|
ベンディング(机上でレンズ形状を少しずつ変えて、最適値を探す作業)を行って球面収差が最小になる曲率半径を探します。ベンディングを行うときに注意することは、第一面の曲率半径を変えたら焦点距離が変わらないように必ず第二面も同時に変更する点です。適当に1つの面だけの曲率半径を変えてしまうと、様々な収差が一斉に発生し、収拾がつかなくなる(*1)からです。 曲率半径を0.1%ぐらいずつ、少しずつ変えていきます。 球面収差の補正は、1つの色でしか行えないので、普通はd線で補正します。 |
(*1)全体の焦点距離を(ほぼ)維持するように2面を同時にベンディングできる光学設計ソフトには残念ながら出会ったことがありません。ここが自動化されていないと、先に進めないのです。 |
|
レンズが2枚しかない場合のベンディングパターンは「( (」「) )」「( )」「) (」の4つしかありません。「( (」「) )」の2種類は、単純に球面収差に直接影響する動きなので、球面収差を変えずにコマ収差量だけを補正するには、「( )」「) (」のどちらかの動きで補正するしかありません。BK7-F2の組み合わせでは、「( )」型に曲げてやると良好にコマ補正できるようです。コマ収差の補正は、球面収差図を見ながら、何度もベンディング(*1)を行います。 | (*1)くどいようですが、コマ補正をするには4面同時にベンディングする機能が必要です。 |
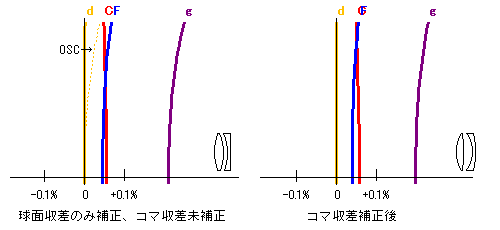
|
↑は、d線の球面収差補正後と、コマ収差まで補正したときの球面収差図です。球面収差図には正弦条件不満足量(OSC)も同時に載せます。黄色い点線がOSCです。これが曲がっているとコマ収差が多いとされます。補正後は、d線とOSCがぴったり重なって、図には現れません。 一連のベンディング作業は、焦点距離=1のデータに対して行います。球面収差図のスケールがパーセントになっているのは、実寸ではないためです。 収差が良好に補正されたら、もう一度、拡大のやり直しから、再計算します。ベンディング作業では、焦点距離を変えないように制御はしていますが、やはり微妙な影響は与えています。焦点距離を求め直して拡大率を見直し、最終的に得られた結果は、次のようになりました。 球面収差・コマ収差補正後のR r1= +479.9824 d1= 11.25 BK7 r2= -421.7763 d2= 0.10 r3= -411.7371 d3= 6.25 F2 r4=-3013.7675 (単位:mm) 曲率半径はかなり変わりましたが、断面図自体はほとんど変わりません。気分的にどう曲げたかを収差図の隅に示します。 |
|
リトロー型は、収差補正よりも作り易さを重視した設計の色消しレンズです。 2枚のうすレンズ(*1)を密着させたとき、f1/f2 = -ν2/ν1 という条件を満足したとき、色収差が最小になります。ν(アッベ数(*2))は、ガラスの種類で決まりますので、ガラスを選ぶと焦点距離の比率が決まります。色収差の量は、使用するガラスの種類を決めた時点で決まってしまうのです。焦点距離の比率が決まっても曲率半径は任意に選べてしまうので、とりあえず、r1= -r2 = -r3 となるように曲率半径を決めます。凹レンズの焦点距離は決まっているので、r4も必然的に決まります。 リトロー型は、この設計のまま制作に入ります。かなりいい加減な設計ですが、F20ぐらいなら実用になるそうです。 さて、ハルチングの解で得られたデータも、肉厚を与えると収差が大きくなりました。どうせ補正しながら進まないと最終的な解が得られないのなら、ハルチングの解を無理に使う必要はありません。そこで、フランホーフェル型の設計図のたたき台として、リトロー型の設計図を使おうという作戦です。今のパソコンなら収差図の描画は瞬間的にできますから、多少遠回りになるぐらいの影響しかありません。 |
(*1)事実上厚さを無視してよいレンズのことです。 (*2)部分分散比の逆数で、ガラスの持つプリズム効果の度合いを示す数字です。 |
|
たとえば、ペッツファール和を求めると、像面湾曲半径が-5311mmの凹面と計算されます。実際の写真では影響が少ない量ではありますが、完全な平面像にする手段は、もうありません。使える自由度をすべて使い切ったためです。像面湾曲の補正まで行うには、最低でももう1群のレンズ(フィールドフラットナー)を追加して補正の自由度を上げなければなりません。 写真用として使えるようにするには、さらに非点収差も補正する必要があり、レンズ構造そのものを見直す必要が出てきます。言うまでもなく、2枚だけでは、もうどうにもなりません。 |
|
色収差もベンディングで制御できない収差です。一度ガラスの種類を決めて、ハルチングの解で色消しになるような焦点距離ペアを決めてしまうと、あとは制御できません。 色収差を補正する手段として、もう一枚レンズを追加して、収差補正のポイントを少しずらして計算し、かけ離れたg線を寄せるような修正も考えられます。しかし、3枚玉ともなると計算が非常にややこしくなることに加え、レンズ系全体が厚くなり、気温になじみにくくなる問題も発生します。 であれば、2枚玉の範囲内で最初から良好な結果が期待できそうなガラスのペアで計算したらどうなるでしょうか? EDガラス(異常部分分散ガラス)や蛍石(フローライト)を使うと、アクロマートと全く同じ手法で計算をしても、諸色収差が著しく良好に補正され、勝手にアポクロマート(3色色消し、2色でのコマ収差補正(*1))になってくれます。たとえば、ハルチングの公式でg線を考慮した計算をしていないのに、ちゃんと寄り添ってくれます。通常、EDガラスよりも蛍石の方が良好に補正できます。 これらのガラス(結晶)の最大の難点は、桁違いに材料費(+加工料)が高価なことです。10cmアクロマート屈折が5〜6万円(定価ベース)なのに対して、EDで10〜12万円、フローライトで20〜25万円ほどです。鏡筒などの他の部品にかかるコストが2〜3万円程度であることを考えると、いかに高価かわかります。 | (*1)厳密には2色コマ補正は、2枚レンズでは無理ですが、事実上無視できるほど小さくなります。 |
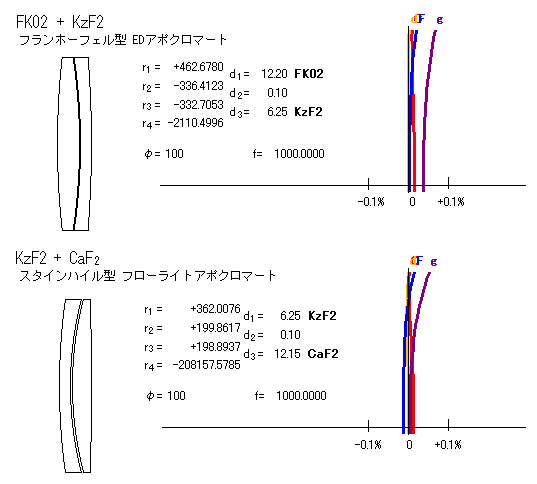
|
眼視向きに補正してみましたが、蛍石の方が全体のまとまりが良くなっています。 EDや蛍石を使うと、諸色収差が著しく良好に補正されるのですが、手放しで喜べない点があります。 上の球面収差図で、g線そのものの球面収差量が蛍石の方が多い点に注目してください。スタインハイル型という形式にしたこともありますが、EDより蛍石の方が屈折率が低いために曲率半径を小さくしなければならず、その影響で他の色の球面収差が多くなっているのです。また、単色の球面収差も直線ではなく、かなり曲がっています。「EDや蛍石は短焦点向き」と、どこかにあったような気がしましたが、本当はあまりF値を明るくしてはいけないのです。 |
|
球面収差図や曲率半径は、自作ソフトによる算出ですので、数字そのものには信憑性がありません。f(^^) しかし、この「最終微調整ノウハウ」を盛り込んだため、球面収差除去まで1分、コマ補正まで入れても5分で設計を完了できるソフトになってしまいました(全自動も可能ですが、あえてやりません。)。光学評価ソフトは数あれど、設計ソフトはなかなかないですねぇ。 |