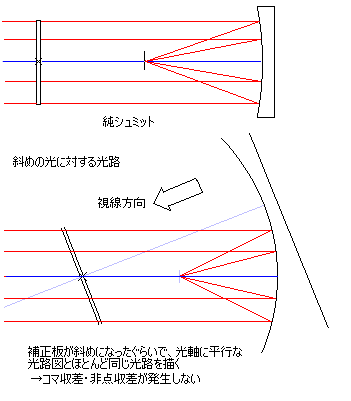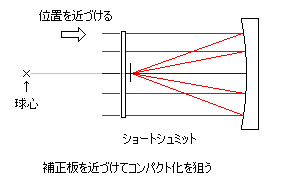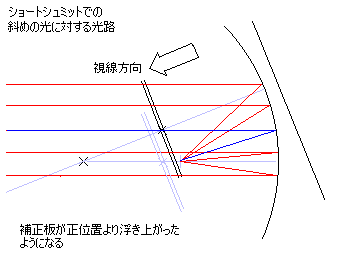140SSは、ハレー彗星ブームの時に発売された、シュミットニュートンという、ちょっと変わった光学系です。当時でも定価ベースでも\65,000程度(鏡筒のみ)と安かったように記憶しています。
値段が安く、寸法も小さいためか、初心者向けのお手軽望遠鏡に見られていたようで、あまり注目されていないようでした。F6のニュートンでさえ「コマ収差が多くて実用的でない」とさえ言われることもあるのですから、F3.57という写真レンズに匹敵するF値は、「きっと良く見えないに違いない。写真専用設計で、精度的にも手抜きをしているだろう」と予測させるに充分な仕様でした。
この140SSは、ハレー彗星特需対応望遠鏡と言い切ってよいでしょう。ようやく非球面の補正板を量産できるようになった時期にハレー彗星特需が重なって、この時期に作られたシュミットカセグレンは評判が良くありません。
ところが、非常に精度の高い作りをしていることが後に明らかになります。
2005/12/05