・入眠障害…寝付くのに普段より1時間以上余計にかかる
・中途覚醒…一旦寝付くが、一晩に2回以上目が覚める
・早朝覚醒…朝早く目が覚めてしまい、それから眠れなくなる
・熟眠障害…寝てはいるが、起きたときに熟睡したという感じが持てない
持続時間による分類
1. 一過性不眠…急性のストレス状況(不安、痛み、旅行、突然の病気や入院等)
持続は数日程度
2. 短期不眠…持続性のストレス状況(仕事や家庭生活上のもの、仕事の時間帯の変化等)や
急性の内科的,精神的な病気に関連して起こる。持続は1〜3週間程度
3. 長期不眠…持続1ヶ月以上の本格的な不眠
1や2は、専門的治療を受けなくても、一般科で処方された睡眠薬で眠れることが多い。
しかし、3は鬱病・不安障害・パニック障害・アルコール依存症などの
精神疾患を原因とする不眠が含まれており
精神科の治療が必要となることもあり、睡眠薬の処方のみでは治らないことも多いようです。
長期不眠が不眠症と言われます。
精神生理性不眠
不眠症の中でもっとも多く、従来神経質性不眠と呼ばれてきたものです。
もともとは原因がはっきりした不眠を除外した後に残る除外診断的な概念でしたが
国際的な不眠症の診断基準ICSDでは
↓2つの要因の相互強化の結果として生じるものと定義されています。
1. 身体化された緊張
心身共に緊張しやすい人に精神的ストレスが持続的に加わると、身体化して
身体に生理的な緊張・興奮・覚醒(筋緊張、交感神経緊張の高まり)が生じ、不眠が起こる。
2. 学習された睡眠妨害的連想
眠れないことについて過度の心配があり
眠ろうと意識して努力するとかえって興奮し、いっそう入眠できなくなる。
いつも使用している寝室・寝具などの環境条件も条件反射的に不眠に結びついてしまい
ベッドに入ると「今夜も眠れないのではないか」と云う気持ちになり、眠ろうと努力する。
寝室以外の場所(リビングのソファーなど)の方がよく眠れるということがあります。
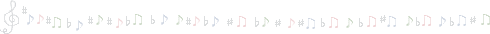
*** メカニズム ***
ストレスを受けると興奮により頭が冴えるため、一過性不眠となります。
(これは誰にでも起こりうる正常反応)
 この段階で
この段階で
ストレスの処理や生活習慣の改善などをして対処できない
→眠ることに自信をなくしたり、不安を抱くようになる
→睡眠へのこだわりや不眠恐怖が次第にに強くなり、新たなストレスとなる
→ストレスが不眠を慢性化させ、長期不眠に
自分で出来る生活習慣の改善点
■生体リズムの規則性の確保
規則正しい食生活と規則的な睡眠スケジュールを守る
日中は軽い運動をする
できるだけ午前中に太陽光を浴びる
寝る時間と起床する時間を一定にする
■日中や就床前の良好な覚醒状態の確保
日中はできるだけ人と接触するように努力する
夕食後の居眠りや仮眠をとることは避ける
■良好な睡眠環境の整備
自分にあった寝具を選ぶ
静かで暗く適度な室温、湿度の寝室環境を維持する
■就床前のリラックスと睡眠への脳の準備
就寝間近のカフェイン飲料や多量のアルコールなどの摂取、喫煙を避ける
就寝間近の厳しい運動や心身を興奮させるものは避ける
就寝間近に熱いお風呂に入ることは避ける(ぬるめのお湯にすること)
眠れない場合には、無理に眠ろうとしない
寝酒はしないこと