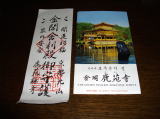133回 点鐘散歩会 〇7年4月更新
京都 鷹ヶ峰 光悦寺から常照寺
本阿弥光悦は、徳川家康から拝領したここ鷹ヶ峰の地に、一族職人を集めて、いはば芸術村とも言うべき工芸の集落を営んだ。その足跡を象徴するのが光悦寺である。
丹念に組み上げた清楚な石畳の道は小さな山門への導入部。両側には楓の木が程よく並んでいて、紅葉の頃を彷彿とさせる。
中には三巴亭・了寂亭・本阿弥亭など七つの茶室が散在する。光悦垣という竹垣は殊のほか有名。
つづいて常照寺へ回る。この寺は光悦の土地寄進を受けて開設された鷹ヶ峰談林の旧跡で、いわゆる学問寺であるが、吉野太夫ゆかりの寺としても有名。朱塗りの赤門は太夫が寄進したもの。境内に太夫の墓と夫紹益との比翼塚もある。
高得点順 一人一句
のけぞると狐になっている桜 井上恵津子
取れそうなボタンとバスを待っている 徳永政二
バス行ってバス来てバス行って四月 峯裕見子
歩く時間は君を想っている時間 赤松ますみ
バス停は選挙の匂いたまっている 西村夕子
四月の水甕はすっからかんである 畑山美幸
馬酔木ほろほろ光悦垣はまだ眠い 笠嶋恵美子
第二幕みぞれ混じりの雨になる 内田真理子
門からの道 門までの道 吉岡とみえ
しぐれしぐれて死ねない傘をさしている 辻 嬉久子
鷹ヶ峰三山 風邪をこじらせる 小林満寿夫
おもろない墓にむらさき挿してある 墨作二郎
この庭はちょうど背丈にあっている 南野勝彦
吉野門 桜時雨でございましょう 森田律子
花の昼 久方ぶりの人と会う 八木侑子
椿地に落ちて美しき後生 前田芙巳代
小学校に通う 鷹ヶ峰の犬 本多洋子
触れないで散りたくないと言う馬酔木 今井和子
濡れた傘に花びら一枚ついてきた 平井玲子
夢は三角 書体は四角 北川アキラ
日 時 平成18年10月4日
参 加 京都・名古屋・大阪各地から21名
京都島原の花街は天正十七年豊臣秀吉の公許を得て柳馬場二条にひらかれたのが始まり。その後、六条柳町に移され、また寛永十八年には朱雀野にうつされて西屋敷と呼ばれた。その移転命令があまりにも急で、九州島原の乱に似ていたため、その花街界隈を島原と呼ばれるようになったと言う。
角屋では当時の一流画人に襖絵の制作を依頼したらしく、丸山応挙や与謝蕪村などの画蹟が残されている。
また幕末の頃には諸大名を始め、西郷隆盛・桂小五郎・坂本龍馬・山縣有朋などの勤皇の志士たちがここを利用し、宴を催したことが伝えられている。そのほか新撰組の壬生狼たちも出入りしたらしく、その刀傷が痛ましく残っている。揚屋というのは、今の料亭と同じく、料理をもてなして宴をはるところで、太夫や花魁が必要な時は置屋から迎え饗していたらしい。
角屋の建物は木造二階建て。表全体が格子造りになっていて、典型的な揚屋建築の特徴を持っている。昭和二十七年に重要文化財に指定されている。
階下には大きな台所が設けられ、二階は幾つもの座敷に仕切られて見事なレイアウトと装飾。「網代の間」「緞子の間」「扇の間」「青貝の間」などなど螺鈿をはめ込んだ壁や源氏物語の釘隠しなどが施され、障子の桟などにも驚くほどの工夫がこらされている。遊興の場とはいえ、当時の文化の粋を集めたもの。
ここで、俳諧や連歌の会などももようされたとあれば、まさしく文芸サロンを呈していたようだ。
約二時間たっぷりを鑑賞に費やして、午後から清記互選の句会に入る。
刀箪笥のなかのわくわくする空気 赤松 ますみ
見たことは忘れてしまう 柳の木 内田 真理子
すすを剥がせば江戸元禄の桃の色 本多 洋子
そうね気分は九条浅葱色 吉岡 とみえ
障子ふすま障子ふすまとかきわけて 徳永 政 二
波打っているのは障子でなく私 峯 裕見子
衝立の布袋の腹が遊びなはれ 川田 由紀子
聴き耳をたてる不似合いな吊り灯篭 平井 玲 子
障子の桟がゆがんでもうすぐ生まれます 笠嶋 恵美子
鞄を前に回して太夫にさせられる 畑山 美幸
源氏絵巻がすすけてわすれられている 墨 作二郎
からっぽの刀箪笥から煙 たにひら こころ
釘隠し太夫の本音秘めてある 井上 恵津子
労わらないと臥龍の松もわたくしも 松本 あや子
帰ったら割箸の簪で内股で歩こ 岩根 彰子
シンプルな部屋に隠れた技ひかる 八木 侑子
京のど真ん中金木犀がしつこい 柴本 ばっは
秋が来ている角屋の塀がきゅっと鳴る 辻 嬉久子
平和な時の平和な太夫の息づかい 今井 和子
島原を通る近道した父子 小林 満寿夫
庭の松 お前何回褒められた 南野 勝 彦
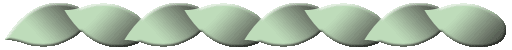
海遊館に入ると先ずは、水槽のなかを通り抜けの出来るアクアゲートを潜る。
天井も左右も透明なアクリル板をとおして魚たちの大歓迎。順路は先ずエスカレーターで8階へ。そこから穏やかなカーブでらせん状にスロープが形成されていて、左右上下の水槽を覗き込みながら、自然に3階の海遊館出口まで降りてくるという仕組み。一行は子供に還ってそれぞれが水中を泳ぐ魚のように
ラッコやイルカやジンベイザメなどと言葉を交わしながら、句箋に鉛筆を走らせた。午後から港区民センターにて清記互選の句会。
平成18年8月2日 参加19名
けっこう怖いマンボウの減らず口 辻 嬉久子
ええとこに行こう行こうというくらげ 峯 裕見子
めし・風呂・寝るといいたそうな魚 前田芙巳代
タカアシガニ黄泉の世界はすぐ隣 本多 洋子
ここまでは魚ここから私たち 徳永 政二
帰ったら金魚の水を替えてやろ 南野 勝彦
キミはワニじっとしてても全部ワニ 今井 和子
けんかなどしないのだろうか水の中 たにひらこころ
これからの予定クラゲと踊ります 笠嶋恵美子
誰かとめなきゃ永遠に右回り 岩崎千佐子
マンボウと目が合うキスをせがまれる 畑山 美幸
地球が割れるのですか超特急のイルカ 八木 侑子
エイよ今イナバゥアーで決めました 柴本ばっは
マンネリの鯵にも美しいうろこ 小泉 敬子
どんなもんだいとエイの尻尾が自慢す 松本あや子
ペンギンのお腹ぽかんと無邪気です 西村 夕子
水面を波立たせるのは私 久恒 邦子
小魚の群れ母さんに会えたかな 平井 玲子
高得点句
埴輪ぼうと立つ百毫寺への抜け道 墨 作二郎
逢いたさは薬師如来の副作用 高橋 古啓
鶺鴒つつと来て水浴び入江泰吉館 本多 洋子
十二神将ハンサムな僕の干支 青木 勇三
竹筒に百円入れて挨拶がわり 笠嶋恵美子
そば屋から覗く奈良町低い屋根 福田 弘
土塀から奈良の空気を吸うている 堀 豊次
虫食いの経木もあらん花和讃 : 竹内 良伸
近鉄奈良駅前に集合。北円堂を回って猿沢池から奈良町へ。元興寺を覗き、庚申堂から格子の言えを回って十輪院・福智院による。近くの蕎麦屋で一回目の句会。午後は新薬師寺と入江泰吉記念写真館に寄って二回目の清記互選の句会。帰路歩きながらの披講呼名をして解散。
第132回 点鐘散歩会 平成7年3月7日
五個荘 近江商人屋敷の雛祭り
東近江市五個荘に点在する近江商人屋敷を散策して、折からの雛祭り巡りをすることになった。
先ずは商人屋敷町にふさわしく「てんびん通り」「鯉どおり」「花筏どおり」などをそぞろ歩きながら雛の公開されている商家に立ち寄った。
外村繁邸は作家外村繁の生家で、作家の遺品の数々も展示されていた。近江上布を使った清楚な清湖雛も印象的。
外村宇兵衛邸では畳二畳ほどの御殿雛。中江準五郎邸では土人形の小幡でこなどが所狭しと飾られていた。
遠くから冠雪の伊吹山が私達を見下ろしていた。昼食は手打ちうどんの店で雛ご膳を戴き午後から「てんびんの里文化学習センター」にて清記互選の句会。
得点順 一人一句
ぎしと鳴るところがあって少し春 峯 裕見子
福助のおでこのあたりに風がある 前田芙巳代
私小説箱階段を降りてくる 笠嶋恵美子
鳥の巣のような私の巣のような 徳永 政二
まっすぐな木はまっすぐに空を指す 内田真里子
雛の足裏をのぞいていった寒のもどり 辻 嬉久子
水という文字を担いでいる母屋 阪本 高士
藪椿 咳ひとつを我慢している 西村 夕子
薄暗き階段があり私小説 里上 京子
プライドがチロチロ燃えるおくどさん 久恒 邦子
近江の雛は読み書きそろばんが出来る 本多 洋子
人形も見る人もみなひなまつり 今井 和子
ソロバンが笑うとおひなさま笑う 北川アキラ
口移し雛人形は瞳を閉じる 小林満寿夫
菜の花のまばらと水の動く堀 墨 作二郎
お二階へどうぞ桜の木の手すり 平賀 胤壽
わたくしを洗ってくれたおひなさま 植野美津江
近江上布のくたっとしたとこ見せません 畑山美幸
角を曲がると水音がする鯉通り 平井 玲子
昔売る里で昔を買っている 八木 侑子
近江商人 観光の街にて生きる 河崎誠太郎
第131回 平成7年2月6日ー7日
点鐘散歩会 一泊二日の旅
一日目 伊勢神宮・おかげ横丁
点鐘恒例の一泊二日の散歩会。本年は伊勢神宮とおかげ横丁を散策。翌日は鳥羽に出て、遊覧船で鳥羽湾一周の船旅も楽しんだ。
おかげ横丁とは、鳥居前で約三百年商いを続けてきた「赤福」が、お伊勢さんのおかげという感謝の気持ちから作った町並み。敷地の中に、伊勢路の代表的な建築物を移築再現し、三重の老舗の味や名産や文化的風物を見易く体感出来るようになっている。サザエのつぼ焼きやうるめぼしなどの味見もしながら伊勢うどんに舌鼓を打つ。
午後三時ごろには木の橋・宇治橋を渡って内宮へ。五十鈴川の緋鯉も機嫌よく出迎えてくれる。
砂利道はすこし砂埃が立っていたが、奥へ奥へと進むうちに、いかにも鬱蒼と鉾杉やモミ松桧などが生い茂り神域らしく森厳な雰囲気になる。
20年毎に神殿を建替える式年遷宮は千三百年続けられていて、第62回式年遷宮は平成二十五年に行なわれるという。
高得点順 一人1句
ほうじ茶匂う伊勢路は版画の似合う町 本多 洋子
ポケットに手をつつこんで春ですね 徳永 政二
日当たりの木におみくじが咲いている 墨 作二郎
ほどよく乾くサンマもわたくしも 今井 和子
あやとりが好き横丁をひとまわり 北川アキラ
茶わん屋の店先にある善と悪 前田芙巳代
日常は組紐にされ吊るされて 西村 夕子
五名さま二名さま二名さま伊勢うどん 畑山 美幸
情けない顔が並んで秋刀魚丸干し 平井 玲子
もう決めました小さな橋を渡るとき 南野 勝彦
ザクザクと神さまからの砂ほこり 峯 裕見子
遷宮の年まで赤い息を吐く 笠嶋恵美子
二日目 鳥羽湾周遊 遊覧船
空は海 忘れたものを捜しだす 前田芙巳代
やわらかに曲線 島は子を産んで 平井 玲子
伝説の島愛人をふたり持つ 峯 裕見子
美しい言葉岬を白くして 徳永 政二
春の帽子は忘れやすくて平和です 本多 洋子
島にぽつんと送電塔にかかる雲 墨 作二郎
アコヤ貝の核にもなれずガムを噛む 畑山 美幸
カモメはピエロ陽気な芸をお見せする 笠嶋恵美子
島が近づく静かになって波が近づく 今井 和子
鳥羽の海に藍色入れて冬にする 南野 勝彦
島揺れる鉛筆揺れる遊覧船 西村 夕子
小さい船が神経を横断 北川アキラ
2007年度 1月 更新
第百三十回点鐘散歩会
堺・妙国寺からザビエル公園
妙国寺は慶応四年に起きた「堺事件」で特に有名である。
これは、当時大阪天保山沖に停泊していたフランス軍が堺浦に上陸して、神社仏閣に乱入し、婦女子に傍若無人の振る舞いをしたので、堺警備隊として妙国寺に駐屯していた土佐藩士が発砲し、フランス軍に負傷者を出した。
これが国際問題に発展し、日本はフランス軍に賠償金を支払いさらに、土佐藩士二十名に切腹を命じられるにいたった。
妙国寺本堂前に於いて、日仏立会い人の面前で割腹自刀が施行せられた。十一人目までの割腹を見て、フランス軍は退場したと言う。
残り九名は土佐に流刑となったらしい。寺には十一名の遺髪や、辞世の詩歌が生々しく残されている。
また寺の庭には樹齢千百年と言う大蘇鉄がありその秘話も有名。
天正七年に織田信長が、この蘇鉄を安土城に移植したが、毎夜「妙国寺に帰ろう」と泣くので、激怒した信長が蘇鉄を斬らせたところ、鮮血が切り口より流れ大蛇のように暴れたので、即座にこの蘇鉄を妙国寺に返したと言う。
さすがに大蘇鉄には霊気をさそうような闇が漂っていた。
寺を出て近くのザビエル公園に寄る。
天文十九年フランシスコザビエルが布教のために堺に上陸した所である。公園の隅には堺ゆかりの安西冬衛氏の「蝶は一匹韃靼海峡を渡って行った」の詩碑もたてられている。刃物会館にも立ち寄った。
高得点順 ひとり一句
両替をしてから春に乗り替える 笠嶋 恵美子
生き残る度においしいお茶の味 北川 アキラ
泣く場所を探す刃こぼれ落ちこぼれ 岩崎 千佐子
少年の顔をしているチンチン電車 本多 洋子
大きくてはかないものを切る刃物 峯 裕見子
刃こぼれの母を砥石に任せるか 里上 京子
ギザギザの刃をひっこめる初対面 赤松 ますみ
空は濡れ鳥のかたちをしたハサミ 徳永 政二
ひと回りしてほんまかいなほんまかいな川田由紀子
煙突がとても痛いと言っている 福尾 圭司
ボタン押すあなたの前でとまります 今井 和子
乗り換えてもやっぱりチンチン電車です 南野勝彦
車内広告にある今日のヒント 平井 玲子
刃物屋の刃物やさしくなれません 前田 芙巳代
エプロンも火宅の人も降りる駅 西村 夕子
雨の日に買う赤い爪切り青い爪切り 墨 作二郎
快い返事お鍋が待っている 植野 美津江
十八切符扉開ければ雪の山 八木 侑子
第百二十九回点鐘散歩会 2006年12月更新
大阪・鶴橋・コリアンタウン
大阪生野区にある鶴橋は、JR環状線・近鉄線・市バス・地下鉄などの交通機関が集中していて、庶民に愛される人情味溢れる街である。
戦後の混乱期に、ここに露天商が多数あつまった。いわゆるその闇市を基盤としてこの鶴橋商店街は発祥した。なかでも特筆すべきはその国際色である。
昭和二十二年に五カ国・・・日本・大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国・中華民国・中華人民共和国・・・の方々が集まって鶴橋国際商店街が結成されたと言う。現在はコリアンタウンという愛称で呼ばれ「どこよりも安く、何でも揃う」をキャッチフレーズに隆盛を極めている。
散歩会一行は、駅周辺の迷路のような商店街を散策、カラフルなチマチョゴリに目を瞠ったり、キムチや豚足に驚きながら買い物や作句に余念がなかった。
得点順 ひとり一句
チヂミ焼くスパンコールをふりかけて 川田由紀子
泣いていいよ ここではみんなそうしてる 南野 勝彦
賢そうな魚がここで干されてる 西村 夕子
赤いもの食べてしっかりと泣いて 峯 裕見子
のり巻きでくるむと とりあえず平和 赤松ますみ
店を出て炎を吐いているのです 福尾 圭司
立ち止まったらキムチにされてしまった 畑山 美幸
豚足ごろりラインダンスの夢がある 里上 京子
6Bで画くとツルハシ海になっている 北川アキラ
やがてこころに沈んでくるチマチョゴリ 前田芙巳代
女子マラソンの踏んばりどころこのあたり 瀬尾 照一
言うたかもしれんコリャンタウンの豚の鼻 今井 和子
冬を彩どる望郷のとうがらし 井上恵津子
悲しみを鍋にくべたらジャムになる 春野ゆうこ
作業着も宮廷衣装もそろいます 八木 侑子
豚の頭ごろんと曇天を睨む 笠嶋恵美子
もう少しですと言われてもうすこし 徳永 政二
うどん・そば腰から下が並んでいる 平井 玲子
ホッケの開き 曇天はさみしい 西澤 知子
チゲ鍋の湯気 民族をあたためる 本多 洋子
きっときっとキレイになれるキムチのキ 岩崎千佐子
コリアンタウンは雨の素通りちりれんげ 墨 作二郎
憎らしいアイツをエゴマの葉にくるむ 小田 明美
第百二十八回 点鐘散歩会
奈良・興福寺 国宝特別公開 2006
奈良興福寺は2010年に創建1300年を迎える。今創建当時の伽藍を復興すべく、急ピッチでその復元工事が進められている。
この秋は、三重塔・北円堂それに仮金堂が特別公開され、国宝館の貴重な国宝とともに一般の目に親しく接する機会を得ることができた。
秋晴れの爽やかないちにち、仏たちの思索に満ちたまなざしに深く心を打たれながら、あるいは忘れていた大切なものを心に呼び戻したようなやすらぎを得て、それぞれ思い思いに句をしたためた。
午後から句会。
各自一句 得点順
千年も下くちびるを噛んでいる 南野 勝彦
失った指のかわりにある宇宙 峯 裕見子
笑いなはれ仁王の口に手を入れて 川田 由紀子
鹿の角にちょいとひっかかったヒミツ 赤松 ますみ
ひとりになるとすくすく笑うほとけさま 徳永 政二
釈迦如来真っ正面に見る気力 平井 玲子
二歳から聖徳太子だったんだ 吉岡 とみえ
日本史の単位を興福寺で取ろう 本多 洋子
あの人に知ってほしくて生きている 春野 ゆうこ
この恋はギョロ目の佛には言わぬ 西村 夕子
柘榴にはざくろの念が゜行き届く 前田 芙巳代
青い空ととんでる私と興福寺 西澤 知子
紅葉はもうすぐ売れない絵を描いて 阪本 高士
扉を開ける弁財天の多産系 墨 作二郎
少し弱気な秋の時計を吐き出そう 辻 嬉久子
おトイレは土塀の中にございます 井上 恵津子
鹿の目に見つめられておはようございます 小田 明美
み仏の裏にまわれば鴉鳴く 植野 美津江
南円堂は口を閉ざしたままである 畑山 美幸
結界に揺れてただよう奈良晒し 菱木 誠
阿修羅のまなこ 夏目雅子を思いだす 柴本 ばっは
塔上を一直線に父の雲 松田 俊夫
階段は思考回路に続いている 福尾 圭司
ある意味ですごいと思う鹿のドン 久恒 邦子
鹿はただぼんやりみんなのそばにいる 今井 和子
阿修羅には一部始終を言うつもり 笠嶋 恵美子
新庄のように目立ちたい鹿がいる 松本 あや子