 生命科学−物質と生命の関係−
生命科学−物質と生命の関係−

●生命現象
●DNA
●ゲノム
●分子生物学
生命科学−物質と生命の関係−
生命現象を物質の分子レベルで理解しようとする試みはワイン生成の仕組みを詳細に調べることから始まったようだ。ワインの品質は樽によって異なる。その原因を追究する過程で、醗酵には生きた酵母が不可欠ということが判明した。アルコールの醗酵現象は数千年前から知られていたが、醗酵現象の科学的な解明は19世紀中頃のこと、醗酵と酵母の存在が明確になったのは、1830年代であった。ドイツのキュッツィングは酵母が砂糖を発酵してアルコールを作ることを確認、テオドール・シュワンは動物の組織から最初の酵素ペプシンを発見し糖とデンプンの発酵を研究した。
醗酵とは微生物が物質を取り込みながら増殖を繰り返す生理過程の中で起きる生物現象である。しかし、醗酵は生きた酵母でなく、酵母の抽出液からでも起きる。酵母内のある種のたんぱく質(酵素)が働いて、糖がアルコールに変化する反応に関連していた。それはブドウ糖が二酸化炭素とエタノールに分解される解糖(醗酵)の経路を解明することでもあった。その道筋には複雑な反応系が存在していた。生物体で起きている現象を化学反応で解明することが可能になった瞬間であった。
糖は最も簡単な炭水化物、CmH2nOn(m,nは数字)のような分子式で表現される。ブドウ糖(グルコース)はC6H12O6、しょ糖(ビート糖:砂糖きびからの糖)はC12H22O11、などである。炭水化物は主に生体のエネルギー源として重要である。
一方、すべての生物は細胞からできており、生体の基本的単位は細胞であり、これは独立の生命を営む微小生物であることが明らかになった。細胞の発見は1665年にロバート・フック(弾性体のフックの法則で有名)が顕微鏡でコルクの切片を観察したことから見つかった。すべての生物は細胞を基本単位とする。このことが明らかになったのは1830年代のことであった。細胞が細胞から生じるとする学説は、ドイツの植物学者マティアス・ヤコブ・シュライデンが1838年に植物について見出し、テオドール・シュワンが1839年に動物について発見した。そして1858年にルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョーが「すべての細胞は細胞から生じる」と提唱した。
細胞は次々と新しい細胞を生み出すことも判明した。生物は環境の中で自然選択により、世代を重ねることで、形質が変化し、その構造も複雑になって、生物の多様性が生まれる進化論が唱えられた。ダーウィンの「種の起源」が出版されたのは1859年であった。その後、メンデルは、エンドウマメの掛け合せから、遺伝の法則を発見した。遺伝情報を持つ遺伝子の存在が明確になったのは1909年のことであった。
当初の細胞学は、主に細胞内の構造を記載する学問、電子顕微鏡や各種光学顕微鏡を用いた形態学的に解析し、細胞を構造レベルから理解しよう試みられた。最近では、分子生物学、生化学、遺伝学、生理学、解剖学などの分野と密接に関係してきた。特に、細胞生物学は、生の発生に重要な役割を担っていることが明かになり、発生生物学とも密接な関係にある。
細胞の構成要素は、一部の特殊な細胞を除くと、細胞膜、染色体、リボソーム、細胞質からなる。細胞膜は内部と外部を隔て、その内部に生体物質を含む水溶液が存在する。生体物質はタンパク質を含み、遺伝情報を担うDNAがある。染色体は遺伝情報を担う生体物質、リボソームは遺伝情報を読み取ってタンパク質へ変換する翻訳が行われる場、細胞質は核以外の領域のこと、細胞質基質の他、様々な細胞小器官や細胞骨格を含む。
人の細胞の主要な構成物質は、たんぱく質、炭水化物、脂肪、であり、三大栄養素と呼ばれる。これに、ビタミンとミネラル(微量栄養素)を加えると、五大栄養素ともいう。たんばく質は体の素材になる栄養素、炭水化物と脂肪はエネルギー源、ビタミンは潤滑油、ミネラルは骨や歯の材料、というように単純化して理解される。本質的にはどれも体を構成する細胞の構成物質として重要である。
細胞の基質はタンパク質を主成分とする。しかし、細胞の内外や細胞内小器官を区分する構造は脂肪から合成されるリン脂質を主成分とする。細胞表面は細胞どうしが互いに相手を認識しあう標識物質で覆われている。これは糖鎖、すなわち炭水化物で構成されている。ビタミンは細胞の中の酵素反応の潤滑油のような補助的な役割をするが、たんぱく質で出来た酵素分子の中で、生化学的反応の主役を演じる部品を構成する。それは特殊な有機物の低分子化合物とみなせる。ミネラルは酵素分子に組み込まれ、酵素やたんばく質分子が機能を発現するときのスイッチの役割を果たしている。
たんぱく質は窒素を含む複雑な有機化合物、炭素原子と窒素原子の結合(ペプチド結合)でつながったアミノ酸からなる。生体を構成する基本の必須アミノ酸は20種類、生体の部品を構成する。20種類の必須アミノ酸は、グリシン[C2H5NO2]、アニラン[C3H7NO2]、バリン[C5H11NO2]、ロイシン[C6H13NO2]、イソロイシン[C6H13NO2]、セリン[C3H7NO3]、トレオニン[C4H9NO3]、アスパラギン酸[C4H7NO4]、グルタミン酸[C5H9NO4]、アスパラギン[C4H8N2O3]、グルタミン[C5H10N2O3]、リシン[C6H4N2O2]、アルギニン[C6H14N4O2]、ヒスチジン[C6H9N3O2]、フェニルアニラン[C9H11NO2]、チロシン[C9H11NO3]、トリプトファン[C11H12N2O2]、プロリン[C5H9NO2]、シスチイン[C3H7NO2S]、メチオニン[C5H11NO2S]である。シスチン[C6H12N2O4S2]やオキシプロリン[C5H9NO3]などもアミノ酸であるが、シスチンはシステインから、オキシプロリンはプロリンから作られ、生体を構成する基本の必須アミノ酸から除かれる。
たんぱく質は食物に含まれ、加水分解によって、アミノ酸という生体を構成する部品に分解される。そして、生命の遺伝子情報を担う物質DNA(デオキシリボ核酸)からの指令に基づいて生体が組み立てられる。DNAは細胞の核から抽出される。当初は白血球からリンを多量に含む酸性の物質として見出されヌクレイン(核から抽出された物質)と名付けられた。すべての生物は共通の構造と物質から成り立っており、生物は生物から生まれ、その性質は子孫に伝えられることが明確になった。
DNAはデオキシリボース(糖)とリン酸、塩基から構成され、塩基にはアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の四種類がある。その構造は、鎖状で二本の逆向きの二重らせん構造をとり、相補的な塩基(AとT、GとC)による水素結合を介している。この相補的二本鎖構造は、片方が鋳型となりDNAの複製を容易に行うことができ、遺伝情報を伝えていく上で決定的な役割を担っている。DNAが二重らせん構造であることを発見したのはワトソンとクリックである。1953年のことであった。
<DNAの構造>
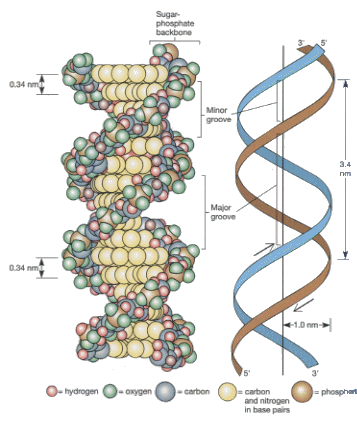
DNAは、増殖や遺伝のための複製機能の情報、たんぱく質合成のための生産の情報、必要な時に必要な場所で必要なたんぱく質を作る調整機能の情報、老化や進化のために変化する機能などの情報を持っているとされる。その詳細な仕組みやメカニズムの解明は今後の課題である。また、DNAは分子構造を持つ物質であり、生命の巧妙な現象のすべてを握っている。単体のDNAは生きているわけではないが、細胞の中で働き始めると、魅力的な生命活動に主役的な役割を果たすことが知られている。
デオキシリボースと塩基が結合したものはデオキシヌクレオシド、このヌクレオシドのデオキシリボースにリン酸が結合したものをデオキシヌクレオチドと呼び、ヌクレオチドが核酸の最小単位となる。糖にリボースを用いる核酸はリボ核酸(RNA)と呼ばれる。ヌクレオチド分子は、リン酸を中心に水酸基と2つのエステル結合を作るフォスフォジエステル結合で連結し、鎖状の分子構造をとる。フォスフォジエステル結合には方向性があり、複製、転写のときはこの方向性に従うとされる。
DNAは遺伝子、遺伝子は生物の遺伝的な形質を規定する因子、遺伝情報の単位である。その実体がDNAの塩基配列である。遺伝子はDNAが複製されることで次世代へ引き継がれる。遺伝子の機能は、転写と翻訳の過程を経て、遺伝情報(DNAの塩基配列)がタンパク質などに変換される。転写とはDNAからRNAに情報が写し取られる現象、翻訳とはRNAの情報に基づきタンパク質が合成される過程である。
ある生物種の遺伝子の総和はゲノムと呼ばれ、遺伝情報を担う生体物質が染色体である。染色体は、塩基性の色素でよく染色されることから、ギリシャ語で「色のついた(Chromo-)」「物体(-some)」を意味し、Chromosom と名付けられた。染色体の基本構成要素はDNAとヒストン、ヒストン (histone) とは真核生物のクロマチンを構成するタンパク質の一群のこと、強い塩基性のタンパク質、酸性のDNAとの高い親和性を持ち、DNAを自身に巻き付けてコンパクトにする。クロマチン(chromatin)は真核細胞内に存在するDNAとタンパク質の複合体である。
染色体の基本構成要素はDNAとヒストン、一本の染色体に一本のDNAが存在する。DNAは二重らせん構造の非常に長い物質、細胞核に収納するためには折り畳む必要がある。DNAは核酸なので酸性、塩基性のタンパク質であるヒストンとの親和性が高く、全体的に見ると、電荷的に中和されて安定している。
ヒストンと呼ばれるタンパク質は5種類(H1, H2A, H2B, H3, H4)が知られている。この内、H2A、H2B、H3、H4の4種は、コアヒストンと呼ばれ、それぞれ二分子があつまりヒストン八量体(ヒストンオクタマー)を形成する。一つのヒストン八量体は、約146bpのDNAを左巻きに約1.75回巻き付ける。この構造はヌクレオソームと呼ばれ、クロマチン構造の最小単位である。H1 はリンカーヒストンと呼ばれ、ヌクレオソーム間のDNAに結合する。
ヌクレオソームヒストンは進化的に非常に強く保存されており、いずれのアミノ酸に突然変異が起こっても、致死または強い異常の原因となる。特に H3 と H4 は最も保存されている。H1 ヒストンはこれらに比べると多様性が大きい。有核赤血球には H1 の代わりに H5 がある。
DNAとヒストンの複合体は転写に対して阻害的に働く。転写が活性な遺伝子座の染色体では、ヌクレオソームが緩んだり、ヒストンが解離していることが知られている。それらの部位はヌクレアーゼに対する感受性が高くなっている。ヌクレオソームヒストンの構造は球形のカルボキシル末端と、直鎖状のアミノ末端(ヒストンテール)からなっている。ヒストンテールのリジンやアスパラギン残基はアセチル化、メチル化、リン酸化、ユビキチン化といった化学修飾を受けることが知られている。例えば、細胞分裂の際には、ヒストンH3の10番目に位置するセリンが特異的にリン酸化される。このセリンは酵母からヒトまで多くの動物種で保存されている。これらの化学修飾は、遺伝子発現等、数々のクロマチン機能の制御に関わっていることが証明されつつある。複数の修飾のコンビネーションがそれぞれ特異的な機能を引き出すという仮説は、ヒストンコード仮説と呼ばれている。
DNAはヒストンに巻き付き、ヌクレオソーム構造を取る。この構造は150-200bpの周期で繰り返され、ヌクレオソーム繊維として折り畳まれ、直径30 nmのクロマチン繊維を形成する。そして、細胞分裂期に、このクロマチン構造がコンデンシン複合体等の働きによってさらに組織的に折り畳まれ、よりコンパクトな染色体構造に変換される。
歴史的には、
1882年 ドイツの細胞学者ヴァルター・フレミング(Walther Flemming)が、特異的な染料によって染められる細胞核内の構成要素を示す用語として、クロマチンという言葉を提案した。
1973年 精製クロマチンをエンドヌクレアーゼで消化したところ、断片はすべて200 bp の倍数であった。このことにより、タンパク質がDNAに規則正しい長さで結合していること、そしてそのタンパク質はエンドヌクレアーゼの消化からDNAを守っていることなどが示唆された。
1974年 オリンズら(Ada & Donald Olins)は、電子顕微鏡を用いクロマチンのビーズ状構造を初めて可視化した。
1974年 コーンバーグ(Roger Kornberg)は、X線回折、生化学、ヌクレアーゼ消化実験の結果をもとに、ヒストンとDNAから構成されるクロマチンの繰り返し構造のモデルを提出した。
1975年 シャンボーン(Pierre Chambon)らにより、この繰り返しのユニットを表す用語として、ヌクレオソームという言葉が提案された。
1976年 クルーグ(Aaron Klug)らは、電子顕微鏡観察をもとにして、30 nmファイバーのソレノイドモデルを提出した。
1997年 リッチモンド(Timothy Richmond)らは、ヌクレオソームの結晶構造を2.8オングストロームの解像度で決定した。
1990年半ば以降、ヌクレオソームをダイナミックに変化させる活性(クロマチンリモデリング活性)やヒストンを修飾する活性が相次いで発見され、クロマチン構造の機能的な重要性が再認識されるようになった。
(この項は書き掛け、未完の状態のままです。)
(文責:yut)
戻る
|
|
|
|