試 論
倭人の世界観
これまでの解釈からわかったことを基にして、倭人の世界観−いわば宇宙観−を考えてみたい。三種の他界もあわせて考察している。また、ここまで言及しなかった星座なども紹介する。
ただし、「倭の神話」の内容は以下の論考よりもっと深いように思えてならない。これを解釈するためには、現代人ならおそらく全力を投入しない限り不可能である。だから、これはあくまでも「試論」である。断定的に書いている箇所もあるが、それは表現上の回りくどさを避けたためであり、読者もぜひ一緒に考えてもらいたい。
世界の創始
伊奘諾・伊奘冉は最初の行動として、ちょうど轆轤を回して土器を作るように、玉矛で「蒼く玄いもの」をぐるぐるとかき回したわけだが、そのとき、彼らは「土器」の内側にいたのだろうか、それとも外側にいたのだろうか。もちろん内側にいたのだろう。それならば、彼らは地の中心(現在の地上)で生まれ、そこから天浮橋に立って天球をかき回したことになる。その天浮橋はおそらく虹からの神話的連想である−第二六詞章「猿田彦」の解説参照−。天球の回転の中心が北の空の仰角三〇度強の位置にあるのはそのためだということだろう。
こうして、彼らは天と地の境界を定めた。だから、天球が天と地の境界である。
ここで、世界の創始がわかる。世界は最初に天球の内と外とに分かれる。天球は「天の国」であり、天にとっての「床」であって、その外に天が広がっている。そして、天球の内側は暗黒である。つまり、第一詞章冒頭の「重く濁るもの」とは暗黒であり、それは夜が暗闇に包まれている理由を説明する起源神話である。また、ここで第一詞章に登場する天常立の役割もわかる。彼は「天の床」を支える神であり、天球上の「もの」が国土に落ちないように天球につなぎ止めておく「引力の神」である。
現在国土があるところは伊奘冉が国土を産む前は中空であり、そこでは第一詞章の国常立以下の神々が天から国土が降ってくるのを待ちかまえている。『紀』第一段が「天地の中」(本文)、「虚中」(第一の一書)、「空の中」(第六の一書)というように、中空感を語っているのはこのためだろう。
では、伊奘冉は国土をどすんと中空に産み落としたのだろうか。おそらくそうではない。伊奘冉は他の神を産むのと同じように天球(高天原)上に国土の神を産んだのだろう。だから、国土の神は高天原にあるときは星(星座)の神でもある。『記』に八島の亦の名として「天之忍許呂別」「天比登都柱」「天之狭手依比売」などとあるのは星の神としての神名だと思われる。そう解して何の問題もない。天球が回転することで国土の神は一日とたたずに「天降り」ができる。それは他の星々の神の天降りと同じ方法である。
そうすると、高天原上では西に本州の神があり、東に九州の神がある。本州の神が先に天降り、国常立がそれを受けとめて東に持っていき、次いで四国の神、九州の神と続いたことになる。
第六詞章「三貴子誕生」の解説で「日神生誕の地」を論じた際、「筑紫の日向の小戸の橘の檍原」の「筑紫」の意味について、まったく別の解釈があり得ると書いたのはこのことである。高天原上の筑紫=九州と解するなら、何も問題はなくなってしまう。だが、そうではないように思える。「筑紫」以外に高天原上の島でこういう用法をしている例が見つからないし、また、「日向(東)」の前に入れる必要もない。誤解による筆録段階での付加と解した方がよさそうである。
常世国と根国
「国産み」に話を戻すが、高天原に伊奘冉が産んだのは「神」としての「国土」であって、「もの」としての「国土」ではない。第一詞章の解説のアリストテレスの用語を借りれば、伊奘冉が産んだのは「形相」としての「国土」であって、「質料」としての「国土」ではない。「質料」としての、つまり「もの」としての「国土」を作るのは第一詞章の国狭槌以下の神々の役割である。ただし、「心」がないと「もの」は形を成さないので、「心」である国土の神が天降ることではじめて「国土」は形を持つ。国常立は形のある「国土」を中空で支える神であり、天球に「落ちて」いかないようにする「引力の神」である。つまり、国土は地の中心にあって国常立が「床」を支えて浮かんでいる。国土が天球の下半分をすべてみたしているわけではない。
なぜなら、そう考えないと「常世国」の所在が出てこないからである。「常世国」は「国(葦原中国)」の反対側(裏側、つまり「床」)にある国だと思われる。だから、「国」にとっての天球の下半分は「常世国」にとっては天球の上半分になり、そこでは「天」の主宰神は神皇産霊になる。
そして、国土の厚み−海の厚みでもある−の分だけ天球と接することになり、この部分が「根国」である。ただし、根国が国土をぐるりと円形に取り囲んでいるのかどうかはよくわからない。第三詞章「神産み」の解説で述べたように、高天原と海(国土)とは何らかの形でつながっていることも確かなので、この接面は不明である。素戔嗚の本拠地は国(葦原中国)の北西にある「根之堅州国」(『記』の表記)だが、これは第一三詞章「大宜都姫」の解説で採り上げる。
だから、正確に言えば、高天原は天球の上半分ではない。国土の厚みの分(厚みを常世国と二分しているならその半分)だけ上方は水平方向より奥行きがない。われわれも空を見上げれば平たく見えるだろう。
中空に浮かぶ国土
ところで、この、「国土」が中空に浮いているという考え方は、当時としては世界的に見ても驚くべき「進歩的」な見解なのではないだろうか。「地球」という概念に到達するまであと一歩である。しかも、個人の思想ではない。神話として採用されているということは、それが当時の倭の社会通念だったことを意味している。倭では西洋のように「揺るぎない大地」ではなかったためかもしれない。何しろ、地震の神がちょいとくすぐると、すぐにぐらぐらする。
この「中空に浮かぶ国土」説が地動説に行き着くためには、まだまだ乗り越えなければならない関門がいくつもある。文字通りの「コペルニクス的転回」も必要である。しかし、仮にこの時代の倭にガリレイが生きていたとしても、彼が宗教裁判にかけられることはなかっただろう。
西洋では、紀元前三世紀のギリシャですでに地動説の先駆を唱えた学者がいたようだが、それはあくまでも個人的な思想にとどまっている。その後キリスト教神学が支配的になると宇宙論はむしろ後退し、神の天地創造により天と地は画然と区別されることになった。大地は揺るぎないものとして信じられ、それに疑いを差し挟むことは許されなかったのである。だから、大地の下に空間があるなどと考える者は「異端」だとして徹底的に排斥された。コペルニクスの説を支持したブルーノなどは火あぶりの刑に処せられた。地動説が一般に認められるようになるのは、コペルニクスの死後七〇年以上たった一七世紀初めにケプラーが惑星の運動法則を発見してからである。
黄泉国
さて、問題は「黄泉国」である。これは「地下の国」ではないように思える。伊奘冉が死んだのは天球上であり、そこからわざわざ自分の子の腹の中に潜り込むとは奇妙ではないか。黄泉国は天球上にあるとするのが常識的な判断だろう。
地上から、北極星は一年中見える。オリオン座やさそり座は時季によって見えたり見えなかったりするが、それでも夜明け前の観測を一年間続ければ見える星はすべて出尽くす。しかし、地上からは決して見ることができない天球の部分がある。天の北極の反対側、天の南極部分である。天の南極を中心にして半径三〇度強の円形部分は倭からは見えない。それでは、倭人たちはその部分がどうなっていると考えただろうか。
先ほど、伊奘諾・伊奘冉が天球をかき回す作業を土器作りにたとえた。土器の底が天の北極である。その反対側は土器の口になる。そこは閉じてはいない。同様に、内側から天球をかき回したのなら、その天球は完全な球にはならず、天の南極部分は開いたままになるだろう。では、その開いた先はどうなっているのか。
次の図は天球を南北に切った断面図である。この図が何から示唆を受けたかは一目瞭然だろう。後円部が天球、前方部が黄泉国である。
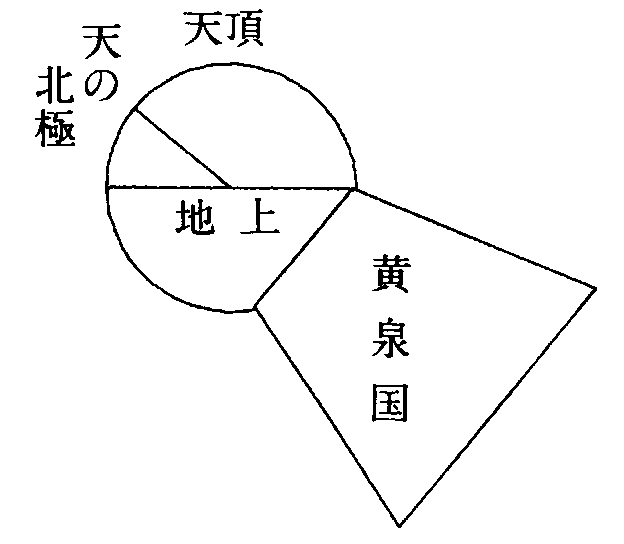 |
「生命(魄)」が死ぬと、「心(魂)」はどこへ行くのか。「故郷」である天球(高天原)に還ると考えるか、「死の国」である黄泉国に行くと考えるか、そのいずれかだろう。彼らがどちらを考えていたかはまだわからないが、いずれにせよそれは天球上にある。墓の形が天球の形を模すことに何の不思議もない。いや、むしろその方が自然だと言うべきかもしれない。
第一二詞章「天岩屋」の解説で箸墓古墳造営の記事を引いた。「是の墓は、日は人作り、夜は神作る」。この記事は、古墳を昼は平面的に造り、夜は立体的に造ったと語っているように思える。昼に天球の形に似せて土を盛っていき、夜に盛った土を星座と重なるように整えていく。それが古墳の造り方だったのではないだろうか。
「倭の神話」が生きていた時代と古墳時代が重なっていることは、両者の密接な関係を推測させるに十分である。それは、単に信仰と墓という関係以上に、より深い部分で不可分の関係にあるように思える。彼らは、その肉体的能力を古墳に注ぎ込み、精神的能力を「倭の神話」に注ぎ込んでいる。そういう思いにとらわれる。
あの巨大古墳は、これからももう二度と造られることはないだろう。その巨大古墳を、古代の倭人はいったい何を考え、何を思いながら、膨大な労力を費やして造営したのだろうか。彼らのその胸の内は、そこで流した大量の汗が古墳の土に沁み込んでいるように、必ずや「倭の神話」の中に深く、そして鮮やかに刻み込まれている。そう思えてならない。
〈〈 「試論(補助解説)」へ
〈〈 「試論(補助解説)」へ