第一四詞章 八岐大蛇
《出典》『紀』本文、『記』
[詞章の解釈]
神話の典型
出雲神話の比喩表現はどれも見事なものばかりなのだが、とりわけ、この八岐大蛇神話の比喩表現は出色である。比喩の美しさという点では、第一七詞章「根国行き」の解説で紹介する神語歌が無双の輝きを放っているが、この神話ほど神々の躍動する様を簡潔に、それでいて生き生きと表現した比喩は比類がない。古代人の奔放な想像力を目の当たりにさせてくれるその比喩表現は感動的でさえある。
また、そこに盛られた内容も表現に劣らず感動的である。それは万人を唸らせるだけの深さを持っている。八岐大蛇神話は、「神話」とはどういうものかを簡明に示す、素晴らしい神話に仕上がっている。
八岐大蛇
まず八岐大蛇から説明しよう。蛇は水神、大蛇だから洪水、と解する通説は、ここでも定型思考の枠から抜け出せていない。そういう外国神話の常套を記紀神話にまで無批判にあてはめるから、これほど出色の比喩表現を何も理解できないことになる。
その上、通説はそこから先の解釈をしていない。素戔嗚はその洪水をどうやって「退治」したのかを叙述に即して具体的に説明しなければ解釈したことにならない。叙述の中心になっている「退治」の過程を一切無視し、素戔嗚が大蛇を退治したという結果と草薙剣(天叢雲剣)を天照に献上したという結果だけを捉える。それを前提にして素戔嗚の神格を云々し、天照と対比するから「天の神と国の神との二元的対立」とか「天孫族への出雲族の服属」などという根も葉もない想念に取り憑かれることになる。そういう政治的解釈や歴史的解釈が記紀神話の世界をどれだけ貧しくしていることか。
八岐大蛇を洪水とすることは、本書の立場からも容認できない。素戔嗚は風神である。むしろ洪水を起こす側の神であって、一旦起きた洪水を鎮めることは彼には不可能である。「倭の神話」には全知全能の神は一神も登場しない。どの神もそれぞれに固有の神格を担い、その神格にとって可能な「神業」しか行使しないのである。
もう一度八岐大蛇の描写を虚心に読んでみよう。
「その目は赤い酸漿のようで‥‥その身に苔や桧・杉が生え‥‥その腹を見ると、いつも血がにじんで滴り落ちている」。
この描写から洪水を思い浮かべる人がいったいどれだけいるのだろうか。私には到底これが洪水をたとえているとは思えない。
では、そのように表現される八岐大蛇とは何なのか。
目は赤く輝き、背にはくすんだ緑が覆い、腹は血のように赤く、その血を周囲にまき散らすもの。そして、蛇のように地を這い、四方八方に広がってそこにあるものをことごとく呑み尽くす恐ろしいもの。
これに該当するものは一つしかないだろう。八岐大蛇は溶岩流(火砕流)である。
これならば素戔嗚は「退治」できる。いや、素戔嗚でなければ「退治」できないと言った方がいいだろう。どうやって「退治」するか。「大蛇」に雨を浴びせかければいいのである。
しかし、素戔嗚だけでは雨を降らせることができない。そのためには水神の協力が不可欠である。そこで、素戔嗚は櫛灘姫を櫛にして角髪に挿す。つまり、櫛灘姫こそが水神である。正確に言えば、櫛灘姫は海の神であるとともに川の神だろう。櫛の柄の部分が海、歯の部分が川である。櫛状に何本もの川が並行して海に流れ込んでいる様を神名としたのが櫛灘姫だと思われる。
こうして、風神・素戔嗚は海と川の女神・櫛灘姫を髪に挿すことで雨という強力な武器(剣)を手に入れ、この剣を持って溶岩流・八岐大蛇に立ち向かう。そして、これに雨を降り注ぎ、浴びせかけてめった斬りにするのである。
ここまでの説明で明らかなように、現実に「大蛇」が現れたとき、その脅威から人々を救ってくれるのは素戔嗚しかいない。人々は素戔嗚に頼るしかないのである。こんなときに日神・天照に縋る者は誰もいない。
しかし、当時も八岐大蛇が毎年出現し、その度に素戔嗚が退治していたわけではないだろうから、おそらく「大蛇の死骸」があり、それもおかしな格好で、それとわかる「死に方」をしていたのだろう。だから、神話の原型は素戔嗚の事績として一地方で創られた「大蛇の死骸」の起源神話だと思われる。
その「地方神話」が「全国神話」にまで昇格し、「倭の神話」の体系に組み込まれていったわけだが、その理由はおそらく二つある。一つは足名椎であり、もう一つは草薙剣(天叢雲剣である。詳しいことは後述する。
神話の舞台
それでは、この神話の実際の舞台がどこかを検討しよう。「肥の河」を出雲の斐伊川とする通説−と言うより定説−は「八岐大蛇」の段階ですでに破綻している。なぜなら、斐伊川の流域には火山がない。「肥の河」の近辺には火山がなければならない。また、素戔嗚神話であることから、その川と火山は北方ないしは西方にあると思われる。
そこで、日本海側と九州をしらみつぶしに当たっていった。神話の舞台に該当するための条件は次の四点である。
一 父・足名椎、母・手名椎となる山が存在していること。
二 その山を源流にして櫛状に何本もの川が並行して流れ、海に注いでいること。
三 櫛状の川の源流付近に「大蛇の死骸」が目に見える形で存在していること。
四 櫛状の川とは別に、「肥の河」が付近を流れていること。
神話の舞台はこの条件をすべて満たしていなければならない。
神名が地名とはまったく別の観点から付けられていることはもうこの時点でわかっていた。総説で述べたことからの当然の帰結として、神名には「天与」のものである「心」が反映していなければならない。「櫛灘姫」の例からもそれは明らかである。それならば、神名に人間の付けた地名が使えるはずがない。ただし、逆に神名にあやかってそれを地名にした例はあるかもしれない。
しかし、記紀神話−特に出雲神話−に記された地名をどう取り扱うか、まだその方針が立っていなかった。そこで、下手な鉄砲でもいつか当たるだろうとの楽観的な見通しの下に、北は鳥海山、月山から西は霧島山、雲仙岳まで、とりわけ「肥の国」(肥前・肥後)は「肥の河」と関係があるかもしれないので、阿蘇山や経ヶ岳なども念入りに調べた。だが、結果から言えば、そんなことをするまでもなかった。それは「斐伊川」のすぐそばにあった。川がちょっと違っていただけである。「肥の河」は伯耆の「日野川」である。そして、山は「大山」である。「櫛灘姫」「大蛇の死骸」も含め、前記の条件をすべて満たす、この神話の舞台として適切な場所はここしかないだろう。そればかりか、条件以外の現実さえ、ことごとく神話の内容と一致する。
「肥の河」と「日野川」は現代では同じ発音になるが、上代特殊仮名遣いで「肥」は乙類、「日」は甲類なので、当時の発音は違っている。よく似ているとは言えるが、前詞章の解説で述べたように地名はあてにならないので、似ている必要もない。理屈ではそうなのだが、解釈結果から見ると、神話に出てくる出雲の地名と実際の舞台の地名とはどれも類似性があるように思える。地名に何らかの作為があるのかもしれない。出雲の地名より前に神話が成立していた?
それはさておき、では神々の本体の具体的な比定を行おう。
まず、櫛灘姫の「櫛の歯」は天神川と日野川の間にある加勢蛇川・洗川・矢筈川・勝田川・甲川・下市川・宮川・倉谷川・車谷川・名和川・川手川・阿弥陀川である。これらの川の源流にある大山が櫛灘姫の父・足名椎であり、母・手名椎もこの付近の山になる。宝珠山、烏ヶ山、豪円山などが候補になるが、櫛灘姫の母なので蒜山まで視野に入れる必要はないだろう。足名椎、手名椎を老夫婦としているのは、倭人たちが大山を老山だと認識していたことを表すものであり、それは現在でも崩壊量が年間七万立方メートルを超えるというこの山の有り様からすれば、的を射たものだと言えるだろう。
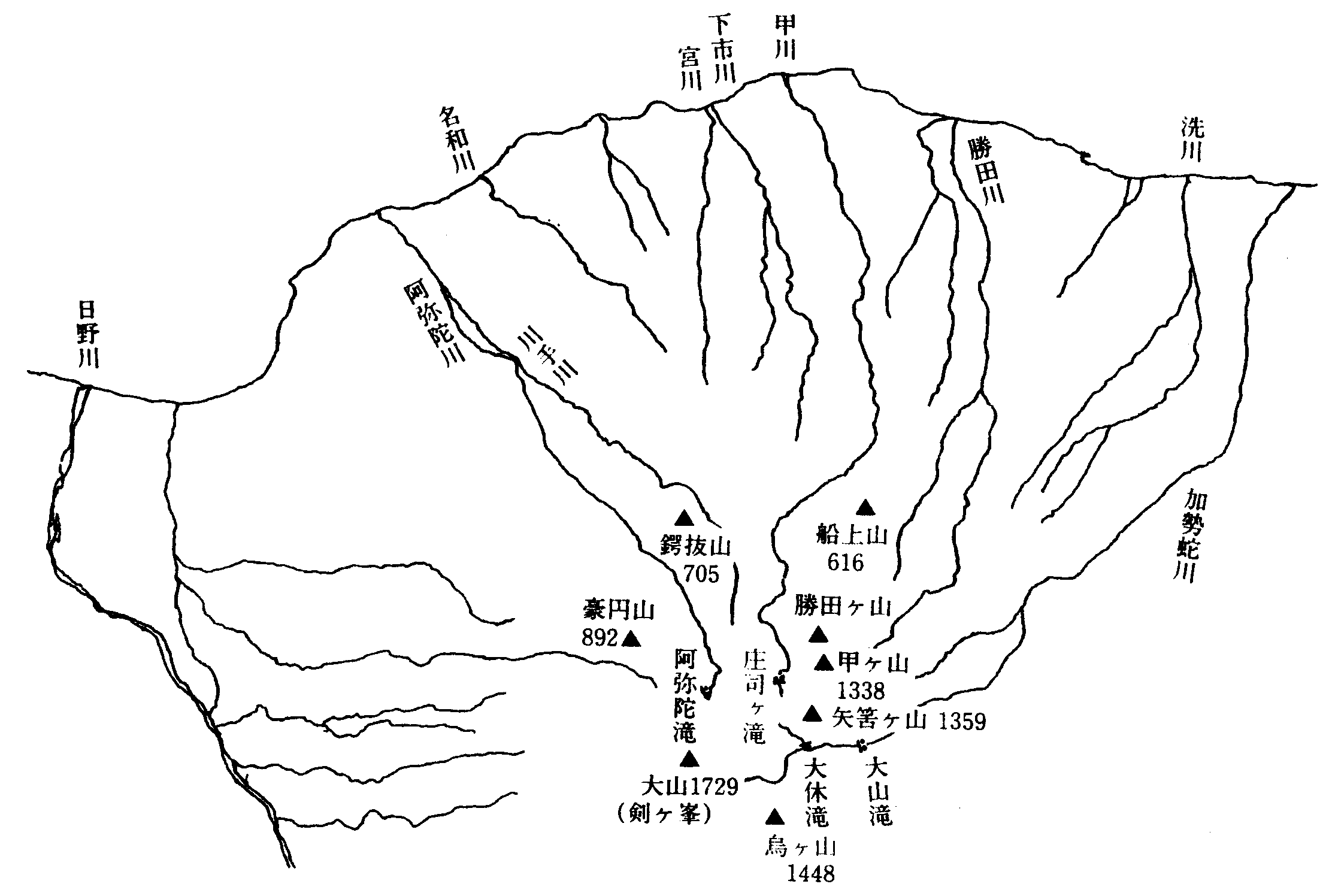 |
 |
この八岐大蛇神話の舞台の比定は、『風土記』によって正当性が傍証される。全文が現存している『出雲国風土記』はこの神話に一言も触れていない。これに対して、『伯耆国風土記逸文』には「伯耆」の国号の由来として記されている。
手摩乳、足摩乳の娘の稲田姫は、八頭の蛇が呑もうとするので山中に逃げていった。そのとき母がなかなか来なかったので、姫は「母来ませ、母来ませ」と言った。それで母来の国と名づけた。後にそれを改めて伯耆とした。(神名の表記は原文のまま)
八岐大蛇神話が国号の由来になっているほどならば、その神話に伯耆一の名山・大山が登場しないと考える方がむしろ不合理だろう。
従来説の欠陥
以上の説明から、従来の解釈のどこに欠陥があったのか、読者にもはっきり捉えることができるだろう。それは、「出雲の肥の河」を頭から「斐伊川」だと決めてかかったように、地名という、人間がいくらでも任意に変更できるものをあてにしたからである。そして、「櫛灘姫」(『紀』の表記は「奇稲田姫」)を無条件に「田の神」だと思い込んだように、漢字という「借り物」の字面の意味にとらわれたからである。
素戔嗚、八岐大蛇、櫛灘姫、足名椎、手名椎、草薙剣と、これだけ「天与」のものが登場するのだから、そちらから解釈すればいい。これら登場神の行動をすべて矛盾なく説明できる解釈、そして現実の中に存在している目に見える事象と一致する解釈、それがこの神話の意味内容である。地名は最終的な検証にしか使えない。漢字の字面の意味は解釈の参考にしかならない。
草薙剣
さて、残るは草薙剣である。八岐大蛇神話は「大蛇の死骸」の起源神話であると同時に、草薙剣誕生神話でもある。天孫降臨の際に天孫・火瓊瓊杵が携える「三種の神器」の一つがここで誕生する。この剣はその後記紀神話を飛び越えて『記』『紀』「人代」の巻の倭建命(日本武尊)の東征説話に再び登場する。この剣によって八岐大蛇神話は「倭の神話」の体系の中で重要な意義を担い、全国神話として通用するだけの話の広がりと深みを持つことになった。
その草薙剣の意義を考えよう。
通説である八岐大蛇=洪水説は、斐伊川の上流が砂鉄の産地であることから、これを草薙剣と結び付ける。そして、素戔嗚が天照に草薙剣を献上したのは、その砂鉄から剣を作り、それを大和朝廷に献上したことの神話的反映だと解する。例によっての政治的・歴史的解釈である。
だが、それでは神話の内容に何も実体がないことになってしまう。神話が何の意義も持たないものになってしまう。
本書の八岐大蛇=溶岩流説でも、草薙剣を鉄と結び付けることはできるかもしれない。しかし、そういう考え方をしている限り、「神話」として解釈することはできないだろう。白紙の状態から、つまり「常識」を疑うことから始めよう。草薙剣とは何なのか、それは本当に「剣」なのか、そこから考えていこう。
ここまでの詞章で「剣」は二回出てきた。一度目は第四詞章「軻遇突智」で伊奘諾が彗星を剣にした。二度目はこの詞章で素戔嗚が雨を剣にした。どちらも、持ち主の神格と場の状況にぴったり適った見事な比喩表現である。それならば、草薙剣も比喩なのではないか。そう考えるのが順当な判断だろう。草薙剣だけが本物の剣だと考える方がむしろ整合性を欠いている。本物の剣を風神・素戔嗚が日神・天照に献上したと考える方がよほど荒唐無稽である。
では、何を剣にたとえているのだろうか。
当然のことながら、その「剣」は火瓊瓊杵が携える剣として最もふさわしいものである。だから、火瓊瓊杵の神格と草薙剣の正体とは不可分の関係にある。
この詞章では草薙剣の誕生の経緯が語られているので、それを検討すれば、この剣がどういうものか推測できるだろう。さらには、火瓊瓊杵はその剣を携えるにふさわしい神なので、その神格もある程度絞り込めることになる。
それでは、誕生の経緯から「剣」の正体を探る手がかりを取り出してみよう。
一 剣は八岐大蛇の尾の中から出てくる。つまり、「剣」は溶岩流の中から出てくる。
二 剣に素戔嗚の剣の刃が当たって欠けている。つまり、「剣」に雨が当たって蒸発している。
三 剣の上に雲が群がっている。つまり、「剣」は雲を群がらせる。
四 剣は素戔嗚が発見している。つまり、「剣」は風神と関係がある。
五 素戔嗚はその剣を不思議な剣だと言い、その価値がわかっている。つまり、風神にとって、その「剣」は魅力的なものである。
六 素戔嗚は剣を自らのものにしていない。つまり、風神はその「剣」を使いこなせない。彼にとっては「剣」ではない。
七 素戔嗚は剣を天の神に献上している。つまり、風神はその「剣」が高天原の神に属するものだと考えた(『記』では日神・天照に献上している)。
何気なく読み過ごしてしまいそうな誕生の経緯の描写が、実はすべて草薙剣の特徴を的確に表現した比喩になっている。練りに練られた、大変な比喩表現である。
さらに、天孫降臨の場面からもう二点付け加えよう。
八 剣は天照が火瓊瓊杵に授けている。つまり、「剣」は日神とも関係がある。
九 火瓊瓊杵はそれを自らの剣にしている。つまり、天孫・火瓊瓊杵の神格にとって、それはまさに至上の「剣」である。
以上九点すべての条件を満たすもの、それが「草薙剣」である。神話的に言えば、「草薙剣」はこういう誕生の経緯があったから、現在見られるような特徴を持っている。
さて、草薙剣とはいったい何なのか。本書の解釈は第二四詞章「火瓊瓊杵」の解説で述べるが、それを考える上では、倭建命の東征説話の内容も十分参考になりそうである。ただし、『記』には「脚色」があるようなので、『紀』の方がわかりやすいと思われる。
また、「剣」を携える火瓊瓊杵の神格も絞り込めることになる。その上で、親子関係や第二七詞章「木花開耶姫」との整合も考えあわせるなら、その神格は確定できるだろう。すでに火瓊瓊杵=穀霊説は成立することが困難になっている。
それにしても、草薙剣の神話は、その構想の前提としてどれほど膨大な経験と思索の蓄積があり、最終型にどれだけの人の思考力が結集されているかを感じさせてくれる。『紀』に草薙剣を天の神に献上しない異伝があるから、そして天孫降臨神話に草薙剣が出てこない異伝があるから、われわれはその進化の跡を知ることができる。古代人の思考力の粋を集めた神話、それが草薙剣の神話であり、ひいては天孫降臨神話である。
足名椎=灘宮主
ところで、八岐大蛇神話が全国神話に昇格した理由は、草薙剣の他におそらくもう一つある。足名椎=大山である。この神話の結果として、足名椎は灘宮主になる。だから、八岐大蛇神話は「大蛇の死骸」の起源神話であり、草薙剣誕生神話であると同時に、灘宮主起源神話でもある。
灘宮主の意義はことさら論証するまでもないだろう。当然「出雲」の盟主である。この神話によって、足名椎は「倭の神話」の中できわめて重要な意義を持つ「出雲」という地の盟主として承認される。現代風に言えば、大山が山陰地方を代表するものとして当時のすべての人々に認知される。「倭の神話」での「出雲」の重要性を考えるなら、これだけでも全国神話に昇格する理由は十分である。
当時の人々にとって、大山は名実ともに「出雲」の盟主だった。そのことをこの神話は確然と語っている。おそらく現在でも、山陰地方に住む人で大山をこの地方随一の名山とすることに異を唱える人は誰もいないだろう。また逆に、大山以外の何をこの地方の代表に置いても異論百出することだろう。つまり、現在でも大山だけがこの地方の盟主になる資格を持つ。「倭の神話」に採用される所以である。
神々の関係
ここで、この神話に出てくる神々の関係を考察してみよう。
足名椎=大山と櫛灘姫=櫛状の川との親子関係は、川とその源流にある山との関係なので、誰からも文句は出ないだろう。ただし、足名椎、手名椎、灘宮主の本体をそれぞれどの山とするかは『記』と『紀』で異なる。『記』では足名椎=灘宮主=大山であり、母・手名椎はその付近の山になる。『紀』本文では足名椎、手名椎の夫婦が灘宮主=大山になっているので、大山の弥山・剣ヶ峰・天狗ヶ峰・象ヶ鼻・三鈷峰という山稜の連なりを夫婦とするのだろう。『紀』第二の一書では灘宮主を櫛灘姫の母にしているが、その場合には大山は櫛灘姫の母になる。こちらの方が古型だと思うが、そうすると時代が下って大山を櫛灘姫の母から父へ変更したのかもしれない。倭の社会の母系制から父系制への移行を反映しているともとれる。
次に、櫛灘姫=日本海を風神・素戔嗚の妻とすることも、日本海と大陸からの季節風との関係を考えるなら、首をかしげる人はいないだろう。山陰地方の天候を特徴付ける山陰型日本海岸式気候は大陸から吹く季節風と日本海を流れる対馬海流によってもたらされる。その影響でこの地は曇、雨、雪の日が多く、天候が変わりやすい。そういう、この地方の風と海との関係を神々の関係として表すなら、夫婦以上の適切な関係はない。
さらに、足名椎=大山が風神・素戔嗚の舅になるという関係も、日本海から吹きつける風の中に凛然と聳え立つ大山の姿を鮮明に印象付けてくれる。
このように、八岐大蛇神話はこの地方の風と海と川と山との関係を三神の関係として簡潔に表現する。
「倭の神話」の中の神々の関係がどれほど入念に構成されているかを、われわれはこの神話からも知ることができる。また、古代人の自然認識の的確さと深さも、この神話から知らされることになる。
英知の結晶
以上の説明から、八岐大蛇神話とはものすごい神話なのだということがよくわかると思う。
素戔嗚が八岐大蛇を退治する場面の比喩表現とそれを生み出した想像力だけでも格段の価値があるのに、そればかりか配意がさりげない描写にまで及び、叙述をことごとく現実と一致させている。そこに、精確な自然認識に基づいて構想された神々の関係を重ね合わせて、何の齟齬も見せない。さらに、他の神話をも視野に収めた別の重要な意義を加えて文脈にぴったりはめ込み、その上で綿密に練り上げた比喩でそれらすべての表現を揃えて何の無駄も余さない。
こうして、八岐大蛇神話はその中で神話世界と現実世界とが完全に融け合って一体となり、現実に即しつつも現実を超越する神々の姿を浮き彫りにする。
「英知の結晶」とは、きっとこういう神話のために用意された言葉なのだろう。
〈〈 「第一部「天地」総括」へ