素戔嗚神話(第一四詞章「八岐大蛇」まで)
第一三詞章 大宜都姫
《出典》『記』
[神話の超越性]
地名の神話的意義
記紀神話を基に「倭の神話」の最終型を復元し、詞篇として現代語に訳すにあたって、「倭の神話」には間違いなくあったにもかかわらず、あまり詞篇には書き記さないようにしたものがある。それは地名である。
天体神話では、ある事件が水平線上で起こった場合、その「場所」というのは本来ない。事件が起こった「方角」があるだけである。例えば、第六詞章「三貴子誕生」の日神誕生の「地」は東という「方角」であり、誕生した「場所」というのはない。
一方、天体とまったく関係のない神話では、事件が起こった「方角」というのは本来ない。その「場所」があるだけである。例えば、第一五詞章「因幡の白兎」の舞台は因幡という「場所」であって、因幡方面という「方角」ではない。
それでは、地上を舞台とした神話に天体が関わっている場合、例えば神話の舞台が原作地から見て西方のある「場所」になっていて、その「方角」に星の神が「天降り」をするという場合、その「地」はどう表記すればいいだろうか。
「倭の神話」では、事件がどこで起こったかを表すのに方角と場所を融合して地名で表している。そして、神話がある土地で作られてから別の土地に伝播していくと、「国譲り神話」のように天体が大きな役割を占めている神話は事件が起こった場所が変わってくる。方角は変わらずに場所が変わる。場所より方角の方が大事なのである。
このことは、前詞章の解説を読み終えた読者には容易に理解できるだろう。神話がいつ、どこで、どのように語られたのかを考えてみればいい。未明に、「夜明け前の祭事」の場で、星々を眺めながら語られたのだろうということはすぐに想像がつく。そうすると、どの土地でも日は東からしか昇らず、星が地平に沈むのは西(北西)しかないので、天体と結びついた神話は方角を変えると事件そのものが意味をなさなくなってしまう。だから、伝播した土地では方角を変えずに場所を変える。
ところが、神話は方角ではなく地名で語られるため、原作地では西(北西)は所によって球磨であり出雲であり越(高志)であったりするにもかかわらず、奈良に伝えられるとすべて出雲になってしまう。出雲を舞台とする、いわゆる「出雲神話」が記紀神話全体の中で大きな位置を占めているのはこのためであり、第二三詞章「事代主と建御名方」のように明らかに奈良起源ではない神話も、つまり本来は出雲を舞台として創られてはいない神話も、奈良に伝えられることで出雲神話に組み込まれてしまう。このような場合、神話の中の地名は原則として方角しか表さない。つまり、「倭の神話」では「日向」が「東の方角」を意味し、「出雲」が「西北西を中心とする方角」の意味で用いられていて、現在のその地名の場所とは直接の関係を持っていない。
通常、地上を舞台とする神話はそこに登場する神や事物が舞台になっている土地と密接に結びついているため、その神格や事物の意味がわかっている者にとっては、どこを舞台としているかが神話の内容から明白である。例えば、仮に「琵琶湖の神」の神名が「ヒコネ」であり、「近江盆地の神」の神名が「ヲトミ」だとして、「あるとき、ヒコネが怒ってヲトミを飲み込んだ」という神話があったとしたら、これだけでどこのどういう事件の話であるかは誰でもわかる。神話の中でわざわざ「滋賀県の近江盆地で」などと断るまでもない。地上を舞台とし、土地と結びついている神や事物が登場する神話には、場所の表記は本来不要なのである。その種の神話で場所を表す必要があるのは、第一五詞章「因幡の白兎」のように「全国神話」になっていないために知名度が低い場合や、第二三詞章「事代主と建御名方」のように本来の舞台とは違う場所(ここでは「諏訪湖」)が出てくる場合だけである。
だから、そういう神話での地名は、既に述べたように天体との関係を、つまり方角を表す役割しか持っていない。それならば、伝播した先でいくら地名を変更しても神話の意味は少しも失われない。むしろ原作地と方角との関係を維持するためには、そのまま平行移動させて地名を変更した方が好ましい。神話が天体を見ながら語られているため、その地名のようなものが実は方角を表していることを誰もがわかっているからである。
こうして、奈良に伝播した「天降り」神話は、舞台が出雲という「場所」になり、その関係から大国主の神話はすべて出雲を舞台とした神話として地名が統一される。その方が体系として見れば全体としての整合性がとれることになる。
「国の神」は伊奘諾・伊奘冉系列の具象神なので、本体から遊離してどこへでも「出張」できる。また、地名はあくまでも「人為」のものなので、いくらでも変更できる。これに対して、神話の内容は「天与」のものなので、勝手に変更されることはない。だから、登場する神々の神格がわかっている者にとっては、それで何も問題がない。神話の内容が現実の何にあたるのかは明白なのである。
つまり、神話を聞く者にとって、大国主に関する出雲神話は次のように理解される。
神話的過去において、大国主は出雲に「出張」していた。出雲を本拠にして「国造り」を行った。そして、出雲に「天降り」してきた星の神と国譲りの交渉が行われた。交渉成立後、大国主はその本体が存在している現在の地へ移った。「出張」中に大国主が自らに受けた事件の結果は、すべて現在の本体に現れている。また、同じく「出張」中に大国主が他の神や事物に対して加えた事件の結果も、すべて現在のそれらの神の本体や事物に現れている。
地上の空間だけを問題にするなら、この中の「出雲」が「東京」でも「大阪」でも、果ては「ロンドン」でも「ニューヨーク」でもまったく問題がないのはすぐわかるだろう。問題になるのは星の神が「天降り」をする「場所」である。これは「天与」のものなので変更できない。つまり、その「場所」は神話が語られる場所の西(北西)になければならない。その「天降り」をする「場所」として定められた地が「出雲」である。こうして、「出雲」という地も「天与の地」となって「倭の神話」に組み込まれ、体系の中で重要な役割を受け持つことになる。
また、「出雲」にはもう一つの「天与」がある。夏至の時、太陽は西北西に沈む。それより北に沈むことはない。奈良から見て西北西の果てにある地が「出雲」である。
それでは、逆に冬至の時、太陽はどこに沈むだろうか。当然西南西に沈む。それより南に沈むことはない。では、奈良から見て西南西の果てにある地はどこだろうか。それは「吾田の長屋の笠狭碕」である。だから、奈良ではそこが、常に「朝日の直刺す国、夕日の日照る国」(『記』)としての「天与の地」であり、「天孫降臨の地」とされることになる−飛鳥にある酒船石は、そこに刻まれた溝が正確に夏至と冬至の時の日没の方向を指し示しているが、この石が「倭の神話」と関係があるかどうかはわからない−。ここでも、神話の地名は現実のその場所とは何の関係もない。それは神話として意義のある「天与の地」にすぎない。
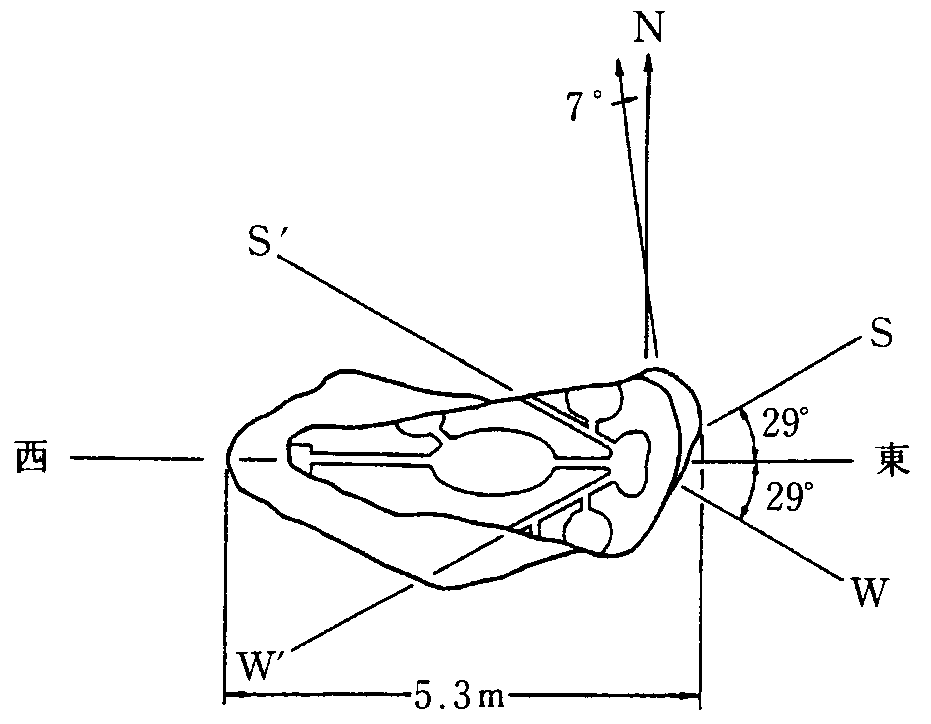 |
もっとも、それは「倭の神話」だけの特質ではなく、すべての神話が有する性質なのかもしれない。少なくとも、どの時代のどこの国の神話でも神は空間を超越した存在である。
また、総説で述べたように、神話の中で起こった事件の結果は時間を超えて現在にまで受け継がれる。このような「超時間性」はすべての神話に共通する性質である。そして、どの神話でも神は時間を超越した存在である。
それならば、空間を超越した「超空間性」も、すべての神話に共通する性質だと考えた方がいいようにも思える。「神とは何か」、「神話とは何か」という問題とも関わってくるが、神話が文字通りの「神話」であるためには、神が時間も空間も超越する存在であるだけでなく、神話の内容自体も時間と空間とをともに超越する必要があるのかもしれない。
素戔嗚と「出雲」
ところで、神話の地名をそのまま信用すると誤解のもとになるのは、「気象神話」にもあてはまる。
素戔嗚は実体不明の神であり、遠くから風を吹かせてくるので、その住む場所として考案されたのが「根国」という他界である。
では、その「根国」はいったいどこにあるのだろうか。
それは雲が流れてくる先にある。そして北風が吹いてくる先にある。つまり奈良から見て出雲方面にある。さらには、その先の朝鮮半島方面にある。だから、素戔嗚の「気象神話」でも地名は方角として表されている。記紀神話で素戔嗚が出雲や朝鮮半島と関わるのは当然なのである。
「出雲」という地名がいつ成立したのかは歴史の霧の彼方にあるが、「雲の湧き出る地」という「出雲」の本来の意味からすれば、その地名はそこに住む人の命名ではなく、「雲の湧き出る地」をその方角に見る人が名付けた地名のようにも思える。それならば、地名の成立と出雲神話の成立とははたしてどちらが先なのかも考える必要があるのではないだろうか。ひょっとしたら出雲神話の方が先に成立し、その神話の舞台とされた場所が「出雲」と呼ばれ、いつしかそれが特定の場所と結びついて地名になったのかもしれない。
「出雲神話」がいつ成立したのか、それも歴史の霧の彼方にあるが、その古さに思い及ぶとき、「地名より先に神話があった」という言挙げは、あながち冗談とばかりは言い切れないもっともらしさを持つ。
出雲神話の解釈の方法
以上述べてきたように、出雲神話は神話的過去の「出雲」を舞台にしてはいるが、必ずしも現実の出雲を舞台にしているわけではない。また、それは出雲神話に限らず、高天原神話でも同じであることは言うまでもないだろう。だから、記紀神話に出てくる地名はその多くが特殊な意義を担って用いられていて、われわれの用法とはまったく異なっている。
このため、解釈に際して地名はあてにできないし、また、あてにしてはいけない。地名を考慮に入れずに、内容から解釈していくしかない。地名は解釈した後の、原作地の推定などに使える程度である。記紀神話を解釈するのが難しい理由の一つはここにある。
本書は、これまでの高天原神話=天体神話では地名にそれほど言及しなかった。神話の舞台が主として天球上なので、地上の場所を考える必要がなかったからである。しかし、この詞章から「出雲神話」が始まり、第一四詞章「八岐大蛇」以後は現実の地上世界が舞台となる。その場所を無視しては解説できない。
その上、先述したように、出雲神話に登場する神々は土地と密接に結びついているため、舞台となっている現実の場所がどこかわからないと神格を判断できない神話がある。神格がわかれば必然的に場所も決まるという神話もある。
だから、以後の詞章解説では、神話が現実のどの場所を舞台にしているのかも考察する。また、それによって、「倭の神話」がどの程度の空間の広がりを持っているかも明らかになるだろう。
外国神話との関連
ところで、出雲神話は神々が土地と結びついているからといって、必ずしもその神話の動機や構想の発祥がその土地であるとは限らない。発祥がその土地ではない、いや、それどころか、実は倭ではない−つまり外国起源である−という可能性も留保しておくべきだろう。現に「国産み神話」「黄泉国訪問神話」「穀物起源神話」「八岐大蛇神話」「天孫降臨神話」「死の起源神話」など、多くの神話で外国神話との類似が指摘されている。外国の神話が倭に伝わり、土着化して「倭の神話」の体系に組み込まれていったとしても少しもおかしくはない。
とは言っても、私には国産の割合はかなり大きいように思えるし、たとえ外国起源のものがあったとしても、倭に入って定着する過程で大幅な変貌を遂げていることは確かだろう。この詞章を除けば、どの神話を見ても、その体系の中につぎはぎのように挿入された痕跡のあるものは一つもない。どれもが完全にとけ込み、その神話世界の一部を構成して自らを輝かせている。
また、人間が創った「神話」であるならば、どの時代のどこの国の神話であれ、本質的な部分で万国共通とも言える普遍性があるのは当然だとも思える。「倭の神話」にその種の普遍性がなければ、かえってその神話性が疑われることにもなりかねない。
神話の普遍性と人間の普遍性
人間が自らを超えるものの存在を措定したのは万国共通と言っていいだろう。神が人間を創ったのではなく、人間が神を創った。人間が現実世界に生を享け、自らの存在を自覚し、周囲の世界のあり方に気付いたとき、人間はその世界を創ったものとしての神を創案した。おそらく、創案せざるをえなかった。
時代によって、地域によって、民族によって、具体的な神の在り方は違う。しかし、それが超越者であるという点では何の違いもない。神という存在が、人間の本質に根ざしたところから生まれてきたことを疑うことはできないだろう。また、神を語る神話が、その神話を信じる者たちの現実世界での生のあり方と深く関わるものであることも確かだろう。それならば、神話の普遍性は、人間の普遍性をも示してくれる。
「神は死んだ」と言われる現代にあって、われわれは自らの問題として神を考え、神について語ることをやめてしまった。神を「過去の遺物」として捉えることで自分とは切り離し、自分たちはもうその「神」を乗り越えていると多くの現代人は考えている。だから、われわれは、「神」という言葉から、人間の無知からくる迷信、未開野蛮な時代の自然に対する根拠のない畏怖、といった印象しか持たない。そして、その印象は現代の怪しげな新興宗教の狂信的所作を見ることで一層増幅される。
しかし、神話が生きていた時代の「神」とは、そういう既成の概念で捉えられている神とはまったく異なる。「倭の神話」はわれわれにそのことを教えてくれるだろう。また、その「神」が、人間そのものと、人間の生き方そのものと、どれほど深く関わっているかも教えてくれるだろう。
「神とは何か」を問うことは「人間とは何か」を問うことと表裏一体の関係にある。「神話とは何か」という問いは「人間にとって世界とは何か」という問いとその本源において重なる。また、その問いは「芸術とは何か」という問いとも究極において交わる。
現代にあっても、「人間」そのものについての問いかけは常に新しい問題としてわれわれの前にある。「生きる」ことの意味は、本来最も切実な問題としてわれわれすべての者に突きつけられている。それならば、神とは何か、神話とは何か、という問いは、古代人を知るためよりも、むしろわれわれ自身を知るためにこそ与えられるべきものなのかもしれない。
記紀神話は世界の神話の中でも類例のない整備された体系を持っている。世界中で最も完成された神話として現代にまで残っている。もし、記紀神話が、本書の主張するように「倭の神話」そのものであるならば、それは「日本人とは何か」を考える際の重要な示唆を与えてくれる「日本最大の精神的遺産」であるばかりではなく、さらに深く「人間」そのものを考える上で貴重な貢献をしてくれる「世界屈指の精神的遺産」でもあることになるだろう。
これについては、第一七詞章「根国行き」の解説も参照してほしい。
[詞章の説明]
疑問点
さて、やっと本来の詞章解説に入れるが、試論(補助解説)で述べたように、この詞章がはたして「倭の神話」の最終型に含まれていたかは疑問がある。ただし、天武・持統朝以後の創作だと考えているわけではない。また、穀物神殺害の「犯人」を第八詞章「月読」の月読からこの詞章の素戔嗚に変更したと考えているわけでもない。いくら『記』でも、そこまでの「脚色」はしないと思われる。
だから、素戔嗚が穀物神を殺す神話は「倭の神話」に間違いなくあったのだろう。ただ、それが最終型に含まれていたのか、そして天岩屋神話と八岐大蛇神話に挟まれるこの位置にあったのかは考えてみるべきだと思っているだけである。星座との整合性だけでなく、天孫降臨神話とも矛盾しないようにする必要があるため、最終型のこの位置にあったとするには、かなり複雑な解釈を求められるだろう。
そのため、殺す側から捉えた意義、素戔嗚神話としての意義は、もう一段詳しく解明されないと論じられない。ここでは、殺される側から捉えた意義、穀物起源神話の意義を説明したい。
穀物起源神話の意義
神話は歴史ではない。歴史は過去の一回的事実を記したものであり、現実の中にはもうその事実は残っていない。そういう、現実に存在しないものは神話にはなれない。歴史が神話として採用されるとしたら、その結果が目に見える事象として現実に残っている場合だけである。神話に出てくる事項は、神話的過去から現在に至るまで、時間を超えて存在し続けている。そのことは、これまでの高天原神話で見てきた通りである。
それでは、大宜都姫の場合はどうだろうか。「殺される女神」として、あるいは「殺された女神」として、現実に存在しているだろうか。われわれは誰もその女神を見ることはできないし、それは古代人でも同様である。われわれも古代人も、目にできるのは女神が殺された結果生じた穀物だけである。だから、そこでは事件の前の状態もその後の状態も現実に存在していない。存在しているのは事件の結果生じたものだけである。
では、そういう神話は何を意味しているのだろうか。
それは、事件の結果生じたものが、現在も繰り返し同じ事件に遭遇していることを表している。穀物起源神話で言えば、穀物の祖神である女神が殺されたために、現在も穀物は殺され、そして女神は殺されることで穀物を生んだように、穀物も殺されることで自らを再生させる。つまり、穀物起源神話とは穀物の死と再生の起源を語る神話なのである。
かつて、穀物の女神は殺された。もし殺されなければ、女神はいつまでも一柱の神として在った。女神は死ぬことで、自らの中から穀物を生み出した。
今、穀物は殺される。もし殺されなければ、穀物はいつまでも一粒の種子として在る。穀物は土に落ちて死ぬことで、やがてたわわに穂を垂らし、豊かな稔りを生み出す。こうして、穀物は自らを殺して自らを生かし、それによって、われわれの命をも支えてくれる。
穀物起源神話とは、そういう神話である。
論者の中には、これを聖書のアダムとイブがエデンの園から追放される、いわゆる楽園追放と同じように考え、穀物神を殺してしまったために人間は働かなければならなくなったという見方をする者があるが、そういう話は聖書のような「人間の神話」にはなっても、この神話のような「神の神話」にはなれない。だいいち、そのような労働苦役観は「倭の神話」にはない。日本の伝統的な思想にもないだろう。それはもともと西洋の考え方である。
穀物起源神話は、聖書で言うなら、むしろヨハネ福音書の「一粒の麦」の話に近いだろう。
もっとも、聖書の楽園追放の話も苦役の起源を語る神話ではない。それは「人間の原罪」を語る神話である。「倭の神話」には「原罪」は出てこないが、人間の置かれている同じ状況を別の思想によって意義付けた「人間の神話」は第二部「国」の中に入っているようである。
[出雲神話の特色]
擬人化された神
素戔嗚を人間の神格化だとする発想はどこから出てきたのだろうか。素戔嗚を人間にするから天照まで人間にしてしまう。さすがに伊奘諾・伊奘冉を人間にする論者はあまりいないようだが、中には天御中主まで人間にするという冗談なのか本気なのかわからないことを言う者までいる。こうなると人間中心主義の発想も極まることになる。彼の目には人間しか映らないのだろう。彼にとっては人間だけが「歴史」の主人公なのだろう。人間以外のものはすべて人間にかしずく存在でしかないのだろう。
記紀神話を歴史的に解釈するという考え方も、つまりは人間を中心にしてしかものを考えられない人間中心主義の表れなのかもしれない。しかし、人間中心主義は、西洋でもどんなに古く見積もってもルネサンス以後の、常識的に考えれば産業革命と近代科学の発達によって「神が死んだ」後の、たかだか数百年程度の近年の風潮にすぎない。日本ではもっと短いだろう。
古代人は擬人化した神を持っていたが、その神を人間の外に置いたので、人間中心主義には陥らなかった。そればかりか、神の視点から人間や世界を捉えるという現代人にはない「客観性」さえ身につけている。
われわれの目から見れば不合理かもしれない。無知かもしれない。だが、彼らはわれわれよりも自然に対して謙虚である。自然の大きさをよく知っている。自分たちが自分たちの力だけで生きているのではなく、自然によって生かされていることも知っている。そして、世界がどれほど驚異に満ちているのかも知っている。
文明国の神話
「高天原神話」は確かに倭人たちの雄大な想像力と麗しい詩情を感じさせてくれる。天体への強い関心と天体に対する彼らの憧憬にも似た思いも感じ取れる。だが、そこに生活の実感に根ざした深い思索はそれほど読み取れないだろう。倭人たちが周囲の自然とどのように関わり、どのような生き方をしていたのか、そして日々の生活の中で何を求め、何に悩み、何を考えていたのか、それを高天原神話から読み取ることは難しい。
それを感じさせてくれるのは、むしろ「出雲神話」である。素戔嗚と大国主の存在である。
私が素戔嗚の神話から感じるものは、自分たちの思うままにならない自然の巨大な力の中で、だがそれに屈せずにたくましく生きる人々の姿である。大国主の神話から感じるものは、自然に働きかけて汗を流し、自然の恵みに感謝して自然とともに生きる人々の姿である。決してただやみくもに自然の力を畏れ、呪術によって救いを求める哀れな姿ではない。この二神の存在があるからこそ、出雲神話は高天原神話と天孫降臨神話に伍してその輝きを放ち、「倭の神話」の価値をひときわ引き上げてくれる。
出雲神話は、どの神話も洗練された比喩表現で彩られている。そして、その比喩がさりげない描写にまで行き届き、全編を統一した印象でまとめ上げている。美しい比喩も、大胆な比喩もある。幾星霜もかけて磨き抜かれたその的確な比喩表現は、時代を超えてわれわれの想像力をも呼び起こしてくれるだろう。そこに広がる精彩に富んだ古代人の神話世界にわれわれをも誘ってやまないだろう。古代人の知性と感性の煌めきを如実に示す、日本文学史に傑出した比喩表現がここに連なっている。
人間が自然の中で自然とともに生きる、その生き方の崇高ささえ感じさせてくれる出雲神話こそ、「倭の神話」を奥深いものにして、これを「文明国の神話」にまで高めてくれる真骨頂だと私は考えている。
〈〈 「第一四詞章 八岐大蛇」へ
〈〈 「第一四詞章 八岐大蛇」へ