大国主神話(第一八詞章「国造り」まで)
第一五詞章 因幡の白兎
《出典》『記』
[神話の表現]
「うさぎ」というあだ名の教師がいたとする。生徒がその教師の様子を見て言う。
「あ、うさぎが新しい背広を着てる。」
日頃よく耳にする、ありふれた比喩である−厳密に言えば、あだ名には比喩以外のものもあるが、本書では話をわかりやすくするために、その「もの」の本来の名やその「こと」の本来の言い方以外の表現はすべて比喩だとして説明する。だから、神名はすべて比喩である−。比喩だということさえ意識していないことも多い。「モーツァルトを聴く」や「電気をつける」を比喩だと意識して話す人はいないのと同じである。もしこの比喩を比喩と取らずに額面通り受け取って、「背広を着るうさぎがいるのか」などと思う人がいるとしたら、彼は喜劇の格好の題材を提供してくれる人であり、その頭の固さはいかんともしがたい。だが、こと神話の解釈では、気を付けていないと、われわれの頭はこういう「いかんともしがたい固い頭」にたやすく変わってしまう。
この種の比喩が通用するためには、話す者と聞く者との間に前提となる共通の知識が必要である。先の例で言えば、「うさぎ」とは何を意味するのかをお互い了解していてはじめて比喩として通用する。そして、共通の知識を持つ者の間で同じことが話されるたびに、月並みな表現は次々に淘汰されていき、文全体が比喩化して表現は次第に素材から離れていく。「うさぎが新しい背広を着ている」は「うさぎが新しい毛皮を着ている」になり、ついには「うさぎの毛皮が生え変わっている」と変わる。こうなると、「うさぎ」の意味がわからない第三者は完全に文の意味を誤解する。
神話が生きていた時代には、神名だけでそれが何の神格化であるかを皆が了解していたはずであり、それを前提として神話が創られている以上、神話の表現は幾ひねりもしてあると覚悟した方がいい。神として擬人化しているだけですでに擬人法であり、記紀神話の場合にはさらに比喩が積み重なっている。当然だろう。「倭の神話」は「夜明け前の祭事」の場で何百回、何千回、何万回語られたことだろうか。あるいはもっと多いかもしれない。そして、語られる度に表現は磨かれ、内容は深まっていく。
神話解釈の難しさはこの点にもあって、神名の意味がわからなくなった現代で、細部の表現にこだわるのはきわめて危険であり、ややもするととんでもない解釈に陥ることになる。むしろ文脈を押さえ、全体の叙述から大枠の解釈を行って、その上で神名の意味や細部の表現を詰め、解釈の検証をしていくという方法を採るべきだろう。「うさぎの毛皮が生え変わっている」の「毛皮」とは何か、「生え変わる」とは何かをはじめに論じても無意味である。
これまでの記紀注釈学が記紀神話の解釈にほとんど何の貢献もできなかったのはこのためである。注釈学は比喩を用いない法律のような文章で力を最大限に発揮する。論理を積み上げた精緻で体系的な学問を構築できる。しかし、記紀神話のように全編比喩表現と言ってもいいくらい比喩が多用されている文章の意味を知ろうとするにはまったく無力である。語句の字面の意味はわかる。だから、叙述にどのように漢籍が引用され、習俗が反映しているかは細密なまでの研究成果が得られる。しかし、比喩としての語句の意味は注釈からは決して出てこない。かえって、字面の意味にとらわれる分だけ、「いかんともしがたい固い頭」の持ち主になってしまう危険性は大きい。
本居宣長の「頭の固さ」はおそらくこのせいだろう。『記』を注釈によって解釈しようとしたために、いにしえの「大和心」の宝庫とも言うべき記紀神話からは「大和心」を読み取れず、天武・持統朝の「脚色」だと思われる倭建命の言葉をそのまま受け取って感激することになってしまった。『記』に対する彼の多大な功績まで否定するつもりは毛頭ないが、彼の『古事記伝』は畢生の大作であったがゆえになおさら、その後の研究の方向性を誤らせた罪は大きいのかもしれない。
[詞章の解釈]
この詞章は「因幡の白兎」としてあまりに有名である。方角は関係ないので、もともと因幡地方に「白兎」説話があり、それをもとに神話化がなされて因幡地方で語られていたものを『記』の原資料である『旧辞』が取り込んだのだろう。イソップの寓話のような教訓も含み、童心をくすぐるかわいらしい神話に仕上がっている。
しかし、残念ながらこの神話は神話としては因幡地方にしか通用しない地方神話である。「全国版」である中央の神話に採り上げるだけの話の広がりがあるとも思えない。『紀』に収録されていないのも当然なのかもしれない。同じく地方神話だった八岐大蛇神話が全国神話に採用されたことと比べると、話の広がりという点で大きな開きがあることは歴然としているだろう。
だが、われわれにしてみれば、この神話を『記』が記録してくれたのはありがたいことだった。この神話は地方神話だからこそ、記紀神話の中でもその素材が最もわかりやすいものの一つである。素材がどう加工され、研磨されて神話にまで進化していったかを知る好個の作品だろう。
ところが、誰もこの素材を考えようとしない。「白兎」が比喩であることは「八岐大蛇」が比喩であることと同様に自明のことなのに、その意味を押さえようとしない。そして、いきなり内容を読む。そうすると、「古代の王には呪医の資格が必要だった」という解釈が飛び出すことになる。「白兎を治療する」の「治療する」だけを額面通りに受け取った結果である。
「セーターのほころびを繕う」という文の「セーター」を擬人化したら、どういう表現になるだろうか。「セーターさんが傷を負って苦しんでいるので、治療する」という言い方になるだろう。「セーターさんの傷を繕う」とは決して言わない。「セーターさんの傷を治療する」と表現して一人前の比喩である。この文の「治療する」だけを捉えて「この人は医者なのだ」と言う者がもしあるとしたら‥‥。
それと同様に、「白兎」が文字通りの兎でないなら、「治療する」の意味も額面通りであるはずがない。
それでは、まず素材を探り出そう。
『因幡国風土記逸文』にも同じ説話があるので、この詞章の前段にあたる部分−『記』に載っていない部分−を引用する。
昔この竹(竹草の郡の竹林)の中に年老いた兎が住んでいた。あるとき、突然洪水が出て、その竹原が水にひたってしまった。波が洗って竹の根を掘ったのでみな崩れ損じてしまったが、この兎は竹の根に乗って流されているうちに隠岐の島に着いた。また水が引いてから後、もといた所に帰ろうと思ったけれども海を渡るだけの力がない。その時水の中にワニという魚があった。(以下この詞章と同じ内容になる)
また、因幡地方に白兎海岸があり、その沖に兎の形をした島があるということも考えあわせて、さて、この「白兎」は何の比喩か。
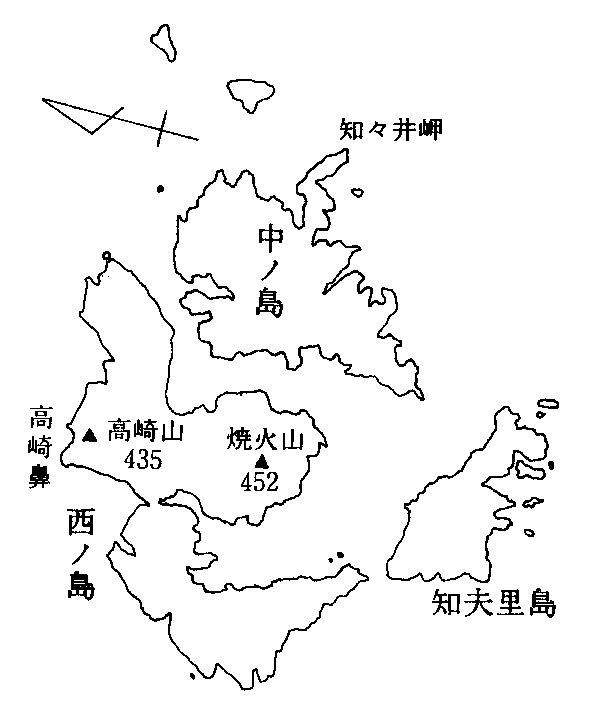 |
しかし、それでは「白兎」にならない。本州側に「白兎」がいなければならないが、その正体は何か。
『因幡国風土記逸文』の内容も考慮に入れると、これは兎の形をした池だろう。
条件としては、
一 池が兎の形をしていること。
二 近くに海に注いでいる川があること。
三 その池に流れ込んでいる川があること。
四 その池からも海に注ぐ川が出ていること。
以上の四点が揃っていれば万全だが、一.以外の一点が欠けていても認められるだろう。
だが、現在ではどの池かを判断するのは難しい。この近辺には海岸に沿って大小の池がかなりあり、池は島よりずっと形が変わり易いので、現在の池の形からでは何とも言えない。今もあるのかすらわからない。現存しているとしたら、湖山池から東郷池までの間のいずれかだろう。
そうすると、この神話の素材は次のようになる。
淡水湖であった兎形の池(白兎)が洪水のために海とつながって塩水湖になってしまった。それが、また海と切り離されて淡水湖に戻った。
その徴証がその池の近辺に残っていて、あるいは当時でも洪水の度に同じことが繰り返されていて、同じく兎形をした二つの島と結びついて兎が島に流されて戻ってきたという説話になる。ここでは当然、隠岐の兎形の島は島に流された兎、白兎海岸の沖の兎形の島は本州に戻る直前で鰐鮫に捕まった兎の見立てである。それがさらに大国主と結びつく。塩水湖が海水で傷だらけになった兎、淡水湖がもとの白兎に戻った兎。こうして、大国主の事績としての神話化が完成する。
「白兎を治療する」とは「塩水湖を淡水湖に戻す」ことだった。そう解してこそ、「国を造った神」という大国主の最初の仕事にふさわしいものになる。
当時の人々は「因幡の白兎」が何のたとえであるかを知っているから、この詞章の真の意味を正確に理解できる。それを踏まえてこの詞章を読んでほしい。
「白兎」という比喩を全編に貫き通し、鰐鮫や蒲の花という小道具を用いて白兎自体の話としても完全に意味が通るまでに表現を揃えている。後続の詞章との整合もきっちりなされている。一編の寓話として見ても申し分のないものに仕上がっている。
素材がどれほど磨き上げられて神話にまで昇華しているかがよくわかる。因幡地方にしか通用しない「地方神話」でさえこの通りである。誰もが文句のつけようのない傑作になっている。ましてや「全国神話」であれば、それがどれほどのものか容易に類推できるだろう。
[大国主の意義]
想像力の貧困
「因幡の白兎」のような大国主の事績に関する神話は、全国に数多くあったと思われる。現存する『風土記』には、その逸文を含めれば播磨・出雲・尾張・伊豆・因幡・伯耆・伊予とかなり広い範囲にわたって大国主の「国造り」が記されている。だが、すべて地方神話としてしか通用しないので、中央の神話には採用されなかったのだろう。やむをえないことではあるが、これは大国主にとって不幸だった。その種の神話がもっと採り上げてあれば、大国主の神格が誤解される可能性も小さかっただろう。
大国主は「倭の神話」の中にもともとあった神だとする論者は、私の知る限り一人もいない。また、大国主の神格については、多くの論者が「天皇家の前の王」、つまり人の神格化だとして疑わない。歴史学者や考古学者が躍起になって探しても、その存在を確認できないにもかかわらず、である。その上、誰もが大国主を「国譲り」という結果の側から捉え、その役割を「歴史的」な、あるいは「政治的」なものとして位置付けようとする。誰も大国主の意義を神話体系の中で捉え、文脈に即して理解しようとはしない。
残念なことである。どうして古代人の神話世界をことさら貧しくするような解釈しかとれないのだろうか。神話は何よりも「神話」として尊重されなければならない。神話を神話として理解できないとき、われわれはそれを「歴史」として解釈する前に、あるいは「造作」と言って切り捨てる前に、まず自らの「想像力の貧困」を疑ってみるべきである。
国を造った神
われわれは、日本の国土が、その誕生から数千万年、数億年という気の遠くなるような時間の中で、幾多の「国土の歴史」の変遷を経て現在の国土として存在していることを知っている。誕生したままの国土が現在の国土だと思っている人はいないだろう。
それでは、六世紀の倭人たちは、彼らの生活の基盤である国土が、伊奘冉(いざなみ)の産んだ原初の国土のままだと考えていただろうか。
とんでもないことである。大地とともに生き、大地と格闘して生活していた彼らが、その当の大地が原初のままの国土だなどと考えるはずがない。そんなことを考えるのは、机上の学問によって頭の中でしかものを考えようとしない後世の宮廷官人や学者だけである。
彼らは打製石器しか知らない旧石器時代人ではない。彼らは、すでに河内平野の大開発を進めるとともにあの巨大古墳を築造するという土木技術を持ち、隣国の新羅・百済からは大国だと敬仰されるだけの国家を作り、来るべき飛鳥文化を花開かせるに十分な文化的素地を身につけている。その彼らが、「伊奘冉が国土を産みました。人間も生みました。それがそのまま今の国土と人間です」などという単純で貧弱な神話をどうして信じるだろうか。
彼らは観念遊戯として神話を作ったのではない。神話は彼らが全能力を注いで創り上げた至高の知の結晶であり、そして何よりも、彼らの生活の実感と一致するものでなければならない。一致してはじめてそれは真実の話として人々に信じてもらえる。
彼らは、自らの踏みしめる大地が、その誕生の後でまさに神業としか言いようのない造作の妙を経ていることを生活体験から知っていた。伊奘冉が産んだ原初の国土は、ごつごつした岩だらけの、そして海と截然と分かたれた荒蕪の国土だった。その国土を、山裾はなだらかにおりて海と交わり、山野には植物が繁茂し、河口には沃野が広がる、そういう豊かな自然にあふれた麗しい国土に造り変えてくれたのは誰か。
国を造った神・大国主は神話が六世紀の「倭の神話」として成立するためには不可欠の神なのである。
倭人たちは大国主の「仕事の跡」をそこかしこに見ることができた。土木作業をしていれば、幾重にも積み重なった地層はいやでも目に入る。「ああ、大国主はこんなに幾度も土を盛ってくれたのだ」。彼らはきっとそう思ったことだろう。そして、大国主のその偉大な「国造り」に感謝したことだろう。彼らが目にするその地層の最上層には、自らの踏みしめる大地と同じ肥沃な土壌があり、そこに群生する植物があった。また時に、彼らはその最下層に伊奘冉の産んだ原初の国土−鞏固な岩盤−を見ることもあっただろう。
〈〈 「第一六詞章 大国主の受難」へ
〈〈 「第一六詞章 大国主の受難」へ