第二三詞章 事代主と建御名方
《出典》『紀』本文、『記』を基に、『紀』第一の一書で一部表現を改めた。
[詞章の解釈]
事代主
詞篇ではこの詞章を前詞章の別伝扱いしているが、『紀』本文も『記』もこの詞章を採用しているため、「倭の神話」ではこちらが六世紀の最終型であり、前詞章はその古型だと思われる。それにもかかわらず、本書が古型を正伝扱いしたのは、この詞章からでは事代主の神格を誤解してしまうからである。
事代主が当初から「言代主」として、つまり託宣神として構想され、その神格が神託を告げる神であったなら、前詞章のような異伝が生じる余地はない。託宣神という性格は、「コトシロ」という神名からの連想で生じた二次的なものだと思われる。少彦根(すくなひこね)が小神だとされたのと同様である。「コトシロ」の原義は「異域」「同域」などではないだろうか。
また、そうでないと神話体系が崩れてしまう。
託宣神であることが事代主の唯一の神格なら、当然抽象神である。高皇産霊・神皇産霊系列の神でなければならない。また、大国主の子として託宣神が生まれたのでは、その親子関係には何の「因果の鎖」もない。大国主系列の神なら具象神であり、その本体は国の中に具体的な「もの」として存在していなければならない。だから、事代主は具象神であり、地理神であって、その本体は固有名詞である。
事代主の本体の比定はそれほど難しくはないだろう。現在の形状が記紀神話に記されているので、そこから判断すればいい。
『紀』本文では「海の中に八重蒼柴籬を造り、船の縁を踏んで隠れた」とあり、『記』では「船を踏み傾けて、天の逆手を青柴垣に打ち成して隠れた」となっていて、ほとんど同じである。これをそのまま現実と照合すれば、本体は特定される。
つまり、事代主の本体は、富士山の子としてふさわしいもので、かつ、船をひっくり返したような格好で海に突き出ていて、その中央に緑に覆われている山が連なっているものである。
これに当てはまるものは一つしかないだろう。伊豆半島である。ただし、伊豆半島自体が本体なのか、天城の連山なのか、あるいはその海岸線なのかはわからない。
『記』に載っている大国主の系譜では、事代主の母は「神屋楯比売」となっている。神名の印象でしかないが、伊豆半島の形をそのまま神格化したような名なので、地盤としての伊豆半島が母神・神屋楯比売で、その上に乗っているのが子神・事代主だということかもしれない。
建御名方
次は建御名方である。
「千人引きの岩を手の先で軽々と差し上げて」という描写から言って、建御名方の本体はおそらく山である。それも山脈だろう。諏訪湖に逃げて行ったのなら、諏訪湖に向かって尾根が落ちている山脈だと思われる。そうすると、赤石山脈(南アルプス)と木曽山脈(中央アルプス)はすぐわかるが、「ミナカタ」という神名からすれば、もう一つ必要なのかもしれない。飛騨山脈(北アルプス)、伊那山地、中信高原などが考えられるが、建御名方の「岩を軽々と差し上げる手の先」や武甕槌がつかみつぶして投げつけた「手」をどう解するかにかかっているのだろう。
とにかく、諏訪湖周辺に「力持ち」である山が集まっているのは「天与の現実」なので、建御名方の話はその理由を説明する起源神話だと思われる。神話的に言えば、建御名方が諏訪湖まで逃げて行って武甕槌に誓ったから、諏訪湖に向かって山脈が落ちている、あるいは諏訪湖の近辺に山脈が連なっている、ということだろう。
ただし、倭人たちが三百万年前にできたと言われる八ヶ岳連峰を富士山の子だと考えていたとは思えない。地形だけでなく、現代の地学上の認識ともそれほど大きくは違わないだろう。
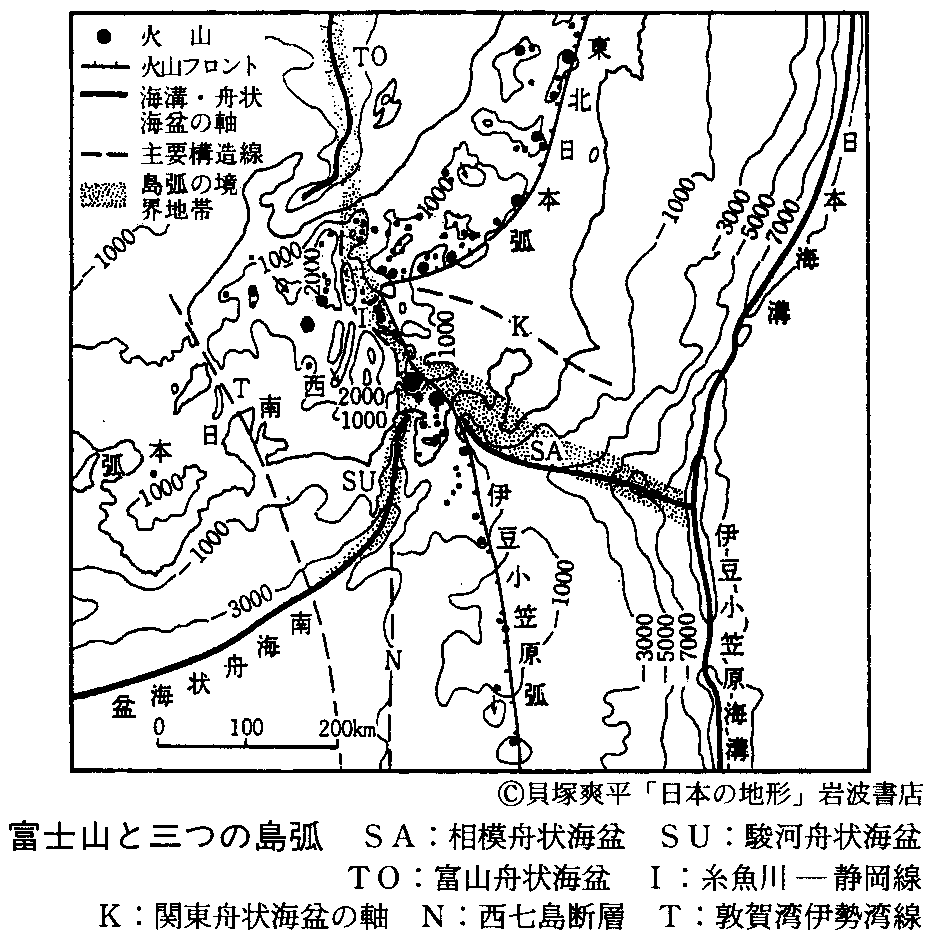 |