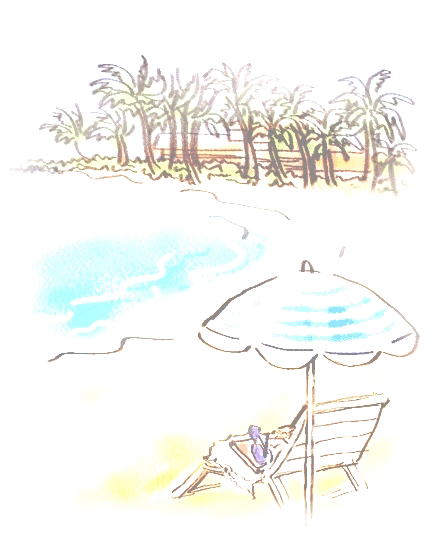
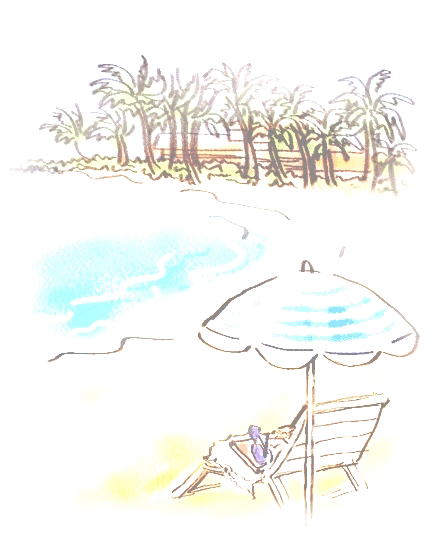
横浜市港北区新羽町 マッサージとリフレクソロジーの店 あいらんだ〜
マッサージと
リフレクソロジーの店
あいらんだ〜
未病とは、何か。
「未病」という言葉、最近TVや新聞などでよく見かけると思いませんか?
すでに一部の国語辞典などにも、掲載されるようになってきていますね。
そもそもこの「未病」、およそ2,000年前に編纂された現存する中国最古の医学書、「黄帝内経」の中において
はじめて登場した言葉とされています。
日本では江戸時代、貝原益軒の「養生訓」に、この「未病」について書かれた箇所があります。
「未病」とは、一言でいうならば「半健康で、病気に進行しつつある状態」とされています。
しかしながら、この「未病」という言葉は前述のとおりかなりポピュラーになってきてはいるものの
概念的にまだ統一され、確立された日本語となるまでには至っていません。
専門組織である「日本未病システム学会」の定義によれば、「自覚症状はないが、検査で異常がある状態」
および「自覚症状はあるが、検査で異常がない状態」の二つをあわせて「未病」としています。
こちらのほうが、より具体的なイメージができる、現代的な説明ですね。
(ちなみに同学会では、前者を「西洋型未病」、後者を「東洋型未病」に分類しています。)
未病、そして生活習慣病。
単なる東洋医学の言葉として捉えられていたこの「未病」、最近になってクローズアップされてきているのは
いったいナゼでしょうか。
その最大の理由は、現代社会に暮らす私たちの健康をおびやかす高血圧・高血脂症・肥満
(メタボリック・シンドローム)・脂肪肝などの危険因子が、日本人の全死因の6割を占めている
「三大成人病(がん・心臓病・脳卒中)」につながる、まさしく「未病」そのものであるからです。
「未病」という言葉そのものは確かに、東洋医学から来ています。
しかしながら、現代西洋医学の世界でも、今まさに問題とされているこれらの病に至る状態こそは
まさに「未病」そのものであり、洋の東西を超えて今、その治療が求められているのです。
「未病」を病気に進みつつある状態と捉えるならば、はやい段階で「未病」のサインを認識し、
しかるべき手を打てばその進行を抑え、本格的な病気に移行することを防ぐことができます。
冒頭の中国最古の医学書に「未病を治す」という表現があらわれているのですが、未病は病気ではないのに
「治す」というのはどういうことなのでしょう。
これは、健康であろうと病気であろうと、つねに自らの生活習慣に気を配り、より本来の姿に
近い心身の状況にもっていこうとする,生き方の姿勢をあらわしている表現なのです。
この人間本来の姿を、東洋医学(漢方)の世界では「中庸」と呼んでいますが、これはすなわち
健康と病気のまん中あたりのことだそうです。つまり、健康すぎても、また病だらけでも、いけない。
からだの状態とは、どちらか一方向への偏りがないのが一番よいのだ、ということを意味しているのです。
未病への意識を高めることこそが、大切。
私たちのからだは本来的に、治癒力・自己回復力が備わっています。
ですから、それを活かす方向、もともとの生命力を十分に活かす方向にもっていくように意識して
それとなく導いてあげるようにするだけでも、その本来の力を発揮しはじめるようにできているのです。
私たちの日々の生活をちょっと振り返っただけでも、このからだがもともと持つ治癒力・自己回復力を
私たちはなんのかんのと都合のよい理屈をつけ、まったく逆の方向に導いていることが珍しくありません。
たとえば、肝機能の低下を示す数値がでているのに、仕事のつきあいだからと、毎晩の飲酒を止めようとしない。
睡眠不足で食欲もなく、過労を自覚していながらも、仕事が終わらないからと家族の心配も振りきって休日も会社に出かけてゆく。
このような、自らのもつ本来的な回復力を、知りながらあえて阻害する方向にもっていくようでは
「未病を治す」ことはいつまでたっても難しいままでしょう。
健康診断などで数値の異常が認められたなら、体調の悪化に自覚がなくとも、その数値改善に向けて、生活習慣を改めていく。
健康診断で数値に異常が認められなかったからといって、気を緩めてしまい、カラダに無理をかける生活を続けたり
喫煙や過度の飲酒にも「少しぐらいいいか」などと、自分自身を甘やかしたりしない。
これからの時代「未病」に対する意識を高めることこそ、「生活習慣病を予防するための最短距離」であると言えるかもしれませんね。
あいらんだ〜での施術は、病院での先生のような「治す」と言う治療とは言えませんが、マッサージやリフレクソロジーを
受けることにより、身体にある「自然治癒力」を高めるための お手伝いは、出来ると思います。

ひとくちメモ 2
ひとくちメモ 2