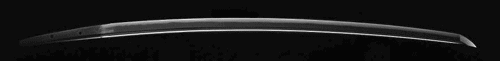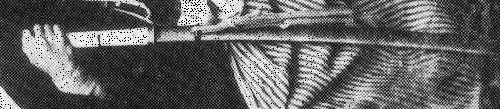
坂本龍馬は複数の刀を使ったと推定される。
一振りは文久二年に脱藩する以前に使っていた刀、脱藩直前に兄権平に取り上げられたという話があるがあくまで伝説。(龍馬百話 p77)
一説に脱藩時、河原塚茂太郎に肥前国忠広二尺六寸を与えたという、坂本権平所蔵之刀を新たに手に入れたので与えたのだろうか。後年、武市半平太にわたり、人斬り 岡田以蔵がこの肥前国忠広を暗殺に使ったという。(刀匠肥前国忠広は肥前忠吉一門、代々襲名前の忠吉の称。初代二代と七代が有名だが人にやる位なので幕末の新新刀では?
「坂本龍馬と刀剣」の小美濃清明氏は二代と推定しておいでる。)
二振りは脱藩時に持ち出した、兄 坂本権平所蔵之刀。
この刀を渡したために、姉お栄は自刃したという有名な伝説があるが、お栄の墓碑が発見され脱藩時すでに没していた事が判明した。(龍馬百話 p77)
戦前に山内家家史編纂所に勤めていた平尾道雄氏によると福岡家に紛失届が出されている。
「三月二十七日御預郷士坂本権平所蔵之刀紛失之旨届出候事」出典の福岡家御用日記は昭和20年5月東京の空襲で焼失し現存しない。(龍馬のすべて 平尾道雄)
これが肥前国忠広だという説も広く唱えられている。小美濃清明氏も坂本権平所蔵の刀は忠広だと書いておられる。
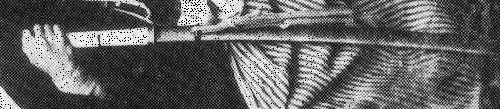


(1)
(3)
(4)
拳の大きさが同じくらいに写真の大きさを調節したが、刀の長さは正確には比較できない。少なくとも拵えは全部別と思われる。
(1)白柄、皮を被せてあるようだ。柄まで緩やかな弯刀。
(3)ごく普通の白皮に黒糸の柄、柄も強く反る弯刀
(4)白柄、白皮に白糸、直刀
丸亀の龍馬?27歳
長崎の龍馬座像33歳
福井?(京、長崎)の床几にすわる龍馬33歳
手の形は頑丈で(1)(4)どちらも第3指と第5指のMP関節が隆起して目立っており、第4指MP関節から手背にかけては不自然に陥凹している。この部分の中手骨に古い骨折があると推定される。知られざる古傷跡だろう。まさに剣士の手だ。
(4)は寺田屋での左手第1指、第2指の傷をかばうようにゆったり置かれている。右手母指球は大きな傷跡があるためにボリュームが減っているようだ。
(1)丸亀の龍馬の刀は、脱藩直前に使っていた刀に相当。緩やかな反りが現存の肥前忠吉一門に一致する。
(3)は弯刀で切っ先と柄とが反っている事が分かる。鈴木(源)正雄作二尺八寸二分の長刀や左行秀の直刀でない事は確か。太刀に近い形状から備前兼光無銘刀か。兼光が本物ならすごい道具持ちの龍馬て事になる。よく売られている龍馬の刀の模造品はこの長崎での写真の刀を模して銘は陸奥守吉行としているが、地下の龍馬が聞いたらさぞ呆れるだろう。
(4)はタバコ盆に隠れて先は見えないし斜めアングルだが、直刀に近いようだ。現存する龍馬の吉行に柄:中心の刀身に対する角度が似ているし暗殺直前の慶応3年秋という時期から、陸奥守吉行と考えるのが自然。
丸亀の龍馬?の刀は脱藩前に龍馬もしくは兄権平が持っていたと思われる肥前国忠廣の特徴と一致。


銘 吉行 坂本龍馬の最後の愛刀(現 京都国立博物館蔵、焼損前)
近藤長次郎(上杉宗次郎)


福井?(京、長崎)の床几にすわる龍馬33歳
丸亀の龍馬?27歳
(4)
◎
右手背にある傷跡の一致から同一人物の可能性が強い。

その刀は直刀で左行秀(新新刀)だろうと言われている。
肥前国住近江大掾藤原忠廣(二代、新刀期)
備前長船兼光 (倉敷刀剣美術館 蔵)
(参)
(参)
解説
![]()
ここまでは丸亀龍馬写真肯定でしたが、実は疑惑の新史料があったのです
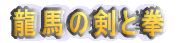
法医学者や科警研のまねして疲れ気味の管理人 湖海苔屋
(本職の方々がいたら笑って読んで下さい、私説にすぎません。)
三振り目は備前兼光無銘刀(古刀)、「坂本龍馬手帳摘要」に「備前兼元無銘刀研代」と記載されているらしい。
四振りは慶応三年に兄権平が土佐に来た西郷吉之助に託して弟に贈ったとされる陸奥守吉行作の刀二尺二寸(新刀)。龍馬の愛刀とされ近江屋で遭難したとき敵刃を鞘ごと受けた。新刀とはいえ当時すでに200年近い刀で坂本家の家宝とするに足る。没後甥の坂本直寛(高松海南男)氏に伝わったが釧路の大火で焼け、京都国立博物館に焼残の刀身が残る。陸奥宗光と交わした最後の書簡に「長脇ざし」と表現しているのはこれ。(龍馬百話 p274) 龍馬の所持刀の中では短めなので「長脇ざし」なのだろう。
この他にも多くの刀が龍馬旧蔵と伝えられている.。伝承が本当ならば人に次々与えているらしい。例えば源正雄作二尺八寸二分の長刀(新新刀)、吉行を受け取ったときに西郷の下僕に与えたという。事実ならパフォーマンス用のダミーだろう。左行秀二尺七寸も持っていたそうで胄と交換したそうだ。なかには龍馬の名にあやかった偽物もあると推定される。
→
→
↓
↓