

第六話 観光散歩
=八月十三日= はこだてサタデー
「あっ、お兄ちゃん! おはよー」
寝ぼけ眼で陽平が台所に顔を出すと、亜美の元気な挨拶が出迎えてくれ、その手元には可愛らしいお弁当箱が置かれそれを花柄の巾着袋にしまいこむ所だった。
「おはよー、亜美ちゃん今日も元気だね?」
陽平は、挨拶とともに笑顔を浮かべる。
「うん、いつだって元気だよ」
亜美はお弁当の入った巾着袋を持つ手とは反対の手を元気にあげながら陽平に答える。
「陽平さんおはよ、寒くなかった?」
雪音が小さなご飯茶碗にご飯を盛り、亜美にそれを手渡すと湯気をたたえているおなべの中をおたまでかき回す。その朝食は当たり前のようなものだが、陽平にとって見れば懐かしく、そして家族を象徴するものだった。
「うん、大丈夫」
寝る前に雪音が毛布を持ってきてくれたおかげで、寒い思いをしないですんだ。
「本当に、北海道って言うのは涼しいんだね? 東京では、いつもパンツ一丁で寝ていたのに、そんな格好で寝ていたら風邪をひいてしまうね」
苦笑いを浮かべながら二人を見るが、二人ともちょっと頬を赤らめている。
「お兄ちゃんはそんな格好でいつも寝ているの?」
亜美が、呆れた表情で陽平を見る。
「うん、東京では夜中でも二十五度なんて当たり前だし、クーラーのタイマーが切れるとすぐに目が覚めてしまうよ」
まるで、お湯に使ったまま横になっているような感覚というのか、体中に湿気がまとわりつくと言うか、目が覚めるとお漏らしをしてしまったのではないかと思うぐらいに、パジャマが湿っているのが常だな。
「東京は、そんなに暑いの?」
雪音はコーヒーを入れ、陽平の手元に置きながら顔を覗き込んでくる。
「暑いよ、一昨年なんかは最低気温三十度なんていう日もあったぐらいだし、去年だって涼しいと言っても最低気温が二十度を下回る事はなかったなぁ」
一昨年は、まるで我慢大会というかオリンピックにかこつけて、新記録ラッシュだった事を覚えているし、去年だっていくらかマシだといっても三十五度以上あった日が何日あったか数えきれないぐらいだ。
「最低気温が三十度なんていったら、きっと私溶けちゃうかも……」
雪音はうんざり顔をして陽平の顔を見つめてくる、その表情は明らかに同情した顔だった。
「函館の最高気温が三十度まで上がるとニュースになっちゃうよね? 最近増えてきたってお母さんが前に言っていたけれど……」
確かに、こっちに来てから三十度という気温をあまり聞かないなぁ、二十八度程度でも、暑いとこっちの人は言っているぐらいだ。しかし、北海道でも気温が年々上がり始めていると言うし、やはり地球温暖化のせいなのか?
Ami でーと……。
「そんな暑い所に、お兄ちゃんよく住んでいられるね?」
あたしがそんな町に住んだら数日で脱水症状を起こしちゃうよ……でもお兄ちゃんは向こうの人だしそれにも慣れないといけないかな? って、あたしなに考えているんだろう……。
「はは、まぁその分、冬はこっちのほうが断然寒いでしょ? 札幌にある営業所の人間は冬に出張に来た時に暖かいなんていっていて驚いたよ、俺は寒くて仕方が無かったんだけれどね?」
陽平は、ニッコリと微笑みながら美味しそうにコーヒーを飲みながらいう。
まぁ、そうかもしれないかもしれないけれど、あたしはやっぱり暑い方が嫌だよぉ、寒いのは着たりすれば何とかなるけれど、暑いのは、脱ぐにも限度があって……って、いやだぁ。
「亜美、早くしないと、学校遅れるわよ」
亜美が頬を赤らめながら味噌汁をすすっていると、雪音が壁にかけてある時計をチラリと見あげて亜美に向かっていう。
「あっ、本当だ、じゃあいってきます!」
その時計は出かけなければいけない時間を指し示しており、少し後ろ髪を引かれる思いをしながらも亜美はカバンを持ちながら腰を上げる。
「うん、気をつけて行ってきな、亜美ちゃん」
あぁ、癒される。この台詞を聞くと今まで『何で夏休みにまで学校に行かなければ行けないのよ!』と、悪びれていた自分が恥ずかしく思うほどね?
「はぁ〜い、いってきまぁーす」
亜美が家を出ると、さわやかな風が吹き、タータンチェックのプリーツスカートを揺らす。
『整理券をお取り下さい……整理券をお取り下さい……この電車は、十字街経由函館どっく行きです』
市役所前の電停から函館市電に乗り込むいつもと同じ日常。でも、いつもとちょっと違う感じがするのは亜美の心の違いだろうか、それとも、カジュアルな服装の観光客が車内に多いせいなのか自分では良くわからない。
「亜美、おはよ〜」
普段の日と違ってあまり混雑をしていない市電の中で亜美は不意に声をかけられる。
「奈津美? おはよー」
亜美が振り向くと、そこにはボーイッシュなショートカットの女の子が立ち亜美に笑顔を振りまいている。
「亜美、昨日あの後『お兄ちゃん』とどうだったの?」
奈津美は、意地の悪い笑顔を亜美に向け、肘で亜美のわき腹を突っついてくる。
「べっ、別に何もないわよぉ……お店が忙しくって、それどころじゃなくって」
消え入るように否定する亜美の声は、電車の車内の音にかき消される。
「あん? なんだって?」
奈津美は、大げさに亜美の口に耳を近づける。
「もぉー、なんでもなかったの!」
「だったらさぁ、もう少し、あんたのほうから積極的に行ったほうが良いんじゃないの?」
奈津美は、まだ耳がツーンとしているのか耳をほじりながら亜美を見る。
「積極的にって?」
函館市電の末広町の電停から学校に向かう坂の途中、いつもなんていうことのないこの坂だが、なんとなく足取りが重いのは、きっと奈津美のせいであろう。
電車の中での奈津美の質問にシドロモドロになりながらも答えていた亜美であったが、電車を降りる頃には既に奈津美の中では陽平は亜美の憧れの人になっていた。
「たとえば『あん、疲れちゃったぁ』なんて、ホテルの前でしなを作るとか『急におなかが痛くなっちゃった』とか言って既成事実を作ってしまえば、まったくおっけいでしょ?」
「だ・か・ら、何で、あたしがお兄ちゃんと既成事実を作らなければいけないのよぉ」
亜美は呆れ顔を浮かべながらも顔を赤らめながら奈津美を見る。
「だぁって、既成事実を作っちゃえば、後々楽じゃない? 『あなたにあんなことやこんなことまでされて』って言って……」
一体どんな事なのよぉ?
「奈津美ぃ、別に、あたしはお兄ちゃんを困らせたいわけじゃないのよ? それになんでそんな事に発展しなければいけないの!」
亜美は、浮き上がりピクついている青筋を人差指でなだめるように押さえながら奈津美を睨みつけるが、奈津美はそんな事関係ないといったような笑顔を亜美に向けてくる。
「だって、あんた好きなんでしょ? お兄ちゃんの事が」
「!」
好き? お兄ちゃんのことが好き? あたしが? やっぱりそうなの? あたしはお兄ちゃんのことが好きなの?
言葉を失い、亜美は口をパクパクさせているが、奈津美はそんな亜美の顔を呆れたような表情を浮かべながら覗き込んでくる。
「なに? あなたひょっとして気がついていないの? あたしからみればあなたはあのお兄ちゃんに恋をしているのは間違いないわよ?」
気がついていた、でも、気がつかないフリをしていた。それがあたしの本音……だって、知り合って間もないし、あんなに歳が離れているし。
「でも……」
亜美は立ち止まりうつむくと、それに気が付いた奈津美は立ち止まり、再び亜美の隣に歩み寄って、その肩をポンと叩く。
「でもも、ストライキもないでしょ? 好きなものは好きなんだから、いくら年が離れていようが、知り合って間もないからとかなんて関係ない、自分の気持ちを押さえ込むぐらいなら、そんなの好きになったって言わないよ、好きになったら一直線!」
奈津美は、亜美に対してこぶしを握り締め、唾が飛ぶほど力説をする。
「奈津美……」
その言葉に亜美は顔を上げて奈津美の顔を見上げると、奈津美のその顔は優しく亜美の顔を見つめ右目を瞑る。
「ほらぁ、あんたはいつだって元気元気でしょ? あんたにそんな顔は似合わないよ、ほらぁ当って砕けろ!」
ポーンと奈津美が亜美の背中を押すと、亜美は身体のバランスを崩したように一二歩前につんのめりながら奈津美の顔を見るその顔には笑顔が戻っていた。
ヘヘ、元気元気かぁ……さんきゅ、奈津美。
「おはよーまひろ!」
亜美と奈津美は目の前を歩いている同じ制服を着たおさげ頭の女の子の背中をポンと叩き、元気に走ってゆく。
「おはよー、亜美、奈津美」
おさげ頭のまひろは一瞬驚いた顔をしていたものの、二人の仕業とわかった途端にその顔には笑顔が膨らんでゆく。
「デート?」
何で、あたしが合宿の打ち合わせに出なければいけないのかなぁ……部長だっているのに、あたしがやる事ないんじゃないの? 毎日そんな事を考えながら、だらだらと学校に来ていたが、今日に限っていえば奈津美とまひろに助言がもらえるといった利点が生まれた。
「そっ、どうせそのお兄ちゃんも観光でこっちに来ているんでしょ? だったら『地元の人間が行くスポットとか案内してあげる』とか言ってさ、デートしちゃえば?」
奈津美はウィンクしながら、亜美に言う。
「そうよぉ、ちょっと制服着てさ、スカートの丈をいつもより少し短くすれば男の人なんてイチコロじゃない?」
まひろはそう言いながらスカートを捲り上げる仕草を見せ、なんとなく周囲にいる男の人の視線がまひろの足に向いたように見える。
……まひろ、あんたたまに凄い事を言うわよね? ちょっとぽやぁとしているかと思ったけれど、意外に大胆だったりして……。
「でも、お兄ちゃんはそういうのが嫌だって言っていたよ……」
昨日の帰りにお兄ちゃんは、恥ずかしそうにちょっとあたしから離れて歩いていた。
「なんで? そんなのおかしいじゃないのよ! せっかく現役の女子高生が一緒に歩くって言ってあげているのに!」
奈津美が憤慨する。まるで頭から湯気を噴出さんかのように。
「うん『まるで援助交際しているおじさんみたいだから』って言っていた」
昨日お兄ちゃんは、そういって顔を赤らめた。もう少しすれているのかと思ったけれど、案外そういうことには真面目みたい。
「へぇー、いい人みたいだね?」
まひろが優しい顔をして亜美を見ると、亜美はほのかに頬を朱に染めながらコクリと頷く。
「……うんおそらく、いい人だと思う」
「亜美、がんばれ!」
奈津美が亜美に向かって親指を立てる。
「うん! がんばる!」
亜美も、それに答えるように親指をぐっと立てる。
「それよりどうするの? 明日から合宿でしょ?」
まひろがボソッと言うと、それまで浮かんでいた笑顔が亜美の顔から消えてゆく。
そうだ、それが今後の最大の課題であろう。
「大丈夫でしょ? 特にこれといったライバルはいないんでしょ?」
奈津美は、思案顔を浮かべている亜美の顔を覗き込む。
「うーん、いるような、いないような、ちょっと微妙かも」
亜美の脳裏にふっと雪音の顔が浮かび上がる。
「だったら大丈夫でしょ? 合宿から帰ってきたら『おにいちゃぁんただいまぁ〜』とか言って抱きついちゃえば?」
奈津美の提案に対して、既に陽平に抱きついた前歴のある亜美は、それは期待できる反応が返ってこないであろうという思いが先にたつ。
「それは無理でしょ?」
苦笑いのまま、亜美は二人を見る。
「そうなの? ずいぶんと淡白なのねぇ、もしかしたら、男の子の方が良いとか?」
まひろも亜美を見る。
「変な事言わないでよ! お兄ちゃんはノーマルよ!」
まひろぉ〜、頼むからお兄ちゃんを最近の女子高生の好きな『ボーイズラブ』物に勝手に当てはめないでよ、好きなのは知っているけれど。
亜美は、まひろにつかみかかる勢いで言う。
「正常な男性であれば、色気をこう使って……」
奈津美はそう言いながら、ただでさえ短いスカートを手繰り上げ、今にもパンツが見えそうな長さまで持ち上げる。
「あぁ〜! ちょ、ちょっと奈津美ちゃんパンツ見えちゃうよぉー」
亜美は、思わず手で奈津美の太ももを隠す。
奈津美ちゃんてば、たまにすごく大胆なのよねぇ。ほらぁ、周りの人がみんな見ているじゃないのよぉ。
「みんな見ているよ?」
まるで我が事のように顔を赤らめながら亜美が周囲に視線を配らせると、その視線と目の合った人――主に男性――は慌ててその視線を外す。
「あら? あたしでも魅力あるのかしら? どぉもぉー」
奈津美はそんな事お構いないように、見ている通行人に対して手をあげながら愛敬を振りまき、その様子に亜美は脱力したようなため息を吐く。
「ただいまぁ」
お店のドアを開けると、昨日とは打って変わってお客さんの姿はない。同時にお姉ちゃんの姿も、お兄ちゃんの姿も見えない。もしかしてあたしがいない事をいいことに、なんかやっていたりしないでしょうね!
亜美のたくましい想像力が、未成年者が思い描いてはいけないような光景をその脳裏に映し出していると、部屋の奥から、雪音のくごもった声がする。
「陽平さんって、上手なのね?」
その声はどことなく熱を帯びたようなそんな感じがするのは、亜美のそのたくましい想像力にせいなのだろうか?
「あっ、だめだよ、そんなにしたら、出ちゃう……」
陽平の声もする。
「お姉ちゃん!」
自分でも驚くほど大きな声が出た。リビングに続く引き戸を、割れんばかりの力で開く。
「あら? 亜美、お帰り〜」
台所から雪音がのほほんとした笑顔で顔を出す。
「えっ?」
亜美は意表をつかれた様な表情で雪音を見る。
じゃっ、じゃぁさっきの思わせぶりな台詞はいったいなん何なの?
「おっ、グットタイミング、亜美ちゃん」
同じ台所からお兄ちゃんも顔を出す、って、何で二人してエプロンなんてしているの?
「何?どうしたの?」
漫画とかなら、亜美の頭の上には大きなクエスチョンマークが浮かんでいるであろう。
「陽平さんがね、お昼作ってくれるって、ほら亜美も早く着替えて、手伝って」
雪音に背中を押されるように自分の部屋に戻る。
「そう、そこでクルっと巻くと……あぁ、中身が出ちゃうよ……そうじゃなくって、こうロットを巻くときみたいにこうやって……」
着替え終わって台所に向かうと、陽平先生の料理講座が再開されていた。
「ほぇー陽平さん上手ね、いつでもお嫁にいけそう」
台所で雪音は、感心した表情で、陽平を見上げる。
「どれどれ? なにこれ?」
亜美が、二人の間に割り込むように首を突っ込み、皿の上におかれている春巻き状のものを見る。
「うん、陽平さんの得意料理の一つで『春巻きウィンナー』って言うんだって」
よく見ると、調理途中のウィンナーと春巻きの皮、それにピザソースと、ピザ用チーズが所狭しと置かれている。
「お兄ちゃん料理なんてするの?」
亜美は陽平の顔を見上げる。
「ヘヘ、一人暮らしが長いからね、結構ストレス発散で作ったりするよ」
ストレス発散に料理を作るって一体……それにしてもさっきから見ていると手馴れているというか要領が良いと言うか、けして広くないこの台所で、よくそこまで作れるものね。
陽平の手元からは、春巻きウィンナーがどんどんと作成されてゆく。
「はぁ美味しかった、さてと、お片付けしなきゃ」
そういい雪音は台所の消える、居間に残ったのは亜美と陽平の二人だけ。
「あのぉーお兄ちゃん、昨日の事なんだけれど、函館観光のこと」
いやだ、奈津美のせいで、へんな意識しちゃうじゃないのよぉ。
「うん、そうだね、お願いしちゃおうかな?」
陽平は、笑顔で亜美のことを見つめる。
「うん! そうと決まれば着替えてくるよ」
いやだなぁ、小学生や中学生みたいにデートではしゃいでいる自分が今ここにいる。
Youhei 函館にて……。
「雪音さん、ちょっと出てきます」
亜美が、自分の部屋に戻り着替えをしているころ、陽平は台所で片付けをしている雪音の背中に声をかける。
「はい、ってどこに行くの?」
雪音はその声に振り向き、陽平の顔を見る。
「さぁ、亜美ちゃんが色々案内してくれるって言っていたから」
「そう、亜美が……うん、いってらっしゃい、今日はお客さんも少ないだろうから、ゆっくりと観光してきてね」
雪音の表情がちょっと曇ったように見えたが、すぐに笑顔が戻ってきた。
「函館は市街でも見所がいっぱいあるから、それに、亜美にまかせておけば、美味しいお店なんかも紹介してくれるかもよ」
再び雪音は台所に体を向け、片付けを再開する。
「お兄ちゃんお待たせ! さっ、行こう」
なんとなく、雪音に声をかけようとした時亜美が着替えを終え陽平の元にやってくる。
「あっ、うん……」
「お姉ちゃん行ってきます!」
元気に雪音に声をかける亜美に対して、見送る雪音の表情はどこか引きつったような笑顔が浮かんでいる。
「さてと、どこに行こうかな?」
亜美は、ピンクのTシャツにデニム地のスカートとまさに夏といった格好をしている。
「お任せにするよ」
陽平は、空を見上げながら答える。空には白い雲が浮かび、その中をまるで泳ぐかのようにかもめであろう、鳥が飛び去ってゆく。頬をなぜる風は気持ちよく、強い日差しを除けば夏であるということを忘れてしまいそうだ。
「うーん、そうしたら、定番でベイエリアかな?」
そういい、亜美は、陽平の腕に手を絡める。
「はいはい」
陽平は、まるで引きずられる様にして、亜美について歩く。
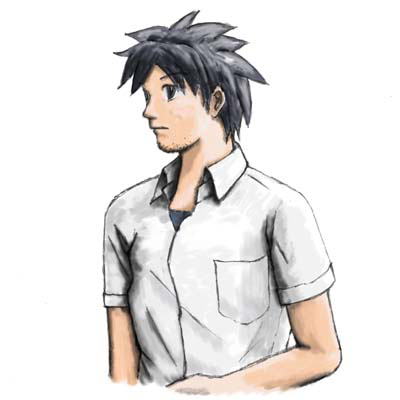
「ここが『はこだて明治館』昔の郵便局を改造してお店が入っているの、中にはガラスの工芸館があったり、オルゴールがあったりして、ちょっとレトロチックな雰囲気よね」
亜美が最初に案内してくれたのは、赤レンガに緑の蔦が絡んで見るからに歴史のありそうな建物だ。建物の前には観光バスがずらりと並び、函館の観光スッポトである事を象徴している。入り口にはレトロを象徴するような丸型の郵便ポストがあり、それがまだ現役で活躍をしているというからちょっと驚きだ。
「綺麗でしょ?」
中に入り、目についたのはガラス製品を大量に置いてあるお店だ。
「ここ『函館硝子明治館』では、日用品のほかにも『サンドブラスト』っていう工房もあって自分の好きな柄をグラスに描けるんだって、お兄ちゃんやってみる?」
亜美は、周りの硝子の輝きを目に移したかのように瞳をきらきらさせながら陽平を見る。
「いや、俺はそういうのはちょっと……苦手」
絵心のない陽平は、すぐに却下する。
「そう、だったらあっちに行ってみよ」
亜美は、ずんずんと明治館の奥に進んでいく。
「こんな方に何があるの?」
まるで裏口のようなところから明治館を出ると路地のようになっていて、そこの両壁も赤レンガだ。しかも、作られたようなものではなく本当に昔からそこにあるといった風合いのあるものだな。
「ほら、ここ」
路地を抜けると広場になっており、ふわっと潮の香りがする。
「へぇ、ここは」
歩き出すと、広場に運河の突端があるに気がつく。
「ここは、この倉庫に船からの荷物を運ぶ為に作られた『掘割』って言うの、そしてそれにかかる橋が『七財橋』初めてお兄ちゃんと来た時に通ったよね」

決して綺麗とは言えないその掘割の先に、小さな橋がかかっている。
端から見るとなんていう事の無い様に見える橋だけれど、そこから見る景色は……。
「そうしてここがベイエリアの中心『金森赤レンガ倉庫郡』ね、よく函館のコマーシャルとかだと、必ずこの景色が映るわね」
どんなガイドブックにも必ず今見ている景色が写っている。まさにここから見る景色は、函館を象徴する景色なのであろう。
「ここは、五棟の倉庫からなっていて、ホールがあったり、飲食店があったりお土産や、アクセサリーとかを売っているお店があったりして、結構地元の人間も来るところ、ちなみに私も好きな場所のひとつ」
亜美はにっこりと微笑み、倉庫の中を案内してくれる。
「次は……あそこに行ってみようかな……」
亜美は思案顔になりながらもひとつの答えをはじき出したように進路を決める。
Yukine 美容室「ひなた」
「はぁ……」
意味もなくため息が出てしまう。こうも暇だと、お店を閉めて、あの二人とどこかに行けばよかったかしら、でも、その暇が確定したのはついさっきだもんね。
『ラジオネーム、イカ最高さんからのお手紙です。笙子さん聞いてください、せっかくのお盆休みだって言うのに、彼ったら帰って来られないんですって! 東京に勤めていて、遠距離恋愛も既に三年になり、ちょっと隙間風が吹いているみたい』
BGM代わりにいつもつけているラジオから、女性DJが軽快に話をしている。
遠距離恋愛かぁ東京と函館。やっぱり離れているわよね。って何を考えているのかしら。
雪音は、一人で顔を赤らめる。
『イカ最高さん、遠距離恋愛はお互いを信じることが必要だと思います、そうね、いろいろ障害はあるけれど、迷わず、焦らず、諦めず、といったところかしらね、それではイカ最高さんからのリクエスト……』
ラジオからはバラード調の曲が流れてくる。
「迷わず……かぁ、なんだか変よね、あの人が来てから」
雪音はカット椅子に腰掛けると再びため息をつく。
カラン……。
お店のドアが開く気配がする。
「はい、いらっしゃいませ」
雪音はすぐに営業用スマイルになる。
「おやぁ? あまり流行っていないみたいだねぇ?」
店先には、中年の女性が立っており、店を見渡す。
「えっ?」
普通なら、いきなり入ってきてそんなことを言われれば腹が立つものなのだが、雪音はその中年女性を見るなり笑顔が膨らんでゆく。
「おかぁさん」
雪音は、思わずその中年女性に飛びつく。
「アハハ、子供じゃあるまいし、そんなに喜ばないでよ」
雪音の母、妙子は優しい目で雪音の事を見る。
「だって、何も連絡くれないんだもの」
雪音は、わざとらしく頬を膨らます。
「アハハ、ごめん、それにしても兄さんはどうしたの?」
大きな荷物を置きながら、妙子は、家に上がっていく。
「うん、さっき酔っ払って帰ってきて上で寝ている」
金曜日の夜から続いた、集まりと呼ばれる大宴会は今朝まで続き、そのままモーニング宴会に発展したらしく、帰ってきたのは約二十時間ぶりの午後一時になっていた。
「はは、兄さんたら相変わらずねぇ……それで、亜美は?」
妙子は、冷蔵庫から冷えた麦茶を取り出し、コップに注ぎ、一気に飲み干す。
「うん、ちょっと知り合いとお出かけ……」
そのとき、雪音の顔が曇ったのを母親である妙子は見逃さなかった。
「ふーん、亜美の彼氏かねぇ?」
妙子は、意地の悪い顔で雪音に言う。
「ちっ、違う、東京から観光に来た人で、三十歳でおじさんだけれど優しい人で、でもおじさんじゃなくって、それで、それで……ってなにを言っているのかしら私」
慌てたように言う雪音の頬は見る見るうちに赤らみ、それを隠すように両手で覆うが、その赤みは既に妙子に確認されたようだ。
本当に何を言っているのかしら、わたしったら、別にあの人と亜美が一緒に出かけていたって別になんでもないじゃない。
「アハハ、そうかい、ふーん、あんたがね、うん、ちょっと安心したよ」
妙子はニヤついた意味深な表情で雪音を見る。
「何よ」
雪音は膨れっ面で妙子を見るが妙子はその視線など気にもせずにしらを切る。
「しかしこの街はいいわね、いつ来ても落ち着ける」
妙子は大きく伸びをすると、その場にゴロンと横になる。
「そういえば、お父さんは?」
雪音は、脱ぎ散らかした靴をそろえながら妙子の方を見る。
「仕事だって、ロスで」
妙子の旦那、雪音の父親は妙子と同じくブロードウェイでヘアーアーチストをやっているが、同様にアメリカで、美容室を展開している。
「あっちも忙しいの?」
次に雪音が片付けに入ったのは、置き去りになっているトランクケースだった、どうせ、洗濯物とかしか入っていないだろうそのBOXは重く、雪音の表情もちょっとゆがむ。
「あぁ、忙しいというか、色々やることがあってね……まぁ、日本と違って、実力主義っていうのには感謝しているよ、おかげで、やりたいことができるからね」
妙子は、横になった体を上半身だけ起こす。いわゆる腹筋をしているのと同じ格好だ。
「お母さん、相変わらずすごいね、鍛えているの?」
その仕草を見た雪音は驚嘆の声を上げる。
確か、もう五十になるはずなのにすごいわね、あたしなんて足を押さえてもらわないとできないと思う。
「体力がないとやっていけないからね? それに比べて、あんたのお店は暇そうだねぇ」
妙子は皮肉っぽい顔をして雪音を見る。
「大きなお世話よ、昨日なんて忙しくって、お昼抜いちゃったぐらいなんだから、今日はたまたま、予約のお客さんがキャンセルになっちゃったからなの!」
本当よ、こんなにお客さんが来ないのなんて久しぶり、だと思ったな……コホン、とにかく大きなお世話なの!
「はいはい、それじゃあ腕がなまってしまうでしょ、どれ、わたしが、あなたの技術を見てあげよう」
そういうと妙子は、お店にかけてあった、刈布を自らに巻く。
「えっ、ウィッグじゃなくって、お母さんをわたしがカットするの?」
雪音は驚いた表情で妙子を見る。妙子は当たり前といった顔でお店に向かう。
「当たり前じゃない、ウィッグでやっているのを見たって役に立たないわよ、ほら、早くして、お客を待たせるつもり?」
お母さんたら。
「あんた、シャンプーをなめちゃいけないわよ? 違うの、こう指の腹で頭皮をマッサージするように、そんなのじゃぁワックスつけているお客さんの髪の毛から油分を取り除くことができないわよ!」
妙子の言うことは、母親というよりもブロードウェイ仕込みの講師の先生のようだった。
「カットするときは、こう毛先を見て、髪の流れを読んで自然に……あんたカットに技術はあるけれど、ワインディング(ロット巻き)が苦手でしょ」
ギク! よくお分かりで、こういう街ではデザインパーマをかけるチャンスがないから。
「ほら、ブローするときは、ナチュラルに、髪の流れに沿うように流す」
鏡越しに見える妙子の顔は、鬼のような形相だ。
「……三十点」
刈布を取りながら、ため息交じりに妙子は力なく首を振りながら雪音に言う。雪音は、がっくりと肩を落としている。
「はぁ、やっぱり東京かどこかの美容室を紹介しようか? あんた素質はいいのだから、腕を磨けばあっちでもやっていけると思うよ」
妙子の表情がそれまでの先生のような表情から母親の優しいそれに戻る。
「それは、いや! わたしはここでこの『ひなた』をやっていくの」
雪音は、真っ向から妙子の顔を見つめると、妙子は諦めたような表情になり、小さなため息をつきながら次に顔を上げるると再び先生のようは厳しい顔に変わっている。
「じゃぁ、特訓だ、ウィッグ出しな、まずワインディングからだ」
それから「ひなた」の中で阿鼻叫喚の声がしたと近所の人が言っていたのは後日談。
Youhei それぞれの想い
「ここは?」
亜美とともに海沿いのバス停でバスを降り国道を横断する。そこには海沿いに小さな公園があり、結構な車が止まっている。
「ここは『啄木小公園』、その昔、石川啄木がこの大森浜と砂山を愛してやまなかったことから、この公園が作られたの、そしてあそこにあるのがその啄木の像」
函館山をバックに石川啄木の像があり、そこにはさまざまな観光客がそれを背景にカメラのシャッターを切っている。

「石川啄木が函館にいたのは十九歳のときで僅かに百三十二日間だけ、でも、その期間で函館に魅せられて、最後は『函館で死にたい』とまで言ったそうよ。ちなみに像に書いてある詩は『潮かをる、北の浜辺の砂山の、かの浜薔薇よ今年も咲けるや』これは、東京に戻った啄木が、この大森浜を思い浮かべながら読んだ詩といわれているの。結局啄木は、若干二十七歳という年齢でこの世を去ってしまったのだけれど、啄木が自分にとって最良であった時期だったといっていたのは、この函館にいた百三十二日間だといわれている。僅かな期間だけれど、それほどにまでこの街を愛したのね」
亜美は、写真を撮る人たちの邪魔にならないように、横に避けながら解説する。
僅かな期間だけれど、この街を愛するかぁ。
「どうしたの、お兄ちゃん?」
陽平は自分でも気が付かないうちにその歌碑をじっと眺めていたが亜美の声で我に返る。
「あぁ、いや、亜美ちゃん詳しいなぁって」
陽平は、ちょっと照れたように亜美に言う
「本当は、何回か来て一生懸命に覚えたんだ、いつでも案内できるように、ってね」
亜美はそういうと、浜辺に降りてゆく。
「おいおい」
陽平は、亜美の後をやれやれといった体でついてゆく。
「ほら、ここから見る函館山や海、あたし大好きなの。こんもりとそびえる函館山、海に張り出す立待岬、海原を見て振り向くと、湯の川。夜になると、漁火が輝いてとっても綺麗なの、いつか……」
亜美の言った言葉の最後の方が波音でよく聞き取れなかったが、亜美はちょっと顔を赤らめ、その海原を眺めている。
「さてと、そろそろ戻ろ? お姉ちゃんも待っているだろうし」
亜美は、赤い顔のまま陽平にそういい、再び国道に戻る。
「ただいまー」
玄関先に亜美の元気な声が響き渡る。その玄関先には、なにやら大きなトランクケースが一つ置いてある。
「おかえりー」
部屋の奥からは、北沢や雪音の楽しそうな笑い声とともに、今まで聞いたことのない声が混ざっているのに陽平は気が付いた。
誰かお客さんかな? よく見れば、玄関先には、姉妹のものとは違うパンプスが置いてあるし、明らかに海外旅行用とわかるこの大きなトランク、……ん? トランクに名前が書いてあるけれど……Taeko Kって、もしかしたら北沢妙子?
陽平の顔色が変わり、その横の亜美の顔の笑顔に変わる。
「お母さん?」
亜美は、靴を脱ぎ散らしながら、部屋の中に飛び込んでゆくと、その中心にいた中年女性に抱きつく。
「お帰り亜美、デートだったんだって?」
妙子は、亜美を抱きしめ、意地悪そうな顔で見つめる。
「デッ、デートだなんて……観光案内しただけで、そんな……」
亜美は妙子から離れると恥ずかしそうな顔で陽平を見る。その視線をたどるように妙子が陽平の事を見ると、不思議そうな笑顔を浮かべる。
本物の北沢妙子だ、まいったなぁ……。
陽平は渋々といった感じで、その視線に向かってぺこりと会釈する。
「雪音、彼かい? 東京から来た人って言うのは?」
妙子は、視線を雪音に移す。
「うん、沢井陽平さん……そのぉ……お母さんも知っている『B‐ネット』の社員さんよ」
雪音の一言に妙子は素直に驚きの表情を浮かべて、雪音と陽平の顔を交互に見る。
「……沢井? あんたがネットの沢井君かい?」
妙子は、驚いた表情と笑顔をうまく使いこなしたような表情で陽平を見る。
「はい『B‐ネット』仕入部の沢井です、いつもお世話になっています」
陽平はそれまでの表情と変わってビジネス的な顔をしながらペコリと頭を下げると、その様子を雪音と亜美はきょとんとした表情をしながら見ている。
「お母さんとお兄ちゃんは知り合いなの?」
今度は亜美の視線が妙子と陽平の間を行ったりきたりしている。雪音も亜美の後ろで言葉無くうなずいている。
「アハハ、直接の知り合いじゃあないけれど、うちの商品企画の室長がよく話しているのを聞いているんだよ『ネットの沢井は一筋縄ではいかない、あの人を納得させるプレゼンを持っていかないと絶対採用してくれない』ってね」
妙子はそういいながら陽平に意地の悪いウィンクを投げつける。
「それにしても、沢井君が兄さんの元部下とはね、それに雪音たちとも……世の中広いようで狭いのね?」
食卓に座り、陽平と北沢、妙子が雪音の作ってきたサラダをつまみに飲みだす。陽平は、緊張した面持ちで妙子からのお酌を受けている。
「ワハハ、どうだ、俺の教えがいいから、こんな骨のあるやつになったんだぞ!」
北沢は既に赤ら顔をして妙子に自慢するように言うと、妙子の心得たようにさらっとその台詞を聞き流す。
「お母さんはどうしたの? こんな急に来て……」
亜美が、お変わりのビールを持ちながら陽平の隣に座る。
「ウフ、だって日本じゃお盆でしょ? お盆休みよ、たまにこうやってリフレッシュしないと体が持たないわよ……ほら、雪音もこっちに来て飲んだらどう? 後片付けは私がやるから」
妙子が立ち上がり、台所で料理をしている雪音に声をかける。
「亜美、早く寝なさいよ、明日から合宿なんでしょ?」
既に北沢は酔いつぶれ二階の自室で眠ってしまっている。居間に残っているのは、妙子と雪音、それに亜美と陽平の四人だ。妙子は楽しそうにテレビを見ており、亜美も眠そうな目を擦りながら一緒に起きている、そこに風呂から出てきた雪音が声をかけた。
「亜美ちゃん、明日から合宿なんだ? どこに行くの?」
陽平が亜美に声をかける。
「うん、大沼に二泊三日で……あーあ、お母さんが帰って来るのがわかっていたら、合宿になんて行かなかったのに」
亜美は残念そうな表情で妙子を見る。
「本当にそれだけなのかな?」
ニヤニヤしながら妙子は亜美を見る。亜美はその妙子を見て、顔を真っ赤にする。
「そうよ! もぉ、お母さんの意地悪!」
赤い顔をしながら亜美はうつむく。
「でも、亜美ちゃんって部活は何をやっているの?」
イメージ的にはテニスとかかな?
「エヘヘ、柔道」
えっ? 思わず絶句してしまった。
「亜美は、こう見えても有段者なのよ、女だてらにと思うんだけれどね」
雪音は苦笑いで陽平にビールを注ぐ。
「いいじゃない、オリンピック目指してがんばれ」
妙子のちょうどいい具合に酔ってきたのか赤ら顔で亜美にガッツポーズを作る。
「ハハ、オリンピック目指せねぇ……」
陽平はそのあどけない亜美が勇ましい事をやっているようには想像が出来なかった。