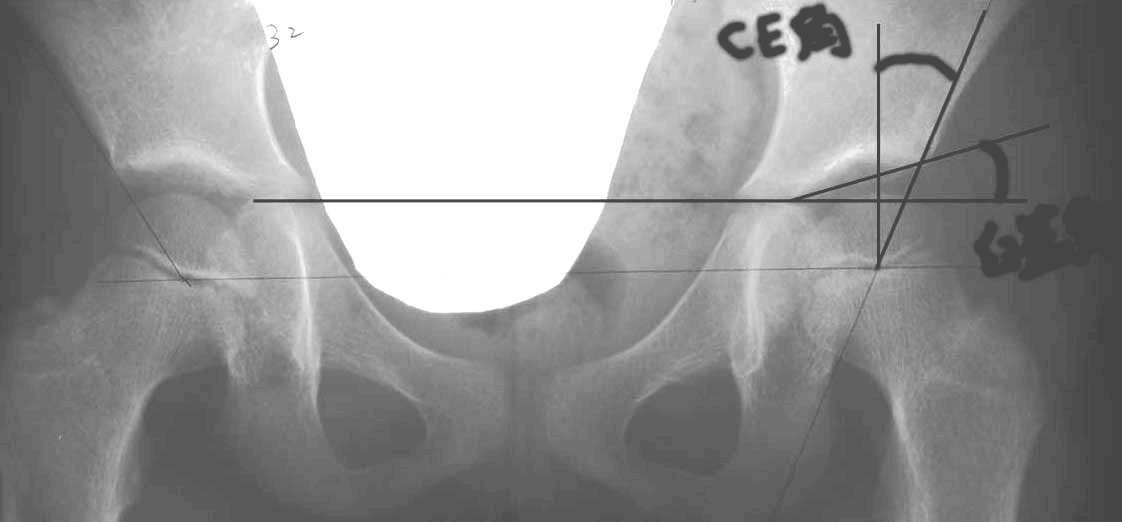
要約:乳児期にX線で臼蓋形成不全と診断された例では、超音波やMRIで詳しく調べると亜脱臼が伴っているのが普通である。大多数は軽度の亜脱臼(タイプAI)で治療を必要としないが、稀に治療を必要とするタイプAIIの亜脱臼の場合があるので注意が必要である。
ここでは乳児期に治療をするかどうかしばしば問題となる臼蓋形成不全の問題を考えて見ましょう。
臼蓋形成不全とは、股関節の臼蓋を構成する骨組織(特に腸骨)の発育が不十分で、骨頭を十分に覆うことが出来ない状態を言います。臼蓋形成不全の程度を表す場合、2通りの方法があります。一つはCE角であり、他の1つは臼蓋角です。CE角は主として5歳以上のお子さんの場合使用します。乳児であれば臼蓋角を用いるのが普通で、これが30度以上ある場合を臼蓋形成不全と定義しています。
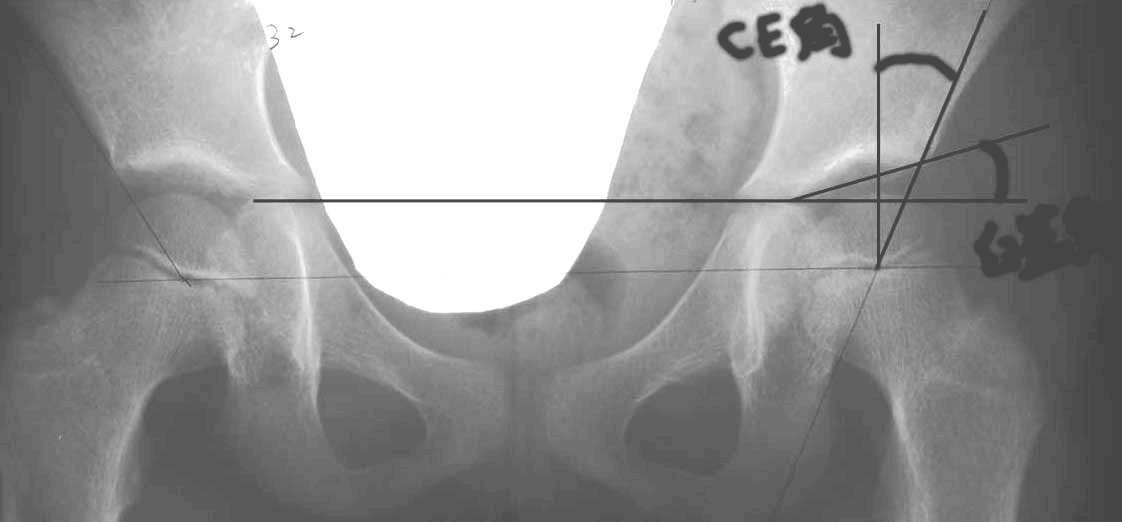
1。臼蓋形成不全の原因。
臼蓋形成不全の原因については長い間論争がありました。「臼蓋不全があるために脱臼が発生したのか?」、それとも「脱臼があるために臼蓋形成不全がおこったのか?」という意見の対立です。現在では多くの研究者が、脱臼があるために臼蓋形成不全がおこったと考えています。なぜかというと、脱臼は臼蓋形成不全を伴うことが多く(全部ではありませんが)、逆に脱臼が整復されると多くの場合臼蓋形成不全が改善する傾向があるからです。
たくさんの例の中には、脱臼・亜脱臼を伴わない臼蓋形成不全があるのも事実です。これらにおいて最初から脱臼・亜脱臼が無かったかどうかは不明です。
脱臼治療開始が遅れた場合には、臼蓋形成不全が残存するのが普通です。臼蓋は正しい整復位になければ形成されません。骨頭がはずれていた期間が長かったわけですから、臼蓋形成不全が著しいのはやむを得ません。もちろん場合によっては早期に治療が完了しても臼蓋の成長が思わしくない場合があります。このような場合は、先天的因子が関与しているものと推測されます。
2。臼蓋形成不全の三次元的病理。
乳児検診において股関節の開排(股関節を曲げかつ開くこと)制限を指摘され、整形外科においてX線撮影の結果、脱臼はしていないけれど臼蓋の発育が不十分である、と診断された場合にどのように対処するかということについて考えてみましょう。実際にこのようなケースはたくさんあると思われます。治療する側としては、治療すべきか否か迷うものと思います。
このような場合、わが国の整形外科学会では、X線写真において、臼蓋の発育が不十分であっても脱臼を認めない場合には、臨床所見(開排制限など)が改善してゆくならば特別の治療をしなくても最終的には臼蓋形成不全は治癒する、という意見が支配的です。私も基本的にはこの考え方に賛成ですが、超音波断層像や
MRI によって詳しく調べてみると、この問題はもっと複雑なことが解ってきました。
1990年代に至り、超音波断層像で脱臼が診断できるようになりました。開排制限などの臨床所見がある赤ちゃんに超音波診断(前方操作法)をおこなうと、「X線画像上、脱臼は無いけれど臼蓋形成不全を認める」という症例では、「ほとんどの場合さまざまな程度の亜脱臼を伴っている」、ということがわかったのです。X線診断で脱臼が判らないことがある、という理由は簡単です。X線診断は三次元のものを投影像によって判断するものですから、股関節伸展位で骨頭が前方に脱臼している場合には診断が困難となる場合があるのです。もちろん、骨頭が前方に転位しているばあいには、同時に外方にも移動しているわけですから通常はX線画像上何らかの異常所見がでてくるのですが、臼蓋が前方に強く回旋している(脱臼していると例外無くこの回旋は健側よりも強い)と投影像では診断不可能なことがある、ということが理解できると思います。すなわち、開排制限を有し、X線画像上「脱臼は無いけれど臼蓋形成不全を認める」という症例では、前方操作法による超音波診断を行うと「ほとんどの場合様々な程度の亜脱臼を伴っている」ということが明らかになったのです。これらの多くはタイプAIの軽度の亜脱臼なので、臨床所見(開排制限など)が改善してゆくならば特別の治療をしなくても最終的には臼蓋形成不全は治癒する、と考えてよいと思います。
たとえば、これは脱臼を伴わない純粋な左臼蓋形成不全と診断された例です(左股関節=向かって右側の股関節)。
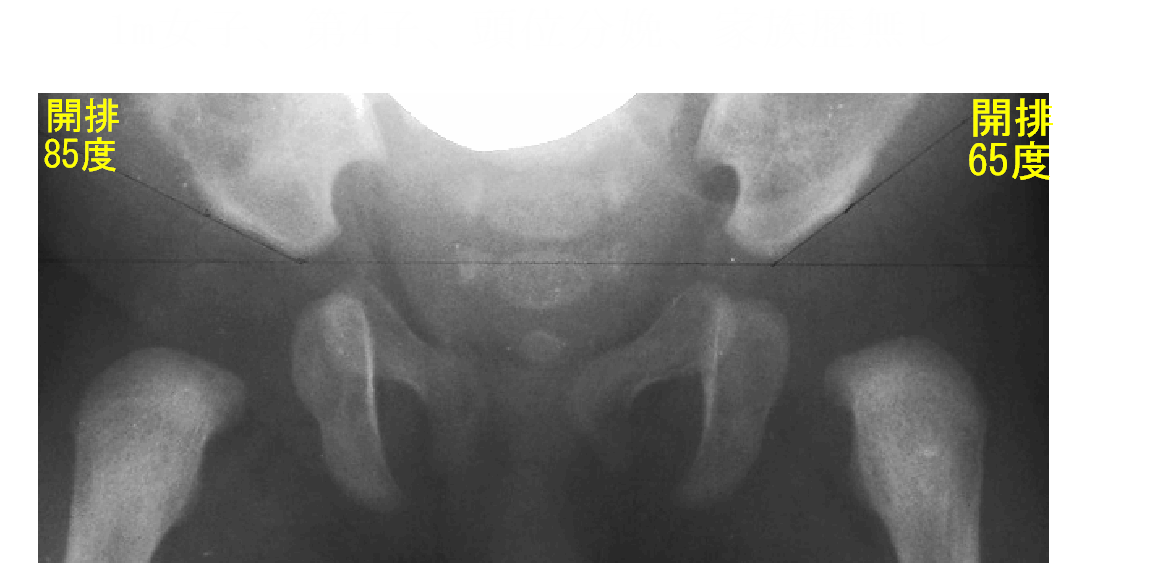
しかしながら、超音波でよく調べてみると、下図のように骨頭は臼蓋の外前方にずれているのがわかります。

この例では下図のように股関節を屈曲した時には骨頭と臼蓋の関係は良好(タイプAIの亜脱臼)でした。自然運動を妨げない注意だけで自然治癒しました。

しかしながら小児整形外科ではさまざまなことがおこります。かならずしも上にのべたように単純にゆかないことがあって、脱臼のない臼蓋形成不全が実は、タイプAIIの亜脱臼である場合が稀ではありますが、存在することも判ってきました。タイプAIIの亜脱臼である場合には股関節をどのように動かしても骨頭が正しい位置をとることが出来ないわけですので、骨頭を正しく臼蓋に向ける操作が必要となります。
たとえば、下図は脱臼を伴わない左(向かって右側の股関節)臼蓋形成不全と考えられた例です。ただし、専門家が見れば単純な臼蓋形成不全と即断はしません。X線上にも問題はあるからですが、ここでは省略します。
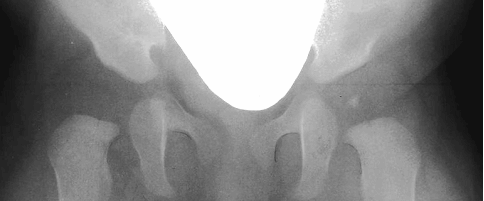
股関節伸展位での超音波所見はもちろん異常ですが、股関節を開いた時にも下図のように骨頭は臼蓋の下方にずれているのがわかります。このような例では自然治癒はむずかしく、実際にこの例はしばらく経過を見ましたが一向に改善しませんでした。結局は本格的治療が必要だった例です。
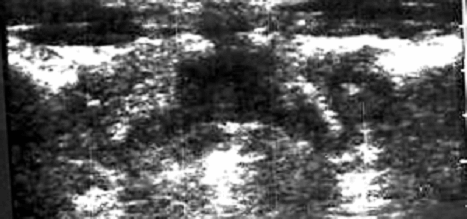
このようにほとんどの臼蓋形成不全は、くわしく調べてみれば軽度の亜脱臼をともなっているのが普通であり、ときとしてAIIのように治療を必要とする亜脱臼が存在することがわかってきました。タイプAIIの亜脱臼であれば、丁寧に赤ちゃんの視診・触診を行えば診断できると思います。また、数週間経過を観察しても一向に軽快しません。したがって、小児整形外科専門医であれば通常見落とすことはないと推測します。
脱臼を伴わない臼蓋形成不全というのは、少数例ですが確かに存在しています。この場合臼蓋形成不全は30〜35度くらいのものが多く、極端な形成不全というのは経験ありません。臼蓋の成長というのも身長と同じで個人差があるからと思われます。
3。臼蓋形成不全の治療について。
臼蓋形成不全について私の元の職場、滋賀県立小児保健医療センターで調査しました。1990年から1993年までにを受診したタイプAIで臨床所見の改善した42症例42関節(多くは臼蓋形成不全を伴う)を経過観察をおこないました。初診時に下肢取り扱いの注意、おしめの当て方、抱き方、ミルクの飲ませ方を指導した上で、これらの関節を超音波断層像とX線像によって1年以上追跡したところ、1才までに38関節は正常となり、他の4関節のうち3関節は3才までに正常となり、残りの1関節も4才までに正常となりました。すなわち、臼蓋形成不全があっても、タイプAI脱臼で臨床所見の改善傾向のある例では特別の治療を必要としないことがわかったのです。ただし、臼蓋形成不全の程度が著しい場合には改善するのにあまりにも長期間必要としましたので、1997年からはタイプAIのうち3ヵ月以上で臼蓋形成不全を伴う場合には治療をおこなうことにしています。一方、タイプIIではどうか?といいますと、初診時に下肢取り扱いの注意、おしめの当て方、抱き方、ミルクの飲ませ方を指導した上で、これらの関節を超音波断層像とX線像によって追跡したところ、自然治癒する場合は少ないことがわかりました。
これらの臨床研究の結果から、臼蓋形成不全に対して以下のような方針が良いと考えています。
(1)超音波断層像で骨頭が開排位において整復位(求心位あるいは向心位)にある場合(タイプ AI-II )。
タイプAI-IIで生後3ヶ月以上の乳児では入院の上リーメンビューゲルという装具を装着して治療します。入院後、リーメンビューゲルを装着し股関節を開いた状態での牽引をおこないます。股関節が70度まで開くようになったらリーメンビューゲル装着のまま退院します。入院期間は2泊3日です。
タイプAI-IIで生後3ヶ月未満の乳児の場合は、下肢取り扱いの指導のみで経過観察します。
軽度の脱臼であれば、赤ちゃんの育児環境を良好に保つことにより、自然治癒を促すことが可能です。赤ちゃんの下肢取り扱い方法とは、特別に難しいものではなく、その基本は赤ちゃんの下肢の動きを妨げないということです。下肢の動きをなるべく制限しないような薄いおむつ(紙でも布でもかまいません)、おむつカバーを股間に当て、赤ちゃんの下肢の自由な動きを妨げないことが基本です。したがって下肢の動きを制限するようなおしめカバーや衣服は使用しないことが重要です。しばしば見られる誤りは、股の間に厚いおしめを当てることによって下肢を無理やり開かせることです。股関節の開きを強制的に赤ちゃんに押し付けると後に、深刻な股関節変形が生じることがありますので注意してください。赤ちゃんを抱く場合は、抱く人と赤ちゃんとがお互いが向き合うようにするのが大切です。そうすれば赤ちゃんの下肢は自然な形をとり、ある程度自由な運動が可能になります。赤ちゃんを横にして抱くと、下肢の動きが制限されるので横抱きは避けるべきです。よく見られる誤りは、抱くときに、赤ちゃんの股に手を入れることです。このような抱き方をすると一方の下肢の運動が制限されますのでよくありません。赤ちゃんにミルクの飲ませる時も、赤ちゃんがお母さんの膝にまたがるようにします。
上のような対応によっても1-2ヶ月以上にわたって症状の改善が無い場合は3ヶ月以上の乳児と同じように入院の上リーメンビューゲルという装具を装着して治療します。
(2)超音波断層像で骨頭が開排位において臼蓋の中にあるが、整復位(求心位あるいは向心位)ではない場合(タイプAII)
まず牽引をおこなって上方に移動している大腿骨頭を引き下げます。その後リ-メンビューゲルというRBを装着して股関節を開いた状態での牽引をおこないます。開排位での牽引で股関節が開くようになったら重垂を少しずつ減らしてリ-メンビューゲル装着のまま退院します。入院期間は2-4週間です。