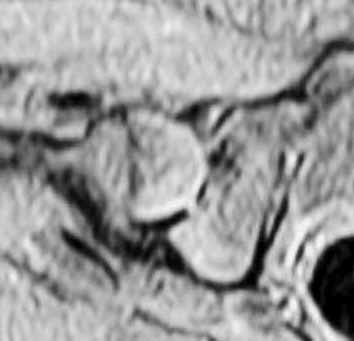
先天性股関節脱臼における
整復・固定終了後の問題
最近、他施設で脱臼の治療をおこない、ギブス固定などをはずしたときに「骨頭が臼蓋から少しずれている」、と説明を受けたご家族が来院されることがあります。すべての病的現象についてはその原因があるはずですので、それらについて解説します。
歩行開始以後の骨頭外偏化。
先天性股関節脱臼の整復(非手術的に、或いは手術的)に続いて固定(ギブス、装具など)或いはリーメンビューゲル装着が一定期間行われます。重度の脱臼であれば関節内介在物があるため整復が障害されるのが普通ですが、通常は股関節周囲筋の拘縮が除去され、骨頭が臼蓋の中心に向かって正しい位置にあれば、整復操作により中心化された骨頭は、患児自身の筋力によって臼蓋の奥にむかって沈みこんで骨頭と臼蓋との正しい適合性が得られます。
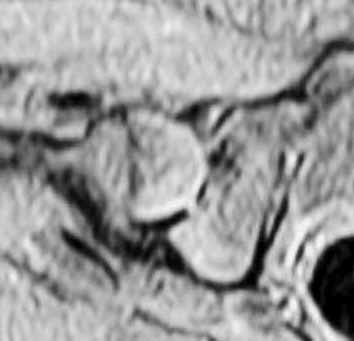
上の図は、筋拘縮が除去され、骨頭が臼蓋の中心に向かって正しい位置に整復された後、骨頭が患児自身の筋力によって関節内介在物を縮小させながら臼蓋の奥にむかって沈みこんでゆく様をあらわしています。
一定期間ギブス固定や装具により、股関節が正しい整復位を保ちかつ安定していればギブスや装具などは除去されます。赤ちゃんはやがて自分の力で下肢を自由に動かして関節の動きを改善し、筋力をつけていっそう股関節は安定してゆきます。健常児と比較すれば歩行開始が遅れます(これも個人差が大きい)が、やがてハイハイ(時にハイハイを省略することもある)を経てつかまり立ちから独立歩行へと発達してゆきます。独立歩行が始まればここで一度、立位でのX線診断を行います。わが国では成人と同じように子供の股関節を臥位で撮影する施設が多いのですが、この疾患においては独立歩行が可能になったならば立位でX線撮影するのが世界共通となっています。股関節が最大の機能を発揮している状態ではどうなっているか、を診断することが重要であって、臥位では荷重したときの骨頭の不安定性が判断できないからです。
歩行開始後の立位でのX線診断では、しばしば「骨頭の外偏化」が問題となります。これは脱臼の既往がある場合にしばしば起こる現象で、私の経験では、女子で、脱臼度が強かった場合に起こる場合があることがわかっています。股関節周囲の筋力が不十分なため、立位の状態では骨頭が臼蓋の中心からず外方にずれてしまうことが原因であると言われています。
幸い、これまでの経験では、骨頭外偏化はやがて自然に改善してゆきます。骨頭外偏化がある場合には、よく観察すると子供は股を開いた状態で歩行しています。これは、股を開くことで骨頭が外偏しないようにして歩行しているものと考えられます。このような状態が半年或いは1年も続くことがありますが、やがて筋力の増強、股関節の発育などによって歩行は安定し、これまでのところどんなに強い外偏化も自然に改善し、装具などを必要とした例は経験していません。
骨頭外偏化が、亜脱臼位で固定されたためにおこる骨頭亜脱臼と根本的に異なる点は、骨頭外偏化の場合には、股関節を開いたときに骨頭が正しい位置にもどる、という点です。骨頭は臼蓋と正しい位置関係にあり、一定期間その状態が維持されたわけですから、関節内介在物は無くなっているからです。
問題は、股関節を開くなどしていくら動かしても骨頭を正しい位置にもってくることができない場合です。これにはいくつかの原因が考えられます。
1.固定期間が短かった場合。
整復操作の後には、一定の固定期間が必要です。固定期間の間に骨頭は関節内介在物を退縮させながら臼蓋の底に向かって沈み込んで安定するわけですから、高度な脱臼の場合、固定期間が不十分であれば関節内介在物がまだ残存している可能性が高くなります。この場合、やがて関節の拘縮がおこってきますので、股関節の動きが制限され骨頭を正しい位置にもってくることは困難となります。
このような場合には、まず股関節の拘縮を除去してから再度整復し適切な期間の固定をおこないます。
3.股関節周囲筋の拘縮が残存している場合。
股関節周囲筋の拘縮が残存している状態で整復操作をおこなっても、骨頭には臼蓋からはずれようとする力が働きます。そうするとギブスなどで固定中に亜脱臼が起こってしまいます。亜脱臼の状態で固定を続ければ、関節内介在物は残存して硬くなってしまいます。このような場合、固定終了後のX線では骨頭は亜脱臼となります。これを防ぐためには整復操作の前に牽引などで拘縮を十分除去しておくか、場合によっては内転筋の解離などが必要となります。
4.関節内介在物が多いために骨頭の正しい位置を維持することができなかった場合。
関節内介在物があまりにも多くて骨頭不安定が著しければ、ギブスなどで骨頭の適切な整復位を維持することが大変難しくなります。骨頭は後方に転位しやすいのでそれを防ぐためにギブス固定する際にきめ細かい工夫が必要ですが、それには極めて高度な技術が要求されます。大腿骨頭が下方に落ちないようにギブスをうまく巻かなくてはなりませんし、その後も超音波断層像でたえず骨頭の位置を監視しなくてはなりません。もし亜脱臼に気がつかなくそのまま固定を続ければ、ギブス終了後に亜脱臼が持続します。したがって、もし亜脱臼が発生すればただちにギブスを巻きなおします。それでもうまくゆかなければ手術的整復も検討する必要があります。
5.手術的整復を受けた際に関節内介在物が十分除去できなかった場合。
手術的整復を行った場合には筋肉にも操作を加えるので、患児自身の力で骨頭の沈み込みはあまり期待することはできないと考えておかなくてはなりません。したがって、手術の際に関節内介在物は完全に除去しなければなりません。股関節の下方から進入した場合には上方の介在物が、前から進入したときは後方の介在物を取りきれないことがあります。手術的整復は保存的整復よりも簡単なのですが、関節内介在物を完全に除去するという点では妥協するわけにはいきません。また、手術的整復が必要な場合は、臼蓋形成不全が強いのが普通です。その場合には関節内介在物を完全に除去したとしても骨頭の不安定は続きますから骨盤骨切りなどの手術も同時におこなわなくてはなりません。もちろん同時に筋肉の拘縮や緩んだ関節包などの処置は必要です。こうした事柄が適切に行われないと手術後にギブスの中で亜脱臼どころか再脱臼が発生してしまうことがあります。手術後のギブス固定の状態で亜脱臼が発生すれば再び亜脱臼によってできた空隙に結合組織が増殖し整復を困難にします。脱臼、亜脱臼が発生した場合には、原因を確かめた上で、必要とあれば再度手術的整復を行なわなくてはなりません。
6.その他。
上に述べた以外にもいろいろな原因があると思います。
股関節を開くなどしていくら動かしても骨頭を正しい位置にもってくることができない場合の治療方針。
全身麻酔下に内転筋などの解離を行って正しい骨頭の位置を維持できるようなギブスを巻けば骨頭は臼蓋の奥に沈みこんでゆく可能性があります。実際何例かで成功しました。しかし、ギブスを除去してから何ヶ月も経ていれば保存的整復はむずかしくなります。関節を取り囲んでいる様々な組織が固くなっているからです。このときは思い切って手術的な整復をおこなうのが良いと考えます。手術的整復では、関節内介在物を完全に除去すると同時に骨頭の安定を得るためソルター手術なども必要となるでしょう。