私の考える茅葺き屋根保存方法
*白川郷や美山町のような特別なものだけでなく、もっと身近に残していきたいものです。
![]()
私の考える保存方法の目標とするところは、
一、格段に安くできる事。
二、かなり長持ちする事。
三、外観や性能は変えない事。
四、葺き方も変えない事。
![]()
対策として、屋根の肉厚方向表面寄りに、波板を、空気は通るが水は通らないように組み入れて、通気性と防水性を確保しました。
いつかは実際の屋根で試してみようと思うのですが、お金もかかりそうなので、まずは茅葺き屋根に詳しい方から意見を頂けたらと思います。
![]()
では説明にいきます。
1、茅が確保しきれない時には、大部分を稲ワラで代用してしまいます。上に防水層があるから大丈夫です。
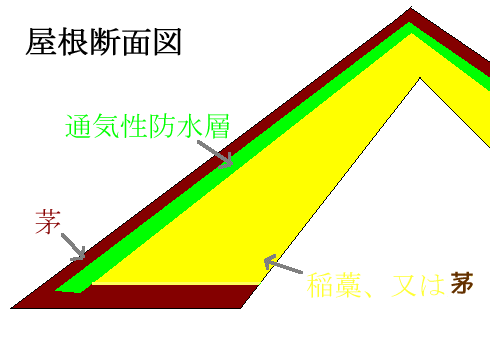
2、茅、もしくは稲ワラで葺き、屋根の厚みを確保します。なを、軒先にをいては、外観上の理由から、茅を使ったほうがよいでしょう。
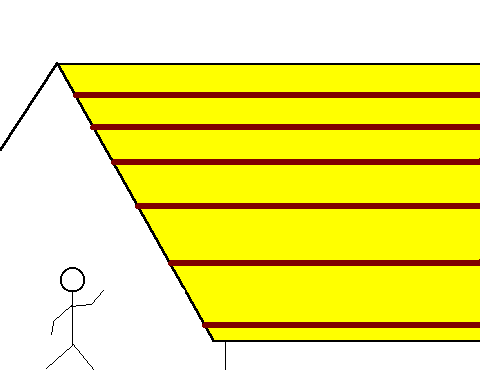
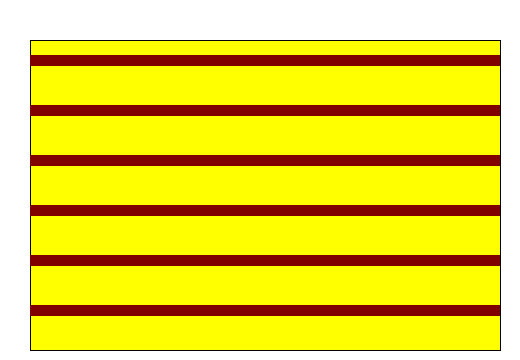
最後は、押え竹(第一押え竹)を表面に出した状態にします。
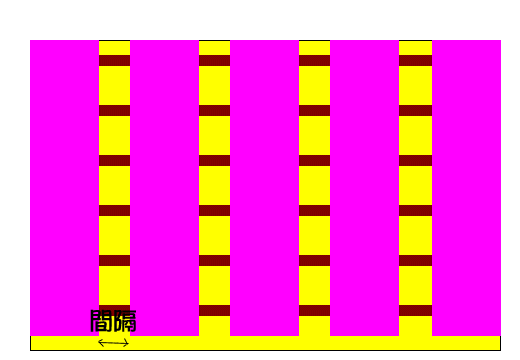
3、長めの波板(下側波板)を間隔を空けて設置します。
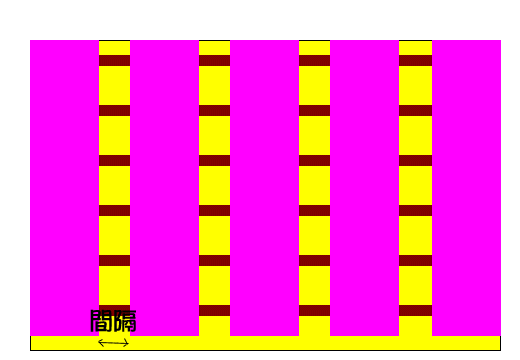
間隔は、波板の幅の3〜4割くらいでしょうか。
4、押え竹(第二押え竹)を押え竹(第一押え竹)の上に設置します。
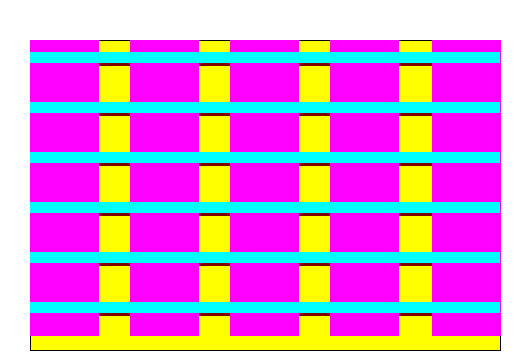
上の押え竹と下の押え竹を結びます。
波板(下側波板)は、押え竹と押え竹に挟まれています。
5、長めの波板(上側波板)を間隔を空けた所に設置します。
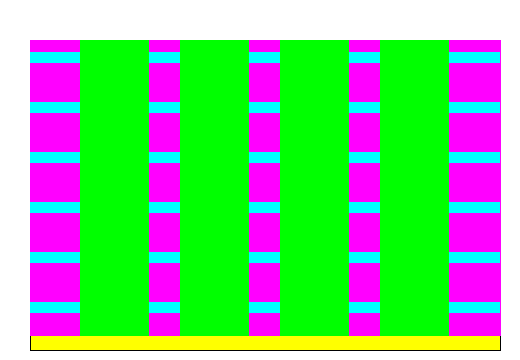
押え竹(第二押え竹)の太さの分だけ、下側波板と上側波板の間には“すきま”が空いています。
空気は上でも横でも動きますが、水は上からしか来ません。
6、押え竹(第三押え竹)を押え竹(第二押え竹)の上に設置します。
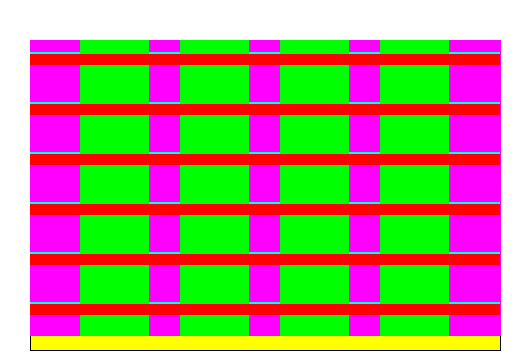
上の押え竹と下の押え竹を結びます。
波板(上側波板)は、押え竹と押え竹に挟まれています。
波板と波板の間に隙間が空いていますが、上から見れば重なっています。
7、押え竹を手がかりに従来の茅で葺いていきます。
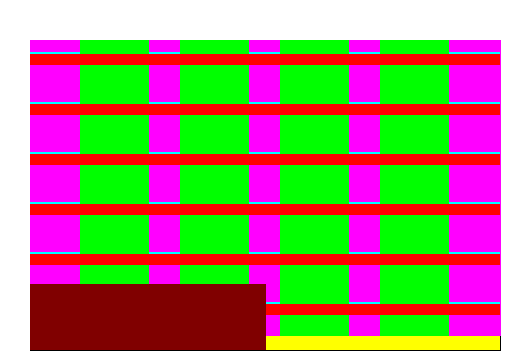
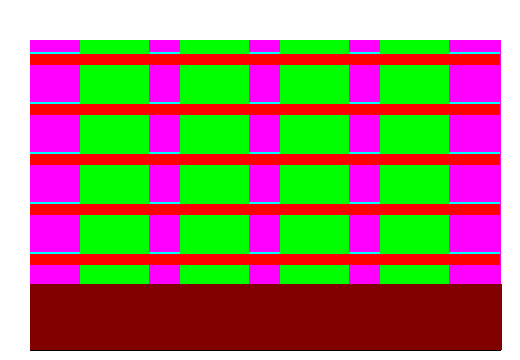
押え竹(第四押え竹)で挟むのは通常通り。
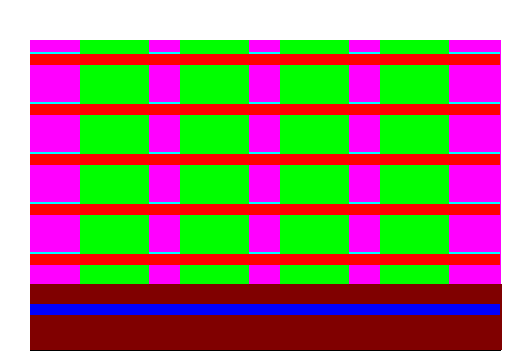
最終層に付き、押え竹は一段ずつ隠して葺いていきます。
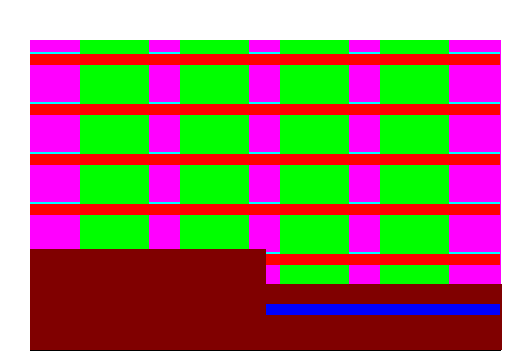
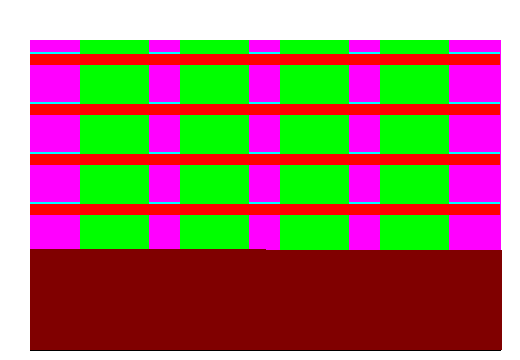
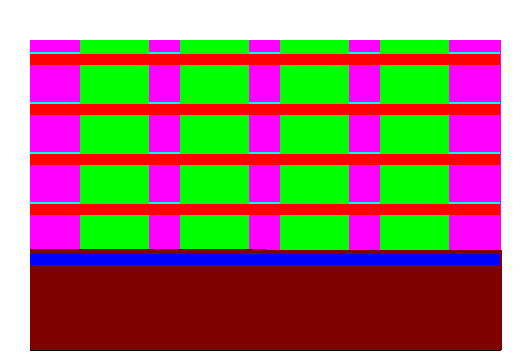
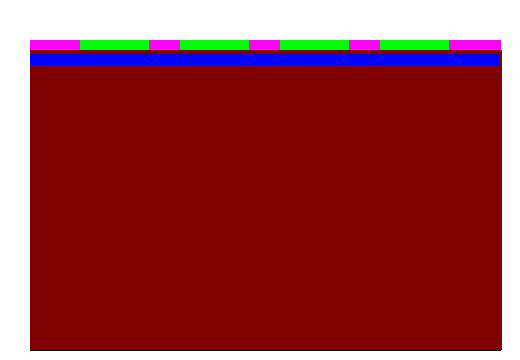
8、完成です。
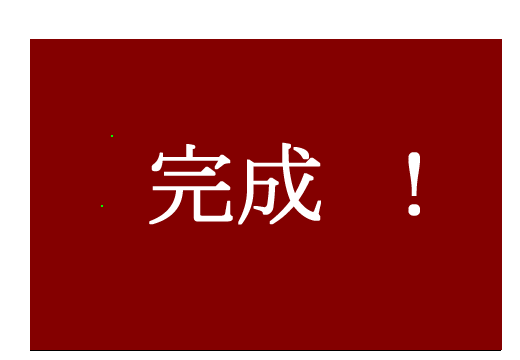
![]()
![]()
その他。
*第三押え竹があるので、茅と波板(上側波板、及び下側波板)の間には少々隙間ができています。これは、通気性や排水性に良い影響を与えると考えられます。
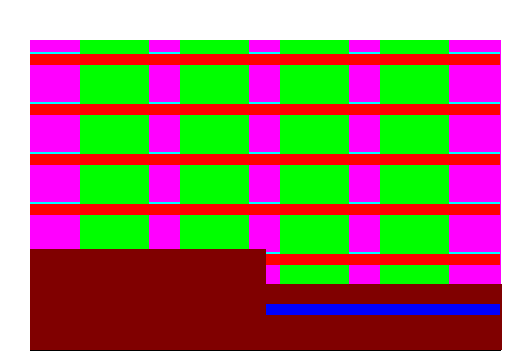
*波板は茅で覆われていますので、かなり長持ちすると思われます。。
*新たに用意するのは、長さの長い波板だけ。茅も、手に入らなければ稲ワラでもOKです。
簡単に適用できると思うのですが・・・・・・。