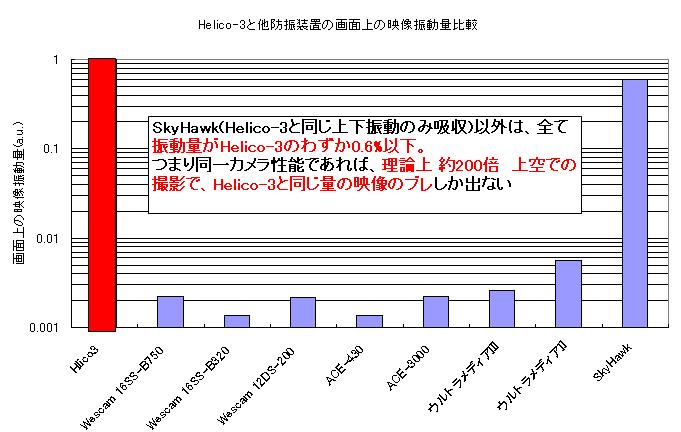【航空取材を取り巻く危険な現状】
(1) 放送会社の自社社員への安全管理責任の放棄
- 自社の社員の安全を
航空会社の操縦士の記憶と経験に一任するという、呆れた放送会社の安全感覚
- 企業努力を伴わない不思議な放送会社の競争
-
航空取材において、
十分なカメラ防振機能を有するカメラシステムを導入していない
放送会社においては、他社との映像におけるブレの差が
明らかであるため、被写体に接近し、
それによって画面上のブレを他局と同程度にするか、あるいはブレの大きい映像で我慢するかの
選択を
迫られる。
一方で航空法
および航空法施行規則においては、最低飛行高度が明確に
定められている。
競争原理が当然働く放送会社関係においては、一般に後者の選択は許されず、
結果として、極めて危険な低空飛行が横行することになる。
しかし、この「危険な低空飛行によって他社と競争せざるを得ない」という判断自体がおかしな話
である。
競争力を高めるためには、高性能なカメラ防振システムを導入するという当然の
「企業努力」をまず行うべきである。
事実、本件事故当時に高性能カメラ防振装置を採用していたのは、全国民間放送73社のうち
5割強に達し、またヘリの機数で算定すれば、
信越放送(SBC)自身の調査でも60機中39機、
なんと65%が採用している。
しかも信越放送(SBC)は、1996年4月27日に同じ長野県内で発生した、
長野放送とTV信州とのヘリ衝突墜落事故(乗員7名全員が亡くなった)の後に、社内外から
高性能なカメラ防振システム導入の要請があったにも関わらず、コストを理由に
導入を見送り続けてきた、との証言もある。
つまり、社員の命とコストを天秤にかけるという信じ難い判断基準を用い、さらに
「コストを優先させる」という、到底信じ難い判断を
信越放送(SBC)という会社は
行ってきたのである。
- カメラ防振システムの比較
信越放送が使用していたカメラ防振システム(Helico-3)と
他社が使用している高性能カメラ防振装置とで、いかに映像上での差があるかを調査した。
その結果、SkyHawk(Helico-3と同じ上下振動のみ吸収)以外は、
全て振動量がHelico-3のわずか0.6%以下。
つまり同一カメラ性能であれば、
理論上約200倍上空での撮影で、Helico-3と同じ量の映像のブレしか出ないことが
明らかになった。
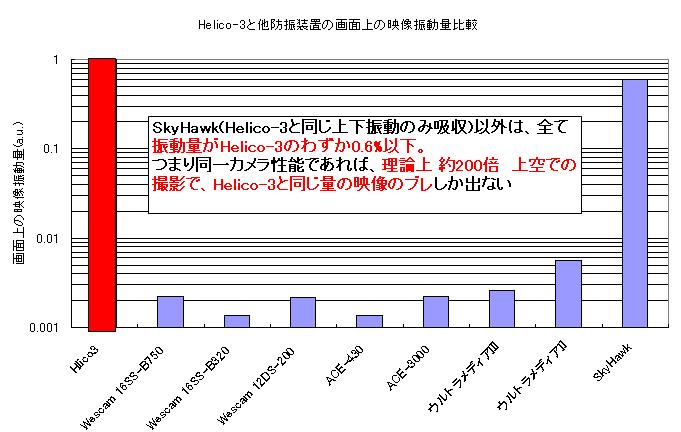
(2) 送電線への航空障害標識設置がほとんど行われていない実態
全国の鉄塔および送電線のうち航空障害標識設置物件は数%という「信じ難い」現状
過去の「ヘリコプター送電線接触事故はなんと131件」もある
- 1964年から2006年までのヘリコプターの墜落事故は575件、そのうち、架線事故は131件を占めている。
- 1998年以降、ヘリコプター送電線接触事故はなんと8件
である。
1990年以降における、志奈の事故と同種の事故 (ヘリコプター送電線接触事故) の詳細は
こちらから。
(3) 放送会社と航空会社との関係
年度末に不必要な航空取材が多発する現状
多くの放送会社が、社外の航空会社と航空取材の契約を締結をしているが、契約の多くは例えば
「6ヶ月飛行時間90時間」という具合に契約期間と
飛行時間を規定している。
そのため契約期間末になり、契約飛行時間に達していない場合、
それまでは航空取材の必要性が無いと
判断されていた類のニュース素材についても、
航空取材を乱発させるケースが多く、
志奈の事故もまさにそのケースであったと言える。
TOPへもどる