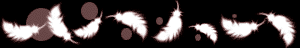「Blood Brothers」に関して、勝手につらつらと考えること
 公演情報
公演情報
東京公演:2003.10.4〜2003.10.19/青山劇場
大阪公演:2003.10.23〜2003.10.26/シアタードラマシティ
キャスト:
ミッキー/坂本昌行
ライオンズ夫人/前田美波里
リンダ/篠原ともえ
ライオンズ氏他/塚田三喜夫
サミー/久松信美
アンサンブル/国友よしひろ・須田英幸・清野秀美・池谷京子・矢野香苗子
ジョンストン夫人/島田歌穂
エディ/赤坂晃
スタッフ:
作・作詞・作曲 ウィリー・ラッセル
演出/グレン・ウォルフォード
翻訳/吉田美枝
訳詞/岩谷時子
音楽監督/杉山正明
振付・演出助手/西祐子
プロデューサー/松野博文(フジテレビジョン)・菅野重郎(R.U.P)
主催/フジテレビジョン(東京公演)・関西テレビ放送(大阪公演)
制作協力/ジャニーズ事務所・キョードー大阪
企画・制作/フジテレビジョン
卯多の観劇日:10/5夜(青山劇場)、10/23夜・10/25昼(シアタードラマシティ)
お断り
以下の文章は、あくまで観劇当時の卯多野亮の個人的見解及び作品の考察であり、制作者・出演者に、何ら関係も意図するものでもございません。
また、ストーリー説明や観劇レポはなく、舞台をご覧になったことのない方には全く解らない、 大変不親切な、極めて自己満足的な内容になっております。
その点、特にご了解のうえ、お読みください。
もうひとつ注意点。とにかく、本当にやたらと長いです。
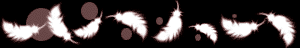
終観劇日のラストのミッキー。
「来んなよ!かあちゃん!」と叫ぶ姿の幼さ・頼りなさと、「なんで俺を(ライオンズ家に)やってくれなかったんだ…!」と言ったときの、ゾッとするほどしわがれた、老醜さえ漂うような声のコントラストが見事だった。
それを、帰りの道すがらに反芻していたら、いろんなことがスコンとはまり、やっと言葉になり始めた。
さらにいろいろ考えていたら、この作品がいかに、イギリスの階級・民族問題に深く関わっているかが見え始め、ちょっと面白くなって、いろいろ考察してみた。
そしたら、止まらなくなってきた。
どうも私にとっては、作品として本当に面白く、好きな舞台だったらしい。
以下、思いつくままに。あくまで私見ですが。(しかも、すべてミッキー中心)
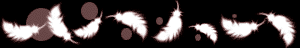
 なぜ、オリジナルは母ちゃんが主役なのに、日本版ではミッキーが主役なのか?
なぜ、オリジナルは母ちゃんが主役なのに、日本版ではミッキーが主役なのか?
この作品の背景にある、イギリスの階級社会、深刻な経済の停滞、アイルランド問題。
これらのことをきちんと理解していないと、ジョンストン夫人がなぜあのような行動をとったのかは、見えにくいだろう。
しかし、これが本来の主題であることは、オープニングのナレーションによって明白。
そうであったところで、たとえ一通りの知識があったとしても、現在の日本人には、感情的な共感は難しい。
このため、日本公演において、観客の視点をジョンストン夫人に重ねあわせることに無理が生じ、主役の交代が必要になってくる。
エディではなく、なぜミッキーなのか
前回の柴田恭兵版日本初演を観た人の感想を読んでいたら、「ギリシャ悲劇的にとらえたほうが、日本人には理解や感情移入がしやすいのではないか」ということが書いてあった。
ギリシャ悲劇的とは、どういうことか?
多くを読んでいるわけではないが、ギリシャ悲劇には、オイディプス・コンプレックスに代表されるように、肉親間での愛憎・執着により、事件が起こっていくものが多いように思う。
「Blood Brothers」に返り、先に書いたラスト・シーンのミッキー。
ミッキーは、「俺は、大人になっちまった…」と自分では言いながら、結局、最期まで母親に愛され守られていなければ生きて行けない子どもだったように思う。
このミッキーの母親の愛情の独占欲が、ラストの悲劇へ向かい、物語を動かしていく。
一方、エディはゆっくりではあるが、着実に精神的なバランスのとれた大人に成長していく。
誰かに愛され、守られなければ生きていけない危うさは、エディにはない。
そう考えれば、双子のどちらを主役にするとすれば、エディではなく、ミッキーの方がより肉親間の感情に行動を支配される要素がより大きく、彼を中心に据える納得性がでてくる。
ここでいうミッキーの母親は、二人いる。ジョンストン夫人とリンダ。
二人の愛情を独り占めしていることが、ミッキーをぎりぎりのところで支えていた。
そして、リンダの気持ちがエディに向き始めたことを知ったとき、彼はリンダの愛情を独占するためにエディの存在を否定しようとする。
しかも、最後の最後で母ちゃんの愛情さえ半分はエディのものだったと知ったとき、彼の正気は揺らぐ。エディの分の愛情まで、自分のものにしようし、反射的に引き鉄を引く。
だが、エディは自らの半身、もうひとりの自分。
自分の存在を自分で否定し、消滅させた以上、ミッキーも死ぬのは当然の帰結。
かくして、悲劇は完結する。予言された運命によって。
極めてギリシャ悲劇的な展開ではないか。
もうひとつの視点。エディとの同化
7歳、14歳、死の間際と3回繰り返される「エディになりたい」という意味の言葉も興味深い。
7歳のときは、単純に自分と全く違う人間への憧れ。
14歳のときは、自分にないものを持つ人間への羨望。
18歳になると、エディが持ち自分が持たないものが、階級の違いにより絶対的なものになる。
どんなにエディに憧れても、自分はエディのようにはなれない。
階級・貧富の差がそれを阻む。
そのことに気づいたミッキーは、羨望が憎しみに変わる前にエディを拒絶し、もう一人の憧れであり、自分と同じ環境にいて手の届くサミー兄ちゃんに引きずられてしまう。
ミッキーがエディを拒絶した後は、刑務所を出てからも、おそらく2人は会ってはいなかったのだろう。
それでも、リンダを通してミッキーを支えようとするエディ。
しかし、全てに絶望したミッキーには、エディが自分からリンダを奪う脅威の存在に見えてくる。
エディは何でも持っている。しかも自分に無償で分け与えるほど豊かに。
だが、自分にはリンダしかない。
エディは全てを持っているのにリンダまでも欲しがるのかと、憎しみに似た感情が生まれてくる。
全てのものはやがていつか奪い去られるという母親達、とくにライオンズ夫人につきまとう呪いは、ミッキーまでも取り込んでいく。
ミッキーはエディの後ろに、ナレーター(=運命)の暗い影を見ていたのかもしれない。
エディとリンダの関係をミッキーに教えるのが、ナレーターに取り憑かれたライオンズ夫人であることは、興味深い。
直接契約を交わした母親達から息子達を奪うためというのがシンプルな解釈だろうが、あの時点でミッキー自身が「悪魔に狙われた」と取ることもできる。
であれば、ここでもミッキーの方がより深く、物語の主軸にかかわっていることになる。
そして、死の直前。
自分がエディになれた可能性があったのに、もはやそれが叶わないことを知るミッキー。
絶望は瞬間的に自己破壊のエネルギーと変わり、エディに向けた銃の引き鉄を引いてしまう。
あの場面は、解説などでは銃の暴発とされているが、同じ暴発でも、不可抗力の偶然によるものではなく、やはりミッキーの絶望が瞬間、無意識の殺意に変わり、自ら引き鉄を引いたと考えたい。
でなければ、この悲劇がたどり着くべき結末が成立しない。
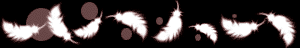
 愛情を注がれなければならない存在としてのミッキー、そして取り巻く人々
愛情を注がれなければならない存在としてのミッキー、そして取り巻く人々
このように、エディに対するミッキーの気持ちは、時間につれ、悲劇を招く方向へ変化していく。
一方、ミッキーに対するエディの気持ちは、形は変わっても、その本質に変化はない。
友情という名の愛情。
つまり、エディは愛情を求める側ではなく、与える側にいる。
何かを求めないエディの感情の流れは、悪魔に取り憑かれることもない。
しかし、彼に愛情を注いだ人たちが、それゆえの愚かしさにより、ミッキーを破滅に追い込んだことも、また事実だ。
ラスト・シーンで、彼らの死を悲しむ人たちが、「嘘だといって」を歌いながら、一人ふたりと舞台に現れてくるシーン。
その中には、サミー兄ちゃんもちゃんといた(服役中じゃないのか?逃亡し続けているのか?)。
そこにいたのは2人を本当に愛していた人たちだけれども、彼らを死なせた張本人たちでもあるのだ。
ジョンストン夫人
わが子をたとえ一人だけでも、安定した幸せな人生を送らせてやりたい。
母親なら自然であろうこの気持ちが、悲劇への道の最初の一歩を踏み出させる。
手放した後もエディを愛するが故に無関心ではいられない行動が、ライオンズ夫人を追い詰め、せめて手元に残ったミッキーを守ろうとするあまり寄り添いすぎた結果が、ミッキーを自立できない弱い人間にし、愛するがゆえにエディに銃を向けたミッキーを何とか止めようと真実を叫んでしまう。
あの時、彼女が現れたことにより、冷静さを取り戻しかけていたミッキーが興奮状態に戻ってしまった。
「かあちゃん!」と叫ぶミッキーは、泣き虫で甘ったれで、すぐかあちゃんの腕の中に逃げ込んでいた小さなミッキーだった。
今すぐ大好きなかあちゃんの腕の中に逃げ込んで、「大丈夫だよ」と抱きしめて欲しいのに出来ない。
そのジレンマが、彼の混乱をさらに煽っていく。そして、死。
彼女があの場に飛び出さなければ、あるいはミッキーとエディは生きていたかもしれない。
しかし、愛する息子2人が殺し殺されようとしているのを見て、夢中で飛び出さずにいられなかった母親を、誰が責められるだろう。
愛するがゆえの愚かしさ。
しかし、愚かになってしまうほどの愛情だからこそ、深く、得がたいものなのだと思う。
ただ運命が味方してくれなかっただけだ。
リンダ
もしこんなことがなかったら、リンダはかあちゃんが年老いて死んだ後も、かあちゃんの代わりにミッキーに愛情を与え、守り続けていったのだろう。
だが、彼女はまだ幼かった。
ミッキーを以前の彼に戻したい一心で、エディに助けを求め、ミッキーから薬を取り上げるリンダ。
彼女にはミッキーの弱さが、ちゃんと見えていなかったのではないか。
だから、形が元に戻れば、心も元に戻ると考え、ミッキーがあの時必要としていたものを見損ねてしまったように思う。
そして、自身も疲れ果て、ミッキーから得られない安らぎをエディに求めた。
それがどのような結果を招くことになるのかまでは、考えていなかったのだろう。
でも、それが彼女のせいだろうか?
ある意味、一番可哀想なのは、ジョンストン家の運命に巻き込まれた彼女かもしれない。
ただ、2人が死んだ後も、リンダは娘を育て、かあちゃんを支えながら、雄雄しく生きていきそうな気がする。
こういう女にならなくちゃな、という憧れも込めて、私はリンダが大好きだ。
サミー兄ちゃん
普通だったら、「お前が一番悪い!」ってことになるのかな。
でも、形は違うかもしれないが、サミーも確かにミッキーを愛していたと思う。
ワルながらも、彼の行動のそこここに、ミッキーへの執着を感じるからだ。
8人兄弟(本当は9人だけど)の7番目である彼にとって、ミッキーはただひとりの弟であり、自分の保護下にいる人間、あるいは自分の一部と思っていたのかもしれない。
子ども時代、いじめながらもミッキーを連れて遊んでいるし、ミッキーの前ではことさら自分を偉く強くみせようとしている。
他の兄姉の前では、サミー自身がボコボコにされ、チビ扱いされていたはずだ。
その彼の後を「サミー兄ちゃん、すごい!兄ちゃん、大好き!」とついてくる弟は、彼が自分自身に虚勢を張るために必要な存在だったのではないか。
だからバス強盗のときも、ガソリンスタンドを襲撃するときも、ミッキーを一緒に連れて行こうとする。
そういう存在として愛していたと。
弱くてバカでどうしようもない奴だけど、どこか人間的な愛おしさを感じる。
だからと言って、ミッキーが狂ってしまう原因をつくった張本人であることには変わりがないが、それも歪んだ愚かな愛情ゆえということで。
エディ
エディは、ミッキーと自分が兄弟であることを薄々気づいていたのではないかと思う。
最終公演近く、ラスト・シーンでジョンストン夫人が「お前達は双子の兄弟なんだよ!」と叫んだ瞬間、エディが胸にかけたロケットをぎゅっと握り締めているのに気がついた。
それがいつからなのかは判らない。
エディは賢い子どもだから、大人達の態度の中に何か秘密を感じ取り、それが少しずつ形を成していったかもしれない。
しかし、エディはそれをミッキーに告げることはしなかった。
そうすれば、二人の関係が壊れてしまうことも、それに耐え切れないミッキーの弱さも、彼は本能的に悟っていたのだろう。
そして、死ぬまでそのことを自分の胸に秘め続けることになる。
ミッキーや自分が愛する人たちや、自分自身を守るために。
そのことにより、エディはミッキーより一段上の立場となり、彼を守る側に立つことになる。
実際、成長したエディは、明らかにミッキーより大人だ。
そして、それが生まれもったものか、育った環境によるものかは判らないが、幼い頃からミッキーよりずっと強い人間だった。
ミッキーが彼に銃を向けたときから、エディは既に自分の死を受け入れていたように見えた。
双子であるミッキーが生きていけないのであれば、自分も共に死ぬのだと。
自らの意思でミッキーに全てを与えたとすれば、彼だけは運命に勝ったのかもしれない。
そして、やんちゃ坊主、ミッキー
とにかく可愛かった!
昔はいたよなぁ、こんなガキ。最近の、特に日本の7〜8歳では希少だろうが。
あんまりまんまガキなんで、「お父さん、公演終わったら、ちゃんと素に戻れるんだろうか?」と、馬鹿げた心配をしながら観ていた。
幼いミッキーの一挙一動に観客がどっと笑う。
しまいには、ミッキーがにひゃ〜とうれしそうに笑うだけで、こっちもつられて笑顔になってしまう。
後になって考えれば、この空気が重要だったんだなと思う。
ミッキーが愛情を求めつづける子どもであることが、悲劇へ向かうストーリーの根幹にある以上、観客の中に愛される対象としてのミッキーをしっかりと刷り込む必要がある。
そこができあがっていなければ、ラストは成立しない。
第1幕の2/3ほども使って7歳のシーンが繰り広げられる理由は、その辺りではないだろうか。
ある雑誌のインタビューで、「7歳のところをしっかりと作り上げなければ、大人になっていくミッキーはできない」と語っていた坂本の言葉は、このことを指していたのか。
彼がまず観客に見せなければならなかったのは、愛し守られる対象としての子ども。
この子を愛しいと思う気持ち。こんなに愛しているのに、なぜ!?
そのやるせなさによって、観客は登場人物の気持ちにシンクロしていける。
ラストの悲惨な結末がより胸に迫る。
その意味で、第1幕のミッキーは魅力的だった。
歌穂さんよりよっぽどでかい図体のくせして、きゅっと腕のなかに収まってるのをみると、思わず頭なでてやりたくなるような。
あんな子、欲しいよな。いたらいたで、大変だろうけど。
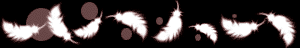
 アイルランドの影
アイルランドの影
階級社会と深刻な不況はストーリーに出てくるが、アイルランド問題は、直接的には見えにくい。
しかし、物語の中で、ジョンストン家がアイルランド系であることは示唆され、そのことがジョンストン家の置かれた環境やこの一家の性質を定義付けている。
つまり、ジョンストン家の貧困の背景には、階級社会だけではなく、民族問題も深く根を下ろしているのだ。
宗教について
第1幕最後の引越しのシーンでローマ法王の肖像画が掲げられる。
ローマ法王は、カトリックの最高権威者。
しかし、イングランドの宗教は、イギリス国教会であり、その最高権威者は国王(女王)である。
一方、アイルランドの宗教は、カトリックだ。
イギリスに住むアイルランド系にもカトリックは多い。
神に感謝するシーンで、エリザベス女王ではなくローマ法王の肖像画を掲げていることで、ジョンストン家がカトリックであることが判り、地域柄、アイルランド系である可能性が大きくなる。
舞台となったリバプールは、リバプール・サウンドなどにより、一見おしゃれなイメージもあるが、実際にはアイルランドから移民としてアメリカにわたる人々の中継地として発展した港町で、貧しい地域だ。
ここの住人の40%はアイルランド系。
アイルランド系の住民の多くは単純労働に従事し、失業率も高い。
お世辞にも豊かな生活とはいえないという。
ジョンストン家の貧困の裏側に、アイルランド系であるということが深くかかわっていると考えても、あながち間違いではないだろう。
ちなみに、リバプール出身であるビートルズのメンバーも、そのファミリーネームからスコットランド系だと推察できるポール・マッカートニー以外はアイルランド系だという。
そしてジョン・レノンの書く詩の世界観には、彼の生い立ちが深く関わっているが、家族離散、貧困など、ジョンストン家のキーワードと一致するものが多い。
子ども達の名前について
宗教について考えていて、気がついたのだが、ジョンストン家とライオンズ家の子どもの名前の付け方にも、両家の社会的背景による違いがあるのではないか。
ジョンストン家の子どもで名前が出てくるのは3人、長女のドナマリン、サミー、そしてミッキー。
ミッキーの正式名は、台詞にもあるようにマイケル。
大天使ミカエルが語源。「神に似たるものは誰か」の意。
サミーの正式名は、サミュエル(「神に聞き届けられた」の意)かサムソン(ヘブライ語の「太陽」が語源)。
どちらも旧約聖書に出てくる聖人の名前。
そして、ドナマリン。たぶん、ドナ・マリンと分かれるのだろう。
ドナは、イタリア語で女性を表すDonna、マリンはMairinで聖母マリアを語源とするMaryのアイルランド変形と推察できる。
ちなみにマリリン・モンローのマリリンも、マリアから派生した名前のひとつ。
このように、ジョンストン家の兄弟達は、キリスト教を語源とする名前が多い。
また、ドナマリンのつづりがこれで正しいとすれば、明らかにアイルランド系の名前が着けられている。
対するライオンズ家。
エディ即ちエドワードは、古英語で「富・繁栄を守護するもの」を意味するEadweardが語源。
イギリス王室に多い名前でもある。
ナレーターのイメージ
観る前は、「キャバレー」の狂言回しのように、神と運命を象徴するものかと思っていた。
しかし、こうしてイギリスという国の背景を考えていくと、シェイクスピアの「マクベス」に出てくる3人の魔女が一番イメージに近いのかと思い始めた。
「マクベス」でも、3人の魔女がマクベス王の破滅を予言し、それに抗おうとするが、結局予言どおりに破滅していく。
「マクベス」は、アイルランドでもイングランドでもなくスコットランドの話なのだが、アイルランドはスコットランドと同じケルト族だから、伝承にも共通したものがあるのかもしれない(イングランドは、アングロサクソン系)。
ちなみに、ヨーロッパにおける魔女は、キリスト教によって弾圧された民族固有の宗教の祭祀者・巫女がイメージの根源になっている。
固有宗教の神がキリスト教では悪魔とされている場合も多い。
ギリシャ悲劇で運命を予言する役割を多く担うギリシャの神々の中にも、キリスト教によって悪魔とされたものもある。
(この構図は、日本の原始宗教と神道・仏教(どちらも外来宗教)の間にもあてはまる)
総じて迷信といわれているものには、失われた原始宗教や民族宗教を源とするものが多く、このあたりにも、ジョンストン家にケルトの血を感じさせる。
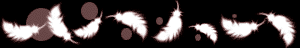
 出演者と役柄について
出演者と役柄について
島田歌穂/ジョンストン夫人
歌穂さんはやっぱ凄い!
その一言で集約。
久々に生で観たけど、やっぱ彼女の歌は心に直撃しますねぇ。
マリリン・モンローにそっくりというにはちょっとコロコロしてたけど、どうせナンパ男のくどき文句だし、実際にどれだけ似ていたのかは謎。
子どもができてからは、いかにも下町の子沢山の肝っ玉母さん。
良くも悪くも愛情深い、無教養で愚かな母親。でも生き抜くパワーは凄いっていう。
ミッキーがかあちゃん大好きなのも、よく判る。
彼女の存在が、物語を説得力のあるものにしていたと思う。
オリジナルのかあちゃん主役バージョンも、歌穂さんなら観てみたい。
前田美波里/ライオンズ夫人
相変わらず、お美しい…。
60年代のノーブルなファッションに包まれた立ち姿と、身のこなしは絶品。
当時のイギリスの中流階級では、まだビクトリア時代の影響が残り、女性は家を守り、子どもを育てることにこそ存在価値があるとされていたと聞いたことがある。
そんな中で子どもができないということは、彼女の存在自体を否定することだったのでは。
それゆえの子どもへの執着・狂気。
ライオンズ夫人もまた階級社会の犠牲者だったのではないのだろうか。
可哀想な人だと思う。
男性に守られて生きる女性の可愛らしさ、頼りなさ、弱さをしっかりと見せていただきました。
考えてみれば、「Footloose」の毅然として雄雄しいかあさんとは正反対だな。
でも、どちらも素敵でした。
憧れの女優さんの一人だから、美波里さん。
篠原ともえ/リンダ
やってくれました。
実は密かに期待してたんだけど、それを遥かに凌駕してる!
パンツ丸見えで暴れまわる子ども時代から、ひとりの妻としての苦しみ、女としての弱さまで。
しかも一環してかもし出されていた母性。
かあちゃん大好きのミッキーにとって、好きになる女性にもかあちゃんと同じ安心感を求めるのはしょうがないことで、この子だったら、ミッキーが好きになるよなぁと思える素敵な女の子だった。
それに、彼女きれいだよ。
前からちゃんとしてたら知的できれいだろうなぁと思ってただけに、今回の舞台でそれが観れて満足。
また彼女の舞台があったら、行きたいと思う。
真琴つばさ/ナレーター
ファンの方には申し訳ないが、率直にいって、主要キャストからアンサンブルまで満足度の高かったこの舞台の中で、唯一違和感があったのが彼女。
確かに存在感はあるし、動きも独特の華があってきれいなんだろうけど、いかんせん、舞台の空気から完全に浮いているように感じた。
その違和感がポイントだったという解釈もあるが、ナレーターが持つだろう闇の部分、陰惨さが感じられず、彼女の持つ華やかさ・きれいさが、逆の方向に作用してしまったよう。
ナレーターは、影の主役。
存在感は必要だけど、あくまで影の存在として、舞台の流れの向こう側でちらちらと見え隠れして、観客の不安をあおっていくのが役割ではないか?
なのに彼女が舞台に現れると、観客はまずその華やかさに目を魅かれ、ナレーターの存在に好ましさを感じてしまう。
それは違うだろう?
ナレーターの存在は、この血塗られた悲劇を牽引するものとして、観る側は恐怖・嫌悪・運命を逃れられない絶望を感じ、「彼らには関わらないでくれ!」と、その登場を押し留めたい衝動を起こさせるべきものではないか。
それには、彼女はあまりに宝塚のトップ・スター過ぎたように感じた。
あと、歌。
ナレーターというからには、物語を言葉(歌詞)によって補完していくのが役割のはず。
なのに、歌詞が聞き取れない。
活舌の悪さがオケの伴奏とのズレを生じさせ、不協和音となっていた。
そこにもともとなのか声が割れる傾向があり、よけいに歌詞を不鮮明なものにしていた。
その度にストレスを感じ、ストーリーに入り込んでいた気持ちがスッと覚めてしまった。
オリジナルと同じ男性でいいから、もっと残酷さと言葉のアピール力を合わせ持った方に演じていただきたかった。
塚田三喜夫/ライオンズ氏&その他いろいろ
坂本版「シェルブールの雨傘」初演・再演に続いて、3回目のめぐり合い。
でも遠い昔、「レ・ミゼラブル」に通っていた頃、アンサンブルにいらしたような気もする。
好きだなぁ、この人の声。
しかも、今回までこんなお茶目な人だとは思いもしなかった!
なんか塚田さんがいろんな格好して出てくるたびに、舞台があったかくフレンドリーになったような気がする。
少なくとも7歳ミッキーの次に観客を笑わせていたのは、間違いなくこの方でした。
久松信美/サミー
もぉっ、こ憎ったらしいやら!
なんなんだ、あの爆笑さそうパワーは!
もともと小悪党大好きだから、サミー兄ちゃんのワルっぷりもお気に入り。憎たらしいけど、好き。
初めて観た役者さんだけど、いい感じだった。
カーテンコールの度に、横の塚田さんとごちょごちょやって爆笑していたのは、何だったんだろう?
赤坂晃/エディ
TVでは観ていたものの、舞台では初めて。
きちんと舞台で実績を積んでいる人なんだなぁというのが、感じられた。
歌・芝居とも、安心して観ることができた。
基本的に王子様キャラなのかな。
ノーブルで生真面目な雰囲気が、エディにピッタリだった。
柴田恭兵版「Blood Brothers」は、残念ながら観にいけなかったんだけど、そこでエディをやった役者さんたちより、エディのキャラクターに合ってたんじゃないだろうか。
三田村邦彦・国広富之・太川陽介とも割と好きな役者さんたちなんで(特に三田村さんは一時ファンだったし)、彼らの演技はTV・映画・舞台といろいろ観てきたけれど、あの気品は難しかったんじゃないかと。
少なくとも、坂本ミッキーに対しては、「赤坂エディでありがとう!」と心から言いたい。
坂本昌行/ミッキー
我らがパパ。
お父さん、この舞台をやってくれて、本当にありがとう!
一度は観てみたかった作品だから、再演があれば他のキャストでも観に行ったとは思うが、パパが主役で観ることができたのは、本当に嬉しい。
今までの彼の芝居の部分には残念ながらどこか弱いものを感じていたから、このほとんどストレートプレイに近い難しい役をどんな風に演じるのか、正直不安はあった。
1回目の観劇のとき、第1幕はしょっぱなから引き込まれたけど 、第2幕は物足らなさを感じたのも事実。
「2幕、弱いな。もっとガンガン狂ってくれよ」って。
しかし考えてみれば、恭兵ちゃん(申し訳ない。彼も昔ながらのお気に入り)はどう演じていたのか知らないが、気の弱い、内面に向かうタイプの坂本ミッキーが狂ったからといって、ガンガン暴れて喚きまわるというのは違うような気もする。
あのミッキーなら、やっぱおどおどしながら、内に閉じこもるように狂うよなというのが、2回目3回目の観劇では納得できた。
開幕直後の1回目に比べたら、やっぱりいろいろな説得力が違ってきてたし。
なにより、3回目のラスト、死の直前に「かあちゃん!!」と叫んだとき、硬いどす黒い塊を喉元に投げつけられたような気持ちになった。
この種の衝動を彼からもらったのは初めて。それだけで今回は満足です。
今回は、共演者にも恵まれてたし。
役者としてはこれからが本当に勝負の年頃。
「雨月の愛」を観てからこの5年間に、彼が遂げた進化と上がっていく作品のレベルを見れば、十分期待していけます。
でも、1年に1回は、存分に歌って踊る作品が観たいよ、パパ!
最後にひとつ。
7歳ミッキーの指かじりや、しゃがみこんで地面を指でいじいじしているところや、かあちゃんの腕の中できょとんと見上げてるときの仕草や表情が、おたくの末っ子にそっくりだったのは、意識的ですか?無意識ですか?
笑って流しといた方がいいですか?
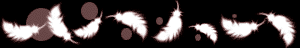
 追記/観劇から半年近くを経て、まだ考えてんのか!?ということ
追記/観劇から半年近くを経て、まだ考えてんのか!?ということ
10月の最初の観劇から、早や5ヶ月。
未だに折にふれ、思い出してはうちうちと考えている自分がいる。
某イギリスTVドラマのDVDを手に入れたことも相俟って、イギリス好きが再燃しつつあるのも、ひとつの要因だろうが、一番大きいのは、少し前に手に入れた英語版と日本語版で違っているという、ある重要な台詞に関する情報のせいだろう。
ミッキーの最期の言葉
オリジナルの英語版のラスト、エディを撃った瞬間、ミッキーは「No―!!」と叫び、次の瞬間に銃殺されるそうだ。
日本版ではエディを撃った銃声とミッキーを撃った銃声は重なっていた。
それって、ラストの解釈にとって、すごく重要なことじゃないか?
確かに英語の「No!」はその状況によってあらゆる意味を含んでくるから、日本語のひとことに置き換えるのは難しいかもしれないが、だったら「No!」のままでいいじゃねぇか。
今の日本人、十分それで通じるよ。
オリジナル公演を観ていないから、ミッキーが撃った銃声と「No!」の叫びが同時だったのか、撃った直後に叫んだのかは判らない。
もし引き鉄を引くと同時に叫んだとすれば、追い詰められて混乱し、なんでもいいからこの状況から逃れたいという衝動が、この事態を構成するひとつの大きな要素であるエディの存在を消したい方向に働き、瞬間的な殺意に変わったという解釈もできる。
また撃った後に叫んだとすれば、ミッキーには自分がエディを撃ったことを否定したいという気持ちが働いたことになり、そのことで彼はエディの死を望んでおらず、自分自身も生きる意志をもっていたと考えられるのではないだろうか。
どちらにしても、ミッキーが自分で引き鉄を引いたのは間違いない。
その時の彼の気持ちが、物語全体やジョンストン夫人の人生の意味を決めてしまうような気が、私にはしてならない。
なのに私の中ですとんと納得できる結論を決めきれないでいるから、いつまでもこうして考えてしまうのだろう。
で、いつまで考え続けるんだ? 自分?
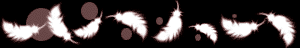
(最後までお読みくださり、ありがとうございます。「お疲れさまでした」かな?)


 公演情報
公演情報 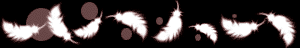
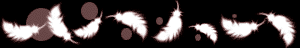
 なぜ、オリジナルは母ちゃんが主役なのに、日本版ではミッキーが主役なのか?
なぜ、オリジナルは母ちゃんが主役なのに、日本版ではミッキーが主役なのか?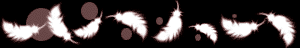
 愛情を注がれなければならない存在としてのミッキー、そして取り巻く人々
愛情を注がれなければならない存在としてのミッキー、そして取り巻く人々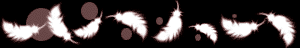
 アイルランドの影
アイルランドの影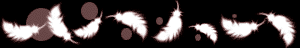
 出演者と役柄について
出演者と役柄について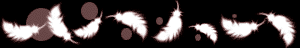
 追記/観劇から半年近くを経て、まだ考えてんのか!?ということ
追記/観劇から半年近くを経て、まだ考えてんのか!?ということ