

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�i���̂P�j�c���^�I�q���w���̍Ύ��L�x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�C���Њ����j��ǂ���c �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�i���̂Q�j�]���[�V��
�@�@�@�@�@�@�w�]���[�V�̃X�s���`���A���l�����k���x
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������_�V�Њ����j��ǂ�Łc�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�i���̂R�j�@�w����l�Q�̕s�v�c�Ȗ���x��ǂ�Łc
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�}�L�m�o�Ŋ����)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�c���^�I�q���@�i�C���Њ��j�@�@�@
�@�@�@�@�@�w���̍Ύ��L�x��ǂ��
�@�@
![]() �@
�@ ![]() �@
�@![]() �@
�@ ![]() �@
�@
�@�@���̖{��ǂ�Łc���̃C���X�s���[�V�����́A�v�������Ȃ��A���낢��ȁA���܂��܂Ȑ��E�ɂ܂ł��y�эL�����čs�����c
![]()
![]()
![]()
![]() �@�@�@
�@�@�@
�@�W���{�́A�ό����ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��W
�����A���Ȃ�ȑO�̂��b�ɂȂ邯��ǁA�w�ėՂ̃L���X�g�x�́A���{���w���Ă��̂悤�ɂ�����������Ƃ����B

�@�����āA�P�X�W�P�N�P�P�����w���ۃn�C�E�F�C�E�v���W�F�N�g�\�z�x�A�Q�O�O�T�N�U�����w���[���h�E�s�[�X�E�L���O�E�u���b�W�|�g���l���\�z�x��������A�w���E��������������x����Ƃ�������ڎw���Ă�����Ƃ���(=���E���ە��a�������H)�B
�@�����āA���̒��œ��ɒ��ڂ��ׂ��́A���{�Ɗ؍������ԁw�C��g���l���\�z�x�ł���c
�@�����̓��{���嗤�ɂȂ���A���̌o�ό��ʂɂ͌v��m��Ȃ����̂�����Ƃ����B�������A����͌o�ϖ��ɂƂǂ܂�Ȃ��A������ʂɂ����Ėc���Ȃ��̂�����Ƃ����c
�@�����āA�����o�c�̐_�l�Ə̂��ꂽ�A���E�����K�V���������A��������Ȃ��ȑO�ɒ����ꂽ���������w�d���̖��@��炵�̖��x�i���Ƃ̓��{�Њ��j�̒��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ�����B
![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�w�c���{�͂����Ǝ���̒����������Ƃ��l���Ȃ���������B�O���͑嗤�I������ǂ����Ă������I�ŕ��ʓI���B�������O�l�́A���{�̌i�ς�����ƒ������đ�ϊ�ԁB���{�̒n�`�͗��̓I�����炾�B
�@���{�͊O���ɉ���^�������Ƃ����ƁA�����^���Ȃ������B�����ł��@���ł��������B�Ȋw�A��w���������̂��݂�Ȗ����Ă���B���{����^�������͉̂����Ƃ����ƁA�����Ȃ��B�Ƃ��낪���{����^������̂��A���������B����́A���{�̌i�ς̔����B�Ȋw�A�����܂��ƂɌ��\�A�������O���ɂȂ����̌i�ς̔��ƁA�ނ�̉Ȋw�̒m���ƌ�������Ƃ��������l���Ȃ���A�Ⴂ���ςȂ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�Ⴆ�A�y�j�V�������������ꂽ�B���������֗��Ȃ��̂́A�S���O�l�̔�������Ƃ��낾�B���������_�ł́A���{�͔��ɕn�����B����͂���ł������Ǝv�����A�Ⴄ���̂����������ɂ́A�^������̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�^������̂͐^��p�U���ł͂����Ȃ��B�i�ς̔���ނ�ɗ^����悢�B����ɂ͂܂��ό������{������Ȃ�������Ȃ��B
�@�c�c�������������ǂ��g�����A��͂�y���݂Ɏg�������Ƃ������Ƃ������B���������_���炢���ƁA�������{���ό����ɂ��邱�Ƃ��A��Ԃ������������v���B�������������ł����E�̋��������Ă���B���̋��ŎY�Ƃ����邵�A���{�͑傫�Ȕ��W������Ǝv���B�����玄�́A�ǂ����Ă��ό��Ȃ��������A�N�Ɉ�牭�Ȃ��牭�̋����o���āA�͂�����A�����ɔ{�����牭�̋��������Ă���Ɗm�M����B���ꂪ���݂̂悤�Ȋό��ǂƂ��ό��ۂƂ����l�����ł̓_�����B�����ƍ��Ƃ��āA���̓_���l���đR�i�����j��ׂ����Ǝv���B
�@���ɂ��킹��A���{�̖�l�͋��������Ƃ������̂ɂ��Đ����ȗ����������Ă��Ȃ��B���������Ƃ͉�����Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��B�{���̋��������Ƃ͐l�X���K���ɂ�����̂��B���̂��߂̊�b�I�Ȋ������Ƃ������Ƃ��A�ނ�͍l���Ă��Ȃ��B�͕̂����I�Ȏv�z�ŁA�o�ςƂ��A���������Ƃ������Ƃ���ɒႢ�A�������̂ɍl���Ă���B�A�����J������ł͂����ł͂Ȃ��B������������b�ɂ��āA�l�ނ̍K�����v���Ă���B���̓_�́A���{�I�ɍl�������Ⴄ�悤���B
�@������A�x�܂��Ȃ�����{�ɂ��ό��Ȃł������l�����ς���Ă���B����͏d�v���Ƃ������Ƃ��킩������A�{�������܂�Ă���B�������������́A���Ԃł��ɂ͂�͂���E����������A�����ɂ���点�A���Ԃł��ł�����͖̂��Ԃł���āA���͑̐��������Ĉ�ďグ��M�ӂ��~�����c�x
�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@![]() �@
�@![]() �@
�@
�@����́A�I�킩��P�W�N�������A�P�X�U�R�N�i���a�R�W�N�j�ɏ��ł����q���ꂽ���̂̂悤�ŁA���̍��ȊO�ɂ��A�u�ό����Ƃ͓��{�̏����ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�v�ł���Ɛ����Ă����A����ɔ����u���H�̏d�v���v�ɂ����y���A�܂��A�u�h�C�c�v�Ƃ������Ɋw�Ԃׂ����̂���������A�Ƃ��q�ׂĂ���ꂽ�B
�@�����āA�͂邩�̂ɓǂ��̖{�̕ʂ̂ǂ����̍��Ɂc
�@�w�A�E�����ɗ������l���A��Ђ����߂Ă����l���A���ׂĂ͂��q�l�ł��B�x
�@�Əq�ׂĂ���ꂽ�����v���o���B
![]() �@
�@![]()
 �@
�@ �@
�@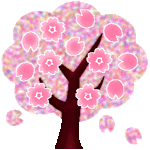
![]()
 �@
�@ ![]()

 �@
�@![]()
�@�����A���̌������{���́A�����I�����s�b�N�A���C���V�����̊J���Ȃǂ���ɁA�ǂ�ǂ��ό������i��ōs�����B
�����āA���̂��Ƃ����肩��ł��낤���A�c���p�h�������ɂ��A���̗L�����w���{�����_�x���o�����鎖�ɂȂ�̂́c�H
�@�����č���A�����e���r�E�ł́A�����̂悤�ɂ������{�̊ό��E���E�̊ό��ɂ��Ăǂ����̃`�����l�������f���A���ɃX�S�C�ȁA�Ǝv���̂́A�e���r�ƒn���̐l���������������Łc
�@�Ⴆ�A�T�X�y���X�E�h���}�ɂ́A�K���ǂ����̊ό��n��o�ꂳ���A��Ǝ��v�����˂��˂炢�ł����ĕ��f����Ƃ����I�@�u�킪�����v�ɂ��A����������ƁE���O���[�v�̂悤�Ȃ��̂��������A���Ă�����B(���E2001�N����)
�@�������́A�f��̐��E���܂߂��̘b�ł��邯��ǁi�w�j�͂炢��x�w�ނ�o�J�����x�Ȃǁj�A�������{�l�Ɠ��̏��@�ɂ͊��S�����������̂�����B
�@�������A���Ẵ��_�������̂悤�ɁA�I���I�v�f�𑽕��Ɋ܂����ł��邱�Ƃ�����������A���̓��{�B���ׂĂ��V�̈Ӑ}�Ƃ͂����c
�@���A�ӂƎv������������ǁc
�@���������A���������e���r�E�h���}�w���ˉ���x�́A������́A�ό������˂��T�X�y���X�E�h���}�̌��c�I���݂ł��Ȃ����낤��!?�@
�@����h���}�̕����ς��Ȃ���A�S���e�n����������d���ĂɂȂ��Ă��āA�o�D������A���̃h���}����₳�Ȃ����߉���ɂ��n���Ĉ����p����A�����������čs���Ă���B
�@����͂�͂�A���{���ό����ɂ������Ƃ����A�����Ԃ��V���ߊ��ł���A�V�̔z���ł���ɈႢ�Ȃ��c!
�@�����Ă܂��A�n���ɂ����Ă��ό��Y�Ƃɂ͓��ɗ͂����Ă��鏊������������悤�ɂȂ�A����͍��ł�����܂Ȃ��������čs���Ă���Ǝv������ǁc
�@���������̎��ɂ��Ă��A�u���Ƃ��Ắv�ˑR�Ƃ��ĉ��̔������Ȃ��A�����w�ό��ȁx�͖����������Ă��Ȃ��i���E2005�N���݁j�B�ό������H�Ƃ������ڂŁA��������������悤������ǁB�@
�@�����ɂ́A�w���ׂĂ̂킴�ɂ́@��������x�Əq�ׂ��Ă���c�ǂ����낤�A���{�͂܂��Ԃɍ����̂��낤�� !?�@���łɎ����Ă���̂��낤���c�u�n���ł��鎖�́A�n���Łv�Ƃ�������̂悤������c!?�@�܂����̖{�����q���ꂽ���_�ł����łɁA�u�x�܂��Ȃ���c�v�Əq�ׂ��Ă���Ƃ��납�炵�Ă��c�H
�@���������́A����͓��{�̍��Ƃ��ĉi���Ɏv���E�͍����E�������Ă����ׂ��ۑ�ł���A���܂�ɂ��傫�Ȗ��ł͂Ȃ����Ǝv���̂��A�����Ēx���͂Ȃ��Ǝv������ǁc!?
�@�����āA�����܂ł�����ł͂Ȃ��A�����Ƃ����w����x�ɓ����āA�����i�����j�̐����i�Ȃ�킢�j�Ƃ��čl���Ă��炢�������̂��ƁA�Ɏv���B
�@���Ȃ݂ɁA���͂Ȃ��������������炸�[�����A�w�ό��x�ɋ����������Ă����B
�@�w�Z�̐}���قł��A�ό��Ɋւ���{�����T�����߂�Ƃ��������������āi�����Ƃ��ẮA�ƂĂ����Ȃ������c�j�A
�@�u���Ȃ��̈��Ǐ��́H�v
�@�ƕ������ƁA���������l���݂ɂ́A���E�̖���A���{�̖�������グ�͂�������ǁA�S�̒��ł͂����A�w�ό��x�Ǝv���Ă����B
�@�u�ό��ł��I�v
�@�Ɠ�����ƁA�������₳��邩�킩��Ȃ����A�����g�A��̓I���ό��̂ǂ������Ƃ���ɋ����������Ɩ���Ă�������p�i���ׁj�͂Ȃ��������A�������{�␢�E�̊ό������A�R��́A�A�Y�ƂȂǂ�{�Œ��߂Ă���S�L�Q���A�Ƃ��������̎�����������A���܂���ɂ����Ȃ���������ǁc�@
�@�����A�h�C�c�I�Ƃ������u�A�E�g�o�[���I�v���A�����Ɣ]�����悬�����肵�āc!
�@�@�@�@�@�@�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�W�V���̍ŏ��P�ʂ͉ƒ�ł����W
�w�ėՂ̃L���X�g�x�́A�܂�������������������B�@
 �@�@
�@�@![]() �@�@
�@�@ �@
�@![]()
�@�w�l�ނ͈�Ƒ��ł���x�Ƃ͂�����@�����q�ׂĂ������ł��邯��ǁA����͐��E�Ƃē������Ǝv���B����A���E�����A�������ɂ��旧���Ă��̎�����{���O�ɂ����A�������ׂ��ł��Ȃ����낤���B
�@�������E�ł��A���̎��X�̏�ɂ�������낢��Ȑl�����Ƃ��o������܂�Ă���B
�@�ŋ߂̏ꍇ�ł����A�������u�b�V���哝���Ƃ����悤�Ɂc�����ߋ��A�߂��ߋ����܂��܂ɁB���]�������������[�K�������������������B���{���������G���c�B���������B
�@�@�@�@![]() �@�@�@
�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�܂��A�c���^�I�q���O�����w�����x�̊W�B
�@����́A��������������Ƃ�������Ő��܂ꂽ�B�@�@�@�@
�@���́A�c���p�h���������p���_�c�w�p���_�O���x�Ƃ܂Ō���ꂽ���̏o��́A���{�ƒ����Ƃ̊W�ɂ����Ė{���ɑ傫�����̂��������B
�@�p���_����������Ղ����A�v�������Ȃ����蕨���A�������{�ł́A�N���ɗN�����B���������ꂾ���́A���������Ă����������Ă͂Ȃ�Ȃ����̂��ƁA���ł����͎v���Ă���B
�@�������A����͎������ł͂Ȃ��A���̎���S�ɔO���Ă��鍑���͂����ς�����Ǝv�����A�����������l�������v���������A�h�i����j�����Ă��̍����Ƃ��������̌�����Ȃ�Ƃ��x�������Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�i�����A���D�������O�q�����́A���̑�\�I���݂������B�j
�@
�@�u�p���_�v�̐�����J���������������A����ȏ�Ɂc�����u�p���_�v�������炵�Ă��ꂽ�w�����������肤�S�x�������厖�ł���A������Ȃ����Ă͂��܂�ɂ��������C������B
�@�܂��A�����c���ǎ��̔g���̔�����`�������́A������������E�m�g�j��̓h���}�w��n�̎q�x�c�wꡂ��Ȃ��J�x�B�@�����E�@���̕ǂ��z�����A�l�Ԉ����������̑��́A���ł����̒������X�����c���Ă��āc�����̊W���e�Ŏx����c�܂����̖����̂��߂ɂ��c�ƂĂ���ŋM�d�ȑ��݂̂悤�Ɏv����c
�@�v���A�c�����O���́A�����w�������x�ɂ��Ɠ��̂������������B
�@��͂肻��́A�c�������琭���̒��ň炿�A�g���̐l���𑗂����啨�����Ƃe�Ɏ��Ƃ����A���̓��قȔ������炭����̂Ȃ̂�������Ȃ��B�����������̐S���悭���i���j�A��i�E�挩�I�Ȍ������炵�Ă��A���i�K�ł͉E�ɏo��҂͂��Ȃ������Ǝv�����A�ǂ����̂ƁE�������̂Ƃ��I�蕪������Ƃ����A�����w�I������x�̐^�������ɂ����āA���́w���x�ɂӂ��킵���c���E�Ƃ����ō�����O�ɂ��āA�i�O���Ȕᔻ�Ƃ����j�w�O�l�����̒n�x��������Ƃ��Ă����l�������c!
�@���ł������R�̂悤�ɁA�O���Ȕᔻ�͂��Ƃ��A�����ᔻ�A�����̔ᔻ���X�{�i�I�ᔻ�𑱂���A�}�X�R�~�ƊE�ł��邯��ǁc�c�����O�����a������ȑO�ɂ́A����Ȍ��ۂ͉e���E�`���Ȃ������C�����邵�A�܂��ɁA������v�̐�N�������̂��c�I
�@�u�c�����O���̎��Ӂv�Ɏ�_�≘�_?���S���Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����A����͂����������i�������j���琶�܂ꂽ�����ł���A���O���́c�܂��������̗͂����ł��ǂ����悤���Ȃ����̂Ȃ̂��B������A���������ɗ��z�����߂�Ƃ����̂͂��܂�ɂ����Șb�ł���A�{�肳���o����I
�@���A�Љ�ۂƂȂ��Ă����w�����߂̖��x�w�ƒ����x�c�����̖��̃��[�c�́A����ȂƂ���ɂ���̂���!?�@�Ƃ����A���͂��̎��i�X�R�����j�����v�������̂������B�����ߖ���͐̂��炠�錻�ۂ�����ǁc���Ă̂悤�ȁA����Ȗڐ�̒P���������ł͂Ȃ��A���̂��́c���̐[�����ȁc�W�c�Łc�k�}��g����c�Ƃ������A������u�����ߖ��v�̑���̍��������悤�ɋL�����Ă���B
�@�����A���E���̐ӔC������āA���X�Ǝ��E����l�����߂Ȃ�����c�܂������I�Ɍ��Ă��A���̃r�W������������ł͂��Ȃ��������c���������ꏏ�����ɂ��Č��O�ł����Ď���ЂÂ��Ăق����Ȃ��A�Ƃ����v���ł����ς��������B
![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]()
![]() �@
�@ ![]()
![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�������A���O���́A�������قȔ������琶�܂�邳�܂��܂ȍ���ɂ�������鎖�Ȃ��A�Ⴋ���X���O���Ɋw���i�z�[���E�X�e�C�̐悪���H�j�A�_�̓����ɂ��A����̐����p���A���̂����Đ��܂ꂽ�w���@��x�w�ώ@��x�ł����āA�����������̖��Ɗ�]�Ɗ��҂ɉ�����ׂ��A���I�i���Ɓj�ɂ��E���I�i���ƒ�j�ɂ��A������ė����l�������B
�@�܂������A�w �n�[�h���@�\�t�g�̎��� �x�ɂ����āA��������O���ɂ́A���̐��E�ɂ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��A��������Ƃ����w�������x���������B
�@�����āA���Ȃ��Ƃ����O���̖ڎw�������ɂ́A���̖��Ɗ�]�Ɖ\�����������B
�@�����āA�������w�|�X�g�x�ɂ���ƌ�����A������w�����x�ɑ��Ă��A���̂悤�����낢����w�ǂ������x���������̂Ɂc!
�@�_�l�̊����́A�c���p�h�����ȏ�ɁA�^�I�q�����ɂ������̂�������Ȃ��Ǝv���ƁA�ƂĂ��c�O�ŁA�������߂���Ȃ��v���ł���B
�@���ꂪ�i�X�R�����j�A�����̉Ƒ��̊ԂɋN�����o�������Ɖ��肵����ǂ����낤�H�@�Ƒ��͎����̖��Ɠ����ɑ厖�ȑ��݂ł��邩��A���Ƃ��C�ɓ���Ȃ����������Ă��A
�u������x�A�A���Ă���Ȃ����c!?�v
�ƁA�Ȃ�̂��߂炢���Ȃ�������͂����B
�@�����A���̎����̔g���͊C�O�ɂ܂ł��y���A�����Ȃǂ́A���Ȃ芴��I�ɂȂ��Ă����B���낢��ȍ�����A�R�����g����ꂽ�B
�@�]�_�Ƃ��U�F���Y�������A
�@�u�Ăі߂����@�͂���!�v
�ƁA���߂���Ȃ��\��Ō���Ă���ꂽ�����v���o���B�@
�@���Ƃ����O���ɔ������Ƃ��Ă��c����������́A�����w�I���x(�L���X�g���p��)�Ƃ����A�Ɍ���Ԃ̒��ɂ����čl����ɂ͂��܂�ɂ���ϓI�ŁA���܂�ɂ����傳�Ɍ�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��������낤���B
�@�����������́A�����ǂ����E�ǂꂪ�A���������炢�́u�����v�������̂�����Ȃ��ł����B����w�E���ꂽ���ň���炢�͂��������낤�Ǝv���Ԃ��Ă݂邯��ǁA���������Ďv��������Ȃ��c�O���Ȕᔻ�Ȃ�āA�Ƃ�ł��Ȃ��������������Ƃ͂����B
���Ƃ����ꂪ�����ł������Ƃ��Ă��A�����ɂ����A���̐l�́A�܂������̖{�ӂ�����ꍇ�������̂��B�u�\���̔��v���ԁA���������{�l�ł͂��邯��ǁB
�@�{���ɁA���܂�ɂ��ˑR�́c�܂��A�������Ȃ����ꂾ�����B
�@���ɂ��Ďv���A�O���Ȕᔻ�Ƃ�������Ŕj�ɒ��킷��A�܂�����Ȃ��w�J��҂̐�N�x���������ɂȂ�̂�����A�����ɂ́A���{���~�����߂ɉۂ���ꂽ�A�V�̐ۗ��̈�̃|�C���g���������ɈႢ�Ȃ��B�@
���ԍ������̖��(=�����哱)������Ă����āA�ǂ�����ĊO���̎d����i�߂Ă����Ƃ����̂��낤�H�@�C�O�̐l�����͐ߌ��ł͂Ȃ��̂��B
�@���y�ɂ��Ă��������A���ꂢ�Ȑ��Ő����������f�B�[���S���Ă��A���ꂾ���ł͂Ȃ��Ȃ��l�͒����Ă���Ȃ��B
�@�܂��w������ς�x�����A���{�l(�}�X�R�~�E���_)�Ƃ����̂́A�u�����̊�v�ł����āA���E�l�i�A�i�i�Ƃ݂Ȃ�����ǁc�l�ɂ͂����Ƒ傫�ȁE����ȑO�́E���������w�V���x�w�V�^�x�Ƃ������̂��^�����Ă���c�Ƃ��������l���Ă݂�ׂ����B
�@���ɂ́A���̗���ł����Ď��R���݁c�\����E������c�����肩�܂킸���u�^�I�q�ᔻ�v���J��Ԃ��}�X�R�~�̕��ɂ��A�������E��炸���u�������v���������ĂȂ�Ȃ������B
�@�����̐S�Ȏ�����͊O���A���ʂȋ�J�Ɣ����Ă��Ȃ���A������\�ʓI�ȋ�J�̂��߂ɑ傫�ȉ�蓹���J��Ԃ��c�܂��A�l�̋�J�������Ă��Ă��A�����̎��Ő���t�Ƃ����A����Ȏ��������{�l�ł͂Ȃ����낤���B
�@����͂�͂�A���{�l�́w�M�ρx���炭����̂��낤�Ǝ��͎v���Ă���B��(��)��ǂ���(�_��)�Ƃ�����̂������Ȃ����߂ɁA�����̌����Ɏ��M�����ĂȂ��c����Ƃ���E�C�x�߂́c���{�l�����ӂ́A�u���v�Ɓu�s���v�̎w�E�̌J��Ԃ��B�@
�@���{���(�ŋ����x�Ȃ�)�ɐG��悤�Ƃ͂����A��ɁE���ɂƂ��܂��܂Ȑ��E�̕s�ˎ��E�^�f�E���E���A�����Ɏ���܂ʼn��X�ƌ��p����E�Njy����ė�������ǁc
�@���x�����ς���(�����哱�E����E�������)�A�����͎��R���ł��čs���ɈႢ�Ȃ��A�Ǝv���鎖�̑������Łc���{�E�}�X�R�~�͂���(�Njy�E���y)�ɂ���āA�����������̖����̂��߂ɁA�����c���Ă��ꂽ�̂��낤�B�@
�@�w���Ղ̃L���X�g�x�ł������A�C�G�X�l�i���m����j�́A���Ɣߊ�̓����p���ꂽ�w�ėՂ̃L���X�g�x�i���m���j�ɂ���ĉ𖾂��ꂽ�A�����w�����{���x(�w��p��)�Ƃ������̂́A�ǂ�Ȋw�҂ł����Ă��A�ǂ�Ȕ����Ƃł����Ă��A�e�Ղɂ͗����ł�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@���Ƃ������ł����Ă��A��͂�A�w��x�̊������Ȃ������ɂ́A����������Ă��E����^�����Ă��E�ǂ�Ȏ��т��c���ꂽ�Ƃ��Ă��A�l�̐S�͓������Ȃ����̂ł���B�܂��Ă��ꂪ�A�厖�Ȃ��̂��]���ɂ�����ɐ��藧�������̂ł���A�Ȃ����炾�B
�������A����Ȏ��������{�l�̎�_���������A���̈Ӗ�������Ɖ����Ă��Ă����̂́A���̎q�������ł���Ƃ����c
�@����̒��ŌJ��Ԃ����A�������̂Ȃ������s�݂̐����_���ɁA���̎q�������͉��̉��l�����o���Ă͂��Ȃ��A�Ƃ������Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�������A����Ȓ��ł����Ă��A�ɗ��C����蒼���āA���ꂩ������E�̂��낢��Ȑl�����ƌ𗬂��Ȃ���A����������w�ό��Ȑݗ��x�̎����Ɍ��������w�͂��Ă����Ăق����A�Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�@�_�l�͂������A�����K�V������������������Ă���悤�ɁA�l�Ԃ̖{���́A�������Ɋ��E�y���肷��Ƃ���ɂ���̂ł����āA�������������̂��̂ɖړI������̂ł͂Ȃ��̂�����B
�@�l�Ɛl�Ƃ̏o��̒��ł����A�l�Ԃ̍K���͐��܂����̂ł���A���̂��̎��A�w�����������Ȃ����y�E�|�\�x�ȂǁA�����|�p�D���������������ɑI�ꂽ�Ƃ����̂ɂ��A�����ċ��R�ł͂Ȃ��A�V�̔z���ł���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���i�����m�̂悤�ɁA���q�������o�D�̓������ł�����j�c(�l�Ԃ̑̂Ɠ����悤�ɁA���ׂĂ̓��͂Ȃ����Ă���B)
�܂��A�����s�m���E�Ό��T���Y�����̑��݁B
�@�u��]�ˉ����v�u�ό��̂��߂̌�y�{�ݗU�v�̒v�Ȃ��w�����ό��x�c�u���ߎw��s�s�E�����v�ɂ������A�Ό��s�m���̐s�͂ɂ͈�����!
�@�܂��A�w�����}���\���x�w�����I�����s�b�N���v�^���x�Ƃ����c���̖c��Ȑ��_�́E�̗͂�K�v�Ƃ�����́c�w�����Ƃ͕����I(�����m���Ƃ�)�E�X�L���I��肾���ɑ�����̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���ꂱ�����A���E�̒��̓��{�̂�����Ƃ��Ă̌��{�E����{�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�������͑厩�R�̂ǐ^�ɐ����Ă���ɂ��S�炸�A���̂��A�㋞���邽�т�(�c�����ӂȂǂ�)�w�����̗x�����āA�A�܂����Ǝv���B
�@�u���Q�v�Ƃ��u�G�R���v�ʼnۑ������Ă���̂́A�ނ���n���ł����c(���Ă̔��Z���s�m����������Ɍ������ӎu���A����̐������炵�Ă����R�̂悤�Ɏp��)�������������ɐ^����Ɏ��g�ނ̂́A���������������B�u���R���Ɂv�Ƃ�������ǁA����͋�_�ł����āA�u���R�����v���������厖�ł���A�b�܂ꂽ���R������ɐ������čs���A�Ƃ������Ȃ̂��낤�B
�@�v���A�����w��t��������x�ɂ��Ă��c�����A���n�ɒ��ڏo�����A�w�������E�C��ۈ����ɋ��͂��Ăт����Ȃ���A�܂��w����̐ݒu�x�ȂǁA�c�������u�̗L���ێ��m�ہE�Ǘ��v�̂��߁A���������s�����E�s�͂��ꂽ�̂��A���̓s�m���������ƕ����Ă���B
�@�ɂ��S�炸�A�������O�������u���������v�Ƃ����ًc�\�����āE���̂��߁A���̐s�͂ɂ�����������A�啝�ɒx��A���̂����u��t�������E�����v�Ɍq����Ƃ����A���O�ȏo�������������B
�@�v���ɁA�����̔��[�ƂȂ������ׂĂ̌����́A�����ɂ���Ǝv���B(�����c���E��������k=�������𐳏퉻����A40�N�߂����o�Ƃ����̂Ɂc!)
�@�Ƃ����Ƒ��Ȏ�i�ɑ��肪���Ȉ����Ȃ����A�킪���̎{���ɂ������c
�@�����{�{�������c�u���p���v�Ȃǂɍv�������Ƃ������(�g��p���_)�A���������������̍��ɒ���E�v������l�����ɂ́A�����E�ǂ�����ʂƂ͈Ⴄ�A�挩�̖��E�������_�͂̂悤�Ȃ��̂��������c�����ʐςɂ����č����ő�l���������A������s�E�����c���������I��肾���ł͂Ȃ��A��ʐl�ɂ͌v��m��Ȃ��A�傫�Ȍ����ƁE�`���̂悤�Ȃ��̂��ۂ����A���߂��Ă���̂����m��Ȃ��B
�@���X�̔ώG���ɒǂ��钆�ŁA�֓�����E�����m�ɂ�����v���▲���A(��E�T���Y�����Ƌ��ɁA�l�I�ɂ��C�̍D����)�Ό��s�m���̒��ɂ́A�܂��܂��A���Ԃ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B(�ǂ����낤�c!?)
�@�������A���̑�ς��ɂ͑z����₷����̂����邾�낤����ǁc�n���ɐ����鎄�������猩��A�{���ɑA�܂�������ł���B
�@�������c����ɍl����i�߂Ă����Ɓc���̋K�́E�X�P�[���Ƃ������̂́A
�@�w�召���܂��܁c�x �w���{���܂��܁c�x
�@�ł����������悭�A�����ł����Ă����A���߂Ă��ׂĂ̐l�����������ɎQ���o�����킯�ŁA
�@�u�������ɂ́A�ƂĂ��肪�͂��Ȃ��c!�v
�@�Ƃ������̂���ł����̖؈����i�������݁j�ŁA���̐i���ɂ��Ȃ���Ȃ��A�Ƃ������������Ɍ�����킯�Łc�n�������Ă����̓����ł���A���{�ł���̂����m��Ȃ��B
�@�Ԃɂ����낢�날���āA�o���̉Ԃ̍D���Ȑl�c�X�~���̉Ԃ̍D���Ȑl�c�Ƃ����悤�ɁB
![]() �@
�@![]() �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@![]() �@
�@
�@���ꂩ����}�X�R�~�̐l�������́A���������炵���������w�����������A���̕\�����������ăo���o���Ɉ����̂ł͂����c
�@��e���A��̉Ƒ��̂��ꂼ��̌��͂������A�����������E�Z�������d���đ厖�Ɉ�ĂĂ����̂Ɠ����悤�Ɂc�����đ��f�ł͂Ȃ��A�T�d���E��Ɍ�����ĂĂ����Ăق����Ɗ肤�̂́A�����āA����l�ł͂Ȃ��Ǝv���B
�@
�Ƃ�����A�����������悤�ɁA�}�̖�����{�͂����ς��E�����ς������Ă����悤�ɁA���ɂ͎v����B
�@![]() �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@![]() �@�@
�@�@
�@�Ƃ���ł��̂悤�ɁA���{�̊ό�����ɂ��āA������w�n�[�h�̖ʁx���玄�Ȃ�Ɍ���Ă݂�����ǁc
�@���x�́A��̓I���w�\�t�g�̖ʁx�ɂ����Ă̂��܂��܂Ȗ��_�ɂ������Ȃ�ɍl���Ă݂����Ǝv������ǁc���܂��\���ł��邩�Ȃ��A�Ƃ����v���͂��邯����B
�@���́A�����ό��{���ɉ������āA�����̐l���̈ꕔ���ł͂��邯��ǂ��̒��Ő����Ă��āA���́w���̗��܂Łx����������ƌ������Ă������A�̊����Ă����B
�@�ό����E���{�̊ό��{���͑S���ÁX�Y�X�A���̋K�����召���܂��܁A���̌`�Ԃ����܂��܁A�������ꂼ��ɐF�Ƃ�ǂ�ŁA���܂��܂�����ǁc�@
�Ƃ������A�Ȃ�ƕ\�����Ă悢���c�����̎��i���̋ƊE�̋�J�j����ϓI�ɍl����A���ꂱ���A���ꂼ��̗���ɗ����A���ꂼ��̗���Ō��ƂȂ�ƍی����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�܂Ƃ߂悤�̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��悤�ȋC�����āA��ςȍ�ƂɂȂ�悤�ȋC������B
�@�������A�ɗ͎�ς�}���ċq�ϓI�ɁA�����|�C���g�������l���Ă݂�Ƃ�����A�Ȃ�Ƃ��܂Ƃ߂鎖�͂ł��邩������Ȃ��B�@
�����Ƃ��A�o�c�҂̋�J�܂ł͖��������Ēm��R�i�悵�j���Ȃ����A���̓����o�c�҂̋�J���́A���łȂ��Ƃ��e���ɂ͌��Ȃ����̂�����Ǝv�����A�c���Ȃ��̂�����悤�Ɏv����B
�@�����������̐����čs�����ő�ςȎ��̈�ɁA�w���q�l�����}������x�Ƃ��������i�Ȃ�킢�j������B
�@�܂��A���������ɂ��Ă��A�����E�����E�����E�Ղ��c�Ƃ������A�݂�Ȗ{���ɑ�ςȍ�Ƃ��B�����l�I�ɍl���Ă��A�����w���q�l���}����x�Ƃ�����Ƃ̋�J�́A�����҂łȂ���Δ���Ȃ��c!
�@�q������āA�����A�����w�Z�֑���o���c�Ƃ���������������ς��B�������A������c
�@�w��l�̐l�Ԃ��K��A��̐��������ċA��B�x
�@�Ƃ�����������A�q��Ă̋�J�A�ƒ�̋�J�Ƃ͂܂�������c�����̊��������ЂƂ܂��Z�[�u���āA���̒��ōs�����Ƃł��邩��A���̑�ς��͕ʊi���B
�@�������A���q�l�̖ړI�͐l���ꂼ���Łc�}�Ɏv�������ċC�y�Ȃ��ŗ����ł���ė���l�B�����������N���O����v��𗧂ĖK���l�B�܂��l�I�A�W�c�I�A���ƓI�c�Ƃ��܂��܂�����ǁA�葤���w���q�l���}����x�Ƃ����C������ْ����ɂ́A�卷�͂Ȃ��B
�@�����āA��������̓I�ɁA�w�\�t�g�̖ʁx����l���Ă����Ɓc
�@���́A�ό��Y�Ƃ̗��̗������Ă��āA���̒��ɁA���_�I�ɂ��E�����i�����j�I�ɂ��A������w�d�_�o�J���x�͂�������������̂ł͂Ȃ��Ȃ��A�Ƃ��������Ă����B
�@�l���K��A��̐��������ċA��̂�����A���̒��ɑ��݂��邠����Y�Ɓi�Ǝҁj��������Ă��鐢�E���B
�@�܂��A�Ⴆ�Ίw�����A�����������߂Â��ƁA���̊��Ԃ͐H�ׂ鎖���E���鎖�������ɂ��āA���g�������Ă��ׂĂ�����Ɍ��i���j����A�����Ă��̐��т��݂ẮA����J����c�����āA���̎������I���A�܂����i�̐����ɖ��鎖���ł���B
�@�������A�����ό��{���ł��w���q�l�����}������x�Ƃ�������(�Ȃ�킢)�ɂ́A�����X�X�������̘A���i���q�l����̃A���P�[�g�j�A�ْ��̘A���ŁA�����͔N�����x�ōs���A���i�̐����ɖ���Ƃ������́A�܂��A�Ȃ��B
�@�ގЂ��A�x���̎��Ԃɓ����Ă��A�܂��A���q�l�𑗂�o���i�`�F�b�N�E�A�E�g�j�A�܂����̂��q�l�����}������i�`�F�b�N�E�C���j�Ԃ̋x���Ƃ�����������A���ԓI�ɂ́A�J��@�ɂ��E���̎��ԂƂ��ė^�����Ă͂��Ă��A�����I�ɂ͉����A�ǂ����C�������Ȃ��B�����Č��x�����A���ꂼ��X�Ɂc�����Ƃ�������Ȃ��悤�ɁB
�@������N���A���ԂƗ���鎖�͂Ȃ��A���ԂƋ��Ɂi�ǂ��j�����Ă���c����Ȑ��������B
�@���q���s�ˎ��ɂ��Ă��c���̓��e�E���ʂ��ǂ�����A���E�����̂��q�ւ͂������A�O���ɂ͐�ɘR�炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��A�����܂ł��A�����ʼn��������Ƃ����̂��A�v���Ƃ��ẮE���̋ƊE�Ƃ��Ă̐ӔC�ł���E�펯�ł���A���{�����B
�@���Ƃ́A(�M�d�Ȃ��q�l�ɑ���)��(��Q��?)���́A�x�ʂ̖�����B����Ƃ���́A���ꂵ���Ȃ��B
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�܂��Ⴆ�A�`�F�b�N�E�C�����I�[�v���̏ꍇ�B
��ʂ��z�e�����f�p�[�g�Ȃǂł́A
�@���Ƃ����q�������ɑ吨�l�߂����A�����i���傤���j�̗�ŁA�u�܂����c�܂����I�v�Ƒ����ł��Ă��A�����Ă����낮���͂Ȃ��A�ꕪ�E��b������āA�I�[�v������B
�@�܂����q�̕����A����R�̎��Ƃ��āA�܂��펯�Ƃ��ĈÖ��̂����ɗ������E�ҋ@���Ă���B�����āA�I�[�v���ɂȂ�ƁA���q�̕����玩���I���\�c�Ђ����炰�ɂȂ��ė��فA���X���Ă�������B�@
�@�������A�����ό��{�݂ł̃I�[�v���Ƃ����̂́A�Ⴄ�B
�@�����E���b�͂������A���Ƃ��莞�̉����ԑO�ł��낤�ƁE�����Ԍ�ł��낤�ƁA���q�l����l�A����l�A�Ƃ������u���q�l�����g�̓������ԁv���`�F�b�N�E�C���ł���A���̂������ɑΉ�����̂ɁA�ꕪ�E��b�̒x�ꂪ�����Ă͂Ȃ炸�A������i�����j�Ȃ�ꂩ�˂Ȃ��i�������A�`�F�b�N�E�A�E�g�ɂ��Ă����l�j�B
�@�q�����A�[���x���w�Z����A���ė������A������������Ă��܂��Ă�����c���̂������s���ɂȂ�A�����̑��݂����ꂽ�悤�ŁA�{����o������E���������Ȃ����肷��c����Ȋ���Ɏ������̂����q�l�ɂ͂���悤�Ɏv���B
�@����قǁA���̂Ȃ�킢�ɂ́A�ƒ�I�ŁE�J���I�ŁA�S����������b�N�X�����߂������̂�����B
�������A���ꂾ���Ɂc���ɂ͎d���𗣂�A�t�ɂ����炪���q�̗���ɗ��������́A���������b�N�X�E�^�C���ɂ́A��ʂ̐l�ɂ͖��킦�Ȃ��A�ō��̂��̂�����̂�������Ȃ�����ǁc(����ɂ��Ă��A���̎�������Ă��邩��A�t�ɂ�����̕����C��z�����肵��?�c��)
�@�Ƃ���ŋߔN�́A��Ɗԋ����̖ڋʏ��i(������)�Ƃ��āA�Ⴆ��(JTB���Ăɂ��)�A�w�o�l�Q�F�O�O�̃`�F�b�N�E�C���\�x�Ƃ����̂����ڌ��������悤�ŁA�葤�͂܂��܂���ςɂȂ��Ă����i�`�F�b�N�E�A�E�g�͂`�l11:00�j�B���̒��́A���X�g���E���X�g���ŁA�o�c�ґ����E�J���ґ����A�ꐶ�����Ȃ̂�����ǁc
�@����ɂ��āA���͍l���Ă݂��B���q�l���o�l�Q�F�O�O�Ƀ`�F�b�N�E�C�������A�ǂ�ȃ����b�g������̂��낤�c�Ƃ��������B
�@�����Ɍ����āA�Q�F�O�O�Ƀ`�F�b�N�E�C���\���Ƃ��Ă��A�Ƃ肠�����������ɂ͂��ē��ł��Ă��A�����C�ɂ͂܂�����Ȃ��ꍇ�������Ǝv�����c�܂��e�����i���X�A�i���Ȃǁj���A���炭�{�i�I�ɂ́A�܂��J�X���Ă��Ȃ��ꍇ�������̂ł͂Ȃ����낤���H�@�����A�̐S�̓��̂��q�ɂ���ẮA����ȏ�����āA�t�ɓ��S�A�C���g����������������̂�������Ȃ��B
�@�����ĉ����A�Ⴆ���ό��n�̏ꍇ�A�������m���������s�������������A���g������A�S�g�S��ł����āA�ό��q�U�v�̂��߂ɓ���z�����Ă����Ă��A����Ȏ��Ԃ��`�F�b�N�E�C������Ă͏����オ������ŁA���̓w�͂��E�s�͂����̖A�ł͂Ȃ����c�Ƃ��������l������B
�@�܂�����ɁA�ߔN�́A�h���Ȃ����w�����x�e�x�Ƃ��������̂��A���������ɂ��ڌ������A�������Q��]�����Ȃ���Ȃ炸�A���̂��ߏh���q�ƁE�����Ƃ̌��ˍ����i�^�C�~���O�Ȃǁj���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B
�@�܂��Љ�̔��W�ɔ����āA���̒��͓��R�̂悤�ɁA�T�x������E�O�������~����Ă����A���̋ƊE�̋����͂܂��܂��������Ȃ��Ă��āA�q�̂��߂ɂ͌l�I�ȕs���E�s�����Ԃ��Ă�����ȂǂȂ��Ȃ����c�������A������ґ�ȔY�݂ł͂��邯��ǁB
�Ƃ��������ɂ́A�����ό��Y���Ƃ������̂ɂ́A�{���ɉ��̐[�����̂������Ǝv���A�_�l���p�ӂ��ꂽ�A��������̖����]�̒��ł��A�w���ɂ̌�y�x�Ƃ��Ă�����̂ł���A���낢����w�o��x������E�n�v�j���O����E�G�s�\�[�h����Łc���ꂱ���A�w�l�����̂��́x���v�킹����̂�����悤�ȋC������B�V��j������Ȃ��c�Ƒ��S����ΏۂƂ��Ă���B�@
�@���̋ƊE�͍����i���Ⴍ�j���킸�A�h���}�ɂ��悭�o�ꂷ��B
�@
�@���E������i�g�o�j�����ׂ��A����M�l�X�u�b�N�ɂ����c
�@���E�ő�̗A�o�Y�Ƃ́A���́u�����ԎY�Ɓv�ł͂Ȃ��A�����w�ό����Ɓx�ł���A������o�ϓI���ʂ����ł͂Ȃ��A���̂܂������𗬂ƂȂ�A���{�ւ̗�����[�߁A�l�X�Ƃ̗F��A�F�D�����R�Ȍ`�Ő[�߂��A�d�v�ȑ��̍������a�O���ƂȂ���̂������ł���B
�@�S���A���̒ʂ肾�ƁA���͎v���Ă���B�@�����炻�ꂾ���ɁA����ɑΉ����悤�Ƃ���A�葤�ɂ́A����w�̓w�͂��K�v�ɂȂ��Ă���B
�@�����K�V������������������Ă���悤�ɁA�ό��ǂƂ��ό��ۂƂ������l�����ł͂Ȃ��A�����ƍ��������āA�w�A�W�v���[�x�Ƃ��čl���Ă����Ȃ��ƁA���ɂ��ꂩ��̎Ⴂ����̐l�����ɂ͌��������̂�����ɈႢ�Ȃ��A�ƐɎv���B
�@�����āA�w��l�̐l�Ԃ��E��̐��������ċA��x�Ƃ������̎Y�Ƃ��A�w�����̗��x�������Ă͐��藧���Ȃ��B���q�l��U�v����܂ł̂Ƃ���A�܂�A�w�n�[�h�̖ʁx�͓��R�̎��E����ȏ�ɁA�Ƃ��������̌�������������Ȃ�������ǂ����悤���Ȃ��B��̉ƒ��Ɠ����Ȃ̂�����B
�@�l�X���y���܂��邽�߂ɓ����d���A�l�X���y����ł��鎞�ɖZ�����d���c����ȏd�v�Y�Ƃ��A�����w��e���Ɓx�w�������Ɓx�ƌĂ���A���{�ɉۂ���ꂽ�Ƃ��������c����͖{���ɑ傫�Ȗ��ł���A��]�ł���A�܂������ɁA�傫�ȉۑ�ł����c�ƁA���͎v���Ă���B
�@�����Ƃ��c�����w�n���̎���x�ƌ����鍡�ƂȂ��Ắc�����A�x���b���Ȃ��c�Ƃ͎v���Ȃ�����A����ȂƂ���ɂ܂ŁA���̎v���͋y��ōs�����B
![]() �@
�@ ![]() �@
�@ ![]() �@
�@ ![]() �@
�@
���́A�c���^�I�q���w���̍Ύ��L�x(�C���Њ��j���ǂݏI�����c���̖{�ɂ́A�^�I�q�����̂����l�I�Ȏ���������Ă��Ȃ�����ǁA���̃C���X�s���[�V�����́A���̂悤�ɁA�v�������Ȃ��Ƃ���ɂ܂ł��y�сA�܂��ꏗ���Ƃ��āA�����������܂ŕ���ł�������U��Ԃ�Ȃ���A���܂��܂Ȑ��E�ɂ܂ł��L�����čs�����c�c�B
�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2006�N1�� �` )�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̃y�[�W�̐擪�ցj
�i�� �̂Q�j�@
�@�]���[�V���@�@�i�������_�V�Њ��j
�@�@�w �]���[�V���X�s���`���A���l�����k���@�x�@
�@��ǂ�Łc�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@���́A����͂��͂�A�w��E���x�@���l�������Ă��̐����ǂ�Ȃɐ[���Njy������Ă݂Ă��A�Ȃ�̖�����]���A�܂��r�W���������i��j���Ă͗��Ȃ��A�ƍl����l�Ԃ̈�l������A�������A���̐l�E�w�]���[�V�i���͂�@�Ђ�䂫�j�����̒����x���w�e���r�o���x�͋ɗ́A�������Ȃ��悤�ɂ��Ă���B
�@�]������̒�����ԑg�́A�������l�Ԃ��A�Ƃ肠������ς��̂āA����������ÂɂȂ��čl���Ă����ΕK���Ƃ����Ă悢�قǎ��R�Ȍ`�Ŏ���A�̊��ł��A�[���ł���d���ɂȂ��Ă��āc
�@���ɁA���̂����w�I���x�Ƃ��w���@�x�ƌĂ��A���R�Ȋw�I�ɂ݂Ă��A�Љ�Ȋw�I�ɂ݂Ă��A�l�ޗ��j�̌���Α����Z�Ƃ����A���܂�ɂ�����������̒��ɂ����āA�u�K�v�s���v�ȁA�u������ׂ����Č���ꂽ���v���Ǝv���Ă���B
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@
�@���Ȃ݂ɁA��E�������ł���A���́E��E��`�}�����A�O�g�N�Y�����̐������̒����ɑ��Ă��A�܂������������S���o���A������̕��́A��������ʌ����Ƃ��ē��{�ł́A�Ȃ�Ƃ����Ă��A���̓����w���c�I���݁x�ł���A�S�������d���A���h���Ă������ł���B
�@�������A��������܂łɊw��ł������̂ƁA����l�̎咣�������̂̒��ɂ́A���܈�A�����̗]�n������i���̕��Ɂj�A�Ƃ�����肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ�����ǁA�Ƃ肠�����A�w��E���x���l���Ă������ɂ����ẮA���̒i�K�œ��Ɏx��͂Ȃ��Ǝv�����A�����g�A�܂��܂����s���ł��鎖�͔��i���ȁj�߂Ȃ��B
�@![]() �@�@�@
�@�@�@![]()
�@���́A
�@�@�w�I���x�@�Ƃ����̂́A���ꂪ�u�`�v�̏�łǂ�Ȃɖ��S�������Đ������Ă��悤�ƁA������w�S��x�������Ă��Ȃ���A�K���O�i���j���������A���E�������A�����͏��ł��Ă������̂ł���A
�@�w�@�P�i��j�����̂ƁA�������̂Ƃ��I�i��j�蕪�����鎞���ł���B�x
�@�Ƃ��������w�B
�@���̂��̓V���ɂ����āA�u���ׂĂ��Č�����v���鎞�v�ł���A�ӎ����Ă��E���Ȃ��Ă��A���R�I�ɁE�����I�ɂ����͐�����Ă������̂ł���A�Ƃ��������w�B�@�����āc
�@�w�I���̑��݂����ړI�́A�����܂ł��l�Ԃ̍K�������߂����̂����ɂ���B�x
�@�c�ƁB
�@�������A�`�Ƃ������ɂ͉��l���Ȃ��Ƃ������ł͂Ȃ��A�������Ȃ���A�܂��A�`�������Ă��Ȃ���A�S�͐������Ȃ��̂�����(���ǂ����A���������������Ȃ���m�b�����A�������Ă����̂Ɠ����悤�Ɂc)�B
�@
�@�����A���̐��Ŋ��������S�ɂ́A��E�ɂ����ẮA���͂���̂𒆐S�Ƃ��������Ƃ��`���Ȃǂ͂قƂ�ǕK�v�Ȃ��Ȃ�A�Ƃ��������̎��Ȃ̂��Ǝv���B�@������A�I���A���@�̎���Ƃ����̂́A�{���ɂ��܂�ɂ��d�v�Ȏ��ł���A���t�ł͌����s�����Ȃ����́A��ςȎ��ł���Ƃ����B
�@
�@�܂��A�w��E�x�́A���̐��Ƃ܂������������l�������A������A�w���x�ɂ��Ă��A�{���A�܂�A�l�Ԃ��w���i���炭�j�x(�w��p��)�����Ȃ�������A
�@�@�@�@
�@�u���ꂶ�Ⴀ�A����ɂˁB�v
�Ƃ��������̂��̂ł��������A���̐��͂��ׂāw�P�x�ł����đn������Ă����i�������j�A���������āA���̎����ܘ_�A�w�P�x�ŏo���Ă��邩��A
�@�u�A�[�b�A���ʁ[�b�I�v
�ȂǂƂ����C���͖���킹�Ȃ��悤�����Ă���B����́A���̌�����������Ȃ����鎖�A���O���Ǝv���B
�@�l���͈�l�c�炸�A�����̒����w�����x�i�_���Z�܂��鏊�j�������Ă����Ƃ����B�@�����玄�����͖{�����猾���A�����_�l�Ƌ��ɐ����Ă����킯���B���̒��̌����͂Ƃ������Ƃ��āc�����܂ł��A�{�����猾���B�@�����āA
�@�u���̐�������̂́A��E�̂��߁B�v
�@�ł���A�_���u�l�ԑn���̖ړI�v�́A
�@�u���̐��Ŋ��������킪���g�ƁA���̗�E�ʼni���̍K���ł����ċ��ɕ�炷���v
�@�ł���A�������Ȃ��������A���̐�������K�v�͂Ȃ������c
�@������A�Ⴆ�͈�������ǁA�_�l���猩��A�u�V�c�É��v���u���v���A�u�܂������������l���������i���Ɓj�������g�v�ł���A����͐̂̐l�������炷��c�܂��u�����_�v�����w��ł��Ȃ������l�������炷��c�Ƃ�ł��Ȃ��A���������������o�����m��Ȃ�����ǁA�ԈႢ�̂Ȃ������Ȃ̂��B�@
![]()
![]()
![]() �@
�@![]()
![]()
![]()
 �@
�@
�@�������A�������������A
�@�u����́A�S��I�Ȃ��̂��B�v
�@���A���R�̂悤�Ɏv���Ă������ł��A�V���猩��A�����̕����I���l�̂��̂ł����Ȃ��A�Ƃ��������ł������肷��B�@�����̎��́A���̐��ɍ��i���j�邤���ɂ悭�悭�������Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ���肾�Ǝv���B�Ⴆ�Č����A���ꂪ�A
�@������������u�ꗬ��Ɓv�u�ꗬ�ƌn�v�ł��낤�ƁA
�@
�@���́u�d�v�ȁE�M�d�ȕ����v�ł��낤�ƁA
�@���Ƃ��A�_���E���{�̒��Ŕ|�i�����j��ꂽ�u�����A�����`���v�ł��낤�Ɓc
�@�Ƃ������A���Ƃ������������̂ł������Ƃ��Ă��A�w�S��x�c������������A�w���̌p���x�̔���Ȃ������ł���A����͂����ɂ�
�@�u�����Ƃ��炵�����́v
�@�Ƃ��āA�����������Ă��������Ȃ��A�Ƃ������ɂȂ�c?
�@������҂������A���̂悤���ƍ��������玟�ւƌJ��Ԃ��Ă������{�̌����̈�́A���̎��i���l�ς̖���j�����łɌ������Ă��āA�������琶�܂��A���̗����ɂ���Ă����Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�]�������́A�����̖�肱�����l�ԂƂ��Ă̍��{�̏d�v�ۑ�ł���Ƃ��āA���܂��܂Ȋp�x�������Ă����邯��ǁc���̂悤�ȁA���k�҂���̎�������ɂ����ďq�ׂĂ�����ӏ�������A���k������ǁA���ЁA���グ�����Ă������������Ǝv���B�i�������_�V�Њ����j
�@�@![]() �@�@
�@�@![]() �@�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@���k�҂̎���c�c�W�q�ǂ����ł��Ȃ����͕s�K�ł��傤���H�W
�@�@�]������̉��c�c�������ɂ��܂��܂ȃP�[�X�����Ă��܂����B�����Ō�����̂́A���̖��̓P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�ł����āA��T�ɂǂ��Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@����́A��l�ЂƂ�A���̐��ɐ��܂�Ă����u�ړI�v���Ⴄ����ł��B�l�݂͂ȓƎ��̃X�s���`���A���ȖړI�������āA���̐��ɐ��܂�Ă��Ă��܂��c�c�B
�@�c�c�ł́u�ꐫ�v�͎q�ǂ��݈�ĂȂ���Ίw�ׂȂ����Ƃ����ƁA����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�u�q�ǂ��������ƂŊw�ԁv�l�Ɓu�q�ǂ��������������ƂŊw�ԁv�l�̓�ʂ肢��̂ł��B�ǂ���������w�тł���A�`�̎��Ƃɏo�邩�A�a�̎��Ƃɏo�邩�̈Ⴂ�ɂ����܂���B
�@���������������ɓ`�������̂́A�q�ǂ�������K���ŁA���Ȃ�����s�K�Ǝv���̂��u������`�I���l�ρv�ł����āA���̍l�����ɂ͐�Ɋׂ�Ȃ��łق����Ƃ������Ƃł��B
�@���Ԃ̐l�́A�܂�Ől������{�����Ȃ��H���̂悤�Ɏv���A��l�ɂȂ����猋���A����������q�ǂ��A�q�ǂ����ł�����}�C�z�[���A�ƒP���ɍl�������ł����A����͑傫�ȊԈႢ�ł��B�O���i���c�ȗ��j�̌����Ɠ����ŁA�u�q�ǂ��������Ɓv���l���̑I�����̈�ɂ����Ȃ��̂ł��B
�@�q�ǂ�������l���Ȃ��l�A���ꂼ��̐l���Ɋ�тƋ�J������܂��B����ǂ������̐l�����g�[�^���Ō���A�v���X�}�C�i�X�����E����đ卷�͂Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B�Ȃ�̋�J���Ȃ��Ɏ��R�Ɏq�ǂ������������l���A�q��Ăɂ͎q��Ă̋�J������ł��傤�B�����Ƃ��̌��ۂ��������čK�s�K�������͈̂Ӗ�������܂���c�c
�@�c�c�ǂ��������ŁA���傫�Ȉ��̐S�������Ă������������̂ł��B�q�ǂ��������Ő��݈�Ă������炢�D���Ȃ�A���l�̎q�ǂ��ł����킢���͂��B�����Ɏq�ǂ������Ȃ�����A�悻�̎q�����킢���v���Ȃ��Ƃ����̂́A������������������A�u�݂�Ȃ������̂������ق����v�Ƃ���������`�I���l�ς̗��Ԃ��Ƃ͂����Ȃ��ł��傤���B
�@���̐S�����z���āA�ǂ̎q�ǂ����S���炩�킢���Ǝv����悤�ɂȂ邱�Ƃ��A�܂��ɐ�قǏ������A�u�q�ǂ��������Ȃ����ŕꐫ����ށv�C���Ȃ̂ł��c�c
�@�c�c�{�q���g�́A���Ăł͂��ƕ����ł����A���{�ł��ŋ߂͂����Ԃ��Ă��܂��c�c
�@�@���̒��ɂ͎q�̂Ȃ��e�ƁA�e�̂Ȃ��q������B���̑o�����u�{�q���g�v�Őe�q�ɂȂ��̂́A�ƂĂ����炵�����Ƃł��B�����̂��Ȃ���ɂ߂邱�Ƃ⌌�̂Ȃ���ɂ������̂́u�����I�ȉ��l�ρv�B�n����ɑ吨����e�̂Ȃ��q�̒�����A��������l���킪�Ƃɗ���̂ł��B����́A�܂��ɃX�s���`���A���ȓ����ɂ����̂ŁA���Ȃ��ɏh��̂Ɠ������炢��ՓI�ȉ����ƒm���Ăق����̂ł��c�c
�@���X�̑��k�̒��Ŏv���̂́A����O�̂悤�Ɏq�ǂ������������v�w���A�s�D�ŔY�v�w�̂ق�����قǍK����������Ȃ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��c�c�q�ǂ������Ă����Ȃ��Ă��A�����́u���ǂ��v�̂��ƂŔY�ނ��́B����́u�ꐫ�����ӂ���܂��܂��傤�v�Ƃ����A���ɑ�Ȃ��܂����̃��b�X���Ȃ̂ł��B�x�@�@
�@�Ƃ����悤�ɁA���̍��̒����]�������͏q�ׂĂ����A�����āc
�@�u�q�ǂ��͐l�i�łȂ��ꍇ������܂��v�c�u�������c�ގq�ǂ��̂��Ȃ��v�w�ɂƂ��ẮA���́w�����x���q�ǂ��ł�������A�܂��l�ɂ���ẮA�w�d���x��u�w�����x���q�ǂ��ł�����������܂��v�@�@
�c�ƁB
 �@�@
�@�@![]()
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߂̗��s�� �̒��ɁA�u�����g�v�Ƃ��u�����g�v�Ƃ������̂����邯��ǁc�]�������̗������āA�X�s���`���A���Ȋϓ_���炢���ƁA
�@����Ȍ��t�����s�i�͂�j��o�����A���̂炢����A�S�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ�����ǁA����͋��炭�O���ɂ͒ʗp���Ȃ����낤�i���ɃL���X�g�����ƂȂǂɂ́j�A�����I���l���ɂ܂݂ꂽ�A���܂�ɂ���x���Ȍ��t�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���c?
�@�]�������́A
�@�u���m���A�n�ʂ��A�w�����A���ׂĂ͕����B�{���̍K���Ƃ͉���W�Ȃ��B���������{�l�́A�傢�ɋ�Y���A�{���̍K�����l�������������Ǝv���Ă��܂��B�v
�@�Əq�ׂĂ�����B
![]() �@�@
�@�@![]()
![]() �@�@
�@�@![]() �@
�@
�@������A�u���q�����v�ɂ��Ă��c
�@������₳�Ȃ��A�Ƃ����������Ɏ������A����ɘA�������A�u�����g�v�u�����g�v�Ƃ����ӎ���v���b�V���[���܂��܂����������悤�Ȏ��ɂł��Ȃ�A���{�͋t�ɁA�ǂ�ǂނ̓������ǂ����A�Ƃ������ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���B��������Ƃ����w���@�x���w�ړI�x�������ėՂނׂ����A�Ƃ����C������B
![]() �@�@�@
�@�@�@
�@�@�w�c���̑��݁x�ɂ��ẮA�����A�悭��荹���i�����j�����B
�@��̂ɂ����Ċv�V�n�̐l�����́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɣے�I�ŁA�ێ�n�̐l�����́A�{�\�I�ɂƂ炦���F�i���ɂ�j���Ă���B
�@�@![]() �@���ւ��̘b�@
�@���ւ��̘b�@![]() �@
�@
�@�Ƃ���ŁA���̂��Ƃɂ͂��ׂ��w���S�x������B
�@�ʕ��ɂ����i���ˁj�B�������s���ɂ��A�K���A���S�����߂ăI�[�v���Ȃ�A�X�^�[�g�Ȃ肷��B
�@�ʕ�������A��������ɂ��鎞�́A���Ǝ��I�蕪���āA��͎̂ĂĂ��܂�����ǁA���N�̂��߂ɂ͂܂���͕K�v���B
�@�����āA�l�Ԃ̑̂ɂ��w�`�i�ւ��j�x������B
�@�������A���Ƃ͂Ƃ��������A��ʂɂ͓����A�`�ɂ��Ĉ�w�I�ɂ͂��܂�d�v�����Ȃ����A�b����o�Ă��Ȃ��B���������A�`���ǂ��Ƃ������Ƃ��c�܂��A���܂�C�W���ƕa�C�ɂȂ�Ƃ��A���̒��x�ł���B
�@�������A�w�`�x�ɂ��Đ^���ɍl���Ă݂�Ɓc����͑�ς��厖�ȑ����ł��鎖�ɋC�Â��B
�@
�@�Ȃ����Ɨ��R����Ă��A���ƂłȂ����̓I�ɂ͓������Ȃ�����ǁA�`���Ȃ��������ς��A�Ƃ������͕�����B
�@�Ƃ��������A�����ɂ��A
�@�w�َ��́A�����ʂ��ĕ�̂���h�{���Ƃ��B�x�@
�@�Ƃ��邩��A�����A���ꂪ�Ȃ�������l�ԂƂ��Ă��̐��ɒa���o���Ȃ����ɂȂ�B
�@����ƍN�́A�w�c���Ƃ��`�i�ւ��j�ł���x�Əq�ׂĂ���B�i�R���������w����ƍN�x���j
�@�����A���{�̍c�����w�ے��x�Ƃ��Ēu����Ă���킯�����A�Ȃ�قǁA�����[���̂������̂�����C������B�@
�@�����āA������V�̌v�炢�ł������̂��A�Ƃ�������������c
�@����ɂ́A���R�̎��Ȃ���A���̂悤�ɁA������Ƃ����Ȋw�����܂܂�Ă���A����ς�A�_�l�Ƃ����̂́A�X�S�C�i�I�@�Ƃ����������߂Ċ����Ă��܂��B
�@�@�@�@![]()
![]() �@�@
�@�@
�@�������c�Ђƌ��ŁA�u�ʕ��ɂ͎�v�Ƃ�������ǁc
�@�Ⴆ�A�����̉ʕ����A�n���̗L�����`���Y���Ƃ��Ă���ꍇ�A�����ɂ����܂��܂ȋ�J���������낤�B
�@�`���̖�����葱�������͂��������ǁA�����w�ړI�x���l���A���̎���ɍ��킹�����o�A�܂��A�������ŁE��葽���̎��n�������邽�߂ɂ́A��ɁA����Ȃ��w�����������K�v���B
�@�܂������A���R��Ƃ���Y�Ƃ�����A�V���ւ̔z���A�Q������̖h���c�ƁA�N����N���A����������ڂ������Ȃ��c!
�@�ɂ�������炸�c���R�ЊQ���A���n�͂������A���������E������ׂĂ�����A�܂��ꂩ���蒼����������Ƃ������ɂ��A���������ɂ͑������邩���m��Ȃ��B
�@�����ł܂��A���x���w�}(��)���x��������A�w��(��)���x�������肵�Ă������i���u���Ȃ���A���̐���ւƌq�i�ȁj���ōs���B
�@![]() �@�@�@
�@�@�@![]() �@�@
�@�@
�@�v���N�����c
�@�c�@�E���q�q�l���w�O���i�������j�x�́A���������{�����̋O���ł������B
�@�����āA���q�q�l���w�S�̗��H�x�́A�������̐S�̗��H�ƂȂ����B
�@�Ƃ͂����A�������͂Ƃ����A�c����肪�����オ�邽�сA�}�X�E���f�B�A��ʂ��Ă��̂��p��q�����Ȃ���A���Ɉ���J���邾���̎�����������ǁB
�@���̑��Z�ȍc���O���A�܂������̈玙���ɔz������钆�ō��ꂽ�w������@�x�́A�V��j������Ȃ��A�玙�ɂ͊֗^���Ȃ��l�Ԃ܂ł��������������B
�@���q�q�l�́A�w�҂x���Ƃ̑�������ꂽ�B
![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@�@
�@�@
�@�����āA
�@�c���q�܁E��q�l�́A�P�O�N�߂��ɋy�Ԓ����Ό���҂��ꂽ���ɁA����ƁA�������������S����҂����i���j���ꂽ�A�S�����̃A�C�h���A�w���q���܁x ��������ꂽ !
�@���̎����w�����x���A�����������͊�Ό�������悤�Ƃ��A�����ĖY��Ȃ��I
�@���A�U��Ԃ��Ă݂Ă��c�����A���Ȃ��Ƃ������������ɂ́A
�@�u�j�̂��q���܂�!!�v�@�u���̂��q���܂��c�v
�@�ȂǂƂ����ӎ��́A���ɂ��Ďv���ƁA�{�����s�v�c�Ȃ��炢�Ȃ������c�����E���������������I
�@
�@�ߋ��̎���̏����c���̕������ɑ�������T�O���炷����A�������ς��ӎ����v���������ɂȂ�I
�@�������c�����������́A�����ȓV�̌v�炢�ɋC�Â��͂����Ȃ��A�܂��A�Ȃ�̜��i�͂��j����Ȃ��A�w���q���܂̂��a���x��S����]�����A����������肾�����B
�@����́A���Ƃ��ė���邠�́A���Ȃ��݂��w��q�l�̉f���x������������悤�ɁB
�@�ł��A���ɂ��Ďv���Ɓc
�@�������ɂ́A�����w���q���܂̂��a���x���ʂ��āA�ӎ��̓]����������悤�Ƃ��Ă����̂����m��Ȃ��c!?
�@�����Ă���́A�]�����������Ă���悤���A
�@�u����O�̂悤�Ɏq�ǂ������������v�w���A�s�D�ŔY�v�w�̂ق�����قǍK����������Ȃ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B�v
�@�Ƃ������t�ɂ��Ȃ����A�_�l�́A���̎����������ɋ������������̂�������Ȃ��ȁA�Ƃ������c�q�ǂ��Ƃ������̂́A�{���̉��l���B
�@�@���q���������a�����炵�炭�o�������A����c���{�݂�K�₳��c
�@�@����ɕ���Œ��Ȃ��Ă���A�吨�̂��ǂ�������O�ɂ��āA���̎p�����߂Ȃ���c�����ꂽ�A�u��q�l�̗܁v�́A���ł��Y����Ȃ��B�@
�@
![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@
�@![]() �@�@
�@�@
�@�����Ă��̂��сA�c�����ɑҖ]���w�j�̂��q���܂��a���x���ꂽ�I
�@���͂��̎��A���Ԃ̑������悻�Ɂc
�@�Ȃ����A�ӂƁA�́E���~�{�l�̎����v���o���Ă����B
�@�@
�@�u�V�{�l�́A������������A���~�{�l�̐��܂�ς��Ȃ̂ł́c!?�v
�@�Ƃ��v�����B
�@�c�����ɂƂ��āc�c���q�l����q�l�ɂƂ��Ă��A�悫�����k����Ƃ��āA�ƂĂ���ŋM�d�ȑ��݂̕��ł���c
�@�܂��A�c���Ǝ����������Ƃ��Ȃ��A���̉������ƂȂ��Đs�͂��ꂽ���������ƕ����Ă���B
�@�c����肪�N���邽�сA���e���̂���l�Ƃ��āA���ɔY�݁A���ɂ���J�Ȃ������{�l������A���̓ˑR�̂��������ɁA�����������͋����A�߂��݁A�S����A���̂��������i�����j�B
�@���ɂ́c
�@���́c���{���������ɕ������A�w�c���q������p���[�h�x �̓��c
�@���T���I�����A���ɓ����ė����A�c���q�l����q�l�̂�����p���[�g�̂��n�Ԃ��c
�@���̌������������������_�̑��ŁA���Ƒ��S�������A��ɂȂ��āA�p���[�h�̂��n�Ԃ����グ�Ȃ���A��т̏Ί�ł��o�}��������Ă����A�����{�l�̂��p���A���ł��Y����Ȃ��B
�@�����c�����j�̒��ł��A���߂Č�����i(�f��)�������B
�@������c�ނ����������͂��Ă����āc�Ƃ肠�����A�V�{�l�́A����Ȏ������Ȃ����c���ƁA�����������ɗ^���Ă����������w�_�l����̑��蕨�x�Ȃ̂����m��Ȃ��ȁA�Ƃ��v���B
�@�A�[�e�B�X�g���A�[�e�B�X�g���������ɂ́A�j���X�^�b�t�E�����X�^�b�t�̑��݂��s���ł���悤�Ɂc
�@�V�c(��)�́A�V�c(��)�����ł͐��藧���Ȃ��B
�@�@�w�ėՂ̃L���X�g�x �͋����A
�@�u�w���A�ۗ��̗��j�x�ɂ����āA���{�� �w�C�M���X���Ɓx (=��p�鍑)�Ɏ����đ���ꂽ���ł���B�v
�@�ƁB
�@���������c���̒m���Ă���͈͂ł����A����V�c���c���q�l���A�Ⴋ�����u���������i���G�o����)�w�C�M���X�c���x�v�Ɋw�ꂽ�B�������A��̓I�Ȃ��̂�����Ȃǂ͒m��R���Ȃ�����ǁB
�@�������E��ʉƒ��U��Ԃ�A�l���Ă݂Ă��c
�@���Ƃ�������������ƁE���Ƃł����Ă��A�܂����ƂƂ�����ł����Ă��c�Ⴆ�Ύo�������̉ƒ�ł���A���Ƃ��疹�{�q���}������E�Ղ��p���B���Ƃ��q���Ɍb�܂�Ȃ��Ƃ��c�{�q�E�{���̗������A�g���E���l�̋�ʂȂ��A���Ƃ���}������E�Ղ��p���c���ꂪ�����ł͂Ȃ��A�l�ԂƂ��čl���鎩�R�̗���ł���A���ꂪ�Ƒ��Ƃ������̂ł���A���̉Ƒ����ꂼ��̐����ߒ��ɂ����A�l�ԂƂ��Ēa���������̈Ӌ`������E�ړI������̂ł���A���������{�l�͎����̍l���œ��{�ɒa�������̂ł͂Ȃ��Ɠ����悤�ɁA����͐l�Ԃ̓��]�����ōl���鎖�ł͂Ȃ����c
�@�܂��āA�w���A�ۗ��̗��j�x�ɂ����āA���{�́A(�a�m��i���̍��Ə̂��ꂽ)�p���Ɠ����A�w�������ƁE��e���Ɓx�̗���ɒu����Ă���̂ł���c
�@���Ȃ݂Ɂc�j���E�����̎Y�ݕ����́A��e�̗��q�ł͂Ȃ��A���e�̐��q�ɂ���Č��肳���c�ƁA(�͂邩��)���Z�̉ƒ�Ȃ̎��ƂŊw�L��������B
�@���������{�l�ɂ́A�������}�������A��������I�Ȕ��z�̓]�������߂��E�����Ă���̂����m��Ȃ��B
�@�����A���̌��@�Ƃ��@���ł͂Ȃ��A���{�I�������炷��c
�@�l�ԂƂ����̂́A��l���]���Ƃ���Ȃ��A�������_�̕��g�ł���c�Ȋw�I�ɂ݂Ă��A�c���q�l�ɂ��E�H�{�l�ɂ��E�I�m�����ɂ��A���łɂ�������ƁA���Ԃ̌�������Ă���̂ł���E�Ȃ����Ă���̂ł���A���ꂼ���l�E��l�̐l�i�E�i�i�̖��ł���c�����������Ƃ͈����������A�����A�������A
�S���ʐ��E�̑��݂Ƃ��Ĉ����Ȃǂ́A�ԈႢ��!�@�����͖����I�Ɍ��āA�����̂��߂́A����ړI�Ƃ�����̂Ȃ̂��낤!?�@
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����A
�@�w�V���̍ŏ��P�ʂ́@�ƒ�ł���x
�@�c�ƁB
�@
�@�����������A�����E�O��������A���ł����A��R�����]��Q�E�o�b�V���O�����т��������Łc�c���q�l�͋����c
�@�w ��q�́@�������܂� �x
�@�c�ƁB
�@���܂��܂Ȏg�������Ȃ����̑O�Ɂc�l�ԂƂ��āE�Ƒ��Ƃ��āA���̍��{�ɂ�����(=�X�^�[�g�̒n�_)�A������ł��邩���A�ے��Ƃ��Ă̂��̂������ʂ��āA�����������Ɏ����ĉ��������B
![]() �@
�@![]()
�@���q�������V�{�����̖����̂��p���c���낢��ɁE���܂��܂ɑz�����Ȃ���E��z���Ȃ���A�v���ɂӂ���A���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�O�O�U�N�X���̉��{�`�@�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̂[�W�̐擪�ցj
�@(����3)
�@�@(��z��)
�@�@�@�@�w����l�Q�̕s�v�c�Ȗ���x ��ǂ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�}�L�m�o�Łj
![]() �@
�@![]() �@�@�@
�@�@�@
�@�u���̎q���傫���Ȃ��āA��������ɂԂ��������A�����V�̉��삪����悤�Ɋ���āc����� �w�܂ȂƁx �Ɩ��t���܂����B�v
�@�m���c�����A��\�]�N�O?�̘b�ɂȂ邯��ǁc�����j�a���̎��A���D�̒|���i�q��������������������Ă����A�w�܂ȂƁx ���w�܂ȁx�B
�@
�@�w�}�i�x �Ƃ����̂́A���E�V���̏����ɏo�Ă����u�̎��v�̖��ŁA�w���[�Z�x���w�C�G�X�E�L���X�g�x�������A���Q������A�ꋫ�ɗ��������ƁA�s�v�c�Ƃ������}�i�������Ă�����A�V����~���Ă����肵��(�����I�\��)�A�ނ���s����X�ŋ~���Ă��ꂽ�A���ł���B
�@�Ƃ���ŁA�w����̎���x �ƌĂ�錻����}�i�́c�H�@���́A���́A
�@�w����l�Q(�����炢�ɂ�)�x
�@�������ł���B�V���ɂ́A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă���ӏ�������B
�@�w���̂���҂́A����i�݂��܁j��������Ɍ������Ƃ����悢�B������҂ɂ́A�B����Ă���}�i��^���悤�B�܂�������^���悤�B���̐̏�ɂ́A�������҂̂ق�������m��Ȃ��V�������������Ă���B�x
�@�ƁB�@�w�����x�Ƃ����̂́A�؍��ɑ����Ƃ�����w�嗝�x�̎��ł���Ƃ����B
�@���͓����i���c�P�X�W�W�N�j�A�킪�g�ł͂Ȃ��ɂ���A�a�C�Ƃ�����ςȏo������g�߂ɑ̌����A��������l�Q���A�܂�����������}�i�ł��鎖�������������A���߂Ă����s�v�c�Ȗ���ɋ����Ă���Ƃ���ł���B
�@����������l�Q���Ǝv���邩���m��Ȃ�����ǁA���̎�̂��̂͏�Ɍ������i�߂��A���X�A���̒�����V��������������A�������A�܂��������̂��̂��܂܂�Ă��邻��������(���c1988�N����)�A���Ԉ�ʂ́u���f�b�J�`����v��u�L���s���s�Ɓv�i���ł����������̐l�j�̐̂Ȃ���̒m���ɘf�킳��Ȃ��悤�A�������Ă݂������̂��Ǝv���B
�@���̏ꍇ�A�{������֒��s���A����������ŗǏ���T���o���ēǂ݁A�܂��n���̐��Ƃ��璼�ڋ����A���̌��ʁA���̌����i���̂����ł͂Ȃ��A�������_�I�����I�j����i�܁j�̓�����ɂ���(=�̒��̉��E�����ɐ��_�̉ɂȂ����Ă���)�A
�@�u������A�l�Q�����c�v
�@�ł͂Ȃ��A
�@�u�������A�l�Q��!�v
�@���Ǝ������A�܂������A�މ@�������ғ��l�i���ː����Â��Ȃ���A����l�Q�����p�j���A�l�Q���̉e���ŁA�s���⋰�|�ɂ��炳��鎖�Ȃ��Ί�����߂��A�������S�{������ !�@(=�a���c�������Ƃ��Z�����Ƃ��c���ӎ����Ȃ��Ȃ����B)
�@���\�N�̋i���҂��E������������l�Q���p�ɂ���āc80��O�ɂ��āE�C�Â��Ă݂�E���̊Ԃɂ��։��҂ɂȂ��Ă����Ƃ����A�g���̗�������B
�@�Ƃ���ŁA���m��w�Ƃ����̂́c���̊����������W���I�Ɏ��Â��鎖��ړI�Ƃ��邪�c
�@���m��w�͈Ⴄ�B
�@�u�̂Ƃ����̂́A�l�ԎЉ�Ɠ��l�ɁA�ׂ����Ԃ̖ڂ̂悤�ȏ�łȂ����Ă���A��Ƃ��ēƗ����Đ����o���鑟��͂Ȃ��A������a�C�������͈�ł���B�v
�@�Ƃ����l������{�ɒu���B�@
�@�Ȃ�قǁA�Ⴆ���������́A�V���i�a�@��j�Ƃ͈Ⴂ�A����ł��̑S�̂��ꏄ����(�p�g���[������)�悤�Ȑ����������Ă���B�����������ڂ��x���ƌ����鏊���i�䂦��j�ł��낤�B
�@�������A�ŋ߂̌������ꂽ�����i����l�Q�j�́A�ȑO�Ƃ͂��Ȃ����ė��Ă���悤�Łc���\�A����������A����p�Ȃ��B����ǂ��납�A������N���镛��p���A�t�ɔr�����Ă����I
�@�����i�D�w�j�������N���܂Łc�\�h�ɁA���ÂɁc�}���ɁA�����Ɂc�ƁB�@�������A
�@�u�������͂��邪�A�A�p����ƕ���p���N���A���Ƃ������B�v
�@�Ƃ����V���Ƃ͈Ⴂ�A�t�ɁA�����ɘA�p�������قǗǂ��Ƃ����̂�����A���̂悤�Șb�ł���B
�@(�V��<������̏ꍇ>�͈ꌾ�ł����A�u�����v�Ƃ������A�������ꎞ�I�Ɂu��Ⴢ�����v�Ƃ������ł͂Ȃ����낤��?)
�@�����A��������l�Q�́A
�@�w���_�ʂɌ����ڂ����A�K���Ȃǂ̍Ĕ��ɑ���s����ő�����������Ȃ��B�x
�@�Ƃ�������A�����������Ȃ��ł���B
�@���́A����̍Ő�[�ɂ����w�X�g���X�x �Ƃ����a��?���A���̍ŌÎQ�ɂ����w����l�Q�x ���A�ł���I
�@�s�K�ɂ��āA�Ⴆ�Ζ����K���ł������Ƃ��Ă��A���_�I��ɂ͂��Ƃ��A���̓I�ɂ݂𑊓��Ɋɘa�i�����j���Ă���邻���ł���B
�@���ނƁA�ꍇ�ɂ���Ă͐H�~�s�U�ɂȂ�����A���Ǐ�Ɋ��i�������j�鎖�����邻���ł��邪�c����͔����̂������؋��ŁA�̓��̓őf�Ƃ����őf�������o������ł���A�����čQ(����)�Ă鎖�ł͂Ȃ������Łc���ꂾ���A���̐l�̓������`(����)����Ă����A�Ƃ������ł���c
�@�Ⴆ�A�q���������C�^�Y������C���������ꍇ�A���̒��x�ɂ���āA�����Ǝ�������A�������������肵�Ă��̎�����ɋ����t������̂ł��邪�A����Ɠ��������Łc��������l�Q���A���̈��p�҂ɂ��̏Ǐ�̒��x�������@�i���Ɓj���Ă���A�Ƃ������ɂȂ�킯���B
�@����͂������Ǝv���B
�@�Љ���ł��A���������v���悤�Ƃ��鎞�A���̃S�^�S�^���Ȃ��E�X���i���Ɖ��P�o������̂��Ƃ͐��̒��ɂ͈���Ȃ��A����Ɠ��������Łc�K���ߓn���Ƃ������̂�����̂ł����āB
�@�����Ƃ��A���p�ɍۂ��Ă̒��ӎ���������A�ꎞ�I�Ɉ��܂Ȃ������ǂ��Ƃ����ꍇ���Ȃ��ł͂Ȃ����낤����ǁB
�@����͎�ɁA�O����̃o�C�L���ɂ��I�f�L���ł������Ȃǂ������ł���(���c1988�N���݂̐�)�B
�@�܂��̂́A����l�Q�́u�������v�ɂ͗ǂ��Ȃ��A�ƌ��������̂�����ǁA����͈Ⴄ�Ǝv���B�@
�@�܂Ƃ߂Č����A�����������E�Ⴂ�������A���̐l�ɂƂ��Ĉ�ԗǂ���Ԃ�m���Ă���̂��A��������l�Q�Ƃ�������̕s�v�c�ȂƂ���ł���A�̑�ȂƂ���ł���Ƃ����c�I�@�����A�Ⴂ�̖��ł͂Ȃ��A
�@�w������h���x�@
�@�܂�A���t�̗����ǂ����邱�Ƃ��厖�ł���c�����A���̂��f�Ɋ҂�(=�|���E�Y�������)���ɂ���āA�C�Â��Ă݂�A�A���I�ɐ��_�̉���(=���K���E���z�̔r��)�ɂȂ����Ă����A�Ƃ������Ȃ̂��낤���B
�@�����܂��A���̑̌�����s���Ɓc���̒��ɂ́A���A�s���Ƃ������̂������āc��������l�Q�ɂ͓��ɂ��̎���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������̂��m���B�@�������A����Ȃ��̈��܂Ȃ��Ă��\���Ɍ��N���A�Ƃ������ɉz�������͂Ȃ�����ǁB
�@�Ȃ�Ƃ������A���Ƃ��a�C�ɂ͂Ȃ��Ă��A��{�I�ɖ�������Ă����̂�(=���S�Ȑ��_)�A����l�Q�̍ő�̓����ł��낤�Ǝv���B
�@�����Ƃ��A�w�����x �Ƃ����h���܂ł͓������Ȃ����낤����ǁB
�@��Ɍ��N�ł��������������Ă��Ă��A�Z���̉^���������Ă���A������(��)�������m��Ȃ��B
�@�t�ɁA�N���a�@�ʂ������A�܂������ԐQ������ł����Ă��A�����̉^���������Ă���A�P�O�O�܂ł������邩���m��Ȃ��B�悭�A
�@�u�a������������l�Ɍ����āA����������v
�@�Ƃ������������c(��)�@�����Ƃ����̂͂����������̂�����c�܂�A�l�Ԃ̔\�͂ōl���Ă��d���Ȃ����͍̂l����ȁA�Ƃ������ɂȂ�c!?
�@�i�V���c�������v����<�킸��>���Ă͂����Ȃ��B�j
�@�Ⴆ�A�w��ɂ�����ƃg�Q���h�����������ł��A���̒ɂ݂͑̒��𑖂蔲�����c���m��w�Ƃ����̂́A
�@�w�Ƒ��S�́i�̑S�́j�̌��N���肤�A�e�̐S��E�Ƒ��̐S��x
�@���v�킹�A�X�S�C�i�I�@�Ǝv���B
�@���̓_�A���ɍŋ߂����m��w�ɂ́A���E�ۑ肪�A���܂�ɂ��������݂���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ�����ǁc�ǂ����낤!?
�@�����A�������̗Ǐ���ǂ݁E���s�������ŁA��ԂɊ��������́c
�@����l�Q�͊m���Ɍ������B�@�������c����l�Q���w���x�ł���Ƃ����A����ł��E�Z��ł��Ȃ��B
�@�{���Ɏ��邩�ȁH�@�P�Ȃ�C�x�߂ł͂Ȃ����H�@�ȂǂƂ͌����Ďv��Ȃ����B�Ⴆ�A�Q�O�N������̎��a�ł���A�Q�O�N�������āA�}�i������Ŏ������Ƃ����C�́B�����Ď�����(=���̊������ӎ����Ȃ��Ȃ���)�Ȃ�A��x�Ɠ����a���ɂ�����Ȃ��悤�ɁA�������}�i�����ށc�����a�Ɗ��S�Ɏ��邽�߂ɂ́A���ꂭ�炢�̓w�͂̐S���K�v�ł͂Ȃ����c�T�N�A�P�O�N�����āA�W�����E�W�����Ɛi��ŗ������a���A�P�A�Q�����̈��p�Ŏ��������ȂǂƎv���̂́A�����ǂ�����̂ł͂Ȃ����c
�@�Ƃ������������B
�@����́c
�@�u���Ⴀ�A���͍��A�W�O������A���Ƃ���łǂ�قǂ̎����Ȃ����낤�ȁc�v
�@�Ƃ������A�����I���l�ς̖��ł͂Ȃ��A�����܂ł��S��I�Ȃ��̂ł���A�N��ɂ͊W�Ȃ��B
�@�Ƃ��������A���ɂ͂��������A��������l�Q�Ƃ����̂́A��x����������A�A���R���v�Z������A�ŎZ�I�ɂȂ�����͂��Ȃ��A�Ƃ������c����������?�@�ق�ƂɌ���������?�@�ȂǂƂ͂��������l���Ȃ��c����ł���Ƃ������ň��S����̂��c�t�ɁA�P�z���Ƃ������c�Ƃ������A�m��Ȃ����ɂ������������ɓ����čs���Ă���Ă���悤�ȁc�{���ɁA�Ȃ�ƕ\��������悢���c�V���̂悤�ɁA���p�O�ƁE���p��̋��E�����Ȃ��Ƃ������A�l���Ȃ��Ƃ������B
�@�ł��s�v�c�Ȏ��ɁA���߂Č��ɓ����ƁA�R�O���ʌo�������c�����A���܂łɖ���������̂Ȃ��A
�@�w�ӂ킟�c�x
�@�Ƃ����A�������G����u�A�̒��𑖂�ꍇ������悤�Łc���̏ꍇ�͂��������� !�@
�@�����A����Ö������łɔƂ���Ă��āA���Ȃ�Ђǂ���Ԃ���������ǁA���ɂ��Ďv���ƁA(�O�q��)�m�l�̂��߂Ƃ������A�����g�̂��߂������̂��Ǝv�����炢�A�ƂĂ��ǂ��^�C�~���O�ł�����Ղ��A���E���������Ƃ��������Ă���B
�@�܂��A�����Ԉ�ĂĂ���?�E���e�w�̐������̗₦���Ƃ������a���A�l�Q�����p�ł킸���R�����ڂɂ��ĕω����N�����i�ӎ����Ȃ��Ȃ����I�j�Ƃ����A�X�S�C�̌������邯��ǁc�]���������������̂��c�������ǂ������̂��c����Ƃ��A�����̐M�O���������̂��c�_�݂̂��m��B(��)
�@�������A���f�͑�G�Ƃ������ŁA�Ȍ�A�����Ɏ���܂ň��ݑ����Ă���B
�@�z�E�������́A������ԐH�ׂĂ����Γ������i�Ɓj��Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�ꐶ�H�ב�������̂�����A����Ƃ܂������������� ?
�@�u�|�p�C���ǂ�Ȃɋ����Ă��A�z�E�������̊ʋl���Ȃ�������A���̐l�v(������ƌÂ������)
�@�������悤�ɁA����l�Q�����ݑ����Ȃ���ΈӖ����Ȃ��Ƃ��������c�V���ł��A�Z��ł��Ȃ��̂�����B
�@�����A�̒��������ȁA�Ǝv�������A���p�𑱂��邩�E�����Ȃ����́A�������A�{�l�̎��R�ł���Ǝv�����A�N��ɂ���邾�낤���A���̎��E���̎��̎���E�S��Œ��߂��A�Ή����čs���悢�Ǝv���B�����A�w���N�x�̒��S�́A����ς�A��H���v���u�^���v(�̑��Ȃ�)���Ǝv������B
�@�܂��́A�w��x�Ƃ������̂ɑ���u����ρv���̂Ăāc�Ƃ����Ƃ��납��n�߂Ă݂������́B
�@���ꂩ��A����͂�����ƎQ�l�ɁA�Ƃ�����������ǁc
�@����l�Q�Ƃ����Ă��A���Q�A�g�Q�A�G�L�X�Ȃǂ��낢��Ȍ`�Ŕ̔�����Ă��邯��ǁA���͒f�R�A�w�G�L�X�x �������߂������B
�@�Ƃ����̂��A����l�Q�Ƃ����̂́A���X�������F�����Ă���A������u�����v���ɂ���āA���߂Ă��̌��͂�����킯�ŁA�u�g�Q�v�́A�������������ɂ��Ă��邩��A�u���Q�v���͗ǂ�����ǁA����ς�A�w�G�L�X�x �ɉz�������͂Ȃ��Ǝv���B
�@����l�Q�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����Ă��A�{������N�����ł���A�؍��ɂ�����l�Q�̐ꔄ��������i���c�P�X�W�W�N���݁j�A���ƎY�ƂƂ��đ厖�ɂ���Ă���Ƃ����B���v�̑���������ł́A�͔|�̖ʂłǂ��Ȃ��Ă��邩�肩�ł͂Ȃ�����ǁA�����ɂ����ẮA��͂萢�E��ł͂Ȃ����낤���c�ڍׂ͕�����Ȃ�����ǁB
�@�K���A�w�������E�o�_(������)�n���x �ɂ́A�̂���L�����w�卪���x�i�������܁@���E�������j�� �w�I�^�l�l�Q�x�i���_�B�l�Q�j�Ƃ����̂������āc���̑卪��������l�Q�́A�u���{�O��͔|�v�ƌ����钆�̈�ł���A���̒��ł��A���ɕi���̓_�ł��w�ŗD�G�x�Ƃ���Ă���A���{�ł͂������A���E�I�ɂ��L���ŁA�ŏ�i�Ƃ���Ă���B
�@���Ȃ݂ɁA���̑卪���Ƃ����̂́c�]�˂̐́A���̍���(������)�̉Ԃł���E�M�d�Ȃ���ł���A����l�Q�𓐂܂�Ȃ��悤�A���̏��݉B���̂��߂ɁA�u�l�Q���v����u�卪���v�ɌĂі���ς����Ƃ����̂��A���̗R���ł���Ƃ̎��B
�@����l�Q�Ƃ����̂́A�͔|�̖ʂʼn����ƍ�������A�卪���̏ꍇ�́A�Ȃ�ƁA�A���t�������w6�N�̍Ό��x���|�������̂����p����Ă���A�܂��A���Y�ʂ̊m�ۂ��e�Ղł͂Ȃ��A�ő�̘J�͂������Ă���悤�ł���B
�@�������A�ƂĂ��L����ɁA���̑卪��������l�Q�́A���Y�E�������Ƃ������������Ă��A��r�̈��p�����E���ԓ��̊����ɂ����āA��ʔ̔��ɔ�r����ƁA���Ȃ�̊i���œ���o����悤�ȋC������B
�@�܂��A�����̗\��̂��鎞�ɂ́A�u1���ԑO�Ɉ���ł����v�ƁA���ʓI���Ƃ��B
�@�܂����̏��i�Ɠ����悤�ɁA�ގ��i�E�̔����@���ɂ́A���ɁA��������l�Q�ɂ́A�����ӂ��B �O�̂��߁B
![]()

![]()
�@����Ɓc�b���A������ƈ�(��)��邯����c
�@���̑卪���́A���ɂ� �w���O�̓��x �ƌĂ�A�������ł��A�L�����ό��n�Ƃ��Ēm����B
�@�����ڂ���̉����A�ό��̂��ߍ��ł́A�ꎞ�G�����ł͂Ȃ������ł������y���߂�悤�A����l�Q���l�A��Ɍ����J�����i�߂��Ă���悤��(���c1988�N����)�B���O�́A�����̌��Ԃł�����B(���́A�����B�������A����)
�@�w����l�Q�x ���w���O�̉ԁx ���@�ׂȐA��������A������ێ����čs���̂͑�ς��B�ǂ�����������j�������A�w�`�����鏤�i�x �Ƃ��Ēm���Ă���B
�@�w���Ј�x�A��������艺�����܂��B�x�@
![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
�@�b����ꂽ���łɁA������B
�@
�@���ە����ό��s�s�ł���A���̓������E���]�s�̋߂��A�������������w�̑�\�w�����߁x ���w�ǂ��傤�������x��x �̔��˒n�Ƃ��Ēm�����A�u�����s�v�ɂ́A
�@�w�����x���w���{��̑�σR���N�V�����x�Œm����A�L���� �w�������p�فx������B
�@�A�����J���u���{�뉀��厏�v���w�W���[�i���E�I�u�E�W���p�j�[�Y�E�K�[�f�j���O�x �ɂ����āA19�N��(2021�N����)�̘A���E���{���ɋP���A�����ł���B
�@50.000�́c�����G�������Ƃ��b���v�킹��A���{�뉀�Ɓc���R������n�߁A�ߑ���{��d��n��グ�ė������������̍�i���厲�Ƃ��āc���ɂ́A�ؒ��E���G�E�������R���N�V�����������p�قł���c�n�ݎҁE�i�́j�����S�N���́c�M�ɂ������A�w��ρx�ւ̎v���Ə�M�����߂��E�����������̔��p�قɂ́A�w���{�̔��x ���w���{�̐S�x �������ɒ��a���E�\������Ă���c
�@�w ����ȓc�ɂɁc�ǂ����āA����ȑf���炵���뉀���������c!?�x
�@�ƁA�N�����v�킹��A���p�فB
�@�w��������S���厖�x
�@�ł���Ƃ����A�n�ݎ҂̐[���v���ƁE�肢�̍��߂�ꂽ�A�c���q�a�����������ɂȂ������̂���A�����w�������p�فx�ցA
�@�w���Ј�x�A���z���������܂��B�x
�@�b�́A���ɖ߂��āc
�@�ߔN�́A�^�o�R���ŁA�A���R�[�����ł��͂��߁A���ɂ́A�R�[�q�[���ŁA�h�����N�ܒ��ŁA��i�����A�Ö������ŁA�܂����Ȗ����A�V���̕���p�Ȃǂ��낢�날�钆�ŁA�������łł��A�����w����l�Q���Łx�ɜ��i�����j��ō��I�i�܂��A�����������o�̂��̂ł͂Ȃ�����ǁc�j�@
�@�w���Ј�x�A�������������܂��B�x�@
�@����ɂ��Ă��c����܂łɎ��������Ȑl����������l�Q�����߂ė�������ǁc�v���A�����̗p�A���p���Ă����l�́A�ƂĂ����Ȃ��B
�@�u�ǖ�@���ɋꂵ�v�@(�܂�����́A��Ƃ������A�����ł͂��邯��ǁB)
�@�Ƃ������c�ł��A�U��Ԃ�A�v���Ԃ��Ă݂�Ɓc!?�@
�@�`���ŏЉ���悤�Ɂc�Ƃ肠�����[���ȏ�Ԃɂ���悤�Ȑl�̏ꍇ�́A����ς�A���p���Ă���Ă���A�Ƃ������ɋC�Â��B�����āA����Ɏv�����́c���{�j�A���E�j�A�����������ɂ�����悤�Ɂc���̎���ɂ��A
�@�u���҂͎̂Ă���c�v �u�{���͎̂Ă���c�v�@
�@�ƌ��������c�Ȃ��Ȃ��A��������l�Q�Ƃ�������������������Ƃ����̂��A�ȒP�Ȏ��ł͂Ȃ��悤���B
�@
�@�����āA�����̓����A�{���̓����́A���̎���ɂ� �w�Ƃ��x �ł��鎖�ɋC�Â��c
�@���[�Z���c���Ղ̃L���X�g���c�ėՂ̃L���X�g���B�����āA�c���B
�@���{�̏@���j�ɂ����Ă��c��y�^�@�̊J�c�ł����A�e�a���l�́w���͖{��x�̎v�z�ɂ��A�����Ƃ��ẮA���Ȃ�v�V�I�Ȃ��̂ł��������߂��A����������̒e�����A�u�������v�ɂ���Ă�����B(�������v�̍D�@������
?)
�@����ɂ����Ă��A�����ƁA��Ƃ̎w���ҁE�o�c�ҁA�X�|�[�c�E���y�E�A�[�e�B�X�g�̐��E�c
�@�}�X�R�~���}�X�R�~�̂��߂Ɂc���ҁE�א����𗘗p���A�U��c!
�@�����̎^�������Ƃ��c���_�����̌������Ƃ��c����Ȃ��̂́A���̂܂����c�ʂĂ��Ȃ����̂�����B�@
�@���N�A���N�̍���_�����v�������ׂĂ݂�c�����Ęb��́A�u�����c�v�u����c�v���v�������ׂĂ݂�c
�@����̂ǐ^�ŁA�擪�ɗ����A�Ƃ�œ����Ă���l�����c����A����ɂ���l�Ԃ́c���X�́u�����Ƃ��炵�����t�̖\���v �ɂ���āA��������čs���c
�@�ł��c!?�@
�@�u�����A���Ȃ������A�����Ɍ��������Ƃ��œ����Ă����Ƃ������c����������ł���A�{���ł���̂����m��܂���ˁB�v �@
�@�Ƃ������Ƃ��A�����Ɍ�����̂����m��Ȃ��A�Ƃ��������B
�@�w ���߂Ȃ��ŁA������ĉ������� ! �x
�@�Q�l�����@
�@�@�w����l�Q�̕s�v�c�Ȗ���x �@�}�L�m�o�Łi���c�P�X�W�P�N�n���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2010�N�`�@)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̃y�[�W�̐擪�ցj �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@